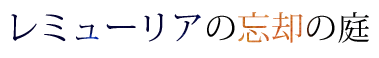
home |

・オフ本のサンプル
・全七話構成のうちの一話目
・アニメの今後の進捗と大きな齟齬をきたす可能性が高いですが、パラレルの一つとしてご容赦ください。
街路樹の向こうから、蝉の鳴き声が聞こえてくる。
夏だ。少年の首筋を汗が一筋伝って、肌と制服の合間に滑り落ちていった。ミンミンミンミン、アブラゼミがうるさい。もう溶けだしてしまっているソーダ味のアイスバーを口に含んで遊馬はあーあ、と溜め息を吐いた。
「俺、基本的に夏は好きなんだけどさ、時々この暑さだけはかなわねえなあって思うんだ。どうにかなんねえかなぁ、確か今日の最高気温は……」
「三十一度。真夏日ですよ、遊馬くん」
「そうそれ! ほんっと堪らないぜここまでくると」
がぶりと残ったアイスにかぶりついて、そのままよく噛みもせずに口の中で適当に舐め転がして呑み込んでしまう。少し遅れて、「キーンってきた!」などと叫ぶ。そうなることはわかり切っているのだからもっと丁寧に食べればいいものを、彼は冷たいものはいつもこうなのだ。かき氷もアイスクリームもアイスバーも、ジュースに入っている氷も。なんでも最後に無理に呑み込んで痛い痛いと言っている。
物好きなんだろうか。そう思うが、遊馬本人は毎回真剣に痛がっているのできっと天然なのだろう。
「こういう日はさっさと家に帰って、エアコンの効いた涼しい部屋でデュエルに限るよなー」
「え、今日はまっすぐに家に帰るんですか?」
「あ、そっか。昨日カード屋行く約束したんだっけ。そろそろちゃんとデッキ持っときたいって言ってたもんな。悪い悪い」
あまり悪いとは思っていなさそうな声と顔で今やっとそれを思い出したふうにポンと手を叩く。今の今までうっかりと忘れていたのに違いない。でも遊馬に悪意があるわけじゃないし、それに急にそんなことを言い出した方にも責任はあるだろう。今日がとびきり蒸し暑くて過ごしにくいことは確かだし、遊馬は悪くない。
「いえ、そんな。遊馬くんが帰りたいのならそれでいいんです。僕なんて居候の身なんですし……」
「いや、こういうのって後回しにするのあんまりよくないんだ。ほらあれ、『思い立ったが吉日』ってやつ! だから予定通りカード屋行っちゃおうぜ。運よくモールへの分かれ道からそんなに遠いところまで来てないしさ」
「それじゃ、行ってくれるんですか?」
「もちろん。光属性、組みたいんだよな」
「はい、六つの属性の中で一番光属性が好きだなって思って。特にこれってカテゴリはないんですけども」
「んーまあ、カテゴリなんてそれこそ海の中泳いでる魚みたいにいっぱいあるし。店に行ってぴんときたの、買えばいいんじゃないかな」
ソーダバーの木の棒を噛み締めるようにしてぶらぶら上下させている。それからぺっとそれを吐き出して一瞥し、遊馬はちぇっと残念そうに眉を顰めた。棒の中央にでかでかと焼き込みで印字された「ハズレ」の文字。この夏に入ってから彼は毎日のようにこのお気に入りのソーダバーを食べているが、今のところ一度もその文字が「アタリ」だったことはない。
そのハズレやらアタリやらの文字列が物珍しかった頃に彼に一度尋ねてみたことがある。もしも「アタリ」が出たらどんないいことがあるのか、或いは、どんなふうに嬉しいのか。すると、その時遊馬はちょっと考えてから人差し指をぴんと伸ばして、上手いことを閃いたとでも言いたげな顔でこんなことを教えてくれた。――「アタリが出たら、きっと、真月にいいことがあるぜ!」
その時から、真月零はずっと彼の隣で待っている。
「なあ真月。なんかさ、これだけは苦手―っての、ある」
「苦手、ですか」
「うん。うっかり買っちゃっても、困るだろうし」
「そうですね。何か、敢えて言うのだとしたら……」
遊馬がソーダバーの「アタリ」棒を手に入れて、何か彼の言うところの「いいこと」が起こるかもしれない時を、待っている。
「闇属性の統一カテゴリが僕、あまり好きじゃないんです」
蝉の鳴き声がまだ、うるさい。二人で並んで通り過ぎたモールへの曲がり角から遠目に向日葵畑が見えた。無数の向日葵が太陽の方を懸命に追いかけて首を折り曲げている。太陽を追いかけるサン・フラワーたち。真月はその花たちが遊馬に群がったり、追いかけてきたりして集まっている彼の友人たちのようだなとぼんやり考えた。九十九遊馬という太陽に追い縋ってくる花たち。
遊馬を楽しそうだったり嬉しそうだったりしながら見る一方で隣の自分を嫌疑している視線が見え隠れして、真月はなかなか彼らのことを好きになれないでいる。
◇◆◇◆◇
「――何故そいつを助けた。お前のいつもの底なしの、呆れる程愚鈍なお人よしだとしても、だ――そうやって後生大事そうに抱えているのはどうしてだ? このことがわからない程、お前は馬鹿じゃなかったはずだろう遊馬」
「でも、シャーク、」
「でもじゃない。いいか。そいつはベクターなんだぞ! どんな姿をしていても!」
シャークの怒号が響き渡る。だがその場に居合わせている者誰一人として彼に異を唱える姿勢は持ち合わせていないようだった。口を堅く引き結んで腕組みをしたままのカイトも、厳しい面持ちで浮かんでいるアストラル、シャークの隣で立っている璃緒、一歩引いた位置で立ち尽くしている小鳥。その誰もが「どうして」という顔をして遊馬をまるで尋問でもするかのように取り囲んでいる。
遊馬はただ一人この場で孤立して、その小さな少年の腕の中にぐったりとした体を一つ抱え込んでいた。オレンジ色の髪の毛はすっかり荒れ果てていて、体中に擦過傷が確認出来る。紫の眼球が嵌っている瞳はぴったりと閉じられ、力なく項垂れて遊馬にその全身を預け眠っていた。
遊馬が抱えている人物が誰なのかは言うまでもない。真月零の姿をした(それはつまり、彼が本来の姿を維持していられなくなる程に衰弱し切っているということを示している)ベクターだ。
「お前を散々に騙し、こっぴどく裏切り、汚ねえ罠に次々嵌めてお前を嘲っていた下衆野郎だ。お前が身を挺して庇いだてする必要なんかどこにもなかった。助ける必要もなかった。聞いていただろう、こいつが言ったことを。自業自得なんだ。バリアン世界とやらの神に契約してその命を差し出したのはこいつ自身の意志によるものだ。……それも、遊馬、お前を殺すために」
「遊馬を殺すために」。シャークが復唱した言葉がベクターの声で遊馬の頭の中でリフレインする。ぎゅうと抱いた傷だらけの体を強く握り締めて遊馬は唇を噛んだ。そのことは嫌と言う程わかっているつもりだった。
ベクターは真実、九十九遊馬を殺すためだけに危険な賭けに出ていたのだ。それはデュエルが始まる前にベクターの口から直接語って聞かされた揺るぎようのない事実である。「アストラルもバリアン世界もどうなろうが知ったこっちゃねえ。ぶっちゃけどうだって構いやしねぇんだよォ、そんなもんは! 俺の望みはただ一つ。九十九遊馬ァ! テメェだけは俺がこの手で握り潰してやる!! そのために俺はバリアンの神に命を捧げた!!」……ベクターは確かにそう言っていた。
宣告を突き付けるベクターの姿に一切の慈悲はなく、また交渉の余地も残されてはいなかった。彼の中には焦りがあった。そして、遊馬に対する並々ならぬ憎悪があった。
そんなことはわかっている。
「でもだからって! 助けることが出来るのなら見殺しにしちゃダメだ!」
「どこまで好き者なんだ?! そこまでの代償を他ならぬお前が支払う理由なんかどこにもない!!」
「ある!」
それでも、断言した。どんなに仲間達に糾弾されても、ベクターが恩を数億倍の仇で返そうとも、遊馬は彼を助けたかったのだ。
ベクターの体を支える他ならぬ遊馬自身も、満身創痍と言って差し仕えない程に傷付いている。洋服の端々が破れ、ほつれ、デュエルによって現実にフィードバックされた無数の傷跡がその下から見え隠れしていた。それだけじゃない。ドン・サウザントとの契約によりその命を燃やし尽くさんとしていたベクターを無理矢理に救出した反動で目に見えないダメージがその小さな体に蓄積している。
腰に備え付けられたデッキケースから一枚のカードがその姿を覗かせていた。遊馬がバリアンの神が造り上げた契約の理を捻じ曲げる為に用いた奇跡の力だ。《ヌメロン・フォース》、過去現在未来その全てを司る《ヌメロン・コード》の力の片鱗を宿すものにして、遊馬にとっての、真月零との間に結ばれた友情の形でもあった。
アストラルが遊馬の気持ちを汲み取って受け入れてくれた、絆の今の在り方だ。
「やり直したい、って言ったらそれは……おかしいのかもしれないけど。俺は真月零を信じてる。今でも。だからベクターとも、もう一度……」
「くだらん夢想だ」
「カイトまで」
「お前の甘えが誰にだって通用するわけじゃない。俺やクリス、その兄弟達にはまだ情があり、理由があり、確かに対話による説得が可能だっただろう。だがベクターの場合はそのどのケースとも通じ合わない。この見下げ果てた男には一切の情けがなく、その清々しい屑っぷりには感動を覚えるぐらいだ。まだ意識を取り戻していない今なら引き返せる。棄てて来い。そんなものは」
捨て猫を元の場所に戻して来いとでも言うような気軽さで無情に言い放つ。でもいやだ。そんなの、駄目だ。遊馬の中の直感がそう告げている。
「……俺に真月は捨てられない」
「やはりな。そんなところだろうと思ってはいた」
「友達を見殺しにしろって言うのかよ!」
「そいつは友達でもなんでもない。敵だ」
カツカツと足音を響かせてカイトがこちらに向かってくる。遊馬は小さく怯えてベクターの体をカイトから守るように抱き寄せた。
その時だ。振動に揺さぶり起こされたのだろうか、今まで微動だにもせず死んだように眠っていた彼の体がぴくりと痙攣した。カイトとシャークが一斉に警戒の構えを取る。衰弱し切っているとはいえ、やはりベクターのまじりっけのない悪意は馬鹿にならない恐怖だ。
ベクターが口を開く。青ざめた唇は僅かに震えているように遊馬には見えた。
「……ゆうまくん?」
――か細い声だ。
のろのろと目蓋が開き、アメジスト色の丸い瞳が姿を覗かせる。そのさまは、つい数刻前まで遊馬を睨みつけていたあの狂気の瞳とはまるで似ても似つかなかった。遊馬が一番近くでよく見ていた、あのおっちょこちょいな少年のものだ。
「しんげつ」
「ああ、よかった、遊馬くん。遊馬くんですよね。ぼく、どうしたんだろう。なんだか体が怠くって……」
何か様子が変だ。そもそも彼は何故「ゆうまくん」と柔らかく名前を呼んで「ぼく」と自分を呼称するのだろう? 今更ベクターの方に真月零を騙るメリットなどもう何もない。ましてやこの衰弱し切った体で、罪を認めて保護を求めるような殊勝な性格であるのならばそもそもベクターは遊馬にあんなふうに接触を図ったりなんかはとても出来なかったはずだ。だというのに顔も、声も、態度もそのどれもが違うことなく「真月零」のもので、どこにも「ベクター」を見出すことが出来ない。
まるでベクターとしての本性がぽっかりと陥没して、偽りの人格である「真月零」だけが残されてしまったかのようなそんな違和感だ。
遊馬くん? ベクター、いや、真月が首を傾げる。愛らしい少年の声音。そんなことがあるはずがないのに、遊馬は今にも「真月が還ってきた」という錯覚に襲われそうだった。
「何か……覚えてないのか」
「ごめんなさい。ぼく、本当に何もわからなくて。ここはどこなんですか? 遊馬くんは、どうしてそんなに傷付いて……」
「何でもないんだ。本当に、何でも」
「……無理、しちゃダメですよ、遊馬くん。それで、あの怖い人は……?」
「オービタル、今すぐそいつの脳波をスキャンして状態を測れ!」
「カシコマリ!」
真月がそう遊馬に尋ねるのとカイトの鋭い命令が飛ぶのは、ほぼ同時だった。
オービタルが俊敏に動いてベクターに迫ってくる。遊馬があっと思った時には既に遅く、気が付けば真月は遊馬の腕の中から奪われてしまっていた。まだ意識が朦朧としているふうの真月をオービタルのアームが取り押さえ、無数のコードが中から伸びてきてその体に張り付く。単調な機械音。時折小さく聞こえる呻き声は、誰が見てもベクターというよりは「真月零」のものに近いよう思える。
「カイト! 何するんだよ!」
「信頼は確かに美徳だが、少しは疑いというものを覚えろ。見てわからないのか、検査だよ」
「こいつは今疲れてるんだ」
「何度言えばわかる。真月零はベクターなんだ!」
乾いた音が響いて、遊馬の体が仰け反った。カイトが我慢ならずに遊馬を叩いたのだ。何が起こったのかが上手く掴めずに遊馬は赤く腫れた頬を抑えることもせずに呆然としている。
カイトにこうして叩かれるのは、真月零がベクターに連れ去られたと思い込んで感情を暴走させ、真月が、真月が、としきりに繰り返していたあの時以来のことだった。
「お前には失望した」
カイトが冷たく言った。
オービタルの検査は簡易的なものだったようで、そんなやり取りの間に案外あっさりと検査自体は終わったようだ。コードが引っ込み真月の体が解放される。反射的にその体を受け止めて、遊馬は頭の中で反響するカイトの言葉の意味を考えていた。
カイトは怒っているのだろうか。失望、というのはどういう意味なのだろう。近頃はずっとカイトに優しくされていて、遊馬はそれを忘れていたのかもしれない。天城カイトは、ただ盲目的に優しくしてくれるわけじゃない、ちゃんとした厳しさを持っている男だ。
だから遊馬に向けた冷たい言葉も、遊馬を思いやってのことなのだろうと頭ではわかっている。また破滅するのか、と彼は問い掛けているのだ。
オービタルがカイトに駆け寄る。カイトは遊馬と真月を一瞥して報告を促した。
「結果は」
「間違いありませんカイト様、記憶喪失です。脳に目立つ損傷はありませんが、記憶中枢にエラーが生じている模様」
「……!」
オービタルの報告に遊馬の目が輝くのとカイトの顔が驚愕に歪むのはほぼ同時だった。アストラルが、それを怪訝な顔で見つめている。彼は次に遊馬が取るであろう行動を理解したのだ。
アストラルだけじゃない。恐らく、この場の誰もが次の遊馬の言葉を予測していた。
そしてそれを阻めないであろうということも。
「だったら俺がこいつを連れて帰る」
「駄目だ」
「俺が面倒を見てやらなきゃ……きっと今、右も左もわからなくて困ってるんだ」
「駄目だ!」
「もうほっといてくれよ! カイトもシャークも、俺の友達を悪く言うな!!」
遊馬の悲痛な叫び声が響き渡って、そしてその後に沈鬱な静寂が訪れた。
「ともだちなんだよ。誰がどう言ったって、ベクター自身がそんなものは嘘だったって言ったって、俺にとって真月零が友達であるってことは変わらないんだ。俺にとって真月は確かに友達だった。今までも、今も、これからも。だから……」
「…………」
「俺は真月が困ってたら助ける。多分、その姿や性格がベクターでもそうしたと思う。馬鹿だって皆言うだろ。わかってるよ。俺はそれで馬鹿だって言われても、そうしたいんだ。俺が信じてる父ちゃんが教えてくれた心って、そういうものなんだ」
反論はもうなかった。今の遊馬の言葉は、アストラルらにもう何を言っても無駄だということをより強く強調づけたし、それに何より彼が静かに泣いていたからだ。遊馬は優しい子だった。彼が泣く時はいつも、その涙は誰かのために流された。
「遊馬くん、泣いているんですか」
「え、おれ……」
「駄目ですよ、僕なんかのために泣いちゃ。遊馬くんは笑ってなきゃ……」
「しんげつ」
「もし僕がいなくなることできみの心がもう痛まないのなら、僕は、あの人達が言うようにされても構わないんです」
「構うわけあるかよ!」
儚い手付きは、遊馬にはとても嘘には見えない。オービタルだって間違いなく記憶喪失だと言っていたのだ。ベクターの罠にもう一度嵌められたって今度は大丈夫だから、今助けなきゃいけない。そう強く願う。
こんなところに置いていかれたらすぐに死んでしまう。
「真月は俺の家に来るんだ。ばあちゃんも姉ちゃんも、オボミも、俺の家族はお前を悪く言ったりしないから。そしたらまた一緒に学校に行こう。俺はずっと、ずっと、お前のこと心配してたんだ」
頭を撫でてやるとくすぐったそうに目を細めて、そのまま彼は意識をまた落としてしまったようだった。二人の姿は、迷子になって寂しさから泣き疲れてしまった子供を優しくあやしている母親の構図によく似ている。
カイトとシャークが諦めから溜め息を吐いた。アストラルだけは、未だに真っ直ぐに強く、真月零の背中を見つめている。
◇◆◇◆◇
モールにあるカード・ショップは今日も学校帰りの生徒達で大変賑わっていて、ごった返している。
「俺の手、離すなよ」
腕を掴んでそう言うと真月は黙って頷いた。記憶を無くしてからというもの、真月は遊馬の言うことに従順だった。
それは養って置いてもらっているという引け目ばかりでなく、遊馬以外に誰も頼れる人間がいないということによる一種の強迫観念によるものだ。
今や遊馬を取り巻く人々のうちにおいて、真月零がベクターであるということを知らないのは当の真月ばかりで、よって彼らは皆真月に不信感を抱きそれを隠し切れずにいる。特にシャークや、時折遊馬の元を訪れるカイトからの風あたりは厳しく、彼らと会う度に真月は随分と精神を消耗してしまっているようだった。
雑然とカードが置かれているストレージ・ボックスの前まで人混みをかき分けてなんとか辿り着くとその一つを手に取りぱらぱらとカードを手繰っていく。一応箱ごとに種族やアイコンで分けてあるはずなのだが、利用客がいい加減に戻すので半分ぐらいしか目安になっていない。
「光属性っていうと、ライトロードとか、天使族かなぁ、やっぱ。カテゴリ合わせなくても属性合わせるか天使で合わせれば結構いけると思うけど」
「うーん? なんとなく、イメージから違うなぁ」
「まあほら、適当に見てろよ。とりあえずこれ」
ボックスの一つをぐいと押し付けると彼は素直にそれに手をつけ、カードを取り出して一枚一枚丁寧にチェックを始めた。《ライトロード・マジシャン ライラ》、《大天使クリスティア》、《ライトレイ・ソーサラー》、《エレキリン》、《セイクリッド・オメガ》……しかしそのどれもがお気に召さなかったようで、次々ボックスの中に押し戻されていく。
しばらく真月はそんなふうに黙々と作業を続けていた。しかし、二つ目のボックスに手をかけて半分ぐらい見終わったあたりで彼は突然手を止めてしまった。
「……遊馬くん」
「? なんだよ、どうかしたのか」
「これ……」
一枚のカードを恐る恐る差し出してくる。モンスターカードの山の中にあるまじき緑色の魔法カードだ。「なんだ紛れてたのか、よくあることだぜ」と言ってやると、真月は「違うんです」と首を振った。
「テキスト、読んでください」
「テキスト……?」
《忘却の都 レミューリア》。真月の細い指が冒頭の一文をなぞりあげる。――『このカードのカード名は 「 海 」として扱う』。
「うみ」
真月が拙い口運びでその言葉を紡いだ。
「遊馬くん、ぼく、海が苦手なんでしょうか」
唐突だ。突然現れた海という言葉に過剰に反応して恐怖している。
「なんでだ? そりゃお前は泳ぐの、下手だけど……」
「怖い。このカードが、すごく――」
《忘却の都レミューリア》を、震える手で遊馬からひったくって、首を振った。心臓を掻き抱くようにして彼は怯えていた。
そうして遊馬の手をすがるように掴む。 その姿は親に棄てられたみなしごが庇護を、救いを求めて神父の袖を握り締めるのによく似ていた。
「僕にとって一番恐ろしいものを思い出させてしまうような気がする」
真月の手が、レミューリアのカードをストレージの「フィールド魔法」ボックスにそそくさと押し込む。無数のフィールド魔法に紛れてその姿はすぐに彼の視界から消えてしまったようだったが、まだ震えは真月の体に残されていた。
今の真月にとって一番恐ろしいもの。彼が思い出す、つまり今忘れてしまっているのは自身がバリアン七皇のベクターであるという事実だ。もっと言えばそのベクターは遊馬を裏切り、殺そうとしていたのだということ。オービタルの検査で彼にはもう「真月零」としての記憶しか残されていないということははっきりしている。理由はわからないけどそうらしいのだ。その記憶がなくなった状態でも、あんなふうになるぐらい怖いことが真月=ベクターの図式の中には隠されているらしい。
(なんで、バリアン警察の警部、とかじゃなくてこの性格だけ残ってるんだろう)
また何もなかったみたいにカードを捲り出した真月を見ていると、ふとそんなことを考えてしまう。不機嫌そうな声で電話越しにカイトが教えてくれた話が遊馬の脳裏に甦った。確か彼は、遊馬の行動にぶちぶちと文句を連ねながらもこんなことを教えてくれたのだ。
『いいか、お前の頭では一度には理解がしきれないかもしれないが話しておいてやる。記憶喪失にはいくつかの典型パターンが存在しているんだ。最も有名なものがエピソード記憶の喪失だな。思い出だけを喪失し、それまでに蓄えた知識や技術は保持する。今回のケースはそれに似ているが、多少、ずれている。どうも人為的なにおいを感じる。
ここから先はオービタルの解析データに基づいた俺の推測になるが――恐らく奴は、自らの意志かまたはそれに準ずるものによって記憶を故意に制御しているんだ。そもそも、奴が意図的に演じていた人格である《真月零》だけが綺麗に上澄みとして残されるなんてことは有り得ん。何を狙ってのことだかは知らないが、この手の操作ならばキーワードなんかの類一発で簡単にその制御を解除出来る。かなり危険だ。また懐に入り込んで、警戒を解かせたところで襲う気かもしれない。とはいえお前は言っても聞かないからな……せめて、くれぐれも注意することだ』
「うん。サンキューカイト。心配させてごめん」
『まったく……わかっているのなら、あの時素直に忠告を聞いてあんなやつ捨て置けば良かったんだ』
「何度も言うけどそれは出来ない。俺の勘、大事なとこでは外れないんだぜ。それにさ、もし、ベクターが意図的に真月の記憶だけ残したんだとしたらそれにはちゃんとした意味があると思うんだ。ベクターだって、ちゃんと生きて呼吸して考えてるバリアン人なんだ。アリトやギラグがすごく優しくていいやつだったみたいに、ミザエルやドルベがものごとをきちんと考えて動く頭のいいやつだったみたいに、バリアン人だって俺達人間となんも変わらない。だからさ、カイト、俺……」
『……なんだ』
「ベクターはきっと後悔してたんだってそう思う」
『甘すぎる』
「かな」
『グラニュー糖にシロップを山ほど掛けてキャラメルと混ぜたよりも、甘い。俺だったらとうに決別を決めているところだ。とはいえ、それを失ったらお前は「九十九遊馬」ではなくなってしまうのだろうな』
「……かな?」
『少なくとも俺はそう考える。ハルトも同じように言うだろう』
その時会話はそこで終わってしまったのだが、未だに、カイトがはじめに言ったことはよくわからないままだ。ベクターは確かに遊馬を殺そうとした。おぞましい顔をして、罵り、蔑み、散々に遊馬やアストラル、仲間達を傷付けた。
でもだからといって、わざわざまた真月零を演じてまで回りくどいことをやろうとするものだろうか?
(俺には、殺されてやる気なんかさらさらないんだ)
もしもいつかベクターがもう一度遊馬を殺そうとしても、それが成功しないという根拠のない自信が遊馬にはあった。ベクターには徹底した性格の悪さと執念深さが備わっていたが、それでも血も涙もある普通の男に違いないのだ。
彼が真月零を演じていた時に見せた涙は全部目薬だったのだろうか? 笑顔は張り付けたマスクにすぎなかったのか。そうなのかもしれない。でも遊馬はそんなことはないと思うし、それに少なくとも背負った痛みや傷だけは混じりっけのない本物であったはずだった。
「ねえ遊馬くん、これなんかどうかな」
「おー、どれどれ」
遊馬を呼び止めた真月の手に握られているのは光属性のモンスターカードだ。
《シャイニング・ラビット》。真月零が、記憶喪失になる前、バリアン七皇のベクターだと明かす前に数少ないデュエルで用いていた「シャイニング」カテゴリのカード。
はっとする。あのカードが、こんなに普通に当たり前にカード屋に置いてあるだなんて。
「うん。僕、これがいいです。このウサギ、かわいいでしょう?」
「あ、ああ、うん。ちょっと目付きが悪い気がするけど……」
「そこがいいんですよ。僕、早くこのカードで遊馬くんとデュエルしてみたいなあ」
カゴに《シャイニング・ボンバー》、《シャイニング・スライ》、《シャイニング・ブリッジ》、《死者蘇生》などのカードを入れながら真月はとても楽しそうにそう言う。それは彼の偽らざる本心だろう。でもそれを考えると胸に一抹の不安が過る。
もしも遊馬が彼とのデュエルで《カオスナンバーズ39 希望皇ホープレイV》やヴィクトリーを召喚したり、《RUM‐リミテッド・バリアンズ・フォース》、《Vサラマンダー》なんかを使ったりしたら、彼とのこの平穏なぞ一瞬で崩壊してしまうのではないだろうか。それだけじゃない。さっきの《レミューリア》みたいに彼が拒否反応を示すカード(海にまつわるものが駄目なのだろうか?)を強引に見せ続けたりしたら、或いは……
(でも、もしそうなら。俺がそのきっかけは持っていた方がいいのかもしれない)
真月がもう二度と見たくないというぐらいの勢いでストレージに戻した《忘却の都 レミューリア》をこっそりと抜き取り、自分の会計用のカードに混ぜて一足先にレジに向かう。
たった一枚のフィールド魔法が増えただけで、遊馬は自分の持っているカゴが随分と重量を増したように感じた。このカードにはきっと何かがあるのだ。
それが自分達を破滅させ得るものなのか、それとも、新しい関係を築けるものなのか。願わくば後者であるようにと遊馬は祈った。もう二度と友達を失うなんてことは願い下げだ。
たとえ相手がもう一度自分を殺しに来るのだとしても。
| home |
・全七話構成のうちの一話目
・アニメの今後の進捗と大きな齟齬をきたす可能性が高いですが、パラレルの一つとしてご容赦ください。
街路樹の向こうから、蝉の鳴き声が聞こえてくる。
夏だ。少年の首筋を汗が一筋伝って、肌と制服の合間に滑り落ちていった。ミンミンミンミン、アブラゼミがうるさい。もう溶けだしてしまっているソーダ味のアイスバーを口に含んで遊馬はあーあ、と溜め息を吐いた。
「俺、基本的に夏は好きなんだけどさ、時々この暑さだけはかなわねえなあって思うんだ。どうにかなんねえかなぁ、確か今日の最高気温は……」
「三十一度。真夏日ですよ、遊馬くん」
「そうそれ! ほんっと堪らないぜここまでくると」
がぶりと残ったアイスにかぶりついて、そのままよく噛みもせずに口の中で適当に舐め転がして呑み込んでしまう。少し遅れて、「キーンってきた!」などと叫ぶ。そうなることはわかり切っているのだからもっと丁寧に食べればいいものを、彼は冷たいものはいつもこうなのだ。かき氷もアイスクリームもアイスバーも、ジュースに入っている氷も。なんでも最後に無理に呑み込んで痛い痛いと言っている。
物好きなんだろうか。そう思うが、遊馬本人は毎回真剣に痛がっているのできっと天然なのだろう。
「こういう日はさっさと家に帰って、エアコンの効いた涼しい部屋でデュエルに限るよなー」
「え、今日はまっすぐに家に帰るんですか?」
「あ、そっか。昨日カード屋行く約束したんだっけ。そろそろちゃんとデッキ持っときたいって言ってたもんな。悪い悪い」
あまり悪いとは思っていなさそうな声と顔で今やっとそれを思い出したふうにポンと手を叩く。今の今までうっかりと忘れていたのに違いない。でも遊馬に悪意があるわけじゃないし、それに急にそんなことを言い出した方にも責任はあるだろう。今日がとびきり蒸し暑くて過ごしにくいことは確かだし、遊馬は悪くない。
「いえ、そんな。遊馬くんが帰りたいのならそれでいいんです。僕なんて居候の身なんですし……」
「いや、こういうのって後回しにするのあんまりよくないんだ。ほらあれ、『思い立ったが吉日』ってやつ! だから予定通りカード屋行っちゃおうぜ。運よくモールへの分かれ道からそんなに遠いところまで来てないしさ」
「それじゃ、行ってくれるんですか?」
「もちろん。光属性、組みたいんだよな」
「はい、六つの属性の中で一番光属性が好きだなって思って。特にこれってカテゴリはないんですけども」
「んーまあ、カテゴリなんてそれこそ海の中泳いでる魚みたいにいっぱいあるし。店に行ってぴんときたの、買えばいいんじゃないかな」
ソーダバーの木の棒を噛み締めるようにしてぶらぶら上下させている。それからぺっとそれを吐き出して一瞥し、遊馬はちぇっと残念そうに眉を顰めた。棒の中央にでかでかと焼き込みで印字された「ハズレ」の文字。この夏に入ってから彼は毎日のようにこのお気に入りのソーダバーを食べているが、今のところ一度もその文字が「アタリ」だったことはない。
そのハズレやらアタリやらの文字列が物珍しかった頃に彼に一度尋ねてみたことがある。もしも「アタリ」が出たらどんないいことがあるのか、或いは、どんなふうに嬉しいのか。すると、その時遊馬はちょっと考えてから人差し指をぴんと伸ばして、上手いことを閃いたとでも言いたげな顔でこんなことを教えてくれた。――「アタリが出たら、きっと、真月にいいことがあるぜ!」
その時から、真月零はずっと彼の隣で待っている。
「なあ真月。なんかさ、これだけは苦手―っての、ある」
「苦手、ですか」
「うん。うっかり買っちゃっても、困るだろうし」
「そうですね。何か、敢えて言うのだとしたら……」
遊馬がソーダバーの「アタリ」棒を手に入れて、何か彼の言うところの「いいこと」が起こるかもしれない時を、待っている。
「闇属性の統一カテゴリが僕、あまり好きじゃないんです」
蝉の鳴き声がまだ、うるさい。二人で並んで通り過ぎたモールへの曲がり角から遠目に向日葵畑が見えた。無数の向日葵が太陽の方を懸命に追いかけて首を折り曲げている。太陽を追いかけるサン・フラワーたち。真月はその花たちが遊馬に群がったり、追いかけてきたりして集まっている彼の友人たちのようだなとぼんやり考えた。九十九遊馬という太陽に追い縋ってくる花たち。
遊馬を楽しそうだったり嬉しそうだったりしながら見る一方で隣の自分を嫌疑している視線が見え隠れして、真月はなかなか彼らのことを好きになれないでいる。
◇◆◇◆◇
「――何故そいつを助けた。お前のいつもの底なしの、呆れる程愚鈍なお人よしだとしても、だ――そうやって後生大事そうに抱えているのはどうしてだ? このことがわからない程、お前は馬鹿じゃなかったはずだろう遊馬」
「でも、シャーク、」
「でもじゃない。いいか。そいつはベクターなんだぞ! どんな姿をしていても!」
シャークの怒号が響き渡る。だがその場に居合わせている者誰一人として彼に異を唱える姿勢は持ち合わせていないようだった。口を堅く引き結んで腕組みをしたままのカイトも、厳しい面持ちで浮かんでいるアストラル、シャークの隣で立っている璃緒、一歩引いた位置で立ち尽くしている小鳥。その誰もが「どうして」という顔をして遊馬をまるで尋問でもするかのように取り囲んでいる。
遊馬はただ一人この場で孤立して、その小さな少年の腕の中にぐったりとした体を一つ抱え込んでいた。オレンジ色の髪の毛はすっかり荒れ果てていて、体中に擦過傷が確認出来る。紫の眼球が嵌っている瞳はぴったりと閉じられ、力なく項垂れて遊馬にその全身を預け眠っていた。
遊馬が抱えている人物が誰なのかは言うまでもない。真月零の姿をした(それはつまり、彼が本来の姿を維持していられなくなる程に衰弱し切っているということを示している)ベクターだ。
「お前を散々に騙し、こっぴどく裏切り、汚ねえ罠に次々嵌めてお前を嘲っていた下衆野郎だ。お前が身を挺して庇いだてする必要なんかどこにもなかった。助ける必要もなかった。聞いていただろう、こいつが言ったことを。自業自得なんだ。バリアン世界とやらの神に契約してその命を差し出したのはこいつ自身の意志によるものだ。……それも、遊馬、お前を殺すために」
「遊馬を殺すために」。シャークが復唱した言葉がベクターの声で遊馬の頭の中でリフレインする。ぎゅうと抱いた傷だらけの体を強く握り締めて遊馬は唇を噛んだ。そのことは嫌と言う程わかっているつもりだった。
ベクターは真実、九十九遊馬を殺すためだけに危険な賭けに出ていたのだ。それはデュエルが始まる前にベクターの口から直接語って聞かされた揺るぎようのない事実である。「アストラルもバリアン世界もどうなろうが知ったこっちゃねえ。ぶっちゃけどうだって構いやしねぇんだよォ、そんなもんは! 俺の望みはただ一つ。九十九遊馬ァ! テメェだけは俺がこの手で握り潰してやる!! そのために俺はバリアンの神に命を捧げた!!」……ベクターは確かにそう言っていた。
宣告を突き付けるベクターの姿に一切の慈悲はなく、また交渉の余地も残されてはいなかった。彼の中には焦りがあった。そして、遊馬に対する並々ならぬ憎悪があった。
そんなことはわかっている。
「でもだからって! 助けることが出来るのなら見殺しにしちゃダメだ!」
「どこまで好き者なんだ?! そこまでの代償を他ならぬお前が支払う理由なんかどこにもない!!」
「ある!」
それでも、断言した。どんなに仲間達に糾弾されても、ベクターが恩を数億倍の仇で返そうとも、遊馬は彼を助けたかったのだ。
ベクターの体を支える他ならぬ遊馬自身も、満身創痍と言って差し仕えない程に傷付いている。洋服の端々が破れ、ほつれ、デュエルによって現実にフィードバックされた無数の傷跡がその下から見え隠れしていた。それだけじゃない。ドン・サウザントとの契約によりその命を燃やし尽くさんとしていたベクターを無理矢理に救出した反動で目に見えないダメージがその小さな体に蓄積している。
腰に備え付けられたデッキケースから一枚のカードがその姿を覗かせていた。遊馬がバリアンの神が造り上げた契約の理を捻じ曲げる為に用いた奇跡の力だ。《ヌメロン・フォース》、過去現在未来その全てを司る《ヌメロン・コード》の力の片鱗を宿すものにして、遊馬にとっての、真月零との間に結ばれた友情の形でもあった。
アストラルが遊馬の気持ちを汲み取って受け入れてくれた、絆の今の在り方だ。
「やり直したい、って言ったらそれは……おかしいのかもしれないけど。俺は真月零を信じてる。今でも。だからベクターとも、もう一度……」
「くだらん夢想だ」
「カイトまで」
「お前の甘えが誰にだって通用するわけじゃない。俺やクリス、その兄弟達にはまだ情があり、理由があり、確かに対話による説得が可能だっただろう。だがベクターの場合はそのどのケースとも通じ合わない。この見下げ果てた男には一切の情けがなく、その清々しい屑っぷりには感動を覚えるぐらいだ。まだ意識を取り戻していない今なら引き返せる。棄てて来い。そんなものは」
捨て猫を元の場所に戻して来いとでも言うような気軽さで無情に言い放つ。でもいやだ。そんなの、駄目だ。遊馬の中の直感がそう告げている。
「……俺に真月は捨てられない」
「やはりな。そんなところだろうと思ってはいた」
「友達を見殺しにしろって言うのかよ!」
「そいつは友達でもなんでもない。敵だ」
カツカツと足音を響かせてカイトがこちらに向かってくる。遊馬は小さく怯えてベクターの体をカイトから守るように抱き寄せた。
その時だ。振動に揺さぶり起こされたのだろうか、今まで微動だにもせず死んだように眠っていた彼の体がぴくりと痙攣した。カイトとシャークが一斉に警戒の構えを取る。衰弱し切っているとはいえ、やはりベクターのまじりっけのない悪意は馬鹿にならない恐怖だ。
ベクターが口を開く。青ざめた唇は僅かに震えているように遊馬には見えた。
「……ゆうまくん?」
――か細い声だ。
のろのろと目蓋が開き、アメジスト色の丸い瞳が姿を覗かせる。そのさまは、つい数刻前まで遊馬を睨みつけていたあの狂気の瞳とはまるで似ても似つかなかった。遊馬が一番近くでよく見ていた、あのおっちょこちょいな少年のものだ。
「しんげつ」
「ああ、よかった、遊馬くん。遊馬くんですよね。ぼく、どうしたんだろう。なんだか体が怠くって……」
何か様子が変だ。そもそも彼は何故「ゆうまくん」と柔らかく名前を呼んで「ぼく」と自分を呼称するのだろう? 今更ベクターの方に真月零を騙るメリットなどもう何もない。ましてやこの衰弱し切った体で、罪を認めて保護を求めるような殊勝な性格であるのならばそもそもベクターは遊馬にあんなふうに接触を図ったりなんかはとても出来なかったはずだ。だというのに顔も、声も、態度もそのどれもが違うことなく「真月零」のもので、どこにも「ベクター」を見出すことが出来ない。
まるでベクターとしての本性がぽっかりと陥没して、偽りの人格である「真月零」だけが残されてしまったかのようなそんな違和感だ。
遊馬くん? ベクター、いや、真月が首を傾げる。愛らしい少年の声音。そんなことがあるはずがないのに、遊馬は今にも「真月が還ってきた」という錯覚に襲われそうだった。
「何か……覚えてないのか」
「ごめんなさい。ぼく、本当に何もわからなくて。ここはどこなんですか? 遊馬くんは、どうしてそんなに傷付いて……」
「何でもないんだ。本当に、何でも」
「……無理、しちゃダメですよ、遊馬くん。それで、あの怖い人は……?」
「オービタル、今すぐそいつの脳波をスキャンして状態を測れ!」
「カシコマリ!」
真月がそう遊馬に尋ねるのとカイトの鋭い命令が飛ぶのは、ほぼ同時だった。
オービタルが俊敏に動いてベクターに迫ってくる。遊馬があっと思った時には既に遅く、気が付けば真月は遊馬の腕の中から奪われてしまっていた。まだ意識が朦朧としているふうの真月をオービタルのアームが取り押さえ、無数のコードが中から伸びてきてその体に張り付く。単調な機械音。時折小さく聞こえる呻き声は、誰が見てもベクターというよりは「真月零」のものに近いよう思える。
「カイト! 何するんだよ!」
「信頼は確かに美徳だが、少しは疑いというものを覚えろ。見てわからないのか、検査だよ」
「こいつは今疲れてるんだ」
「何度言えばわかる。真月零はベクターなんだ!」
乾いた音が響いて、遊馬の体が仰け反った。カイトが我慢ならずに遊馬を叩いたのだ。何が起こったのかが上手く掴めずに遊馬は赤く腫れた頬を抑えることもせずに呆然としている。
カイトにこうして叩かれるのは、真月零がベクターに連れ去られたと思い込んで感情を暴走させ、真月が、真月が、としきりに繰り返していたあの時以来のことだった。
「お前には失望した」
カイトが冷たく言った。
オービタルの検査は簡易的なものだったようで、そんなやり取りの間に案外あっさりと検査自体は終わったようだ。コードが引っ込み真月の体が解放される。反射的にその体を受け止めて、遊馬は頭の中で反響するカイトの言葉の意味を考えていた。
カイトは怒っているのだろうか。失望、というのはどういう意味なのだろう。近頃はずっとカイトに優しくされていて、遊馬はそれを忘れていたのかもしれない。天城カイトは、ただ盲目的に優しくしてくれるわけじゃない、ちゃんとした厳しさを持っている男だ。
だから遊馬に向けた冷たい言葉も、遊馬を思いやってのことなのだろうと頭ではわかっている。また破滅するのか、と彼は問い掛けているのだ。
オービタルがカイトに駆け寄る。カイトは遊馬と真月を一瞥して報告を促した。
「結果は」
「間違いありませんカイト様、記憶喪失です。脳に目立つ損傷はありませんが、記憶中枢にエラーが生じている模様」
「……!」
オービタルの報告に遊馬の目が輝くのとカイトの顔が驚愕に歪むのはほぼ同時だった。アストラルが、それを怪訝な顔で見つめている。彼は次に遊馬が取るであろう行動を理解したのだ。
アストラルだけじゃない。恐らく、この場の誰もが次の遊馬の言葉を予測していた。
そしてそれを阻めないであろうということも。
「だったら俺がこいつを連れて帰る」
「駄目だ」
「俺が面倒を見てやらなきゃ……きっと今、右も左もわからなくて困ってるんだ」
「駄目だ!」
「もうほっといてくれよ! カイトもシャークも、俺の友達を悪く言うな!!」
遊馬の悲痛な叫び声が響き渡って、そしてその後に沈鬱な静寂が訪れた。
「ともだちなんだよ。誰がどう言ったって、ベクター自身がそんなものは嘘だったって言ったって、俺にとって真月零が友達であるってことは変わらないんだ。俺にとって真月は確かに友達だった。今までも、今も、これからも。だから……」
「…………」
「俺は真月が困ってたら助ける。多分、その姿や性格がベクターでもそうしたと思う。馬鹿だって皆言うだろ。わかってるよ。俺はそれで馬鹿だって言われても、そうしたいんだ。俺が信じてる父ちゃんが教えてくれた心って、そういうものなんだ」
反論はもうなかった。今の遊馬の言葉は、アストラルらにもう何を言っても無駄だということをより強く強調づけたし、それに何より彼が静かに泣いていたからだ。遊馬は優しい子だった。彼が泣く時はいつも、その涙は誰かのために流された。
「遊馬くん、泣いているんですか」
「え、おれ……」
「駄目ですよ、僕なんかのために泣いちゃ。遊馬くんは笑ってなきゃ……」
「しんげつ」
「もし僕がいなくなることできみの心がもう痛まないのなら、僕は、あの人達が言うようにされても構わないんです」
「構うわけあるかよ!」
儚い手付きは、遊馬にはとても嘘には見えない。オービタルだって間違いなく記憶喪失だと言っていたのだ。ベクターの罠にもう一度嵌められたって今度は大丈夫だから、今助けなきゃいけない。そう強く願う。
こんなところに置いていかれたらすぐに死んでしまう。
「真月は俺の家に来るんだ。ばあちゃんも姉ちゃんも、オボミも、俺の家族はお前を悪く言ったりしないから。そしたらまた一緒に学校に行こう。俺はずっと、ずっと、お前のこと心配してたんだ」
頭を撫でてやるとくすぐったそうに目を細めて、そのまま彼は意識をまた落としてしまったようだった。二人の姿は、迷子になって寂しさから泣き疲れてしまった子供を優しくあやしている母親の構図によく似ている。
カイトとシャークが諦めから溜め息を吐いた。アストラルだけは、未だに真っ直ぐに強く、真月零の背中を見つめている。
◇◆◇◆◇
モールにあるカード・ショップは今日も学校帰りの生徒達で大変賑わっていて、ごった返している。
「俺の手、離すなよ」
腕を掴んでそう言うと真月は黙って頷いた。記憶を無くしてからというもの、真月は遊馬の言うことに従順だった。
それは養って置いてもらっているという引け目ばかりでなく、遊馬以外に誰も頼れる人間がいないということによる一種の強迫観念によるものだ。
今や遊馬を取り巻く人々のうちにおいて、真月零がベクターであるということを知らないのは当の真月ばかりで、よって彼らは皆真月に不信感を抱きそれを隠し切れずにいる。特にシャークや、時折遊馬の元を訪れるカイトからの風あたりは厳しく、彼らと会う度に真月は随分と精神を消耗してしまっているようだった。
雑然とカードが置かれているストレージ・ボックスの前まで人混みをかき分けてなんとか辿り着くとその一つを手に取りぱらぱらとカードを手繰っていく。一応箱ごとに種族やアイコンで分けてあるはずなのだが、利用客がいい加減に戻すので半分ぐらいしか目安になっていない。
「光属性っていうと、ライトロードとか、天使族かなぁ、やっぱ。カテゴリ合わせなくても属性合わせるか天使で合わせれば結構いけると思うけど」
「うーん? なんとなく、イメージから違うなぁ」
「まあほら、適当に見てろよ。とりあえずこれ」
ボックスの一つをぐいと押し付けると彼は素直にそれに手をつけ、カードを取り出して一枚一枚丁寧にチェックを始めた。《ライトロード・マジシャン ライラ》、《大天使クリスティア》、《ライトレイ・ソーサラー》、《エレキリン》、《セイクリッド・オメガ》……しかしそのどれもがお気に召さなかったようで、次々ボックスの中に押し戻されていく。
しばらく真月はそんなふうに黙々と作業を続けていた。しかし、二つ目のボックスに手をかけて半分ぐらい見終わったあたりで彼は突然手を止めてしまった。
「……遊馬くん」
「? なんだよ、どうかしたのか」
「これ……」
一枚のカードを恐る恐る差し出してくる。モンスターカードの山の中にあるまじき緑色の魔法カードだ。「なんだ紛れてたのか、よくあることだぜ」と言ってやると、真月は「違うんです」と首を振った。
「テキスト、読んでください」
「テキスト……?」
《忘却の都 レミューリア》。真月の細い指が冒頭の一文をなぞりあげる。――『このカードのカード名は 「 海 」として扱う』。
「うみ」
真月が拙い口運びでその言葉を紡いだ。
「遊馬くん、ぼく、海が苦手なんでしょうか」
唐突だ。突然現れた海という言葉に過剰に反応して恐怖している。
「なんでだ? そりゃお前は泳ぐの、下手だけど……」
「怖い。このカードが、すごく――」
《忘却の都レミューリア》を、震える手で遊馬からひったくって、首を振った。心臓を掻き抱くようにして彼は怯えていた。
そうして遊馬の手をすがるように掴む。 その姿は親に棄てられたみなしごが庇護を、救いを求めて神父の袖を握り締めるのによく似ていた。
「僕にとって一番恐ろしいものを思い出させてしまうような気がする」
真月の手が、レミューリアのカードをストレージの「フィールド魔法」ボックスにそそくさと押し込む。無数のフィールド魔法に紛れてその姿はすぐに彼の視界から消えてしまったようだったが、まだ震えは真月の体に残されていた。
今の真月にとって一番恐ろしいもの。彼が思い出す、つまり今忘れてしまっているのは自身がバリアン七皇のベクターであるという事実だ。もっと言えばそのベクターは遊馬を裏切り、殺そうとしていたのだということ。オービタルの検査で彼にはもう「真月零」としての記憶しか残されていないということははっきりしている。理由はわからないけどそうらしいのだ。その記憶がなくなった状態でも、あんなふうになるぐらい怖いことが真月=ベクターの図式の中には隠されているらしい。
(なんで、バリアン警察の警部、とかじゃなくてこの性格だけ残ってるんだろう)
また何もなかったみたいにカードを捲り出した真月を見ていると、ふとそんなことを考えてしまう。不機嫌そうな声で電話越しにカイトが教えてくれた話が遊馬の脳裏に甦った。確か彼は、遊馬の行動にぶちぶちと文句を連ねながらもこんなことを教えてくれたのだ。
『いいか、お前の頭では一度には理解がしきれないかもしれないが話しておいてやる。記憶喪失にはいくつかの典型パターンが存在しているんだ。最も有名なものがエピソード記憶の喪失だな。思い出だけを喪失し、それまでに蓄えた知識や技術は保持する。今回のケースはそれに似ているが、多少、ずれている。どうも人為的なにおいを感じる。
ここから先はオービタルの解析データに基づいた俺の推測になるが――恐らく奴は、自らの意志かまたはそれに準ずるものによって記憶を故意に制御しているんだ。そもそも、奴が意図的に演じていた人格である《真月零》だけが綺麗に上澄みとして残されるなんてことは有り得ん。何を狙ってのことだかは知らないが、この手の操作ならばキーワードなんかの類一発で簡単にその制御を解除出来る。かなり危険だ。また懐に入り込んで、警戒を解かせたところで襲う気かもしれない。とはいえお前は言っても聞かないからな……せめて、くれぐれも注意することだ』
「うん。サンキューカイト。心配させてごめん」
『まったく……わかっているのなら、あの時素直に忠告を聞いてあんなやつ捨て置けば良かったんだ』
「何度も言うけどそれは出来ない。俺の勘、大事なとこでは外れないんだぜ。それにさ、もし、ベクターが意図的に真月の記憶だけ残したんだとしたらそれにはちゃんとした意味があると思うんだ。ベクターだって、ちゃんと生きて呼吸して考えてるバリアン人なんだ。アリトやギラグがすごく優しくていいやつだったみたいに、ミザエルやドルベがものごとをきちんと考えて動く頭のいいやつだったみたいに、バリアン人だって俺達人間となんも変わらない。だからさ、カイト、俺……」
『……なんだ』
「ベクターはきっと後悔してたんだってそう思う」
『甘すぎる』
「かな」
『グラニュー糖にシロップを山ほど掛けてキャラメルと混ぜたよりも、甘い。俺だったらとうに決別を決めているところだ。とはいえ、それを失ったらお前は「九十九遊馬」ではなくなってしまうのだろうな』
「……かな?」
『少なくとも俺はそう考える。ハルトも同じように言うだろう』
その時会話はそこで終わってしまったのだが、未だに、カイトがはじめに言ったことはよくわからないままだ。ベクターは確かに遊馬を殺そうとした。おぞましい顔をして、罵り、蔑み、散々に遊馬やアストラル、仲間達を傷付けた。
でもだからといって、わざわざまた真月零を演じてまで回りくどいことをやろうとするものだろうか?
(俺には、殺されてやる気なんかさらさらないんだ)
もしもいつかベクターがもう一度遊馬を殺そうとしても、それが成功しないという根拠のない自信が遊馬にはあった。ベクターには徹底した性格の悪さと執念深さが備わっていたが、それでも血も涙もある普通の男に違いないのだ。
彼が真月零を演じていた時に見せた涙は全部目薬だったのだろうか? 笑顔は張り付けたマスクにすぎなかったのか。そうなのかもしれない。でも遊馬はそんなことはないと思うし、それに少なくとも背負った痛みや傷だけは混じりっけのない本物であったはずだった。
「ねえ遊馬くん、これなんかどうかな」
「おー、どれどれ」
遊馬を呼び止めた真月の手に握られているのは光属性のモンスターカードだ。
《シャイニング・ラビット》。真月零が、記憶喪失になる前、バリアン七皇のベクターだと明かす前に数少ないデュエルで用いていた「シャイニング」カテゴリのカード。
はっとする。あのカードが、こんなに普通に当たり前にカード屋に置いてあるだなんて。
「うん。僕、これがいいです。このウサギ、かわいいでしょう?」
「あ、ああ、うん。ちょっと目付きが悪い気がするけど……」
「そこがいいんですよ。僕、早くこのカードで遊馬くんとデュエルしてみたいなあ」
カゴに《シャイニング・ボンバー》、《シャイニング・スライ》、《シャイニング・ブリッジ》、《死者蘇生》などのカードを入れながら真月はとても楽しそうにそう言う。それは彼の偽らざる本心だろう。でもそれを考えると胸に一抹の不安が過る。
もしも遊馬が彼とのデュエルで《カオスナンバーズ39 希望皇ホープレイV》やヴィクトリーを召喚したり、《RUM‐リミテッド・バリアンズ・フォース》、《Vサラマンダー》なんかを使ったりしたら、彼とのこの平穏なぞ一瞬で崩壊してしまうのではないだろうか。それだけじゃない。さっきの《レミューリア》みたいに彼が拒否反応を示すカード(海にまつわるものが駄目なのだろうか?)を強引に見せ続けたりしたら、或いは……
(でも、もしそうなら。俺がそのきっかけは持っていた方がいいのかもしれない)
真月がもう二度と見たくないというぐらいの勢いでストレージに戻した《忘却の都 レミューリア》をこっそりと抜き取り、自分の会計用のカードに混ぜて一足先にレジに向かう。
たった一枚のフィールド魔法が増えただけで、遊馬は自分の持っているカゴが随分と重量を増したように感じた。このカードにはきっと何かがあるのだ。
それが自分達を破滅させ得るものなのか、それとも、新しい関係を築けるものなのか。願わくば後者であるようにと遊馬は祈った。もう二度と友達を失うなんてことは願い下げだ。
たとえ相手がもう一度自分を殺しに来るのだとしても。
| home |