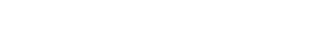01 心ある兵器
——だから、どうかあなたは私のことを殺してくださいね。
かれが死んだ。男の見ている前で、それも触れ合うほど近く、かれは己の喉にナイフを突き立てた。突然の終わり。しかし巧妙に仕組まれた自死。入念に、かれ自身の手で、逃れられぬ結末になるよう丁寧に描かれた、まるで舞台の演出みたいな悲劇のかたち。
「ほんとは」
かれの残り香が呻く。ほんの数秒前は土の上にいたくせに、今はもう墓の中からしか彼の声は響かない。墓という概念の中に己を貶めた亡霊は、口なしの亡者のくせして、生きていた頃よりも雄弁に弁舌をふるい、男の心臓に目に見えぬいばらを突き刺す。
「あなたに——ころしてほしかったのに……」
一番星を見つけた幼子のようにきらきらした目をしながら。
そうして彼はいなくなる。救世の旗を見いだされた偶像、かつてはジャンヌ・ダルクと揶揄さえされたもの、世界に作られたもの、因果でその身を象った悪魔、この世の理を外れた天使、〝カイ〟と呼ばれた少年は、5189065200001982回目の自殺をする。
男を呪い、世界の因果を道連れに、この世全てを——滅ぼすために。
◇◆◇◆◇
だって神様は死ななくちゃいけないでしょう? と、いつか天使は目を細めて仰いました。
「神様がこの地上に生きていたら、人は神に頼り、己の足で立ち上がらなくなってしまうでしょう。ですから、神は天界へ隠居なさったのです。でも天界というのは、この世に生きる人間が死して召される場所。それはつまり、神の死こそが地上の繁栄における必然である……ということに他なりません」
「不在証明ですらない、既死証明ときたか。それも極めて敬虔な信仰に基づいた。相変わらず救われねぇ思考してやがるな。ソイツも父親譲りか、坊や」
「さあ……父の考えていることは、私にはよくわからないので。あなたの方がいくらも詳しいでしょう」
「は……親子揃ってとんだ碌でなしどもだよ」
酷い言い様ですね、とむっとした調子で顔をしかめた少年を放って男は部屋の外へ歩いて行ってしまう。机の上には未決済の書類が山ほど残っていたが、懸念した様子さえなさそうだった。
あの男はいつもそうだ。興味関心があるものごとへの集中力は他の追随を許さないが、そうでないものごとなど、彼にとっては路傍の石ころにも劣るのである。それを差し引いても優秀な人材ではあったが、そういうところは、まるで彼女と正反対だ。だから、きっと彼女は父親ではなく母親に似たのだろうな、と少年はいつも思う。
諦めがちに書類を手に取ると、男と入れ替わるように一人の少女が部屋に入ってくる。つい今しがた思い浮かべたばかりのその姿を認め、少年はぱっと顔を輝かせると書類を全て机の上に置き直した。先ほど男に神の証明について語っていた時とはあまり似つかない、年相応の表情だ。
その理由は、少女と、それから彼女が手に持っているティーセット一式にある。
「ディズィー! お茶の時間ですか? うれしいな、ちょっと仕事に嫌気が差してきた頃だったので……見てください、この山。これ全部、巡り巡って私にお鉢が回ってきたものなんですよ……」
「これ、全部が……ですか? それじゃお父さん、またカイさんに押しつけたんだ。後で言って聞かせます、そのぐらい自分でやって! って。何も言わないよりは、きっとましですよ」
「はは……そうだといいんですけどね」
苦笑すると少年……カイは腰を上げ、デスクからソファの方へいそいそと席を移した。
この世界は、もう随分と長い間戦争の中に身を置いている。人に反旗を翻した生体兵器・GEARとそれに抵抗する人類との百年戦争、人々が「聖戦」と呼ぶもの。
戦争が始まって数十年が経った頃、無作為に増え続けてゲリラ的な戦いを仕掛けてくるギアに追い詰められいよいよ困窮した人類は、そこでようやく小競り合いを止めて世界規模で手を取り合うことを決定し、本格的な対ギア組織を創設した。それが二一一五年のグリンデルヴァルト条約に基づいて発足したこの組織、聖騎士団である。カイとディズィーも、未成年ながらそこに籍を置くれっきとした構成員の一人だ。
聖騎士団は基本的に子供を内部に置かない組織だが、そこに二人が在籍していられるのには二つ理由がある。一つは、彼らが抜きん出た力を持った戦略的に価値のある存在だということ。そしてもう一つが、二人それぞれの父親が組織にとって重要な存在だということだ。
今年で創設から五十八年になるこの組織だが、そこに創設期から携わり、現在も変わらず要職に就いている存在が二人いる……というのは、団内において公然と周知されている事実である。技術顧問の飛鳥=R=クロイツ。それから、技術顧問補佐兼軍部大隊長のフレデリック。「ある特殊な方法」を用いて創設期……或いはそれ以前から変わらぬ姿で聖戦終結の方法を模索し続けている二人は、聖騎士団という組織の要だ。これまでもこれからも、彼らなくして騎士団は立ちゆかないだろう。
そんな人物をそれぞれ父に持つ二人だが、かといって、親の七光りだとか、そういう心ない誹りを受けることは今はもうない。昔、それこそ入ったばかりの十の頃は散々言われていたけれど、一年も経たないうちにぱたりと途絶えてしまった。
人々は、戦場に立つ少年少女の姿とその下に積み上がる骸の山を指して、口々にこう囁き合っている。彼らは戦場の天使——或いは、悪魔、なのだと。
「先日、またイングランドの方で大規模な襲撃があったでしょう。〝たまたま〟父さんが開発してた新式装備を〝幸運なことに〟フレデリックが持っていたので掃討が出来た、みたいなことを聞きましたけど、どう考えても実験段階のものをいきなり実戦で使わせたとしか思えないんですよね……。それ関連の書類の決裁で、今手間取ってるんです。ディズィーは……何か聞いていませんか? 確か貴方は該当作戦に参加していましたよね」
「ええ、お父さんの手伝いで。カイさん、あの時はローマの方で動けなかったですものね」
「まあ、こっちはこっちで父さんの無茶ぶりに付き合わされてしまいまして……。あのひと本当に滅茶苦茶ですよ……。でも、聖戦を早く終わらせたい、っていうのは、わかるんですけどね」
「……はい。お父さんも……お母さん……ううん、ジャスティスを、一日も早く解放したい、って。ずっと、言ってる」
お母さん、と口にした瞬間、少女がカップを持つ手が僅かに震えたことを、カイは見逃さなかった。ディズィーの母・アリアは、ある手違いから理性を失い、人類の怨敵になった。アリアの恋人であったフレデリックと彼ら二人の親友だった飛鳥は、アリアを取り戻すために聖騎士団を作った。聖戦を終わらせることは、フレデリックと飛鳥にとっては大義などではなく、もっとずっと、個人的な願いなのだ。でもこれは家族だけの秘密だから……二人の本当の気持ちは、カイとディズィーしか知らない。
「本当、戦争なんて、世界じゅうからなくなってしまえばいいんです」
カイが呟く。ティーカップの中でたゆたう紅茶は透き通っていたが、底に茶こしで濾しきれなかった茶葉が僅かに沈んでいて、彼の心を映し出しているみたいだった。カイは大人びて頭も良いが、けれどまだ、十四歳の少年なのだ。
「本当は戦争の中に身を置くべきじゃないし、ギアを殺すことを覚えさせたくはなかったよ」
……そんなことを、十になって聖騎士団に正式に身を置くと告げた時、珍しく弱り顔をした飛鳥が言っていた。
それはディズィーもきっと同じだ。ディズィーなんか、失った恋人によく似た一人娘である分、父親の反発もより強かったであろうことは想像に難くない。
それでも彼女が自らの意思で立ち上がり、決断をしたこと自体は、実を言うとカイは好ましいと思っている。自分と似た境遇である彼女に共感しているのもあるし、そういう芯の強さに、幼いながらに真剣に惹かれたからだ。でもやっぱりカイも、彼女に戦って欲しくないと考えることはある。彼女は強い。心も、力も、両方、きっとカイなんかよりずっと強い。それに甘えてしまって、守ってやれなくて、いざという時は彼女の父親任せになってしまうのが、歯がゆくて仕方がない。
そんな葛藤を誤魔化すように首を振ると、カイは努めて明るい声を出して、違う話題を彼女に振った。
「ところで、ディズィーは紅茶を淹れるのが上手ですよね」
「そう……ですか? だったら、嬉しいな。カイさんのために練習したんだから。お父さんはあんまり紅茶は飲まないもの」
「ああ、彼はコーヒー党だから」
「飛鳥さんはグリーンティー派でしょう?」
「うん。改めて言われるとてんでばらばらですね、私たち」
「ふふ。でも私は、紅茶党ですよ」
「え……」
「カイさんのために、一番たくさん淹れてるからかな。気がついたら、私も自然と」
ディズィーがはにかむ。その顔を見て、カイはかあっと頬を赤くした。存外にうぶなのだ。少女に歯の浮くような台詞を言うことはなんてことなく出来るのに、こうして少女から言葉を貰うと、すぐに茹だってしまう。
「ねえ、カイさん」
そんな少年の姿に幸せそうに微笑んで、少女が歌うように彼の名前を呼ぶ。
「次の遠征は、わたしたち、一緒ですか?」
「はい。明日から、スウェーデンへ。父さんとフレデリックは再度イングランドの事後調査に行く手はずになっていますから……しばらく本部の最高責任権限は、クリフ様に委譲かな」
「そうなんだ。二人揃って前線に出るのは、久しぶりですね」
「言われてみれば……本当だ。ううん、半年ぶりぐらい、ですか? 確かそれぐらいの時に……」
「アメリカへ行きましたよ。お父さんの故郷だからって、わたしたち、無理を言って着いていったでしょう」
「ふふ、そうですね。フレデリックはなんだか嫌がってましたけれど」
少女の笑顔につられるようにして、少年も微笑む。二人して花が咲いたみたいに、手と手を取り合い、見つめ合って、指先を交わす。
「私、戦いは好きじゃないです」
「……知っています」
「でも、誰かが傷付かなくちゃ、争いは終わらない」
「ええ……」
「だったら、傷付くのは、わたしたちで終わりにしたい。……約束ですよ、カイさん」
「もちろん、ディズィー」
その手で、彼らは明日ギアを殺す。今日触れ合った指先は一昨日は血にまみれていて、薔薇色の頬も明後日には色を失っている。戦場に立っている間、二人は少年であることと少女であることを放棄する。彼らは子供だ。けれど何よりこの救われない戦争を終わらせるための兵器であることを、彼ら自身が一番よく理解しているのだ。
◇◆◇◆◇
子供達が生まれた時、抱いたのは狂喜と葛藤だった。
聖戦が始まるよりずっと昔、未だ法力が発見される以前の生まれである飛鳥とフレデリックが、聖戦が始まって百年近くが過ぎ去った今になって自然生殖で子供を得る方法などあるはずがない。カイはともかく、ディズィーなど、とうの昔に発狂して人類の宿敵となったはずのアリアの娘なのだ。二人をこの世に生み出すことは、飛鳥とフレデリックにとって非常に大きな決断だった。今でも、その選択が正しかったのかどうか迷いを抱えているほどに。
ディズィーはギアの血を引くハーフギアだ。正真正銘フレデリックとアリアの娘だが、様々な事情が絡み合い「卵」としてジャスティスにより残されていたものが、長い間、孵化しないように冷凍保存されていた。
卵自体は、ジャスティスが人類に反旗の宣戦布告をする前に生み落とされたもので、その時点で孵すことは無論出来た。しかしフレデリックの焦燥が酷く、それを凍結するように飛鳥が進言する。これから地獄に成り代わっていく世界の中で子供を育てることが出来るとは、とても思えなかった。
それから長い年月を掛けて抑止力の開発に乗り出し、オラトリオ聖人やアウトレイジの研究を進めたものの、二人だけではどうにもならないと判断したのが今から五十八年前。そうして聖騎士団を組織してからも、卵の処遇は厳重に保管するに留まっていた。卵は二人にとってパンドラの箱に等しかったのだ。何しろジャスティスの産んだ唯一の卵である。中から何が出てくるかはわからないが、とりわけ強力なギアの力を備えていることだけは確実だろう。いわんや子供……何らかの生命が生まれてきたとしても、どんな姿をしているかわからない。人間の側につく存在になる保証などまったくなく、厄介の種になるかもしれないものをこれ以上増やすことは出来なかった。
だが二十年前、それにすら縋らねばならない状況が訪れる。クリフの養子であったテスタメントがギアにされ、ジャスティス側に洗脳される形で寝返ったのだ。これはクリフは勿論、飛鳥とフレデリックにとっても大きな衝撃だった。それまで人型のギアは特例のフレデリックを除いて殆ど観察されていなかったため度外視されていたのだが、これにより、ギア側が人間を戦力として取り込む可能性を無視出来なくなってしまった。
ギアに人を……とりわけ聖騎士を取り入れ、あちらの戦力にされてしまうのならば、これに対抗するにはどうするべきか。
二人は深く思い悩んだ。ただでさえエゴの塊で聖戦を動かしている自覚があるのに、それ以上の禁忌に自分たちは手を掛けてしまっていいのだろうか。神への信仰などとうの昔に棄て去ったはずなのに、何年も不敬の苦しみに苛まれ、とうとう六年後、二人は決断を迫られる。
卵を孵化しよう、と最初に言い出したのは、フレデリックの方だった。
「いつになったら、本当のことを教える気でいる?」
飛鳥が根城にしている研究室の奥へ踏入り、フラスコを手にとってフレデリックが尋ねる。無数の試験管と破棄された生命になるはずだったものたち。かつてカイという少年を生み出すためのひな形として創作され、造物主に見放されたもの。それを憐れみの眼差しで一瞥し、親友が振り向くのを待つ。
しかし飛鳥はそんなフレデリックの視線を受けながらも、振り返らぬまま口を開いた。
「フレデリックにしては、野暮なことを聞くんだね。あの子達はきっともう気がついている。なら僕から言うべき事は、もう何もない」
「俺が言えたことじゃねえがな、親でなしすぎだろう、テメェは。……ディズィーが俺の娘であることと同じように、アイツは……カイは、テメェの息子だろうが」
「うーん。僕なりに愛情は注いだつもりなんだけれど。カイの方が僕を父と認めてくれているのか、近頃は自信がないよ……だって君の方がよっぽど慕われている。それは君も分かっているだろう?」
「ハッ。俺はあんなクソガキの父親になった覚えはねえな」
吐き捨て、フレデリックは無理矢理飛鳥の顔を振り向かせて苛立たしげに舌打ちをした。
目に入った飛鳥の顔は、ぞっとするほどカイによく似ている。当たり前だ。カイは飛鳥の遺伝情報から生み出された。クローンだ。旧科学技術とバックヤードから読み取った幾らかの越権法術、それらを掛け合わせ、飛鳥の遺伝子をベースにより良い人類として造られたデザインチャイルド。
卵から孵化した少女をひとりきりの兵器にしないために、もうひとつの兵器として造られた飛鳥の最高傑作品。
飛鳥が「何かを造っている」ことにフレデリックが気がついた時、既にカイはフラスコの中で生命を得てしまっていた。今までの飛鳥の開発品の中でも類を見ない恐ろしいスピードで生み出され、そのくせ、文句のつけようがないほど完成したものとしてそれはフレデリックの前に現れた。
フレデリックは百年ぶりに飛鳥の胸ぐらを掴み上げ、激しく彼を糾弾したが、カイを殺せ、とはとてもではないが言えなかった。自分たちはもう十分にひとでなしだ。であるからこそ、選べなかった。その子供を殺せ、などとは……口が裂けても。
「何度も言ってるけどね、僕は僕なりにカイを大事に思ってるし、そうしてるよ。あの子を物だと思ったことなんて一度もない。ちゃんと血を分けた、一人息子だ。必要だったから色々な場所は弄ったけれど」
「……ディズィーに耐えうる相手が必要だとは言わなかったはずだ。弄る必要なんざ……」
「でも、理論的に考えて、あれぐらいの能力を持った存在じゃなければ育てる意味がない。僕達は暇じゃなかった。慈善事業にわざわざ手を出していられるほど」
「だから人でなしだっつってんだよ、大馬鹿野郎が」
「実を言うと君にそう罵られるのは嫌いじゃない」
「……知ってる。ああ……くそ……」
二十年前のあの日、パンドラの箱を開くと決意したフレデリックにいつもと変わらぬ調子ですぐさま同意した飛鳥の顔が、今もフレデリックの脳裏にこびりついている。その瞬間カイを造ることを決めていたのだ、とは微塵も悟らせない、あの顔。
結果的に卵から孵った子供は、人を愛する心優しい
「彼女、カイのことを好きなんだろう? 恋とか愛とか、そういうのは人間の専売特許だ。彼女はハーフギアだけど、ちゃんと人間に育った。僕のやったことは必ずしも正しい行為ではなかったと思うけれど、でもあの時選べた最善だ。フレデリック、君に何と言われようと、僕は自分のこの考えだけは曲げられない」
「……ああ。そんなことは、俺だって分かってるんだ。だがな」
「うん」
「その、ディズィーがカイをどうやら好いているらしいっていうのも、近頃は気にいらねえ」
「あ……うん……そうなんだ……」
フレデリックの苦々しい口ぶりに、さしもの飛鳥も言葉を濁らせた。
それまでの人間としての憤りではなく、一転して父親としての戸惑いが滲む声音に飛鳥も慎重に言葉を選ぶ。彼は思春期の一人娘を持つ父親で、飛鳥は思い人の父親だ。この話題の最中、飛鳥はフレデリックの秘密を共有する親友ではなく、娘を奪うかもしれない男の親として彼との会話に臨まねばならない。
「いや……でもほら……そういうのは親が口出しすることでもないし……」
「……。正直、いつかディズィーを連れて行かれるのならどこぞの馬の骨とも知れない野郎よりはテメェの息子の方がいくらもマシだとは思う」
「あ、そうなんだ。まあカイは品行方正だしレディファースト徹底してるし頭いいしディズィーを守れるぐらい強いしそうだよね」
「親バカかテメェは?」
「フレデリックが思っているよりはそうだよ。……いや、ごめん。そんな顔しないでくれると助かる。分かってるよ。結局、心配なんだろう? だって彼らは……あまりに痛ましい時を過ごしすぎた。そしてそういう生活を強いたのは僕達だ。人間として育って欲しいなんて傲慢を言いながら、兵器として、抑止力としての側面を何より求めている。僕達は揃って親でなしだよ、フレデリック。子供達が殺したギアの数を君は数えられるのかい? 彼らがもうどれくらい命を奪うことに心を痛めずにいるのか、その日数は?」
「……は。そう来るかよ」
飛鳥の真剣な眼差しにフレデリックが深く息を吐く。二人は出来るだけ良い親であろうと努めている。今もだ。けれどそれ以上にどうしようもなく、科学者なのだ。
フレデリックは額のヘッドギアを抑え、重々しく口を開いた。どうにも、口の中が乾いて仕方がなかった。本当のことを言うと、ディズィーのことは、もうそんなに心配していない。でもカイのことはそうじゃない。いつまで経っても消えることのない光景が、今もフレデリックの頭を悩ませ続けている。
「俺はな、飛鳥。あいつが初めてギアを殺した時に見せた……上手に出来たでしょう、ってツラが、もうずっと忘れられずにいる。子供が蟻を笑いながら踏み潰すみてえな……さながら狂気のような。泣きじゃくりながらギアを殺したディズィーの方がまだ理解出来る。だがアイツはそうじゃなかった。カイは純粋無垢すぎる。……俺には時々、アイツが人間に見えない……」
懺悔するようなその言葉に、飛鳥はただ小さく、そうか、とだけ言った。