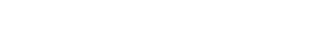02 自覚のない病・前
「何度も言っていると思うんですけど。私の机の上に乗るな。せめて書類は尻に敷くな。出来れば会議もさぼらないで。本当、それさえ守ってくれるならあとは何も求めないのに……」
「ソイツは無理な相談だな。俺をルールで縛ろうなんざ百年早ぇよ。まあ、坊やがもういくらか大人になったら……その時、少しぐらいは考えてやってもいい」
「それはもう、何も聞く気、ないでしょう? ほんの少しでも期待した私が馬鹿でした。……あーあ……私だって早く大人になりたいですよ……。そうすればせめて、指相撲で負けてトトカルチョの対象にされることもなくなるでしょうに……」
部屋には柔らかな陽射しが入り込んでいた。野良猫が勝手に上がり込んで身体を丸めるのよろしく部屋に入り込んでは机上を占拠している男を見ながら、少年は溜め息を吐く。出会ってから数ヶ月が経って、ようやく、こんなことを言い合えるような間柄になってきた。
これはすごい成果だ。こうして話をしてくれるだけ男は少年を認めてくれるようになったということだし、それは出会ったばかりの頃に比べたらとてつもない進歩なのである。
それはわかっている。……わかっている、けれど。
「あなたが……ギアメーカーへの復讐に躍起になっているのは、私だって承知しています。でもそれなら、私達と求めるものは同じでしょう。足並みを揃えてとまでは言いませんから、こっちの作戦にのってくれるぐらいしたって、何も罰は当たらないですよ。いい提案だと思うんです。だから……」
少年が上目遣いで躊躇いがちに言う。男はそれに黙って首を横へ振った。彼の拒絶のサインは、いつもわかりやすく簡潔で、そのぶんとりつく島さえも残されていない。
「ごめんだな。何度も言わせるな、坊主。テメェはまだまだケツが青すぎる。俺の全ては……今はまだ、明かせない」
「……なんだ、それ。じゃあいつかは、私に教える気があるとでも?」
「……。テメェが生きていればな」
慰めのつもりなのか、大きな手のひらがぽんぽんと無遠慮に少年の頭を撫で、そしてすぐさま離れていく。少年はこの手が好きだ。でも同時に、泣きたくなるくらい大嫌いだ。だから触れられる度、どうしても複雑な思いを抱えずにはいられない。
その手はまるで父親みたいだ、とぼんやり思う自分と。
その手つきに別の意味が欲しい、と浅はかに願う自分。
「もう……〝ソル〟! だから子供扱いはやめてくださいって、いつも言っているでしょう?!」
誤魔化すようにむくれて唇を尖らせると、男は笑った。束の間の安息みたいな笑い方。でもそんな顔をして見せても、彼が復讐者である事実は、何も変わってくれはしない。
◇◆◇◆◇
眠りのうちに、何処かの光景を見ることがある。とりわけ、現実によく似た、しかしよく見るとどこか一部分があまりにも乖離している……そういった夢をカイはよく見る。
ゆるやかに目を見開き、瞼の裏にある暗闇の中へ消えてしまった夢の記憶を辿ってカイは手を伸ばした。ゆるく握ったり開いたりする手のひらは、夢の中身も、その続きも、何も掴めなくて酷く空虚だ。小鳥の鳴き声が聞こえる。明け方特有の、きつく差して部屋中をわっと夜から朝に染め上げるような、夜明けの光がベッドの上を横断している。
起き上がってあたりを見回すと、既に父はベッドにいない。もう起きているのか。いや或いは、昨日からずっと、寝ていないのか。
親子でほど近くに並べられたベッドからもぞもぞと抜け出し、カイは父の姿を探した。十五にもなって父親と同じ寝室で寝ていることを、カイは別段不思議だと思っていない。騎士団寮は部屋が少ないのだ。一部屋に詰め込めるだけ詰め込まないと合理的ではない。普通よりちょっと大きい部屋に詰め込まれているだけ、贅沢なぐらいである。ディズィーは近頃流石に別室らしいけど、カイは男だから、彼女と違ってまだ父親と一緒でいいと考えている。
それに、兵器は、管理者と一緒の方が何かと都合がいいのだから。
「なんだか、へんな夢を見ました。具体的にどうへんだったのか、あんまり思い出せないんですけど。でも……すごく、へんな夢だった……」
大机が置いてある部屋の方へ移動すると、思った通り、ろくに寝てなんかいなさそうな父の姿が目に入る。その後ろ姿に殆ど独り言のつもりで話し掛けると、彼はふいと振り向いて、カイの姿をつま先からてっぺんまで眺めてから「そうか」と頷いて見せた。
「夜中にうなされていた様子はなかったし、見たところ肉体は健康そのものだ。ならきっとその夢は、悪い内容じゃなかったんだろう。しかし珍しい。夢なんか、普段滅多に見ないじゃないか」
「父さんほどじゃないですよ。あなたは百年ぐらい夢なんか見てないって豪語しているでしょう」
「うん、まあね。何しろ真っ当な生き方をやめてしまったから、その代償で二度と寝てる間の夢なんか見られない身体になってしまった」
ちょっとした当てつけみたいに言ってやったのに全然へこたれた様子がない。それでやや気分をくさして、カイは話題を変えると事務的な事柄を尋ねる。
「起きて見る夢に忙しいですからね。……それで、フレデリックはあのことについては何と?」
「現状何とも言えないって。ま、要観察かな。本人に自覚症状もないようだし」
「わかりました」
返ってきた答えだけ耳に入れると、とてとてとクローゼットのある寝室の方へ戻った。
なんてことのない朝の会話。汚れた白衣を羽織っている父親に軽い挨拶をして、必要なら報告を終えて、それから着替えて仕事に行く。パジャマを脱いでインナーをひっかぶり、姿見の前に立った。大きな鏡の中に映り込む自分の顔は、うんざりするぐらい父親そっくりだ。
それを特に面白くもなさそうに確認すると、すぐさま踵を返す。
父である飛鳥と己の姿形が酷似している理由を、もちろんカイは理解している。まだ三つの頃、寝物語を読み聞かせる代わりに飛鳥が夜毎語って聞かせたからだ。いいかいカイ、君にはお母さんがいないんだよ。君は僕の息子だということになっているけれど、実際のところ、僕の遺伝子だけで造られた、僕のクローンだからだ。理論的には、君は僕の息子と言うよりは兄弟——それも双子の弟、と言った方が正しいのかもしれない。けれど、君は僕の息子だ。僕はそういうふうに君を育てる。君のことを、そういうふうに愛したい。
三歳のカイは、それに頷いた。そこで二人の間に契約が定められた。その瞬間から飛鳥とカイは親子になった。契約は今も履行され続けている。親子以外のものになりたいと思ったことは、カイにはない。
首に掛ける前にロザリオを手に持ち、日課にしている朝の祈りを済ませる。本当は教会できちんとミサに出たいのだけれど、日曜礼拝だけに限ってもあまり時間を確保出来ずにいるのが現状だった。この百年、戦況は日増しに悪くなっていっている。百年前とそれほど変わらない生活事情を維持出来ているのは騎士団と一部の富裕層だけだ。聖騎士団は、その贅沢な生活を享受する代わりに、世界のために滅私奉公せねばならない。
時計をちらりと見てから、インナーのまま大机の方へ戻った。さっきはなかったはずの簡単な朝食がそこに用意されていることに気がつき、今朝は食堂へ寄っている時間がないことを思い出す。このあとすぐ、カイはスウェーデンに行くのだ。そして飛鳥はイングランドに。
「ところで」
机の上に手を伸ばして無言でサンドイッチを囓り始めると、父が言った。彼が「ところで」なんて話の切り出し方をする時は、たいてい、ろくなことを言ったためしがなかった。
「君のそれは、なんだか聖痕みたいだよね」
そうして、父が——カイを造った男が言った。
彼の眼差しは、まだボタンを留めきっていなかったインナーの隙間から覗いている、カイの喉元に浮かぶ十字傷をまっすぐに見ていた。まるで自分で喉を潰した時に出来たみたいな傷痕。身に覚えのない傷。だってこんなところに傷を付けたら、ひとは簡単に、死ねてしまうのに。
「生まれた時からずっと消えないんだもの」
口の中に含んだままのサンドイッチから急速に味が抜け落ちていく。唾液を含んでいるはずのパン生地がいやにぱさぱさしてくる。最早判別できない臭気を発し、喉をえづかせ、胃袋から食道を伝って口の中へせり上がってくる何かを助長するばかりになった食材を無理矢理その奥へ押し流し、カイは唇を開く。
「……ご冗談を。あなたみたいな俗っぽい造物主がいてたまるものですが」
「うん、でも、聖痕みたいだ。僕は十字架と薔薇のことは、モチーフとしてけっこう好きだからね。……きれいだよ、カイ。たとえそれが刺のある花でも。だけどね」
父が人差し指をそっとこちらへ差しのばしてきて、ひくつく喉を押さえて息を呑んだ。自分と同じつくりをした顔が、寸分違わぬ未来の自分のかたちをした生き物が、語りかけてくる。そうするとカイは錯覚してしまいそうになるのだ。彼の言うことは根拠のないまったくの当てずっぽうかもしれないのに、逃れられない死への宣告を聞かされているような気がしてきて、たまらなく不安になってしまう。
「自覚症状のない病を抱えているのは、ひょっとすると君もなんじゃないか?」
カイは喉を押さえた手が己の首を締め付けそうになる衝動を必死に堪えた。父の言葉を受けてひとりでに痛み始めた傷が、今にもとめどなく血を吐き出しそうな気がして、悪寒が酷い。
◇◆◇◆◇
スウェーデンに現れたギアの群れは、久方ぶりに一個大隊と呼べるほどの大規模なものだった。今まで、この規模を相手にする戦いでフレデリックを派遣しなかったことはない。イングランドの事後調査がそのくらい重要なものだということをカイとて理解していたが、ここをディズィーと二人だけで凌げるのかにはやや不安が残る。
「カイさん、大丈夫ですか? 顔色が随分悪いみたい。……でも、緊張、しますよね。わかります。私もそうですから」
「ええ、お恥ずかしながら。こういう局面では、いつもフレデリックに頼り切りだったから。でも、いけませんね。私達も、いつまでも子供じゃないんです。このぐらい出来なければ、鼻で笑われてしまう」
「鼻で笑われて……それは嫌、かも。昨日、お父さんに靴下そのへんに脱ぎ捨てないでって言ったばかりなのに。まだおまえは子供だなって言われるの、最近ちょっと飽きてきました。どうせならお父さんに一泡吹かせて帰りたいな」
「……ディズィー。あなたちょっと、鬱憤溜まってます?」
「だってお父さん、本当にだらしないんだもん。カイさんもそう思うでしょう?」
かわいらしい顔をぷうと膨らませて見せる少女にカイは穏やかに頷いた。今朝方飛鳥に確かめた、彼女の「自覚症状がない病」。それを密かに思い、彼女の手を握る。
ハーフギアである少女の身体はどっちつかずで、酷くアンバランスだ。後天的ギアのフレデリックと違い、彼女は生まれた時から人間の身体とギアの翼を持っていた。少女として成り立っている肉体部分はほぼ人間に近い組成をしているのに、翼だけが分離されて濃縮したギアの証になっているのだ。
ギアとしての能力が殆ど翼にしか備わっていないので、当然、本体には重い負荷が掛かる。体内を巡る法力がかろうじて一定になっているので今まで何とか過ごせてきているが、彼女のギアの力が成長して強大になるにつれて負荷は高まり続けている。でも彼女はそのことを知らない。フレデリックが、出来れば彼女自身が気付くまで教えたくない、と言うから。
(まるで彼女自身が、ゆるやかに時を数える時限爆弾みたい……)
勿論彼女が生きていくうえで支障がないように、飛鳥とフレデリックが出来るだけの手を尽くしてはいる。だからうまくいけば、彼女は一生、その病について自覚をしないで済むだろう。もしかしたら身体が成長しきって安定を迎えてしまえば、飛鳥達の手助けなんかなくても大丈夫になるかもしれない。でも今のところはどうなるかわかっていない。だから彼女の任務には、必ず、フレデリックかカイが一緒に行く。
(私には、そういう不具合はないって父さんは言っているけど)
カイという存在はそも、ディズィーを補佐するスペアとしてデザインされた。そのカイに欠陥があっては元々のディズィーを支えるという目的が果たせない。だからこそカイのことは、度を超して完璧になるように調整したのだ、と飛鳥も言っていた。何も問題が起きないように。より安定したパフォーマンスを発揮出来るように。
そして兵器でありながら、人の心を上手に持てるように。
(だから、全部だいじょうぶ、のはずなのに……)
それなのに、どうして。
(私に、自覚症状のない病だって?)
あの人はあんなぞっとしないことを言ったりしたのだ?
「……あ。レーダーに反応が出ました。目標距離まで二〇〇〇、予測到達時刻まであと五分です。……指揮を、カイさん」
気がそぞろになっているカイの代わりに、ディズィーが作戦本部に設置されたレーダーを確認する。生体法力によりギアの接近を関知するそのモニタに目を走らせ、彼女が滑らかな声音で数値を読み上げた。それから彼女は、先を促すようにカイの袖を引く。
「はい。第一連隊及び第二連隊に告ぐ。目標距離まで二〇〇〇、到達時刻までおよそ五分。各員第一種戦闘配置に着き、開戦に備えよ。繰り返す、第一種戦闘配置に着き開戦に備えよ! 敵部隊、こちらに接近中である! たった今、レーダー上に敵影を捕捉」
それでようやく浮ついた思考から回帰し、カイは伝達用の音声拡散機に口を近づけて伝令を読み上げた。この規模でこの移動速度なら、危惧していたほどの乱戦にはならずに済むかもしれない。どうかそうであって欲しい。本当は、ギアによる死者など、一人も出ない方が望ましい。
こういう大きな戦のあと、どうしても守りきれなくて出る死体を見ると、カイは最早祈ることも出来ずに立ち尽くしてしまうのだ。洗礼の証に父から授けられたロザリオは、いつも重たい。そこに何が詰まり、引き寄せられていくのか、薄々分かっているからこそ真実に触れたくなくて、カイは骸の前で祈ることが出来ない。
だからいつも祈りは始まる前に済ませる。最初のうちに、ありったけ吐き出して、神様に祈りを捧げてしまう。神様どうか、仲間が無事でいられますように。どうかディズィーが、心優しい少女が、ずっと幸せでいられますように。いつか世界が、救われますように。
それから……それから、どうか……
「詳細解析終了。敵は小型ギアが多数、中型ギアが約三十五体。それから…………え?」
滑らかに続いていたカイの言葉が、不意にそこで止まった。
(うそ。なんで……)
カイは驚きのあまり口を噤む。レーダーに信じられない反応が出ているのだ。つい先ほどまではなかったはずのものが、びかびかと瞬いている。次いで、画面が赤く染まり、警告表示に切り替わった。デンジャー。モニタの故障かと思いたいぐらい無機質で無遠慮な、でかでかとした警句。デンジャー。もはやあなたがたに、猶予はない。
(ッ……馬鹿な)
口にしかけた言葉をすんでの所で押し込み、カイはディズィーと繋いだままだった手のひらに強く力を込めた。
「——緊急連絡! 敵影にメガデスギア二体とジャスティスを確認! 総員速やかにその場を待避し、特別警戒態勢にて行動せよ! 余力のある者は非戦闘員の撤退を支援。第一連隊は、優先して支援にあたること。第二連隊は私の元へ。 ——繰り返す!! ジャスティスの接近を確認! これより特別警戒態勢に移行する!!」
あらん限りの力を込めて絶叫し、カイは胸に当たるロザリオを空いている方の手のひらで押さえる。はやく。急いていく気持ちと相反する、布越しでも伝わる金属の無機質な冷たさ。カイは泣き出したい気持ちでいっぱいだった。ここが戦場でなくて、カイが弁えを知らない子供だったのなら、三秒と我慢することも出来ずに泣き出していたのに違いない。
(どう、して……)
呻きが漏れる。
ロザリオの冷たさが、心臓を侵食する。
(ああ……)
神様。
どうして私の祈りは、聞き届けられないのですか。