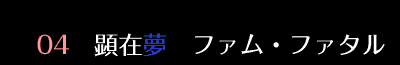
教室の前に出来ている人だかりを認めて凌牙は深く溜息を吐いた。数人の女子生徒がきゃあきゃあと黄色い声を撒き散らして一人の男に群がっている。とても不快な気分だ。出来れば関わり合いになりたくない。
しかしその願いが叶わないだろうということも凌牙にはわかっていた。男が誰に用があってここにわざわざ来ているのかということは、考えるまでもなく明瞭なことだ。
「お、やっと帰ってきたか。——凌牙」
案の定だ。舌打ちをする。その声で俺の名を呼ぶな、俺を見るな、俺のテリトリーに入ってくるな。感情がぐるぐる渦を巻いて、しかし、すぐに強烈な一つの感情で上書きされる。
「お前のことを探していた。来てくれ」
……俺に気安く触れるな。凌牙は首を振った。言ったところでこの男は態度なんか変えやしない。
そんなことはもう十年も昔からわかりきっている。
「……俺からは何も用はないぜ」
「なんだ、御挨拶だな。大体俺が用があるから来たんだ。高等部と中等部は地味に離れてるから、用もなきゃわざわざ来ない。凌牙の声は昨日聞いたし」
「気色の悪ぃこと言ってんじゃねえ」
「しばらくぶりに帰国したら声ぐらい聞きたいと思うのは当たり前のことだろ。お前なんか殆ど俺の弟みたいなものなんだから」
酷く傍若無人な言葉だった。
中等部校舎の屋上は閑散としていて、初夏の湿っぽさを含んだ大気に包まれていた。貯水タンクが片隅でぽつんと居心地悪そうに佇んでいる。凌牙が授業をふける時に頻繁に訪れる場所は、普段は喧騒と離れた静寂で凌牙を迎えてくれるが、今はその真逆だ。
高等部二年の制服を着て、(あまりそれを認めたくはないが)幼馴染みの男は凌牙の前で偉そうに腕組みをしている。この男が自分よりも三つ年上なのがふとした瞬間に我慢ならなくなる時があって、今がまさにそうだ。背が微妙に足りないのも、格下だと蔑まれているようで腹立たしい。
実際のところそれは単なる被害妄想にすぎなくて、トーマスが腕組みするのも彼の悪癖でありそれに何の意味もないことを凌牙は知っている。トーマスが凌牙に対して悪い感情を抱いていないことも。だがそれでも、胸糞が悪いのだった。
トーマスの弟だなんて、真っ平御免だ。
「用だけ言ってさっさと失せろよ」
「なんでそう愛想がねえんだ? お前はただでさえ可愛げがないんだから、少しぐらい素直になったって罰は当たらねえと思うんだがな」
「テメエみてえな気色悪ぃもんなんか振りまけるかよ」
「ファンサービスは仕事だぜ。別だ。……それはそうと、璃緒のことなんだが」
ああ、これだ。
深い苛立ちが沸き起こった。
トーマスが話を持ってくる時、大抵の場合話題は璃緒に関係したことで、凌牙本人の事となるとああいうお小言ばかりだった。そりゃあ、非常に忌々しいことだが璃緒はトーマスの婚約者だ。気にかけるのはむしろ喜ばしいことなのだろう。だがむかつく。
璃緒のことなんざ璃緒に聞けばそれでいいはずなのに。
「近頃様子が変だったとか、そういうの、知らないか」
「——知らない」
「そうか。なら、いい」
まただ。無性に腹が立って仕方なくなる。この男の何もかもが気に入らない。璃緒と婚約していることも、凌牙と同じ学校に通っていることも。家同士が親しいことも。
それでいて、凌牙のことなど歯牙にもかけぬふうなのが、どうしようもなく、嫌なのだ。
「手間かけたな。用も済んだし、お前はそんな顔をしているし……俺は高等部の校舎に戻るぜ。一人になりたいんだろう?」
わかったふうにひらひら手を振ってトーマスがくるりと踵を返した。わざわざ呼び出しておきながらこんな程度の用件か。反吐が出そうだった。この男は、神代凌牙のことを便利屋か何かと勘違いしているのか?
そうじゃない。凌牙の頭の中で警鐘が鳴る。このままで終わらせられるか。本当は、凌牙だって、言いたいことがあって……
「待てよ……」
そうして無意識に手が伸びて、屋上から去ろうとしたトーマスを引き留めた。制服の裾を握りしめ、迷子になった子供のようにトーマスを見ている。泣きそうな顔だった。本当に子供だった頃と変わらずに。
「お前、本当に璃緒と結婚するのかよ」
トーマスが目をしばたかせた。
——『おれから、璃緒をつれてかないで!』記憶の中の悲壮な声がトーマスの脳内に響き渡る。記憶の中の幼子が泣き喚いて叫んだのも、初夏の日のことだ。
「俺さぁ、璃緒と婚約するんだって。一番あにきのクリスじゃなくて、年が近いミハエルでもなくて、俺なんだって。なんでだろうな。俺は、いいんだけど」
トーマスが八歳の時だった。当の凌牙と璃緒はまだ五つで、誰がどう見てもそんなものは子供同士のままごと擬きにしかならなそうな、そんな頃だ。実際どちらの家にも二人の将来を雁字搦めに束縛しようという意志はなく、両家の子供達にある種の自覚を促そうという程度のものだということを、クリストファーあたりはきちんとわかっていた。
「結婚なんてぜんぜん先のことで俺にはまだわかんない。なんで父さん達はそんなこと言い出したんだろう?」
「……トーマス、それでほんとに、璃緒とけっこんするの」
「どうだろ。その時になんなきゃ、わかんない気もする。でも、俺、そういうの関係なく璃緒のこと大事だから。結局そうなる気がちょっとする」
「……だいじ?」
「大事。凌牙も璃緒も。ミハエルとおんなじ」
「なんで」
「理由なんか、別にない」
「え……」
「璃緒は俺が守ってやらなきゃ」
トーマスは目を閉じた。瞼の裏に、赤い色をした陽炎が映っていた。
ふと、何かがトーマスの服の裾を掴んで引っ張る。凌牙の手だった。泣きそうな顔をして、いや、もう既に泣きながら凌牙を見上げてきているのだ。
びくりとする。トーマスにはどうして凌牙が泣いているのかがわからない。
「おい、凌牙」
「璃緒を……」
「?」
「おれから璃緒を、つれてかないで」
ぞっとした。
「おれだけひとりにしないでよ」
それは紛れもない懇願だった。凌牙は孤独を恐れている。璃緒を奪われるという恐怖にそれが勝り、璃緒を連れ去る対象のトーマスにすがりつくのだ。落伍者の追いすがりのようで、しかしそれよりももっと純粋で他意のない絶望にトーマスは生唾を呑む。
なんで。
なんで、そんな、おぞましい目を。
「凌牙。泣くな。男なんだぜ、お前。俺のふたりめの弟……だと俺は思ってるんだ。たから泣くなよ。一人には、しないから……」
凌牙は答えなかった。ただ嗚咽だけがひぐひぐと漏れ続けている。子供の小さな両腕でもっと幼い子供を抱き寄せた。
まるで赤ん坊をあやすように。
「そしたらお前もうちの屋敷に来ちゃえばいいんだ」
ミハエルを寝かしつける時と同じようにおでこにキスをした。
昔、クリストファーにそうされることが好きだったということをなんとはなしに思い出した。
「本当に、親の言いつけを守って良い子のふりをして璃緒を連れて行くのか。俺は賛成出来ない。お前なんかに……璃緒を……」
「……さあな。そいつは璃緒が決めることだろう。俺でもお前でもない。ついでに、父さんでもお前の父親でもない。……璃緒が嫌だというのなら、俺は大人しく身を引くさ。今の体裁もやめる。他に好きな奴がいるんだったら、家族ごっこなんか邪魔なだけだろうしな」
「はっ。そうやって口先では余裕こきながら確信してるわけだ。体のいい使いっぱしりにされていることに一種の安堵を見出している。マゾかよテメエ。ほとほと呆れ果てるぜ!」
「別に。璃緒の面倒見るのは特別なことじゃない。慣れてるってだけだ。それとは別に、璃緒は俺が守ってやんなきゃいけないってことも、まあある。璃緒は俺が守る。それはあいつが誰と結婚しようが、俺から離れていこうが、変わらない」
「……ふざけんなよ!!」
その言葉に激昂し、叫び、そしてトーマスの顔を思い切り殴った。トーマスはそれを避ける素振りも見せなかった。避けようと思えばトーマスの身体能力なら可能だったところを、そうしようとはしなかった。
自然と呼吸が荒くなる。僅かに赤くなった頬を見せたままトーマスが向き直った。赤い瞳。璃緒と同じ色。同じ顔で、凌牙を見る。
「璃緒を守るのは俺だ。俺一人だけで十分だ。お前なんか、要らない——」
「凌牙。昔言ったろ。璃緒を連れて行ってお前を一人にするようなことをしない。俺と璃緒が結婚したらお前は血縁関係上で俺の弟だ。……一緒に来ればいいだろ。三人養うのが五人になったところで俺は問題ねえよ。そのぐらいの甲斐性はあるつもりだ」
「違う。そうじゃない。俺はそんなふうになりたいわけじゃない……」
耳を塞いだ。出来るのならば目も塞ぎたい。それから感覚を閉ざし、心を塞いで、目の前の男を消し去ってやりたい。
でもそれは出来ないのだ。凌牙は舌打ちをした。ああ、なんて心底、憎たらしい。
したり顔で、わかったふうな面をして、トーマスは凌牙を心から案じて見ているのだ。ありありと想像出来て、目を瞑った意味がまるでない。
「お前に嫌われてるのは知ってるが。ったく……にこにこ笑えとは言わないがな、もう少し可愛げのある表情をした方が、人生得だぜ。俺や璃緒みたいにそのままのお前を見てお前が本当は繊細だとか、寂しがりだとか、わかってやれる奴なんてそうそういねえんだから」
トーマスが言った。そうして幼い頃のように親愛のキスをする代わりに頭を撫でた。凌牙の脳裏に九年前の夏の日が蘇る。
『凌牙。泣くな。男なんだぜ、お前。俺のふたりめの弟……だと俺は思ってるんだ。たから泣くなよ。一人には、しないから……』
『そしたらお前もうちの屋敷に来ちゃえばいいんだ』
『凌牙。たいせつな俺の……』
「俺は……!」
凌牙はかぶりを振った。
体中が震えて止まらない。嫌い嫌い大嫌い、嫌い、好き、大嫌い。花占いをしているみたいな不明瞭な感情が駆け抜けていく。嫌い好き嫌い好き大嫌い嫌い。この男が憎たらしい。どうしてこうも、憚りなく、家族面なんかしているのだ?
頭を抱えて大声で泣き喚いてしまいたかった。
「おれは……おまえ、なん、か……」
膝をついてくずおれてしまいたい。だがプライドがそれを拒み許さない。自尊心。とても厄介な感情だ。それが結局のところ本音を殺してしまう。
胸中で祈るように呪詛の言葉を繰り返した。
——気安く。
気安く俺の中に、入ってくるな。
◇◆◇◆◇
「凌牙、とても不機嫌でしたわ。何を話したんです?」
学校から帰る道すがらで璃緒が不意にそう問い掛けた。トーマスは大仰に肩を竦め、「さあな」と首を振る。
「『本当に璃緒と結婚するのか』と聞かれた。大方、妹が取られるとか、そんなことを思ってるんじゃねえか」
「あら。別に、私が嫁いだからって何も変わらないと思うのだけど」
「苗字が変わるのがまず嫌なんじゃねえの?」
「困りましたわね」
「困ったな」
「凌牙はいつまでも、それですわ……」
もう子供じゃないのに。璃緒が上品に右手を頬に添えて嘆息する。それを横から見ていた観月小鳥が少女期の憧れ特有のきらきらした眼差しで見て、興奮気味に隣の少年の手を引っ張った。
「璃緒さん、すっごく大人っぽい……いいなぁ、年上の婚約者がいるってだけで、普通の女の子達とは全然違うけど、それに輪をかけてレベルが違う感じ」
「俺にはよくわかんねーよ。シャークが不機嫌なんだなーとは思ったけど」
「もー、遊馬はほんっとお子様よね。なーんにもわかんないんだから……」
「しょうがないじゃん。俺、男だし」
「それは遊馬が馬鹿だからよ。トーマスさんは、わかってるわ」
ええ? と腑に落ちない様子で反芻している遊馬に小鳥がぷいとそっぽを向いてしまう。その様子に気がついて璃緒がくすくすと微笑んだ。
「二人とも、本当に仲が良いのね」
「え、そう見えます?」
「ええ。とても」
嬉しそうにはにかむ小鳥に肯定の言葉を返す。小鳥が幼馴染みの九十九遊馬に親愛以上のものを抱いていること、また遊馬がそれにまったく気が付いていないことは彼らの周囲にいる者達にとっては周知の事実だった。だから彼女は余計に「恋人同士」の体裁を取っている璃緒とトーマスを羨んでいるのだろう。
いつかああなりたい、だなんて思ってでもいるのかもしれない。
「小鳥さんと遊馬は、お家が近いんでしたっけ?」
「うーん、家の距離は、そこそこかな。祖母同士が懇意にしてて、その縁で物心つく前から一緒だったみたい。何をやるにも一緒だった、ってほどではなかったんだけど……いつからだったかなぁ? 遊馬、一生懸命だったから」
確か、小学生の時だったかな。小鳥が顔いっぱいに破顔した。初恋で、今もまだそのまま追い続けているのだとすぐにわかった。
「璃緒さんは、やっぱり生まれた時から?」
「そうね。私と凌牙が生まれた時、トーマスがもう三つでクリストファーは六つでしたから。メイドもそうでしたけど、年の近い子供と一緒の方がいいだなんて言ってクリストファーが託児所代わりだったらしいわ。向こうにしてみればいい迷惑よね……ミハエルだってあの頃はまだ一歳でしたのに」
「兄貴は子供の面倒みるの得意だったからな。一緒の方がいい、って言い出したのは兄貴だったらしいぜ。別に気にすることねえよ」
「あら、そうでしたの。今初めて知りました。あの方、本当にあなたとは正反対なんですね」
「どういう意味だ、璃緒」
「あなた、身内以外の子供、嫌いでしょう」
「あー、あぁ……」
璃緒が澄まし顔で言う。トーマスはぽりぽりと頬を掻き、図星を当てられた人間特有のなんとも言えない微妙な顔になって頷いた。彼は弟のミハエルにはとことん甘いし、凌牙と璃緒にはそれなりに親切だが、ファンサービス以外の意味で言えば子供には冷たい方だ。
子供は面倒くさい、という顔をしている。
或いは他人を嫌がっているのか。
「言われてみりゃ、そうかもしれない」
「子供に群がられると嫌そうな目をするもの。ほんの一瞬ですけど」
「はー……璃緒さんってトーマスさんのこと、よく見てるんですね……」
「小鳥さんと同じよ。ただ、ずっと一緒だったから」
トーマスの横に立ち、なんでもないことであるかのようにそう言う。小鳥を挟んでトーマスの反対に立つ遊馬は何が何だかよくわからないふうな顔をしていたが、トーマスが目配せをするとああ、と頷いた。お互いに身に覚えのある話をしているのだと眼差しが物語っている。
二人の少女がしているのは「当たり前」の話だった。隣に定まった誰それがいること、それがきっとずっと続くのだろうということ、幸福であること。変わらないものがあること。
そしてそれに目を細める少女の姿を、少年が見ていること。璃緒の背後を潜り遊馬のそばに寄ってくるとトーマスは少し困ったように笑った。
お互い苦労するな、という労いの表情であるように遊馬には見えた。
「何年になる?」
「んー……覚えてねーけど、十年は」
「俺もだ。もう何年だとか、思い出せねえ」
「ずっとだもんな」
「そうだな。凌牙も璃緒も……」
物心がついた頃から。あまりにもそれが自然すぎて、もう、それに疑問を抱いたこともない。このまま、いつか大人になり年老いて、死ぬ時まで何も変わらなかったとしても、きっと遊馬もトーマスもろくに驚きはしないのだ。
だからといって、途中で何か転機が訪れてもそれに対して取り乱したり変化をなかったことにしようとすることもない。
幼馴染みの延長線にある対人関係は奇妙で複雑な、知恵の輪に似ていた。
「ああ、そうですわ、トーマス。日曜日ですけど」
「空けてある。買い物か?」
「話が早くて助かるわ。いつも通りお願い出来るかしら」
「そりゃ、勿論。急な仕事さえ入らなければ」
「か、かっこいい……」
二人でそんな遣り取りをすると、小鳥がまた目を輝かせて璃緒とトーマス、それから遊馬とを交互に見比べる。たいていの物事に疎い遊馬も流石にこの流れで自分がトーマスと比べられていることに気がついたらしく、露骨にげっそりとした嫌そうな表情になった。
「なんだか、二人で全部通じ合ってるって感じ……うちの遊馬もせめてあの半分……四分の一ぐらい機敏になってくれればいいのに……」
「う、うるさいなぁ、俺だって小鳥の部屋が意外と汚いってこととか、結構よく知って……」
「それ以上言ったら、遊馬が最後におねしょした日がいつなのかと十三歳にして痔持ちだってこと、クラス中に言いふらすわよ」
「はぁ?! 卑怯だろそれ!!」
そのまま低レベルな言い争いに発展してしまう。トーマスと璃緒はそれに面食らったように顔を見合わせ、ほどなく、二人してくすくすと笑った。「笑うなよお!」と遊馬が抗議すると「いや、悪い。そういうつもりじゃない」「あんまり可愛らしいものですから、つい」と横並びの補足が入った。ぷぅと膨らんだ頬の遊馬はちょっと涙目だ。「痔は、気が付いたら、なってたんだよ……」とどんよりした声でぼやくと、がっくりとうなだれる。
「っていうかなんで小鳥がそんなの知ってるんだよぉ」
「ふふん。あんまり幼馴染を舐めない方がいいわよ」
「舐めねーよ、セクハラしてるみたいなこと言うな!」
「遊馬、慣用句知らないの? ちなみに本当に舐めたりしたらこの先一生わんこ遊馬って蔑んであげるから」
「ぜってーやらねー……っていうか、そうか、誰経由でばれたかなんとなくわかったぞ。くっそ、ばーちゃんの口軽め……」
「……遊馬は尻に敷かれて頭が上がらなくなるかかあ天下のタイプだな、こりゃ……」
トーマスがどこか同情的な声で言った。
夕方五時半を告げる地域放送のメロディベルが鳴り、遊馬達と道が分かれる十字路がやにわに近付いてきたあたりになって、不意にトーマスが手を打った。何か忘れていたことを思い出した時のあの仕草だ。不思議に思った璃緒が「どうかしたの」と問うと「まあ、ちょっとしたことを」と頷く。それからひそひそと彼女に耳打つと途端に璃緒の表情が複雑なものになった。
「……なんて言ったんだ?」
「別に、大したことじゃない。『お前は俺にとってのファム・ファタルみたいなもんだ』、ってな。お前らを見て引っかかってた言葉を今しがた思い出したもんだから。深い意味はないぜ」
「その割に随分と失礼な言葉よね。悪女ですって」
「当たらずとも遠からず、だろう?」
トーマスが素っ気なく言う。「ファム・ファタル?」と首を傾げる小鳥に璃緒が「フランス語ですわ」と問われる前に解答を寄越した。
「フランス語で『悪女』または『魔性の女』、そういった意味合いの言葉です。あまり、レディを形容する時には使いませんわね。言ったが最後破局したって文句は言えませんから」
「じゃあ、トーマスさんはものすごく自信があったんですね」
「……何にですか?」
「璃緒さんが、それを許してくれるってこと」
だってそうでしょう? と小鳥が他意なく尋ねると璃緒は急にその意味に思い至ったらしく、いつも冷静な彼女にしては珍しいくらいにかあっとその整った顔を真っ赤に染め上げた。トーマスも遣り取りの意味に気が付いて若干だが顔を赤らめる。どうやらこちらも無自覚だったらしい。
「いいなあ。お互いにそんなふうに信頼し合ってるなんて……」
「そんな……付き合いが、長いだけ、ですから……」
「私だって付き合いは長いのに、遊馬ったら気の利いたこと一つ言えないんだもの。——やっぱり、すごく素敵だと思います。そういうの」
きっぱりと小鳥が言い切ると、トーマスはまだ狼狽えていたが璃緒は赤い顔を引きずりながらも小さな声で、「ありがとう」と答えた。遊馬が他人事のようにそれを眺めていると、突然ぐいと腕を引っ張られ、そのままずるずると引きずられていく体になる。「それじゃあ、今日はこれで失礼しますね!」という小鳥の声が遊馬を引きずる腕の方から聞こえてきて、トーマスがそれに気圧されるように「お、おう」と手を振り、遊馬をちらりと見た。
それからしばらくの間引きずられていた遊馬だったが、トーマスと璃緒が十分に遠ざかって見えなくなったあたりで解放されてドスンと尻もちをつく。「いってえ!!」と涙交じりに反論するが、小鳥は澄まし顔だ。つまらない。というよりは悔しい。
「何するんだよ!」
「私達、どう考えても邪魔だったもの。二人っきりにさせてあげるべきだったのよ。ほら、遊馬、手貸してあげるから早く立って」
「ったく……誰が転ばせたと思って……」
「遊馬がにぶちんなのが悪いのよ」
ぷいと顔を背けた。あれだけ名指しで会話していて、それでもムードひとつ作れないのは、小鳥の中ではもう遊馬の才能の一つみたいな認識になってしまっていた。
夕暮れ時の土手を二人でてくてくと歩いた。「ファム・ファタル」という言葉が遊馬の頭の中にわだかまって、流れていかない。「ファム・ファタル」。フランス語で「悪女」。でも本当にそれだけだったっけか? そんなネガティブなばかりの言葉だったようには思えない。何か、もっと他に意味があったような……。
唸りながら考えている内に、ふと明里がいつか言った言葉が蘇る。
『この映画の主人公、ほんとにタイトル通りの性格よね……え、意味がわかんない? そっか。遊馬には難しいかもね。あのね、フランス語で魔性の女、っていう意味の言葉なのよ。カルメンとか、そういう、好きになった男の人の人生を滅茶苦茶にしちゃう女の人のこと。すっごい話よね。ああ、でもね、それだけじゃなくて……』
「——あ。思い出した」
「何を?」
「さっきの。『ファム・ファタル』ってさ、確かもう一個意味があったと思うんだ」
手をポンと叩いてそう言うと小鳥が食いついてきて先を促した。遊馬は頷いてたどたどしく姉の言葉の続きを手繰る。それだけじゃなくて、もう一個。ゆっくり口を開くと、まっすぐに沈んでいく夕日を見ながらこう口にした。
「姉ちゃんが前、そういうタイトルの映画見ててさ。教えてくれたんだ。確かにあの言葉には悪女とかそういう悪い意味もあるんだけど、こっちは素敵でしょ、って」
「へー。ねえ、勿体ぶらないで早く教えてよ」
「うん。『ファム・ファタル』っていうのは」
崖側に面した通路からは、ハートランドシティはずれの臨海部が遠くに見えていた。夕日が沈んでいく赤と青の入り混じった海が覗いている。きっとあれが『ファム・ファタル』の色なんだろうとその時遊馬はなんとはなしに思った。トーマス・アークライトと神代璃緒の、赤と青。
握りしめた指を開く。無意識にその手は小鳥に伸びて、手を掴み取り、小鳥と自分の目をまっすぐに向い合せて息を吸う。
「——『運命の女』、って言うんだって」
遊馬が言った。