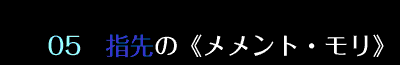
夢は見ない。元々滅多に見る性質ではなかったし、ここしばらくは輪をかけて見ない。
トーマスが覚えている一番古い夢は自転車に乗る夢だった。その頃丁度補助輪つきの自転車に乗り、クリストファーに見守られながら、補助輪を外した自転車に乗れるようになりたいと練習をしていたのだった。しかしいつも失敗続きで擦り傷ばかり増え、なかなかうまくいっていなかったそんな時期にその夢を見た。
夢の中でトーマスは自由自在に自転車を操り、丘を駆け上って、風を切って走っていた。憧れていた風景が夢の中にはあった。その夢を見た次の日、興奮気味にクリストファーを引っ張り出し自転車にまたがったことをよく覚えている。そしてその日、とうとうトーマスは擦り傷を作らなかったのだ。
あれから、トーマス・アークライトは一度も二輪自転車に乗って転んだことはない。
「夢とそれに伴う倦怠感……」
何とはなしに紙飛行機を折って窓の外に飛ばす。紙飛行機は風に乗りすいと飛び立ち、やがて視界から消えた。
「じゃあ、俺はここ最近夢を見ているのか?」
「——僕はそう思います」
「ミハエル」
「兄様、毎晩うなされていますから。きっと酷い悪夢ですよ。僕、知ってるんです」
ノックの音どころか足音一つ立てずにミハエルがトーマスの横に立っていた。「ノックは」と聞くと「しましたよ」とむっとした顔で答える。つまり聞こえていなかったのだ。それほどに深く過去の幻影の中に沈みこんでしまっていたらしい。
ミハエルがティーポットとカップをテーブルの上に置き、紅茶を注ぎ始める。慣れた手つき。紅茶を淹れるのは、もう随分長いこと彼の仕事だった——ように、思った。
「遊馬に会ったよ」
「お墓でですか? やだなあ、遊馬ったら、本当に行ったんだ。よくあんな辛気臭いところに行こうなんて思えるなあ」
「その辛気臭いところに毎日通ってる兄貴の前でそう言うなよ」
「だから大声で、これ見よがしに言ってるんです。僕は嫌だって何度言ったらわかってくださるんですか?」
「わからずや。俺はあそこに通うのは、なんと言われようとやめないぞ」
「わからずやは、兄様の方ですっ!」
ミハエルには珍しく語気の荒い強い口調で咎められる。本当にあまりないことだ。驚きにトーマスの目が大きく見開かれるのにそう時間はかからなかった。あの、大抵のことに素直で従順で、そして諦めの良いミハエルが。どうして。
それほどまでにあの墓が嫌だというのか。
「兄様は、いっつも、わがままで! 僕の言葉なんかちっとも聞いてくれやしない。僕は……っく、嫌ですって、何度も言ってるのに……兄様っ……。きっと兄様は、兄様はおかしくなってるんです。誰が見たってぞっとするにきまっている。あんなに、ピラミッドか子供の砂の城みたいに花を積み上げて。僕にはあれが気狂いの所業にしか思えなかった。とてもじゃないけど、正気の沙汰じゃない。兄様。なんであの墓にこだわるんですか。どうして、あんなに青い花を捧げるんですか……」
「おい、ミハエル、落ち着け。発作みたいな声になってる」
「そのうち心臓や魂も取られてしまいますよ」
「ミハエル」
「そしたら、兄様は……」
「ミハエル!」
抑えつけるように勢いよく肩を掴むとびくりと体を跳ねさせ、怯える目つきになってミハエルは言葉を切らした。トーマスを見上げ、浅く荒い呼吸を繰り返している。そのうちミハエルは両手で顔を覆い、小さく首を横に振った。
「みないでください」蚊の鳴くような懇願の声。
「おねがい、みないで、にいさま……」
「ミハエル。どうしたんだ。お前らしくもない……」
「みないで……ああ、僕、兄様の前でなんて……なんて姿を……」
ミハエルは両掌の覆いを頑なに取ろうとしなかった。恐らくは羞恥と焦燥とで感情がぐちゃぐちゃになって、ひどい顔をしているものと思われた。昔から、ミハエルが稀に見せる表情だ。幼い嫉妬心が剥き出しになり、ブレーキが効かなくなってしまう。
その顔をミハエルは忌み嫌っている。特に、トーマスに見られることを恐れていた。
「僕、トーマス兄様の前では……クリス兄様も、父様もですけど、聞き分けの良い子でいなきゃいけないって。駄々をこねてはいけないって。そう、思っているのに。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい兄様」
ミハエルが壊れたラジオのようにそう繰り返した。ごめんなさい兄様。ごめんなさい。悪い子でごめんなさい。僕のことを嫌いにならないで。
唖然とした。それほどまでに、この子が追い詰められていたとは思いもよらなかったからだ。
確かに遊馬にも言った通り近頃トーマスはミハエルに対して、多少遣り取りがおざなり気味だったとは思う。それで不機嫌なのだろう。まるで墓に兄を取られたみたいで、嫌なのだろう。そういうふうに考えていた。
しかしどうもそればかりではないようだ。そういう不機嫌さも含むが、それを通り越してもっとネガティブな悲壮感があふれている。切迫感は本物だ。ミハエルは本気で死別という形であの墓にトーマスを奪われてしまうことを危惧しているのだ。
「……おまえは。良い子だが、聞き分けがよすぎるのは悪いところだ。クリスから見た俺ほどじゃなくってもな、多少は聞き分けがない方が自然で、手もかかるがいい。教えてくれ。お前は俺の行動の何がそんなに嫌なんだ? 青い花が、どう思えるんだ? 教えてくれミハエル……」
「それは……きっと、兄様の望む答えではありませんよ……?」
「望む答えしか返ってこないのに、何故問いかけなきゃいけない」
トーマスは溜息を吐いてミハエルを抱きしめた。
「そんなのは問いかけじゃないし、自己満足の欺瞞だ。意味がないじゃないか。ほら」
ちゃんと俺の目を見るんだ。そう言ってやるとミハエルは小さく頷いて赤く染まった顔をようやくのことでもたげた。
「兄様、ドッペルゲンガーって信じますか? あの、世界に自分と同じ顔の人間が三人いるという話です。それから、合わせ鏡も。合わせ鏡の怪談では、合わせ鏡のある特定の並びに映る虚像と目が遭ってしまうと、不幸になったり死んだりしてしまうのだと言います。……僕は、今の兄様はその状況に似ていると思う。それもすごく、すごくよく似ている」
「……どういう意味だ?」
「青い花です。兄様はきっと悪いものに憑りつかれているんですよ。そうに違いない。今の兄様は僕には病的で、それから言い方を憚らなければ、怪談的に映るんです。夜な夜な五寸釘を打ちに行くのと同じ。花を供えるのがまるで何かの儀式的な義務みたい。だってそうでしょう、じゃなきゃ兄様、どうして毎日あそこに花を持って行くのかその理由を合理的に説明出来ますか?」
ミハエルが人差し指をたてて、内緒のひそひそ話でもしているみたいに神妙な面持ちで問いかけてくる。そんなことを聞いてくるからには、お前はそのオカルト話を信じているのか。そう思ったが、なんとなく聞くのは躊躇われた。
「合理的にって……」
「僕が納得いくように、説明出来ますか。霊的なものの力を借りずにです……どこそことこういう契約を交わして土地を購入したから、通い詰めなければいけないだとか。でもそうじゃないんだ。兄様があそこに行くのに理由があるのだとしたら、きっと『呼ばれている』からですよ。お墓に、呼び寄せられている。或いはその墓石の下に眠る何者にか……」
「だから、墓の下には誰も何もいないんだって。掘り起こしたって遺骸どころか石ころ一つ出てくるかも怪しいぞ」
「そうですね、それは事実でしょう。兄様はそんなところで嘘を吐かないですし……あ、別に、すんでのところで踏みとどまったから墓荒らしはしていないですよ、流石に……だけど僕は何もないからなおさら怖いんです。兄様、だったら何故? あの場所の何が兄様をそこまで強く引き付けるの?」
「それは、」
「——それは、幽霊か何かなんじゃないですか?」
こてん、と首を傾げる。幽霊。形のないものの最たる例。人間の幻想が作り出した幻の名前だ。心理学的には何らかの不安を抱えている時に脳が見せるまやかしだとトーマスはそう理解していた。墓下の幽霊。それではトーマスは今不安を感じているのか。
不安だなんて、どうしてだろう。だってこんなに満ち足りた生活なのだ。母こそ、病で早くに亡くしたが……父は優しく、兄弟仲も良く、自身の仕事も軌道に乗り極東チャンピオンとして高い名声を得ている。忙しさにかまかけて特定の女性などはまだ出来ていないが、それにまだ不満を感じる年でもない。トーマスはまだ十七歳なのだ。
「……いや……」
しかしそこまで考えて違うな、と気が付いた。父は優しい。これは正しい。兄弟仲にも恵まれている。これも正しい。極東チャンピオンとして安定した名声と収入を得ている。これもまた正しい。しかし、最後の一つ。これは正しくない。
自分には誰か守らなければいけない、責任を取るべき相手がいたような気がする。
しかしその誰かが誰なのか、ということは判然としない。もやがかかったみたいに、意図的に隠されでもしているかのように、ぼんやりとして雲を掴むような曖昧さだ。しかし誰かにそういう感情を抱いていたことは間違いない。考えているうちに確信を持ってそう断ぜられるようになってきた。いたのだ。一生をかけて償うべき相手が。
「あれは、贖罪なんだ……」
「え?」
「青い花を選ぶのとはまた別で、俺が毎日、必ずあそこを訪れるのは贖罪のかたちなんだ。今までは無意識だった。だが、お前の問いかけでそれを今はっきりと自覚した。俺には守ってやらなきゃいけないやつがいたんだ。だからその代わりに、花を捧げる……」
『死んだ女より、もっと哀れなのは、忘れられた女です』。昔読んだ詩の一節がトーマスの思考をかすめた。あたかも死んだかのように墓にまつり、花を捧げ、黙祷を捧げる。墓の下の忘れられた女。いいや、女だけではない。そこには忘れられた男女がいる。
「ドッペルゲンガー……」
知らずその言葉が口をついて出た。
「あれ? 兄様、そういうの信じるタイプでしたっけ……?」
「お前が言ったんだろう。それにまあ、そういうのを信じるタイプじゃないよ。幽霊にしたって然り、だがそれとこれとは別だ。俺の中に大きな矛盾がある。俺は今、確かに知っていたはずのものを思い出せないんでいるんだ。ミハエル、お前が部屋に入ってきた時、俺は夢見の悪さについてぶつぶつ言ってただろ?」
「ええ。兄様が夢を見ないのは確かに昔からですけれど、それはきっと眠りが深いからですよ。お仕事を始められてから一段と疲れた顔をされることが多くなりましたから」
「夢だよ。夢の中の俺と、この今現実だと信じている俺が、ドッペルゲンガーなんだ」
「……それってどういう」
「夢を見ている俺が現実なのか、それともその夢の中の俺こそが現実の俺なのか、その境界なんてものは所在定まらない曖昧なものだってことだ」
胡蝶の夢のように。トーマスはこの時わけもなく確信した。夢の中の自分は、その忘れ去ってしまった女と男のことを知っている。
だから胸にぽっかりと穴が開いてしまったかのような喪失感がトーマスの中にある。その虚無感が不安となり、墓に招きよせる。あの墓は代替物なのだ。見えない何かのオルタナティブ。
名前も知らない誰かを抱きしめる代わりに花を手向ける。
「……でも兄様、それって。抱きしめる代わりにお花を供えるだなんて……なんだか偽善じみていますね。手が届かないからって諦めないあたりが、兄様らしいですけれど。まるで遊馬みたい。ああ、そんなことないか。遊馬は、近頃は手が届かないってわかったら届くようになるまで無茶をしに行ってしまうもの」
アストラルの時みたいにね。そう言って微笑んだ。トーマスが聞いた話では九十九遊馬を庇ってアストラルは一度この世界から消滅し、アストラル世界へクリスとカイトの助力で助けに行ったものの何かのきっかけでまたいなくなってしまったということだった。何がきっかけだったのかは知らない。
遊馬がそれを語らない以上知る術はない。
机に置かれた筆立ての隣の花瓶に目を止めて、ミハエルが儚げにまぶたを伏せった。花瓶の中には御多分に漏れず青い花が活けてあり、咲き誇っている。ブルーファイアーにネモフィラ。ブルーファイアーはミハエルがとみに苦手な、嫌いな花だ。花言葉は「命を捧げます」。だってそれってつまり……そういうことなのではないか?
トーマスをその花が彼の贖罪の相手の元に連れ去って神隠しにでも遭わせてしまうのではないか? もし彼が眠ったまま、起き上がってこなくなったりなんかしたら……。
不意にミハエルは、何の邪気もなく、さりとて意図もなく、ただ単にそこに花があったから花を摘みむしった。トーマスが驚いて「何をしているんだ」というふうに眼差しで訴えてくる。ただ花を摘んだだけだ。そこにそれ以上の意味なんかない。
単純に純粋にきらいなだけだ。
だから端的にそう言ってやった。
「兄様、その青いお花達、特にブルーファイアーは僕には死の警句に見えるんです。ほら、ラテン語の。兄様の指先にしみついた青い死の色が見えるみたい。——《メメント・モリ》、死を想え、って」
◇◆◇◆◇
「よお」
「へ?」
「間抜けたツラしてんじゃねーよ。用があるから来たんだ。もう放課後だろ。暇は?」
「あ、あるけど……」
ハートランド学園中等部一年の赤い制服を着た遊馬がそうして捕まえられたのは、彼と墓で会ってから一週間ほどが経った日のことだった。トーマスはどうにも思い詰めた顔をしている。遊馬は振り返るとおっかなびっくり彼に尋ねる。
「……用って、なんだ?」
「決まってんだろ。あの、墓のことだ」
「ああ、やっぱり……でも俺にそれで何の用が出来るのかわかんない。俺が知ってることは、もうないよ」
「まあそう言うだろうな。……夢について考えたんだ。ミハエルに聞いたら、俺は毎晩酷くうなされていると。だからきっと夢は見ているはずです、なんてあいつは言っていた。……遊馬」
「なんだよ」
「話が聞きたい。お前の隣から消えてしまった、九十九遊馬にとっての幽霊の話を」
「…………。真月は、幽霊なんかじゃねえよ……」
トーマスの言葉に遊馬はむっとして答えた。真月零はそんな儚い幻覚なんかじゃない。確かに遊馬の隣で笑っていたのだ。
しかしトーマスは遊馬の不機嫌な受け答えなぞにはまるで関心がないようで(そもそも、真月零を指すつもりで言ったわけでもないのかもしれない)、「それならそれで別にいい」なんて言うばかりだった。
真月零。あの愛おしい自分自身に捨てられてしまった遊馬の友達。ベクターは真月零を棄てた。踏み躙って、正体をあらわにし、遊馬を貶めた。
「悪い。勝手に俺と同じかと思ってた。——ドッペルゲンガーと幽霊の話をミハエルとしたんだ。世界に三人いる自分と同じ顔をした他人と出会ってしまうと死んでしまうっていうつまんねえ怪談話。自らのコピーを目にした時、そいつはアイデンティティが崩落して自我を保てなくなるっつうタネだ。だったら一卵性双生児はどうなるんだって話だよな……広義ではそれもドッペルゲンガーに含むらしいけどな」
「その、ドッペルなんたらがどうしたっていうんだよ」
「そこで夢の話に戻る。俺が見ているはずの、朝になると消えてしまう夢の中の俺こそが今の俺に対するドッペルゲンガーなんじゃないかって。……ミハエルと話をしていて俺は気が付いた。俺は、あの墓の下にいるやつらを、『知ってる』……」
「え……」
「勿論墓下には何もない。名前もわからない。姿形なんてもってのほかの、幽霊より透き通って薄暗いやつらだ。だがそいつらは確かにいて……俺に花を手向けさせるんだ。——どうだ。興味が出てきたって顔だな。話に付き合えよ」
別に取って食いやしねえからさ。近所に住む親切な年上のお兄ちゃんみたいな顔でにっこり笑う。うすら寒い。笑うような話をしているはずじゃない。
「別に取って食おうってわけじゃねえし、お前が一筋縄じゃいかない相手だってのは俺が一番よく知っている。それにさ」
「……」
「そろそろ一人で秘密を抱えているのにも疲れてきた頃だろう? ばればれだぜ。この前はあれ以上追及することはしなかったがな。あの時もう、顔に書いてあった。誰かに吐露して楽になりてえってな……」
「……でも。知らないほうがきっと幸せだぜ。知っていても知らなくても不幸なのかもしれないけど、どっちかっていうと知ってるほうが不幸だ」
「そんじゃなんだ、お前ひとりで不幸を抱え込むからほっといてくれってか? は——甘く見られたもんだな。それとも地獄のファンサービスでも喰らいたいか?」
トーマスの声はわざと挑発しているような軽薄さがあって、かちんとくるよりも先にまず感じる虚しさがあった。もしかしたら昔の遊馬はすぐにつられて逆上してしまっていたのかもしれないが、少なくとも今の遊馬に彼の挑発に乗ってやるような気はしてこない。遊馬は一つ乾いた息を吐くと首を横に振り、咎めるような眼差しでトーマスを見る。
「……後悔しても知らないぜ?」
「ほお。言うようになったじゃねえか」
「そういうふうに言われるほど俺はお前と話したこと、ないよ。まあ確かにカイトとタッグ組んで戦った時は俺のこと、さんざんカイトのおまけ扱いしてたから随分待遇良くなったなーって思わないこともないけど」
「なんだよ根に持ってんのかぁ? 器が小せえぞ。ぐだぐだ言うな、あんときゃ本当にお前なんかオマケ程度のチビガキだと俺は思ってたんだ」
「別に。俺は今もガキだよ。小鳥や姉ちゃんに『遊馬はいつまでも子供ね』、って言われなくなる日なんて俺には想像つかないもん」
そうしてお手上げのポーズを取った。やれやれといったふうに肩を竦めてトーマスの手を取る。思いのほか強く、そうして小さく華奢な少年の手のひらの感覚に一瞬トーマスの知覚が鈍った。その一瞬の油断が隙になる。
次の瞬間にはもう、遊馬は走り出していた。繋がれた腕から引っ張られ、トーマスの足も駆け足に歩を刻む。「おい、どこへ行く気だ?!」尋ねると遊馬は曖昧に返事を濁し、河川敷へ一直線へと向かっていく。
「してやるよ。俺のいなくなった友達の話。トーマスが勝手に幽霊にした方も含めてちゃんと二人分な。だからまずは一人分。そいつは、俺の友達の真月零は、お日様みたいに笑って、夕焼け空みたいに憂う、そんな奴だった」
地平線の向こうへ夕日がだんだんと沈み落ちていく。河川敷の向こうの山の下めがけて太陽が沈殿するみたいに沈み込んでいくのがわかる。もうしばらくで夜の時間だ。ハートランドシティの夜は人工の灯りがあちこちに設置されているから真っ暗にはならないし、むしろぴかぴかと眩しいぐらいだったが、それでも夜になることには変わらない。
夜は幽霊の時間だ。これほど、遊馬にとっての幽霊とトーマスにとっての幽霊、彼らの話をするのに相応しい時もそうない。
「真月はいつも真っ直ぐに俺を見て、尻尾を振る犬みたいに俺によく懐いて、『遊馬くん』って俺を呼んだ。ある日突然現れたのにそいつは全然違和感なく俺の周囲に溶け込んで、気が付いたらいつも隣にいるようになってた。今思えば、現れたと思ったらすぐ消えてたりして、捉えどころのない、確かに幽霊みたいなやつだったかもしれない。名前に『零』って入ってるの、多分そういうことなんだろうなあ。新月のゼロ。元々あいつはそこにあるようでないものとして設定されてたんだ……」
でもいたんだよ。熱のこもった声でそれを繰り返す。真月零はとうめいに透き通った水硝子のような存在で、まるで一過性の熱病のような存在だったけれど、彼が真夏の夜の夢なんかじゃないことは遊馬自身がよく知っている。
川べりに降りて行って、緩やかに流れる河川を認めると遊馬は振り返った。逆光。沈みゆく太陽の影になってまるで月に隠れているみたいな暗さだった。
「真月零は人間じゃなかったんだよ」
当たり前のような口調で、かつて太陽と揶揄された少年はそんなことを言った。