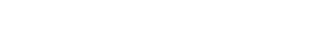03 恋の呪い
イングランドの南、ソールズベリーからいくらか離れたところで移動用のカーゴを降りてフレデリックは髪を掻き上げた。見上げた空は嘘みたいに晴れ上がって雲一つない。子供が無造作にバケツをひっくり返したようなピュアリー・ブルー。
こういった空の巡り合わせを見る度、皮肉なものだとフレデリックは思う。今頃子供達は、スウェーデンで血の海を見ているかもしれないのだ。彼らはどれだけ空が青かろうと、そんなものを見ることはない。
「子供達が心配かい? フレデリック」
立ったまま考え込んでしまった様子のフレデリックに、唯一連れだってこの地にやってきた飛鳥が尋ねる。「そりゃあな」と素っ気なく返してやると、君は心配性だね、と飛鳥が軽く笑った。
確かに、もうカイもディズィーも随分大きくなって、力もよくつけた。今回彼らに持たせた隊はかなりの大所帯だが、それらをまとめあげる能力についても問題はないだろう。十五歳の少年と少女はその強大な力故に恐れられているが、同時に愛くるしい見目と幼い年頃のおかげで、高い求心力も兼ね備えている。子供だからと指示を聞かない兵士が出ることは万が一にもあり得ない。そういう人間は、もうここに至るまでにみんな死んでいる。
こと兵器としての彼らに心配はさほどないのだ。でも彼らは、望んで兵器を選んだけれど、そうである以上にフレデリックにとってはまだ小さな幼子だった。
「まあ、君も人の親だ。心配になるのは仕方ないか」
「人ごとみたいに言うがな、テメェはどうなんだ。あれだけ親馬鹿晒しておきながら、カイのことがかわいいんじゃねえのかよ」
「まあね。でも、今朝、顔は見てきたし。ものごとはなるようにしかならないよ、フレデリック。ディズィーのことは多少心配だけれど……彼女は自分の抱える身体の不具合に無自覚だ……カイの抱える自覚なき病は、戦闘の局面においては無関係だよ。あの子はギアを殺めることにおいて、必ず想定されるポテンシャルを発揮出来る」
「機械みてぇに言うなよ」
「まさか。でも、彼は僕の息子だよ?」
飛鳥がなんてことないみたいな顔をして、あっけらかんと言う。それを見て、フレデリックは追求をやめた。これ以上の問答に意味があるとは思えない。この友人は、時折、もしかして本当に人の心がわからないんじゃないだろうかと疑わせるような素振りを見せる。百年以上前からずっと。
飛鳥の姿を脳裏から追い出し、今朝会話を交わした少女の姿を思い描いた。行ってきますお父さん、と手を振ってくしゃりと笑うその顔が、年を経る度彼女に似通っていく。皮肉なものだ。これもまた、皮肉なのだ。フレデリックのまわりには皮肉ばかりが転がっている。禁忌を犯したあてつけに、世界じゅうが皮肉を言いに来ているのに違いない。
それに文句を言う代わりに、深く溜め息を吐いた。
本当は娘を……特に不安定な近頃の彼女を一人で行かせるのには、最後まで反対していた。飛鳥だけで行け、とはじめは何度も突っぱねたのだ。しかし状況が進むにつれ、そうも言っていられなくなった。飛鳥とフレデリックが、二人だけで、速やかに現地に赴く必要が出来た。
先日、ここイングランドである実験を行った。試作段階のハーフ・アウトレイジの、実戦における試用運転だ。結果は失敗。当該ギアの殲滅は為し得たものの、「理論上オラトリオ聖人になるはずだったもの」がこの土地に重大な影響を及ぼしてしまったことが観測からわかったのである。
ちょっとした手違いから緊急事態の速やかな解決を迫られたフレデリックは、無理を押してオラトリオ聖人(になるはずだったもの)を発動した。そのためにショートカット策としてバックヤードを回路に噛ませたのだが、どうもこれがいけなかったらしく、このあたり一帯の時空間にひずみが生じてしまったのだ。
ひずみは数日のうちにイングランドの中でも最も自然法力密度の高いエリア——ストーンヘンジに集約する。そしてとうとう一昨日、何者かが引き寄せられるように虚数域から現れた。これを出来うる限り迅速に確保・調査するのが二人に課せられた火急の任務なのである。
「気がかりなのは発見報告があってから現地駐在員と連絡が取れないことだな。調査機器から送られてくるデータでは、発生した何者かはそこから動いていないことになっているんだけど……」
「つまりだ、はっきり分かってるのは未知数ってことだけだろ。だから他の奴らは連れて来なかったんだ。余計な犠牲を出すわけにはいかねえからな」
「そうだね。それにちょっと気になることもある。何者か……の観測データが、理論上人間の数値を叩き出しているにも関わらず、閾値を大きくオーバーフローしてしまっている話は、もうしたよね」
「ああ」
「……実は、これを君に言うと、ここまで来てくれないか、或いは僕を殴り倒して一人で行ってしまうかもしれないと思って今まで黙ってたことがあるんだ」
組み上がった石柱の群れを気にした素振りもなく、先導するように飛鳥が歩く。用途不明の古代遺跡・ストーンヘンジ。かつては観光名所としてひっきりなしに人が訪れていたそこも、聖戦が始まってから殆ど寄りつく者のいないひっそりとした場所になっていった。それを利用して飛鳥が設置した諸々の観測機器から、無数のコードたちがストーンサークルの中央へ向かって伸びている。
「……やっぱり、そうか。フレデリック……ちょっと、ゆっくりこっちに来て」
そう言って、フレデリックよりいくらか前に出たところで飛鳥が足を止めた。手招きされるのに従って歩を進め、中央部に侵入する。
そうして目線を下へ動かし、目に入ったものを確かめ、フレデリックは言葉にもならないようなひくついた音を喉から漏らした。
「彼女が、オラトリオ聖人の射出失敗以降、このストーンヘンジに現れたものだ。外面データからは人間の女性、精神感応観測の反応からは、人類というよりは現象、概念に近い数値が出ている。でも何より奇妙なのが、個人を特定するのに用いられるような種々の波長めいたものだ」
ストーンヘンジの中央には女が横たわっていた。しかも外気温が摂氏三度まで下がっているこのイングランドの寒空の下、全裸で転がっている。だが女に寒気を感じている様子はない。ただ静かに目を閉じ、眠り続けている。
死体が、模型の真似事をさせられているみたいだった。しかしこの女は生きている。生きているのに死んでいる。この世界に生まれきっていないもののように、この世界に生まれてきてはいけないものだったのだと言わんばかりに、そこにある。
「ここまで来れば、君にもなんとなくわかるんじゃないか、フレデリック。彼女からは、僕の記憶にあるものと同じ波長を感じる。生体法紋から魂の波長に至るまで、その全てがだ。しかし同時に彼女から感じるそれは不完全でもある。それらのデータから、僕はここに来る前に一つの仮説を立てていたんだけど……どうやらそれは正しかったみたいだ……」
フレデリックは最早紡ぐ言葉もなくその場に立ち尽くしていた。隣に立つ飛鳥でさえ、声に震えが混じっている。生まれていない女の美しい死に顔は二人にとって非常になじみ深いものだ。でも、何故? 彼女がそこにいていいはずがない。彼女は人を憎み、世界を憎み、人の姿を棄てた。なのにこの女は……この女は、彼女なのだろうか……?
「彼女は——人と呼べる存在なのかは怪しいが——アリアの半分、としか言い様がないものなんだよ、フレデリック」
飛鳥=R=クロイツはフレデリックの耳元で囁いた。その呪いの言葉に呼応し、死せる女は目を醒ます。
◇◆◇◆◇
フレデリックの人生に呪いがひとつあるのだとしたら、それはきっと彼女という存在の全てだ。
「ねえ、フレデリック。私、大丈夫だよ。だって最後の瞬間まで、あなたと一緒にいられたんだから。大丈夫。だからそんな泣きそうな顔、しないで。私、あなたの笑ってる顔が好き。これは、わがままだけど……本当の、最後の最後まで、あなたの笑顔を見てたいの」
集中治療室の中で無数のチューブに繋がれて、余命僅かになった彼女が弱々しく微笑んでいた。不治の病に罹患した彼女を救う手立ては、その当時には残されていなかった。冷凍睡眠を施して治療法が見つかった後に起こせば或いは……と飛鳥が提案してきた時、フレデリックは藁にもすがる思いでそれを受け入れようとしたが、それを拒んだのもまた彼女自身だった。
「やだなあ。私、フレデリックと一緒に年を取るのが夢だったんだもの。私がしわくちゃのおばあちゃんになる頃、フレデリックもよぼよぼのおじいちゃんになってる、そういう、他愛のないどこにでもあるような夢。……冷凍睡眠をして、いつか治療法が出るとして、でもそうしたら私が助かるのはいつ? 五年後? 十年後? ううん、それならまだ、いいの。けど、違うでしょう。百年後……ひょっとしたら、もっと先の未来かもしれない。目が覚めて、病気が治ったとしても、そこにフレデリックがいなかったら。……私はきっと、生きていけないよ」
彼女は毅然としてこの方法を退けた。それにフレデリックは酷く葛藤する。生かしたい。彼女をどうしても、こんなところで失いたくない。彼女に先立たれたとして、生きていける自信がないのはフレデリックも同じだった。
そのことを、二人をずっとそばで見ていた飛鳥も知っていた。
「どうして……? フレデリック……」
彼女の命が終わりを告げる間際、二人は同意を得ないまま彼女を冷凍睡眠させた。そうして、いつか彼女の病が不治の病ではなくなるその日まで生き続けられるよう、二人は自分たちを改造する。
フレデリックには、研究途上だったギア細胞の付与による延命を。そして飛鳥には、気属性の法力学を触媒に、バックヤードのバックアップ利用を用いた生命転換による延命を。
狂気の沙汰だという自覚はある。今も昔もそれは変わらない。彼女を起こす時、怖かった。怖くて、こわくて、恐ろしくて、彼女を起こして治療をし、フレデリックと同様の身体へ造り替える施術を行った時、フレデリックはそこへ行けなかった。
だからフレデリックはあの日施術室の中で何があったのかを知らない。飛鳥が彼女と何の言葉を交わしたのか。彼女が何を思っていたのか。今彼女が何を見ているのかさえ、知らない。
わかっているのは、たった一つの、この世界を切り裂くような叫び声。
「わたし、永遠に、あなたのことを恨むわ——フレデリック!」
けれどそれを耳にした時、それでもいい、と思ったのだ。
彼女が恨み続けてくれる限り、フレデリックはアリアの中で生き続ける。永遠に彼女の中で一番大きな存在になれる。彼女はフレデリックだけを見てくれる。ああ、なんと浅はかな思い。腐敗した感情。でも、それでも確かに、フレデリックは……
目覚めた女が上体を起こしまぶたを擦る。起き抜けのアリアは機嫌が悪い。いつもそうやってまぶたを擦っては、大きくあくびをして、背伸びをする。
「テメェは——!」
「だめだ、フレデリック!!」
反射的に掴み掛かろうとしたフレデリックを、飛鳥が必死に後ろから押さえつけた。裸体を晒したまま長い髪の毛を垂らす女は、目の前で鬼の形相をしている男のことなど意に介さないように呑気にあくびをすると、ぐっと背を伸ばす。それから思い出したように辺りを見回し、そこでようやくフレデリックと飛鳥の姿を認めると二度、三度瞬きをする。
「ここは……。そう。そういう、ことなのね。その服装、この世界もまだ聖戦の最中なのかしら? でも奇妙だわ。ギアメーカー、あなたまでそんな服を着ているなんて」
女が口を開き、言葉を発したことでようやくフレデリックの動きが止まった。女の声を頭の中で反芻しているようだった。女の声音は、よく似てはいるが、彼女のそれとは微妙に声質が異なっていた。
考え込んでしまったフレデリックから腕を放し、飛鳥が女の質問に答える。
「そんな服……って、この聖騎士団の制服のことか。なぜ?」
「〝私が見てきた世界では〟……ギアメーカーが聖騎士団に与することはなかった。あなたはいつも……ううん、だからこそなのか。私がここに現れた理由は、あなたが聖騎士団に関与しているから……」
「何の話だい? しかしその口ぶり、君はもしや」
「多分、あなたの考えている通りね」
飛鳥の言葉を継ぎ、女が頷く。女は飛鳥とフレデリックの瞳を交互に真っ直ぐ見つめると、これから言うことに嘘偽りがないことを誓うみたいに、深呼吸をする。
「ええと……それじゃ、まずは自己紹介から。私はヴァレンタイン。この世界ではまだ生まれていない異物にして、あなたたちより先のパラレル・ワールドからの異邦人。この世界に来たのは……そうね……多分、世界の終わりに立ち会うため。こんなところで、大丈夫かしら?」
そうして女は人差し指を立てると、そのようなことを一息に述べた。
飛鳥がヴァレンタインと名乗った女の言葉を整理している隣で、フレデリックは変わらず無言のままだった。しかし目だけが異様に血走って、女を睨んでいる。ヴァレンタイン。聞き覚えのない名前。ではこの女は、アリアではないのか。これほど似ているのに? ……本当に?
「ヴァレンタイン、な。ならテメェは、アイツとは違うってのか? 飛鳥はテメェの波長はアリアの半分に近しいものだと言っていた。コイツはクソの付く変態だが、鑑識眼は随一だ。事実は事実だろう。ソイツに自覚は」
「ああ、ごめんなさい。そんなに睨まないで貰えると助かるわ。でも本当に、申し訳ないんだけど……私は彼女ではないのよ。よく似た顔をした、よく似た世界の別人。あなただって違うということはもう感じ取っているんでしょう?」
「なら……」
「そのためにも対話が必要なの。私自身、自分がここにいることについて情報を整理しきれていないのよ。あなたたちが私を起こしてくれたことは分かる。それから、この世界の抱えている非常に大きな病巣についてもね」
女が立ち上がる。両手を胸の辺りにかざし、何かを起動するような仕草をすると、たちまちその場にホログラムのような鍵盤が現れた。指先が鍵盤を叩き、音色を奏でる。交響曲第五番、ベートーヴェンの「運命」。
鍵盤の操作に従い、女の周辺に無数のホロウィンドウが浮かび上がった。猛烈な勢いで記述されスクロールしていくその内容は、どれもこの世界そのものの統計観測データに関連している。
彼女が何をしているのかいち早く察知した飛鳥が息を呑んだ。つまり彼女は、バックヤードに直にアクセスしてバックログを取りだしているのだ。彼女が今しがた「この世界」と呼んだ、時空間が辿ってきた歴史を指先一つで読み取っている。生半可な存在が出来る所業ではない。飛鳥でも、それをやろうとすればもっと大がかりな設備と時間が必要になる。
「……やっぱりね。この世界にはイノちゃんがいない。なのに、人々の抱く『生きたい』という願いが希薄すぎる。まるで何かがそれをかき集めて、暗い虚の中に落とし込み消し去っているみたい。そのせいで世界は正しく機能出来ず、『ギアメーカーが聖騎士団に関与する』なんてバグが発生してしまう。……でも、そうしたら一体誰が? 誰が何の為に、そんなブラックホールを呼び起こしているのかしら……」
「バグ……僕が、彼と聖騎士団を興したことそのものが綻びだと言うのか」
「ええ。だって私の世界では、あなたは世界の敵だったわ。ギアメーカーが世界の、ひいては彼の憎しみを一手に引き受けることで歴史の均衡を取っていたのよ」
「それは……」
飛鳥の問いを女が平然と肯定した。それに飛鳥が何かを言おうとして口を開いたが、彼の言葉が最後まで続くことはなかった。
「——!」
飛鳥とフレデリックの胸元に付いているメダルから一斉に緊急コール音が鳴り響いたのだ。晴れ渡ったイングランドの空を引き裂くような音にヴァレンタインが慌てて両耳を塞ぐ中、フレデリックに視線で示し合わせて飛鳥の端末でコールを受けた。途端に、ノイズが混じって割れた音声がストーンヘンジに響き渡る。
『た——たすけて……助けて、フレデリック! お願いです……はやく、帰って、きて……!』
メダルから聞こえてくる焦燥しきった音声はカイのものだった。飛鳥の顔色が一瞬にして緊迫したものになる。よく出来た子供の手本みたいなカイという少年が、こんなみっともない声で助けを請うようなことは、今までに一度もなかったのに。
「カイ?! 一体どうしたんだ。まず状況を報告してくれ」
『その声、父さんですか?! い、いえ。この際誰だって構いません。報告します、本日一〇三〇、スウェーデン該当区域に〝ジャスティス〟が出現しました……!』
「ジャスティスが?! あれはあと半年は休眠を余儀なくされた状態だったはずだ。それが何故……いや、まさか……」
『同時刻、本作戦を掃討戦から撤退戦へ変更。同一一二〇、ジャスティスの侵攻止まらず、戦線に一次崩壊を確認。同一一五〇……それで……それで……』
飛鳥がちらりとヴァレンタインの方を見る。通信先のカイは父が何らかの心当たりを持っていることになど気付く素振りもなく、余裕のない声音で規則通りの報告を続けていた。しかしそれも途中まで来て詰まってしまう。そして言葉の代わりに啜り泣くような嗚咽が混ざり始め、数秒のち、泣きじゃくる赤子みたいな声で、彼が言った。
『ディズィーが。……ディズィーが、皆を逃がすために身体を張って……う、うごか、ない……んです……!!』
一瞬、あたりは重苦しい沈黙に包まれた。
成長途上で出力が安定しないディズィーにとって、彼女の持つギアとしての能力は日に日に危険なものになっている。それこそが、ディズィーという少女が抱える根本的な自覚のない病。それでも通常の使い方をしていれば、さほどの問題は起こらないようになっている。定期的にケアをして、偏った法力の流れを正し、淀みを排除する。そのような対症療法でこれまでをしのいできたのだ。
だがジャスティス相手に身体を張ったとなれば、当然そうはいかない。彼女は父親に言い含められていた自らの限界を無視し、身体にどんな負担がかかろうとその全てを放出したのだろう。カイには、もしもの時の為にある程度の対処方を教えてある。しかし使った力の大きさを考えると、一時しのぎにはなっても命の危機までは覆せまい。
「カイ。教えてあげたことは、やっているかな」
『やって……やって、ます! でも駄目なんです。私の命なんか全部あげたっていいのに……そのぐらい、彼女に分け与えているはずなのに、ちっとも、目を開けてくれない……!』
「把握した。カイ、君の命を与えるのはほどほどにしておきなさい。そのままでは君が先に死んでしまう。場所は? スウェーデンのどこだい? 確か予定交戦区域はオスロの付近だったと思うけど」
『そこから西に撤退を始めて……一時間半、あまりですから……ドランメンかその周辺だと……』
「わかった。では先にフレデリックを向かわせる。僕も追っていく」
現在地を確かめ、短く言い含めて通信を切ると飛鳥は改めてフレデリックに向き直った。少し前まで憤りに赤くなっていたはずの彼の顔面は、かわいそうなぐらい蒼白になってしまっていた。
「……ご指名だ。行ってやってくれ、フレデリック。行きに使ったカーゴと君の脚力なら、日が暮れる前には着けるだろう」
「ソイツは……」
「彼女については、僕が段取りをつけておく。必要に応じて本部に連れて帰るし、得られた情報は必ず君と共有する」
「……だがな、」
「履き違えるな、フレデリック! 目の前に現れただけの彼女と、今死の淵に瀕している実の娘と、どっちが大切なのか——君はわかるだろう?!」
むごいことを言っていると自覚して、飛鳥は敢えて常識的な人間のようにフレデリックを怒鳴りつけた。
フレデリックの目が驚きに見開かれる。フレデリックが飛鳥を怒鳴りつけることはあっても、その逆など滅多にない。いやもしかしたら、今まで一度たりともなかったかもしれない。だから飛鳥はフレデリックを怒鳴りつける。混乱しているのはわかっている。いきなり現れたアリアに似た女に、アリアによく似た娘の危篤。冷静に判断しろと言ってもとても出来る状態ではないだろう。ならば今は飛鳥が適切な判断をしてやらなければいけない。
「早く。あの日施術室に入らなかったことを、後悔しているんだろう、だったら!!」
そう言いながら飛鳥がフレデリックの背を押すと、彼は一目散に、弾かれたように走り出した。
その背を見送り、カーゴの中に姿が見えなくなると、飛鳥はヴァレンタインに向き直る。一連の出来事を黙って見守っていた女は、飛鳥の顔を見ると人差し指を唇に当てて小さく唸る。
「あなたってやっぱりおかしな人ね、ギアメーカー?」
女の口ぶりは、飛鳥を批難するふうだった。飛鳥が純粋に友人としての気持ちだけで彼を行かせたわけではなく、何らかの思惑を持っていることに、彼女は勘付いていた。
「だろうね。でも今の行いは、割と人道的だと思うよ。更に言えば僕自身は、フレデリックをギアにしたことも、アリアをギアにしたことも実はまるで後悔していない。だから多分君を造った僕も考えていることは同じだ」
「あれ? 気がついてた?」
いつから? 女が謳うように尋ねる。休眠状態だったジャスティスを共鳴反応で叩き起こした元凶は、場違いな笑顔で飛鳥を詰る。
「最初から。アリアの魂を入れてものを造ろうなんて考える人間が僕以外にいるわけがないからね。いたとしたら、そいつには多分人の心がないよ」
アリアと同じ笑みを意に介した素振りもなく、ギアメーカーが淡々と言った。