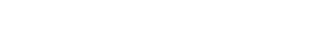04 自覚のない病・後
——神様、でもわたしは、祈ったじゃないですか。
どうか世界を救ってください、ううん、そんな大それたことお願いしませんから、『世界を救わせてください』と、そうお祈りしたはずではありませんか。
神様。それさえも大それた願いだというのなら、せめて私の仲間達は、私と共に育った彼女は、誰よりも心優しい、あんなに戦うのがきらいだったのにそれでも人々のために戦い続けている
それなのに、どうして。
どうして私の世界は救われないのですか、神様。
ありったけカーゴを飛ばし、あとは四肢が千切れるほどの勢いで走り続けたものの、フレデリックがスウェーデンに着いた頃にはとっぷりと陽が沈んでいた。あれきり、カイとも飛鳥とも通信をしていない。ディズィーが陥っているであろう状態を思うと気が気でなくて、指先は何度もメダルを掠めたが、ついぞ起動は出来なかった。
カイ達聖騎士団の部隊が駐留している場所は、ドランメンで集落が残っているあたりを訪ねてすぐに見つかった。ある一角に密集した無数のテントと、その周りに溢れている意気消沈しきった兵達。皆一様に重苦しい表情をして、時折、少し離れたところにある建物の方を見ている。
「お待ちしておりました」
人の群れを掻き分けて建物内に入ると、余程待ちかねたのか、慌てた様子ですぐさま一人の男がやって来てフレデリックを先導した。
ベルナルド。カイのお守りを、飛鳥ではなくクリフに命じられている男。
彼が仕えているクリフはざっくばらんな性質だが、この男自体は何を考えているのかよくわからず、いつも腹が読めない。端的に言ってあまりフレデリックは好かないタイプの人間なのだが、さしもの彼も今は表情から焦りを隠し切れずにいるようだ。
……この男はこんな顔もするのか。焦燥でまともに思考が働くなりかけている脳味噌が、そんな現実とは乖離した事柄を思う。
「ディズィーは」
混迷する思考を覆い隠そうと、短く問うと彼も手短に応えた。
「今夜が峠といった様子です。一応救護班の者に診させてはいますが、カイ様の命で止血程度の応急処置と経過観察に限らせています。そのカイ様も、長時間付き添われ……今は重篤の状態です」
「チッ……飛鳥の言っていた通り、法力譲渡をしたのか。あんなものやらせたらどうなるのか、互いに分かってただろうに、あの坊やは」
「言って聞いてくださるのなら私がこの身に変えてもお止めしましたとも。ですが無駄だということをあなたもおわかりでしょう。カイ様はディズィー様を失いたくなかったのです。そのためならご自身の命さえ惜しくない、と繰り返し言っておられた」
「馬鹿野郎が。失われていい命などありはしないと普段説いてるのはどの口だ」
急ぎ足で廊下を歩き、案内された部屋の中にノックもせずに入り込む。簡素な部屋に質素な二台のベッド。その上に一つずつ横たわる、生と死の狭間にいる子供達。
「ディズィー……カイ……!」
一瞬、二人の胸元にぽっかりと大きな穴が空いているかのような錯覚を覚えた。
ろくな設備もない中、かろうじて息を繋いでいる子供達とその周りに侍る救護班の人間達。その構図は、死者の骸に手向けをする葬儀の参列に似ている。荷を降ろし、最低限身を清めて手袋をはめるとフレデリックは二つのベッドの間に割って入った。微弱だが、脈はある。生き返る。今なら、まだ。
「ベルナルド。人払いを頼む。救護班の人間も全てだ。テメェと数人だけ、部屋の外で哨戒を続けてくれ。出来るか」
「無論です。頼みましたよ、フレデリック様。……ここだけの話、私は飛鳥様のことは信用しておりません。あの方はどうにも得体が知れない。しかし……あなたにはカイ様を預けられます」
「余計な口を回してる暇があれば出て行け。俺はカイもディズィーも平等に救う。何を心配しているのかは知らねえが、ディズィーを優先してカイを見殺しにするなんざ俺はしねえよ。……俺の娘はディズィーだけだが、同様に息子はカイだけだ」
「……失礼しました」
フレデリックが目もくれず言い切ったのを確かめ、一礼と共にベルナルドが部屋を後にする。それに気付いたからなのかはわからないが、カイの瞼がぴくりと動いた。手を握ってやると、血の気の引いた指先から幽かに鼓動の音が聞こえてくる。
◇◆◇◆◇
ひどくつめたい。景色も、音も、五感の全てがひんやりして、変な感じだ。
でも、一体何が冷たいのか。それを確かめるためにカイは瞼を開いた。
(ここは……)
カイは知らない場所にいた。知らない場所だったが、目を開けてすぐ視界に映った男が何者かはすぐに理解する。カイの大好きな顔。ひょっとしたら……いや、ひょっとしなくとも、もう自覚している……実父の飛鳥よりも慕っている男の姿がそこにある。
でも、彼の正面に立っている誰かの姿を認め、カイは不可思議な現象に首を傾げた。
(フレデリックと、それから、あれは……わたし?)
自分の視界の中に、自分の姿? 不可思議に思って瞬きを何度もして目もこすったが、一向に見慣れた自分が消える気配はない。じゃあ、偽物だとか、よく似た他人だとか。しかしその可能性もなさそうだった。きっちり着込まれた聖騎士団の制服も、その中に収まっているやや童顔めいた顔立ちも、忙しくてあまり手入れできずにいるのを気に掛けている短い金髪も、カイが持っているもの、普段鏡の中に見るそれと寸分違わない。
(なら、これは夢なのかな)
そう思うと途端に色々なものがしっくりときて、カイはふむふむと頷いた。
自分は今、夢の中にいる幽霊なのだ。だから色々なものはちぐはぐだし、今目の前にいる自分らしきものがこれから何をするのかもさっぱり見当が付かない。であれば自分がどうしてここにいるのか理由がわからないのも当然だし、前後の記憶がはっきりしないのも仕方がないこと。
そこまで考えて、カイは首を振った。自覚している幽霊の身体は、己の思うようにきちんと動く。
改めて視線を戻した先にいる夢の中のカイは、フレデリックを正面に見据えて、何か酷く真剣に話し込んでいる様子だった。内容は、距離が離れていてうまく聞き取れない。でもきっと、とても深刻な話に違いない。だってあのフレデリックが顰め面をして、でも怒り出したりもせず、じっとカイの話に耳を傾けているのだから。
(何を話しているんだろう?)
気になって、ふわふわと二人の傍へ近寄った。自分は幽霊だと認識したから、そういうふうに移動出来るのだろう。明晰夢というやつだ。これが滅多に見られる性質じゃなくてひどくつまらながったものだ、と父が昔言っていた。
(——って、えっ!?)
けれど、彼らの傍へ寄るなり物騒なものが目に入って、カイは面食らって口を押さえてしまう。
「おい待て、カイ! 馬鹿なことをするんじゃない!」
カイの目の前に立っているフレデリックも声を荒げている。でもそれは当たり前だ、と幽霊のカイは思った。だって夢の中のカイが手にしているのは鋭利に光る銀色のナイフだったのだ。食事用のものではなく、ちゃんと戦闘に使えるような業物だ。
それにしたって、何故。カイはナイフも得物として扱えるけれど、それでもやっぱり剣が一番手に馴染む。それは、腰のベルトに剣を下げている夢の中のカイだって同じのはずだ。
(……あ! もしかして……いえ、そんな、まさか……)
そこである可能性に思い当たり、誰にも聞こえていないのに思わず口に手を当てて噤んだ。
一つだけ、思い当たる理由がある。用途の違いだ。カイが剣を用いるのは、敵との交戦にそれが最も適した武器だから。同じように、たとえば林檎を剥く時はナイフを選ぶ。剣では対象に対して効率が悪い。
だとすれば、今、この場でナイフを使うのに一番適したものは……。
「止めても無駄ですよ、×××。あなたが悪いんです。あなたが……私をちゃんと見てくれなかったから……」
はっとしてそこへ視線を向けた瞬間、夢の中のカイが、うっとりと口を開いてナイフの切っ先を己の身に当てた。
幽霊のカイはぞっとしてそこから目を離せなくなった。(だって、)ナイフが当てられているその位置は。(父さんが、聖痕みたいだって言った、私の……)彼の喉元、人間が持つ急所の一つに他ならなかったのだから。
「さようなら、×××。次はちゃんと、私のことを、あいしてくださいね?」
カイが笑う。微笑さえ浮かべ、安らかに。フレデリックの手が伸びる——でも無駄だ。届かない。カイの口角が上がり、嗤い顔が、目撃者の目に灼き付く。
そうしてかれは、引き留める男の手も虚しくナイフを喉元に突き立てた。
ぶちゅりという、肉と皮を突き破るいやな音。そのままずぶずぶと奥深くまで刃が侵入していき、中程までめり込んだところで、残された最後の力で勢いよく引き抜く。動脈をしたたかに傷つけられ、喉が悲鳴を上げる代わりに血をまき散らし始める。あかいろの噴水。場所だけでも致命的だが、出血量も致命傷だった。最早かれに生き残る術は残されていない。
まだなまぬるい「さっきまでは生きた少年だった肉塊」がゆっくりと床に崩れ落ちる。フレデリックは届かなかった手を藻掻くように動かしてそれに追いすがるが、手遅れだ。残された体温もほどなく消えてかれは完全な死体になる。
それを確かめ、フレデリックが絶叫した。
彼の雄叫びには、悲しみも勿論含まれていたが、それよりもうんと強く怒りが滲んでいた。まったく当然だと幽霊のカイは思った。目の前でいきなりわけもわからず自殺される。しかもそれはおまえのせいだなどと詰られる。夢の中のカイとフレデリックがどういう関係なのかは知らないけれど——やはり続柄は、親子ぐらいのものに見えた。だとすればその怒りには、我が子同然の存在が追い詰められていることにも気がつけず、むざむざと殺してしまったことへの自責の念も含まれているのだろう。
幽霊のカイは恐る恐るかがみ込み、自分と同じ顔をしている少年の顔を覗き見た。すっきりした死に顔だった。こんな顔をされたら、フレデリックはよけいやるせないだろう。でも、それにしたってどうしてこんなことをしようと思ったんだろう。幽霊のカイにはそれがよくわからない。彼にはまだ、自死に至るほどのプロセスが理解出来ないのだ。
(ねえ、私。どうしてそんなことを、したんですか、あなたは。だってこれであなたの何もかも、終わってしまうじゃないですか……)
人差し指でかれの頬に触れようとして独りごちる。指先は何に触れる事も出来なかったが、代わりに、死んだはずの少年の瞳がぎょろりと動き、幽霊のカイを凝視する。
悲鳴を上げる間もない。死体の眼球はカイを射貫き、金縛りにする。動かない身体に死体から無数の糸が伸びる。死体が、かれが、笑う。決してその笑みは狂気的ではない、むしろ優しいくらいだ、でも悲しいぐらい、狂っている。
「——ねえ、わたし。どうして、これで終わりだなんて思うんですか?」
そうして〝かれ〟の囁きと共に地獄が始まった。
一度目の死は、喉を突き刺した自殺。
二度目の死は左胸を深々と貫いて。
三度目は男の前で服毒をして。
四度目は男の見ている前で崖から身を投げ。
五度目はまた喉を切り裂き。
六度目は男がギアを殺そうとした刃に己を投げ出し。
七度目は逡巡の後に喉を切り裂き。
八度目は炎の中に身を投じ。
九度目はわざと前へ出てギアに四肢を引き裂かれ。
十度目は心臓を抉り抜いて男に差し出し。
十一度目は笑いながら首を切り離して。
十二度目は男の腹の上で舌を噛み切り。
十三度目はまたもや喉を突き刺して。
……その果てに、ああ、もはや数えることも愚かだが、
五千百八十九兆六百五十二億千九百八十一回目に、やはり喉を切り裂いた。
形を変えて繰り返される狂気の光景。生きていたものが、必ず男の目の前で自殺をして巻き戻る。死の瞬間だけが延々と続き、そのたび、死んだはずの無数の少年たちが幽霊のカイに語りかける。
「ねえ、わたし」
「まだ、わかりませんか?」
「わたしが死ぬのは」
「わたしたちが死ぬのは」
「どうしてなのか。もう、わかっているでしょう?」
違う。その度に首を横へ振る。違う違う違うそんなことはない。死にたくない、生きてたい、こんな惨めな、無様な、子供の癇癪みたいな終わりなんて、望んでいない。
「うそつき」
「本当は知っているくせに」
「まだ見てみないふり」
「だけどね、わたし」
「いつかはわかりますよ」
「だってそういうふうにあなたも出来ている」
「いつか目を背けられない決定的な瞬間がやってくるのに」
「苦しいでしょう。わたし」
いやだ。そんなことは知らない。失われていい命などどこにもないのに、況んや、誰かに繋がらない死など、無意味だ。等しく無価値だ。この屍の羅列は、全て全て何の意味も持たない独り善がりの行為に過ぎない。
「無自覚でいたいんですね」
百八人目の少年がくすくす笑いと共に眼球を抉り。
「でも無自覚でいたいということは、かえって自覚的であることの証明にすぎないんですよ」
五千十一人目の少年が哄笑しながら頭蓋を砕き。
「だってあのひとにもう言われたでしょう。あなたの抱える、最も大きな病巣」
三千二百八十八万九百五十四人目の少年が瞼を伏せってロザリオを心臓にねじ込み。
「そう。自覚症状のない病、です。ないものねだりの私」
七百十九億四千二百七十八万六千八百二十二人目の少年が楽しそうに腹を捌き。
「いやだ……いやだ、こんなのは、いやだ! 私はそんなもの知らない。知りません。自覚症状のない病だなんて! 父さんが、あのひとが、勝手に言っているだけなんです。そんなものは存在しないんだ。全部全部夢の中の幻なのに!!」
そうして、五千百八十九兆六百五十二億千九百八十二人目の少年は頭を抱えて蹲る。
どれもこれも酷い死に様の生温かい死体が彼の周りに積み上がり、致命傷を帯びた少年達が彼をぐるりと取り囲んでいた。「本当に?」目玉のない死体はちょっと驚いてみせる。「意地っ張りですよね、わたしは」首なしの少年は、抱えた頭蓋から言葉を投げつける。「でもあれを見て、その上でまだそんなことを言っていられるんですか、わたし?」
土手っ腹に風穴の空いた少年がけたけた笑いをして幽霊を詰ると、途端にさあっと風が通り抜け、五千百八十九兆六百五十二億千九百八十一人の死体がたちまち消えてなくなった。嘘みたいに、出来損ないのスプラッタホラーみたいなものたちが世界から消えてなくなる。
幽霊のカイは恐る恐る、顔を上げた。もしかして自分は、この悪夢から解放されたのだろうか? どうかそうであって欲しい。もうこんなのはたくさんだ。カイは願う。帰りたい。一秒でも早く、彼の待っているはずの現実へ!
そう祈りながら振り向いた先に、フレデリックの姿が見える。ああ、やっぱり。良かった。フレデリックと、ディズィーと、それからカイ。カイとディズィーはベッドに横たわり、それをフレデリックが必死に介抱している。
幽霊のカイはほっと胸を撫で下ろした。きっとこれなら、もう「わたし」が死ぬ場面は来ない。あの延々と繰り返される悪夢を見なくていい。だってあの「わたし」はナイフを持っていない。剣もない。何より深く眠りに落ちていて、意識がないし、フレデリックはそんな「わたし」を必死に生かそうとしている。
『死ぬな』
フレデリックの懐かしい声が、カイとディズィーに向けられていた。平等に。彼が血を分けた娘と等しく真剣に。まるでカイ自身、フレデリックの血を分けた息子であるかのように。
『死ぬな。俺の娘を生かそうとして死ぬなんざ、んな馬鹿な真似、許せるわけねえだろ。テメェは、ディズィーが生きた方がいい……なんぞと、考えたのかもしれないが。ディズィーが死ぬのも坊やが死ぬのも、同じぐらい、最低のことだ』
フレデリックの声は恐ろしく優しかった。大好きな人の優しい声。とても嬉しいものだ。不快な要素などどこにもない。
だというのに、その声にどうしてだかちくりとする痛みを覚えてカイは胸元のロザリオを握りしめる。……かみさま。お許しください、かみさま。私は今おかしなことを考えています。この胸の痛みが、あなたを疑えと、私に語りかけてくる。
確かに私は、祈りました。日々あなたにお祈りを捧げました。どうか世界を救わせてください。あの愛らしい少女をお救いください。そのために私は全てを捧げましょう。兵器であることを受け入れますし、わがままも最後まで言いません。
でも——かみさま。
私の世界を救ってくれない神様、あなたは一体、何者なのですか?
『なあ、カイ』
フレデリックの声音は、依然としてカイに向けられている。その光景に段々と「安堵」と「恐怖」の乖離が始まり、カイはいつの間にかロザリオを手から取りこぼしてしまっていた。思考が段々と冷え渡っていく。悪夢から逃れられた喜びが、蘇ってくる事実による恐怖で塗り潰される。
(あ……うそ、そんな、なんで……)
そうしてはくはくと息を漏らし、思わず口を手で覆った。
夢の中のカイは、目の前にある光景の意味を思い出しはじめていた。そう、この光景はまぎれもなく〝今生きているわたし〟にとっての現実。現在進行形で進んでいるもの。私たちはスウェーデンでジャスティスと遭遇し、ディズィーは瀕死の重傷を負った。それを助けるために私は彼女へ持てる全てを明け渡し、彼女は短い命をほんの少しだけ生き長らえさせ、代償に私自身も死の淵を彷徨うことになった。
だから〝この〟悪夢は、生と死の狭間で見る限りなく真実に近い幻で。
起きている自分が絶対に自覚したくなかった、深層心理の現れだったのだ。
「ああ……そういう、こと、なんですね……」
カイはがくりと膝を折ってへたり込んだ。自覚が自意識の隅々にまで及び、幽霊のように薄ぼんやりしていた自我が次第に輪郭を得ていく。激しい動きにロザリオが揺れ、心臓の位置に当たるとチェーンが切れてぽとりと床へ落ちた。カイは恐怖に目を見開き、浅い呼吸を繰り返す。
カイは頭を抱えた。もう二度とこの夢を見る前には戻れない、と思った。カイはとうとう自覚してしまった。ずっと目を逸らしていた、自分の本当の気持ち。父が指摘したもの。抱いてはいけなかった禁忌。
自覚症状のない病。
「酷い。むごいじゃないですか、かみさま……」
ぽつりと漏らすのと同時に水滴が落ちる。ああ、でも、もう誰にも嘘は吐けない。何故ならばこれこそが私の抱える大いなる病巣。ディズィーのそれが肉体に巣くうものなのだとすれば、わたしのそれは、精神に巣くう逃れられない病。
だって、わたしの信じるかみさまは。
わたしが、本当にお祈りしていた相手は。
わたしが五千百八十九兆六百五十二億千九百八十一回死んでも欲しかったものは……。
『死ぬな。例え血が繋がっていなくとも……テメェも俺の息子に変わりない』
カイはフレデリックの声を聞きながら、愕然として己の手のひらを見ていた。手のひらは赤かった。それはきっと、今までに死んでいった全てのカイの血がそう見せているからに違いなかった。今にもやわらかな心臓が飛び散っていきそうなあかいろを眺め、カイは泣き笑いをする。最早、五千百八十九兆六百五十二億千九百八十二人目のカイも、五千百八十九兆六百五十二億千九百八十一人の亡霊が囁いた事を無視することが出来ない。
「私の事を、血が繋がってなくたって、息子にかわりない、って」
フレデリックの言葉が頭の中でがんがんに鳴り響いていた。嬉しいです、フレデリック。私の事も、ディズィーと同じように、あなたの血を分けた少女と同じように、本当の子供として愛してくれたんですね。それは喉を掻きむしりたいくらいとても嬉しい。
でもね、フレデリック。わたしの——かみさま。
かみさま。わたしのお祈りしてきたかみさま。わたしの信じる世界全てを形作るかみさま。違うのです。わたしはそんなことを望んではいなかった。
あなたの子供になりたいなんて、一度だって、願ったことさえなかったのに。
こんな絶望を知るぐらいなら、わたしはあなたに近しい人間として、生まれたくなんかなかった。
◇◆◇◆◇
その晩は、フレデリックがこれまでに経験した中でも間違いなく、五指に入るほど長い永い夜だった。
ありったけの知識と法力を駆使し、精魂使い果たしてばたりと腰から崩れ落ちた頃には、もう夜が明け始めていた。窓の外から見える朝焼けがこんなに美しいものなのだということを、今日この日が訪れなければ一生知らぬままだっただろう。
白む空が滲んで見える。夜明けを知らせる鳥が、ひどく澄み渡った声音でさえずっている。
「……サヨナキドリの、声……」
ベッドの上から、少年の幽かな声が聞こえた。
「私、生きてるんですね、まだ」
「……ああ」
「もう、死ぬのかとばかり思っていました。私の役割は、ディズィーの補助。彼女を生かすための延命装置だったのだから」
「馬鹿を言え。テメェの父親が何を言い聞かせて育てたのかは知らねえが、俺の目が黒いうちは、坊やをこんなところで死なせない」
「……。そう、ですね。私の死に場所はここじゃない」
ゆるやかな動きで、少年が起き上がる。まだ顔色は僅かに白く、全快と言える様子ではない。殆ど死にかけていたところを強引に生者へ引き戻したのだ。代償として、いくらかの休養期間は必要だろう。
窓近くに伸びた木の枝に小鳥が止まっている。先ほどカイが言った、サヨナキドリだ。薄茶色い体毛に覆われた鳴き声の美しい鳥。それを不意に指さし、カイが呟く。
「私って、あの鳥みたいだなって、思ったんです」
「ああ……別名が、ナイチンゲールだったな。その通り、つきっきりでディズィーを生かそうとしたからか?」
「いいえ。ただあの鳥が、墓場鳥とも言うから」
「——はあ?」
「……ううん。なんでもない。なんでもないんです、フレデリック。……私を生かしてくれて、ありがとう」
ぽつりとぼやいたカイの台詞にぽかんとしてしまって、フレデリックは死の淵から生還したばかりの少年の瞳をじっと見つめた。エメラルドブルーの眼球は、見慣れているはずなのに、その時どうしてだかガラス玉みたいに見えた。彼の瞳の中には希望がなく、ただ、薄暗い深遠にまで続く悲しみだけが見え隠れしている。
「あなたがくれたこの命、ちゃんと有効に使いますよ」
カイが言った。彼が窓を開けて手を伸ばすと、枝に止まっていたサヨナキドリは急に飛び立ち、どこにもいなくなってしまった。