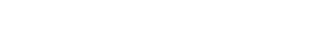06 たった一つの奇跡
ずっと変わらないものがあると信じていた。
たとえばそれは、親友の男が変わらず傍にいたことと同じように。
愛したものは、その愛を理解して返してくれるという、根拠のない妄想を百五十年の間抱いていた。
「あなたに、お別れをしなきゃ。さようなら、私を愛してくれてありがとう、って」
かれがナイフを喉に当てて宣告する。変わらないものは世の中に一つもなく、与えた愛情は正しく理解されないということを証明するように。衝動的にナイフをひったくろうとして腕が動かないことに気がつき、立ち上がったはずの身体もいつの間にか床へ落ちていたことを自覚した。法術により拘束されている。しかもそれなりのギアを長時間縛っておくための強力な術式でだ。
まさかあの状況でこの相手に拘束式を使われるとは思ってもいなかった、その油断が招いた結果だ。くそ。唯一自由に動く口で盛大に舌打ちをしてやると、かれはちっとも悪びれていないふうに「すみません」なんて宣う。
「あなたに抵抗されると、面倒なので。一応これも、ディズィーに許可は取りました。多分フレデリックは私を止めようとするから、その時は拘束術式を掛けますよ、と」
「さっきからゴチャゴチャ何言ってやがる……! 一体何をするつもりだ。俺の娘に、何、吹き込んで……」
「何って、自殺ですよ。ディズィーには、その断りを予め入れただけ。彼女に黙ったまま行くのだけは、ちょっと、胸が痛んだので」
「はあ……!? 自殺だ!? 寝言は寝て言え、このきかん坊が……!!」
「聞けません。あなたの言葉でもこれだけは。ううん……あなたの言葉だから、聞きません」
フレデリックの言葉にきっぱりと首を振ると、かれは一度、喉に当てていたナイフを降ろした。しかし自殺をやめる素振りはこれっぽっちもない。フレデリックは力の限りかれを睨み付ける。そんなことしか出来ない自分がこの上なく恨めしい。
カイは本気だ。こんなつまらないことで笑えない冗談を言う子供ではないことを、フレデリックは誰よりよく知っている。
「なんで……んな、馬鹿なことを言い出した? ディズィーに断りは入れただ? それで、止められなかったから、自殺をするとでも言うつもりか、坊や」
「ええ」
「阿呆が。それはディズィーの優しさを利用しているだけだろうが! ディズィーが……例えどんな決断だろうと、テメェの決めたものを絶対に遮らないと、俺が分かってるんだ。テメェ自身、分かっていたはずだろうが!!」
「……ええ。そうですね」
糾弾の声は、自分でも驚くほどするするとフレデリックの口からあふれ出した。先ほどヴァレンタインにそうできなかった分、悪し様にかれを罵り立てる。何故。何故だ。どうして。疑問符ばかりがフレデリックの胸中に渦巻く。昨日まで、いや、ついさっきまで、かれがそんなことを考えていたとはフレデリックにはわからなかった。かれはディズィーが死に瀕している際は己の命を譲渡しようとしかけたが、それだって、父親の言いつけを守ったからにすぎず、死にたがっていたからではなかったはずだ。
あの時、胸騒ぎがなかったわけではない。自分を墓場鳥だと言ったかれの目はガラス玉に似ていた。けれどそれ以降はいつも通り元に戻っていたから、ただの見間違いだろうと思い込んでいた。
それになにより、かれは言ったはずではないか。「あなたがくれたこの命、ちゃんと有効に使いますよ」、と。
「テメェの命、有効に使うんじゃなかったのかよ。それが自殺だなんざ……」
「一番有効に使いたいから、自殺するんですよ。あなたに貰った命をあなたに返すんです」
しかしそんな儚い希望も瞬時に打ち砕かれる。めまいがした。許されるなら、この場で意識を失って、目が覚めてから全ては夢だったんですよと言って欲しかった。
「揚げ足取りだ、そんなもんは。大体、ディズィーに断り入れてくるぐらいだ、あいつが悲しむことはわかってんだろうが。……テメェは——愛していたんじゃ、なかったのかよ。俺の一人娘を。テメェになら、まあ、やってもいいかな、なんて馬鹿みてえなことを、俺は思ってさえいたというのに……」
「ええ。彼女のことを私は愛しています。そして彼女も、私を愛してくれました。だから彼女は私の裏切りを許してくれたし、私を送り出してくれました。彼女は私の数少ない理解者の一人だ。それはずっと変わりません」
「なら、なんで、んな真似」
「……でもね、フレデリック、違うんですよ。足りないんです。私はそれじゃ、満たされないんです。だって……」
簡単なことなんです、と人差し指を唇に添えてかれは言う。栄華を誇るものがいつか滅びるように、満開の薔薇の花もいずれ朽ちるように、そのくらい、簡単なことなんです、そう囁いて。
「私が父になれないように。彼女も、あなたにはなれないんですよ、決して」
そうしてぞっとするような笑みを見せ、かれは、「それはおよそあらゆる全てへの冒涜なのだから」と口ずさんだ。
「私は父にはなれない、だからあなたも私を父と同じように扱いません。父がいる限り、私はあなたにとって、父の子に過ぎないわけです。むしろ私を父と同一視する方がよほどおぞましい所業でしょう?
……それと同じなんですよ。私は彼女を愛するからこそ、彼女にあなたの面影を一切求めたくはなかった。彼女はあなたの娘であって、決してあなたの代替品ではないのだから。でも……でも、です、フレデリック。私は彼女が愛してくれたのと同じように、あなたに愛されたかった。これが、私の唯一にして最大の罪。私の背負った最も深き業。そして言い換えるならば、何度繰り返しても逃れられない、私という存在そのものに課せられた原罪……」
「何……わけわかんねえこと口走ってやがる。それじゃテメェはなんだ?
「……そうだったら、いくらもましだったでしょうね。でも私の父は——飛鳥=R=クロイツという男は、神様なんかじゃないですよ。私にとっての、それでさえない。
フレデリック、私はね、これまでに5189065200001981回の自殺をしました。その全てで私はあなたに惹かれ、そうしてあなたは私のものにはならなかった。ううん——私のものになってほしい、なんてそんな傲慢、一度も願ったことさえない。私はただ、本当に、あなたに愛されたかっただけなんです。親友の息子としてではなく。はたまた、愛娘の恋人としての情でもなく。一人の人間として……」
唇から離された指先がフレデリックのヘッドギアをなぞり上げた。
五千百八十九兆六百五十二億千九百八十一回の自殺。その途方もない数字を、妄言は大概にしろなどと言い棄てることが、フレデリックには出来ない。間近に迫ったかれの喉元に刻まれた傷痕に目が吸い寄せられて、離すことが出来ないからだ。生まれつきそこにある消えない傷なのだとかれが嘆いていたそれを、或いは聖痕のようだと飛鳥は評した。ヘッドギアの下にフレデリックが隠しているあの痕跡のように。聖痕とは、決して祝福の名前ではなく、呪わしき象徴を示す言葉。
ならばかれの聖痕は。
かれの、呪いとは……。
「……だけど、また、叶わなかったから」
飛鳥が度々口にしていた、「自覚のない病」の正体に思い至ってぞっとする。なら、「止められない」のか。アリアから手を離してしまったように、かれからも、この手は離れて行ってしまうのか。
そんなことは許されない、と思う。
「さようなら、フレデリック、善き人。あなたは本当にいい人だ。あなたのことを知らない人からはいつも誤解されてしまうけれど、私はあなたより善い人を、きっと他に知りません。あなたは人としての規範をよく守っている。神様が我々に与えた倫理観、即ち長寿と繁栄のための本能をきっちり理解している。私とあなたは——近すぎたんです。中途半端に。もっと、赤の他人に生まれていればよかったのにな。そうすれば、あなたと出会えないかもしれない代わりに、こんなものを手に取る必要もなかったかもしれないのに……」
なのに身体はちっとも、動いてくれやしないのだ。
「おい、馬鹿、やめろ、クソッ——やめろ、カイ!」
「次に会う時はせめて、あなたが私のことを殺してくれますように」
そうしたら、もしかしたら……あなたの中で私は永遠になれるかもしれないでしょう?
かれは微笑んだ。主命を果たした今際の天使が、その命を主上へ返還しようとしている、そういう題の絵画に描かれているような顔をしていた。認められなかった。たった十五年生きたぐらいで辿り着けるものじゃない。かれが何億何千兆と、数えるのもばからしくなるくらい、自殺を繰り返していることをその顔が雄弁に物語っている。
嗚咽がせり上がってくる。まだ指一つろくに動かない。きっと術者である彼が倒れるまで、呪縛は消えてくれない。この感触を知っている、とフレデリックは思う。この感情を知っている。この悲しみを、苦しみを、やるせなさを、怒りを、知っている。
「だから——どうかあなたは、私を殺してくださいね」
そうして、フレデリックが喉からせり上がってきた感情を吐露しようとしたその間際、かれは死んだ。
死んだのだ。確かに、もう二度と還らぬ命と成り果てた。かれは男の見ている前で、それも触れ合うほど近く、己の喉にナイフを突き立てた。
「馬鹿野郎、が……!!」
その瞬間自由になった両腕で床に転がる前にかれを抱きとめ、無駄だと知りながら脈を測った。止まっている。喉を一突きしただけで上手に死ねるように、ナイフに法術的な仕掛けをしていたのかもしれない。或いは即効性の毒か。いずれにせよ、手遅れだ。
「何が、殺して欲しい、だ」
喉を突き破った嗚咽がでろりと零れ落ちる。あんなに聡明だったのに、こんなことも分からないくらい分からず屋だったのは、あの男の子供だからなのか。
「テメェが何度望もうが、何度自殺を繰り返そうが! 知ったことか。俺がテメェを殺すなんざ、ありえねえ。だってそうだろう。生きて欲しかった。生きていて欲しかった! たったそれだけの、単純な願いだろうが! 親だとか——子供だとか——関係ねえよ。ひとが、ひとに、生きていて欲しいと切望する、この何がいけない。何がテメェをそうまでさせたかなんざどうだっていい。俺は絶対、テメェを殺したりなんかしない……!」
フレデリックが叫ぶ。獣の挙げる雄叫びのように咆吼する。この感情をどうすればいい。吐き出し方が、わからない。
「——いや、だめだフレデリック。〝次は〟君にあの子を殺してもらわなきゃいけない」
その慟哭を、不意に響く冷静な声が遮り止める。
「だめだよ。次こそ、君があの子を殺すんだ。今回はもうこれで終わりだが……次は、どうしても」
聞き慣れた声にかっと頭へ血が上り、フレデリックは死体を抱き抱えたまま声がした方へ振り返った。飛鳥=R=クロイツ。百五十年一緒だった悪友。カイの父親。その男が、いつの間にかそこへ現れ立っている。
「……飛鳥……!?」
「落ち着いて。もう術式は始まっている。カイの死によって訪れた世界の終わりはもうそこまでやって来ている。無駄かもしれないが、せめて僕は出来る限りのことを伝えてから行かないと」
見慣れないフードを被った飛鳥は、心なしか顔色が白く病的に見えた。けれどそれより目を惹くのが、右手のひらに掲げている仄かな光だ。光はヴァレンタインの女と同じ色をしてゆらゆらと明滅し、こちらへ差し出されている。でも今のフレデリックにそれ以上を考える余裕はない。
分かるのは、息子の死体を見ても眉一つ動かさない男が、かれがこうなることを知っていたのだろうという予感だけ。
「テメェ……見ていたのか。いや、違うな。
やり場がなくもてあまされていた怒りの矛先が飛鳥へ向く。かれの死体から手を離し、その手で飛鳥の首根っこを掴み取り、乱暴に壁に押し当てた。そうしてフレデリックは子を奪われた獣の顔つきで犬歯を剥き出しにし、飛鳥を睨み付ける。
「なんとか言ったらどうなんだ、テメェは!!」
飛鳥は酷く醒めた声でそれに淡々と答えた。
「ああ、そうだね。僕は概ねを把握していた。カイが自覚のない病を……君への恋慕を患っていたこと。自殺を繰り返していたこと。故に今回も、どこかで必ず自殺を図るであろうこと。最近になって、かなり正確にそのあたりの実態が掴めた」
「ならなんで止めなかった!」
「じゃあ逆に聞こう、フレデリック。何故僕が止めてやらなきゃならない?」
「……!!」
フレデリックの指先が布地を越えて飛鳥の皮膚に食い込む。しかしその状況においても、飛鳥に恐怖の色は見られず、彼の瞳はただ静かにフレデリックを見据えている。フレデリックは口ごもった。何かもっと恐ろしいことが問い詰められた飛鳥の唇から飛び出してきそうな気がして、喉がひくつく。
聞きたくない。でも耳を塞ぐための指は、彼を締め付けるのに使ってしまっている。
「まず第一に、僕は彼の意思を尊重したかった。いいかフレデリック、カイの決断は、決して誰かがそそのかしたものではない。むしろその逆で、カイはそんなこと、一度たりとも僕に話してはくれなかったよ。彼は僕を信用していなかったからね。その上で勝手に聞き知った内容で止めるなんてこと、僕には出来ないさ。それにね」
「やめろ……」
「カイがどうなろうと、どうだっていいんだよ、僕は。だってカイが死んだところで僕のやることは変わらない。僕の立ち位置は揺るがない。フレデリック、君は、僕だけを、僕として見続ける。これまでもこれからも。あの子はそれが耐えられなくて何度も自死を選んだけど——それってただの弱さだろう。
あのね、フレデリック。君はきっと、まだあの子がどうしてそんな決断をしたのか、君を求めて死んだのか、その本質を理解していないんだ。ただ……確かに、それを理解している時点で僕は親としてはどこまでも不的確だったのかもしれないね」
「やめろ……聞きたくない……!」
「カイは、僕のクローン。あの子は、僕のコピーなんだよ、フレデリック。それも成育環境をオリジナルに近づけすぎた。そうしたら、オリジナルとコピーが抱く願いなど、同質になるに決まっているだろう? そうしてたいていの場合、それらの問題に直面するとオリジナルではなくコピーの方が自己存続の証明が図れなくなって自死する。昔大学で習わなかったかい? 人間の自我をAIとして複製すると、己が複製品——偽物である事実を認識した瞬間、自己肯定が行えなくなってしまい自壊してしまうんだ。それと同じ。ただカイには肉の器があったから、心臓を壊さないと自壊出来なかったんだよ。それだけの話なんだ」
「——やめろ!!」
飛鳥を壁に押しつけたまま、フレデリックは絶叫した。聞きたくなかった。知りたくもなかった。カイが仮に親への慕情を越えた感情をフレデリックに抱いていたとして、「それが飛鳥のコピーだから」なんていう理由は、永遠に知らないままでいたかった。
「でも、フレデリック。喜ばしいこともある」
「何が……」
「仮にカイが僕のコピーであることを自覚しないまま成長したとしても、あの子は何度でも君を求めるだろう。そもそも、遺伝子が左右するのは嗜好の傾向までに過ぎないんだ。双子が同じ人間を好きになったりするのだって、嗜好が似通って同じ空間に生息している結果、矛先が向き得る人間が一人しかいなかったりするからだよ。でも、そうじゃないと彼女は証言した。彼の嗜好に選ばれ得る人間が君よりそばにもっといたとしても、彼は辛抱強く、君が現れるのを待っていたのだとね。しかるに彼の千兆を超える自死はその証明式だったわけだ」
「言ってる意味が、よく、」
「わからないって? じゃあ要点だけ抜き出そう。つまりあの子の願いは君がアリアに求めたものと何一つ変わらないということだよ」
ぴしゃりとした物言いに、頭に冷や水を被せられたような心地になった。
それまで現実味を持たずにふわふわしていたものが、急に鋭利な刃物になって襲い掛かる。アリアへの願いと同じだと言われてしまうと、途端に、フレデリックにはもう目が背けられず、何も否定出来なくなってしまう。一気に熱が冷めて、フレデリックは何かを言い返す気力というものをまるっきり失ってしまった。身勝手な幻想ほどたちの悪いものはないという言葉が、全て自分に返ってくるのはかなり嫌な気分だった。
「わかってくれた?」
飛鳥が邪気もなく問う。フレデリックは力なく首を振る。
「……当てつけか、そいつは」
「いや、時間が無いから手短に済ませただけだ。ともかく——だから君は、次はあの子を殺さなきゃいけない。そうしないとカイも、君も、たいへんに苦しむことになると思うから。これはお願いでもある。散々言っておいてなんだが、僕はこれでもカイの父親だからね。なら最後には子供に幸せになってもらいたいと、そう祈るのは、何かいけないことかな」
「そういうのはあいつが生きてる内に言うもんだ、馬鹿親」
「生きてるとあの子は僕の話なんか聞いてくれないからなあ。それに僕が息子をかわいがってるってことは、君には十二分にアピールしていたはずだよ」
首筋に食い込んでいた手から力が失われて、ずるりと飛鳥の身体が地面に落ちた。尻餅を付く格好で着地した姿に、けれど少しも笑いがこみ上げてこない。こんな遺言みたいなことを言い始めた人間が何を覚悟しているのか、ついさっき見せられたばかりだ。筋肉が隆起した己の腕を見てフレデリックは嘆息した。大事な時に大切なものを守れないのに、こんなものに、何の意味があったのか。
「テメェも死ぬのか、飛鳥」
弱々しい声で確認すると、飛鳥がはっきりと頷いた。
「そんなに望んでいたわけじゃないんだけど、もう時間なんだ。僕もあの子の元へ行かなきゃいけない。だけど悲観することは何もないよ、フレデリック。じき君も同じ運命を辿る。全ての生命体は一度ゼロに還る」
「俺には言いたい放題言って、勝手にくたばるのか。本当にろくな親子じゃねえ……」
「……いいかい、よく聞いて、僕の親友。最初に言ったね、もう始まっているんだと。もうすぐこの世界は崩壊する。そうして僕達は全ての記憶を失い、新しい世界を迎え、そこでまた一からやり直すことになる。だから今度こそ、カイを殺してあげるんだ。次の、次へ進むために」
飛鳥の右手に翳された光が勢いを増していく。視界が灼けるように白くなり、思考がホワイトアウトする。
「もし次の世界や、その次の世界で君が僕を愛してくれなくても——僕はずっと君を愛しているよ、フレデリック」
それを最後の言葉にして、飛鳥=R=クロイツはゆるやかに瞼を閉じた。
並べた死に顔は、息子と同じ表情をして、眠り姫のように凪いでいる。
◇◆◇◆◇
ゆるやかに瞼を開く。それからおもむろに起き上がり、カイは瞬きをした。
「……おかしいな。私は、確かにこの喉を潰して、確実に自分を殺したはずなんですが」
精一杯皮肉を効かせた声を絞り出し、事の首謀者であろう男の方へ振り返った。見慣れない白いフードを目深に被った男は、カイの問いかけにそうだね、と短く肯定を返す。
「確かに君は死んだよ。出血多量でもう心臓も止まった。おめでとう、五千百八十九兆六百五十二億千九百八十二回目の自殺も完了だ。今回もフレデリックは君を殺してくれさえしなかったが」
「あなたがそれを言うと嫌味にしかならないって自覚してます?」
「もちろん。だって君が望むものを手に入れられなかったのは、いつだって僕というオリジナルの存在が邪魔をしていたからだ。でも君は僕を殺そうとはしなかったよね。これまで、ただの一度も」
「……そんなことをしたって、フレデリックは私を選んではくれません」
「そうか。つくづく思ってはいたけれど、君は聡明すぎたな。ごめんね」
心にもなさそうな言葉を心底申し訳なさそうに吐いて、カイの父である男はフードを脱いだ。重苦しいフードの下から現れた相貌はカイが見知った父の姿より幾分も幼く、カイと同じぐらいの年頃の顔つきをしていて、右目を覆う羽や額の赤い十字なんかがなければ、まるで鏡と会話しているみたいだ、とカイは思う。
それにしても、どうして。父の姿にカイは首を捻る。死んだはずのカイがあたりを認識出来る空間なのだから、彼がおかしな格好になっているのは理解出来る。この空間は死後の世界で、だからきっと彼も死んでいるのだ。でも、その理由がカイには分からなかった。父は滅多なことでは殺したって死なない人間だった。寿命を超え、禁術を己に施し、百五十年近く経ってからクローン体とはいえ子供をこさえた男だ。
「それで、どうして貴方はここへ?」
だからそう尋ねてみると、父はひらひらと手を振ってみせる。
「死者の君と会話をしているんだ。もう薄々分かっているんじゃないかな」
あくまではぐらかそうとする姿勢にむっとして、カイは唇を尖らせた。大事なことを意地悪してなかなか教えてくれないのは、カイが知りうる中でもかなり高位の、父が持つ悪癖だった。
「結果がわかったところで、あなたの動機まではわかりませんよ。あなたの行動理念が理解出来た試しなんか、一度もなかった。父さん」
「そうか……それはちょっと悲しいな……」
「父さんの悲しみなんかどうでもいいです。それで、何故」
「んー、ああ、まあ、少しね。『最後』くらいは、親のエゴを押しつけたって構わないかなと思ったからだよ」
もやもやした気持ちのまま問い詰めると、彼は何故か非常にすっきりした表情でそんなことを言ってみせる。カイは露骨に信じられないという顔をすると父親の顔に思い切り指をさした。こんな真似は滅多にしないが、そんな心にもないを通り越して嘘で固めたような言葉を言われると、人の顔でも指さないとやっていられない。
「今更になって親のエゴですって? 自覚が遅いんですよ、あなたは! 父さんはいつだって私にそれを押しつけてきたじゃないですか。良い子でありなさい、ディズィーのスペアとして役割を全うしなさい、与えられた以上を望んではいけない、と」
「それはねえカイ、君もきっと親になることがあれば分かるのだろうけれど、決して親のエゴではないんだよ。ただの製造者のエゴだ。従順な兵器に対する期待でしかない」
「はあ……? なら、一体、何を……」
「僕はね、君に幸せになってもらいたいんだ。カイ」
その上大まじめな顔をして飛鳥がこうまで言うので、カイは父親を指さしたまま凍り付いたように固まってしまった。
「……は?」
「どうしたんだい、そんな顔して。何かおかしい?」
「何かって……全部おかしいでしょう……だってあなたは、私の事を、いつだって、そんなふうに見ては……」
「うーん。僕としては不器用なりに愛していたつもりなんだけどねえ。フレデリックにはたまさか親ばかと罵られたものだ。君の自死についてだって、科学者としての僕は歓迎を示したが、父親としての僕は複雑だった。君の祈りを無碍には出来ないから止めはしなかったけれど。でも君の死を見て、僕はエゴイズムを抱かずにはいられない。カイは本当に幸せになれなかったのか……とね」
「ッ……そんなものは、あなたの都合のいい言い訳です!」
「そうだよ。だから最初に言ったじゃないか。親のエゴを押しつける、って」
してやったりというふうに飛鳥が笑う。ふわりとした笑みは、新しい兵器を開発して上機嫌な時の彼がするものと同じだ。ああ、このひと、本当に、駄目な親。カイは唇を噛みしめる。だって飛鳥はカイの父親だ。カイが深く理解している相手なのだ。そんな顔をされたら、その言葉が他意も悪意もない本物だって分かってしまう。
「それじゃ……私に一体どういうエゴを押しつけるつもりなんです? 幸せになれなんて抽象的な言葉ではなく、詳細なプランがあるんでしょう。そんな顔をするからには」
カイが嫌々といったふうに尋ねると、飛鳥は目を細めた。
「聞いてくれる気になった?」
「聞かないと納得出来ませんよ」
「それじゃ、遠慮なく。有り体に言うと君にまた自殺されると困るのでそうならない世界に送り出してあげたい、ってことだ」
指しっぱなしだったカイの指をひょいととりあげて飛鳥が言う。かと思うとそのままぐいと顔を近づける。この近さになるとますます鏡合わせみたいだったけれど、目の色だけあまり似ていない。クローンのはずなのに、そういえば、おかしな話だ。飛鳥の目はエメラルドグリーンで、カイのそれはエメラルドブルーの色あいをしている。
「因果に引き寄せられたヴァレンタインによると、君の『死にたい』という願いに付き合わされた世界はもう限界なんだって言う。これ以上死なれると、再生する——バックヤードにおいて演算をリスタートするためのリソースが尽きてしまう、というギリギリの状態にある。君が死ねるのは、死んでも世界の存続に問題が起きないのは、あと一回きりだ。それが最後の世界からやってきた彼女の弁。僕はこれを信じた。そうでなければ、逆説的に、ヴァレンタインはこの世界に流れ着いてはこれない」
「ええと……? 世界が、なんですって?」
「でも自殺を繰り返している限り世界は前に進めない。演算は同じ構成要素でしか始まらないから、そのままリスタートさせると自殺以外の結果に繋がらず、結果、リソースを食いつぶして行き詰まる。そこでヴァレンタインの介入が起こったわけだ。彼女の介入によって世界のあらましを理解した僕には、たった一つだけ奥の手を使うことが出来た。リスタートする際に、演算の構成要素を変えてしまうんだ。数式が変われば結果も変動する。カイはもう自殺しなくて済むだろう。その代わり、僕はもうフレデリックのそばにはいられなくなるかもしれないが……」
そこで一度飛鳥が言葉を切る。彼の語った内容を反芻し、カイはその意味を考えた。カイが自殺を繰り返したのは、フレデリックがカイを息子としてしか愛してくれなかったから。そのカイが自殺を選ばずに済み、飛鳥がフレデリックのそばにいなくなるということは、つまり……。
顔を上げて飛鳥の目をまじまじと覗き見る。彼の目は相変わらず、
「だから次の世界では、君は僕と関係ない人間としてフレデリックに出会うよう調整した。彼は僕の面影をカイの中に見ない。僕の息子だからという理由で君に接しない。それは翻って、彼が君に興味を持たないかもしれないという危険性の示唆でもある。でも、カイ。僕の息子として愛されるより、興味さえ持たれない方が、今の君にとっては遙かにましだ。そうだろう?」
ね? なんて気安いふうに同意を求められて、カイは反射的に父親をはね除けた。近くにいた分激しく突き飛ばされて、飛鳥の身体がふらつく。
「し……信じられない……」
いきなり何をするんだ、酷いじゃないか、という父の言葉を遮ってカイはわなわなと身体を震わせた。この親にしてこの子ありだと妙に納得してしまった自分が心底腹立たしかった。
「あなた、わかってるんですか。自分が何をしてしまったのかが」
「概ね理解しているつもりだよ。でもそうしないと世界は今度こそ永遠に終わってしまう」
「そんなのは詭弁です。あなたは世界なんてどうでもいい人種でしょうに!」
「でも世界が終わったら、もうフレデリックを見つけられないし」
「違います。そうじゃない。そうじゃないんだ! だって父さん——私のオリジナル——あなただって、フレデリックを永遠に独り占めしたかったんでしょう!? ディズィーに彼を奪われないために、彼女へ与える供物としての私を作ってまで……!」
震えたままの指先で父の首根っこを掴み取った。まったくこの人は自己矛盾の塊だ。最低の親だ。ずっとフレデリックを独占したかったからカイを造ったはずなのに、そのカイを生かそうとして今度はフレデリックを手放すなどと、どの面下げて、言えるのか。
首を締め上げられている飛鳥は、息子に睨まれていることなんかまったく意に介していない調子でああ、と軽く手を叩く。緊張感がない。まるでカイが一人で空回ってるみたいだ。
「そういうことか。うーん、でもね、彼は僕の息子をこれだけ追い詰めただろう? 五千百八十九兆六百五十二億千九百八十二回も自殺に追いやるとか相当だよ。ならフレデリックだって、一度ぐらいは辛い思いをしてもらわないとな。苦しみに喘ぐフレデリックを見られるならギリギリ、チャラだ」
「へ、変態……こんなのと自分が同じもので出来てると思うと泣きたくなってくる……」
「あはは、褒めない褒めない。それにねカイ、そう悪いことばかりじゃないんだよ、本当に。だって僕がそばにいられないということは、彼が僕を失うということでもあるんだ。アリアを失い、ディズィーを失い、君まで失い拠り所ひとつなくなったフレデリック。それを見られるのなら後悔はない」
笑顔のまま言い切る彼に絶句する。なんて図太い神経。自分が繊細気味な自覚はあったが、ここまでくると太いを通り越して鋼だ。崇敬の念すら芽生える。
「父さん、あなたってひとは……」
「ううん、でも。そうだね——たった一つ悔いがあるとすれば、この選択を取ったことで、もう二度と君の父親にはなれないかもしれないということだ。それはちょっと、さみしい」
「——、」
だからその直後に彼が何の気はなしに呟いた内容に、カイは意表を突かれて、何にも言えなくなってしまった。
カイは息を呑んだ。フードの少年は、ここに来てからずっとカイと鏡合わせのような顔をしていたはずなのに、いつの間にか、毎朝自分に声を掛けてくれていた父親のかたちをしていた。
「とうさん」
その時初めて、カイは目の前にいる男を心の底から愛せたような気がした。一度もパパとは呼んであげられなかったけれど、でも彼だけが、カイにとっての本当の父親であることに間違いはない。フレデリックやベルナルド、クリフ、カイの父親みたいに接してくれた人はたくさんいる。しかし彼らはどこまで行っても「父親代わり」であって、本当の父は、どれだけろくでなしで自己中心的で空気も読めない人の心がわからないエゴイストだったとしても、世界中にたった一人しかない。
「私が望まなくても、あなたが望まなくても。この先私が、何度死んで何度生まれ直しても。私の父親は、あなただけですよ。あなたしかいない」
きっと、いつの世界でも。
それを言うと、父はここにきてやっとびっくりしたような顔をして、無言のままカイを手招きした。カイは大人しくその手に従って父との距離を詰める。
「ありがとう、僕の息子。……いつか、君の望んだものが、手に入りますように」
父はカイを抱きしめ、誰より優しい声で耳元にそう囁いた。身体に伸ばされた手のひらは小さく虚弱だった。ああ、そうだった。この人は頭脳一極集中で荒事も法術一つで何とか出来る規格外の存在だったから、フレデリックと違って身体をろくすっぽ鍛えたことがないのだ。ばかなひと。カイは口に出さずに独りごちる。知っていますよ、あなたが身体を鍛えなかったのは、フレデリックが完成された肉体を持っていたからだ。なんてばかばかしい理由だろう。あなたは望めば、何にだってなれる人だったのに。
ならばこのひとから生まれた自分も、同じくらい、きっとばかなんだろう。
それが今は少しだけ嬉しい。
「父さんも」
カイがそう返すと、父は返事をする代わりにカイをもっと強く抱き寄せた。
五千百八十九兆六百五十二億千九百八十一回の人生の中で、カイの死はいつも冷たく空虚だった。目を開くことのない死体になり、怨嗟の声をあげているうちに、全ての記憶を失ってまた次の人生が始まる。どこまで行ってもその繰り返し。死に方が違えば、死ぬまでの苦しみも異なるが、でも最後に見るものはいつだって変わらない。暗く、冷たい、虚だ。世界の終わりだ。
でも五千百八十九兆六百五十二億千九百八十二回目は、ひどくあたたかなものに抱きしめられてカイは瞼を閉じた。一度くらい、こういう終わりがあってもいい。それならきっといつかは、終わらない場所へ辿り着くこともあるだろう、と信じられるから。
だって父さんが最後に祈ったのだ。
あの誰よりろくでなしのエゴイストが、カイのために、たった一つの奇跡を、願ってくれたのだから。
/プライマル・レッド END