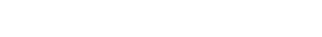07 幽霊の男の子
墓の前に立つと、いつも、こいつは唇を尖らせる。
『もう。またこんなところに来て。はじめのうちこそ、おまえが墓前に花を手向けるなんて殊勝なことだ——とは言ったが、足繁く通えなんて、一度も言ったことはないな。むしろ口を酸っぱくして言い含めている。
無視して花を手向ける。この花を手に入れるのも近頃はなかなか厳しくて、昔は白百合など花屋で買ってきたものだが、最近はそのへんの野草で精一杯だ。
希望のない戦争は加速度的に人類を疲弊させた。もはや花屋など世界じゅうどこを探したって見つからない。花を買うような余裕がある人間がいないのだ。人々は、ただ終わりの日を漠然と待ち、シェルターの中で蹲り命を浪費している。戦えるものの多くは死んでいった。その背を見て新しく立ち上がるものは減り続けている。例の「天使が死んだ日」から元々減少傾向にあった人口グラフの下降はより顕著になった。今生きている人間は減り、新しい命も減り、ギアだけがこの世に増え続ける。
『こんなことをしたって、墓の下の私は、永遠に物言わぬ白骨死体のままだよ、ソル』
自分の名前が彫られた墓石の上に腰掛け、幻影が溜め息を吐いた。あの日己の手のひらから零れ落ちた時と寸分違わぬ姿をして、それは男を悲しげに見つめる。
『永遠にだ。私は死んだ。死者はもう蘇らない。なのにおまえは、まだこうして、私の幻影を飼っている。もう忘れろ、ソル。こんな未練は棄ててしまうべきだ。カイ=キスクは死んだ。十年も前に。驚くべきことに私の遺言を守ったりなんかしたんだ。おまえだってもう、その意味を理解しているはずだろう? 当代聖騎士団団長——ソル=バッドガイ』
唇を尖らせたまま、もう何度目かも分からない提言をする幻影を男は無視した。その肩書きを、彼の姿をした幻の口から言われると酷く惨めな気持ちがしてきて、暗澹たる気持ちになるのだ。
「くそっ……」
悪態を吐き、墓石を掴むとその場に座り込んだ。ローマ会戦の直後、彼の死体を埋めた墓を聖騎士団の敷地内に作らせたのは男だ。戦況が悪化し、地下シェルターと僅かな飛空挺を残してパリの本部敷地を放棄せざるを得なくなった後も、男だけはこの墓へ通い詰めている。ずるずると十年、この墓に縋り、男は生き続けている。
本当は知っている。この墓がある以上、彼はどうしようもなく絶対的に死んでいるのだ。だけど墓に通い詰める男はその事実を認められない。まだどこかで、彼の生を願っている。花を手向ければ、それが積み重なって、天国から彼を引き戻してくれるという妄想を棄てられずにいる。
幻が男を見遣る。悲しみをたたえ、男の首に手を回し、耳元で囁くようにもう何度目かも分からない懇願をする。
『だから——早く私を殺して、ソル』
男は首を横へ振った。その言葉を受け入れれば、ソル=バッドガイがカイ=キスクの死を認めてしまえば、この十年間信じて縋ってきたものが、全て消えてなくなってしまう。
◇◆◇◆◇
聖戦。忌まわしき人類との長きにわたる争い。他を虐げ、この星に蔓延り、大地を汚染し、自然を破壊し、星の命を貪った人間への正当な報い。それが聖戦におけるギアの大義名分。
そう聞かされ、少女は育った。
「お母さん……」
生まれて五歳の少女は、母の顔を一目しか見られなかった。生まれたその日は雪が降っていて、酷く寒く、あたりは血みどろで、少女が記憶している限り最悪の日だった。卵の殻を割ったばかりの少女は目の前で倒れ伏していく巨大なものを見た。それが母親だ、というのは直感的に理解出来た。
『ああ……ディズィー……』
母は少女に向けてそう言った。これが最初で最後の、彼女がくれた唯一の言葉。これだけは、少女にとって絶対に揺るがない本当。例え世界が終わっても、これだけは確信を持って信じられる。ディズィー。私の名前は、ディズィー。お母さんがくれた、私を私として証明する唯一のもの。
『フレデリック……あなたの娘を、どう、か……』
だけどその後の言葉は、少女に向けられたものではなかったから。
『どうか、愛して。私と違って、自由な心を持ってギアに生まれた、あの子を……どうか救って……』
続く言葉の内容を、少女は理解しない。母が語りかけていた男は、母を殺したのだ。あの忌々しい神器で母の心臓を貫き、ギアの司令塔は斃れた。男はそれを確かめると生まれたばかりの子供を見た。まだ卵の殻が付いた小さな少女に、母の返り血でどろどろになっている手を伸ばした。
『テメェが、アリアの娘か』
自我が芽生えたばかりだった少女は、その手を恐れて逃げ出した。母親を殺した血にまみれた手が恐ろしかった。あの男が私の母を殺したのだという思いが幼い心に憎しみを駆り立てた。でも一番怖かったのは、あの男が、ギアを裏切って母を殺し、よりによって聖騎士団なんかの団長をしているあの男が、自分の×××××なのだということを、認めるのが——
怖かったのだ。何より。
だってそれは、裏切り者の血を引いている自分は本当のギアではないということの、証明になってしまう。
ギアの本拠地である巨大プラントの中を少女はぼんやりと歩いていた。戦争は順調だ。最早地上に人が住まう安息の地はなく、その全てをギアが掌握した。小賢しい人類の生き残りは空と地下に身を潜めているが、その数も殆ど残っていない。絶滅寸前だ。世界中あちこちに点在しているせいでひと思いに掃討は出来ていないが、放っておけばいずれ全員死ぬだろう。
唯一目障りなのが空に居を構えあちこちを移動する聖騎士団だったが、これも最早恐れるに足る相手ではない。少女の教育係と補佐官を務めている男はいつもそう言っている。人類の希望であった少年を失い、裏切り者のギアなどを戴くしかないあの組織は今や風前の灯火だと。その証拠に、裏切り者は前線へ出て来ない。彼が騎士団最後の戦力だから、失うことを恐れて出せないのだという。
だから少女は大抵、ギアプラントで留守番をしている。裏切り者が出て来ない雑兵戦に、ギアの姫たる少女の手を患わせることなど出来ない、というのが教育係の言い分だ。
「でも、退屈。ギアメーカーと話をしても、つまらないし。あの人は本当のことなんか言ってくれないし。いつも謎かけみたいな事を言って煙に巻くだけ」
退屈。もう一度そう繰り返して、少女は不意に立ち止まった。
ギアメーカーが所有していたギア製造用のプラントを乗っ取ったのが、少女が生まれてすぐのことだ。この十年の戦いで唯一裏切り者のギアが前線に現れたあのパリでの戦いで、ジャスティスと一緒に配下のギアも多くが失われた。無理矢理女王を殺したことで人類が被った被害はギア側以上のものだったが、こちらに負わせた損失も大したものだ。教育係が、少女が次の司令塔に収まることがなければギア側はあの一戦を境に負けていたかもしれない、と言っていた。
よって戦力を補充するために、ギアプラントを手に入れる必要があった。それまでギアは各地に放置されたプラントやギアを製造し何とか制御しようとした人間達の手によって細々と生み出されていたのだが、もっと大量に早く生み出さねば、人類に負けてしまう。そのためのプラント奪取戦が少女の初陣。そして少女が全力を出せた、最後の戦い。
少女の初陣は華々しく飾られ、その結果、戦果として手に入れたギアメーカーのプラントに軟禁される生活が始まる。このプラントの元々の持ち主だったギアメーカーは牢に繋がれ、自分は我が物顔で闊歩出来るという違いこそあれど、私とあの人は実は大して変わらないのではないか、と少女は思う。
自分がハーフギアだから。半分が人間だから、本当は信用されていないんじゃないかということを、ずっと考えている。
「わたし、ちゃんと、ギアなのに……」
人間なんかいくらでも殺せる。この星に巣くうシロアリの退治なんか、大したことはない。息を吸うのと同じくらい簡単なことだ。踏めば死ぬ。それに、アリが群がった程度で傷付くほど自分はやわじゃない。自分は人間じゃない。ギアだ。だから自分と違うものを殺すことに心を痛めない。
「お母さん、どうして私、半分なの。お母さんから生まれた私は本当のギアのはずじゃないの? ギアメーカーは私を指していつも言うわ。その心が、葛藤が、私が人間である証拠だって。嘘よ。私は人間じゃないの。ギアじゃなきゃ、いけないの……」
頭を抱えて蹲り、少女は誰もいない部屋で一人泣いた。こんな姿、誰にも見せられない。泣いてるところなんか見せたら、ますます人間みたいで、ギアの皆から嫌われてしまうかもしれない。
もう今日は、ベッドで寝よう。服の下にさげているロザリオを握って少女はそう決めた。母親が死んだあの日、卵の殻のそばに落ちていた十字架は少女の秘密の宝物だった。誰のものかは分からない。生まれたらもう目の前にあったからだ。ずっとそこに落ちていたのかもしれないし、もしかしたら、母か、或いは母を殺した男が戦いの最中に落としたのかもしれない。
なんだって構わない。このロザリオだけは、ずっと少女のそばにいてくれた。母みたいに死んだりしないし、教育係みたいに自分をプラントに置いて何処かへ行ったりしない。それにギアメーカーみたいに嫌なことも言わない。私の秘密の宝物。何も言ってはくれないけれど、たった一人のお友達。
「あなたとお話出来たら、私こんなふうに、寂しくて一人で泣いたりしないですむのかしら?」
そんなことがあるわけないか、と少女は自分の言葉に苦笑いをする。でも、全てのギアが司令塔の力で自分の言葉に従うこの世界で、自分と対等な関係を持てる、友達と呼べる存在は……ロザリオしかいないのだ。
◇◆◇◆◇
だから——その晩、夢を見ているみたい、と少女は思った。
『こんばんは、レディ』
声がする。自分以外誰もいないはずの部屋に、明るいソプラノの声が響いている。少女は寝ぼけ眼をこすって声がするほうをきょろきょろと探す。
『ああ、やっと私の声が聞こえましたね。ずっと待っていました。あなたが私を手にしてくれた日から、ずっと、この時を待っていた』
男の子が、開け放たれた窓の枠に腰掛けていた。男の子。人間の男の子。生まれてはじめて見るものだった。プラントにいる人型のギアはみんな大人の姿をしていたし、人間達が身を寄せ合って生きているというシェルターには、行ったことがなかったから。
『あなたと話せて嬉しいですよ、レディ。あなたが生まれてから五年間、ずっとそばにいたのに私達は言葉を交わすことが出来なかった。だからずっと待っていました。あなたが私の声に、耳を傾けてくれるその瞬間を』
「誰……? 人間は、こんなところに、来られないはずなのに。どうして。……あ……」
むくりとベッドから起き上がり、窓際まで近づいてはたと少女は気がついた。間近で見た男の子の身体は透けている。幽霊だ。本で読んだ知識の中から少女はその言葉を引っ張り出した。この子はもう、死んでいるのだ。
『……お気づきの通り、私は死人なので。それに、ここに迎え入れてくれたのはあなたですよ、レディ。私はそのロザリオの中にずっといたんです』
「ロザリオの中に……?」
『はい。それは生前、私の持ち物でしたから』
にこりと微笑み、男の子の幽霊はふわりと窓から飛び降りた。
足下が透けているのに立っているというのもおかしな話だが、少女の目の前に降り立った男の子はどうやら身長が同じくらいのようで、そうしているとぴたりと目線が合ってしまう。その上、彼は少女の顔をまっすぐ、慈愛に満ちた表情で見つめてくるのだ。きらきらして綺麗なその瞳を見ているのがなんだか無性に気恥ずかしくて、少女は顔を赤らめると困ったように俯いた。
「あ、あの。あんまり……見ないでください。そういうの、慣れてないんです」
『あ、す、すみません。そうですよね……レディ、実を言うと、私も年頃の女性と話をするのは、はじめてなので……』
不慣れですみません、と幽霊も俯く。お互いして俯き合い、そのまま、まんじりともしない沈黙が続いた。何もかも初めて続きだった。ディズィーのことを年頃の女の子と評する、同じぐらいの背丈をした男の子。彼は少女を兵器として恐れないし、姫と呼んで、無闇矢鱈に持ち上げたりもしない。この感情は何だろう。少女は胸の内に生まれはじめた何かを手繰り寄せる。本で読んだ言葉の中に、この気持ちの答えは、載っていただろうか?
「……ええ、と。あなたは、人間の幽霊なんですよね」
『はい』
頭の中でいっぱいいっぱい考えたが、答えは見つからない。仕方ないので少女は沈黙を止め、おずおずと幽霊の顔に視線を戻した。
「人間って、集団を作って暮らしてるんですよね。それなのに、その……女の子と喋ったことが、ないんですか。人間でその大きさになるぐらいだと、十五年ぐらいは、生きていたはずじゃ……」
『ああ……それは。私は生前、聖騎士団の一員でしたから。あそこには、少女は愚か女性がまず殆どいないですし、子供もいません。食堂のおばちゃんは、いましたけど。だから初めてなんです。あなたが私の、初めての人です』
「そ、そういう言い方はどうかと思います。……っていうか、今、聖騎士団、って……」
『ええ。あの聖騎士団ですよ。あなたが敵だと信じているものです、レディ』
幽霊はやはり真っ直ぐに少女を見つめたままその言葉を肯定した。
心臓のあたりに手を当て、ぎゅうと握りしめた。なんということだろう。初めて喋った幽霊の男の子、その人が、よりにもよって聖騎士団の人間だったなんて! 聖騎士団は少女にとって、五本の指に入るほど嫌いなものなのだ。教育係のテスタメントがギアになる前にいた組織で、ギアを皆殺しにしようとしている、シロアリの中でも特に凶暴な人間達の集まり。しかもあそこのトップは、ジャスティスを殺した裏切り者。
男の子がその一員だったという事実は、少女に少なくないショックを与えた。そのショックの理由は、ロザリオの中——少女があの日から肌身離さず持っていた「お友達」から出てきた男の子なら、人間の幽霊でも、きっと味方だと思いたかったからなのだということは、すぐに分かった。
「じゃあ、あなたは、私の敵なんですね。このロザリオも……」
『いいえ、レディ。私はあなたの味方です。少なくとも、そうありたいと願っています。レディ、私はそのロザリオと共に常にあなたと一緒にいました。あなたがどんな悩みを持ち、何を求めているのか私は知っている。その手助けがしたいのです』
しかし突き放すように尋ねると幽霊は首を振る。それから彼は肩に掛かっていたケープを脱ぐと、腰にさげていた剣も棄て、武装を解除した。幽霊だからそんなことをしなくたって元々危害なんか加えられっこないのだが、そうすることで敵意はないということを示そうとしているようだった。
「でも、あなたも、私のお母さんを殺そうとしたひとでしょう?」
けれどそれでも聖騎士団という存在が恐ろしくて、少女は拒むように尋ねる。
「聖騎士団は、ギアを殺すための組織。たくさんの同胞を手に掛け、お母さんの首も狙っていた。剣を提げていたあなたが、ひとりも私の仲間を殺していないとは思えない……」
『そうですね。それは否定しません。私はギアを殺していました。けれどジャスティスは——あなたのお母様も、私達人類を根絶やしにしようとしていたんです。でも私達だって死にたくはなかった。そうしたら、相容れぬ者たちは、殺し合わねばならない。相手を殺すことでしか己の存在証明が出来ないのだとしたら』
「ほら、やっぱり。人間はみんなそう。やさしいことを言って、結局、私達を騙そうとしているだけ。……出て行ってください。幽霊とはいえ、人間と口をきいたなんてわかったらテスタメントに何分お説教されるかわからないわ」
ああ、やっぱり。彼の答えに少女は落胆した。今は優しそうな声で語りかけてきているけれど、この男の子も腰の剣でギアを殺した人間なのだ。一瞬でも人間に心を開きかけてしまったことに怯え、少女は駄々をこねるように首を振る。ロザリオは私のお友達じゃなかった。私の敵だった。だったらきっと、何もかも嘘っぱちだ。
例え目の前の男の子が、嘘なんか一つとして吐けないような、きれいな目をしていたとしても。
今まで少女の世界にはなかった、美しい海の色をして真摯に自分を見てきていても。きっと最後には裏切る。お母さんが頼んだはずの男が、お母さんを殺したみたいに。
『いいえ、レディ。それは出来ない相談です。だって私はあなたと話をするために留まっていたのだから』
だというのに、幽霊ははっきりと少女の言葉を否定して尚も少女から目を離す気配がなかった。
『第一、聖騎士団は本当にあなたの敵なのでしょうか? つまりレディ、私が言いたいのは、『我々は殺し合わなくても存在証明が出来るのではないか』、ということなんです。生前私はギアを殺す事を使命にしていました。そしてあなたも、生まれてすぐ母親を奪われて、人を殺すことしか知らずに生きて来た。でもねレディ、攻撃されなければ、対象に恐怖を覚えなければ、人は剣を取らずに歓迎の手を挙げられます。私は死後常々考えていました。ギアは、本当にただの悪なのですか?』
「何を馬鹿なことを。私達を勝手に生み出して、勝手に悪者にして、勝手に攻撃してきたくせに、そんな、自分勝手な——」
『人類に初めて攻撃を行ったのは、ジャスティスでした。二〇七四年のことです。それまで人類はギアを敵と見なしてはいなかった』
「——っ、」
口を噤む。幽霊のエメラルドブルーの瞳は、酷く悲しげに、でもとてもやさしい光をその中に映し込み、少女を見ている。
「でも、それ以前の人間はギアを兵器として、道具として扱っていた……元々私達の存在を認めてなんかいなかった。私は、そう、教わりました」
『ええ、私も、生前はそう教わっていました。けれど……あなたがたが捕らえたあの男、ジャスティスを生み出したギアメーカーはこう言ったんです。『彼女は僕の友人だ。そして共通の友人の恋人でもあり、そんな彼女を道具として扱ったことは一度もない』のだと』
「ギアメーカー? あんな大罪人の言うことを、真に受けろと?」
『そうですね。私も初めはそう思いました。何しろギアメーカーさえいなければ
「そ、それは……」
『それに彼の言うことは、辻褄が合うんです。レディ、私はずっとあなたの存在を不思議に思っています。原初のギア『ジャスティス』には生殖機能がありません。理論上、〝ジャスティスの娘〟なんて存在は、生まれようがないんです』
「な、なにを……! 私は、確かに、母ジャスティスの娘として生まれたんです……!!」
静かに告げた彼の言葉に、両手の平を握りしめて少女は激昂した。
それだけは、触れてはならない琴線だった。ぞっとして立ち尽くしている足が震える。そこまでの言葉は信じてあげられても、それだけは否定しなければならない。だって「ジャスティスの娘」であるという大義名分を失えば、少女には何も残らない。ジャスティスの娘だから、ギア達は付き従ってくれる。ジャスティスの娘だから、母を奪われた復讐として、人を殺していい。ジャスティスの娘だから、半分はヒトで出来ている自分も、ギアでいられる。
だけど。もしそうでなかったとしたら?
少女は己の足下が瓦解していく空想にきつく唇を噛みしめた。もしその全てが、誰かが自分を旗頭として利用するために吹き込んだ嘘だったとしたら。ならば少女は一体——何者なのだ?
『……すみません、レディ。あなたにそんな顔をさせたかったわけじゃないんです』
弱り果てたような声と共に、幽霊が少女の固く握りしめられた拳に己の手を添える。何も触れられないはずの透き通った指先の感触が、でも何故かその時、少女にはわかった。
『けれどあなたはこの事実に向き合わなければいけません。あなたも、不思議に思ったことがあるでしょう。自分がどうして、〝完璧なギア〟じゃないのか。テスタメントのような人型ギアと同じに見えてもどこか違う、生まれながらにギアだった故の不完全さが、今でも怖いのですよね。正統なるギアの女王の後継者、ギアの姫、そう呼ばれながらも、心の何処かで不安を抱いている。自分は本当にジャスティスの娘なのか。誰かが生み出したただのバックアップコピーではなく、本物の子供なのか……』
幽霊の言葉は全て、少女が一度は抱いたことのある恐怖だった。少女はギアの姫と持て囃され、ギアの女王ジャスティスの血を引く者として冠を載せられていたが、それらは全て周りからお仕着せられた役割だった。そのお題目でずっと見ないふりをしていたけれど、でもどうしても、少女は不完全なギアだった。ヒトを素体として生まれ変わったギアとは違い、最初からギアだったくせに、最初から人間でもあったから、どっちつかずで中途半端だった。
ギアを統率する能力があるから、周りのギアはみんな自分は本当にジャスティスの後継者なのだと認めてくれている。だけど少女は聡明だったから、もう気がついていた。はじめにギアを造ったのが人間なのならば、「ギアを統率する」という機能自体、後からいくらでも付け加えることが出来たっておかしくない。ならば本当に自分が仕組まれた存在ではないという証明は、どうしたら出来るのだろう。自分が傀儡ではなく、確かに足をつけた、一人の少女だという証拠は、一体どこに?
『だから、一緒に確かめたいんです。あなたが一体どこからやって来たのか。あなたに母がいるというのなら、父もどこかにいるはずです。そして私の予想が正しければ……その男は、きっと分からないままあなたのことを殺そうとしている。私はそれが嫌だ。家族とは、もっと暖かなものであるべきだ』
「……理想論者ですね。生きていた頃、そう言われませんでしたか」
『ええまあ、しょっちゅう。しかも正義の押し売りだとまで、言われましたね。でも、いけないでしょうか? 誰かの幸せを願うことは、悪いことですか?』
「……わからない。そんなこと、考えたこともなかったから。でも……きっとあなたは、本当に心からそう思ってるんでしょうね。私を助けたいって。だって幽霊はもう死ねないから、生きるために私にへつらう必要はないもの」
そう呟き、少女は伏し目がちに顔を上げる。このひとが生きていたら、たぶん、今触れている指先はあたたかかっただろう。ふとそんなことを考えた。もしかしたら自分は、その温度に涙さえ流したかもしれない。そうとさえ思える。
なのにどうして、触れられないんだろう。少女は幽霊の瞳をじっと見つめた。この手が暖かだったら、私はこの苦しみから自由になれたのかもしれないのに。この手が質量を持っていたら、私は彼に救って貰えたのかもしれないのに。
どうしてだろう。少女は呟く。この手を振り払えない、いいや、振り払いたくない。たとえ聖騎士団の人間でも——この男の子を、信じたい。彼の目を見ていると、そんな気持ちで胸がいっぱいになる。
「私、今、不思議な気持ち。人間にこんな気持ちになるなんて、どうしてだろう。私、あなたのことを信じてみたい」
『そうしていただけると、私もとても嬉しいです』
「……じゃあ、約束してください。絶対に私に嘘を吐いたり、裏切ったりしないって。そうしたら、信じてあげます」
『勿論です。そのロザリオとあなたに誓って』
少女から手を放したかと思うと幽霊は跪き、美しい仕草で手を伸ばす。急な動作にびっくりしたが、すぐに彼が何をしようとしているのか思い当たり、少女はおずおずと自分の手の甲を差し出した。
幽霊がそこにそっと口を付ける。本で読んだ、騎士がお姫様にする誓いの儀式と一緒だ。
『では改めてお名前を訊いても、レディ?』
立ち上がり、幽霊が真剣な面差しでそう尋ねる。手の甲に、ないはずの感触が残っている。少女は心臓に手を当て、ばくばく言う胸の鼓動を悟られないように出来るだけ意地悪く彼へ言い返す。
「人に名を尋ねる時は、まず先に名乗るものじゃないんですか?」
すると幽霊はあっという顔になり、己の失態を恥じるようにかあっと顔を赤くした。それから本当に済まなそうにまなじりを下げ、すみません、と丁寧に断り、頭を下げる。
『私の名前はカイ=キスク。十年前、聖騎士団で大隊長を務めていました。今はただの幽霊です。……あなたは?』
「私……私の名前は、ディズィー。お母さんが、最後に私にくれた言葉」
『とっても素敵な名前ですよ、ディズィー』
男の子が柔らかく微笑んだ。そうやって褒めてもらうのは少女にとって初めての経験のはずなのに、何故かその言葉はとても懐かしく少女の胸に響いた。