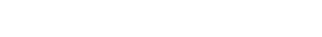08 みにくいアヒルの子
「かわいそうに。きみは親の愛を知らないんだね」
牢に繋がれた男は一瞥さえせず壁に向かってそんなことを呟いた。
かつて
「かわいそうに。ギアのお姫様なんて言われたって、きみは本当は友達一人いない、さみしい子供のままだ……」
そうしてたまに少女の話をしたかと思うと、いつもそうやって、少女が嫌がることばかり口に出して彼女の不興を買い、癇癪を引き起こさせる。
「最低。人間はみんなきらいだけど——おまえは一番だいきらい! 世界で、一番……!」
「きみのお母様を殺した男よりもか? それは光栄だ」
「ッ……この、ろくでなし……!」
思うに彼は、少女に癇癪を起こさせることだけを、人生に残された数少ない楽しみだと思っているのだ。そうに違いなかった。ギアメーカーと呼ばれ、原初のギアジャスティスを生み出し、聖戦を引き起こしたこの世最後の大罪人は、今や自由を拘束され、それだけはよく回る口先で、メビウスの輪みたいに出口も意味もない空言を投げつけるぐらいしか、人生に意味が見出せないのだ。
「かわいそうなのはおまえよ! 私じゃないわ。私は……人間じゃないから……そんな同情なんか、される謂われはないの!」
「ふうん。でもきみ、本当は人間になりたいんだろう? 醜いアヒルの子と同じだ。アヒルの集団の中にいる白鳥は、鳥なのに鳥になれなくて、必死に自分をアヒルだと言い含めている」
侮蔑の笑いさえ見せず、淡々と告げる男に少女は踵を返した。憤りも露わに靴音を立て、廊下を振り返らずに歩いて行く。泣き出しそうな顔を腕で拭い、胸に下げた十字架を掴み取った。言葉はもう声にならない。祈りは、彼女の心の中でだけ、しんしんと降り積もる。
ああ、ロザリオ、私のお友達。
神様なんかいなくたって、
◇◆◇◆◇
『おはようございます、ディズィー。昨晩はよく眠れましたか? なにしろあんな真夜中に目を醒ましていたわけですから……え? ぐっすり? そうですか。それはよかった』
目が醒めて朝になっても、満月の夜に現れた幽霊の男の子は夢みたいに消えてなくなったりせず、ディズィーの傍らにいた。あなたは眠れたの、と聞くと彼は首を横へ振る。彼は、幽霊は眠れないんです、となんだか申し訳なさそうに言うと腰掛けていた少女のベッドからすとんと降り立ち、背をぴっと折り曲げると恭しくエスコートの姿を取った。
『では着替えて朝食を、レディ。ギアはとても燃費のいい生き物ですけれど——例外は、ありますが——それでも栄養の摂取は必要です。健全な精神は健全な肉体に宿り、それには朝の光とバランスの整った朝食が不可欠。朝食のあとは散歩にでも行きましょう。このプラント内での行動は制限されていないんですよね』
「それは……お散歩ぐらい、許されてますけれど。でもいいんですか、幽霊さん。幽霊さんは人間でしょう? ギアの食事なんて、見られたものじゃないかもしれませんよ」
『その点はご安心を。言ったでしょう? 私はあなたが生まれた日からそのロザリオの中にいて、あなたを見守って来たんです。あなたに用意される朝食が大体いつもトーストとサラダ、ポタージュのスープだということは把握しています』
「……プライバシーとか、考慮しないんですか?」
確かに食事はいつもそんな塩梅だけど——思わず厳しい声がディズィーの口を突いて出る。すると彼はたじたじになって、両手の平をぶるぶると振って謝り始めた。
『それは……その。すみません。なにぶんロザリオからあんまり離れられないもので……。……あの……怒りました?』
「ふふ、まさか。怒ってないですよ。幽霊さんは私のお友達だもの。あなたが私を裏切らない限り、私もあなたのことを信じます」
ついさっきまで王子様みたいに手を差し出してきていたはずなのに、ちょっと口を尖らせて言ってみると、途端に声が弱々しくなる。それがおかしくてくすくす笑うと、幽霊はほっとしたように息を吐き、触れない手のひらでディズィーの腕をきゅうと握る。
『ううん。女性の心は、難しいです……』
「エスコートは出来るのに?」
『いつかそういう日が来るかもしれないって、本で読んだことは練習しておいたので。結局そんな日、来なかったんですけどね。生きてる内には』
でも幽霊になってあなたに会えたから、無駄にはなりませんでしたよ。腕から手を離してまた立ち上がる頃にはすっかり素の面立ちになり、そんなことを言う。
「幽霊さんって、変なひと」
『そ……そうですか?』
「はい。でも、良かったな。ロザリオの中にいたのが、あなたみたいな人で。……ええと、私の独り言も、全部聞いていたのなら知っていると思うんですけれど。ロザリオだけが、私にとって唯一心を許せるものなんです。だから出来れば、ロザリオから出てきたあなたのことは、嫌いになりたくないの」
『光栄です、レディ。私が一番危惧していたのは、あなたが私を受け入れてくださらないことでしたから』
「そうなんですか?」
訊ねると彼ははぐらかすように微笑んだ。きれいな顔。つい見とれてしまって、ディズィーはぼんやりとそんなことを思う。
(人間がみんな幽霊さんみたいに、剣を向けるより先に手を差し出してくれたら、私、こんなに人間のことが嫌いにならなかったのかしら……)
でも今更そんなことを考えたって仕方がない。ディズィーが出会った人間はみんな、例外なくディズィーを殺そうとしていた。プラントで皆殺しにしたやつらも、あの日母を殺した男も。
食事の後、庭園へ出た。庭園の世話は、プラントに軟禁されているためやることがあまりないディズィーにとって数少ない娯楽の一つだ。植物のことは嫌いじゃない。彼らは人間みたいにわらわら増えて、誰かを無闇矢鱈に傷つけたりしない。花は手を入れられた分だけ慎ましやかに咲き、身を守るための刺も、不用意に手を伸ばさなければ肌には刺さらない。
「ねえ、幽霊さん。私を裏切らないっていう約束は、本当よね」
薔薇に手を伸ばしていたカイは、振り返ると寂しそうに笑う。
『心配ですか、レディ』
「だって幽霊さん、人間なんだもの。人間って嘘つきなの。約束だってすぐ破るわ」
『それはあなたの経験談ですか?』
「半分はテスタメントからの受け売り。半分は、ギアメーカーが私にした仕打ち。幽霊さん、昨日の口ぶりだと、あの大嘘つきと話をしたことがあるんでしょう? どうして? あんな男と、何を話すことがあったの?」
ベンチに腰掛けてぶらぶらと足を揺らす少女は、ちょっとへそを曲げたように唇を尖らせてカイに問いかける。ギアメーカーと言えば、ディズィーの中で大嫌いな人間リストのトップに君臨している男だ。性悪で、ディズィーをいじめるのが大好きで、いやなやつ。それなのに殺す事が出来ないのは、ギアを生み出した造物主である彼が死に際に何をしでかすかわからないからなのだった。「いいのかい? 私を殺しても。自分の死と引き替えに全てのギアを根絶させる手段を持っているかもしれないのに?」——それが、プラントを占拠されてホールド・アップをしながらギアメーカーが口にした台詞だ。
本当は殺してやったってよかったのだ。あの時ディズィーはまだ生まれて一年と経っていなかったが、ギアの統率は既に完璧にこなしていたし、かっとなった子供の癇癪の勢いで、あんなやつ一ひねりに潰してやれた。だけどテスタメントがそれを諫めた。テスタメントは、幼く判断力の低いディズィーの補佐をするという名目で、ギア軍の全権指揮を実質担っている。
『ギアメーカーと話したこと、ですか? うーん。たいして、面白いことはないですよ。ただ……彼は私に伝えたいことがあったようです。彼の友人たちの話も、興味深かったですし』
「友人……? あんな最低の人にお友達なんていたんですか」
『大昔に、と彼は言っていました。あなたのご両親が、彼にとって数少ない親友だったんだそうです』
カイが指折り数えて答えるとディズィーは信じられない言葉に目を丸くした。
自分の両親、という言葉も耳慣れなくておかしな感じだが、何より、母——ギアの女王ジャスティスが、よりによってギアメーカーなんかの友達をやっていたということをディズィーはあまり信じたくなかった。でも確かにそう言われると、納得出来る部分もある。ジャスティスは最初のギア。ギアメーカーは、初めてギアを造った男。そこに繋がりがあった方が自然ではある。
『ギアメーカーもそのこと自体は、とても幸運なことだと繰り返し言っていました。友人達のことを心から愛していたとも』
「……心から愛していたのに、ギアに改造したんですか」
『愛しているから一番特別なギアにした、というのが彼の言い分です。流石にこれは、私も閉口しました。ソルが手帳の冒頭にこいつだけは殺すと書き添えて彼の名前を記していた意味が、その時私にもわかりましたとも』
カイが苦笑しながら手を振って見せた。
ソル、と名を呼ぶ時、彼の顔は安らぎを見せる。名を呼ぶ相手への信頼が垣間見えるような、そういう優しい表情だ。ディズィーは自分の頬をぺたぺたと両手の平で叩いた。自分は、そういうことをしてみた覚えがない。だってこの城のギアたちを、誰一人、そういう意味では信頼していない。テスタメントのことだって、疎んではいないけれど、友達だとか、親代わりだとか、そういった特別なものとしては見ていなかった。教育係であり、補佐官ではあるが、それ以上でもそれ以下でもない。
だけど、そんな顔をするのだ。カイは——少なくともソルという男のことを、余程信頼しているのだろう。ディズィーがこれほど憎んでいる男の名を、ああまで優しげに呼ぶ以上。
それがなんだか気に入らなくて、意地悪い声でディズィーは頬を膨らませる。
「ギアメーカーにいたぐらいです。幽霊さんにも、生きていた頃にはお友達がいたんでしょうね。私の知らないお友達が」
『え? ええ。レオなんかは、あなたが生まれる前の友人ですから、それはそうですね。ソルも。でも、当たり前ですけれど、死んでからは一度も会っていません。このロザリオがあなたのものになってからは、私はずっとあなたと一緒でしたよ?』
「……でも、その中に、私は入っていないんでしょう?」
飛び出してきた言葉は、ディズィー自身びっくりするぐらい子供っぽかった。
それに困り顔だったカイが合点がいったとばかりに手を叩く。少女が突然機嫌を損ねてしまった理由がはっきりして、彼は胸を撫で下ろす。
『おや。……ふふ、そういうことでしたか』
それからカイは、眼を細めて穏やかに微笑むと、甘く囁くように唇を寄せた。
『勿論あなたは私の大切なひとです。そして特別な相手。五年間、あなたが私のロザリオに向けてくれた親愛を私は全て覚えています。私がこうしてお話出来るのは、あなたのおかげなんですよ。だからそんな顔をしないで』
「……え?」
ディズィーはきょとんとして言葉を失ってしまう。耳障りの良い言葉が次々とディズィーの中に転がり込んでくるのだ。
大切。特別。あなたのおかげ。一度だって言われたことのない言葉たち。ディズィーは今までギアを統率して、人間を殺したことで、そんな言葉を貰ったことはない。だってギアの統率はディズィーに課せられた役割で、人間を殺すのはギアとして当然のことで、当たり前のことが出来たからって、みんなディズィーを褒めてはくれない。
「特別? 私が? ……本当に?」
『嘘は吐かないって誓ったでしょう? 特別なお友達、です。——ね?』
それなのにカイはディズィーに優しいことばかり言う。従僕でもなんでもないのに、どうして? 次はそれを訊ねようとして、ディズィーは彼の正面へ向き直る。
「ねえ、幽霊さん……」
だけどディズィーが言い切るより、彼が唇をディズィーの頬に寄せる方が早かった。
「あ、う、——うそ、」
うまく言葉が回らず、変な声を漏らし、ぱくぱくして唇を震わせる。何も触っていないはずなのに、その時頬に確かに唇の感触が落ちたのだ。ディズィーは急に横に身体をずらし、カイから距離を開けた。男の子が、女の子に、唇を寄せることの名前は、ディズィーだって知っている。キス、だ。確かにそれは、特別な相手にしかしない行為だろうけど。
だけど……だけど、だからって、いくらなんでも。
なんてことをするんだろう、彼は。あまりの事に両手で顔を覆い、ディズィーは頬に残る感触を確かめる。ほんの一瞬口を付けられただけのはずなのに、まだほっぺたがふわふわしている。
だって初めてだったのだ。ディズィーは俯いてふるふると顔を振った。彼が自分にくれるものは初めて尽くしだったが、これはその中でも特大級のものだった。唇じゃなくて、ほっぺたにでも、パパもママもしてくれなかったキスは生まれてはじめてのものだった。
一体、今自分はどんな顔をしているだろう。子供みたいに真っ赤な顔? だとしたら彼には見せられない。
『あの、ディズィー? ……ええと。い、いやでしたか。だったら……その……す、すみません……』
カイがおろおろして右往左往しているのが伝わってくる。自信満々に人の頬にキスしてくるくせに、ディズィーが顔を上げないので大変なことをしてしまったと途端に心配してくるのだ。
(幽霊さんはいいひとね)
そんなことはわかっている。
(たぶんこの人、ほんとに、少しでも私を裏切っちゃ駄目だと思ってるんだ)
大丈夫だ。別にこれは裏切りなんかじゃない。裏切りは冷え渡って固くて悲しい。でもこれはふわふわしてあったかくて嬉しい。でもそれと、顔を上げられるかどうかは、まったく別の問題で。
「いやじゃないです!」
それで思考の覚束ない頭で叫ぶと、声はぐしゃぐしゃになっていて全然大丈夫そうじゃなかった。
『えっ?! そ、それはよかった。いえ、本当に大丈夫ならですが』
「いやじゃ、ないですけど。でもどうして、こんなこと、したんですか。私が知らないだけで……お友達にはみんな、こういうことを、するものなんですか」
顔を覆ったまま上ずった声で問いただす。ディズィーが今までに読んできた本の中では、こういう行為は大抵、恋人同士でするものとして描かれていた。友達同士でしていたことも何回かあったけど、でも昨日会ったばかりの相手にはあり得ない。そういう人達は、たくさんの時間や困難を一緒に乗り越えて、固い絆で結ばれていたりなんかして……
(あ……)
そこではたと思い当たり、ディズィーは顔を手で覆ったままほんの少し顔を上へ向けた。
(でも、そっか。幽霊さんは、生まれた時から私を見てる。私が生まれた時からロザリオをお友達だと思い続けてたみたいに……だったら、わたしたち、昨日会ったばかりなんかじゃないんだ。わたしたち五年間、ずっと一緒にいた……特別なお友達、なんだ……)
それに、ディズィーの方は五年前は生まれたてだったけれどカイは十年前から今と同じ年頃なのだ。理性が発達していて、恋と愛の差を知っていて、特別なものを自分できちんと見つけられる大人だ。
だから、もし——カイが、自分を本当に特別なお友達だと思ってくれているのなら。
今のキスはそういうことの証明だったのかもしれない。
ディズィーはそっと手を広げ、指の隙間からカイの顔色を伺った。あわあわしながら、触れられもしない手を伸ばそうとしては躊躇いがちに引っ込め、どうしよう、なんて困ったように呟いている少年の眼差しには、嘘も偽りも隠し事もない。彼の身体というものは、その四肢から眼窩にはまっている眼球、抜け落ちていく毛髪の一本に至るまで、本当に美しいものだけで作りあげられているようにディズィーには思えた。彼の肢体は虚偽と正反対の清いものだけで紡ぎ上げられている。
きれい。この人の言葉なら、私は信じられる。
生まれた時から一緒にいてくれたから、出会った瞬間から、信じたいと思えた。
『ディズィー、その、ちがうんです。誰にでもするわけじゃ、なくて! 昔……私に生きている意味を教えてくれた人も、私にこうしてくれました。このキスは、あなたが必要で、一緒に生きてほしいなっていう、気持ちの証明なんだって。だから……その……私も……一応、唇は避けて……』
「……必要で、一緒に生きてほしい……」
『はい! ディズィーはずっと悩んでいたでしょう? 自分の居場所がどこにあるのか。自由のないこの城の中で、与えられた役割をこなすことだけが、お母さんに生んで貰った意味なのか、って。私はロザリオの中でずっとそれを見ていたけれど、声さえ聞いて貰えなかったから、今までは祈るだけで何も答えてあげられなかったんです。だけど今なら……今だけは、こうしてあなたに伝えられるから』
おずおずと距離を詰め、隙間を開けたまま顔を覆っていたディズィーの手にカイの手が掛けられた。触れられないものだから強制力なんかこれっぽっちもないはずなのに、それだけでディズィーの手は顔から離れて降りていく。きっとまだ顔は赤い。でもカイは一つも笑ったりなんかせず、心からディズィーを案じて頭を撫でてくれる。
(このキスが、幽霊さんにとって、大切な人にあなたには意味があると伝えるための手段だとしたら)
触れられないだけで、見えないだけで、五年前からずっと、彼はディズィーに意味を教えてくれていたのだ。そうに違いないとディズィーは確信し始めていた。それで全部すっきりする。心の中のもやもやも、カイが自分に優しい言葉だけをくれる理由も。
彼は、生まれた時にお母さんを亡くし、お父さんにも愛してもらえなかった自分を、その瞬間から認めてくれていたのだ。
ギアを統率するための道具としてではなく、一人の女の子として。
あなたの居場所はここにあります、といつも隣で祈ってくれていた。
(だからこのロザリオは、私の宝物になったんだ。いつか私が幽霊さんにこうやって本当のことを教えてもらうために。私が幽霊さんと、ちゃんとお話を出来るように)
感情がすとんと心臓に降りていって、動揺が去り、代わりに喜びが胸をいっぱいに満たした。こんな気持ちをディズィーは知らない。これはもしかして、本の中で見た、「あの」気持ちのことなんだろうか。そうでもいいし、そうでなくてもいい、と思う。
だってその気持ちにどんな名前が付いていたとしても、ディズィーが彼に返したいことは一つしかない。
「ありがとう。私、とっても嬉しい」
名前のないその感情を伝えるため、ディズィーは自分の目の前にある整った顔に不意打ちで唇を近づけ、それを彼の口に重ねた。驚いたカイが声にならない声を漏らす。ああ、かわいい、幽霊さん。表情がくるくる変わって、ちょっぴり子供っぽい。
長く留まらずにすぐ唇を離して——本当に触れられたわけじゃなかったけど——思いがけない出来事に頬を赤く染めるカイをディズィーはじっと見た。それからディズィーは、生まれてはじめて、祈るために手を合わせる。
(あのね、天国のお母さん。私の願いがもしあと一つだけ叶うのなら、私、幽霊さんに恩返しがしたい)
私を認め、私を許し、私に意味をくれた幽霊さん。ほっぺたへのキス一つで、ディズィーがこれまで抱いてきた願い全てを叶えてくれた、魔法使いみたいな男の子。
私、あなたの役に立ちたい。
あなたが私を、許し続けてくれたように。