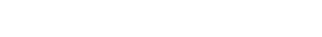09 ファントムドラッグ
「戻ったぞ」
乱暴に団長室のドアを開けると、副官の男が既に席について待っていた。律儀なことだ。彼が手に持っている書類の束を一瞥して息を吐く。
「団長。どこへ行っていた」
「パリだよ」
「……またか」
聞き飽きた溜め息。短い会話。この男と自分との間で会話が弾むことはない。ソルはどさりと椅子に座り込んで渋い顔の男を正面に据えた。
ソルの副官(という名の制御役)を買って出たポチョムキンという奴は、仕事は出来るがつまらない男だ。彼は元々口数が少ない方だったが、先の大戦で敬愛する上官ガブリエルを失い、ツェップという国が瓦解して聖騎士団に統合されてから、ますます無口でおもしろみのない男になった。
五年前に行われたジャスティス討伐戦は、その当時持てる全ての兵力を集結し投入した、歴史上類を見ない巨大な戦となった。聖騎士団を筆頭にツェップ・アメリカ・中華連邦・EU及び世界各国が軍事力を提供し、その筆頭指揮をクリフとガブリエルが執った。しかし結果は痛み分けにもならない惨敗。こちら側は多大な犠牲を払い、両指揮官と引き替えにしてまでジャスティスを討つことに成功したが、ギア側の参謀であるテスタメントを取り逃がしてしまう。更にジャスティスのスペアとして機能する司令塔個体も捕縛に失敗し、ギア側の有利は以前として不動のままだ。
「テメェはしねえのかよ、墓参りは?」
意趣返しのつもりで意地悪く聞いてやると、素っ気ない返事が返ってくる。
「ガブリエル大統領に墓はない。その魂は我々ツェップ国民の心にある」
「……そうだったな」
「団長も、あまり墓など行くな。兵達の士気に関わる」
「行かねえと俺の士気に関わるんだよ」
「……いい加減忘れてやれ。それがせめてもの手向けになると、何故まだわからない」
ポチョムキンは憮然とした口ぶりで吐き捨て、しかしすぐにかぶりを振り、それより仕事の話だ、と言ってソルに書類を差し出した。
それはかねてより検討を重ねている、ギアプラント襲撃計画についての最終計画立案書だった。これまで幾度か、少数の人員を派遣して内々に行ってきたギアプラント——ギア陣営の本拠地捜索にやっと目処がつき始めている。残されたプラントの候補地はもはや北欧エリアをおいて他にない。あとはその詳細を詰めて行くのみだ。
「一番いいのは、奇襲を掛けることなんだがな……」
ソルがぼやくとポチョムキンがはやる考えを制するように首を横へ振る。
「ああ。だがそう簡単に事は運ばないだろう。こちらの部隊が壊滅させられる可能性の方がどう考えても高い。場所を特定した兵が帰還出来れば御の字、と言ったところだ」
「まあ、ギアを生み出す伏魔殿だからな。しかもあそこにはディズィーがいる。よしんばテスタメントの野郎を外に引き剥がしている間に襲撃出来たとしても勝率はそう芳しいもんじゃねえだろうな」
「ではどうする。捜索を止めさせるか」
「これ以外にマシな策があれば元よりやらせてねえ。どっちみち、人類に残された猶予は無いに等しいんだ。プラントを見つけ、総力戦に持ち込み、今度こそ司令塔を全て潰す。……それしか、もう道はない」
立案書にサインと判を押してソルは息を吐いた。ギアの姫として君臨し、今やジャスティスに代わって全世界に殺戮命令を出しているアリアの娘。あの少女のことを思うと、ソルは自分の感情が分からなくなる。
(俺はどうしたらいい、カイ)
そうして歯を食いしばり、常にソルの傍らに侍る幻影にそう問いかけた。
ジャスティスを殺すその瞬間まで、ソルはあれがかつて己が愛した女だと知らなかった。アリアは百年以上も前に、不治の病で死んだとずっと信じていたのだ。それなのに生きていた。あんな姿になって……人間への憎悪をまき散らし……それでも、生きていた。そしてソルに遺言を残して息を引き取った。
(どいつもこいつも、無理難題ばかり押しつけて逝きやがる)
十年前、腕の中で息絶えた少年は「お前になら出来る」と言い残した。お前になら世界を救える。自分の代わりに、この救われない戦争を終わらせられるのだ、と。
五年前に心臓を刺し貫いた女は、「あなたにしか出来ない」と言い残した。生まれたその日に母親を失った娘を愛してやれるのは、あなたしかいない。だからあなたの娘を、どうか愛して欲しいのだ、と。
(馬鹿野郎。向いてねえんだ、俺には。そんなことは……テメェら二人とも、知っていたはずだろうが)
遺された言葉はソルを縛り付ける。雁字搦めにして、出口を塞ぎ、地獄の淵以外見えなくする。ソルにはわからない。あの時、アリアに請われ、生まれたばかりの赤子に手を伸ばした。伸ばした手で、自分は何をしたかったのだろう。あの娘を殺したかったのだろうか。それとも、抱き上げてキスをしてやりたかったのだろうか。
(俺があの娘を抱き上げていれば、世界は救われたのか? それともあの時完璧に殺していれば、戦争は終わっていたのか?)
だが全ては済んだことだ。この問答に意味はない。問いかけた幻も答えない。少年の幻影は、黙って首を横へ振り、ソルの顔に手を掛ける。
『でもおまえはもう、ディズィーを許せないのだろう?』
幻は悲しげにソルを見ていた。血を分けた娘でさえ最早愛せない、かわいそうなソル。でもね、そうしたら、本当にかわいそうなのは、一体誰だったのかな。蠢く唇がソルの皮膚に肉薄し、彼にしか聞こえない謎かけをする。
(わからねえよ)
ソルは瞼を閉じた。分からない。もう何も。十年前、カイを失ったあの日から、ソルの目には光が射し込まない。
(だがあいつは人間を殺しすぎた。無垢で無知だという言い訳も通用しないほどに。例え俺が許しても……世界が決してディズィーを許さない。俺が庇い立てしても、その俺ごと、人間は正義の名の下にディズィーを殺す。……どこの馬の骨とも知れぬ輩に殺されるなら、いっそ俺が殺してやったほうが、まだマシなんじゃないのか)
幻の相貌を思い切り睨め付けてやると、彼は問題児を宥めるように肩をすくめる。
『それはおまえのエゴだよ、ソル』
そうして、十年前からぴたりと時を止めてしまったカイの幻影は平坦な声で答えた。
『でもきっとおまえはそうするだろう。十年の間、欠かさず墓に花を手向けたおまえには、最早個人のエゴイズムしか残されていないからな。私を忘れられないのも、ディズィーを殺すのも、全ておまえの選んだ答えなんだよ。私がおまえに望んだわけじゃない。ジャスティスが、おまえに望んだわけじゃない。私達の遺言に勝手に縛られているだけだ。勝手に……身勝手に、傷口を引っかき回して、膿を溜め込んでいる』
触れられもしない指先がソルの鼻筋をなぞる。そのまま指は首筋にまで辿り着き、喉元の一点を指し示す。
(それでも俺は忘れたくない)
『私が忘れて欲しくても?』
(出来ない。忘却は死の肯定だ。俺の手が届かないところでテメェが死んだなんてことを、俺は認められない……)
『ああ、やっぱり。結局おまえはそういう男だよ』
ソルの喉をつついていた指先が幻影の喉を指し示した。その場所には傷痕がある。カイが生まれた時から持っていたのだという消えない傷。十字架を焼きごてにしてつけたみたいな聖痕。彼という少年が救われないことの証のような。
『私は殺して欲しかったって、あんなに言ったのに』
幻が嗤う。口が耳まで裂け、指先が喉に食い込み、血が噴き出す。
それでもカイ=キスクは死ねない。ソルが全てを認めるまで、幻は彼のエゴに蘇生され、生かされ続ける。
◇◆◇◆◇
不意に視線を感じて、テスタメントは後ろを振り返った。
ディズィーを置いて前線へ出向いて三日が経つ。その間に行ったのは、ただただ、人を殺すことだけ。人間を殺すのは、全てのギアに課された宿命だ。それは素体が狼であろうと人間であろうと変わりのない不文律。
かつて戦場で聖騎士として戦い、ギアに殺され、瀕死の重傷を負ったテスタメントはA国にギアへ改造されることで生き長らえた。否——生まれ変わったと言ったほうが正しいのか。女王ジャスティスの指令を受け取り、テスタメントはギアとして起動してまず最初に自分を改造した研究員達を皆殺しにした。個体の意識を獲得した時には、床中に死体が散らばっていた。
「……気のせいか?」
テスタメントは首を振る。疲れが溜まっているのか、城に置いてきたディズィーが言いつけを破っていないのかどうかが気に掛かって、注意力が散漫になっているのか。それとも、今殺した人間の中に、サングラスを掛けた金髪の男がいたからだろうか。兵器として生まれ変わり、殺人行為に快楽を感じるようになったテスタメントは、殺した人間の顔をいちいち覚えていない。でも、一人だけ、忘れられない男がいる。五年前、生まれたばかりのディズィーを拾い上げ、遁走するテスタメントの前に立ちふさがった男。そいつの姿だけは、いつまでも記憶にこびりついている。
テスタメントは物思いに耽り、目を閉じた。
『おっと、この先は通せないな。アンタの父親にそう頼まれたんでね』
飄々とした態度でコインを弾いた男の肩には、年老いた老人が背負われていた。父親? テスタメントは首を傾げ、獲物を手に取る。父親など——ギアに、そんなものが——
『……覚えちゃいないか。クリフ=アンダーソン、悪いが、約束を果たせなかったとしても許してくれ。こいつぁ……ちっとばかり、シビアな戦いになりそうだ……』
老人を地面に置くと、黒コートの男は抜刀してテスタメントに襲い掛かった。それから先のことは、何故か記憶が混濁してうまく思い出せない。はっきりしているのは、テスタメントは男を殺したのだということ。それから男が、テスタメントに何か長い言葉を掛けていたはずだ、ということ。
『お前さん、……があるのなら、せめてその嬢ちゃんを人間らしく育ててやることだな』
それから、男が最後に、囁いた言葉だけ。
息絶えた男の遺言を、テスタメントは守り続けた。ディズィーには人間の服を与え、人間の食事を与え、人間の言葉を与えた。どうして守ろうと思ったのかよく理解出来ないまま、テスタメントは死人との約束を遵守している。今も。
ギアの本能はテスタメントに常に命じ続ける。人間の心など、機械には不要だ。そんなものをディズィーに与えるべきではなかった。ディズィーのことは完璧な機械として育てるべきだった。彼女を苦しめたくないのならば尚のこと。
しかしそれを上回る何かが、テスタメントに語りかけている。人を殺している瞬間はそのことを忘れられても、常について回る得体の知れない感情が、テスタメントに人の真似事を強いるのだ。
「あの……老人が、一体私にとって何だと言うんだ」
テスタメントは独りごちた。答えるものはどこにもいない。率いてきた彼以外のギアは余計な思考を持たないし、人間は全部殺し尽くした。奇妙な倦怠感を引きずり、テスタメントは早く仕事を終わらせてディズィーの元へ戻らなければと己を叱咤する。
ディズィーをあまり一人にするわけにはいかない。自分がいない間にギアメーカーに何かを吹き込まれていたら困るし——それに何より、〝心配〟なのだ。彼女のことが。
◇◆◇◆◇
「え、テスタメントのことですか? さあ。あの人のことは、私もよくわかりません」
ベッドの背にもたれて本を読んでいたディズィーは首を傾げてカイに答えた。そういえば彼はいつ帰って来るんでしょう、と聞かれた流れでカイが訊ねたのだ。ディズィーを育てたギア、彼は、どういう存在なのですか、と。
だけどわからないものには答えようがない。そう言って本を閉じると、カイは呆気にとられたような顔をしてディズィーをまじまじと見た。
『わ……わからないんですか? だって五年間あなたを育てた人でしょう』
「それを言うなら、五年間私と一緒にいた幽霊さんも同じぐらいはテスタメントと一緒にいたはずじゃないですか」
『いえレディ、私も四六時中あなたを見張っていたわけではありませんからね。こう……空気を読んで席を外している時はあります。ギアメーカーとあなたが話している時も、半分ぐらいはロザリオの中にいましたよ』
「あれ、そうなんですか。……じゃあ、ギアメーカーが私に言ったことも全部は知らないんだ」
『ええ。……何か嫌なことでも?』
「ううん。ただ、一回だけ、私にも奇跡が起こせるって言われたことがあるんです。嘘か本当かは、知りませんけど」
本をベッドの上に置き、カイの方を向いてちょこんとたたずまいを直す。それから顎に手を当ててテスタメントという男のことにディズィーは考えを馳せた。
人型ギアが希少な存在であるこのプラントの中で、ディズィーの成育の全権を預かっていたのがテスタメントだった。いきさつはよくわからない。生まれた日のことのように鮮烈な出来事が彼との間にあったわけではないから、ぼんやりとしか思い出せない。ただ確かなのは、彼はいつもディズィーを城の中に置いておこうとしていることだった。だからなんとなく、彼には信用されていないのではないかという気がしていて、それもディズィーの孤独を深める原因になっている。
「でもどうして、そんなことを訊くんですか? いつ帰ってくるのか気になるのはわかりますけど」
『ええ、まあ……ちょっと、不自然に思うことがあったんですよね。確か、ギアメーカーを牢に繋ぐように指示したのは彼なんでしょう?』
「はい。私はあんな最低の人、殺してしまえばいいとずっと思ってるんですけど」
『……レディ、確かにあの男はまあ……アレですけど、そういうことを言うものではありません。うーん、それにしても……元が人間だから、名残なのかな。単なる……』
カイはどうやら本気で考え込んでいるらしい。でもどんなに考えても、やっぱり、テスタメントというギアのことは、ディズィーにはよくわからなかった。
確かに、言われてみれば、彼はどこか変わった存在ではあった。基本的にギアはディズィーの命令を聞いて動く生き物だ。だから自由意思というものが彼らには存在しない。与えられた役割だけを三百六十五日遵守し続けている。でもテスタメントは自分で考えるし、自分で動く。テスタメントにディズィーが与えている命令は人を殺せというものだけだが、それにしたって、ジャスティスがずっと送っていたものを固定しているのにすぎない。あまりにも当たり前のことすぎて考えたことがなかったけれど、変と言えば変だ。
『なんだか、彼って人間っぽいんです。いえ、元が人間ですから、そういうものなのかもしれないですけど。素体の影響を引きずっているのかなあ……ソルは司令塔の指揮下になかったから、比べようがないし……』
「……またあの男の話ですか?」
『あ、す、すみません。そうですね。ソルの話は、もっと改まってからにしましょう。でも、テスタメントについてはいずれ奥の手を使わないといけないかもしれないな』
「……奥の手?」
『独り言です、お気になさらず、レディ』
ぱんと両手の平を合わせて、カイがこの話はおしまいです、と宣言する。どうも腑に落ちないところが残っていたが、カイがてこでも話してくれなさそうな強情な顔をしているので、ディズィーはこれ以上問いただすことを諦めた。どうせテスタメントはあとしばらくの間帰ってこないのだ。帰ってこない人のことを考えていても、仕方がない。