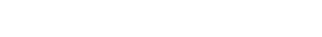10 孤独なお姫さま
「お姫様は元気? 彼女を絆す策は、順調かい?」
格子窓から漏れる僅かな星明かりに照らされ、暗闇から浮かび上がった男はカイに手招きをした。時刻は午前零時を回り、丑三つ時にほど近い。ディズィーはもう寝付いた。ロザリオに紐づけられた幽霊であるカイは基本的に彼女が持つ本体たる十字架から離れられないという制約を持つが、持ち主であるディズィーが眠りに就いている間はその限りではない。その僅かな時間を利用して、ギアメーカーが幽閉されている地下牢へやって来たのである。
『絆すなんて言い方、しないでいただけますか? 私は彼女にソルと会っていただきたいんです。私的な目的は確かにありますが、ソルと和解してほしいという気持ちも本物です』
「やれやれ、潔癖症だな。それで、調子は? うまくいっているのかな」
『……。ええ、きっと。私が心から彼女を信頼すれば、彼女も心を開いてくれます。ギアメーカー、あなたは五年間も彼女と対話をしてきたのに、どうして彼女の心を閉ざすばかりだったんです。あなたがもう少しましな態度を取っていれば、ディズィーだってあんなに人間不信を拗らせなかったでしょうに』
「そうかな。あの子は
両手を拘束されているのにも関わらず、牢の中央にどこからともなく椅子を呼び出して着席を促す。無詠唱で出てくる幽霊さえ座れる椅子について、ギアメーカーは「バックヤードから『そこにあるものには座れる』という状態情報を引っ張ってきてるだけだよ」と述べていたが、法術にそれなりに長けていた自信のあるカイでもこの理屈はよく分からない。近代に魔法使いが生き残っているとすればそれはこの男を置いて他にいるまい。
「どこまで話したかな。君と、世界の因果の話だったか」
『ええ。私が死ぬことによって、加速度的にこの世界は歪み始めた、というくだりです』
「ああ、そうそう。君の死が世界のループを決定づけていた、という話だ。世界の終焉は〝カイ〟という識別個体によりもたらされ続けていた。正確には他にもいくつかループ起点になる適合条件があるんだけど——実際に起点として機能したのはカイだけだ。それを、今回僕が完成形としてのヴァレンタインを過去のループに放り込むことで強制的に終了させた。その結果、君はこの世界で幽霊になってしまった。……このあたりだったな」
灯り一つない地下牢で饒舌に喋り、ギアメーカーは一人で頷いて見せた。カイの理解が追いついているかどうかを気に掛けている様子はない。でもそれは今に始まったことじゃなくて、これまで顔を付き合わせてきた何回も、ずっとそうだった。
それでもカイが彼の話に耳を傾けるために夜毎ここへやって来るのは、最初に彼が見せた顔に、言葉に、嘘偽りが見られなかったから。
彼に……ディズィーがソルへ抱くものに似た戸惑いを、覚えたからだ。
『回りくどい話でしたけれど、結局のところ、あなたは何が言いたいんです?』
ちょっと眉をしかめて「早くしろ」と急かすふうに言うと、ギアメーカーがのんびり答える。
「世界が正しく終了するには、君が死んでいる必要がある、ってことさ。こちらで目覚めてから僕なりに色々調べたんだけど……五千兆を超える試算で同じ条件付けを使ってしまったから、どうもそれだけは絶対必須条件になってしまったらしくてね」
『はあ……よくわかりませんが、じゃあ、いいんじゃないですか? 私はもう死んでいるから、こうして幽霊なんてやっているわけで』
「ところがそうもいかない。この場合の『死』とは即ち、世界の根幹——バックヤードからの情報承認処理のことだ。それが正しく行われていれば幽霊なんてものにさえなれない。ソーマは悉く回収され、バックヤードの中に収められる。君はまだ正確には死ねていないんだよ、カイ。フレデリックが、未だ君の死を許していないと以前言ったね。だから世界は救われない。だから世界は終わらない。……だが、因果律の許容値に限界が来ている。このままいけば、君が死ねないまま世界は強制的にループさせられるだろう。カーネルが消失した状態で強制再起動されるんだ。次の世界はもうまともに動けない」
ギアメーカーは極めて冷静に淡々とその事柄を述べ立てた。
この世界はバックヤードの上で繰り返されるループ式のプログラム。その中で、世界の終わりはカイの死によって定義されている。しかし例外処理として「ヴァレンタイン」なる存在を過去ループに挟み込んだ結果、計算式にズレが生じた。そのためこの世界では、カイの肉体は死んだが、魂が死んだという処理が行われない。だからいつまで経っても、次のループに辿り着かない。これがギアメーカーの言い分。
荒唐無稽な話だ。カイとて、この男が幽霊になったカイにさえ物理法則を無視して干渉してくるような規格外の存在でなければ、一笑に付していたところだろう。しかしそこまで自在にこの世の法則を操れる男が相手となると、ここまで手の込んだ作り話をする理由が今度はなくなってしまう。
『……言いたいことは?』
息を呑んで、かぶりを振った。それに何より、ソルが自分の死を認められていないという言葉だけは、どうしても無碍には出来ずにいた。
「うん、話が早い。流石だ。ここで話は、最初に戻るということだな。時間がない。人間に与えられた時間も、君に掛けられた可視の魔法も、残り僅かだ。来る人類とギアの最終戦争までにお姫様の説得を終わらせる必要がある。お姫様には、ギア軍の大将と聖騎士団の団長として、親子の再会をしてもらわなければいけない」
『……それは……でも……戦争の場でソルに引き合わせたら、聖騎士団の長である以上、彼は絶対にディズィーを殺します! もっと、他の場で……』
「いや、そんな猶予はもうない。君がフレデリックと再会するにはディズィーをギア側の大将として外へ出すしかない。そもそもフレデリックぐらいの脅威に対する切り札としてしか、テスタメントは彼女をこの城の外へ出さないだろう。それはもう分かっているんだろう?」
『……だ、だけど』
口ごもるカイに、ギアメーカーが肩を落とす。まだまだ子供だな、と言われているようだった。だけどうまく言い返せる言葉が見つからない。カイが一人許したところで、認めたところで、世界はディズィーを許さない。それはもう揺るぎのない事実なのだ。
でも、それでも。
ディズィーにそんな終わりを選ばせることを、カイはしたくない。
たとえそれが最適解でも。ギアメーカーが、お前は甘ったるいと言いたげに、カイを見てきていたとしても。
「それに彼女は人間を殺しすぎた。どっちみち、死ぬ時は顔も名前も知らないような人間達に汚辱の限りを尽くされるだろう。それだけの恨みを買っている。なら、終わり方ぐらい、彼女の手で選ばせてやった方が——」
『……やめろ!』
だから、とうとうぶつけられた冷徹な現実に、カイは無様に叫んだ。
分かっている。この世界の殆ど全ての人間がディズィーを殺したいと心の底から願っている。プラント奪取をした時、彼女が蟻でも見るような顔をして人間を殺した現場もカイは見た。彼女は花を愛でる少女だったが、そうである以上に、あまりにも兵器のコントローラーとして完璧すぎた。彼女の指示で死んでいった人間の数は、生前のカイが人殺しの顔をして殺し尽くしたギア達の数百倍に上る。
『そんなことを、私に言えというのですか?!』
「いいや、それは違うよ、カイ」
それでもいやいやとかぶりを振ることしか出来なくて、子供のように惨めに喚くと、ギアメーカーはいやに優しい声で、もっと恐ろしい事をカイに告げるのだ。
「彼女はきっと自らそれを選ぶ。君のためにね。ディズィーは〝いつも〟そうだった。君の願いのために、人知れず己を犠牲にしてしまうところが、実によくアリアに似ていたよ。だから……その覚悟はしておきなさい、ということだ」
ギアメーカーの宣告はおぞましいほど冷徹だった。
窓の外の雲が動き、月明かりがギアメーカーの顔を照らし出す。格子窓に切り分けられた夜空は残酷なほど美しい。照らし出された不健康な相貌がカイを捉えて離さない。カイは呻いた。この縁もゆかりもないはずの男は、いつも誰より優しい顔をして、何より惨いことをカイに囁く。
それが彼が交わした最後の約束に応えることなのだと言いながら。
◇◆◇◆◇
テスタメントがもうじき帰ってくるらしい、ということを聞きつけ、カイが大聖堂へディズィーを誘ったのは、ギアメーカーがカイに囁きごとをしてからそう日が経たないうちのことだった。
現在ギア陣営の本拠地となっているこのプラントはスウェーデンの首都にあり、かつて人が暮らしていた頃はストックホルム宮殿と呼ばれていたらしい。ギア製造プラントに魔改造されたあともその名残みたいなものは建物のあちこちに見て取れ、ここを根城にする知能あるギアは、その枠組みの中で人の真似事みたいな生活をしている。
大聖堂に入り込むことはほぼ禁止されているに等しいのだが、教育係のテスタメントがまだ不在であるのをいいことに宮殿エリアから抜け出し、大聖堂へ忍び込む。この聖堂は不思議な場所で、人の手から放棄されて長いこと経つのに、あまり寂れた様子はない。ギアに信心深い者などいるはずもないのに、蜘蛛の巣一つ張っていないのだ。
こんな場所には縁がないのでディズィーは滅多に来ないのだが、ロザリオの幽霊ことカイの熱心な頼みとなると断る理由もない。
「こんなところに来て、一体何になるんですか?」
案内はしたもののカイがこんな場所に来たがる理由がよくわからず、訊ねると、彼は短く『お祈りのためですよ』と言った。
『生前は、日曜日に礼拝堂で祈りを捧げるのが習慣になっていたんです。死んでからもう十年ぐらい出来ていないので、せめて一度は、と』
「テスタメントが、神様なんかどこにもいないから礼拝堂に行くのは無駄だって言ってました。ギアのみんなも、ここには寄りつきません」
『……そうですね。神様は確かに、どこにもいないのかもしれません。けれど祈りは無駄になりませんよ。それは我々自身の心への誓約だからです。だから私も大事の前には礼拝を行います。……お祈りすると、いいことがあるんですよ?』
含みのある言葉を投げかけると、彼は微笑み、手を合わせる。
しんと静まりかえった大聖堂。その中央で跪き、巨大なパイプオルガンの方へ手を合わせる幽霊。変な組み合わせ。だけど不思議といやな気持ちはしない。それどころか、一緒に手を合わせようかな、という気さえしてくる。
いつもざわざわして落ち着かない心が、そうしていると、凪いで穏やかになっていく。灯り一つない聖堂の中には、窓硝子を通して差し込んでくる柔らかな陽射しだけが満ちていた。今まで一度も目を向けなかったものが、新しい世界みたいな顔をして、ディズィーの前に顔を現す。
(きれい……絵本で見た、天使みたい)
祈りを捧げる少年の姿に、思わずそんな言葉を思い描いた。
もし彼の背から羽根さえ生えていたら、ディズィーは「みたい」ではなく「やっぱり」と思っただろう。でも彼の背に羽根はない。だって彼は天使なんかじゃない。普通の、神様に裏切られて死んだ男の子なのだ。
彼みたいな信心深い男の子が、『確かに神様はどこにもいないのかもしれませんね』なんて言うのだから、やっぱりカイも神様に裏切られたに違いないとディズィーは勝手に思い込んでいた。私と同じね、幽霊さん。あなたと私は、よく似ている。
(この羽根、私なんかじゃなくて幽霊さんに付いてたらよかったのに)
己の背に付いている一対のギアを後ろ手に撫でてディズィーは立ち尽くしていた。ギアとしての破壊衝動と本能を閉じ込めた羽根の形の兵器、ネクロとウンディーネ。自分のギアの力は、どうしてこんな形をしているのだろう。他のギア達は、自分の身体の中にギアの力の全てを宿している。なのにディズィーだけが人間としての肉体には余計な部分にそれを飼っている。
ギア達は、それはあなたが特別な存在だからだと言ったけれど。
母ジャスティスは、別にそうじゃなかった。
だからこの分離した羽根も、己が中途半端であることの証明みたいで、そのことを考えると、いつも複雑な気持ちになってしまう。
『……お待たせしました。やっと私も、覚悟が決められそうです。では、すみませんがそこに腰掛けていただけませんか』
しばらくすると、お祈りを終えたカイが立ち上がり、ディズィーの方へ振り返った。
「あ……はい。そこの、長椅子の隅でいいですか」
『助かります、レディ。それから、これからする話は、出来るだけ小さな声でね』
人差し指を立てて唇に添え、カイが密やかに告げる。ディズィーは小さく頷いた。内緒話と秘密の約束。今までの人生の中になかったもの。幽霊の男の子がディズィーにくれるのは、初めてのものばかり。だからきっと今度も、きらきらした初めてをくれるのだろう。ディズィーはそう信じて疑っていない。
「それで、何のお話をするんですか?」
次は一体、どんなきらきらしたものをくれるんだろう? ディズィーが期待に胸を膨らませて問うと、カイは夢にも思っていなかったような答えを一つ、ぽんと返して寄越す。
『私が聞きたいのは——あなたの、お父さんのことです』
その、まるで研ぎ澄まされたナイフみたいな言葉に、ディズィーは全ての感情を一瞬取りこぼした。
それまで胸の中にあったふわふわした温かい感情が、ぱちんと弾けて急速に萎んでいく。やめて。呟いたはずの声は、言葉にならず、ひくついた音として喉から絞り出される。やめてよ。嫌なの。あの男だけは、嫌! どうしてそんなひどいことを聞くの。あなたは私のお友達なのに。嫌いになりたく、ないのに……。
不快感と嫌悪が代わりに渦を巻き、ディズィーを苛んだ。こういう時、相手がギアだったら、司令塔の力で口を塞いでしまえる。でもカイはギアじゃない。人間だからディズィーの命令は聞いてくれない。命令を聞かないからお友達になれたのに、その矛盾が今度はディズィーを傷つける。
『すみません、レディ。私達には時間がないんです。……けれど、私には幽霊の身になった今も一つだけ望みがあるんです。あの男に……ソルに、あなたと共にもう一度だけ会いに行くこと。それだけが、私に残された未練。唯一の願い……』
ディズィーはいやいやをしながらごくりと生唾を呑み込んだ。喉がからからに渇き、唇がひっつく。
幽霊になったカイはロザリオからあまり離れられない。だからカイがソルに会うためには、ロザリオの持ち主であるディズィーも彼の前に行かなければだめだ。そのためにはディズィーに頼むしかない。それに彼は、家族とは暖かなものであるべきだと言っていた。きっと、親子がいがみ合うことも嫌っている。ディズィーがうんと言いさえすれば、それらが一気に解決出来る。素晴らしいことだ。
でも……ディズィーは頭を抱えたままカイの目を見た。写真でしか見たことのない澄んだ海みたいな瞳は、いたって真剣で、決して、ディズィーをいたずらに傷つけようとしている様子ではない。そんなことは……分かっている。
(どうして……)
ディズィーは首をぶるぶると振り、でもやっぱりカイから目を離し続けることが出来なくて、今にも泣き出しそうな困り顔で彼の目を見据えた。
痛い。痛いよ。でもどんなに〝心が〟痛くたって、この男の子に、彼だけには、嘘を吐きたくない。
◇◆◇◆◇
ギアのお姫様にはパパがいない。ギアの女王から生まれた子供がハーフ・ギアになるんだから、父親がどういう存在なのかはみんな分かりきっている。だからギア達の中でお姫様のパパのことはずっと禁句。お姫様もママを恋しがってもパパのことは口に出さない。どっちつかずのお姫様は、ギアに道具として拾われたから、必死に人間を否定していないと居場所がなくなってしまう。
居場所がなくなることが、お姫様には一番怖いのだ。どこにもいられなくなることが、胸が張り裂けるほど恐ろしい。自分を認めてくれる人が一人もいない世界なんて、生きていられない。ママもいない。パパも自分を愛してくれなかった。だったら自分の中の「人間」なんて、殺してしまわなきゃ。そうしてお姫様は人間を殺してギアになろうとする。幽霊の男の子が現れるまで、そうすることだけが、彼女のよすがだった。
そういうわけだから、ギアには女王と姫がいるけれど、でも決して、王はいない。王様は、この世界のどこにもいてはいけないのだ。
「アリアには『ユノの天秤』。フレデリックには『背徳の炎』。二人とも、特別なギアに相応しい種を持っている。だからもし君のパパが人間を憎んでいたら、この城には王様もいたのかもしれないね」
そんな中、ギアメーカーだけが、禁を破って言い含めるみたいに彼女の父に触れ続けた。目を逸らすな、どんなに見ないふりをしたところで、お前は人間であることから逃れられないんだぞ、と言うみたいに。
だけどそんなことを言われなくたって、ディズィーは最初からちゃんと分かっている。だって殺しても殺しても、自分の人間性は消えてなくならない。友達が欲しいと思うことも、母親が恋しくて起こす癇癪も、みんなみんな、人の心がなければ抱かない願い。そもそも、ギアじゃないといけないと言い聞かせるのだって、「自分は人間だ」と理解しているからなのだ。ギアの仲間達に同胞意識を寄せきれないのは、自分が半端物で彼らとは違うものだと知っているから。
自分がアヒルになれないことなんか、生まれた時から気がついていて。
卵の殻を突き破り、顔を見た瞬間から、あの男が自分の父親だとはっきり分かっている。
ギアを棄てて人に与する裏切り者。聖騎士団第五代目団長ソル=バッドガイ、だけどあの男だけが、世界で唯一、ディズィーを娘として迎えてくれたかもしれなかったのに。
「あの男に、会え、って言うんですか」
ディズィーは震える声で確かめた。カイは無慈悲に頷く。ディズィーが父親を嫌っていると、カイが知らないはずがない。それでも、連れて行って欲しいのだろう。
カイの願いは出来れば叶えてあげたい。
だけどそれ以上に、あの男だけは、嫌なのだ。
「嫌……それだけは、嫌。怖いの。あの男が、また、生まれた時みたいに……私を認めてくれないかもしれないのが、怖い。ねえ幽霊さん、あの時も、ロザリオの中から、私を見ていたんでしょう? だったらどうしてそんな恐ろしいこと、聞いたりなんかするの。私の気持ちも知ってるはずなのに……」
『すみません。確かに私は、ロザリオの中からあの瞬間を目撃していました。幽霊として目覚めた直後、一番最初に目にしたものが、その場面です。……でも、今、あなたの口から私に向けてそれを言っていただくことにこそ意味がある。あなたはやはり、ソルが……怖いんですね』
「怖いに決まってる。私は娘として愛されたことがないの。あまつさえ、生まれたばかりの私を殺そうとまでした。だったら、父親に向ける感情なんて、そうなるしかない……!」
静かに、なんて言われたことを忘れて感情的に叫ぶ。カイはディズィーのその様子に、静かに首を振った。
『……そうですね。でも、私は、そんな感情でさえも、親に対して抱けるものがあるだけで羨ましいんです』
「……えっ?」
洪水のように喉元へせり上がってきていた言葉がそこでぴたりと止まった。
羨ましい? 彼の言う意味が、よくわからなかった。どうして。父親は生まれたばかりの子供を殺そうとし、生き延びた娘は父親をいたずらに恐れている。それなのに、うらやましい、だなんて。
『私には、親がいないんです。父も母も、誰一人。だから、私は悲しい。あなた方は生きているのに、そうやってお互いを拒んでいる』
だからディズィーは、続く言葉に、今度こそ全ての声を失ってしまった。
『ねえディズィー、そもそもどうして私達は……子供は、生まれてくるんでしょう。私だってもうそれほど純粋じゃないですから、全ての子供は親が愛し合ったから生まれるのだなんて、言えやしませんけれど。でも理由なく生まれてくる子供はいません。私が見たこともない両親は、それなりの過程を踏んで、私をこの世に生み出したのでしょう。それはあなたも同じです。ジャスティスは、あなたを生み落とした。途中で堕胎させたり殺そうとしたりはせず。然るにソルとの——
彼の理想論を煮詰めたみたいな口ぶりを思い出す。『その男が、何も本当のことをわからないままあなたを殺そうとしているのが、私は嫌だ』。なんておかしなことを言うんだろうとしか、その時は思わなかったけれど。
ディズィーもソルも、お互いの本当のことなんか、ちっとも知らない。だけどカイはソルを知っている。ディズィーも知っている。二人をよく理解しているから、より深くすれ違いを悲しんでいるのかもしれない。
『私が知っているあの男は、理由もなく赤子を殺すような人間じゃありませんよ。あの時だって、五年ぶりに見て、ずいぶん、人が変わってしまったようには見えたけれど……その一線を超えるようには思えなかった。そもそも彼は本当にあなたを殺そうとしたんですか? もしかしたら、ただ、手を差し伸べただけなのでは?』
振り絞るような彼の言葉に、やはり声など出せないまま、ディズィーはカイの辛そうな顔をじっと見た。
生まれた時に見た血まみれの手を、ディズィーはよく覚えている。でもその時男がどんな顔をしていたかは、忘れようと努めていたから、思い出したくもなかったから、考えないようにしていた。だけど……今その記憶を手繰り寄せ、ディズィーは呆然とする。確かにあの時、彼の顔の中には、少女に対する憎しみのようなものはなかった。
なら、あの男は、ディズィーを殺そうとしたわけじゃなかったのだろうか。
母と同じように自分を始末するものだと思い込んでいたけれど、本当は、ディズィーを受け入れ、認め、愛する準備が、彼の中にあったかもしれないのだろうか?
「あ……ああ……」
『ディズィー? どうしましたか?』
「ああ……う、うう……で……でも……でも……! それでも、あの男は、母さんを裏切ったのよ……!」
混迷を極める思考の中、ようやく絞り出した声と共に目頭が熱くなった。カイの透き通った指先が心配そうにディズィーに伸ばされる。けれどディズィーはその手を直視したくなくて俯く。感情がぐるぐるに丸まって、一所に集約し、爆発してしまいそうな心地になる。
「私……わからないの。あの男が私を本当はどう思ってたかなんて、知らないわ! はっきりしてるのは、お母さんを殺したのはあいつだってことだけ。どうしてあの男はお母さんを裏切ったの? どうしてお母さんを殺したの。どうしてギアなのに、人間の味方をするの! それにお母さんは、死ぬ直前にあの男にお願いをしたのに……あいつは何一つ守りやしなかったじゃない……」
『……。それはひどく難しく、デリケートな問題です、ディズィー。私は一年と少し、彼と一緒に暮らしていました。私が知っているあの男は、ディズィーが思っているより、ずっとましな生き物です。少なくともジャスティスの言葉を歯牙にも掛けなかったわけではないでしょう』
「だったらどうして……!」
『では逆に訊ねます。果たしてギアの旗頭となり女王に代わって人間を殺してやることが、本当にジャスティスがソルへ求めたことだったんでしょうか? そもそもあの男は人間に肩入れしているというのは置いておくとしても、ディズィー、私が記憶しているジャスティス最後の願いは、殺戮の要請なんかではありませんでしたよ』
よく思い出してみて。カイは生真面目な声でそう問いかける。あなたのお母さんの、最後の言葉を。
ディズィーはままならない思考のまま、求められるままに頷いた。ずっと目を背けていた言葉だったけれど、記憶は蓋をされていただけで錆び付いてはおらず、まるで昨日のことみたいに鮮明な映像になって脳裏に蘇る。
——フレデリック、あなたの娘を、どうか。
——どうか、愛して。私と違って、自由な心を持ってギアに生まれた……
——あの子を、どうか救って。
「お母さんは……私を、救って、って。だけど……どうしてそんなことを……」
『ああ……そうか。それじゃやっぱり、そういうことなのかな』
ディズィーの呟きにカイが頷いた。どうも彼には思い至るところがあるらしい。
「幽霊さん、分かるんですか。お母さんが言いたかったことが」
『ええ。推測ですけれど。ディズィー、ギアはね、不自由なんです。大元が兵器として造られたものですから、司令塔の指示に従い、司令塔の意思で動くようにプログラムされています。心当たりはあるでしょう? あなたがジャスティスの代わりを務め、人を殺せという命令を出し続けている限り、全てのギアは人を殺そうという心しか持てません。ギアになる前にどんな思想を持っていたとしても関係なく。テスタメントなんて、いい例でしょう。彼は元は聖騎士だったのに、今や人間を殺すことにしか意味を見いださなくなってしまったんだから』
「それが……どうしたんです」
『だから、そういうことなんです。もし……ジャスティスでさえ、本当の心を押し潰すような破壊衝動に突き動かされ、人を殺していたのだとしたら。死の瞬間に自我を取り戻した彼女は、そういったギアの宿命から、あなたを解放したかったというふうに考えられるんじゃないでしょうか?』
違いますか。カイが訊ねる。ディズィーはそれに「違う」と返すことが出来なかった。彼の言葉は理論立てられていて筋が通っていたが、そんなことよりも、ディズィーの中のもやもやとわだかまっていた感情がそれでやっと腑に落ちて、あるべきところに収まったような気がしたからだ。
全てのギアがジャスティスの怒りと憎しみに従っていた中、ソル=バッドガイだけは、彼女の意思に逆らった。その仕組みはわからないけれど……確かなのは、彼はギアでありながら自由を得ていたということだ。あの男は自らの意思で人に味方し、ジャスティスの破壊を決めていた。自分の気持ちで、自分の道を選んだのだ。
でもディズィーはそうじゃない。周りに言われるがままにジャスティスの後継を努め、破壊を指示している。ディズィーのやってきたことで、自分で選んだことなんか、今までに殆どない。着るものも食べるものも、何をしたいかでさえ、全部他人に押しつけられたものばかり。
唯一自分で選んだものがあるとすれば、それはあの時落ちていたロザリオを拾って逃げたことだけだ。
「お母さんは、私に何を望んでいたの?」
カイは静かに口を開いた。
『恐らくは、ギアと人の殺し合いとは無縁の人生を。でも、残されたギア達にとっては、それでは不都合だったんでしょうね。あなたという代替品があればそれで人間への復讐は続けられる。もう途中で止まることが出来ないぐらい、人間もギアを殺していましたし、ギアも人を殺していました。この戦争を終わらせる手段は、五年前のあの時、既にどこにも存在していなかったんです。戦争が終わったから新しい時代がやって来ると信じられるほど、人にも、ギアにも、最早希望は残されていなかった』
「じゃあ……私、どうしたらいいの?」
『それは、これからあなたが決めることです。自分の未来は、自分で選ばなきゃ。プログラムではなく心で動くことが出来るのなら、あなたにはそれが出来るはずだ』
答えを求めた少女に、ロザリオの幽霊は首を振った。その言葉はまるで、「だってあなたは人間なんだから」と諭しているようにも少女には思えて。
それがふと恐ろしくなり、少女は触れられない少年の腕を掴む。
「ねえ、幽霊さん」
『はい』
「ギアメーカーは、私のことを人間だってずっと言っています。幽霊さんも、私は、自分で自分の心を決められると信じているんですよね」
『……はい』
「だったら……もし、私が本当に人間なのだとしたら。私が今までやってきたことは、人間が、人間を殺したってことに、なるんですか」
『……それは、』
「私は、人殺しなんですか?」
少女は思い当たった可能性に怯えきり、震える声でそう訊ねた。
縋るような目がカイを見る。ロジックエラーを起こした心はぎしぎしと軋み、救いを求め、否定の言葉を欲しがっている。
少女は今まで、自分はギアだから人間とは別種の存在なのだという免罪符を使って、罪悪感に蓋をして人間を殺してきた。だけど少女がプログラムされた兵器でないのなら、それは全部嘘になる。自分で自分に嘘を吐いて殺戮をしていただけの、単なる人殺しになってしまう。
その様子にカイはあっと息を吐く。
ギアメーカーも言っていたではないか。「それに彼女は人間を殺しすぎた。どっちみち、死ぬ時は顔も名前も知らないような人間達に汚辱の限りを尽くされるだろう。それだけの恨みを買っている」。彼女はギアになろうとして、人の心を完全に棄てようとして、人が抱えるにはあまりにも多すぎる命を奪ったのだ。だけど殺しても殺しても完璧なギアにはなれない。その結果、ただ自分は命を殺めてしまったのだと、今更になって、気付かされたのだとしたら。
自覚なく犯した罪は、急激な重さを持って少女を襲うだろう。その痛みはカイにとって推し量るに容易かった。カイも歯車のように集団に填め込まれてギアを殺していた。ギアにも心があるかもしれないなんてことは死ぬまで知らなかった。死んで、ジャスティスの死に幽霊として立ち会い、その時ようやく、ソルの額にある紋様を見てそれに気がついたのだ。
『……ええ、残念ながら。あなたが人を殺した事実は、もう、変えられないんです、レディ』
カイはまなじりを下げ、しかしはっきりとした声音で彼女の問いを肯定した。残酷だが、それに嘘を吐くことは彼女のためにならない。
「じゃ、じゃあ……」
『でも、その先を選ぶことは出来ます』
その代わり、精一杯、労るように彼女の手を握りしめた。そこには肉がない。何の温度も伝わらない。だけどそれでも、その行為に意味があると信じたい。
かつてあの男が、カイの手を握りしめてくれたように。
馬鹿だな坊やはと、彼が笑い飛ばしてくれたみたいに。
自分の生き方は自分で選べる、と知って欲しい。
『私もギア殺しでした。その意味ではあなたと何一つ変わらない、殺人鬼ですよ。殺したギアの数は、もう、覚えていません。私はまだ十とそこらの子供でしたが、その時既に、自分のことをギアを殺すための機械だとさえ考えていたんです。……でも』
俯いた少女の顎に手を添え、顔を上げるように促す。視界の中に浮かび上がるサルビアの瞳は、カイの知っている男のそれとはあまり似ていない。
『ソルは……あなたのお父さんは、それでも私を、ただの子供として見てくれた。だから私は今もまだここにいます。あなたに言葉を伝えることが出来ます。私はあの男と出会えてよかった。あなたに出会えてよかった。だから……あなたにも、最後は、ソルに出会えて良かった、と思って欲しい』
きっと彼女は父親ではなく母親に似たのだ。それでよかった、とカイは思う。もし二人が同じ目をしていたら、動揺してしまって、こんなふうに彼女に言葉を掛けてあげられなかったかもしれない。
『昔話をすることをお許しください、レディ。少し長くなりますが、私の知っているソル=バッドガイという男のことを、あなたにお話ししましょう』
耳元で囁くと少女は頷いた。彼女の隣に座り込み、一呼吸をすると、カイは長い昔話をするため、喪われた十年前の日々に想いを馳せた。