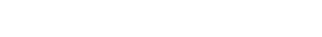11 星の王子さま
「神様が——いらっしゃることと、既にこの世を去られていることは、相反する事柄のようでいて、実は共存可能な事項なのではないか、というのが私の持論です。神がこの地上に生きているのなら、百年続く聖戦を見過ごされはしないでしょう。この戦争は人々を疲弊させすぎた。最早終末戦争の如き様相を呈し始めています。それなのに奇跡が我々を救わないのは、この世のどこにも神が生きておられないからなんじゃないか、って」
十字架を胸に掲げて祈る少年がいた。この地獄のような世界の中、積み上がった骸に向けて、彼はいつも丁寧に祈りを捧げる。死した者に黙し、己が手に掛けた敵へ礼をする。これは少年が辿り着いた一種の儀式なのだ、と男が理解するのにそう長い時間は掛からなかった。共に戦場へ赴くようになって、三回も経つ頃にはその意味を正確に把握していた。しかしそれでも、彼という少年が「そういうかたち」に出来上がってしまったことは、男が考え得る限り五指に入る不幸な出来事であり共感出来ない考え方だった。
「はあ……信心深いこったな。そこまで辿り着いて、なお、その十字架を棄てないか、坊や。ならもう神なんかどこにもいないと言い始めたっていいだろうに」
「まさか。神様は、いますよ。つまるところ神というのは私達の信仰が形作る偶像だからです。私達が信じる限り神は存在します。でも祈るだけでは世界は救われない。祈るだけで救われるのだったら、人は神に頼り、もう二度と己の足で立ち上がることはないでしょう。ですから、神様は死ななくちゃいけなかったんです。人が、踏みしめた足で明日を目指すために」
「仰ることはご立派だよ、本当にな」
ソル=バッドガイは溜め息を吐き、半ば吐き捨てるようにそう言った。首から下がる彼の十字架は、いくら磨き込んでも消えなかった手汗や血が染み込んで、鈍い光を放っている。あの中に彼が看取った全ての死がある、と理解した時、ソルは得体の知れない悪寒に襲われて吐き気をさえ催した。彼は一面的な正義の体現者であり、それ故騎士団員たちからまるで神の子の如く崇められていたが、ソルからしてみれば、多くの声なき身勝手な妄執から神の代理人を押しつけられた、被害者そのものだった。
「テメェは、かわいそうだとは思わねえのかよ」
「かわいそう? 何が」
「……いや、いい。わからねえんなら、その方がいっそ幸せなのかもな」
無意味な問答を切り上げ、こちらへ付いてこいと手を振る。出会ってまだ三ヶ月にも満たないが、それでもわかることはある。この子供は何も知らない。己が兵器であることしか、教えられて来なかった。そして偶像兵器であること以上を多くの人間は彼に望まない。あのクリフ=アンダーソンでさえ、聖騎士団の長である以上、ここまで彼の自我を確立させて守ることで精一杯で、その先へは行けなかった。
いや或いは、かつて人間らしい人間として育ててしまった養子がああいう末路を迎えてしまったからこそ、あえて自分が人間性を与えすぎないように抑制しているのかもしれない。
「帰るぞ、坊や。その血まみれの身体をどうにかしろ。テメェはもうちっと自分を顧みろよ。返り血なんか本当は浴びない方がいい。傷口から入り込めば、不衛生がたたって感染症を呼び起こすこともある。それにだ……何より、俺が気にくわねえんだよ。坊やがんな格好で平然としてやがるのがな」
ならその役割も託すために、きっとソルを呼んだのだろう。神の愛を説くくせに人の愛を知らない少年に、新しい価値観を教えることが出来るなら、と。
「はあ、まったく、注文が多い人ですね。わかりましたよ。帰ってシャワーを浴びます。でも、別に、私が血まみれでいるのが嫌だっていうあなたの意向を汲んだわけじゃないですから。そこは勘違いしないでください」
十字架を降ろしてソルの方へ向き直り、少年が小さく舌を出す。この三ヶ月の間だけでも、彼は少しずつ、人間らしい表情を見せるようになってきた。こういう反抗的な態度など、その最たるものだ。
豪語する限りでは、彼はソルのことがあまり好きではないのだという。傲岸不遜で規律破りの常習犯、人と足並みを揃えるということを全くしないうえに彼よりうんと強いソル=バッドガイという男は、彼が与えられたルールに則った世界の中ではまず現れてはいけないような異端児だった。言うなれば巨大なバグの塊だ。
システムの守護者たるアドミニストレータにバグを愛せよというのもどだい無茶な話だろう。だからソルは彼に愛されようとは思わない。そんな傲慢なことは言わない。クリフはそういう期待を持っているようだったが、彼の父親代わりになりたいなどとも思っていない。ソルのような人間が、この期に及んで人並みに人の親の顔をするなど、滑稽以外の何者でもない。
自分から彼に与えるものはたった一つでいい。
ただ、カイ=キスクという存在を、どこにでもいる十五歳の男の子として守りたいというこの願いだけ、許されるならば秘めていたい。
◇◆◇◆◇
聞いた話では、四十五年前に死んだというクリフの養子も、それは敬虔に神を信じていたのだという。
「ねえソル、もし私があなたを残して先に行くことがあったら、私の事は、別に悼まないでくださいね」
いつも死に急ぐようにギアを殺す少年は、その日ふと思い出したようにそんなことを言った。よく晴れた日のことだった。嘘みたいに晴れ上がった空には雲一つなく、まるで子供が無作為にペンキをぶちまけたみたいなピュアリー・ブルーが広がっている。平和という平和を日々享受していた、大学生時代の夏休みのようだ。なのにほんのちょっと顔を下へ向けるだけでその様は一変してしまう。
ソルはごきごきと音を立てて首を鳴らした。こんな子供がそばにいるからだろうか、聖騎士団に入ってから、自分が若い頃のことを思い出して憂鬱になることが、増えたような気がする。
この日はソールズベリーで発生したギアの集団を片付け終え、その後始末に入っていた。カイが先行し、ソルがそれを追い、一帯を殲滅する。一応それなりの部隊を連れてきてはいたが、現れたギアは殆ど二人で殺しきってしまっていた。はじめはカイのことを焦って追いかけない部隊員達のことが不思議で仕方なかったが、この現場を見せられてしまうと、巻き添えになりようがない分、彼らの判断は正しいと思わざるを得ない。
「出会って殆ど間のない相手に、何言い出してんだ、テメェは」
「え? ああ、気に障ったのならすみません。でも私は、大体全ての団員に同じ事を言っているので、気を悪くしないでもらえると嬉しいな」
厳しい口調で彼の言葉を受けると、少年はまるでおかしなことを言った自覚がないみたいにふわふわと返事を寄越す。全ての団員に同じ事を——遺言をしているだ? ソルには彼の言葉が理解出来なかった。そんな、余命半年の人間が恋人に耳打ちするような言葉を、会う人間会う人間に言って回っているというのか、こいつは。
『ねえフレデリック。私が死んでも、そのことで気に病まないでね。私に縛られて、ずっと後ろを向かれるなんて嫌だな。私はフレデリックの笑ってる顔が好きなの。あなた、滅多なことじゃ、笑わないけど。だからかな……一番、あなたの笑顔が好きなの』
脳裏にいつか告げられたアリアの台詞が蘇る。あの時と、まったく同じような焦燥感がソルの中に渦巻き始めている。けれど明確に違うのは、アリアは決して、ソル以外の人間に、そんな馬鹿げた遺言を残さなかった、ということだった。
「あんまり、深く考えてもらわなくて結構なんですが……要するに、私はこの組織の中では珍しい子供ですが、だからと言って死んだあとにそれを気に病んだり特別扱いしないでくださいね、という以上の意味はないですよ。戦っていればいつか人は死ぬものです。聖騎士団の中だけでも、人死には毎月出ている。いつかその葬列の中に私も加わるというだけのことで」
「そりゃ、確かに力のないやつから死んでいくのは仕方のないことだ。だが坊や、テメェはその全てをいちいち悼んでソイツに祈ってるじゃねえか。そのくせ他人には、悼むなと言うのか」
「ええ。だって彼らの死は、私の力不足のせいでもありますから。それに……彼らは、生きるために生まれてきたでしょう。でも私は、そうじゃないんです。目が醒めた時からずっと騎士団にいた私は、この戦争を終わらせるために生まれました。だから死ぬのは怖くありません。私は、いつか死ぬために、今生きてるんです」
「……っ、この、馬鹿野郎が!」
機械が定められたフレーズをでろでろと吐き出しているようなその言いぐさに、ソルはかっとなって彼の頬をひっぱたいた。
思わぬ張り手を喰らったカイは流石に面食らったようで、何が起きたのかを正確に理解出来ないまま目を白黒させて死骸の上に尻餅をつく。どうして? 今まで一度も、ぶたれたことなんかなかったのに。私の何が落ち度だったのですか? 眼差しは雄弁にそのようなことを語り、しかしソルを非難する色はその中にない。
多分彼は、今ひっぱたかれたことが理不尽だと分かっていないのだ。
「死ぬために生きてる、だ!? 阿呆が。テメェには確かに両親がいねえな。ソイツは、初日に聞いた。だから……何があっても生きろ、とは、誰も言ってくれなかったのかもしれねえ。だがな。死ぬために生まれる奴なんざ、この世のどこにもいねえんだよ。生まれた以上、誰も彼も必死になって生きようとする。生きたいと願う。生命とは、そういうものだ。そうじゃなきゃ……機械となにも変わりない。テメェが今ブチ殺した、ジャスティスに支配されている兵器と同じだ」
「じゃあ、そうなんじゃ、ないですか? だって団の皆さんが私に期待している役割は、それと同じでしょう。ジャスティスが下位のギアに人間の殺戮を望んでいるように、私が人類に望まれているのだって……」
「——っ、の、クソガキ……!」
カイはやはり淡々と反論をする。ソルは力の限りに右腕を振り上げた。衝動が彼の身体を支配していた。何度ぶん殴っても、今自分を衝き動かしているこの感情の、名前は分からないんじゃないかと思った。
一体どんな生き方をすれば、こんな考え方をするように育つのだろう? それには子供だとか大人だとかは関係なくて、ただ、人間としての欠如だけが見え隠れしている。誰もこの子供に愛情を伝えなかったのか。いや、そんなことはないはずだ。団員達は多少歪でもカイのことを愛していたし——クリフやベルナルドは、出来る限り、彼の父であろうとしているようにソルにも思えていた。
その愛が、正しくカイに伝わらないのだとしたら。
父としての愛では、彼には足りないのかもしれない。
一度はたかれた後だからなのか、ソルの右腕を警戒してカイが身構える。だけど殴らないでとは言わない。ひょっとすると、痛みがないのかもしれない。ギアに突っ込んで行く彼のやり方は、とてもじゃないが、正常に痛みを感じられる人間が取るやり方ではなかった。
それに……カイが泣いている姿も、三ヶ月も経つのに、祈りの時間でさえ見たことがない。
だから。
「テメェが機械だなんて、誰にも言わせるかよ。坊や自身にだって、これ以上言わせてたまるか」
ソルはカイを抱きしめた。抱き上げて、腕の中に抱えた。
「え。そ……ソル……?」
腕の中から、これまで聞いた中で一番に狼狽した声が聞こえてくる。それに続いて、「降ろして」というか細い声が耳に入った。だけど構うものか。ソルは逆に、抱きしめる腕に力を込める。
「人間だろ、テメェは。人間だ。機械じゃない。テメェのことが、好きな奴はごまんといる。テメェが死ねば奴らは皆心が痛む。そいつらに死を悼むなと言って回るのは、拷問だ、はっきり言って。それともまさか坊や、自分は誰にも愛されてないから悲しまれない……なんてことを言うつもりか?」
「それは……だって……確かに、クリフ様とか、ベルナルド、レオは……大事な人ですけど……でも私が期待されているのは……」
「大事な人間には、生きて欲しいもんだ。どんな手を使ってでも、生き延びて欲しいと願う。俺だって坊やに死なれたくはない」
「……。ソルも?」
恐る恐る名前を呼ぶ声は、初めて見た愛に触れる者特有の透明さを孕んでいた。
「ソルも……私が死ぬのは、悲しいんですか……?」
顔を上げてソルを見つめる少年の顔は、世俗に触れて見たこともないものに囲まれ、揺れ動いている天使のそれに似ている。人の心を知らなかったものが、人になっていく過程を見ているようだ。カイはゆっくりとソルに手を伸ばした。ソルの頬に触れた指先は、今にも折れてしまいそうなほど華奢で頼りない。
「ああ」
短く肯定すると、カイは小さく息を呑む。
「ほんとに?」
「こんなことで嘘なんざ吐かねえ」
「……本当に?」
「疑い深いな。なら、証拠が必要か?」
それでも、カイは何度も訊ねてくる。そうか。人の心が分からないなら、それにうまく触れられず自分の中で構築が出来ていなかったのなら、わかりやすい表現をしてやらないと、彼には伝わらないのだ。今こうして抱き上げ、生きろ、と言われて初めてカイは自分に生きて欲しいという願いが向けられていることを知ったのだ。
なら愛情も、よりわかりやすく注いでやらないといけないだろう。
「要は……こういうことだよ、坊や」
抱き抱えた顔をぐいと引き寄せ、ソルはカイの柔らかな唇を啄んだ。
途端にあたりに素っ頓狂な声が響き渡った。息絶えたばかりのギアの死骸が転がるその中心で、カイ=キスクは、初めてのキスを経験する。
◇◆◇◆◇
『私に生きる意味を教えてくれたのは、ソルでした。ずっと自分のことを機械と同じだと思っていた私に、彼は死ぬな、と言ってくれた。初めてのことでした。すごく……嬉しかった』
彼との出会いから、短い日々の中で起きた交流までをかいつまんで話した。ディズィーはそれに真剣に聞き入り、冒険物語でも聞いているみたいに興味津々の顔を見せる。カイの話の中に出てくる男は、ディズィーがあの日見て、その後聞き及んでいるような、血も涙もない悪の親玉ではない。一人の血の通った存在だった。誰かのことをちゃんと思いやって、誰かのことを愛せる人間として語られていた。
『私も今でこそこうしてあなたと話せるぐらいには人間らしくなりましたけれど、その頃は思い返すだに酷い有様で。そんな私にソルは根気よく付き合ってくれましたし、たくさんのことを教えてくれました。いいことも悪いことも。夜遊びは、誘われてもしませんでしたけれどね』
「よ……夜遊び? テスタメントがそれは一番やっちゃいけないことだって言ってましたよ」
『私も悪しき慣習だと思いますよ、レディ。彼は規則破りの常習犯でしたからね。決まり事というものに対してあんなにルーズな人間は見たことがありません。実際そういうところには今も嫌悪感があります。彼に多くを与えられ、私にないものを持っているのだと自覚した後は、彼に対してコンプレックスを抱いてもいました。……でも、尊敬してるんです。世界で一番。だから……最後は、そういう意味で、私のことを悼んで欲しくはなかったな。でも……私は多分、選択を誤ったんです』
そこで一度カイが言葉を切る。悲しげにまなじりを伏せ、まるで懺悔でもする時のように、辛そうに声を振り絞る。
『私は死ぬ間際、彼に遺言を残しました。彼の腕の中で。聖騎士団の団長になって、私の代わりに、聖戦を終わらせて欲しいと。彼にならそれが出来ると思っていましたし、そうすることで、私の事を忘れてくれるんじゃないかなって、思っていたんです。……私の事は、思い出にして欲しかった。彼はあまり、人と深く関わろうとするタイプではなかったから。そうしてもらえると、甘えていました』
「……でも、忘れて貰えなかったんですね?」
『ええ、恐らくはね』
ディズィーが訊ねるとカイは頷いた。
『ソルが人と深く関わらないようにしていたのは、そもそも一度、あなたのお母さんを失っていたからなんです。あなたのお母さんは……不治の病で、ギアにならなければ死んでしまうはずだった。ギアメーカーは私にそう言いました。そういった過去があるから彼は大切なものをこれ以上作らないようにしていたと。なのにソルは、私を愛してくれました。私を大切だと言ってくれました。そんな彼が、二度目の喪失を経験して、あまつさえ遺言を果たせる立場にいたら。……私を忘れてなんて願い、叶えられるはずがない』
そのロザリオを戦場へ持ち込んだのはソルです、そうカイが呟く。あの男が五年間肌身離さず持っていた私の墓標です。それがあなたの手に渡ったのは、宿命だったのかもしれませんね、と。
ディズィーは彼の言葉を反芻し、首を傾げた。カイの死がソル=バッドガイという男に影響を与えたという話とは別に、自分の認識と食い違う発言がその中にあったからだ。
「お母さんは……最初からギアだったわけじゃないんですか?」
その問いにもカイは頷いた。
『そうみたいです。そもそもギアは、大元の生物を改造して生まれるものでしょう? だからあなた方も戦力の補強にギアへ改造するためのプラントを必要とした。生まれた時からギアだったのは、きっと一人だけ』
「一人……お母さんから生まれた、私……」
『はい。出会った夜に、ジャスティスには生殖機能が備わっていないはずだった、と私は言いましたね。あれは、あなたがジャスティスの娘ではないという意味ではなくて……人間だった頃の子供なのではないか、ということなんです。ジャスティスに改造される前に、授かったものなのではないかって。だってソルは百年以上ギアの敵側に立ち、ギアを殺して生きて来たんですよ。だけどジャスティスはソルのことをあなたの父親だと断定したんです。だとしたら、敵対する前に出来た子だと考えるのが自然だ。……だからディズィー、あなたは、望まれず生まれた子供ではない。私は……そう思う。ソルにも、あなたを愛する用意が、本当はあったはずだ』
カイが静かに言った。
その言葉に、ディズィーはどうしてだか、目尻が熱くなっていくのを感じた。
ずっと自分ははみ出しもので、本当は誰からも認められていないのではないかと思っていた。そんな少女にとって、「あなたは望まれて生まれたのだ」という言葉は、呪いのいばらを解く魔法のキスと同じぐらいてきめんの効果があったのだ。それに、ずっと話の通じない裏切り者で、だから自分が受け入れられる余地はないと信じていた父親らしき人も、もし本当にカイが話すような人間であるのならば……ひょっとして、自分を認めてくれるのではないだろうか? そんな風に思える。
こんな自分でも、親に、愛してもらえるのだろうか?
「幽霊さん。……本当に、彼がそうだったとして。〝お父さん〟は……私を、許してくれるんでしょうか」
『少なくとも私の知っている男は、誰かを叱っても、最後には許せる人間ですよ』
「だったら、」
『……でも、この十年で、少なからず事情が変わってしまった可能性があります』
ディズィーの希望に満ちた問いかけを、しかし冷静にカイは遮る。ディズィーに本当の意味で選んで欲しいからこそ、この先を隠すわけにはいかない。
『ギアは、ソルの大切なものを二度までも奪いました。ディズィー、人とギアは争いすぎたんです。あなたがこれまでに人間を殺している以上、ソルも人間の代表として、手放しであなたを許せはしないでしょう。問答無用で殺しに来るかもしれない。それだけのことを、あなたは指示しています。今も』
「そんな……」
『それに、彼の周りには多くの聖騎士団員がいます。だからまず彼と一対一で話せる環境を作る必要があるのですが……あなたはギア側の総大将です。いわば人類最後の希望である彼を、これが人類側最後の総力戦というところでもない限り、そう軽々と出しては来ないでしょう。それについてどう交渉していくかは、おいおい考えるしか……』
カイが黙り込む。ギアメーカーの忠告通り、穏便に事を進められるだけの猶予など無いに等しい。しかしそれでも、強攻策を取った結果ただソルが彼女を殺してしまっては元も子もない。
カイだってなるべく早くロザリオと共に彼の元へ連れて行って貰いたいのだ。一刻も早く彼に『殺してもらわなければ』、カイにも、世界にも未来がない。だけどディズィーを騙して見殺しにするようなことはしたくなかった。五年間彼女を見守って来たカイは、彼女に十分以上に感情移入していた。
彼女は、ソルに人間にして貰う前の自分と同じだ。
ならば、自分がソルにそうして貰ったように、彼女に伝えたいものがカイにもある。
『すみません、ディズィー。口ばかりで、動かす身体もなくて……』
「ううん、大丈夫です。幽霊さんに身体がないのは、しょうがないし。お話してもらわなかったら、私、あの人がどういうことを考えているのか知らないままだった。……もっと知りたいとか、会ってみたいとか……きっと思わなかった」
『……! 会いたいと、思ってくれるんですか? ディズィー』
「はい。だって私をずっと見守ってくれたロザリオの幽霊さんが、会って良かったと思って欲しいとまで言うんだもの。本当か嘘かは、確かめないと。それに私、選びたいんです。自分で、自分の未来は、決めたい」
そんなカイの意思を知ってか知らずか、ディズィーがカイの手のひらに自分の手を重ねた。
カイが言い淀んだ理由を理解し、ディズィーは指先に意識を集中する。カイは優しい。作戦なんか立てなくたって、「ギアと人類の総力戦さえ行えば」ほぼ確実にソルとディズィーが一騎打ちをする形になるだろうことは、彼自身口にしているのだ。ならそうしろと言えばいいのに、それは避けようとする。
(だけどね、幽霊さん。これだけ説明してもらえれば、私だってわかります)
ディズィーは人間を殺しすぎた。ディズィーの父親は人間を守護する最後の砦としてギアを殺す。彼がカイの言うとおり血の通った愛情を持つ人間だったとして、それでも、ディズィーを匿うことは出来ないだろう。彼はどうあってもディズィーを殺すはずだ。そのことは最早彼女の中で確信に近くなっている。そうすることが、ギアにカイを奪われたソルにとってのけじめでもあるだろう。
(不思議。あんなに、お父さんに会うのは怖かったのに。自分が人間だって認めるのも怖かったのに。居場所さえあれば、認めてくれる人さえいれば、私は最初から、人間になれたのかもしれない。でも、もう、遅いのよね)
いつかこの手に、本当に触れたい。そう思う心を自覚してディズィーは目を瞑る。ギアメーカーが言うとおりだったのだ。自分にはやっぱり、人間の心がある。それに目を背けてきた代償を払わなければいけない時がじきに来る。
「……私に、一つ提案があります。聞いてくれますか?」
ディズィーはそっと深呼吸をした。それから彼の耳に顔を近づけ、密やかに耳打ちをする。
『——! そんな、』
ディズィーの言葉にカイは息を詰まらせ、いけません、ディズィー、と震える声でわなないた。でもその否定を続く言葉で遮る。
「私、決めたんです。あなたが言ってくれた通り、その先を、自分で選んだんです」
ずっと、お仕着せられたギアのお姫様として生きてきた。群生の核としてだけ少女はあった。だけどあなたがたった一人の女の子にしてくれた。だから、許されるなら最後ぐらい、精一杯のわがままを叶えたい。
「だから……私の願いを叶えてください、カイさん」
終わりにそう言って、少女は儚げに笑う。
私が生まれた時から、ずっと一緒にいてくれたロザリオのお友達。
あなたは私に意味をくれた。私を認めてくれた。私の居場所はここ以外にもあるって、自分の隣を示してくれた。
それだけで嬉しかったんです。あなたの願いを叶えるためなら、私は
一番最初に拒まなかったのは、あなたを待っていたからなのかもしれない。お仕着せられたお姫様の冠を脱ぎ捨てて、自由になっていいと言われるのを、夢見ていたからなのかもしれない。
誰かに背中を押されるのを、ずっと待っていたのだ。
だから——私を鳥籠から解き放とうとしてくれた、私のお友達。
どうかそんな顔を、しないで。
私はあなたの笑っている顔が、一番好きです。