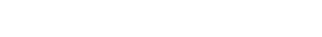12 罪の対価、永遠の贖罪
それでよかったんだね? と訊ねると、幽霊の少年は唇を噛み、両脇に下げた拳を握り込んだ。苦渋の表情。苦しいが、それ以上の選択は望めなかったのだということが、言われずともわかった。
「だから言ったじゃないか。彼女は君のために、自ら終わりを選択する。ディズィーはいつもそうだった。カイの願いを叶えるために、己の望みを犠牲に出来てしまうのが、彼女が母親から引き継いだ最も大きな特質だ。良いか悪いかは別としてね」
『そんなの、悪いに決まってます』
「どうかな。彼女はそのことについて後悔をしたことはきっとないよ。幸せだったんだ。なら、外野がとやかく言うべきではない。たとえ君でも」
ギアメーカーが立ち上がり、幽霊の方に振り返る。カイは俯いたまま、頭に伸ばされた彼の手に甘んじた。
ディズィーはカイとの交流の末に一つの決断を下した。ソルとディズィーが対面するのに一番手っ取り早いのは、最終戦争を起こすことだ。これ以外に方法はない、と彼女はカイを説き伏せた。それ以外の策を選ぶには、時間がないのでしょう、と。
ここしばらく、聖騎士団が躍起になってこのプラントを探し回っていることは分かっている。プラントはギア軍の心臓だ。これを奪えれば、人間側にも起死回生の可能性がごくごく僅かに見えてくる。だからテスタメントは常より強固にプラント周辺を守らせ、ディズィーを置いて自分も前線へ出ていた。
ならば、解法はただ一つだ。意図的に周辺の守りを崩し、聖騎士団が送り込んでいる偵察部隊にこの城の場所を知らせればいい。それで長きにわたった聖戦は、本当の終わりを迎える。
『幸せって、なんなんでしょう。ディズィーも、ソルも、家族になりたいだけなんです。きっと。……なのに誰も彼も痛みの多い手段を選択する。血だらけになって、苦しい思いをして、そうして手に入れるものが本当に幸せなのか、私にはわからない』
「とても幸福な疑問だな。持てる者の傲慢を手本にしたらそういう言葉になるんだろうね」
『嫌味ですか、ギアメーカー』
「いいや。僕の息子なら絶対に口にしなかったであろう言葉だと思って」
『……あなたの息子がどんな人間だったのかは知りませんが、随分なひねくれ者だったことは確かなようですね』
カイは肩をすくめ、でも彼の手ははね除ける気にならず、息を吐いた。
テスタメントの帰還を待って、ディズィーはプラント周辺を警護するギア達に命令を下した。もうぞろ、聖騎士団側にプラントの位置を報せる報告が届く頃だろう。戦争が始まる。この五年間、ギアから人類への一方的な報復戦になっていたものが、再び戦争に戻る。カイは北欧神話に描かれた終末戦争を思い出していた。長く続いた冬が終わり、スルトの劫火が吹き荒れる。ではギャラルホルンは私か。カイは自嘲的にまなじりを伏せる。この戦争を影からコントロールしている要素が一つあるとすれば、それは確かに、カイ=キスクという男の子の生き死にのことだった。
「何? 僕の息子の話が聞きたいのかい? 多分君にとってはあまり面白い話じゃないと思うけれど」
『ええ、そんな話は結構です。それより気に掛かることがあって。最後ですから、それだけは聞いておきたかった』
「へえ、君がそんなことを言うなんて珍しいな。……なんだい?」
『テスタメントのことですよ』
その名前を挙げると、ギアメーカーはなるほど、としたり顔で頷いた。
プラントにやって来てからの五年間、テスタメントというギアはカイにとって最も不可解な要素の一つだった。昔クリフに聞いた「ギアにされてしまった養子」が彼だということはすぐに分かったが、彼が抱えている矛盾はそれを差し引いても大きかった。
たとえばそれは、ディズィーに人間らしい暮らしを提供していたこと。彼は毎朝きっちり、人間と同じ食事をディズィーに与え、人間らしい服装をするよう彼女を教育していた。人間の言葉も教えた。これを不可解と言わずして何と言おう。ギアは人間を憎んでいたのだ。人間と同じ様式に揃えさせる必要などまるでない。むしろ人を滅ぼす旗頭として据えるのであれば、人と真逆の教育を施すべきだった。司令塔に支配されたギアは人語によるコミュニケーションを必要としない。ディズィーは、いつも思考そのものを命として下位のギア達に飛ばしているとはっきり答えた。
その矛盾は、彼が元聖騎士であったことの名残なのだろうか。そう考えたこともある。けれどそれでも奇妙な点は残されていた。誰も使っていないはずなのに清潔に保たれている、あの聖堂がカイの心にいつまでも引っ掛かった。
『彼はギア軍の参謀として誰よりも残虐に人類への報復を担ってきましたが、その一方でディズィーには誰よりも人間らしく接しました。ギアが本当に破壊のための獣なら、物事はもっとシンプルに力関係だけで決まるべきです。摂政制度なんて人間以外用いませんよ。思うに、彼にはディズィーを抑えておく必要があったんだ』
「なるほど。なんのために?」
『さあ。それは彼自身、わかっていないのかもしれない。彼の中に残された人間としての最後の願いが、不可解な行動を己に強いていたのかもしれない。けれど一つだけ確かなことがあります。彼はまだ、神を棄てていません』
「では誰が彼の神なのかな、カイ」
『クリフ様でしょう。あの人にとっての神は、然るに、己の父親だったわけだ』
カイが結論を告げると、ギアメーカーは手を叩いた。正解、ということなのだろう。やはりこの男はそれも見越していたのか。知っていて、彼には手を差し伸べなかった。人でなしの彼らしいことではある。
「僕もまったくその通りだと思うね。そして不幸なことに彼はそれに対する自覚をしていない。では、カイ。そんなことを訊いたぐらいだ。僕に対する『お願い』があるんだろう、言ってごらん」
『……。よりによってあなたにこんなことを頼むのは、私としても不本意なんですけどね。最後の最後に、ディズィーの邪魔をされてはかないません。彼を無力化してください。どうせそのぐらいあなたには朝飯前でしょう? 最後の食事は、ディズィーではなく彼が持っていくようにしておきますから』
言い終わると、ギアメーカーは手を叩いたまま大笑いを始めた。
「ははは! いいね。いいとも。博愛主義の権化みたいな顔して世界の全てを救おうとしていた男の子とは思えない言葉だな」
『何が面白いのか知りませんが、私は今も世界の全てを救いたいと願っていますよ。そのために、彼に邪魔をされるのは困るというだけです』
笑いすぎて涙まで滲ませているギアメーカーにじっとりとした視線を送るが、堪えた様子もなく爆笑を続けている。一体何が彼の琴線に触れたというのだろう。彼を理解したいとは一ミリも思わないがこの状況は不愉快だ。思わせぶりで意味深長な言葉が多いところまでは百歩譲るとしても、これはいただけない。
『帽子が落ちるだけで笑い出す年頃の少女ですか、あなたは。やめてください、きもちわるい』
「いや、いや、いや。今までで一番かわいらしいお願いだなと思うと、止まらなくて。悪気はないんだ」
『悪気がない方がろくなことをしでかさないとソルはもっぱらあなたを評していましたけれど』
「そうなのかもしれないな。しかし、まあ、いいとも。君の願いは、僕が叶えよう。少しばかり高く付くが、ポケットマネーで贖うとするよ」
『はあ……?』
疑心暗鬼の表情のまま立ち尽くしているカイにギアメーカーが微笑み掛ける。その表情に胸をちくりと刺す痛みを覚え、カイは小さく息を漏らす。
この顔を見たことがある。昔。どこかで。どこで? 十歳から始まっているカイの記憶の中に、ギアメーカーの姿が映り始めたのはディズィーにプラントへ連れて来られた五年前からだ。でもそんな最近のことじゃない。もっと……もっと昔、彼のこういう顔を、いつか……。
『僕はね、君に幸せになってもらいたいんだ。カイ』
(——!)
脳裏でフラッシュバックした光景にカイは呆然とした。
知らない男が(うそだ、知ってる、)カイの前に立っている。その時男は死者で、カイも死者だった(カイのために彼は死んだようなものだった)。彼はカイを造った男で、同時にカイのオリジナルであり、更に別の役割を与えられていた。そのことがカイはあまり好きじゃなかった。男は最低の変態で、(でも、彼という存在はたったひとりだけだったのだ、)図太い神経の持ち主で、だけど……。
「じゃあ、行きなさい、カイ。最後まで彼女のそばにいてあげたいんだろう? それがせめてもの償いだと信じてね。君は僕みたいなろくでなしじゃないんだから、ディズィーを泣かせるのはだめだ」
『あなた……あなた、まさか……』
「ん? 僕がどうしたって……ああ、そういうことか。何か、勘付いてしまったんだね」
ギアメーカーがカイの目尻に溜まった液体を指先で拭う。幽霊の涙も舐めたらしょっぱいのかな、なんて笑いながら。
心底、彼のことをひどい男だと思った。業を背負い、支払いきれない罪の対価を、五千百八十九兆六百五十二億千九百八十三回目になってもまだ精算し続けていることを、しかし誰にも明かさなかった。
彼の名前を呼ぼうとする。この言葉の並びが合っているという保証はなかったが、それが正解だという確信がカイの中にある。けれど、最初の音を形作ろうとしたところで、カイの唇を彼の手が押さえた。それから彼はもう片方の手で人差し指を己の唇に添え、しーっ、と子供に言い含める真似をする。
「その秘密は、墓まで持って行きなさい」
それが、カイがこの世界でギアメーカーを見た最後の姿になった。
◇◆◇◆◇
カイの墓を建てたことについて、かつてクリフ=アンダーソンは珍しくソルを詰った。ソルが記憶する限り最初で最後のことだった。聖戦で養子を失っていた男は、愛する相手を喪い失意の淵にいるソルを気遣いながらも、しかしそれはかえってソルを苦しめると言い、彼の死を必要以上に悼まないよう進言した。
「過去に囚われては、前に進めぬ。かつてわしがそうだったようにな……。悪いことは言わんから、その十字架を持ち歩くのだけは止しておけ。お前さん、今に取り憑かれてしまうぞ」
だがソルはクリフの進言を受け入れなかった。生前のカイがそうだったように、彼の形見になった十字架を常に首から提げるようにした。クリフはそれに気がついていたが、それ以上諫めようとはしなかった。もう諦めていたのかもしれない。喪う辛さをクリフも知っている。死を認められなかった人間に、生者の言葉は正しく届かない。
「お前さん、いつか地獄を見ることになるぞ」
それから程なくして、ソルは消えない幻に取り憑かれた。
近頃、シェルター各地で奇妙な噂が飛び交っている。地上への扉を閉ざして長いシェルター内部に、五年ぶりに外からの人がやってくるというのだ。五年というと、丁度ジャスティス掃討戦が行われたぐらいの年である。人類が大損失を被ったあの戦い以来、各シェルター間の交流は途絶えた。人が行き来するのに必要な護衛を行える人員が失われてしまい、人々は生き残るためにシェルター内への自主監禁を余儀なくされた。
今も外部——空に浮かぶ船に居を構えている聖騎士団の人間は、聖戦が終わっていないことを知っている。だからシェルターに入ってくる輩がまともなわけがないとすぐにわかるが、しかしシェルター内部の人間はそこらへんの感覚が麻痺しきってしまっている。情報と物資、それから刺激に飢えた人々は簡単に来訪者を受け入れ、その何者かに殺害されている、のだという。
「世も末だな。ただでさえギアが人を殺し続けているのに、とうとう人間が人間を殺すか。この手の恐怖犯罪を起こすような体力のある人間は、もうとっくにのたれ死んだもんだと思っていたが……」
『まるで人ごとだな、ソル』
「ああ、人ごとだとも。俺の目的は聖戦を終わらせることだが、坊やと違って人類の守護はそこに含まれてねえよ」
それらしき言葉を投げかけてくる幻影を一瞥し、ソルは団長室へ戻るために甲板の戸を開けた。
この十年間ソルに付きまとう幻の正体を、ソル=バッドガイは理解している。これはソルの脳が生み出した幻覚だ。カイの人格を模倣した言葉を喋るが、それはソルが自分の記憶の中にある彼の言動から構築したものに過ぎない。幻影がソルを非難するのも、嘲笑うのも、全てソルが一人で抱いている罪悪感の表れだ。いわばカイの幻影は、ソルの中に僅かに残された理性の擬人化なのだった。ただ、ソルが自分自身に抱いている嫌悪感が、カイの形をとって見えているだけ。
それでもソルにはこの幻が必要だ。気休めの偽物で、なんの慰みにもならない代替品以下だとしても。あの柔らかな肉や愛らしい温もりがどこにもなくても。それだけが今のソルを生かす全てなのだから。
形見の十字架は、五年前に無くした。
今はどこにあるのかもわからない。土に埋まっているのか、あるいは誰かの手に渡っているのか。あの十字架さえ手元にあれば、十字架の中にカイの魂が宿っているのだと自分に言い聞かせ続けることも出来たのかもしれない。幽霊なんか信じているわけではないが——どちらがましだったのか、今のソルにはわからない。
「団長、いるか」
「入れ」
団長室へ戻り椅子に座ると、程なくしてポチョムキンがノックの後にやってきた。彼が手に持っている書類を事務的に受け取り、ソルは顔をしかめる。作戦立案書だったが、時間稼ぎにしかならないような下策が堂々と書かれていたのだ。
「……それより、情報部はどうだ。ギアの製造プラントは見つかったのか」
作戦立案書から目を逸らして仕方なく訊ねるとポチョムキンは首を横へ振った。
「偵察部隊は消息を絶っている」
「……もういい、俺を行かせろ。そうすりゃ、多少は早く片が付く……」
「許可出来ない。団長は人類最後の砦だ。ここに控え、皆に指示を出せ。それが団長の仕事だろう」
「くそ……! こういうのは、あの小僧が得意だったんだがな……」
「言うな! …………。一時間後に攻撃開始だ。兵達に言葉を掛けてやってくれ」
ポチョムキンは言いかけた言葉を呑み込み、踵を返した。ソルは舌打ちをする。「兵達に言葉を掛けろ」など、ソルに出来るわけもないと知っていてよくもそんなことが言えるものだ。そういうのは、カイが得意だったことだ。カイが得意なことの九割はソルの不得手である。部下を気遣う、連携を取る、作戦を立案する、指揮を執る、兵の士気を高める、何一つソルに向いたものがない。なのに何故ソルは聖騎士団の団長など務めているのだろう。全部カイが死んだからだ。苛立ちが募り、床を蹴った。
「お前やっとけ」
「おい、待て!」
「くそっ……!」
カイが死ななければ、聖騎士団の団長などという面倒ごとしかない職務はあの小僧が勤め上げるはずだったのだ。カイが遺言など遺さなければ、ソルはまたフリーの賞金稼ぎに戻って、ギアを殺して回るだけのはずだった。そもそも聖騎士団にやって来たのだって、一時的に力を貸せとクリフに請われたからで、神器さえ手に入ればこんな場所に用などなくなるはずだった。何故。ソルは神器を握りしめる。この剣を手にして、自分はまだ、こんなところにいる。
『そんなにいやなら、甲板から飛び降りればいいのに。おまえは頑丈なギアだけど、流石にこの高さから落ちれば死ぬだろうに』
幻影が囁く。黙れ、と低く唸ってソルは甲板へ向かった。船から身を投げるなど、そんな真似が出来るはずもなかった。カイの死体を抱き上げて帰還した時の腕の感触が今でも身体にこびりついている。カイはソルを信じていた。ソルだけを最後に頼ったのだ。これ以上のない喜びだった。死をもって、カイ=キスクという子供は、ソルに目に見えないものが実在することを証明し、呪いを掛けた。ソルの心臓の欠片を奪い取って、二度と手に戻らないようにして、永遠に醒めない夢の中へ陥れて……
その欠片が心臓に返還されない限り、カイ=キスクは決してソルの中で死ぬことはない。幻影が消滅することもない。終わりはいつまでもやってこない。幻影を消せるのは本物のカイだけだ。でも死人は二度とソルの前に顔を出したりなんかしない。
『かわいそうなソル。死んでいると分かっているから、意地を張って、死んだことを認めない。理解と承認は別だからな。クリフ様があんなに仰ったのに、馬鹿な男。なあソル、知っているだろう? クリフ様の養子だったテスタメントが、どんな末路を辿ったか。死者に理想を押しつけるのはいい加減やめろ。ただ、惨めだ。私の骸はギアにさえされなかった。おまえを救えるものは、最早この地上のどこにも存在しないのに』
(なら救われなくていい。俺はただの殺戮兵器で構わない)
『本当に救われない。おまえはきっと、私を愛したりなんかしなければよかったんだ。私に変に同情したりせず、兵器は兵器のまま放っておけばよかった。情なんか移して、私に手を掛け暇を掛け、人間にしてしまったから、こんなに苦しむことになる。自分の娘は認知もしなかったくせに。ただきれいな顔をした機械が、愛を知らなかったからという理由で、逆にのめり込んでしまった。愚かしいと思わないか? その結果おまえが今度は兵器に成り下がる』
(惑わせるつもりか。俺はカイを愛したかったからそうしたんだ。後悔なんざない)
『お前は博愛主義者にはなれないな。お前の愛は……重たいよ』
(……知ったことか!)
荒々しくドアを開け放ち、甲板に再び出る。
「な——」
その先で視界に映ったものにソルは己の目を疑った。
無人のはずの甲板に何者かが立っていた。更に驚くべきことに、その何者かの姿にソルは見覚えがある。赤。女。ギター弾き。全身の血が沸騰していくのを感じ、話し掛けていたはずの幻影も掻き消える。獰猛な感情がソルの中を駆け回った。こいつさえ——こいつさえいなければ。この女さえいなければ——カイは死なずに済んだのに……
「あら、久しぶり! 私のこと、覚えてる?」
女が気安く話し掛ける。一目散にその人影へ向かって駆け出し、ソルは神器を振りかぶった。紅の楽師。あの日、ローマでカイが死んだ原因を作った女。カイが最後まで探していた「一般人」。そいつが、十年前と寸分違わぬ姿をしてべったりとした笑顔で手を振っている。
◇◆◇◆◇
「お帰り、しばらくぶりだ。聞いたよ。聖騎士団が派遣した偵察隊がとうとうここを嗅ぎつけたそうじゃないか。それじゃいよいよ、戦争が始まるね?」
耳に入ってきた軽薄な言葉に、男はそこでぴたりと足を止めた。最後の晩餐にしてやるつもりで多少色の付いた食事を持って来てやったことを、既にその声だけで後悔し始めていた。
確かに、聖騎士団全艦隊が集結し、ここストックホルムへ向かっているという情報を先ほどディズィーに進言したばかりだ。牢で身動きの出来ないこの人間が、何故もうそのことを知っているのか。そこまで考え、男は首を振った。考えるだけ無駄なことだ。こいつになら何が出来てもおかしくはない。五年間、繋がれた牢から脱出を一度も図らなかったことが一番の謎であるぐらいだ。
地下牢に繋がれたこの世界最大の罪人は、いつもつかみ所のない言葉でギア達を翻弄した。ギアメーカー。この世に生体兵器GEARを生み出した最低最悪の造物主。多くのギアにとってこの男はとりわけ深い憎悪の対象だった。こいつさえいなければ、ギア細胞なんてものが作られなければ、ギアの女王ジャスティスが創造されなければ、ギアはこのような苦渋の歴史と戦いの道を選ばずに済んだはずだとどこかで考えてしまうからである。
「やっとだ。やっと戦争が始まる。そして同時に世界が終わる。世界の希望は散り、因果律は収束し、新しい世界へ進む。お膳立てには時間が掛かったけれど……ようやく、〝僕〟の役目も終わりだ。これで私は〝僕〟を棄てられる」
「……何のことだがわからないな」
「フレデリックがやってくる。今度こそ、ギアのお姫様を討ち取りにね。背徳の炎を相手にするとなると……流石に、彼女が出ざるを得まい。どちらが勝つにせよ、決着が付く。このさもしい食事とも今日でおさらばだ」
「食事を供されることに感謝しろ。貴様のような罪人は生きているだけでこの上のない恩寵を受けているということを忘れるな」
「ああ、まあ、そうだな。だって私が生かされているのは君のおかげだ。あの時も、それからも、ディズィーはずっと機会さえあれば私を殺そうとしていた。だが君の言葉がそれを咎めていた。けれどね。彼女は馬鹿正直に私が最終手段を行使する可能性を信じていたみたいだが——君は別に、そんなこと信じちゃいなかっただろう? だって聖騎士団の出身なんだから。例え思考をジャスティスに上書きされても素体が持っていた知識は消えたりしない。全てのギアを一瞬で滅ぼす開発者側のセーフティなんか、最初からありもしない。それを……知っていたはずだ、テスタメント」
ね? 小首を傾げてにっこりと笑いかけると、ギアメーカーは目を細め、薄っぺらい笑みを貼り付けたまま痩せこけた手をひらひらと振って見せた。
男——ギアの総指揮を執る立場にまで上り詰めたかつての聖騎士、テスタメントは苦虫を噛み潰したような顔でその言葉を聞く。彼の言うことは一部分正しい。聖騎士は、ギアを殺すために、まずギアの構造を教えられる。効率よく敵を殺すために急所とその突き方を伝授される。完全な解明には至っていないとはいえ、全てのギアに共通した弱点などありはしないということは、全ての聖騎士が熟知していることだ。
ギアはタフな生き物だから、まず首を取れ、司令を受け取っている脳を潰せ、最後に心臓を刺せ、とは教えられる。しかし脳を潰せば終わりだというわけではない。それはギアになったテスタメントが一番よくわかっていた。テスタメントが実戦で生死の境をさまよい、A国の手でギア化させられた原因は、脳を潰して殺したと思い込んでいたギアが、細胞で活性化した身体に残された最後の力を使ってテスタメントの臓腑を抉り取ったからであった。
しかし何故、突然そんな話をテスタメントに向かって始めるのだ? 理由が分からず、正体不明の悪寒に襲われてテスタメントは身震いをする。今までテスタメントは何回かこの男のいる牢へ足を運んだことがある。いずれの時もギアメーカーは何も語らず、格子窓の外を見ているばかりだった。出される食事を文句を言わず食し、何一つ望まず牢に繋がれていた。彼は手の掛からない囚人だった。ディズィーを除き、世話役に話し掛けることがまずなかったのだ。
「不思議そうな顔をしているね」
「……」
「そろそろ種を明かす頃だ、ということさ。世界が終わる前に、本当のことは知っておいた方がいい」
テスタメントの沈黙を無視し、彼は微笑んだ。ぞっとする笑みだった。ろくなことをしでかさないだろうという予感を、対面した誰もが抱くような、おぞましい顔をしていた。
「さて——ギアに対する最終安全装置についての話だが、仮に人間が使えるセーフティがあるのなら、百年も人間の叡智を集結させていた聖騎士団はとっくに答えに至っていたはずだ。天才が三日で為したことは、凡人には一見再現不可能に見えても、実は三十年も掛ければ到達出来る事柄に過ぎない。なのに見つけられないというのは存在しないということの証明と同じだ。それは君の養父が教えてくれていたはずだろう?」
ギアメーカーは饒舌にまくし立てる。今まで我慢してきた分を一気に吐き出すように、決壊したダムよろしく話し続ける。
「養父……? 何の話だ、それは」
「なるほど、これは根深いな。では君には養父がいるという前提で話を進めよう。君の養父……クリフ=アンダーソンは晩年に一人の少年を育てた。カイ=キスク。彼は天才だったが、ギアに対するセーフティを使うことなく死んだ。あのクリフ=アンダーソンに育てられた天才の子供がだよ? ギアにセーフティなんか本当についているなら、あの子はあんなにあっさり死なないさ。でも死んでいる。それはつまり、そんなものはないってことだ。カイが死んだ段階で、人間がギアを制御する方法なんてないことを、君は確信していたんだよ。違うかい?」
「……ッ!」
その言葉に、テスタメントは手から盆を取りこぼしてしまった。
陶磁器の皿は割れ、中身が床中にぶちまけられる。飛び散ったトマトソースがギアメーカーの顔に跳ねた。醜いスプラッタショウのような有様だった。
カイ=キスク。十年前、ローマ会戦で死んだ人類最後の希望だった少年。そのような話は聞いたことがあった。天才。確かにそうだったのだろう。たった十五で騎士団の人望をあまねく集め、前線を率いていたかの少年は、初陣で呆気なく人間としての命を失った雑兵とはまったく違う存在だった。
その子供と、ギアメーカーに何の接点が? 新たな疑問がわいてくるが、ギアメーカーはテスタメントに考える時間を与えてはくれない。
「なのに何故、君は私を生かしたのか。かわいそうだから、ずっと言わないであげたんだけど……答えは非常に単純だ。だろう?」
「ッ……あ……ああ……よせ、ギアメーカー……」
続けてギアメーカーが口にした問いにはっきりとした恐怖を覚え、テスタメントはギアメーカーの目を睨み付ける。五年近く牢に囚われていながら、まったく変わることのない生に対して執着も絶望もないその眼差し。それが今、テスタメントを正面に見据え、最後の推理を披露する探偵のように淡々と口を動かしている。
盆を取りこぼしたことで空いた手のひらで己の左胸を鷲掴んだ。長い間目を逸らしてきたことを、詳らかに暴露されてしまうのではないかという予感が頭の中で警鐘を鳴らしている。
「つまり君は、五年前に人間性を取り戻してしまったんだ。だから君の行動はいつも不合理的だった。君は——父親の仇を取りたかっただけだよ」
「貴様——!!」
そうして告げられた言葉にかっとなり、身体の中を駆け上がる衝動に駆られるまま、テスタメントはエグゼビーストを召喚してギアメーカーの方へ獲物を振りかぶった。
『お前さん、もうちっと、自分に素直になりな。苦しいんじゃないのか? 今のままじゃよ。あーあ……俺も、ヤキが回ったかね。自分を殺したギアになぁにとうとうと語ってんのか、自分でも分からんなあ。……だけどな』
『アンタいつか、後悔するぜ。心と身体の乖離にな。お前さん、本当に人が憎いのか? 本当に憎かったものはなんだ? そいつは、お前さんの父親を奪ったもんじゃないのか?』
脳裏に昔殺した男の声が蘇る。ずっと思い出せなかったはずの光景が、鮮明に映し出されていく。古傷の疼きにテスタメントは歯ぎしりをした。ジェリーフィッシュの長が遺した言葉はテスタメントの心の奥で封をされていた人間性を強く揺さぶった。かつて父と仰いだひとを殺したギアの女王への強烈な憎しみと、ギアの女王に与えられた絶対命令が二律背反を起こす。その矛盾が、テスタメントから記憶を奪った。でも、浮かび上がってきた人の心を完璧に押し戻すことは、出来なくて……。
ギアメーカーにエグゼビーストが襲い掛かる。だがその身体に当たる直前に、召喚した魔物が掻き消えてしまう。バックヤードへの強制退去術式を当てて相殺されているのだと気付くのに少し掛かった。
「ジャスティスに支配されて忠実な狗として殺人を続けながら、でも君は常に、人の勝利という形で戦争が終結することを望んでいた。私を生かしたのはそのための保険だ。ディズィーを城の外へ出さなかったのも人類の生存確率を少しでも上げるため。思えば君の行動は矛盾ばかりだったな。大聖堂を綺麗に掃除していたんだって? カイが訝しんでいたよ。ギアは神に祈らない。ならあんな場所、とっくに廃墟になっていなきゃおかしいだろう。なのに蜘蛛の巣一つないというのは、あまりに不自然に過ぎるな。そこから分かることは一つしかない。自由にこの城の中を動けるギアの中に、神に祈り、聖堂を清潔に保っている存在がいたということだ。そんなやつは君しかいるまいに」
「ぐ、ぅ、き……貴様に、何がわかる……! ギアを生み出した諸悪の根源である、貴様に!」
「そうだね。わかるなんて傲慢は言わない。だけどお礼と謝罪はしておかないと」
ギアメーカーが立ち上がる。彼を縛っていた枷は瞬く間に消え、自由になった男は、己の精神を蝕む二律背反に身動きが取れなくなったテスタメントの方へ悠然と歩み寄った。それじゃ失礼して、なんて呑気な言葉が転がってきて、テスタメントの右胸に造物主の指先が触れる。心臓の反対、ギアの紋様が記された忌まわしき場所を押し潰す。
その瞬間、テスタメントの身体が跳ねた。瞳は白目を剥き、再起動を命じられた機械のように小刻みに震え始める。
「一つ、教えてあげよう。ギアには確かに最終安全装置はないよ。でもそれは、兵器として、武力装置としての無力化をするという意味でのセーフティだ。どうして全てのギアに紋様が入るのか、考えたことはなかったのかな? ただの識別記号だと? だとすればそれは誤りだ。
……これはね、司令塔の命令を送受信するための媒介なんだよ。ギアの思考部分に対する心臓だ。で、ギアを造った僕は、ここから君の思考を書き換えることも出来る。残酷なことだが、君の神のことは忘れて貰おう。中途半端に人に操を立てられると困るからね。そして……ありがとう。これで世界は、僕の息子だった子はやっと救われる」
誰も聞くことのない言葉を語り終え、指先が胸から離されると、テスタメントは焦点の定まらない目でギアメーカーを見た。そうして命令を受理した証にこくりと頷き、踵を返す。彼はもう永久に自分の養父だった男のことを思い出せない。だけどそれが幸か不幸かは、誰にも決められない。死者の想い出に縛られ過去を抱きしめて眠るのと、死者と決別をして明日を夢見て歩くことの、どちらが正しいのかを決める権利は、決して誰にもないのだ。
テスタメントの後ろ姿を見送り、ギアメーカーは独りごちる。
「君が過去のループへ旅立つ前に僕に言い残した言葉も、そういう意味だったのかもしれないな、ヴァレンタイン……いや、ジャック・オー。父の愛しか受け取れずに自殺を繰り返した子と、愛を手に入れた故に死して相手を縛り付けてしまった子と。テスタメントもそれと同じか。業が深い、と君はアリアの顔をして言ったが。それを言うなら十分君も……いや、それは僕のせいか。うん。僕が悪いんだな、これは……」
弱り顔で額をぽりぽりと掻き、困ったように笑う。アリアを人に戻すためのツールとして生み出された彼女は、こと今生のギアメーカーにとっては、息子を運命の鎖から解放するための鍵に等しかった。そのことをジャック・オーは怒らなかったけれど、その分、五千百八十九兆六百五十二億千九百八十二回目のギアメーカーには苦言を呈するだろう。あの叱責は、少なからず今のギアメーカーに影響を及ぼしている。
「さあ——始めよう。舞台の用意には〝僕〟を使った。魔器がここに辿り着く頃には最早私の中に〝僕〟は残っていないだろうが、それでいい。この次の世界では、今度こそ、僕達は他人にならねばいけない。だから……フレデリックを頼んだよ」
格子窓の向こうを見上げる。遠くで爆撃の音が聞こえ始めている。聖騎士団の先遣隊が、この城に到達したのだ。テスタメントはギアの姫を補佐する冷徹なギアとして指揮を執ることだろう。その裏で何が進行しているのか知る頃には、世界は終わっている。
願わくば、次の世界でも出逢うことがありますように。小さな祈りを掛け、ギアメーカーは十字を切った。たとえお互いのことが分からなくても、出会えるのならそれだけで構わない。