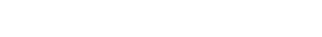13 かみさまがもういないなら
まばゆい光が帯になり、空を疾走った。
散開させていたのにも関わらず、艦隊の五割が消滅したとの報告が入る。あの娘が出ているのか。ソルは面を高く上げた。ガンマレイ——五年前の決戦でも少女の母だったものが用いた、空間そのものを削り取るほどの破壊の力。
紅の女がもたらした情報により、人類側は最終戦争を起こすことに決めた。ギアが人間を罠に掛ける道理はない。試算では、ギア側の兵力は聖騎士団の五倍を優に上回っている。だから予備兵力も残させず、総攻撃を仕掛ける他にもう手がない。ソルが負ければ終わりだが、ソルさえ生きていれば、勝てる可能性はある。シンプルな博打だ。
『死にに行くのか、ソル』
歩を進めると、幻が気のない声で訊ねた。
「副官殿は止めなかった」
『いや。自殺行為だと、ポチョムキンは分かっていたよ。だけどおまえの目を見て……もう無駄だと判じたんだろう。おまえは死に場所を探す亡者と同じだ。勝手に苦しがって、身勝手に救われたがる。その上、死にたがりの理由を私に押しつけて』
「死ぬ気はねえ。あの娘は俺が片を付ける。五年前に殺せなかった俺の落ち度だ。落とし前はキッチリ付けなきゃいけねえ」
『うそつき。本当はまだ、あの時どうしたかったのか、その答えすら見つかっていないのに。ディズィーを殺せばそれですっきり出来るとか、許されるとか考えているのなら、とんだお門違いだな』
幻影の声は苦々しい。でも、ソルはそれ以上の答えを幻に与えてやれなかった。
十年にわたる悔恨の中で、とうとう、ソルも精神を磨り減らしきってしまっていた。限界がやって来たのだ。人間が敗北する前に、ソルの終わりが近づいている。死ぬ気はないと言ってはみたが、本当に死にたくないのかどうかさえ、もう確信が持てない。
『おまえに待っているのは地獄だけなのにな』
しばらくして、黙り込んでいた幻影がぽつりと漏らした。
『地獄だ。地獄しかないんだよ——ソル。なのに、その地獄に向かっておまえはこんなにがむしゃらに突き進む。それは……地上の方が、遙かに煉獄に近い、ということなのかもしれないけれど。……ならば私は、いいや、カイ=キスクの姿を真似た幻は、おまえにとっては何だったんだ?』
「それは……」
『答えをくれないか、ソル=バッドガイ』
幻の声音はあまりに悲壮を極めていた。許されたがっている幻影は、ソルの映し身だ。ソルはばつ悪く床を見る。吐き気がするほど青い空から目を逸らし、地獄があるとされる方をぼんやり見つめる。
「……ドラッグだよ、坊や」
するとカイの幻は、心底げんなりしたふうに自嘲の笑みを漏らした。
『脳内ドラッグか。ならば私は、さながらエンドルフィンの申し子か』
「ああ、そうだな。テメェを何度も殺し、その度に蘇生させて、生きていると騙し続けて。……忘れられねえんだ。忘れたくない。坊やが……俺を置いて……アリアのところへ行ってしまったと、信じたくない……」
『そのために剣を取るか。騎士道精神の欠片もない。ならばおまえを本当の意味で救えるのは、死だけなのに。どうして……この十年、生きようとなんか、したんだ……』
幻の声がどんどん弱っていく。それは次第に蚊の鳴くような声になり、泣きじゃくる子供のそれになる。
生きていた頃のカイは泣かなかった。あの感情の欠如した子供は、泣き方も知らなかった。なのに幻はぼろぼろと涙をこぼす。
ソルはざりざりと砂埃を踏み潰した。この涙がある以上、やはりどうしても、これは嘘の塊なのだった。幻はソルの良心。これから死にゆくのだから、最後には、それくらい自覚しろ、と懇願している。
『わたしはもう死にたい』
そうして振り絞るようにカイの形を借りた心が呟いた。
ソルの心臓から漏れる膿が、どろりどろりとあふれ出す。ずっとかさぶたで蓋をしていた本音が、解き放たれ、自由になり、落下して死んでいく。そうだ。本当は分かっていた。この十年間、ソル=バッドガイはずっと死にたかった。アリアも死に、カイも死に、ソルにはもう何も残されていない。残っているのは己を憎悪する娘らしき少女だけ。でも彼女はギアの手に渡り、今この瞬間も人を滅ぼそうとしてきている。そこに対話の余地はない。
だけど……ソルは首を振る。わがままを言う幻に、再び呪いの言葉を振りかざす。
「そいつはカイ自身に言え。あいつが俺に生きろと言ったんだ。あの日、あの時、生きろと呪い、俺から死を奪った。生きていれば救われると、性善説の申し子みてえな世迷い言を俺に遺して逝った。だから俺は死なない。死にたくても許されない。抜け殻になっても——柄でもねえ正義の味方の真似事をしてでも——死ぬわけにはいかない……」
『……おまえは、馬鹿だ。わかっているのか?』
「ああ、そうだな。分かってるよ。カイに出会った日から、俺は少しずつ馬鹿になって……今じゃこのざまだ」
だからもうテメェも消えろ。顔を上げたソルの眼差しを見て、幻はかぶりを振る。そうして望まれた通りに姿を消し、甲板に静寂が戻る。
もし——ディズィーに人の心があって、アリアの言葉を理解していたのならば。
まだ……僅かでも望みはあったのかもしれない。ディズィーはソルの拠り所になり、ギアと人間は和解し、物語はめでたしめでたしで幕を降ろす。
だけど全てが机上の空論だ。でもしか論だ。父娘は、敵と味方という線引きで引き離された。人間は少女を殺せと言う。少女は人間を殺せと命じる。ソルには娘の言葉を聞いてやることさえ出来ない。その間に、殺されるかもしれないのだから。
ディズィーがギアの姫になった時点でソルは彼女の父親であることを許されなくなった。もしソルが再び彼女の父親になることがあるとすれば、彼女の心臓を穿ち、頭蓋を潰し、肉片にすりつぶしたその後だ。肉塊にまでしなければ、もう彼女を娘として愛することは許さない、と世界が言う。
「ああ——ほら、おいでなすった……」
だからとうとう真正面に両翼を持つ少女が現れた時、ぼやかれたソルの声は、酷く乾ききっていた。
これは予定調和の幕開け。決められたエンドロールへの一本道。ソルはニヒルに笑む。見ろよ、あの、人への憎悪という憎悪で凝り固まった表情を。我が娘ながら……なんと恐ろしい顔をするのか。
「この、裏切り者が! 何故……人の味方をする!」
わななく少女の叫びは痛ましく、同時に、どこか浮ついた響きを持っていた。これから命の奪い合いをするということに対する恐怖が彼女の中に感じ取れない。今まで城に引きこもっていた司令塔がのこのこと前線までやって来たのだ、それは当然のことなのかもしれないが。
(しかし……)
冷静な分析をするのと同時に、まるで親戚の集まりに顔を出した時のような場違いな感情が顔を出し、大きくなったな、という言葉が口をついて出そうになる。彼女を最後にまともに見たのは、ジャスティスを殺したあの現場でだ。あの時は生まれたばかりの赤子だったはずなのに、たった五年でもうソルの胸あたりにまで身長を伸ばし、成熟した姿を見せている。
「何故母を殺した。私達を——裏切った……!」
「は、裏切りもの、か。ま……俺は確かにギアだが」
裏切り者。そうなのかもしれない。アリアの遺言は守れなかった。彼女の期待を裏切ったのは事実だ。彼女が兵器に成り下がることを無理にでも止めることが、ソルには出来たのかもしれなかったのに。
だけど……首を振る。それでも今の形を選んでしまったのはディズィー自身なのだから。
ディズィーはハーフギアだ。人の心を持つ資格が彼女にはあった。
「何故、はこっちの台詞だ。ジャスティスと違って……テメェの心は、自由なはずだ。……何故! 人を殺す……!」
「気安く母を語るな! おまえは……おまえだけは、殺す……!」
「泣き言か?」
「なんだと!?」
ディズィーからはやはり理性的な言葉が返ってこない。自由になれるはずの心は縛り上げられ、地獄にしか辿り着かない。ではやはり、この娘も救われないのか。カイを喪ってから亡者のように地上を這いずるソルと同じように。母親を喪ったこの娘も、生きる意味を持たないのか。
ソルは封炎剣をゆるりと持ち上げた。だとすれば……ソルの救いが死である以上、等しく、この娘の救いも死にしかない。
「この……ガキが。癇癪で人が滅ぶか! 救われねえ……テメェは、死ね!!」
「母への手向けだ。朽ちろ!!」
刀身が炎をまとう。宣告と同時に、ディズィーが食ってかかるようにこちらへ飛び込んでくる。だが遅い。ディズィーの攻撃は生ぬるく、ソルにかすりさえしなかった。燃え盛る炎を差し穿ち、ソルは小さく呟く。——せめてもの情けだ。お前は一足早く、楽になれ。
「あああああああああっ!!」
その瞬間、耳をつんざくような絶叫があたりに響き渡った。
高熱で灼かれながら、刃物で身体を切り裂かれるのだ。痛みは想像を絶するだろう。だけど……ソルは奇妙な手応えを覚える。司令塔の支配下に完全に置かれたギアは機械と同じだから最早叫びすらしない。痛みに藻掻く間があればその隙に反撃を狙う。でもディズィーは、叫ぶだけで次なる一手を加えようとはしてこない。
「痛いか、小娘。それがテメェの報いだ。次はどうして欲しい。羽根をもぐか? 目玉を潰すか? 悪いが命乞いは聞けない。最後には脳髄をぶちまける。聖騎士団の長になった以上、そうすることが俺の義務だ」
「……っ、く、あ……」
「だから大人しく……ああ?」
ソルは違和感を抱えたまま少女の首を掴み取り、持ち上げた。両腕を己の首に伸ばし、苦しげに藻掻く彼女へ次の言葉を向けようとする。
しかし言葉は途切れ、どこかへ消えてしまった。
伏せられていた瞼が開き、緋色の眼球がソルを見た。そこに填っていたのは、決してエラーに対処できずフリーズした機械が出来る目ではなかった。ソルの中の違和感が増大し、それに呼応するようにそこから透明な液体が流れ出す。
液体は少女の首を伝い、ソルの手に落ちた。生温かった。涙だ。人間みたいな涙を、ついさっきまで狂気の色を宿していたはずの瞳から、ぽろぽろと流し続けている。
少女が口を開く。
緋色の目で救いを求める赤子のように、ソルを見ている。
「おとうさん」
首を掴む手から力が抜けた。
少女の身体がどさりと崩れ落ち、腹部に深々と突き刺さった剣だけが彼女を空中に縫い止める。だが彼女の身体を再び持ち上げることがソルには出来なかった。訪れた衝撃があまりにも大きすぎた。
今この娘は、何と言った? ソルの思考を混乱が埋め尽くす。一生、聞くこともないと思っていた言葉だ。まかり間違っても自分を串刺しにしている男に対して使う言葉ではない。第一彼女はついさっきまで自分を憎んで憎んで憎んでいたではないか。こんな……十年前に死んだ少年と同じような顔をして父と呼ぶ道理がない。
(だが、それじゃ、さっきの違和感は)
一方で納得出来るものもあり、ソルは小さく喘ぐ。あの妙に生ぬるい攻撃。ふわふわと浮ついた決意の感じられない言葉。だから——もし、もしも、だけれど。
人を憎みソルを殺すと糾弾した、あの言葉こそが、他のギアを騙してソルに接近するための嘘だったとしたら?
「やっと会えた。わたしの、おとうさん。……やっぱり、こうなっちゃったな。これ以外に、方法、なかった、ものね。でも……いいの。私を殺す相手はせめて選ばせて、って私が幽霊さんにお願いしたから……」
少女の指先がソルの頬へ伸ばされる。身体が力なくソルの方へしなだれかかり、服の隙間から十字架が顔を出した。五年前にソルが無くした十字架だった。あの、敬虔に神に祈り、裏切られて死んだ少年の、形見になったものだ。
「幽霊さん……わたし、あなたのお願い、叶えましたよ」
ディズィーが囁く。恋する少女の面持ちで、晴れやかに。
◇◆◇◆◇
——どうしても、その方法を選ぶのですね? と幽霊さんは言いました。
私はその問いかけに頷く。警戒されずに近付くためには、ギアの司令塔らしく振る舞わなければいけない。だって私は大量殺人の指揮官で、お父さんは人間を守護する最後の砦。私がやったことを、世界は、お父さんは、決して許さないと幽霊さんも言っていた。だとすれば、お父さんが私と話してくれるのは、私が兵器としては完全に役立たずになったあとだけだ。幽霊さんの願いを叶えるには、私の心臓を差し出す必要がある。
——そんなことをしなくても、あなたは救われていいはずだ、と幽霊さんは首を振る。
ううん。私も首を振って、幽霊さんの言葉を否定した。私はもう、救われました。あなたが私を許してくれた。あなたが私を人間にしてくれた。救われました。救われたんです。だから今度は、お父さんを救う手伝いを、私がする番。
そう言って笑うと、幽霊さんはとても悲しそうな顔をしました。そんなことを言わないでレディ、と泣きながら呟きました。だけどね、幽霊さん。駄目ですよ、と私はあなたに言います。だってあなたは正義の味方なんでしょう? 世界を救おうとして、死ぬまで、戦っていたひと。だったら世界を救えなくなる選択は、しちゃいけないの。
——私は、あなたたち親子が、温かい家族になるところを見たかったのに。
幽霊さんの言葉は、優しい。でも優しすぎる。優しいから、かえって残酷なことを、あなたは望んでしまう。
ごめんなさい、と私は幽霊さんに謝りました。私はもう知っているんです。幽霊さんがお父さんに会える、唯一の方法。私が使える、たった一度きりの奇跡。
それは私が死ぬこと。
私が死んで、この十字架に込められた祈りが全て解放された時、一度だけ奇跡が起きるのだと……ギアメーカーは私に告げていた。
「よかった。やっと、わたし、お父さんに聞けるのね。ねえ……お父さん。あの時私のことを、殺そうとしたの? それとも……本当は、手を差し伸べてくれただけだったの?」
耳元から、幼い少女の声が聞こえてくる。もたれかかってきた肢体を今度は支え、ソルは息を詰まらせた。
あの時。ジャスティスを殺した時。アリアが遺言をして逝った時。ソルは赤子に手を伸ばした。剣ではなく——指を伸ばした。
「俺は……」
「ふふ、意地悪なこと、聞いちゃったかな。あのね、私、恨み言を言いに来たわけじゃないんだ。聞きたいことがたくさんあって、来ただけ。それから、お父さんに殺してもらいに来ただけ」
少女が笑う。ソルが愛した女と同じ顔で、ソルが喪った少年と同じように微笑む。
「ね、お父さん。家族って、なんだろう? 私、言われたの。きみは親の愛を知らないんだねって。だってお母さんは生まれた日に死んでしまったし、お父さんは、私の敵だもの。お母さんもお父さんもいない場所で、私、人を殺すことしか教えてもらえなかった。ギアでいたければ、人を憎み、殺す事で、自分が人でないことを証明しなさいと、私を育てたギア達は、そればかりを言い続けた」
そこまで話し、ディズィーはげほ、がは、と咳き込んだ。腹を封炎剣が貫通した状態で無理に喋っているのだから、当然の反応だ。肉と刀身の隙間からは血が滴っており……咳き込むと同時に、べったりとした血液が飛び散り、ソルの顔に付着する。
彼女から漏れ出た血は赤い。人間と同じ色をしている。「わたし、血、赤いのね」。ギアの姫が呟いた。まるで人間みたいな色よね、へんなの……。
「私……こわかった。ギアと人が憎み合い戦っているこの世界で、人でもギアでもない中途半端な私には、本当はどこにも居場所がないの。人間はジャスティスの血を引く私を絶対に受け入れない。ギアは、私が継いだジャスティスの力にしか興味がない。私には、確かに全てのギアを従わせる力がある。でも、ギアは……命令を聞くだけで、私の声は聞いてくれないのよ。私のことを私として見てくれないの。ギアのみんなにとって、私は母ジャスティスの代替品に過ぎない。『ジャスティスの娘』でしかない。誰も、私の本当の姿を見てくれない……!」
「……それは、」
「でも、幽霊さんは、違ったわ」
力強い言葉と共に深紅の瞳がソルを捉える。ソルは彼女から目が離せない。彼女の目は、人間の色をしている。触れられさえしなかった赤子はいつの間にか人間になり、恋する少女の瞳をさらけ出している。
吐き出しそうな気持ちを抑えて呻いた。あの日殺し損ねた娘は、知らぬ間に恋をして、大人になって……でも今は父親に心臓を貫かれている。
「あの人は。私をディズィーと呼んでくれた。ギアの姫じゃなくて、ディズィーっていう名前の、どこにでもいる女の子として私を見てくれた。一緒にお父さんに会いに行こうって言ってくれた。私がつらいって言ったら、人間だから仕方ないって言ってくれた。私にはじめてをたくさんくれた。私は私なんだって、認めてくれた。私はジャスティスのバックアップコピーなんかじゃなくって——お母さんとお父さんの子供なんだって、言ってくれた……!」
「……ッ、もう、喋るな。そんなことを……言うな……!」
それに我慢がならなくて、ソルはからからになった胃袋の中身の代わりに泣き言を吐瀉する。
みっともない顔を自覚も出来ず、叩き付けるように。
「テメェは、癇癪持ちの、クソガキじゃなかったのかよ。だから俺はテメェを刺したんだ。だから殺すしかないと思った! なのに……なのに急に……人間と同じ顔をして、俺を見るなよ……!」
「……そっか。やっぱり、優しい人なんだね、お父さん。幽霊さんが言った通りだった。最初はちょっと疑ったりして、悪かったな」
少女はそんな父親を責めない。ひどい顔ねとさえ言ってくれない。ただ傲慢なまでの寛容さで、余計にソルを追い詰める。
どうして自分は、何も聞かずに少女を刺し貫いてしまったのだろう? ソルはわだかまる後悔を噛みしめた。話が出来る相手なら、話せばよかったのだ。それで全て解決したではないか。致命傷を与えてしまう前に、予定調和の悲劇を、ハッピーエンドのお伽話に書き換えることだって出来たはずじゃないか。
でもそんな思いを、ソルの中に僅かに残された理性が否定していく。いいや無駄だ。こうするしかなかった。身勝手なエゴでも、いつか誰かがどうしても殺すと言うのならソルの手でそうしてやる方がまだマシだと、ずっと考えていたはずだ。ディズィーが許される道はないのだ。例え彼女が人間になっていたとしても、もう、何もかも全てが、手遅れだったのだから。
苦悶の表情を浮かべるソルの手を、ディズィーの柔らかい指先が掴もうとする。だけど握りしめるだけの力が足りていない。弱々しく添えられる手のひらを、ソルの方が掴み取ってやるとディズィーが照れくさそうにする。
「お父さんの手、あったかい。お父さんも人間なんだね。大切なものが、たくさんあるんだ。守りたいものがいっぱいあって、聖騎士団にいるんだよね。私……今になって、やっとそれがわかったの。お父さんはギアだけど……それよりずっと強い気持ちで、人間でいることを選んだ。……私ね、ずっと、お父さんから生まれたことを、認めたくなかった。だけど今は……私はお父さんの娘だって、ちゃんと言えるよ」
ソルは歯ぎしりをして唇を噛んだ。触れ合うディズィーの肉体が生温かいという事実が、ソルを苦しめていた。死ぬ間際のカイの身体も、同じように温かかったのだ。
十年前の出来事がフラッシュバックする。おまえなら出来る、と言い残したあの少年の声が聞こえる。
だというのに、いつもソルに付きまとっていた幻影は、こういう時に限っていつまで経っても現れる兆しを見せない。そんなものよりも、今目の前で死んでいっている少女の存在の方が大きくソルの心にのしかかって、心がもう、幻を思い描く余裕すらないのだ。
「お父さん、ごめんね。こんなふうにしか、お話出来なくて。でも、私は、人間になるのに、時間を使い過ぎちゃった。もっと早く気がついていたら、違ったのかもしれないけれど。ギアって……ままならないね。私も……テスタメントも……みんな、振り回されて、ばっかりで」
「やめろ……ディズィー……やめてくれ……」
「……あのね、お父さん。人間か、そうじゃないかは、生まれでは決まらないんだって。幽霊さんの受け売りなんだけど。何を選んで、何をしてきたかで、決まるって。……幽霊さんは、まだやり直せるって言ってくれたけど。けれど私はいっぱい人間を殺したから、もう人に憎まれるギアにしかなれない。でも……」
みっともない懇願に、それでも娘は笑い掛けた。しょうがないお父さんね、と彼女は嬉しそうに目を細める。
——しゃんとして、ちゃんと世界を救ってね。
少女は血まみれの唇で父親の頬にキスをする。キスは、あなたが必要で生きて欲しい、という気持ちの証明。
だから。
——きっと救われて、お父さん。
少女は祈る。
幽霊の男の子が、今度こそ救われるために。
「でもね。最後は、ギアのお姫様じゃなくて、お父さんの娘として死にたいな。だから、これでよかったの」
ディズィーは夏の終わりに咲く向日葵みたいな顔をして今際の言葉を囁いた。
最後の力を振り絞ってソルの身体を突き飛ばす。反動で封炎剣が引き抜かれ、腹に空いた大穴から多量の血を噴き出しながらディズィーの身体が落ちてゆく。彼女の背から生えた両翼はもう動かない。神器による一撃は致命傷となり、残された僅かな時間も、全て使い切った後だ。
「——ディズィー!!」
ソルは蒼白になり、それを慌てて追った。
加速度的に重力が掛かり、フリーフォールしていく娘の亡骸へソルは追い縋った。これほど必死になったのは、十年前、ローマでカイを失う直前の、あの時以来だった。
「馬鹿が……テメェらは……揃いも揃って……!」
墜ちる。翼をもがれた鳥のように、少女は墜落する。ギアプラント争奪戦や先の艦隊攻撃であれだけの殺戮を行い、人を害虫のように潰していったはずのギアをやっと殺せたというのに、ソルの心はちっとも晴れやかにならない。
ソルには最早墜ちていく少女を憎めなかった。あれはアリアの娘だ。そして己の娘。一度も愛情一つ注いでやることが出来なかったのに、それでも、自分を父と呼んだ……。
無我夢中で手を伸ばすが、ディズィーが墜ちていく速度の方がどうしても早い。このままでは地上に衝突し、死体は肉片になり粉々に飛び散ってしまうだろう。この手で殺したのだ、生き返れなどという傲慢は言うまい。だがこれでは弔いさえ出来ない。
亡骸を抱き上げることさえ出来ないのは、何一つ親らしいことをしないまま娘を殺してしまった自分に相応しい末路ではあるのだろう。でもやっと親子に戻れたのだ。ディズィーは自分を父と認めて愛した。それに対する答えを、まだ出来ていないのに。
「畜生……!」
無理なのだろうか。これが、幻だとわかっていてそれに縋り続けた男への報いなのだろうか。本当に大切なものを見失い、漫然と十年の時間を使い果たした男への……裁きなのか。
ディズィーの肉体が、いよいよ地面に迫って行く。もう、間に合わない。ソルは愕然として目を瞑った。せめて、自分を父と呼んだ少女が肉片になって飛び散る瞬間だけは、見ないでいたかった。
……だけど、いつまで経っても、少女が潰れる音がソルの耳に届かない。
『——大丈夫ですよ、ソル』
肉が飛び散る音の代わりに、凛として透き通った少年の声が聞こえる。最早この世のどこにもあるはずのない誰かの声。ではこれは幻か? いつもの、脳が生んだ、記憶の中の想い出で構成された嘘っぱち。
いいや違う。はっきりとソルには分かる。幻の声はいつもソル=バッドガイを糾弾し、淀みきっていた。こんなふうに澄み渡る声は、十年前から一度も聞こえていない。
そのはずだ。
『ディズィーはここです。もしも神様があなたにお別れの言葉を言う時間もくれないのだとしても、私がそうはさせません』
恐る恐る目を見開くと、墜ちゆく少女の身体を、女神の手のひらがすくい上げているところだった。
ソルは言葉を失う。それは十年前まで戦場で度々目にした、「彼」の守護精霊だ。雷を操る少年が愛されていた、至高術式で呼び出される女神。
ソルが目に留めたことに気がつくと、空中で少女を抱きとめた女神がどこかへ目配せをする。思わずその視線を追った。心臓が早鐘を打っている。あまりに脈打つのが早いものだから、そのまま、人生に定められた鼓動の上限回数を使い切って、死んでしまうのではないだろうか、とさえ思う。
「カ……イ……?」
ソルは怯える子犬のようにその名前を呼んだ。
あの日喪ったはずのものが、寸分違わぬ姿で目の前に佇んでいた。震えながら絞り出した声はかすれている。ソルは尚もしつこく、それは己の脳が生み出した幻影ではないかと疑ったが、幾ら消えろと念じたところで女神を従えた少年は消えてなくならない。
『あなたを迎えに来ました、ソル』
喪われたはずの少年が手を差し出した。
この世から奪われたはずの子供——カイ=キスクが、慈母の如く柔らかな顔をしてソルを見ている。