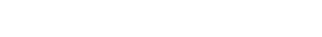14 世界の終わり、人の祈り
——世界はもうすぐ終わるよ。
現代最後の魔法使いは、謳うようにかたちなき亡霊の頬をなぞる。
人々の明日を生きたいという願いがいよいよ限界へ達した。明日を採択するため、この先行きのないどん詰まりの世界は廃棄される。だから未来へ生き残るため、僕は君に手を貸す。
そう言ってギアメーカーがカイの浮かばれぬ魂に輪郭を与えたのは、ディズィーがロザリオのお友達と出会う少し前のことだった。
「君に魔法を掛けてあげよう。これこそが〝僕〟に残された最後の役割。そして五年間、こんな場所でじっと蹲っていた理由でもある。さあ、君の魂の拘束は解かれた。お姫様を連れて行きなさい——カイ」
薄暗い地下牢の中で、鎖に繋がれた男が微笑む……そう、微笑んでいたのだ。カイは大変に驚き、疑いの眼差しを彼へ向けた。だってカイがディズィーの持つロザリオの中から覗き見た男は、いつも大体、人を人とも思わないような顔をしていたり、ディズィーの心をいたずらに傷つける酷いやつを体現したような表情ばかり浮かべていたのに。
でも男はそんな胡乱な眼差しなど気にも留めていなかったようで、幽霊になって永遠に年を取らなくなったカイの姿を慈しみの眼差しで眺めてはカイの手に触れた。驚いたことに、男の年老いはじめた指先はカイの質量がない手のひらを正確に捉えていた。幽霊に触れるだなんて! しかしカイがいくら疑念を深めて観察したところで、男が生者である事実は絶対のまま揺らがない。
そのことにカイが混乱で目を白黒させていると、男はなんだか奇妙なまでに優しく言葉を重ねる。
「だけどね——忘れてはいけないよ。魔法の効き目も、世界が終わる日までのカウントダウンも、とても短い。もし期日までに君がちゃんと死ねなければ、最悪、次の世界で君が目を醒ますことはもうないだろう」
『……ギアメーカー? それは一体、どういう……』
「世界は限りなく五分の詰みを迎えている。プラントを占領され、ヴァレンタインを一つ前の因果へと逃してもう五年近いんだ。ディズィーは大きくなり、世界は疲弊し、蓄積された願いはいよいよこの世界に魔器を生むだろう。それが終わりの合図だ。魔器はこの世全ての負債をリセットし、それが望む新しい世界を造る。歴史は巻き戻る。死者も生者も等しく、新しい演算の中でもう一度次の人生を繰り返す権利を得る。でも」
カイの手を握りしめたまま、ギアメーカーはゆるりと立ち上がる。目深に被っていたローブを脱ぎ捨て、カイの眼前に立つと彼はカイの頭を撫でた。ずっとこうすることが夢だったとばかりに、手つきは優しかった。
「何事にも例外はある。幽霊だけは、次の世界で目を醒ます権利を得ることが出来ない。だから君は魔器が世界を巻き戻すより早く、正しく死者になる必要があるんだ。
『……え? それじゃまさか……ソル……ソルは、私の死を認めていないというのですか。だから私は、今も成仏出来ずにこうして地上を彷徨っているのだと? ……そんな。嘘ですよね。だってもう、十年も経つのに……!』
「残念ながら本当のことだ。彼は今もって君の幻影と共に暮らしている。なお救われないことに、それが己の脳味噌が創り出したありもしない幻だと頭では理解しているのに」
告げられた内容に愕然とするカイを、ギアメーカーが抱きしめる。両腕が背中に回され、ぬくもりがじんわりとカイの身体を包む。誰かに抱きしめてもらうなんて、もう十年ぐらいなかったことだ。
だからだろうか。嬉しかった。相手は恋人でも友人でもなかったが、不思議とそれに嫌悪感はわいてこない。
『どうやら……私に断るという選択肢はないようですね』
カイは抱きすくめられたままふるりと首を振った。
世界が終わる。もう明日なんか来なくなる。それらの言葉が信用に値するかどうかを吟味する時間はなかったが、ソルがカイの死を未だ認められていないという言葉だけで、カイが決意をするのには十分だった。例え嘘でも、それを確かめる必要がカイにはある。
いやむしろ嘘ならそれでいい。あの男が、カイという少年を過ぎ去った思い出に出来ているのならば、それにこしたことはない。
だけどもしそうではなかったら。
ギアメーカーの言葉が本当だったら。
その方が、カイにとってはずっとずっと恐ろしいのだ。
カイは上目遣いで、幽霊を抱きしめている男の顔を覗き込んだ。プラントに監禁されて長い男の顔色はあまり良くなく、髪にもつやがない。色が落ち白くなったぼさぼさの髪や、栄養不足で歪んでいる顔からは、彼の元の面影を探ることも難しかった。だけど目の色だけは美しい。深いエメラルドグリーンの瞳。いつかどこかで、見たことがあるような。
『あなたは何故私に力を貸してくれるのですか、ギアメーカー。私が聞いた限りでは、あなたは最低のろくでなしで、自分さえよければそれでいいというような人だということだったんですけれど』
わりと厳しいことを訊ねた自覚はあったが、それを聞いたギアメーカーは面白そうにくすくすと笑うのみだった。
「……フレデリックから聞いたのかい? いやまったく、非道い話だな。まあ、でも、その怒りは甘んじて受け入れよう。同意を得る前に彼をギアに改造したのは〝私〟だからな。それで……僕が何故、君に魔法を掛け、短い奇跡を与えるのか、だけれど……」
そうして、ギアメーカーは慈愛に満ちた声音でカイの耳元に魔法の言葉を囁く。
『——ッ、……あなた、は……』
カイは金縛りにあったような気持ちになり、喉元にまでせり上がってきた言葉を手で押さえて堪えた。どうしてそんな言葉が出ようとしたのか、自分でもよくわからない。だって目の前の男はただの大罪人で、自分とは縁もゆかりもない、赤の他人でしかないはずなのに……
「簡単なことだ、カイ。僕は最後に彼と約束した、たった一つの願いを叶えたいんだよ」
だけどギアメーカーは、やはり微笑みをたたえたまま、カイの冷たい頬にキスをするのだ。
◇◆◇◆◇
『やっと会えましたね、ソル。ずっと会いたかった。あなたが私の死を認めていないと聞いてからは——特に。……お元気ですか、なんて言葉は、おかしいのかな。……なんだかうまく言葉が出てこなくて』
女神の手からディズィーの亡骸を受け取り、両腕で抱き抱えるとカイは物言わぬ少女の頬にキスをした。少女の顔に埋まる少年の頬を一筋の涙が伝う。——泣いているのか。ソルはぼんやりとそんなことを考えた。あの、上手に泣く方法を知らず、痛みさえ感じ取れない、神様が他の全てを与えた代わりに人間性を失ってしまった人形みたいだった、カイが。
『ごめんなさい、ディズィー。私は……私は、もっとあなたに……生きていて欲しかったけれど。でもこれがあなたの思い描いた最も幸福な結末だということも、理解出来てしまったんです。……こうでもしなければ、本当の本当には、人間になれなかったなんて。私達は……悲しいところばかり、よく似ていましたね』
顔を上げたカイの頬には涙に濡れた跡がくっきりと残り、瞳は潤んでいる。知っているのか? ディズィーのことを? 不思議とそのことはすぐに納得が出来た。父親失格のソルより、カイみたいな他人を思うことに魂を磨り減らすような人間が少女と親しくしている方が、よほど健全に思えた。
「今まで……何をしていた」
『十年ほど、幽霊を』
「馬鹿言え。俺に霊感なんざねえよ。……生きていたのか? そうだと……言ってくれ……」
『いいえ、ソル。私は死者です。そうでなければ、ただの人間である私は十年前と同じ姿でここにいない』
宙に浮かぶ少年はふわりと歩を進め、ソルの方へ歩み寄る。ソルは思わずカイに手を伸ばした。彼の頬を撫でようとした指先は肉の中にすうと吸い込まれ、空虚の海の中を泳ぐ。
『ね? だから触れないでしょう? だってソルはまだ生きているから』
骸になった娘を抱き抱えたまま少年は眼を細めた。
そこにあるはずのものに触れられないという事実は、思いの外強力にソルを追い詰める。十年間飼い続けていた幻にも触れられなかったが、でもあれは、偽物にすぎないと脳で理解していた。だから仕方ない。だけど今目の前にいるカイはソルが生み出した幻とは違う。本物なのだ。本物なのに触れられないというのは……それはもう、ソルが目を背け続けてきた事実の証明に他ならなくて。
ディズィーを抱き抱えていられるのを理由に追い縋っても、彼はきっと、最早彼女が死者になってしまったから可能なだけだと告げるだろう。カイの考えることの半分ぐらいは、ソルにだって分かる。彼を人間にしたのはソルだったのだから。
ソルは半ば敗北したような心地で悪態を吐いた。
「ああ……くそ。テメェが幽霊だとして……今更、何しに来た。来るならもっとさっさと俺にとどめを刺しに来いよ。何故……こんな、誰も後に引けないような、どん底の世界になってからのこのこと」
『今この瞬間が、世界の終わりだからです。ギアメーカーは終わりの瞬間ぎりぎりまで準備が必要だった、と言っていました』
「は……? ギアメーカー? 野郎、まだ生きてやがったのか。だが……テメェとヤツの間には、何の関わりもねえだろう、坊や」
『まあ、色々あったんです。あの人は——飛鳥=R=クロイツは、莫大な代償を支払い、彼の息子の望みを叶えようとしました。私に手を貸し、ソルともう一度だけ引き合わせようとしたのも、その一環です』
触れられない頬をソルの方へすり寄せてカイが淡々と告げる。飛鳥=R=クロイツ、確かにそれは、ギアメーカーの本当の名前だ。ソルがフレデリックという名を捨てて以来、もう二度と聞くこともないと思っていた文字の並びだった。それにしても、奴に息子が? そんな話は聞いたこともない。だがもう百年も会っていないのだから、そういうものが出来ていてもおかしくはない。
ソルはまじまじと眼前に浮かんでいる少年の顔を見つめた。深い海の色をしたその瞳の面影を、昔にもどこかで見かけた気がする。
『私も最初は半信半疑でしたけれど、彼の願いを叶えたいという思いはちょっとびっくりするぐらい純粋で、純真で、穢れのないものでした。思えばあの人は最低の父親でしたが——五千百八十九兆六百五十二億千九百八十二回の生の中で、いつも——でも五千百八十九兆六百五十二億千九百八十三回目だけは、ちょっとだけ、認識を改めてあげないといけないな。五千百八十九兆六百五十二億千九百八十四回目では、もう私達はその全てを失い、今度こそ赤の他人になっているのでしょうが』
「何の話をしている」
『魔法の代償を支払い続けるひとたちの話ですよ。……ねえ、ソル』
よく動くカイの唇は、あの花が咲いたような紅色ではなく、どこか青ざめて冷たい。それらの、彼をじっと見つめると出てくる一つ一つの要素が、カイ=キスクという少年の死を、色濃くソルに印象づけようとしている。
『昔私が言ったこと、覚えていますか? 神様は、死ななくちゃいけない、という話。私達が信じる限り神は存在する。でも、神の実在と存続は実はまったくの別で……人が踏みしめた足で明日を目指すためには、存在していても、実在してはいけないんです。現人神なんてどこにもいません。神の子も。少なくとも今はもう』
縋ってきたものが、足下で音を立てて瓦解していく。幻が幾度言い含めても耳に入ってこなかった言葉が、身体中の血管を這いずり回って心房へ入り込もうとする。本物のカイ=キスクは、いつもこうしてソルを動かしてしまう。ソルは首を振った。自分に嘘を吐き続けることが、これ以上はもう出来ない。
ああこれは、確かに、あの日失ってあの日々の中で愛した少年なのだ。ソルは顔を覆ってカイから目を逸らした。泣きたい気持ちでいっぱいだったけれど、ディズィーのために涙を流した少年とは違い、人でなしの男は、一滴たりとも泣けそうになかった。
『神様はいないんです。もう、死んでいなければいけなかった』
「なら……俺に何を望む、坊や」
『今度こそ——ちゃんと私を殺してください、ソル』
震え声の問いかけに、幽霊が懇願した。
心臓を抉り、臓腑をすりつぶし、脳髄を啜り、その果てに私を殺して、と言われているみたいな気分だった。
「テメェもそれを言うのか、カイ」
『ええ。私だからこそ、言います。……知らないでしょうけれど、あなたはこれまで、五千百八十九兆六百五十二億千九百八十二回にわたって私を一度たりとも殺してくれなかった。だけど今度だけは、ソルが私を殺さなければいけないんです。どうか私を殺して、ソル。これはナイフのいらない殺人です。ごく単純な、あなたの認識における、私という魂の殺害。だけど気に病むことはありません。あなたがそれによって罪を重ねることはない。それで私は、ようやく救われる』
「俺には出来ねえよ」
『いいえ。ソルにしか出来ないんです』
乾いてひりつく喉で生唾を飲む。本当は分かっている。カイの言葉は実に正しい。正しいことしか並んでいないから、こんなにも気が狂いそうな気持ちになる。
既にソルは半分、カイを殺している。ソルはカイの墓を建てた。墓を建て、花を供え、死を悼む真似を十年欠かさなかった。ソルの抱くカイの死体にはもう半分ナイフが突き刺さっていた。このナイフを抜けば、カイは死ぬ。完膚無きまでに。恨み言一つ残さず安らかに。
だけどそうはしなかった。出来なかったのだ。彼を殺すなんてとんでもなかった。死体を抱いていれば、いつまでもカイはソルの傍らにいてくれる。どこへもいなくなったりしない。大人になり、ソルを置いて、消えてなくならない。
ソルは一人になるのが怖かったのだ。
もう何も大切なものを作るつもりはなかったのに、それでも愛してしまったものに、今度こそ置いていかれたと認めたら……もう生きてはいられなかった。
『大丈夫です。言ったでしょう? ソル。私は迎えに来たのだ、と』
だけどそんな葛藤を全て見透かしたかのように、カイが優しい言葉を重ねる。ああ、と呻き、ソルはカイの頬に手を伸ばした。今度は、指先が皮膚の向こうへ沈み込むことなく、彼の柔らかな肌の感触が手のひらに残った。
幽霊が微笑む。
『一緒にいきましょう、ソル。私はあなたを離しません。あなたが、私を忘れなかったように』
ソルはぼんやりとカイの愛らしい相貌を眺め見た。それがテメェの答えか、坊や。いつまで経ってもナイフを抜かない男に、カイの死を認めさせる方法。こんな土壇場で……いやこの間際だからこそ、使えた選択肢。
あのギアメーカーが吹き込みそうな手段だ。だけどギアメーカーも、カイも、責める気にはなれない。選択を先延ばしにしたソル自身、心のどこかでこういう答えを望んでいたのではないかという気持ちを否定出来なかったのだ。
「そうか。そういう……ことか……」
『はい』
ソルは娘を抱き抱えた少年を、二人丸ごと抱きしめた。
『だから——きっと次の世界でも、私達は……』
華奢な身体は今にも音を立てて折れてしまいそうなほど細いし、冷たくて、温度がない。その氷のような冷たさがソルの心臓を、喉元に埋められた種子を、全てを貫いて連れて行ってくれるのだとすぐに分かる。
それなら……もう、いいのかもしれない。
孤独に怯えて空虚な年月を過ごすこともなく、一つの答えとしての永遠をさえ手に入れられるのなら。
もう十分罰を受けたのだ。
「テメェが俺の死神か、カイ」
こういう終わりがあったとしても、ソルの神は許してくれるだろう。
ソルはゆるやかに目を閉じた。伏せられた瞼の裏に走馬燈が走る。愛を知らないと言った男の子。私が死んでも気に病まないでと馬鹿正直な面をして言い切ったその面影に、いつかどこかで見たはずの、私は父の代替品ではない、と喚いた少年の姿が被る。
一人の人間として愛されたかったと言い残して逝った男の子と。
あなたに貰った愛を返すと墓の中から手を差し伸べた男の子と。
一度くらい父親らしいことをしてやりたい、と言ったあのエゴイスト。
「は……馬鹿親子が」
落ちていく意識の中で口を突いて出た言葉は、ソルが自覚した中で一番優しい、甘ったるい声音をしている。馬鹿だな。本当に、みんな、みんな大馬鹿者だ。そのせいで正しい答えを選ぶまでにこんなに時間が掛かってしまった。
でもたくさん回り道をしたから、次はきっと間違わないですむだろう。
「もう二度とあんなのはご免だからな、俺は」
記憶が光の欠片になって剥離していく。因果律干渉体が時を巻き戻し、過去の事象を改変しているのだ。過去に起きた五千百八十九兆六百五十二億千九百八十二回のループと同じように、五千百八十九兆六百五十二億千九百八十三回目の歴史もそうして闇に葬られる。あるべきことも起こるべきではなかったことも等しく奔流の中に奪い取られる。
ソルは目を瞑ったまま手と手を合わせた。記憶が消え、全てがなかったことにされても、残るものがあるというのなら、ソルにも一つだけ残したいものがある。祈りだ。誰かを思う美しい願いの気持ち。それも、世界を救ってくださいだとか、そんな大それたことではなくもっと小さな……。
誰にも聞かれない祈りだからこそ、ソルは飾りっ気のない夢を希う。
——今度こそ、あの誰より世界の平和を願った少年が、幸せになれますように。
/リバース・ブラック END