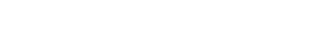15 幸せの青い鳥
「オヤジィ、こんなとこにさあ、何があるって言うんだよ。森じゃん。見渡す限り一面、ただの真緑。なんもねえって、マジ、ほんと」
「うるせえ、黙って歩け」
「やだよオレ腹減ったもん! カイにダメって言われてるのに野ウサギに手ェ出しちまいそう。なんでこの森カンサツホゴクイキとかいう場所なんだよ」
深い森の中を黙々と歩き続けて数時間、流石に限界を迎えてしまい、シンがぶちぶちと文句を垂れ流す。だが急ぎの行程なので、シンの気疲れに付き合って休憩を取っている時間はない。ソルは答えられる部分にだけ返事をしてやり、肩をすくめる。
「なんで観察保護区域かって聞かれると、まあ、そりゃカイが連王になったあとに制定したからだな」
「マジ? ええ……なんで? 見たところさあ……フツーの森だろ。特殊な生態系ってワケでもない。フツーの動物がフツーに暮らしてる。なのに……」
「いいから黙って付いてこい。奥まで行きゃ、わけがわかる。ついでに要求すれば腹を満たすもんも出てくるだろ……多分」
グルメ向きかは知らねえがな、と前置いてソルはシンを宥めた。
ソルとて、用がなければ——用があっても——極力こんな場所には近づきたくない。ここにはあの男が住んでいて、そしてある人物の墓がある。ディズィーを巡る騒動で何度か訪れたが、それっきり、もう二度と拝むことはないと思っていた場所だ。
悪魔の棲む森。それが、カイがこの森を「ウェストモ−ランド観察保護区域」という名で法律に定める前まで、まことしやかに囁かれていた通り名だった。カイが突然ここを指定地にした理由など、推してはかるまでもない。妻の故郷と、そこに未だ住む一人のギアを俗世から保護したかったから以外に理由などなかろう。
好き放題に生い茂った木々を掻き分け、奥地にある小屋を目指す。数年前、五十万ワールドドルの賞金を掛けられていたディズィーはここで外界の全てを拒絶していた。賞金稼ぎとして高額案件には手を出しておこうと出て行ったソルがそこで見たのは、無様に倒れて意識を失っているカイと、火の付いた破壊衝動が抑えきれずに叫ぶディズィーの姿だった。
その後ディズィーはとりあえず叩きのめし、カイには治癒を施し、よく見たら隅の方で伸びていたテスタメントを放置し、ソルは不可思議な感覚を胸に森を後にする。今思えばそれは、ある一種の共鳴反応だったのかもしれないが……とにかく、今重要なのはそういった思い出でなければディズィーでもカイでもない。音信不通になって長いテスタメントの方だ。
聖皇アリエルスの居場所が判明し、そこまでの足を確保しようとしたところ、ジョニーが取引を持ちかけてきた。ここしばらく森に寄る余裕もなく、また、定期的に取っていた連絡もうまくつかなくなっている。船は出してもいい、だからその代わりに——というのが彼の打診内容。作戦の立案をしていたカイとあの男達は彼の打診を呑み、魔の森へ人を派遣することに決定する。
場所柄、本来ならディズィーを連れて行くべきなのだろうが、長い封印状態から目を醒ましたばかりの彼女に負担を掛けたくない。カイは当然城を動けない。あの男が行ったら戦争が起きる。そういうわけで、お鉢がソルとシンに回ってきたというわけだ。
幸か不幸かあの男が諸準備をしている必要時間内に片が付く内容だったので、断り切ることも出来ない。渋々魔の森方面へ足を伸ばすことになったのだが、森の奥地というのは記憶にあるより遙かにへんぴな場所で、ソルは内心げっそりしていた。ジョニーはよくこんな場所に通っていたものだ。
いくら歩いただろうか、ようやく茂みの向こうに光が見え、強引に掻き分けて前へ進む。急激に視界が開けたかと思うと、妙に生活臭のある小屋と小さな畑が姿を現した。しかし表に生物の気配はない。シンに手招きをし、小屋の裏手に回ると、そこにようやく尋ね人の姿が見つかる。
「ったく、手間掛けさせやがって……」
ソルは息を吐いた。裏手の小さな墓の前に、手を合わせて祈る黒髪の男が蹲っていた。
「——その無粋な声、背徳の炎、貴様か。貴様と話す事など何も無い」
「俺にはあるんだよ。でなけりゃこんなところまでわざわざ来るか。ジョニーの野郎がテメェの安否確認を交換条件に出して来やがった。ヤツもここのところはクルーの娘が抱える病状に掛かりっきりだったからな」
ソルの声に気がつき、立ち上がってこちらを向いたテスタメントの顔はあからさまに不機嫌そうに歪んでいる。ソルの方はとんと心当たりがないが、テスタメントは異様にソルを嫌っているのだ。彼のソル嫌いはきっと永遠に治らないだろう。
「今日この日が父の命日だと知って来たのなら、とんだ命知らずだな。ジョニーの頼みでなければ多めには見なかったものを……いや、待て」
テスタメントは憎々しげにソルを睨み、ぶつぶつ悪態を吐く。しかしそのうちにソルが連れているシンの姿に気がついたらしく、彼の声色は次第に怪訝なものに変わっていった。
「その後ろの子供は何だ。あの姦しい小僧に似ているが」
「それ、オレも聞きたいっていうか……オヤジ、こいつ誰?」
「お、オヤジ……? 背徳の炎、貴様まさか……いや、とうとうと言うべきか……」
「違ぇよ。ディズィーの子供だ。今年で六つになる」
盛大な溜め息と共にソルが告げると、テスタメントは真っ青になって震える指先を恐る恐るシンの方へ持ち上げる。まさか……知らなかったのか? あのカイとディズィーのことだ、こういう事の報告ぐらいはしているだろうとたかをくくっていたのだが。いやしかしシンが出来た時の二人は焦燥しきっていた。結婚報告まではしていても、その先は手が回っていなかったのかもしれない。
「子供……? ディズィーの? どこも似ていないではないか。……いや……確かに……よく見れば目元がうり二つで……」
「ええ……。オレ確かにカイに似てるってよく言われるけど、カイはオレのこと母さん似だって言うぜ。それよかオヤジ、こいつの安否確認が用事なら、もうやること済んだだろ! 帰るか飯か、どっちか早く……あだっ!?」
認めたくない現実に自問自答を始めたテスタメントを横目に唇を尖らせはじめたシンに、ソルの拳骨が落ちた。途端に頭を抱えてさすり始めたシンに、ソルが無言で墓の方を指し示す。
「墓参りも用事ってこと?」
「ああ」
ソルが小さく頷くと、シンはまだ納得いかないという様子で引き下がる。
「……誰の墓?」
「読んでみろ」
そこまで言われると反発が出来なくなり、シンは墓石に歩み寄り、文字に目を走らせた。K、L、I、F、F……クリフ・アンダーソン。二一八〇年没。
名前を読み上げて顔を上げると、ソルがふんと鼻を鳴らす。
「カイの……まあ、じーさんみたいなもんだ。十歳のカイを拾って育てた。森に行くならついでに手を合わせてきてくれ、とテメェの親父のご要望だ。たまには親孝行でもしとけ」
「オレ、いつも親孝行して……うわ、わ、わかった。わかった手合わせる。……それでいいんだよな?」
「ああ」
ソルの視線にびくりと肩を跳ね上がらせ、シンはしゃがみ込むと墓を正面に据えて両手を合わせた。いつも首から提げている十字架が合わせて揺れる。
小さい頃母親に教えられたものをしっかり覚えているのか、祈りの手つきは思いの外確かだ。その後ろで、ソルも手を合わせる。こちらはあまり教義に則ったものではなかったが、それでもソルが何かに手を合わせるだけで一大事である。
流石に異様な光景だと感じたのか、テスタメントが驚きを隠しもせず口を開いた。
「貴様が墓に手を合わせることがあるとはな、背徳の炎」
「ほざけ。テメェ俺をなんだと思ってやがる?」
「……いや。あの日……父に引導を渡したのは殆ど私のようなものだ。その私が墓を作っていることを咎めず、そこに同じように祈るような心が、貴様にもあったのかと」
祈りを解き振り返ったソルに、テスタメントはばつ悪く言葉を濁す。第二次聖騎士団選抜武道大会で暗躍し、己を支配する指令のままジャスティス復活の儀を執り行おうとしたテスタメントを阻むため、引退したはずのクリフも老体を引きずって大会に出場した。直接とどめを刺したわけではなくとも、クリフの死期を早めたのは確かにテスタメントだ。
だがその後、自我を完全に取り戻したテスタメント自身がそのことを一番引きずっているだろうことはソルでもわかる。それにあの時蘇ったジャスティスが全盛期の姿に比べて異常に弱かったのは、支配されている状態でも彼に父を思う心があったからなのだ——とはカイの受け売りだが、とかく、そういう『人間』に対して追い打ちを掛けようというほどソルも性悪ではない。
首を振り、ソルはひらりと手の平を返した。
「……子は、親を悼むもんだろ。逆も然り、それが友や恋人であってもまた然り、だ。俺はテメェが死んだと思って毎年手を合わせていた頃の爺さんを知ってる。人間であるために必要なサイクルなんだよ、それは。……まあ度が過ぎりゃ、毒になるがな」
「貴様にしてはえらく含蓄のある言葉ではないか」
「うるせえ」
ぶっきらぼうに吐き捨て、ソルはぼりぼりと顔を掻いた。今度こそ、ジャスティスを仕留めなければならない。そしてそこからアリアを引きずり出す。ギアメーカーは、アリアは人に戻せる、と言った。そこに縋る自分をあの老人は笑うだろうか。笑わないでくれよ、とソルは独りごちる。悪友の一人となり、ソルを先に置いていった老人がいつかソルに掛けた言葉を思い出して。
——わしはもう後がない。お前さん、カイのことは全部任せたからな。
——ま、そのうちカイの方がお前さんの世話を始めるかもしれんがな……
「は、縁起でもねえな」
覚悟を決めなければいけない。ソルは唇の端で小さく笑った。覚悟の内容は簡潔だ。世界を救い、願いを叶え、今度こそ全てを取り戻す。
それだけだ。
◇◆◇◆◇
「やっほー! どうどう? 元気してる?」
「えっ? あ、うわ、びっくりした。ジャック・オーさんですか。どうかなさいましたか」
突然、後ろからぽんと肩を叩かれた。扉が開いた気配は感じなかったが、仕事に打ち込みすぎて気がつかなかったのだろうか。
振り向いて訊ねると、ジャック・オーはやや意表を突かれたような顔をして、ぱちくりと瞬きをして見せた。
「あら、動じないのね……。流石、高学歴高収入高身長の男は違うってことかしら……」
「ええと……なんでしょう? それ」
「昔の言葉よ。もてる男は三高って言われてた頃が、あったのよね……」
「はあ……そうなんですか」
そうそう、と元気よく答えてジャック・オーはぱっと明るい表情を形作る。ソルが捕獲してきた直後はまだコアダンプからのメモリーインストールが中途半端で、大人と子供の間を忙しなく行き来していることが多かったが、ギアメーカーがこちら側の作戦に合流する頃にはそういうことも減ってきた。今は大体、大人の人格で固定されている。その方がカイとしても接しやすいので助かるのだが、ギアメーカーの持つ技術の高さには驚かされてばかりだ。
「身体の具合はどうですか? 私は政務がありますから、作戦の詳細はギアメーカーに任せきりで……申し訳ありません。何か私にご用でしょうか」
「ううん、平気よ。彼、ずーっと一人でやりくりしてた人だから、慣れてるの、そういうのは。今はザッパくんっていう助手も確保出来てる状態だし。それに……あなたは多分手伝わない方がいいわ。前話した限りだと、ちょっとあなたには、思うところもあるみたいだから」
「え、私に? ギアメーカーが? ……ソルに、ではなく」
「まあ、ほら、あなたはソル=バッドガイの親友、でしょ。彼はフレデリックの親友だったから。あとは……少し、本人にもわからない感覚としてのものかな。
……それより、ディズィーは? うーんと、あの子は私の本来の意味での娘みたいなものだし。出来れば、話をしておきたいんだけど」
「ああ……あなたのオリジナルが、ジャスティスの素体となった女性なのですよね。ディズィーもそのことは随分と気に掛けていました。彼女なら、奥離宮の方ですよ。居住エリアで家のことをしてくれている時間でしょう」
「離宮! やだ、バブリー。王様ってすごいわね。あら、でも、一人で待たせてるの?」
「シンもソルも、今はちょっと忙しいですからね。仕方ありませんよ」
「ふうん。そしてあなたは年中ご多忙、ということね。なるほど……なら、私がそちらに行っても構わないかしら?」
含みのある言葉を投げかけ、ジャック・オーがカイに問う。実質的にディズィーの母と言える存在であるジャック・オーは、言うなればカイにとっては姑だ。定義的には生まれきっていなくとも、人格や知能は立派な大人のそれ。一人家族の帰りを待つディズィーにとっても、有意義な時間になるに違いない。
カイは頷き、案内を呼ぶためのコールを入れた。
「ええ、勿論です。そこまでの案内は執事に任せましょう」
◇◆◇◆◇
「お母さん」という生き物は、私にとって、「お父さん」よりもっと遠い存在だった。何故なら私は「お母さん」が死んでいることを知っていたから。おじいちゃんとおばあちゃんに育てられ、それから二人と別れて森の奥に暮らすようになり、テスタメントさんが私を守るためにやって来た頃には……もう、そのことを理解していた。
「お母さん」はギアの司令塔だった。人類殲滅の旗頭として、ギア達を操り、人間を殺した。ソルさんやカイさんは人類守護を掲げた聖騎士団の一員としてその蹂躙に抗い、百年にわたる聖戦はソルさんが「お母さん」を殺して終結する。これが私の知っている、この世界の歴史だ。
ソルさんが——たぶん、私のお父さんなんだろうということは、あの人が魔の森にやって来た時に薄々勘付いていて、以来幾度となく目を掛けてくれるようになって確信に変わった。基本的に他人に関わろうとしないソルさんが目を掛けるのは、子供の頃に一緒だったらしいカイさんを除けば殆ど私だけだった。同じギアだから……というだけの理由であの人は他人に干渉しない。だから私は、私達の間に、もっと深い結びつきがあると信じたのだ。
「母親が恋しいのか」
一度、ソルさんが私にそう尋ねたことがある。
母親が恋しいか。例えそれが理性を失ったギアの獣でも。その母親を——ジャスティスを殺した自分が、憎くはないのか、と。
私はそれに首を振った。ソルさんはびっくりしていたみたいだったけれど、「いいえ」しか彼に渡せる答えはなかった。
だってお母さんは、きっと私のお父さんである人を愛していて。
そのお父さんや、お父さんが守ろうとした世界を傷つけることは、本当は望んでいなかったはずだから。
だからソルさんはお母さんを救ってくれたのだと思う、と返すとソルさんはもっと不可解そうな顔をして、そうか、と照れくさそうに額をぽりぽり掻いてみせた。この人は自分のことをしょっちゅう人でなしのように扱いたがるけれど、本当はすごく人間くさい男なのだ、とカイさんが言っていた言葉を思い出した。とにかく、不器用なひとなのだ。だから私はソルさんがお父さんで良かったなあと思う。
カイさんには、そのことはまだ言っていないけれど。
だって(不思議なことに)ソルさんが私のお父さんだと気がついていないらしいあの人にそれを耳打ちしたりなんかしたら、きっと三日ぐらい、ベッドの奥に潜り込んで出て来なくなってしまいそうだもの。
……遠い存在であるはずの「お母さん」が私の前に姿を現したのは、そんなふうに、過去の記憶を反芻していた時のことだった。
「こんにちは。あなたの旦那様に、話をしてきて良いって言われたものだから、来ちゃった。……いいかしら?」
急な来客。カイさんの執事であるベルナルドさんが招いた客人は、そう言ってにっこり微笑むと私が座っているソファの隣を見遣る。はい、と答えると彼女はすとんとソファに収まった。どこか緊張しているみたいで、すらすら出てくる言葉とは裏腹に動作はぎこちない。
「……私は……」
「カイさんから、聞いています。ジャック・オーさん、ですよね。『あの男』さんの側近で……『お母さん』をひとに戻すための存在なんだって。……私、こうも聞きました。あなたは私の『お母さん』の記憶を持っている。つまり、あなたは、私の……」
「ええ、まあ、そうなるのかしらね。私の中にはアリアの記憶がある。アリアの体験が……アリアが抱いた感情の残滓が。だから、あなたに会いたかったの。……会って、何か劇的なことが起こるってわけじゃ、ないんだけど」
ジャック・オーさんは、やや俯きがちにもじもじとそう告げる。彼女は何かタイミングをはかっているふうだった。胸の内に抱えた秘密を、どの瞬間に詳らかにすれば、出来るだけ私を驚かせないで済むのか考えあぐねているかのような……。
「それでも、どうしても話したいことがあったの。だからここへ来たわ。あなただけに話しておきたいことが、そこそこ……たくさん。たとえばそれは、
細い指先が私の手を握りしめる。これが、お母さんの指先なんだろうか? 私が森にいる頃に度々出会ったお母さんの姿をしたもの——ジャスティスの模造品は、人の身体を持っていなかった。指先は細くなく、人の肌色をしておらず、だから私は、もう自分が母親になったというのに、今の今までお母さんの指先というものを知らないのだ。
人の形をした指先は温かい。ソルさんがいつか私に触れてくれた時の指先と、同じように……。
「ねえ、ディズィー。貴方は今、幸せ?」
ジャック・オーさんが私に訊ねる。
こわごわと、でもはっきりと私の目を見て、もしかしたら——何かを、恐れているかのように。