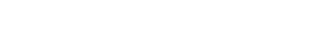16 キスと素敵なもの、私達の世界
レイヴンに連れ戻され、目が醒めてすぐ、自我の確立と共に訪れたのは寂寞。「生まれきっていない」身体にインストールされた大量の情報。バックヤードに接続され、直にインストールされた「アリア」という女の記憶、体験としての感情、それから——消えていった、無数の——五千百八十九兆六百五十二億千九百八十三回ぶんの、世界のログ。
目覚めた私に彼は言った。おかえり。それは、私の中にインストールされたアリアのデータによれば、「いい天気だね、コーヒーでも飲む?」と提案する時の彼のものと、九十八パーセントの様相で酷似していた。
「うん、ただいま。いい天気ね。コーヒー、ある?」
だからそう答えると、彼はその一言だけで全てを察したようで、わかった、コーヒーを入れるね、と言ってレイヴンを伴い少しだけどこかに消えてしまう。後から、コーヒーを作成するためにわざわざラボに向かったのだとわかった。だってここにはコーヒーメーカーがない。この場所は世界の墓場。死んだ世界の残骸が積み上がる場所。有り得た世界の墓、ヘヴンズ・エッジ。まるで死者の霊魂のように浮かび上がるそれらのレコードに触れると、私は不思議と安心する。それは私がユノの天秤を持っているからなのだろうか? それとも……私が、託された者だから?
アリアの記憶と共に、私は無数の壊れた世界の欠片に触れた。五千百八十九兆六百五十二億千九百八十三通りの世界の終わり方をつぶさに観察した。その中で五千百八十九兆六百五十二億千九百八十三通りの少年の死を観た。金髪の小さな男の子、その子が息絶えると、世界にもまた終わりが訪れた。
私は、アリアの記憶の中から、セラフィムの姿を思い描く。
「……こういうのを、人間は、皮肉って言うのかしら」
恋しいひとに殺してもらいたくて、でも五千百八十九兆六百五十二億千九百八十二回も叶わなくて、その度自分の息の根を止めた男の子のことを思うと、私は会ったこともないのに胸が締め付けられるような気持ちになって、かぶりを振る。私の中にあるアリアの記憶が、どうしようもない感情をロードして、私の中に再現する。恋人に殺してもらえなかったアリア。一人生き延びる未来をあれほど恐れていたのに、殺してと頼んだ恋人の手で永久を与えられたアリア。わたし、永遠に、あなたのことを恨むわ。そう言ってフレデリックを呪ったことさえある、いつかのアリア。
だけど私は——アリアの記憶を客観的に受け継ぐ第三者である私は、その先にあるものも正確に理解している。アリアは普通の女の子だった。恋人を失いたくない、一緒に年を取りたい、それぐらいのありふれた願いを抱くような、ふつうの女の子。そのためにフレデリックを呪った。彼を呪うことで、彼は、彼女だけのものになると信じた。奇しくも、呪われている限り自分はアリアの中で永遠になれると信じていたフレデリックのように。
だから、フレデリックは、アリアしか愛せなかった。
彼が他の誰かを愛するには、フレデリックではない、新しい自分になる必要があったのだ。
「不器用なひと……」
不器用な人。誰も、彼も、みんな。五千百八十九兆六百五十二億千九百八十二回の繰り返しの中で、人は不器用さゆえに、同じ結末しか選べなかった。男の子は世界に耐えられず、数え切れないぐらい自分を殺した。フレデリックは己を呪い、アリアは恋人を呪い、飛鳥は、自分の持つ愛を歪んだ形で放置した。堂々巡りが続いて、世界に限界が来る頃になって、ようやく、一人が真実に気がつく。
五千百八十九兆六百五十二億千九百八十三回目の世界で、ヴァレンタインを過去のループに送ろうと提案したのは、本当は飛鳥じゃない。アリアだ。もしくは、私の口を借りたアリアの記憶と言った方が、正しいのか。
アリアも不器用な人間の一人だったけど、彼女は決して、飛鳥やフレデリックほどの自己中心的なエゴイズムを持ち合わせていなかった。むしろ彼女はいつも自己犠牲的だった。だから彼女は、大切な人のために、身勝手に、崖から飛び降りてしまえるような豪胆さを発揮しようとした。
世界を救ったのは、たとえば飛鳥のひとかけらの親としての愛や、カイ=キスクの祈りだったのかもしれない。けれど、その一番最初の切っ掛けは、アリアの願いだったのだ。
彼女は自分が愛した世界が幸福に続くことを望んだ。その礎に己が使われることを承知した。それでも最後の世界で自分が発狂に耐えられないことも理解して、五千百八十九兆六百五十二億千九百八十四回目の歴史を選び取るため、私というヴァレンタインを用い、記憶と蓄積された思考パターンから、私と飛鳥を操作した。
「やあ、ごめん、ちょっとコーヒーを入れるのに手間取ってしまって。はい、どうぞ。アリアはいつもクリームたっぷりだったから、同じように作っておいたよ。……あれ?」
戻って来た彼が、私の顔を覗き込んで首を傾げる。そばに控えるレイヴンも、へんな顔をした。どうして? 私は彼からコーヒーマグを受け取り、口に含む。コーヒーは甘ったるい。クリームも砂糖もこれでもかというほど入っている。
なのに、ほんの少し、甘じょっぱい。
「泣いているのかい、ジャック・オー。何か辛い記憶でも観たかな。バックヤードに格納しておいたアリアの記憶と、その魂の半分を入れ込んだからね。……覚えていたくなかったものを、ロードしてしまったのか」
彼は私を気遣うようにして前屈みになる。ああ、そうなの。このコーヒーが甘じょっぱいのは、私が流す、涙のせいなのね。
「泣いてる……泣いているの、私」
「うん、僕が見た限りでは。……何が観えた?」
「世界を救おうと、奔走した人達、かな。膨大な罪の負債を返済するために、また別の、悲しい道を歩んだ人達も。……ねえ、ギアメーカー。私、気になった子がいるの。彼よ。さっき、フレデリックと一緒にいた男の子の……父親。ええと……イリュリア連王国の、第一連王、かしら?」
「ああ、彼。フレデリックの新しい友人だな。その彼が何か」
「うん。……あなたが、彼のことをどう捉えているのか、それが知りたい」
尋ねると彼はぽかんとして、おや、なんて間の抜けた声を漏らした。
放棄され、廃棄処分になった世界の中で飛鳥はいつもその子の父親だった。ろくでなしで、親でなしで、子供の幸せより自分の欲求を優先してばかりだったけれど、でも歪な形で、飛鳥は息子のことを愛していた。五千百八十九兆六百五十二億千九百八十四回目の今も、二人が親子なのかどうか私にはわからない。与えられた情報から、少なくとも二人がお互いを意識していないことはわかるけれど、そこから踏み込んだ先は知り得ない。
だから気になったのだ。ねえ飛鳥、フレデリックは——その名前を仕舞ってソル=バッドガイになった彼は、あなたより多分あの子のことを見ているわ。そのことに、きっとあなたは気がついているのよね。いつもフレデリックに見ていてもらいたがったあなたは、それで……大丈夫なの。
けれど私の不安とは裏腹に、彼は穏やかな表情のまま唇を開く。
「彼は……そうだな。僕に似ている、と思うよ。だってフレデリックの友人をやっているんだから。僕が言うのもなんだけど、フレデリックはちょっと奇天烈なところがあるからな。上手く付き合っていくには、付き合う側もある程度風変わりな必要がある。そういう意味で、僕と彼とは多分波長が近いだろうね」
「……似てる? そう……かしら?」
「多分。顔とか、声とか、そういう部分じゃなくて内面の……根源とでも言うべき部分が。きっとものすごくどうしようもないところが、どうしようもないぐらい、はっきりと、相似しているはずだ。ひょっとすると、親と子の相伝みたいに」
「親子……」
「あ、別に、僕は彼の父親じゃないというか……誰の父親でもないんだけど、なんとなく。これで疑問は氷塊したかな」
彼が微笑む。私はそうね、ありがとう、と頷いてまたコーヒーに口を付けた。聞くまでもないことを訊いてしまったことに、ちょっとだけ恥ずかしくなって、疑問符を浮かべているレイヴンやにこにこ笑っている彼から目を逸らす。
そっか。あなたはずっと、そういう人だったわよね、飛鳥。私の中のアリアの記憶がそう言っている。五千百八十九兆六百五十二億千九百八十三回死んだところで、その性質は変わりようがないのだ。あなたは永遠にそういう人。未来永劫——不器用な男。
だからきっと、フレデリックは、飛鳥という存在を……あの日信じたのだ。
◇◆◇◆◇
「あれ? 随分早かったな。それでどうだった、彼は」
「ぴんぴんしてやがる。まあありゃ、単に出不精してるだけだ。ディズィーに手紙を出さなくなった煽りだな」
「そうか、それは良かった。ディズィーも安心するだろう。これで足も確保出来たことだし」
シンを置いて執務室に戻ると、カイは例の「ケツが固くなる椅子」に腰掛けて書類仕事を進めている最中だった。許可を取るより早くソファに沈み込み、ひとしきり首を回す。なんだか非常に疲れた。かなりの強行スケジュールで魔の森くんだりまで行って帰ってきたのもそうだが、カイの顔を見た途端、安心したのか、どっと疲れが押し寄せてきたというような塩梅だった。
離れていた間に随分仕事が捗ったようで、カイの机上は出掛ける前よりかなりすっきりしている。あの男の方も、経過は順調らしい。まあ当然か。二人とも計画をし損じるような性分ではない。決めたことは、大体いつも、取り決め以上にきっちりと仕上げてくるタイプだ。シンに爪の垢を煎じて飲ませた方がいいかもしれない。
「爺さんにも手合わせてきたぞ」
「おまえが? なんだ、珍しいな……槍でも降らせる気か?」
「おいテメェもか。どいつもこいつも俺をなんだと思ってやがる。悪友の墓ぐらい寄ったら手は合わせる」
なんの気はなしに報告するとカイは悪戯っぽく笑ってそんなことを言う。そんなに意外なことか? むっとして眉をしかめ、文句を付けるとカイは妙にしんみりとした声を出す。
「……ああ、そうか。おまえはクリフ様と友人だったんだものな。もし私が先に死んだら私の墓参りも頼むぞ」
「馬鹿野郎、そういう笑えねえ洒落は言うもんじゃねえよ」
「うん、ごめん。私だって死ぬ気はないよ——もうしばらくはね」
書類にさらさらとサインを書き入れ、決済の判を押すとカイが立ち上がった。
ちょうどカーテンの隙間から夕陽が差し込んでおり、立ち上がったカイの横顔を、どこか物寂しい茜色が染めあげていた。その様に、ふと、「はかない」という言葉がソルの口を突いて出そうになる。
まるで昔も、こういうことがあったかのような……。
不意にソルは瞬きをする。いつかもこうして、夕暮れに染まる場所で自分の死を語る少年の横顔を眺めたことがある気がしたのだ。
黄昏時は魔を引き寄せる。東洋でも西洋でも古くからある伝承だ。それはたぶん、この哀愁や郷愁といったものを想起させるような色あいが、錯覚を引き起こすからなのだろう。
ソルはその時カイの喉元にありもしない傷痕を見た。その傷痕から、何度も、何度も、血が噴き出しては少年を死に至らしめた。死に方は種々様々だったが、確かなのは、数え切れないほど少年が死んだということだった。
ぞっとして目を擦る。瞬きをしてもう一度見ると、カイの喉元には傷なんか付いていやしない。つるりとした滑らかな皮膚が繋がり、内に詰まる肉を守っている。
「おい、カイ」
「うん? どうした、ソル」
「テメェは……」
口まで出かかった言葉をそこで呑み込んだ。その先を言ってはいけないと感じた。言葉には力がある。口にしたが最後、それは二度と消すことの出来ないしみになる。
その代わり、首を振ると手招きをする。カイは何故も何も聞かずに大人しくソルの方へ歩いてきて、目の前でぴたりと止まる。
ソルはおもむろに立ち上がるとカイの身体に両腕を回した。
「——どこにも行くなよ」
絞り出された声はソル自身驚くほどか細かった。
カイは抱きすくめられていることに文句一つ付けず、急なソルの態度に対しても言及せぬままソルの抱擁に甘んじ、そっと俯いたソルの頭を撫でる。
「うん」
「どいつもこいつもすぐ俺の前からいなくなりやがる。クリフも俺を残して死にやがった。アリアも……エルフェルトも。掴んだはずのものでさえ、手の隙間から零れていく」
「……うん」
「クリフが今際に言った。テメェを頼むとな。その時もう坊やは二十いくつを数えていたのにだ。いつまで坊やを孫扱いしてやがる——と思わなかったわけじゃないが……テメェのそういうところが、まあ、心配だったんだろうな、あいつも」
「そうだな……」
カイは優しい声でソルを宥め続ける。ソルの持つ人間らしい心が抱く恐怖を見透かし、身体は抱擁されながら、心は抱擁し返している。あんなに小さな子供だったのに。ソルはかぶりを振る。自分が優秀な兵士だと信仰していたような子供だったのに、今はこんな顔をしてソルと対等の場所に立っている。
「私はどこにも行かないよ。一見して危険な賭を選んでいるように思える時もあるかもしれないが、覚えておいてほしいのは、選択の全てにおいて私は生還を確信しているということだ。一つの犠牲もない成功を信じていなければ事を為さない。……ソル。私はかつて守られる子供だった。私のわがまま一つで、世界が変わると多少は信じていた。欲しい物が手に入らなければ駄々をこねようという考え方も持ってはいた——まあ滅多に欲しい物自体が見つからなかったわけだけど。だから……つまり、何が言いたいかというと」
はっとするほど透き通った青い瞳でカイがソルを見つめている。この目を知っている。何度も見た。はじめてカイと会った日。何も知らなかった彼の身体に悪徳を為した日。二人でパリの公園に行った時。封炎剣を持ち、逃げようとした時。第二次聖騎士団選抜武道大会の会場で再会した時。それから……思い出せないけれど、いつかの時も。
この目を見ていると気が狂いそうになる、と思ったことが、幾度あったことか。
「おまえを信じている、ということだ、ソル。だからもしおまえがおかしなことをやり始めたら私はそれを止めるし、私がおかしなことを始めたら、きっとお前やディズィー、シンたちが止めてくれるだろう。……大丈夫だよ。私達は取り戻せる。全てを」
昔は頭を撫でられるばかりだったカイが、今はソルの頭を母親のような顔をして撫でる。背伸びばかりしていつもソルの背を追いかけて、だけどいつの間にかソルを追い抜いて、今はソルが、カイの姿を追いかけているような気さえする。
どうしてだろう。ソルはずっと、カイは永遠に大人になれないような気がしていたのだ。子供のまま、背伸びをしてつま先立ちをしたまま、背が伸びきる前にその生涯を終えてしまうのではないかという恐怖が常にソルに付きまとっていた。聖騎士団にいた頃、カイのそばにいると、いつもその恐怖がソルを打ちのめそうとした。怖かった。ローマでギアの群れに突っ込んで行ったはずのカイが、傷もなくぼんやりと座り込んでいる姿を見た時は、心底安堵した。
誰かが——彼自身が、少年のままその時を永遠に止めてしまうのではないかという恐れから逃れられず、ソルは一度カイの元から姿を消した。
「昔、俺は坊やを置いて行ったが」
「……ああ」
「俺が置いて行かなきゃ、いつか坊やが俺を置いてどこかへ行っちまうんじゃねえかと思っていた」
「そうか」
「怒らねえのかよ」
「うーん。今更それを言うのは、まあ卑怯だなあとは思うよ」
でもね、と呟いてカイが耳打ちをする。もう時効だし、全部許してるよ、なんて甘ったるいことを言う。挙げ句の果てにとんでもないことを言い出して、内緒だぞ、なんて悪戯っぽく笑っている。
ソルは観念したように大きく息を吐いた。カイが口ずさんだ秘密の言葉は、雪が溶けるようにすうっと、静かな部屋の中に吸い込まれていく。
◇◆◇◆◇
しあわせって、すごく難しい言葉ですね、と昔カイさんは私に言いました。
「こんなに短いスペルなのに、どれほどの言葉を尽くしても定義出来ないほど多くの意味を孕んでいる。難しい言葉です。だけど抱くのは、こんなにも簡単で」
だから私は今すごく幸せなんです——とカイさんは微笑み、私も同じ気持ちで彼の手を握りしめました。
私達は少なからずしあわせとは言い切れない時期を持っていました。カイさんは、そもそも幸不幸の区別が昔は付いていなかったと言いましたし、私は私で、カイさんと出会ってジェリーフィッシュ快賊団に入るまで、あんまり幸せという気持ちを知りませんでした。でもそれは多分、私達が不幸な人間だということの証明にはならないんです。だって私はもうしあわせの意味を知っているもの。それを教えてくれる人が、私を選んでくれたから。
私と同じ世界を見てくれる人が、私を見つけてくれた。
それだけで、世界はうつくしいと思う理由に、なりませんか?
「幸せですよ。とっても、心の奥底から、身体中の全てで。今より幸せな瞬間はないですし、これから先の未来はきっともっと幸せです。私は幸福の中に生きている。……この答えで、十分ですか?」
私が答えると、ジャック・オーさんは瞬間信じられないような顔をして、ぱちぱちと瞬きをして見せた。なんだか覚えのある仕草だった。カイさんが、私が驚いたときによくやる癖ですよ、と教えてくれたものと同じだ。
ジャック・オーさんはそれからすぐにほっと胸を撫で下ろし、握りしめていた私の手を放すと、私のことをぎゅうと抱きしめた。
「その言葉を聞けて、良かった。ここに来た甲斐があったわ。……不安だったの。何て言えば、いいのかな。私は……どちらかというと、幸せになれなかった子達をたくさん見てきたから」
「たくさん……?」
「そう。世界はね……バックヤードっていう絵本に描かれた物語なのよ。その中で、同じ物語を何度も繰り返すの。読み直す度に物語は姿を変えていくのだけれど、何度形を変えても、悲しい思いをして、罪の対価を支払って……そういう人達も、いたわ。でも、今は違う。もう悲しいことは、全部終わり」
私を包み込むジャック・オーさんの身体は温かい。生きて涙を流す、感情のある人間の温度。はじめて私を見つけて手を差し伸べてくれたカイさんみたい。
ジャック・オーさんはぼかして言ったけれど、私のところに来てわざわざそんなことを訊ねるのだから、彼女の言う、「何度も悲しい思いをした人」たちが誰なのかは、うっすらと見当が付く。まず一人は、私。それから次は、きっとソルさん。それから……あとは……カイさん、なのかな。当てずっぽうだけれど。多分そうだ。何故ならこの三人が、ジャック・オーさん……お母さんにとっての、家族、だから。
彼女は、私達の知らないどこかで、そういうものを一人で見たのだろう。不思議と、それについてはすんなり納得出来た。
「みんな不器用な人だったの。でも後から、気がついたのよ。人間って、当たり前に、不器用なのよね。器用になんでも出来たら苦労しないわ。彼……ギアメーカーなんか、一見何でも出来る人に見えるけど、ぶっちぎりで不器用なんだから。大事な子に、愛してるって目を見て一回も言えなかったの。でも伝わったと思ってるから、それでいいんだって。……私、ちょっとぽかんとしちゃった。言葉にしないと伝わらないものだって、絶対あるのに」
だからちゃんと訊いたの、とジャック・オーさんは切々と語った。そうかもしれない、と私も思う。ちゃんと口に出して、話し合わないと、わからないことはたくさんある。シンがカイさんのことをずっと誤解していたみたいに。簡単なことも、口に出さないようにした途端あっという間に拗れてしまうのだ。
だから私達は言葉を交わす。ちゃんと気持ちの確認をする。私はカイさんに大好きですって伝えるし、カイさんは、ええ、私もです、と返してくれる。それは私とカイさんだけに限らなくて、シンとソルさんだとか、カイさんとソルさんの間でも、同じように、気持ちの遣り取りをしているはずだ。
「大丈夫ですよ。私達みんな、そのことはちゃんと知っています。カイさんやシンはもちろん、ソルさん……お父さん、も。……あの、もし出来たら、お父さんと、お話してみてください。だってもう何も悲しいことがないのなら、ジャック・オーさん……ううん、お母さんも、ちゃんと、伝える必要があると思うから」
「……わたし?」
「はい」
「うん。……そっか」
お母さんが、私の顔に子供みたいに頬ずりをする。私に抱っこされている時、シンも、こういう気持ちだったのかな。大きくて広くて、温かい、幸福な気持ち。だとしたら、私は嬉しい。
それからお母さんは、私の頬にキスをした。キスは、貴方が必要で生きてほしい、という親愛の証。昔カイさんが教えてくれた、秘密の遣り取り。そのことをカイさんに教えてくれたのは、ソルさんだった、らしい。ならきっと、ソルさんにそれを教えたのは……お母さんだ。私達家族は、キスと素敵なものと、幸せで繋がっている。
親愛のキスを終え、顔を向かい合わせると、私達は小さく微笑んだ。その後は二人で並びあってとてもたくさんの話をした。お母さんが知っている若い頃のお父さんの話や、カイさんとつきあい始めた頃の話、お父さんのかわいい失敗、カイさんのちょっとズレていたこと、初めて喜んで食べて貰えた料理、そういう他愛のないことを、日が暮れるまで話した。
いくら話してもまだ話したいことが出てきて、でもちょっとお腹が空いたな、と思い始めた頃、扉の向こうから足音が聞こえてくる。聞き覚えのある三人分の音。どすどすという重たい足音に軽快なスキップの音、それから、しとやかに歩いてくる音。
私達は顔を合わせ、頷き合う。誰の足音か、私達にはすぐわかる。
足音が扉のすぐ近くで止まると、コンコン、という礼儀正しいノックの音が聞こえてきた。私達は揃ってソファから飛び上がると扉の方に駆けていく。
お迎えをしなきゃ。扉の向こうにいる、私達の大好きな家族に。
「——お帰りなさい!」
そうして私達は、幸せを確かめるためのハグをする。
/ピュアリー・ブルー エンド
/プライマル・レッド 完