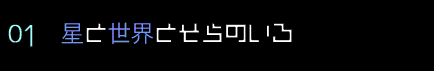
転校生は変な奴だ。
いや。僕自身を含め、このクラスに在籍している「今年度からの転校生」はみんなどこかしら変な奴だったけれども、そいつは僕にとって群を抜いて(鋼の乙女であるアイギスよりもずっと)変な奴なのだった。
望月綾時。帰国子女らしく、常識という物があちらこちらで欠如している。順平に言わせると常識欠如は僕やアイギスにも当てはまる特性らしいので、それほどの驚きはないらしい。しかし、そこまでは序の口だ。望月はまず、ものすごいナンパ野郎だった。手当たり次第に女の子に声を掛けてキャーキャー言われている。毎日ものすごい量の女の子が群がって手作りの弁当や菓子を差し出し、まるでハーレムだ。
別段それが羨ましい訳じゃないんだけど、なんというか、軽率な奴だなというのが僕の彼への第一印象だった。そう。軽率だ。あっちこっちに笑顔を振りまいて、希望だけ持たせて、そして誰も選ばない。
「いいのよ、綾時君は。彼に群がってる子達はそれをわかって遊んでるんだし」
ゆかりが遠巻きにそのハーレムを眺めながらそんなことを言っていた。僕にはよくわからなかった。
それから望月は、何故か常にマフラーを首に巻いていて滅多なことではそれを外そうとしなかった。体育の時間ですら、あの長ったらしくてびらびら風に靡くマフラーを大事そうに巻き付けて運動をしていた。そういうこともあり、マフラーは望月綾時のトレードマークとして機能した。黄色いマフラー、オールバック、それから、泣きぼくろ。
その三つが望月綾時の象徴だ。
「君の象徴は、そのイヤホンと前髪、それから音楽プレイヤーだね」
これも確かゆかりが言っていたことだった。望月の三つと比較して、「何でだか君達、比べたくなるのよ。よく見たら、ちょっと似てるし。そのせいかな」とかなんとかぶつぶつ呟いていたと思う。イヤホンとマフラー。オールバックと顔の半分を覆う前髪。泣きぼくろと携帯音楽プレイヤー。
前髪に隠された右目の下に、望月と対になるように僕にも泣きぼくろがあることを、僕は彼に教えていない。
◇◆◇◆◇
そういう、望月綾時という「なんか変な」男が僕と関わりを持つようになるとは実のところ僕自身はまったく、予想だにしていなくて、それどころか、もしかすると無意識に避けていた節すらあるのかもしれなかった。
今となってはそれは不可思議というか「不自然」なことでしかないのだけど、もしかしたら一つの防衛本能だったのかもしれない。有里湊と望月綾時は「近すぎた」。あんまりにも本質というべきものがよく似ていた。
経緯を考えれば当然と言えば当然だ。そうして、僕達二人が互いに近寄り、歩み寄って手を取り合って、上貼りされた絆創膏はぺりぺりと剥がれ始めたのだ。
——結局それって結果論なんだけど。
望月が転校してきて三日ぐらい経った日の屋上。天気は快晴。どこから入り込んできたのか、野良猫が丸まってひなたぼっこをしている。僕はベンチの上にぼうっと座り込んで天を仰いでいた。何も考えていない時、一人になりたい時、そういった時にこの屋上は便利だった。
あまり人が寄りつかない場所なのだ。多分立ち入りを禁止されていないからだろう。禁止されていればもっと、僕以外の誰がしかが寄りついたんじゃないかと思う。あと、ここは運動をするのには狭すぎる。
ひとりぼっちで眺めている空は相変わらず青かった。あお。言葉にするとたった二文字の、すごく、便利な単語だと思う。空があおい。海もあおい。花もあおい。制服、地球、宇宙、ありとあらゆるあおいろ達。
青は好きだ。静かな感じがする。騒がしい順平なんかはきっと赤が好きだとか言うのだろう。ゆかりはピンク。そういうのと同じ感じで、僕は青色が好き。多分。
ふと、屋上の戸が豪快に開け放たれる音がしてカツコツという靴音が僕の耳に入り込んでくる。振り向くと、入り口のところで困ったようにきょろきょろしている件の男の姿があった。そいつは僕の方を向いて、僕の姿を認めるとものすごく嬉しそうにこちらに寄ってくる。犬みたいだ。
「わあ! 有里君だ。すごい偶然だね。僕ね、一度君とこうして二人っきりで話をしてみたいってずっと思ってたんだ」
そして容赦なく腕をぎゅうと握り込んでくる。首尾よく僕を捕獲した望月は満面の笑みを浮かべ、そう僕に話しかけた。
「ほ……」
「ね、隣いいかな。ふふ……何から話そうかなぁ……」
「あ……う、ん」
「ほっといて、ひとりにして」。僕ははっきりとそう言ってやるつもりだったのに、何故だか僕の口はその言葉を音にすることを拒絶した。望月に遮られたぐらいで止めるつもりなんかなかったのに喉奥の向こうに言葉が呑み込まれていく。なんでだろう。この笑顔を、きっと曇らせちゃいけないんだ。だってこれは、多分だけど奇跡みたいに尊いもの。
「君と話したいことね、いっぱいあるんだよ。だけどアイギスさんは怖いし、君もすぐどこかへふらっといなくなっちゃうしで今日までなかなか時間も取れなくて」
「そう」
「そうだよ。だから今すっごくワクワクしてるんだ」
はにかむ望月の顔に僕は吸い寄せられるように目を向けていた。僕にじっと見られると居心地が悪いって、そういえばゆかりと順平に言われたことがある。だけどそんな僕にお構いなしで望月はぺらぺらと「いかに僕と話したかったか」を熱弁していた。僕なんかと会話を持つことの何がそんなに彼を惹き付けたのだろう。そこまで言われるとちょっと気になる。
そんな望月も一通り熱意を言葉にし終えたところで僕の視線に気がついたらしい。彼は急に縮こまると、もぞもぞと身を屈めて「ごめん、一人で喋っちゃって……」と恥じ入るような声を出した。
「つまんなかったよね……それに、お邪魔しちゃった、のかな。そうだよね。だってこんなに空が綺麗なんだもの……」
「え、いや、なんていうか……」
「うん、そうだ。今日の空は一際あおいね」
君もそう思って屋上に来たんでしょ? 違う? 望月が首を傾げる。子供みたいな屈託のない顔をして、「ハロー、今日も地球は青いよ」と宇宙飛行士ごっこをしているみたいに言う。
僕は目を丸く見開いてそこで固まってしまった。
「あれ? 有里君、僕何か変なこと言った? 空……青い、よね? 晴れてるし。雨も降ってないし……」
望月があわあわと僕の顔色を伺う。そうだよ。空は今日も澄み渡って青々としている。バケツの中のペンキをひっくり返したみたいにむらなく染まりあがっているぐらいだ。だから、「今日の空は一際あおいね」なんていうのはなんでもない時候の挨拶に過ぎない。
そんなことはわかっている。
「わかんない……」
「え、……」
「わかんないけど……」
変なのは僕の方だ。それを自覚して僕は望月から目を離した。その時、望月の顔を長い間直視していられる気がしなかったのだ。
だって。望月の目は、あおい。
「……望月を見てると、懐かしい、ような気がして。別に大して、話してもないのになんでだろう。ああ……気を悪くしたらごめん」
「そんなことないよ。それに、確かに今はまだあまり話せてないけど、これからたくさん話せばいいでしょ? それに不思議だね……君に懐かしい、って言って貰えて僕今とっても嬉しくて幸せな気持ちなんだよ」
「しあわせ」
「そう。幸せ。僕はどうも君といるとどんどん幸せになっていっちゃうみたいだ」
指先が伸びてきて、僕の手を掴んだ。望月の手は背がそうであるように僕よりも幾らか大きく、広かった。でも繊細だ。男性の無骨さというよりは女性のなめらかさがその中には見受けられる。
アイギスの鋼鉄のボディを重ねるように思い描いた。あの鋼の塊の重くて冷たい指先は、しかし無機質な冷たさと同時に人間の感情という質量を孕んでいるように僕には思えたのだ。相反する要素の共存とそこから導き出される二律背反。
本当は相容れない物が、歪に、しかしであるからこそ美しく溶け合っているんだ。
僕はもう一人そういう奴を知っている。この前消えてしまった愛しい僕の「ともだち」。死神コミュニティ、というふうに僕が認識していた絆を僕との間に築き上げ、あの子は最後にその結晶体を僕に寄越してどこかへ消えていってしまった。
いてもたってもいられなくて、すぐにその形見とも言えるペルソナを創りあげるためその日の午後にベルベットルームに向かった。グール。ペイルライダー。ロア。サマエル。モト。アリス。存在自体はイゴールに結構前に教えて貰っていたけれど、ペンタゴン・スプレッドを使ったのはその時が初めてだった。六体の素材とか面倒臭がりの僕がわざわざ用意することは多分ないだろうなと思っていたけど、いざその時になるとそんなことを考える余裕もなくて、恐らく覚悟から違ったんだと思う。
六体の死神を集め、それを寄り合わせ、そうしてタナトスは僕の心の海から生まれた。棺桶を背負った死刑執行人のようなその姿を見て、ああ、あの子は死を司るものだったのだ、と理解したのだ。
タナトスを見たエリザベスは彼女にしては珍しく本当に驚いたように目をぱちぱちとしばたかせて「まあ……」と息をんだ。
『とても希有なペルソナです。それもまた、貴方の得た絆のかたち……』
『そう……なの?』
『ええ。私はこれほど純粋で強い意志が込められたペルソナを今までに見たことがありません。——よほど、大事な方との絆なのですね……』
そう思いませんか、主。呼び掛けられたイゴールが相変わらず感情の変化を悟らせない顔で緩慢に頷く。
『左様、これは貴方様にとって非常に大きな意味を持つペルソナです。いわば分岐点。選択は、常に後戻りできない決定として貴方様を左右するのです。よろしいですかな。貴方様の選び取ったその一体……それが今、確実に、この先に貴方様の出会いを一つもたらしました。吉と出るか凶と出るか……見物ですな』
それからタナトスは僕のペルソナのストックの先頭にある。マガジンラックの、一番上の弾丸。メメント・モリを脳天にぶち込む僕達特別課外活動部の拳銃の中に詰められた銀色の鉛玉達。
影時間の外でこそ出さないが、今もタナトスは僕に取り憑き、降魔された状態になっている。
「昔友達が一人いたんだ」
「ひとり?」
ぽつりと零すと綾時は過敏に反応した。「君って友達そんなに少なかったっけ?」という不思議そうな、でも暢気な声。そうだね。ここに来るまでは、あんまりそういうのなかったし、欲しいとも思わなかったし、関わろうとしなかったから、きっと少なかった。
「確かに順平とか友近も僕の友達なんだけど。彼らとは全然別に、まったく違うところで、だけど出会ったから僕はその子と友達だった。友達になるっていうのは、その子と僕の間に限っては儀式の上で交わされた契約のようなものに似ていたかもしれない。特殊な結びつきだった。だけど愛していた。大事な夜の友達……」
「大切な人なんだね」
「うん。でもいなくなっちゃったんだ。八日前に」
「そうか」
望月は黙って僕の話に耳を傾け、ただ相槌だけをくれた。余計なことは言わなかった。
「ねえ有里君、僕はその子の代わりにはなれないけどね」
「うん」
「僕と友達になって欲しいんだ」
「……うん」
僕がいいよってちいさく頷くと望月は花が咲いたように顔をほころばせる。そんなに僕と友達になることが嬉しいんだろうか? 繋がったままの指先から伝わってくるのは全部プラスの感情だった。身体は嘘を吐かない。望月は嫌な汗もかいていなかったし、鼓動は緩やかで、満ち足りて穏やかだ。
「そうしたら、僕達は今日から友達だ。あ、放課後どこか出かけようよ。ポロニアンモールの案内してほしいな」
「いいけど、女の子がいっぱいぞろぞろ着いてくるのは嫌だよ」
「うーん、そうだね。申し訳ないけど今日の放課後は君と二人だからって伝えてこなきゃ」
首を捻って大真面目にそんなことを言う。どうやら既に放課後は女の子達に詰め寄られていたのか、或いはそうなるであろう確信があったようだ。その辺りから推察するに、望月の女たらしとしての能力は、ゆかりがぼやいていた通りやはり相当やばいみたいだった。そのくせ本人には自覚がないんだ。誰に似たんだろう。父親とか、そういうタイプなのかもしれない。大穴で母親。
昼休み終了五分前の予鈴のチャイムが鳴る。それを聞いて慌てたように望月がベンチから立ち上がった。やっぱりひょろひょろともやしみたいに背が高い。「行かなきゃ」。望月はそう口に出して、それから思い出したように手を叩いた。
「あ、そうだ。修学旅行、もうすぐだよね。もしよければ君と一緒に行きたいな。班分け、僕は好きなところに頼んで入れて貰いなさいって鳥海先生に言われてるんだ。僕は君のところがいい。順平も来いって言ってくれたんだ。……ダメかな?」
「いや……いいよ。面倒、見てやればいいんだろ?」
「やった!」
「だっておまえは危なっかしいから」
「ふふ。君に言われると、なんだかそんな感じがしてくるね……。でもほっとした。あと、問題はアイギスさんが許してくれるかかなぁ。彼女はなんでだかすっごく僕のことが……その、気に入らないみたいだから。何がいけなかったんだろう。やっぱり出会い頭に食事に誘ったことで彼女を怒らせてしまったとか……」
「……。それは確かにどうかと思うけど、アイギスのはそういうのじゃないよ。もっと根源に近い何かで、自分でもよくわからないんだって言ってた。僕は、アイギスと望月は友達になれる、と思う」
「ほんと?!」
「思うだけ。逆に言えば……僕は二人に友達になって欲しいってことなのかな……?」
気持ちの整理がうまくついていない時みたいにごちゃっとしていて、それ以上は明確な言葉に出来なかった。そうこうしている間に本鈴が鳴ってしまう。まずい。次の五限は確か……現代国語の江古田だ。江古田教師は何かと細かい難癖を付けてくるし転校生の望月は「チャラい」とか何とかであまり好かれていない。
二人で大急ぎで階段を駆け下りていく。道すがら、「望月」と声を掛けると彼はちょっとだけ唸ってから真面目な顔で僕に振り向いた。
「ね、もし良ければ僕のこと『綾時』って呼んでよ。望月、だとちょっとよそよそしくて残念だ。友達なんだし、いいでしょ?」
「…………い、いいけど……」
「やった! そしたら君のことも、湊君って、呼んでいいかい?」
どかどかと廊下を走り抜けながら望月——綾時はすこぶる嬉しそうなきらきらした笑顔でそうやって僕に迫ってくる。選択の余地はない。僕は小さく、躊躇うようにこくりと頷いた。すると更ににこにこと笑う。
なんだろう。母親に褒められた子供とか、母猫に撫でられた子猫とか、とにかくそういう感じだ。
(やっぱり、変な奴……)
教室になだれ込むように入って、江古田のお小言を右から左に聞き流しながら席に着く。ノートと教科書を広げ、ペンを握ってから口の中で密やかに「綾時」と反芻した。
昔飼っていた子猫の名前を呼んでいるみたいな気持ちになった。僕は猫を飼っていたことなんか、一度もないんだけど。
◇◆◇◆◇
「影時間には星がないね」
まだ死神のあの子が僕のそばへ時折訪れてくれていた頃のことだ。八月、夏の蒸し暑い真夜中に僕達はベッドに並んで腰掛けて他愛のない話をした。その日は格段に星が綺麗に夜空を彩っていて、誰からともなく誘い合わせて寮の屋上で天体観測をしていたのだ。美鶴先輩がどこからか望遠鏡一式を持ち出したりして結構皆ではしゃいでいたと思う。
影時間に入ると、あの子がやって来た。『今日はどうだった?』って聞かれたからそのことを話して聞かせると首を傾げられ、そういえば、と思い立って窓の外を覗いて見ればそこにはぎらぎら光る月があるばかりで星なんか一つも見えなかった。何分雲が分厚くて、あの不気味な月以外はそれにすっぽりと覆い尽くされてしまっているのだ。
『星?』
「そう。星。あの空じゅうを埋め尽くす光、だと思えばいい。綺麗だよ。僕達人間が天体観測なんて言いながらわざわざそれを眺めることもあるんだから、そうなんだと思う。ファルロスは見たことないの」
『影時間にないんじゃ、仕方ない。見られないよ』
「そうなんだ。一度、見せてあげたい。僕の記憶を共有出来たら便利なんだけどね……」
『……そうだね。僕は随分君からたくさんの物を貰ってきたけど、そればかりは少し難しいかもしれない』
ファルロスは見るからにしょぼくれて、足をぶらぶらと揺らしていた。『君は星が好きなの?』上目遣いで尋ねられる。『君が好きな物は、やっぱり僕も好きになりたいよ』。
「好きなんだと思う。綺麗なもの、うつくしいものは、いい」
『じゃその星っていうのは随分と壮麗なんだろうね』
「どうして」
『君がそうやって言うなんてよっぽどのことだよ』
そうだろうか。あまり自覚はなかった。『ついでに言うと』ファルロスが何かを数えるように指を折る。『君が何かを褒めること自体がまず珍しいよ。だから尚のこと。僕はずっと、君ってあんまり外の世界に興味がないんだろうなって感じていたから……』。
「実際、前まではそれに何も言い返せなかったと思うよ。自分以外も……自分も、どうでもよかったから。何で生きてたのかさえ説明出来ないんだ。こんなに何もかもがどうでもいいのに」
『君は繊細なんだね』
「さあ」
『きっとそうさ。ああ、君の世界が、全てうつくしいものだけで出来ていたら良かったのにね……』
ファルロスが言った。
全てうつくしいものだけで出来ている世界? ファルロスの言葉はいつもそうだけど、謎かけめいていて小難しい。ファルロスの口ぶりではまるで僕の世界には「うつくしくない」というレッテルをべたべた貼り付けられたがらくたがごろごろとあちらこちらに転がってしまっているかのようだった。確かに、全部が全部美鶴先輩が「ブリリアント」と賞賛するようなものばかりでは出来ていないだろう。だけど僕の生きている世界は、確かに、美しいのだ。
この青く澄み渡った世界。それをそういうふうに思われているのは少しだけ悲しかった。
「それじゃまるでこの世がきたないものばかりみたいだ」
『実際そうじゃないのかい? この国は特にそうだけど、自ら命を絶つ人だって全く絶えたりしない。それって世界が醜くて嫌気がさすからじゃないの。世界中高潔でうつくしいものばかりで出来ていたら一体人々は悲観するのかい?』
「……神話か何かみたいなこと言うんだね。それを言ったら、結局人間っていうのはうつくしいだけの世界に耐えられなくて、林檎をかじってこのぐちゃぐちゃした世界に降りて来ちゃったような生き物だよ」
『……それもそうだね……』
どうやらそれでファルロスは納得をしたようだった。ファルロスの知識は微妙に偏っていて、星は知らないくせに神話のことは知っていたり、その上僕の身の回りのことは時として僕以上に熟知してたりもする。満月の度に口にする「予言」なんかその最たる例だろう。
この少年は一体何者なのだろう、という疑問は全く明かされる兆しがない。
『じゃあそれで君が苛まれていくのも理通り?』
「……どういうこと?」
『君はこんな世界が好きだと言えるの?』
ファルロスはあのあおいろの眼でまっすぐに僕を見据えてそう問いかけた。世界。繰り返したその単語はとてもアバウトで当然両手の平になんか収まりそうにもなくて、僕の思考をぐらつかせる。世界が好きかどうか? わからない。そもそも世界って何なのだろう。何をもって世界というのだろう。
顔も名前も知らない人達がうじゃうじゃと住んでいるこの星を世界と呼ぶのだろうか。それとももっと広大な何か。宇宙? 違う。僕にとっての世界は、そんな手で触れもしないような無闇矢鱈に大きなものじゃない。
それだけはすぐにはっきりした。そうだ。ファルロスにとっての世界がどんな認識だろうと僕にとっての世界はもっと矮小でともすると卑近なものだ。
「世界っていう言葉にされるとすごい漠然としていて曖昧だ。そんなにぼんやりしていてスケールの巨大すぎるものは僕のものさしじゃ上手い具合に測れない。……だけど、僕が今生きている友達や、この街の人達、彼らと関わっている時間は全然無駄じゃない。きらきら輝いてる。……多分僕はそれをあんまり壊されたくはない」
『……ふうん』
「だからもしそれを守りたいのかって聞かれたら、イエスって答えるかもしれない。壊されたくないものは失くしたくない。この街に戻ってきてから随分とたくさんのものを貰ったし、たくさんの人と話したり色々するようになった。それが全部なかったことになってしまうのは、ぞっとしないかな。——それは勿論、ファルロス、おまえも」
『僕も?』
「当たり前。ファルロスも僕が失いたくないものの一つなんだ。確かにね」
『……君に面と向かってそう言われるとなんだか照れるね。そういうの、思ってるんならペルソナ使いの仲間にこそ言ってあげるといいよ。君がもしそういうふうに素直に口に出して気持ちを伝えたならば、彼らは僕以上にびっくりして面白い顔をするんじゃないかな』
「そうなの?」
『まあ試してみなって』
「気が向いて、覚えていたらね……それはそれとして」
ちょこんと腰掛けているファルロスの頭を上からぐしゃぐしゃと撫で付ける。「うわ」と小さく声を漏らしてファルロスは目を細めた。癖の強い短髪、色は紺。
子供が一人出来でもしたみたいだとこっそり思った。それか子猫だ。予知能力のある不思議な猫。ちゃんと色々なことを教えてあげなきゃ、そういうふうに思った。
「ファルロスにはもっと教えてあげたいことがたくさんあるんだ……」
『その気持ちだけで十分以上に嬉しいよ』
「ううん。折角こうして話すことが出来るんだから。ファルロスは基本的には博識だけどたまに変なすっぽ抜け方をしてるからはらはらする。僕が面倒見なきゃって感じも、ちょっとする」
するとファルロスはちょっとばかり困ったような顔をして、『参ったね、おかあさんみたいで』と苦笑した。お母さん。僕は男だから物理的には一生そういう名前のものにはなれやしないけれどその五文字の言葉はいっそ奇妙なほどにすとんと僕の胸の中に落ちていくのだった。
おかあさん。おとうさんではなく、母、だ。
『そうしたら、今度は愛情を僕に教えてよ。いつかね』
ファルロスが人差し指を唇に当てて内緒話をするような声で囁いた。
影時間が終わる。