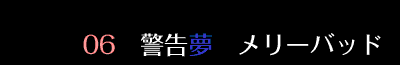
「ねえ、トーマス。私達が、結婚する時にね」
割合それは唐突な切り出し方だったと思う。いつも通り神代とアークライトの子供達、それからクリストファーのおまけのカイトとで広間に集まり、各々てんでばらばらに会話に興じていた時だった。カイトとクリストファーは何やら難しそうな学識高い話をしていたし(尤も彼らの高尚趣味はいつものことだ)、ミハエルは機嫌の悪い凌牙と口喧嘩みたいな軽い遣り取りをしていた。璃緒は学友に借りてきたのだという少女雑誌を読みふけり、トーマスは暇を持て余して知恵の輪をいじくっていた。
テレビは点けっぱなしで、世界情勢なんかのニュースをだらだらと垂れ流していたが、誰一人そんなものは聞いちゃいなかっただろう。いつものことだ。いつもの光景。それが璃緒の一言で中断遮断される。知恵の輪は、ちっとも解けそうになくてがっちり絡み合っている。
「……いきなりどうしたんだ?」
「あら、私何かおかしなことを言ったかしら。今は法律上無理ですけれど、私達はいずれ、それもそう遠くない未来に結婚するわ。私、何か間違ってる?」
「い、いや……そりゃ、そういうことになってるし、まあ少なくともお前が十六になるのと……凌牙の。あいつの納得を、待たなきゃいけないが。今までそういう話を面と向かってしたことがなかったとそういえば思って。……俺達にはまだ先の話だと、避けていた節もあったからな。どうした? ぼちぼち、何か言われ始めたか?」
誰に、という主語は省略されていたが、それがトーマスと璃緒それぞれの父親を指していることは明白だった。璃緒は定期的に呼び出しを受けている。そろそろ、そういう話が出たのだろう。そう考えるとまだ話の突然さにも納得がいった。
璃緒が頷く。
「そうね。うちの父が、思っていたよりもろくでなしだったものでちょっと思うことがあったのも確かよ……。まったく、失礼しちゃうわ。今更になって許嫁関係を破棄してもいいんだぞ、ですって。馬鹿にしてるのかしら」
「それで、なんて答えたんだ?」
「決まってるでしょ。私はトーマスがいいの、あとはトーマスに聞いてって、そう言い捨てて帰ったわ。だってそれ以外にあの人達に何か言って差し上げることがあるの? 私には思いつかないわ。せいぜいが、『余計なお世話よ』って罵ってあげるぐらいね」
「はあ?! それで俺に丸投げしたのかよ!」
「あの人達は双方の意思が云々みたいなことを思っているようでしたから。だからもしかしたら近いうちにあなたの方にもお呼び出しがかかるかもしれないわね。そうしたら、あなたからも何か言ってあげて。勿論トーマスの思うところでいいわ。私なんか願い下げだっていうのなら、そう言えばいいのよ」
「ああ、早いうちに俺から言っておくよ。璃緒以外の女の面倒なんかまるで見れる気がしねえってな。大事な人間はこれ以上増やせねえよ。家族だけで手いっぱいだ」
トーマスが憤慨したように言った。これは璃緒に、というよりは父親達に呆れ果てているといった様子だった。
幼馴染という楔に、許嫁同士というくびき。それらに二人が縛られて逃げ出したいと考えているのではと、ちらとでも思ったのか? そう思うと酷く不愉快な気持ちになる。ばかばかしい。二人はもう随分と昔にその関係性に納得していたし、将来の展望にも、期待と希望とを密かに抱いていた。
「父さんは狐みたいな顔をしてただろう」
「そうね。うちの父の方は、間抜けな狸って感じだった。見え見えなのよ、あの人は……」
「父さんもそれぐらい見え透いてりゃ、俺の方は楽なんだがな……昔から魂胆が見えないんだ。参るぜ」
トーマスが璃緒に同調し、彼女の頭をぽんぽんと撫でた。
どうやら二人の意見は合致しているらしい。それを確かめてクリストファーは安堵したように頷くと、カイトに向き直って腰の折れた話を再開させる。カイトの方はわかりきった結末とでも思っているようで、溜息ひとつで会話に戻っていった。ミハエルも興味が薄れたようにテレビの方に注視し、リモコンを弄ってチャンネルを変えだす。
こんなものだ。神代にとってもアークライトにとっても、ついでに古いなじみの天城にとっても最早アークライトの次男坊のところに神代の一人娘が嫁ぐというのはわかりきった確定事項となっていて、それは揺らがないし些末なことなのだ。今更騒ぎ立てることも何もない。何故双方の父親がそれを今になって問うのか、わからないほどだった。
もう十年早ければ、何か違ったのかもしれないが。
とはいえそもそも選択肢を奪って束縛するための縁談ではなかったので、特に娘を持つ神代の方で罪悪感みたいなものが出てきてしまったのかもしれない。普段の二人の様子をよく見ている子供達からしてみれば理解不能だが、(多忙とはいえ)子供のことをろくに見ていない父親からしたらそんなものなのだろう。
璃緒はやがてトーマスの元に嫁ぐ。そののちトーマスは家督を継いでアークライトの当主になる。誰にも異存はない。それはいつかの話だったけれども、とても明確で鮮明な未来予想図だ。
「それでトーマス。私達が結婚したらよ。私達どうなるのかしら。何か、変わったりするのかしら」
「さあな……どうだろう。そりゃあ変わるところは変わるだろうぜ、生活サイクルとか多少はな。まず寝起きが一緒になるから、俺は通学のために璃緒を迎えに行かなくて済むし……」
「あなたいつ頃を想定してるわけ? 私が結婚出来るようになる頃には、あなたはハートランド学園の高等部はとっくに卒業してるわよ」
「大学も行くつもりだけど」
「日本の大学に行くの?」
「拠点が日本だからな。璃緒は日本から動かないほうが何かと楽だろ?」
それ以上の考えはないみたいで、トーマスはぽりぽり頭を掻くとソファにぼふりと座り直してちょんちょんと璃緒を隣に手招きした。ずるずるとソファの上を移動して璃緒も素直に示された場所に落ち着く。相変わらずクリストファーはカイトと小難しい話をしているし、ミハエルはようやく定めたらしいチャンネルの古代オリエント時代の遺跡特集に夢中だった。
璃緒の手をトーマスの指が取る。武骨だが、男にしては美しく整えられた指先はデュエリストの誉れであり象徴だった。高貴なデュエリストたるもの指先は常に美しくあらねばならない、という訓示のもと育てられた、太さや骨ばった感覚でようやく女と見分けがつくようなそういう手で璃緒の少女の手を取ると、ほんの一瞬、それが少女同士の幼い秘め事にも似て目に映る。
「そのうち子供とか、出来るのかしらね」
「そりゃ、まあ……出来るだろうな。俺達はそういう結婚をするんだから。ミハエルはともかくクリスの野郎はこのまま一生涯を研究に捧げて果てるようなタイプだろ。俺が残さないとうちの家系が途絶えちまう」
「そうね……そのために守ってきたものですものね……」
純潔を。古いしきたり通りに守り抜いている璃緒の純潔と、それからトーマスの純潔。二人は婚約者同士だが、こうして指と指を合わせることはあってもそれ以上のことは一つもない。キスもしない。抱き合ったこともない。セックスなんて望んだことすらない。多分、だからなんだろう。その純潔を結婚という垣根でお互いに捧げ合うということにあまり現実味が感じられないのだ。
子供なんか出来たら、関係性が変わってしまうのではないか?
「でもまだ先の話だ。お前はまだ十四歳なんだから……それに高校にいるうちに結婚するのは世間体とか、面倒だろ。きちんと結婚してたって子供が出来るととやかく言われるぞ、この国は。そういうのはもっと後でいいんだ。もっと。多少遅くなったって変わらないよ」
「私達のモラトリアムが?」
璃緒がトーマスの手を握り返して、しかし視線は虚空に向けたままぽつりと尋ねた。決断を先送りにしていられるモラトリアム。トーマスと璃緒が二人で身を置いている現状はまさにモラトリアムそのものだ。その中では時間は停滞し、変化は起こらず、緩やかで、穏やかで、あくびが出るほど退屈な平穏が約束されている。
明日もその次の日も変わらない毎日が訪れては繰り返す。
「私、きっと怖いのよ。ずっと何も変わらない世界の中で平穏に生きてきたのが、もしそれで変わってしまったら、どうすればいいのかなって。だって読めないんだもの。私がアークライトになって……子供が出来て……お母さんになるなんて。全然想像つかないわ。子供ですって。私達自身まだこんなに子供なのに。おかしいわね。背伸びして何を考えているのかしら」
「別にいいんじゃねえの? 背伸びの一つや二つぐらい」
「でも私、あなたと結婚したら子供を産んで育てたいなあって思うのよ。きっとよく似てるわ。その抑え付けても直らないくせっ毛とか、赤い目の色とかね」
「まあ、目は赤いだろうなあ。だが俺に似たら目つきが悪くなるぜ。お前の目を貰った方がいいんじゃないかと俺は思うね。髪の色も、俺みてえなぼさぼさのツートーンよりは水色の方が綺麗だ」
「前々から思ってたけれど、あなた自分の容姿きらいでしょう」
「ナルシストになるほどじゃないってだけだ。ただ、俺から出来たちびが俺と同じ顔つきだと、なんか嫌だなって話」
「ふーん、そう」
トーマスと同じ顔をした子供の手を引く、少し年を取った彼の姿を想像して璃緒がくすりと笑む。暴れたくて仕方ないというふうのやんちゃ坊主と、それに困り果てるトーマスの図。確かにそれは、何かみょうちくりんな感じがした。そもそもアークライトで彼のように荒っぽく、男の子らしい性質を持った人間が珍しいのだ。高貴と優雅を掲げる貴族の末裔なのだから、それは仕方ないのかもしれないけれど。
トーマスこそが異端で、彼の家系としては恐らく父バイロンやクリストファーみたいな男が好まれるのだろう。しかし璃緒としては、トーマスのその性質にこそ惹かれるところがある。貴族らしい高潔さと同居するどうしようもない子供っぽさがかわいいのだ。
「私はあなたの容姿も好きよ。アークライトの中では目立って粗野なところも含めてね」
手を伸ばして頬の十字傷に触れた。昔暴漢に絡まれた璃緒を庇って退けた時に彼が受けた傷だった。あのあとは、璃緒の押しにたいてい弱くて甘い傾向にあるトーマスにしては珍しくくどくどと璃緒に説教を垂れたものだ。もう二度とこんなところに一人で来るんじゃない、お前は女なんだから。
無傷の璃緒に対して、血の流れっぱなしの頬を気にも留めず璃緒の無事を案じるトーマスの姿は衝撃的なものだった。この先もう二度と拝む機会はないだろうし、璃緒としてももう一度見たいものではない。顔出しをする職業の彼にとって顔は商売道具なのだ。それなのにあんなふうに傷をつけて。
「どうせ俺は我が家のはみ出しっ子だよ」
「あら奇遇ね。私、型にはまった男性よりは型破りな方が好きよ」
「お上品な一族に囲まれると俺自身は肩身狭いんだがな」
「どうかしらね。私、あなた方のお父様は存外トーマスみたいな性格だったんじゃないかって思うのだけど。実家に帰らないあたり、やましいことでもあったりするんじゃないの?」
「面倒くさがりなだけだ。怠惰なんだよ。クリスと一緒だな」
「まるであなたが怠惰じゃないみたいな言い草ね」
わざと意地悪っぽく言うとトーマスはくすくすと笑った。実際のところ、トーマスはそういう粗野な外見や言動に反して非常にまめで几帳面な男だった。
メールの返信はすぐに返ってくるし、仕事や何かでどうしても手に着かなかった時は用事が終わった後すぐに謝罪つきで電話がかかってくる。ファンレターの類も無下にせずこまめに読んでいるらしい。サインを頼まれれば笑顔で応じる。そのうちの何割かは仕事として行っていることなのだろうが、彼の性質がなければ損なわれてしまうものだろう。
「……なんだか」
ミハエルがトーマスと璃緒には聞こえないような小さな声でぼやく。古代オリエントの特集が終わって古代マヤ文明の特集になる。マヤ・カレンダーの破滅の日の予言についての解説を流し聞きして凌牙の方を振り返った。思った通りのむっつり顔だ。非常に機嫌が悪い。
「僕が思うに、あの二人が結婚したところで何かが変わるってことはないんですよ。何か決定的な変化は。些細なことはあるかもしれないけど。住居とか……だからそんな顔しなくたっていいのに。璃緒が兄様に取られるとか、そういうことはないですから、ほら」
「……うるせえ」
「凌牙と兄様は別々なんですよ。比較対象じゃない。璃緒にとって兄の神代凌牙というのはもう次元の違うところで絶対に定められたものなんです。多分。僕にとっての兄様がそうだから。たとえば僕は遊馬のことを一番の友達だと思っていますけれど、それって兄様と比べられるものではないんです。わかんないかなあ」
「わかりたくねえよ」
「いい加減もうちょっと、大人になるっていうか……譲歩を覚えたらどうですか?」
手にしたリモコンでまたチャンネルをいじる。くだらないバラエティー、名前も知らない芸能人達の恋愛トーク、興味のないプロスポーツの生中継。
気乗りのしない番組達。凌牙の表情を伺ってミハエルはテレビの入力を地上波デジタルからホームビデオの貯蓄してあるHDDに繋がれている入力に切り替えた。ずらりとアークライトの子供達の成長記録が見出しになって並ぶ。最初のうちのいくつかは八ミリビデオのデータだ。サムネイルの中には、まだ幼い神代兄妹もしっかり映り込んでいた。
「いつかこういう日が来るって、もうずっと前からわかっていたじゃないですか」
そのうちの一つを選んで再生ボタンを押した。画面にまだあどけない顔をしたトーマスの、傷一つない顔が大写しになる。子供特有の柔らかく弾力のある頬。それを画面の外から伸びてきた指が摘みあげて、捻った。
凌牙の指だ。トーマスより三つ幼い凌牙がふにふにとやわらかそうな指でトーマスの頬をつねっている。何か気に入らないことがあってその仕返しらしい。トーマスの顔が不機嫌そうに歪んだ。こんなことをされては、怒るのも仕方ない。
「ずっと前からわかってたからなおさら嫌なんだよ」
「でも、顔も名前も知らない男がぽっと出てきたらもっと嫌でしょう?」
「んなもんぽっと出る前に俺がぶちのめす。璃緒の半径五メートル以内に入れさせてたまるかよ」
むっすりと口を引き結んで当然のようにそんな返事をした。
◇◆◇◆◇
「トーマスの、ばかっ! きたない手で璃緒に触んなっ!」
「ってーな何するんだよ凌牙! 馬鹿って言った方が馬鹿なんだぜ、それにおれはちゃんと手を洗ってる、別に汚くない!」
「うるさい! きたないって言ったらきたないんだ」
ビデオの中の幼い二人がそんな言い合いをしている。騒動の発端はどうやらトーマスが璃緒に手で触れたことであるようだった。トーマスはただ、庭に咲いていた花を摘んできて花冠を作り、それを璃緒の頭に載せてから彼女のおでこにキスをしただけだったのだ。キスといっても、リップ音もそうしないような本当に触れるだけのもので、子供の邪気のないスキンシップに他ならず、そこにはこれといったいやらしさや汚らしさはないとはた目にも思われた。
そんな凌牙とトーマスを横に見ながら、璃緒は貰った花冠を両手で押さえ、マイペースにずり落ちないように位置の調整をしている。そこにクリストファーが寄ってきて、璃緒に挨拶をすると小声で喧嘩中の二人に聞こえないように尋ねた。
「璃緒、きみは、あの二人を止めて欲しいかい?」
「……うーんと。わたし、よく、わからないわ。トーマスがお花くれて嬉しいの。だからなんで凌牙があんなに怒ってるのかぜんぜんわからない」
「そうか。なるほどね……」
「クリスでも、お花あげるのは、やーよ。ねえ、きれいでしょ?」
「勿論とても綺麗だ。青い花……これは、ネモフィラと……ガーベラかな。うちの庭から摘んできたのか」
「きっとそうよ。トーマス、さっきまでお庭でしゃがみこんであちこちのお花を探してたもの。それと、おはな、ネモフィラとガーベラのふたつだけじゃないの。もう一個あるのよ」
「へえ、そうなんだ」
「そうよ。もう一個のお花はね」
凌牙とトーマスはまだいがみ合いを続けている。とうとう暴力沙汰に発展してしまい、お互いにお互いをむんずと掴みあげての大喧嘩になってしまった。凌牙が噛みつけば負けじとトーマスも凌牙の腕を掴む。クリストファーはそれに気が付くと流石に危ないと判断して間に割って入り、璃緒の言葉に耳を傾ける姿勢がおざなりになる。
「こら、やめなさい」というクリストファーの叱り声。画面に映らないところでミハエルがぐずりだして、音声の大半を埋め尽くした。それにトーマスの怒号と凌牙の金切り声が重なる。
だから璃緒が花冠を頭から降ろし、物憂げにそれを眺めて零した一言はそのホームビデオの中にいる人々にも、ホームビデオの音声データにも残されていない。
「……もう一個の花の名前はブルーファイアーというのよ。ねえ、トーマス、あなたにならこの意味が分かるでしょう?」
ただ、彼女の口元の微かな動きとして記録に残るのみだ。
◇◆◇◆◇
映像をぼんやりと眺めながら凌牙は深く溜息を吐いた。トーマスと凌牙のこういった形での、なんだかどうしようもない確執というのはあの頃からずっと続いている。
こうして客観的にそれを見せられると流石の凌牙本人も堪えるものがあるらしく、もう一度深く息を吐くと右手で顔を覆った。
「結局、おれが璃緒の相手に認められる男もあいつしかいなくて……だから俺はそれがいやなんだ……」
「へえ。意外です。兄様よりは遊馬の方がいいとかなんとか、言うのかと思ったのに」
「あいつにはもう女がいるだろ。その気もない奴に押し付けてやれるほど俺の妹は安くない」
「彼、単に色恋沙汰に疎くて興味がないだけだと思いますけどね?」
「——璃緒が望まないから」
「へ」
「璃緒は。あの幼馴染みの女が遊馬に思いを寄せてんの、見てるのが好きなんだってよ」
凌牙は彼岸を見るような目でそう言った。
ホームビデオから入力をまた切り替えて、チャンネルを変え続ける。民放を二周ほどしたところでミハエルのチャンネル選びは結局一番最初の古代文明特集のところで手が止まった。テレビの中ではリポーターがマヤ・カレンダーについての込み入った話をしている。「誰が信じるんだこんなもん」とぼやく凌牙の横で、ミハエルは困ったように「さあ、それは、信じる人が決めることです」と曖昧に答える。
現地入りしたリポーターがマイクを持ってその道の学識者にインタビューを取っていた。神妙な顔つきで語る口ぶりに日本語の翻訳音声が合成され、なんとも胡散臭い。
「こういうの、どうせやらせだろ」
凌牙がつまらなそうに言った。
「第一こんなんで世界が終わっちまうんなら、俺は璃緒がアイツの家に嫁ぐのを見なくていいわけだし、いちいち悩んでるのがばからしくなってくる」
「世界が滅ぼうが滅ぶまいがばからしいと思いますけど」
「俺にとっては深刻なんだよ。璃緒はある意味で俺のすべてで……だからトーマスも……」
そこで口ごもった。続きを口にするのが恥ずかしくて躊躇われてしまったのだ。
ミハエルはそれを追求しない。テレビでは、「やはり、二〇一二年十二月二十二日で世界は終わってしまうのか?」そんなテロップが画面を埋め尽くしている最中だった。スタジオに映像が戻ってタレント達がわいわいがやがや意見交換をしている様子が映りだす。実にばかげた話だ。凌牙は内心でそう繰り返した。
あと一ヶ月かそこらで世界が終わったりなんかしてはたまったものではない。