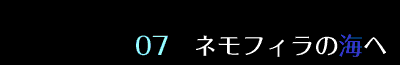
川面は穏やかに凪いでいた。トーマスの心持ちとは正反対に、静寂を良しとしてただただ穏やかだった。どこか遠くでからすが鳴いている。一日が終わろうとしている。
振り向いた遊馬の顔はとろとろとした微睡から覚めて、永遠が一瞬になり、信じていたものが瓦解した後のような、しかしそれでも全てを棄てることを許さずしがみついているかのような、哲学者のような難しい表情をしている。要するに、トーマスには彼が何を考えているのかがこれっぽっちもわかりそうにはないのだ。
「真月零は人間じゃなかった。結論から言うと、そういうことになるのかな。あいつは人間の姿をして、俺に近付いてきて、そうして俺の懐にもぐりこむと、俺の大切なものを色々と手に入れて……俺にとってものすごく大事な存在になった。勿論そこまでが、あいつが考えた通りの作戦だったんだ。真月零の目的は最初から俺の信用を勝ち取ることだった。俺はあいつのことを友達だと思ってたけど、その実、真月の方ではそんな気はさらさらこれっぽっちもないみたいだった」
緩やかな風を受けながら遊馬が口を開く。真月零。遊馬が裏切られたのだと伝え聞いたことがある。その誰かが、トーマスの夢とどういうふうに関係してくるのか、それを考えるのは怖かったのでやめた。
「はた目から見た真月は、子犬みたいなやつだった。人懐っこくて、俺によくじゃれついてきた。『ゆうまくん』っていつも柔らかい声で俺の名前を呼んだ。——『真月零は、九十九遊馬のファンで、九十九遊馬が大好きで、九十九遊馬の為なら何をも厭わない』。そういう、キャラ付けをされてた。全部あいつが考えた演技のための人格だったけど、俺の知っている『真月零』のまず初めの姿がそれだったんだ。
でも、そのうち俺は真月の第二の姿を知ることになる。真月はある時、俺に自分は『バリアンズガーディアン』という組織に属する存在で異世界人だと名乗った。それでも俺にとって真月零は人間の友達だったんだけど……それを境に、少しずつ、少しずつ、俺の世界はずれていった。
真月はすごく話のうまいやつで、俺を丸め込む方法ってやつを熟知してたんだ。まずあいつは俺との間に上司と部下の関係性を構築して、『アストラルを救うため』という口実を使って俺に協力を迫った。俺は真月を信じていた。正しいことのために戦っているんだって考えていた。だから頷いた。それで、俺達の間に取り決めは出来あがった。すごく簡単で、単純なことだった。
俺はそうやって心から真月零っていう友達を信頼した。唯一無二の替えがきかない存在だった。だけどある時、真月零は幽鬼のように俺の世界から消え去った。消滅した。いなくなった。
真月零は確かに異世界人だった。でも、バリアンズ・ガーディアンだなんていうのは嘘っぱちで、あいつ自身がバリアン七皇という存在で、その上、『真月零』っていうのは俺をたぶらかして上手いこと利用するためだけの仮初の存在だったんだと俺に暴露した。衝撃だった。何言ってんのか、すぐにはわかんなかった。嘘ついて、騙してたんだ。俺にはそれが許せなかった。何より、『真月零』っていう存在を、道端に落ちてるちり紙みたいにポイって捨てたことが許せなかった。
——その時真月零は、俺の世界で一度、死んでしまった」
「……どういうことだ?」
「俺がトーマスと同じことを、あいつに対してしたってことだよ」
そうだろう? 遊馬が目線で問いかけてくる。「おまえもころしたんだろう?」だが、誰を? トーマスにはその自覚がない。
「ベクターがその存在を否定して、独立した、それ以外の何物でもない『真月零』っていう存在は文字通りなかったことにされた。でも俺は真月を忘れることが出来ない。それで思い出を棄てられないからベクターの中に真月を見つけようとした。だけど否定されたことを嘘だって考えて否定するのは、最初の否定を受け入れてしまったからなんだ。いなくなったものを求めることで、俺は真月が死んだことを認めてしまった。
トーマスと墓の下にいるやつらも、おんなじだよ。すごくよく似てる。ただ違ったのは、あいつらの方が真月よりも深く世界に根付いていて、そのくせ、最初っから何もなかったふうなふりしていなくなろうとしたってこと。真月も卑怯だったけど、そいつらはもっと、さみしい別れ方を選んだんだなって俺は思うよ。だって覚えていることすら許されなかったら、そのことを考えることだって出来ないんだ。
まさか、墓を作った挙げ句その死を悼むやつが出てくるなんてことは、流石に思ってなかっただろうけど」
きっと本当は世界中の全員に忘れてもらいたかったんだ。遊馬がこぼす。だが九十九遊馬は自身の特異性か、はたまたその他の要因でか、その誰かを忘れることが出来なくて一人で完全に記憶していたのだ。
トーマスは既に酷い後悔をはじめていた。聞くんじゃなかった、聞きたくない、という感情が溢れて思考を席巻する。開いてはいけないものを、閉じておくべきだったものをこじあけてしまった時の絶望感が、じくじくとトーマスを苛みだす。
しかしトリガーを引いたのはトーマスだ。もう引き返せないし、彼の抱えたものを彼の中に押し戻すことは、出来ない。
「……それで。話は、まだあるだろう? 墓の下の、俺にとっての『幽霊』の正体は?」
「ああ、そうだな。まだ、墓の下に埋められた俺の友達の話、してなかったな。ごめん。それじゃ、二人目のいなくなった友達の話、するよ。ちゃんと最初っから端折んないで全部。きっとその方が痛いだろうから」
痛みという言葉をを口にすると遊馬は口元だけで笑い、あの赤い目を細める。からすの鳴き声さえあたりに響かなくなり、環境音が、川が流れるささやかな音ばかりになることで、トーマスはようやく日の半分が沈んだことを知った。独白は短く、そして長い。
痛みを伴う独白。まるでそいつは、心や魂といった形のないものを砕き削り落としているみたいではないか? だからこそ破片となって相手に突き刺さり、双方で痛みを感じるのだ。
要するに遊馬は死者を蘇生させようとしているのだった。まず真月零という幻を幽霊にまで還元し、多分次は名前のない幽霊達を生きている記憶に復元しようとするのだろう。名前のないものを名前のあるものに言葉で戻す。奇跡というよりは禁忌という言葉が相応しかった。思わず唾を飲む。いつの間にか、喉はからからに乾いてしまっていた。
そうして遊馬はとうとう、深く息を吸うとトーマスの幽霊の話を始めた。
◇◆◇◆◇
「そいつと俺が会ったのは、ええと、半年前ぐらいのことだったかな。中学入って割とすぐ。出会いってやつは、多分最悪の部類に入るやつだったよ。あいつ、壊したんだ。俺の宝物……父ちゃんに貰った皇の鍵を。真っ二つだった。不良だったんだ。悪い奴らとつるんで、ずるずるとやさぐれてって、滅茶苦茶に荒れてた。その理由は、しばらく経つまで俺にはわからなかったけど。
とにかく、そんな状態のそいつと、俺はデュエルをした。その時の俺っていうのは本当にデュエルに関しては初心者で、右も左もわからないような状態だった。『トラップを伏せる』なんて素で言っちまって、そいつにも馬鹿にされた。うん、今思うと正直俺自身もそれはないだろって思う。まあそんなことはどうでもいいんだけど……それでデュエルをしているうちにわかった。あいつ、別に悪いやつじゃないんだ。ただすごく寂しそうなやつだった。後から知ったけど、荒れに荒れてたせいで不良として遠巻きに見られるか祭り上げられるかで友達らしい友達っていなかったんだって。自業自得だって本人は言ってたけどな。一匹狼みたいなのが好きだったのも原因だと俺は思う。でも本当は、心から誰かの為に戦えるような、そういう優しい奴だった。
そいつには妹がいた。妹のために、カードを手に取って戦ってた。妹は、火事で酷い大やけどを負って長期入院してた。そいつは妹にやけどを負わせて意識不明の重体に送り込んだ男を憎んでた。そりゃそうだよな。だって妹は、そいつにとってたった一人の家族だったんだ。そいつは優しかったし、何より妹を大事に思ってたから、本当に、本当にその男を恨んでたんだ。だけどお決まりってやつで、その男も根っからの悪人だとかそういう人間じゃなかった。まあ性格は悪いと思うけどな、俺は。——そいつの妹にやけどを負わせたのも、死にそうだったところを身を挺して助けたのもその男だったんだ。それも後からわかった。憎むべき男は命の恩人で、実のところ、大火事は男にとっても想定外の、不慮の事故だった。でも、そのことを、男自身も酷く気に病んでいた……いいやつだったんだ。そいつも」
これも、お決まりってやつかな。トーマスは何故だかぎくりとするものをその声のうちに感じて身構えた。大火事。その単語にまぶたの裏側に焼き付いた赤色のことを思い出したからだ。
その、男というのはもしかして。
だがそれを口に出すことは許されない。遊馬の淡々とした喋りはまだ続いている。
「ある日因果の巡り合わせってやつで、俺の友達と、その妹を傷付けた男がデュエルで戦うことになった。男は焦っていた。父親の役に立たなきゃいけないって意気込んで、認められたくて、対戦相手といがみ合った。めちゃくちゃなデュエルをした。相手を傷付けることを厭わず、がむしゃらに勝とうとして、……でも負けた。認めて貰いたかった父親自身に馬鹿にされての、自爆みたいな負け方だった。そいつは去り際にまるで憑き物が落ちたみたいな顔で謝罪をして消えた。そのことに関して俺の友達はものすごく複雑な感情を抱いたみたいで、しばらくぶつぶつ言ってた。気に食わない、って。
俺から見てその二人は多分同族嫌悪ってやつなんだろうなって思えた。二人とも実はすごいよく似てるんだ。兄弟を……家族を心から愛していて、そのためならいくらでも無茶が出来たし、どんな酷いことでも自分の心を騙して手を汚した。それが、我慢ならない時もあったみたいだけど。だから、お互いを認め合ってからの二人は、息の合ったコンビネーションで戦えた。軽口叩き合って、仲が悪いのか良いのかわかんないような、喧嘩友達みたいな感じだった。——俺は、ちょっとそれが羨ましかったよ。丁度アストラルがいなくなった後だったから……俺とアストラルは別に似た者同士じゃないけど、ぶつかりあって、前に進んでいく二人がまぶしくってさ。ごめん、これは蛇足かな。
それから、男がその妹のことを胸を痛めて案じてるってこともその時わかったんだっけ。責任感ってやつかもしれないけど、本気なんだって俺には思えた。本気で妹のことを……その兄妹のことを考えてた。もしかしたら……やめとく。これは、どうでもいいし」
そこで初めて遊馬は大きく息を吸い、何か重大な事実を告げるための準備みたいなことをした。まずトーマスの手を取った。ミハエルがそうするような強さだ。多分それは、 「これから大事な話をするから絶対に逃げるなよ」という意思表示だった。
それから子供らしい丸く大きな瞳でトーマスの目を射抜くように見た。鮮血の紅がトーマスのブラッドベリーの目をともすると睨めつけるかのように見た。これもまた、逃すまいとするそれだけの強さを感じさせる色だった。
「それで。その、俺の友達の名前はな……」
ゆっくりと声が紡がれる。身震いする。全身が情けなくかたかたと震え縮むのをトーマスは抑えられない。手を握られていなかったら確かに逃亡を図っていたかもしれないし、そうでなくとも身を竦めて両腕で自らの体を掻き抱いていたはずだ。己を守るために。
しかしそれは許されていない。遊馬は冷徹に、トーマスに現実の受容を求める。
「神代凌牙って言うんだ」
——やはりだ。
頭を思い切り殴られたような衝撃だった。鈍重な金槌か何かで情け容赦なく後頭部をぶん殴られ、そのまま、仰向けに倒れて意識を失うことすら許されないみたいなそんな感じだ。トーマスは頭を抱えた。遊馬がその次に繰り出す言葉が、今はもうはっきりと、予測することが出来た。
「その妹の名前が神代璃緒。それで、璃緒を傷付け、救った男は……」
思った通りだ。
「?——トーマス・アークライト。お前のこと。神代凌牙と神代璃緒はお前が毎日通っている墓の下にある形のない、お前自身が作り上げた遺骸の名前だ。あの二人は、わけあって俺達の前から姿を消し、そのせいで記憶から消えてしまったけれど、でもやっぱり完全に忘れることは出来なくて……その違和感が、墓を作るっていう行動になってトーマスへ襲い掛かったんだ。死を認められない気持ちと消えてしまった現実がせめぎ合ってお墓になった。……んだと俺は思う。根拠はないけど」
体の震えが酷かった。神代。神代凌牙。神代璃緒。凌牙。璃緒。凌牙と璃緒。トーマスが傷付けた兄妹の名前。手段を選ばなかった相手の名前。どうして今まで忘れていたんだろう。どうして忘れてなんかいられたんだろう。忘れていい名前じゃなかったのに。忘れられるような名前じゃないのに。
たとえその相手が、忘却を望んだのだとしてもだ。
トーマス・アークライトはその名前を胸に血が溢れて止まらなくなるほどにしかと刻み込んでおかなければならなかったのに。
「お墓と供えられた花は、トーマス自身の矛盾と無意識の呵責からくるものだったんじゃないかな。忘れたくないけど、忘れていなきゃいけなかった。神代兄妹はこの世界から消えてしまったんだ。存在しないものを知っていることは出来ないから。そこで矛盾が生じる。だから、青い花を供える。忘れているけれど覚えている。それがトーマスに出来るつぐないの形だった。青い花は、シャークと妹シャークの色の花なんだ。二人とも水属性デッキ使いだったし、髪の毛の色とかそういうのもろもろ、青っぽかったし。この辺からはもう全部憶測なんだけど、ブルーファイアーの花さ、あれもそういう気持ちからきてたんじゃないかなあ。命を捧げてもまかなえないって、わかってたとは思うんだけど」
ぐるぐる回る。とても苦しい。青い花達の幻がまたトーマスに訪れる。今はもうはっきりとトーマスはその二人の人間の姿を思い浮かべることが出来た。神代凌牙と神代璃緒が、目を瞑り、死んだように眠り……いいや、死んでいるのだ……両手を胸の上で合わせて無数の青い花に取り囲まれている。死化粧。棺桶の中に横たわっているみたいに、青い花に押し潰されるようにして死んでいた。青い花は全てトーマスが手向けたものだった。ブルーファイアー。リンドウ。カンパニュラ。ガーベラ、パンジー、モスフロックス、ムーレアナ、ビオラ、ローズマリー。オーブリエチア、クレマチス。ネモフィラ。
埋まって、その死体は二度と目を見開くことはない。
トーマスが殺したのだ。
心の中の二人を、完膚なきまでにそうして花で殺した。
「でも仕方ないんだよ」
「仕方ない? 何がだ? 俺が、俺があいつらを殺したことがか?!」
「そうだよ。仕方ないんだ。二人は本当は死んでない。ただいなくなっただけ。でも、名前も存在も奪われていなくなるっていうのは、死んじゃうのと同じだ。何も変わらない。ミハエルは、俺にしきりに『兄様はおかしくなった』って言ったけどその逆だな。トーマスは自分の心を守ろうとしたんだ。そうしなければ本当に気が狂ってしまいそうだったから」
「何を——わかった——ふうに——!」
「わかるよ」
ぽつりと漏らされた遊馬の声はぞっとするほど低かった。とてもじゃないが、普段彼が見せているような調子に乗りやすくてばかな子供のものではない。
「最初に言っただろ? 俺も自分を守るために真月を殺したから。本当はそういうわけじゃないって理解していたけれどでもやっぱり真月零は、あの時一回俺の中では死んじゃったんだよ。俺が殺した。そうしないと俺はもう、立っていることすら出来そうになかったから」
既に無くすことの出来ない傷痕となった既成事実を淡々と語る横顔を、彼の幼馴染や友人達が見たら一体なんと言うだろう。
ああ、これがミハエルの気持ちだったのかと今になってトーマスは理解した。
「俺も、出来ることならもう一度会いたいなあ。無理だって知ってるけどな」
だってあいつ、名前は呼んでもらいたがるくせにもう俺の前でその姿を見せてくれないんだもん。ぶすくれるように、そうぼやいた。おおよその諦観とそうしてまだ諦めきれていない未練とがごちゃごちゃになって彼の表情を重く染めていた。
そうだ。未練だ。
「青い花は……」
「んん?」
「お前は、あれを璃緒と凌牙の色だと言ったが。それだけじゃない。確かに二人とも総じて青かったが。あれらは——未練の色だよ。未練だ。俺が知る限りこの世で最も情けなく狂執的で生々しく、人間らしい色だ。遊馬。お前が今見せたような」
血の気の失せた、青褪めた死体の色を思い起こす。トーマス・アークライトの中で死を迎えた少年と少女の色。それに手向ける花だからこそ花々はあの色でなくてはならなかった。彼らを喪った喪失の感情と、それを死として処理してしまった冷徹さの象徴として花々は青かった。
「俺達はお互いにたらたらの未練を胸に抱えてるんだ……あたかもそれは花束のように」
「別に俺、青い花買ったりしてないぜ?」
「お前が供えたの向日葵だろ。それは真月零がお前の中でまだ人間だった頃を象徴する色合いをしているはずだ。……つまりそういうことか遊馬。俺達は、単に同じ穴の貉だったと……」
「ん……そっか。すごいな、この、誰も救われない感じ」
「ああ」
胸元に提げてあるロザリオを服の上から押さえ、トーマスは吐き棄てた。
「クソったれが」
祈るべき神がいないのに、一体この十字架を誰に向けて懺悔すればいいのだろう?
既に空には星が出ていた。川面は変わらず凪いでいる。見上げてもまばゆく光る真円がないない。今夜はつごもりの夜であるようだった。新月なのだ。
それぞれに帰る気もしなくて、ぼんやりとコンクリートの上に座り込んだ。トーマスの手の中にはあの鈍重なロザリオが握られている。西洋のデザインらしい重苦しいロザリオは、皮膚に食いこんだら簡単に血を流させてしまいそうな形をしている。
「どうしてあいつらは消えちまったんだ」
思い出したようにトーマスが尋ねた。あいつら、という言葉が誰を指示しているのかはもはや明白だった。
「理由があるんだろう」
「神代凌牙と神代璃緒はバリアン七皇だった。そっちに本拠地を移すから、人間として生きてきた時間が邪魔になったんだ。憶測だけど、そんな感じだと思う。体は一つしかないからな。まあ、やろうと思えば分身作れるのかもしれないけど最終的に二人は人間ともアストラル界とも決別する選択をしたから、人間としての自分を消すしかなかったんだ」
「あいつらは俺の敵なのか」
「どーかな。明確に敵対してるのはアストラルだろうし、俺はアストラルよりもあいつらの方が間違ってると思ってるから、シャークを止めるためにも敵対しちゃうことになるんだろうけど……トーマスのことはもしかしたら考えてないかもしれない。シャークもシャークで大変なんだ。どうも色々情報が増えすぎて、うまく処理出来てない感じがしたから」
「はー……俺の方はこんなに頭を悩ませてんのに、向こうは歯牙にもかけてないかもしれないって? たまったもんじゃねえな」
自然と深い溜息が漏れた。出来ることなら綺麗さっぱり、花を手向けることさえ忘れてしまいたかった。
「やっぱり夢は見てたよ」
「あ、そうなんだ」
「毎晩毎晩、それでぐったりだ。……聞いて笑うなよ。その夢の中じゃ、俺と璃緒が婚約してて、凌牙と俺は幼馴染で……家族同然だった。なんなんだろうな? 俺は、そういうことを望んでいたのか……?」
「?って妹シャークのこと好きだったのか?」
「知らねえよ。俺が知りたいぐらいだ」
「でもその夢、結構いい夢だったんだろ」
「……否定はしない」
「じゃ、そうなんだな。夢は願望の表れって言うし、心のどこかで、自分でも気が付かないうちに好きだって気持ちをもてあましてたんだよ」
遊馬はやっぱりわかったふうに言う。でももう、同じ境遇の少年につっかかる気はなかったし、その元気もない。
吼えるのにはそれなりの体力が必要なのだ。
「……璃緒は」
「うん」
「俺が……大やけどを負わせただろ。助けた時、俺自身死にかけでそりゃもう必死だったんだが、その時抱き上げた璃緒の体がやたらと軽かったことを、俺はいつまで経っても考えてるんだ。羽みたいって言うと聞こえはいいかもしれないが、実際のところあれは幽霊の重たさだった。死人を抱き上げているみたいで」
「うん」
「俺はこの女を離してはいけないと思ったんだ」
璃緒の体に、後遺症らしい後遺症は最終的に残らなかったのだという。トーマスが身を挺して庇い救い出したから、目に見える傷は彼女からみんな離れて行った。しかし凌牙の方でそれを強烈な憎悪として刻み込んでしまったため、彼女の中にも少なからず複雑な感情として目に見えない傷跡は残った。
それを喜んでいた自身を嘆かわしいと断じてやれるほどの善人さはトーマスには最初からないけれど。
「事故の責任をどんな形でもとるっていう決意は半分は口実みたいなもので、ただ、あの火事が風化してしまわなければ俺と璃緒を繋ぐものが残り続けるだろうっていう打算もあった。欲と罪にまみれたどす黒い赤い糸だ。人為的で汚い。運命なんて、そこには欠片もないだろうさ」
「?って運命信じてるんだ?」
「信じたがっちゃ悪いかよ。都合のいい偶然は喜びたいだろ、人間なんだからよ」
「人間か……」
人間。遊馬の小さな口の中で反芻された言葉は、そういえばさっきの独白の中でも度々使われたものだった。人間じゃなかったから、だから、いなくなった、と。
「なあ?、俺さ、神代凌牙と神代璃緒は、紛れもない人間だと今でもそう思うよ」
「ああ?」
「あの二人は人間だ。だからきっと……」
「なんだよ」
「きっと帰ってくるよ」
それは小さな声だったが、トーマスの耳によく響いた。
「遊馬、お前は、夢を見るのか」
立ち上がって、別れ際に興味本位でそれを尋ねた。夢は願望の表れだからもしかして、と問いかけてきた遊馬自身はどんな夢を見ているのだろう。純粋な好奇心だ。遊馬はそれを聞かれると「あー、うー、」と呻き、トーマスの顔を見上げてくる。
「別に人に話せない内容じゃないんだけど、お前はなんか鼻で笑いそうだから嫌だ」
「笑わねえよ。言え」
「うえー……」
でもさあ、ほら……と尚も言い淀む。まどろっこしい。
「早くしろ」
声にわざと苛立ちを滲ませて催促をする。
「馬鹿になんてしたりしない」
でもちょっと意地悪くしたり顔をして。
「本当に、本当の本当に馬鹿にしたりしない?」
「約束は守るぜ」
「うーん……あのさ」
それでも遊馬は、まだ滑舌が悪くてはっきりしない。遊馬の右手が首に提げられた皇の鍵に伸び、お守り代わりに触れた。それからトーマスのロザリオに触れる。理由はわからない。単に触ってみたかったのかもしれない。
「アストラル界の人達も、バリアンのやつらも、俺達も、分け隔てなくみんなで幸せに不自由のない世界を生きている夢を、俺は見るよ」
遊馬が囁いた。
見上げた遊馬の頬が僅かに染まっていたことが、あたりがとっぷりと暗く暮れていたのにも関わらず、どうしてだかその時トーマスにははっきりとわかったのだった。