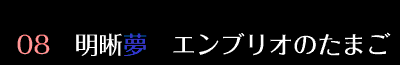
「これがきっとあなたが見る最後の夢になるわ」
璃緒は顔を向けないまま宣告をした。トーマスは曖昧に頷いて彼女の隣に座る。座る、という動作を起こすことでそこに見慣れた——夢の世界で、だが——ソファーが現れた。アークライト家の、子供達がしょっちゅうたまってはだらだらしていた部屋に置かれていたシックなワインレッドのソファーだ。
理由は分かっていた。もうぼちぼち、夢から覚める時間が迫ってきていた。
「楽しかった?」
璃緒が手を伸ばすと、そこにテーブルと籐の籠、その中に入れられたテレビのリモコンが現れる。リモコンを手に取り電源スイッチを彼女が押すと同じように虚空にテレビが現れた。
「恋人ごっこ。……ううん、違うわね。そんなに簡単な問題じゃないわ。家族ごっこ? それとも幸せのシミュレート?」
あたりは深い霧に包まれていて、古いが高級な壁紙も、天井も、そこからぶら下がったシャンデリアも見えなかった。右も左もなく、上も下もない。かろうじて足が触れているカーペットは視覚化されていたが、それも部屋の形になる前にぼやけて途切れてしまっていた。
「贖いごっこは、さぞや満ち足りたものだったでしょうね……」
トーマスがそこが夢だと自覚してしまったから、構築が追い付かないのだ。彼は既にここを現ではないと自覚してしまった。
信心深くないものを夢は慰めてはくれない。
「あなたの贖罪は、独り善がりよ」
璃緒の顔は酷く恨みがましかった。
幼馴染の婚約者。お互いに、結婚するという未来を受け入れている。その先に幸福を思い描き、二人で手を取って、毎日やってくる怠惰な平穏に身を浸している。
「夢は現実の続きでもあるけれど、つまるところ、還るところとして、現実は夢の終わりなのよ。夢に現実の埋め合わせを強いていたあなたがそのことに気が付いてしまったから、幸せな夢は終わるの」
「そうして現実に帰ると?」
「そうね。だからあなたがお墓に花を供えることも、もうじき終わるのでしょうね」
関係性を隠すことなく、二人で同じ学校に通って、毎日一緒に過ごして。ずるずるだらだら、恋人のいる春を謳歌する。
青春ごっこ。現実のトーマス・アークライトには輝ける青春は存在しなかった。幼い頃に父の失踪で一家はばらばらになり、再び集まった家族は見るも無残な復讐鬼に姿を変えてしまっていた。
優しかった兄は厳しく恐ろしい表情ばかりするようになった。純粋無垢だった弟すら憎しみの感情を知った。父親は悪魔のような子供になって子供達を道具として扱った。そこに幸福など入る余地があるだろうか? トーマスに出来たのは、恨むことだけだ。
家族を引き裂いたものたちを、トーマス・アークライトは恨んだ。
そして同時に、神代凌牙に嫉妬したのだ。父親が、それを自分より役に立つ道具だと評価したから……。
「考えるだに惨めよね、あなたの人生って」
「……否定はしない」
「人生で一番充実して輝いてるって一般に言われている時間を、名前を奪われ、復讐の道具として生かされていた気分はどうだった?」
「最低だよ。だが、もうそれも終わった。俺達家族の復讐は終わったんだ。結局それは意味のないことだった……」
「それって一番どうしようもないじゃない」
璃緒は無慈悲な声で言い放った。
「あなたのしてきたこと、全部無駄だったんでしょ?」
「な……」
「突き詰めればそうよ。極東チャンピオンになったことも、毎日毎日神経遣って嘘の愛想笑いをし続けたことも、心を削って父親に奉仕したことも、何もかも全部無駄だったのよ。あなたはそれによって何を得ることもしなかったわ。残ったのは疲弊と虚無感だけ。違う?」
「だが……ミハエルは友人を得たし……」
「私、あなたの話をしているんだけど」
つまらなそうに、「ばかなの?」と見下した表情で尋ねてくる。神代璃緒の二つ名を「氷雪の女王」というのだと思い出してげんなりする。不良鮫の妹が女王とはとんだ兄妹ではないか。
しかしその仮面の下が、年相応の少女であったこともトーマスは知っていて、一層複雑な気分だった。
「それともなあに? 私をあの炎の中から助け出したこと、一人で満悦して恩着せがましいことでも考えてるの? これでもう私はあなたのことを忘れられないって?」
「…………」
「それこそ、惨めな思い込みというものよ。神代璃緒はトーマス・アークライトのことなんかどうとも思ってやいないんだわ」
「やめろ……」
「あなたみたいなどうしようもない男のことを好いてくれる優しい女の子が、いるわけがないじゃない?」
「やめてくれ……頼むから……」
「思い込みを押し付けないでちょうだい。何がどうしたら自分を傷付けた男を好きになるって言うのよ。そのあと助けたことなんて微々たることだって、あなたわかっているんでしょう」
「お前は……璃緒の顔をしているが、結局、俺の心の中に棲んでいる璃緒の投影にすぎないんだ。お前は俺だ。だから、もう、許してくれ……!」
叫んだ。ガン、と振り下ろした拳が机をすり抜ける。机というオブジェクトがデジタルホログラムのようにぶれて、そしてすぐに再生された。
ここはトーマス・アークライトの心の部屋なのだ。だからトーマスの精神の不安定さがそこに現れる。目に見える少ない家具たちが、電波が波打つようにぶれ、揺らめいて、トーマスの荒い息遣いと共に再構築され続けた。
璃緒は足を組んだまま、トーマスの胸ぐらを掴み取る。
「うそつき」
そしてずいと顔を寄せると、瞳を見開く。血の色をしていた。
「本当は許してほしいなんて思っていないくせに」
反射的にはねのけた。押し倒された璃緒の体がのけぞり、ソファーに沈み込む。心臓の音がうるさい。規則性を無視して、トーマスの鼓膜を苛む。
「許してくれ……もう、たくさんだ……!」
「許して? 変なことを言うのね。何を許してほしいの? 神代璃緒に爪痕を残したこと? それとも蓋をして見ないふりをしてきた気持ち悪い自慰を暴かないでほしいの? もっと他の何か? だけどね、トーマス・アークライト、そんなことしたってあなたは救われないわ」
「わかってる……わかってるんだ……」
「あなたを許せる人は、もういなくなってしまったのよ」
少女が宣告をする。
それきり璃緒は——璃緒の姿をしたものは、黙り込んでしまった。
◇◆◇◆◇
ソファーの下はすっかり水たまりのようになってしまっていた。突然どしゃ降りの雨が通り過ぎていったかのような有様だ。水たまりは舐めると塩辛い。涙の海だった。
どちらの涙なのかはもうどろどろに溶けて混ざり合って判別がつかない。トーマスも璃緒も子供みたいに泣き腫らした顔をしていて、まるで夢の世界で過ごした子供時代の二人のようだった。
「……結局、俺はお前をどう呼べばいい?」
「神代璃緒」
「だがお前は俺なんだろう」
「あなたの目から見た神代璃緒よ。そういう概念を与えられていないから私はこの世界でこれ以外の姿を取れないわ。……これはあなたの理想の姿なのよ。想像上の、存在しない、都合のいい自動人形。あなた人形使いですものね。限りなく本物に近付いたギミック・パペットよ。自分で作った人形を代わりにして欲望を満たそうとしたの」
神代璃緒のオルタナティブ。お墓もそうだけど、と彼女は呟いてソファーの上でふてくされて体育座りをする。本物がいなくなったから創った代替品。
「本物の神代璃緒とはメールアドレス一つ交換できなかったくせに」
「うるせえ。俺がハートランドシティにいる間はあいつはずっと意識不明だったんだ」
「だからあんなに大きな花束を持って隠れるように手だけ握っていったの?」
「凌牙に見つかったら戦争になるからな」
「そうね。凌牙は自分の妹のことが世界で一番心配だから、胡散臭いファンサービス男なんかが手を握ってるところを見てしまったらきっとそうなるでしょうね」
目じりを赤くしたままくすくすと笑う。中学の制服のスカートの下から覗く細い両足は黒いソックスにぴっちりと覆われていて、余計に艶めかしく映った。トーマスは実際に彼女がこの姿をしているところを見たところがない。
一瞬だけそこに手を伸ばして、躊躇うように引っ込めた。たとえ彼女が本物でなくても神代璃緒であるのだから、それには触れてはいけないのだと思ったのだ。
それを認めて璃緒が二度三度瞬きをする。
「あなた、潔癖症なのか奥手なのか、どっちなの? 夢の中ぐらい自由にしていいのに、トーマスは結局最後まで手を握る以上のことをしなかったわ。キスもしない、セックスなんてもってのほか、古いしきたりにのっとって……あなたはそういうふうに言い訳をしたけれど、あれもあなたがした選択の結果なのよ。トーマス・アークライトそのものが神代璃緒をそれ以上穢してしまうことを怖がっていた」
「臆病なんだよ」
「臆病。確かにそうね。でも、『私』自身は、あなたが純潔を良しとする人間だったことを幸運に思うわ。この夢はトーマス・アークライトが支配するもの。あなたはその気になれば、『私』を犯すことも孕ませることも、暴力を振るうことも、檻に閉じ込めることも、なんだって出来たんですもの」
「そんなことして何になる。俺は最も紳士的なデュエリストで通っている極東チャンピオンの?だぞ。そんなばかげたことをどうして望まなきゃならない。虚しいだけだ。……第一…………」
「……なあに?」
「…………惚れた女を守りこそすれ、傷つけるなんてことは、俺には出来ねえよ…………」
「そうね。あなたはそういう人だったわね。ばかな人……」
心から悔いている表情で、絞り出すように告げるトーマスに寄り添う。肩にもたれると、トーマスと璃緒の体格差が明るみになった。現実でも、夢の中でも、トーマス・アークライトと神代璃緒は違う人間で、違ういきもので、男と女で……流れる血も違えば髪の色も違うし、肌の色も人種も違って、でも目の色だけは一緒だった。
「優しすぎたのよ」
「……それ、俺のファンサービスを喰らった奴らが聞いたら揃って首を横に振るだろうな」
「あなたはとても繊細な人。傷付くことを怖がって自分から殻にこもるのね。そうして自分が傷付くのが怖くて、過剰に防衛して相手を傷付けてしまうの。でも誰かのことを心から案じることが出来るし、それをまるで自分の痛みであるかのように感じることが出来るわ。優しすぎるの。凌牙と私が毒に犯されていた時も、そう……」
そして遊馬の痛みを分け与えられた時も。
「家族の痛みも一心に背負って、それで疲れるなとかまっすぐに成長しろとか、そんなこと、誰も言うことは出来ないのよ。夢ぐらい幸せなものを見て逃避したいっていうのは自然な願い事ではあるわ」
「だが俺の夢はもう終わりだ。夢から醒めることを俺自身が選び取った。そうだろ?」
「そうよ。それもまた残酷な優しさね。気持ちの押し付けに気が付いてしまったから、幸せな蜜月を続けることは良心の呵責が邪魔をしてもうあなたには出来ないのよ」
「……考えてみりゃ、俺はまだあいつに何も言ってないんだな」
「凌牙には言ったけど、本人には一言もないわね。ご挨拶なこと」
少女特有の細く頼りない指先がトーマスの頬の十字傷を撫でる。夢の中でさえ、この傷痕は消えなかった。どちらとも璃緒のために負い、そうして消せない罪の形のようにトーマスに纏わり続ける罰の形。
「よく見るとこの傷、十字架みたいな形をしているのね」
璃緒が息を吹きかけるように言った。
「でもきっとあなたは聖職者には向かないわ。告解を全部自分の罰のように受け入れてしまいそうだから」
人差し指で十字を切るように傷をなぞると、くすぐったいのかトーマスはむず痒そうな表情をしてその指を摘みあげて離した。
「ね、トーマス。あなた、この傷と一緒にずっと背負っていくんでしょう?」
「ああ」
「お墓、もう一度行くの?」
「あと一回だけな。けじめが必要だろう。そうしたら俺は璃緒に告げるつもりだ。自分勝手ですまないが、俺はやはりお前のことを喪いたくなくて……だからこの傷痕は決して消えてなくなりはしないのだと……」
「そう」
璃緒はトーマスの言葉をもう咎めない。トーマスは二度三度瞬きをし、彼女の目を真っ直ぐに見つめた。石榴の色をした瞳の中に、まるでプラネタリウムのように、長い永い夢の思い出を投影する。
「永遠に」
そうして目を瞑り、また見開いて、彼は決別の言葉を口にした。
◇◆◇◆◇
立ち上がると、ソファーが消え、テーブルも消え、その上に載っていた種々のものも、テレビも、果ては足元のカーペットも綺麗さっぱり消え去った。決別の挨拶みたいに、夢の名残がなくなっていく。
足元の水たまりだけが形のあるものとしてそこにわだかまる。流した涙は蒸発しない。
「夢が覚める前に、一つだけ、わがままを言っていいか?」
「どうぞ、好きにして。わがままも何もないわ、結局私もあなたの作り出した幻みたいなものなんだから……自分に言い聞かせるのにわがままも何もないでしょう?」
「……そういうこと言うなよ……」
頭を抱えて溜息を吐いた。仮にも、好きな女の顔をしたものにそう言われるのは興ざめでしかない。
しかし璃緒の方はそれをわかってやっているようで、余計にたちが悪い。
「キスをしよう」
気を取り直して彼女の手を取った。それは夢の中で彼女とした一番大切な約束事で、未だに果たされていないものだった。宙ぶらりんのいつかのエンゲージ。トーマスの見た夢の中で最も重たい誓約でもある。
しかし璃緒は毅然とした態度できっぱりと首を横に振り、それを拒んだ。
「それは出来ないわ」
「何故だ?」
「今となっては、もうそれは私の役割ではないからよ」
璃緒が悪戯っぽく微笑んだ。トーマスの心が作り出した、その中に棲む璃緒を投影した姿だと思っても、彼女のその仕草は疑いようもなく神代璃緒の姿で、美しく、愛おしく、
「それは、本物の神代璃緒にお願いすることね」
どうしようもなく儚くて、トーマスはただ彼女の幻を抱きしめた。