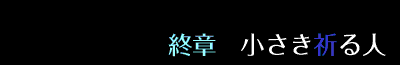
これで墓を訪れるのが何度目なのか、もうトーマスは数えていないし考える気もなかった。小さく粗末な墓の前には相変わらず気が狂ったように花束が積み上げられている。青い花。トーマスの未練が具象化されたような、青褪めた死人の花達。
同じく青い花を握りしめている自らの指先を、開き、握り、単純な開閉運動を繰り返す。ミハエルに死が見えるようだと言われた指先には、確かに花の色素で青く染色されたようなしみがついていて、死の警句を思わせた。
最初のうちに供えたいくらかの花が腐り落ちて、土の中に還ろうとしている。あまり心地の良くない感触。だが不快な臭いはしない。世界に痕跡を残さないようにした墓の中の二人のようだと思う。死してなお美しく爪痕を刻もうとする。
「璃緒……凌牙」
手にしたブルーファイアーとネモフィラの花束を手向けた。あんまり同じような花ばかり買うものだから、近頃はとうとう花屋の店員に青い花を買う男として記憶されてしまっていたらしい。この花を買う時、店員は何も言わずにブルーファイアーの花を束ね、そうして「今日はネモフィラがいちだんと綺麗に咲いているんですよ」とその中にネモフィラの花を突き刺して花束を拵えてよこしたのだった。
「ネモフィラが一面に咲いているのを、『ネモフィラの海』って言ったりするんです。お兄さん、この花がお好きみたいですから一度行ってみたらどうでしょう。ちょっと遠いんですけど、国立の海浜公園ですよ。丁度、春の終わりから夏先にかけて、それはもう幻想的で……」
「いや……そのうち、考えておくよ。別段この花がそんなに好きってわけでも、ないし……」
「あら、そうなんですか? ごめんなさい、てっきりそうなのかと。そうしたら、彼女さんが好きなのかしら。いいお花ですものね」
「彼女?」
「うふふ。そうでしょう? この花は女性に贈られる方が多いんです。和名は瑠璃唐草といって、たおやかな印象がありますから。花言葉も素敵なんですよ。『絶対の成功』、って言うんですって」
「絶対の成功、なんてさ。璃緒らしいな。お前は本当に強い女だよ。俺は負け続けだ。デュエルだってあんなせせこましい手を使ったとあれば俺の負けみたいなものだし、それから先リベンジする機会も特になくて、まだ一度も勝てたためしがない」
墓は初めて訪れた時よりも明らかに美しくなり、苔むしていた石は磨きこまれ、多少なりとも見られるものになっている。「潔癖症なのね」夢で聞いた璃緒の声が蘇った。大切な人が眠る墓を、汚れたまま放っておくことはどうしても出来なかった。
「俺は、まだお前に謝罪の言葉一つ贈っちゃいないんだな……」
誰もいない墓の中に花が還っていく。花葬。このいっそおぞましいほどの花の量は、花で死体でも拵えるためだったんじゃないかと他人事のように思う。
帰ったらミハエルに謝らなくてはならない。だけどあの弟のことだから、素直に謝ったら謝ったで、クリストファーあたりに「トーマス兄様、何か悪いものでも食べたんでしょうか……」なんて相談しに行くのだろう。目に見えるようだった。トーマスは天邪鬼で負けん気が強い、というふうに思われているのだ。
概ね事実だが、自らの非を認めた場合はとことんまで殊勝になるのも事実だった。
「まったく……お前は俺の運命の女だったよ……」
ファム・ファタル。運命の女。神代璃緒はトーマスの心を縛り付けて離さない。
初めは贖罪だったのだ。彼女の人生を棒に振りかねない事態を招いたことの責任みたいなものを感じて、くずおれて震える手のひらを呆然と見つめたりした。火事で大火傷、全治一年以上、意識不明の重態。凌牙が来る前に病院に搬送し、付き添った中で医者にはそんなふうに告げられた。
助かったのは奇跡的なことです。完全に回復する見込みは低いですし、よしんば可能だったとして長い時を要するでしょう。そして、心の傷の方は……治るかどうか……。まだ真新しかった十字傷を包帯の上から抑えながらその言葉を聞いていた。治らない? 俺のせいでか?
俺がやってしまったのか?
しかしあの火災を引き起こしたカードをトーマスに渡した父親を憎みきることも出来ない。重たい感情だけがそこに残る。俺はいったい、どうすればいい?
どうにかして贖わなければならないのだと、そればかりを幾昼夜にも渡って考え続けた。
「この先璃緒より大きい存在感を伴って俺の心に棲みつく女なんていねえんだろうなぁ。言ってみりゃ、初恋だったんだぜ、これでもな。小さな頃はミハエルを守るので必死でそれ以外に目を向ける余裕はなかったし……極東チャンピオンの座についてからも、すり寄ってくるのはつまんねえ女ばかり……璃緒だけだったんだ。俺が自己紹介しても特に反応を示さない相手。『ああ、凌牙の対戦相手の方ですわね。存じ上げております』、とは驚いたぜ。兄貴以外の奴は眼中にないと言わんばかりに……まぁ……それは俺も同じか。俺も、家族以外はどーでもよかった……」
もしあの事故が原因で璃緒の人並みの幸せがこの先一生奪われてしまったのだとしたら? 後遺症で歩けなくなったり、酷い顔になったりして、それを嘆いたら? そんなことをだらだらと考えた。
いつだったろう。そうしたら自分が娶ってやればいい……そんなふうに自分勝手で、ぶん殴られても仕方ないようなことをちらりとでも考えてしまったのは。
挙げ句の果てにそれで償いになるとすら考えていた。それを思うほど、トーマスは多分、思い切り頭を殴られるべきだった。
結局そんな心配は杞憂に過ぎなくて、神代璃緒に後遺症は殆ど残らなかった。形のあるものもないものも両方だ。相変わらず彼女は万能で身体能力は男子に引けを取らないどころか完全に追い越していたし、学問にも秀で、完璧を絵に描いたような女だった。精神も同じ。気丈で、明るく、兄を残されたたった一人の家族として愛していた。
「許してくれなくていいんだ」
それを伝え聞いて、ああ、なんて馬鹿な思い込みだったのだろうとトーマスは思い知らされたのだ。自分なら彼女を幸せにしてやることが出来るのだと考えていたことがどんなにか酷い無知で浅慮な考えだったのかを突きつけられた。神代璃緒はトーマス・アークライトと一ミリも関係ないところで立ち上がり、幸せになり、本人もそうと自覚しないままトーマスを突き放して先へ歩いて行ってしまう。
隣には兄がいる。トーマスは必要ないのだ。
失恋に似た感傷だった。
「ただ、俺は自分勝手でわがままに恋をして、ひとりでにふられたような気分になって、そうしてその思い出すら奪われたからどこかに安息を求めようとしていただけなんだ。許してくれなくていい。だけど、許しすらせずに、忘れてくれてもいい。許されたくないっていうのは結局そうすることで俺を忘れて欲しくないっていう願望の転化にすぎないから」
胸元からロザリオを取り出す。ここしばらく着ていた喪服じみたモノクロの装いをやめ、復讐の象徴である「極東チャンピオンの?」としての服に身を包んでいるので、重たいロザリオはどうも場違いな印象がある。合わないのだ。クリーム色の衣装は、死を悼む服ではない。
でもそれでいいのだ。神代兄妹はトーマスの中で棺桶から起き上がって、どこかへ走り去ってしまった。二人は生きている。
「璃緒。凌牙。俺が傷付けた『人間の』兄妹……」
俯き、ロザリオを胸に掲げ、祈った。
「お前らのこと、俺は、嫌いじゃなかったよ」
祈りの最中に様々なことがトーマスの思考をかすめた。遊馬の独白により蘇った兄妹達とトーマスの関わりが走馬灯のようになって駆け巡る。初めて彼らを知ったのは確かトロンに与えられた写真でだった。次の対戦相手の写真だよ。かわいい顔してるよね。そんなふうに趣味の悪い声で父の姿をした悪鬼が囁くのだ。絶対に勝つんだよトーマス。良い子の君なら出来るだろう?
言われた通りに妹を手加減一切なく叩きのめし、兄を薄汚い罠にはめた。妹は病院送り。兄は汚名を着せられデュエルの表舞台から退場。トーマスが望んだことではない。けれど、手を汚したのは疑いようもなくトーマスで、?で、その事実は拭えないのだ。
どちらとも余裕はなかった。璃緒は強く、逞しく、勝つためには手段を選ばざるを得なかったし、凌牙には醜悪な退場劇を演じさせなければ、?はトロンに見捨てられかねなかったから。
?はトロンにとっての良い子、都合のいい操り駒であることを優先した。他人の人生と秤にかけてもう一度父に名前を呼んでもらいたいというエゴイズムを優先した。
その報いを、今になって知らしめさせられる。
もしも、そういうしがらみのない世界であの二人と出会うことが出来ていたら? トーマスは璃緒にやはり惹かれるのだろうか。凌牙とは、もっといい友人になることが出来ただろうか。何もなければ。今とは違う結末が得られただろうか。
黙祷の間トーマスは瞳を開かなかった。瞼を閉じた暗闇の中にあの炎が爆ぜて熱風の吹き荒れる火事の光景が蘇り、十字架を心臓の位置に強く押し当てる。
だから後ろから近付いてくる足音に気が付くのが、随分と遅れてしまった。
「——ネモフィラのもう一つの花言葉、知っているかしら?」
「……あ?」
「花言葉よ。知らないの? なら教えてあげる」
声がする。女の声だった。少女だ。勝気な少女の、かわいげのない声。その声はトーマスの頭上から降り注ぎ、感傷に浸る思考を中断させた。
細く華奢な腕がすっとトーマスの横を伸びてすり抜けていくのを風の動きで感じる。もさりと花束が押されて揺れる音。そのままぶちりとむしる音が続いた。閉じていたまぶたを慌てて開くと、ちょうどネモフィラの花が摘ままれ、白い指先に持ち上げられていくところだった。
腕の動きを追って顔を上にあげる。ワンピースを着た少女がネモフィラの花を数本束ねて持ち、それを鼻のあたりに近付け、香りを嗅いでいた。
聖書を元にした絵画のような粗雑で俗っぽい美しさがその中にはあった。少女は人間だった。トーマスが知っている人間の姿をして花を持っていた。
「ネモフィラのもう一つの花言葉はね、『私はあなたを許します』と、そういうのよ」
そうして彼女——神代璃緒は、手にしたネモフィラの花をトーマスに向けて投げた。
「何よ、泣きそうな顔なんかして。情けないわね。それに少し、気持ち悪いわ」
「おまえ……おまえは……」
「おまえ、おまえって、人のことちゃんと名前で呼ぶことも出来ないの? 紳士が聞いて呆れるわ。ファンサービスがモットーなんだからそのぐらいちゃんとしなさいよ。それとも私の名前なんて、もう忘れちゃったのかしら」
「忘れたりするもんか。璃緒。神代璃緒」
「呼び捨てなのね。まあいいわ……何かつけられた方が、変な感じがしそうだし。『イモシャ』なんて呼ばれるよりはずっとましですもの」
「本物なのか? それとも俺はとうとう、幽霊の姿を脳味噌が作り出すところまで追い詰められているのか?」
「失礼ね。生きてるわよ。ほら、こうやって手と手を合わせると、触っている感触がするでしょ」
ロザリオから手を引きはがされて、指と指が強引に合わせられる。夢の中で何度かしたのと同じように、男と女の手のひらの性差がそこにあり、体格差があり、感触があった。柔らかい。そして少し力を込めれば、簡単に砕けて飛び散ってしまいそうに儚い。
実際に彼女の声を聴くのは、もう一年ぶりぐらいのことだった。デュエルをした時以来だ。そういえば、あの時彼女は、炎にまかれたことに関して恨み言をトーマスに向けて言わなかった。
「璃緒……」
「なぁに」
「俺は……俺は、お前に、伝えたいことがたくさんあるんだ……」
「そうね。私も、あなたに言ってあげたいことがあるの」
「ああ……。なんでもいい。なんでも、言ってくれ。罵りの言葉でも、失望の言葉でも、別れの言葉でも、なんでも」
「ネガティブな選択肢しかないじゃない。あなたってマゾヒストなの? ——それに人の話をちっとも聞いていないわ。私が今さっき教えてあげたネモフィラの花言葉、もう忘れてるわけ」
「……『私はあなたを許します』?」
「そうよ。まだわからないの」
璃緒がしゃがみ込んで、トーマスに目線を合わせる。彼女を炎の中から助け出す一度だけ間近に見た赤い瞳は、火を映し込んで朱色に染まっていたあの時よりも、もっと可憐な紅梅の色をしていた。柘榴色。何度か忍んで訪れた病院では、それは包帯に覆われて一度も見ることは叶わなかった。
「あなたが私の病室に何度か訪れていたこと、私、知ってるのよ」
顔が埋もれてしまうほどの大きな花束と、誰も食べない果実の詰め合わせを持って来ていたことをよ。璃緒がぽつぽつと喋る。そうして返事が返ってこないと知りながら声をかけ続けたことも、私は知っているのよ。
「あなたのうちでは、私に聞こえてるっていうカウントになっていないのかもしれないけれどね。本当は全部覚えてるの。凌牙と絶対に鉢合わせしないように必ず平日の午前中を選んで、身の上話とか近況報告とか、してたわね。喋ることで楽になろうとしていたみたいだった。それで実際に楽になれたのかどうかは、知らないけれど」
「あ……わ、悪ぃ。聞こえてるとは思ってなくて……殆ど、壁打ちみてえな、そういうつもりだったから……」
「別にそのことをとやかく言いやしないわよ。ともかく、その中で一つだけ、私がすごくよくはっきり覚えてる言葉があるの。これから先もきっと忘れられないわ。私が人間の神代璃緒を棄てられない限り……凌牙が、神代凌牙という個人を縁の強さで捨てきれないのと同じぐらい確かに」
柘榴の瞳がトーマスを射抜く。まっすぐに。ひたすらに強く。神代璃緒という女の強さをぶつけるように、彼女は墓に花を供えていた男を見遣る。
「『幸せになってください』」
鳥のさえずりが聞こえた。
風が吹き抜けて、敷地に生えている木々を揺らす中をハミングバードが飛んで消えていった。璃緒の唇とトーマスの唇が触れ合い、合わさって、そしてまた離れていく。二人してまぶたを伏せり、そして睫毛がぶつかった。いつの間にか手に持っていたロザリオはトーマスの手の中から離れ、ぶらぶらと、首から下がって不恰好に揺れていた。
風も草木も、太陽も雲も鳥も世界中の何もかもが、スローモーションで見えるようだった。その時世界は停滞していたし、その中で二人は生きていた。呼吸をしていた。
そして、キスをしていた。
「……どうして」
トーマスが呆然として零すと、璃緒が首を振る。
「夢の中で約束したこと。まだ、してなかったから」
「……はあ?」
「あなたから見た私って、あんなふうなのね。なかなか興味深いものだったわ。ねえトーマス」
「お、おう」
「あなた、顔が真っ赤よ」
かわいいひとね。璃緒が微笑む。意地悪く「それは私の役割ではないから」と突き放した最後の夢で見た璃緒の幻の姿とすっかり一緒の笑い方だった。すごく眩しくて、目が眩んでしまいそうになり、手放したくなくなるような名残惜しさを彼女は持っている。
「おまえ……まさか……」
「案外子供っぽくて、びっくりした。でもちょっと突飛じゃない? あなた私との間に本気で子供なんて欲しがってたの? 凌牙が知ったら生半可なことでは済まされないと思うから、覚悟しておいた方がいいんじゃないかしら」
「あれは、俺一人で勝手に見ていたものじゃないのか」
「共有夢って知ってるかしら。潜在意識のシンクロニシティが起こってそういうことがあるらしいわ。私と凌牙は双子だから、しょっちゅうだった。どうも、私って元々受信してトランスしやすい体質みたいなのよね。あなたの夢は明確に私に充てられていたものですから」
「……なんだよそれ。俺一人でばかみたいに……恥ずかしい……」
「恥ずかしいのは私の方よ。男の子の願望を追体験させられてるんだから」
璃緒がむくれたふうに言う。しかしそれから目を細めて、とても愛おしいものを見るようにトーマスの十字傷に触れ、それを指先でなぞり、
「だけどちょっと嬉しかったわ」
そんなふうなことを、息のかかりそうな距離で教えてくれた。
リトルプレイヤー・END