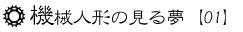海馬コーポレーションとインダストリアルイリュージョン社が共同主催を務める「グランプリ・リーグ」も決勝まで順調に試合が進み、残るは今大会チャンピオンの初代決闘王へのチャレンジマッチのみとなっている。状況は決闘王のライフが一二〇〇、チャレンジャーのライフが五〇〇とややチャレンジャーの側が厳しくなっていた。だが、あの武藤遊戯のライフに傷を付けられるデュエリストなどというのは海馬瀬人以外にはこのチャレンジャー一人ぐらいのものだ。圧倒的な神の威圧の前でもなおワクワクと楽しそうにカードを繰る男は遊城十代をおいて他にはいない。
「『E・HEROネオス』に『ネオス・フォース』を装備。このカードの効果でネオスの攻撃力は八〇〇ポイントアップし、装備モンスターがモンスターを破壊した時、破壊されたモンスターのコントローラーはそのモンスターの攻撃力分のダメージを受ける! 俺は『ブラック・マジシャン・ガール』を攻撃対象に選択。いっけえネオス、『ラス・オブ・ネオス』!!」 「罠発動、『ブラック・スパイラル・フォース』! このターン、指定されたモンスター一体の攻撃力を二倍にする。オレは『ブラック・マジシャン・ガール』を選択。残念だが返り討ちだぜ十代、『黒・魔・導・爆・裂・波』!!」 「えっ?! うわ、あ、うわああああっ!!」 遊戯の高らかな宣言と共にブラック・マジシャン・ガールの一撃が決まり、十代はソリッド・ヴィジョンのネオス共々ステージに倒れた。アタック四〇〇〇の強烈な一撃がチャレンジャーに直撃したことでデュエルに決着が着き、会場は王者を賞賛するコールとチャレンジャーの健闘を称えるコールでわっとわれ返る。ネオスのヴィジョンが消えたのを確認して十代は立ち上がり、ぱんぱんと衣服を払った。それから名誉ある王者との対戦に敬意を込めて彼に握手を差し出す。 『原初にして至高、あらゆる頂点に今なお君臨する生ける伝説、初代決闘王武藤遊戯に五回目のチャレンジをするもやはり歯が立たず! チャレンジャー遊城十代またしても勝利はならなかった! やはり王者の不敗神話の壁は厚いか! ……いやしかし、チャレンジャーもまたその実力は年々師を追い止まるところを知らず、現行リーグでは向かうところ敵なしの天才。武藤遊戯、あまりにも圧倒的だ!!』 「また勝てなかったぁ。やっぱ師匠は強いや」 「狙いは悪くなかったが、想定が甘かったな。再戦は次のグランプリで優勝したらまた受けてやるよ。……帰ったら相棒と反省会だぜ、十代」 「勿論です。よろしくお願いします」 ぺこりと頭を下げて意気揚々と楽しそうに十代は言う。遊戯は十代の師として彼に応えた。現在は現役を引退しこうしてエキシビションマッチやタイトルをかけた挑戦に応えてステージに上がるのみの「生ける伝説」初代決闘王武藤遊戯は、普段は「天才寵児」二代目決闘王遊城十代の師匠として彼に指導を行っている。 「ネオス・フォースを装備してブラック・マジシャンとブラック・マジシャン・ガールの攻撃力を上回る。狙いはそんなに悪くないんだけどちょっと単純すぎたかな。もうちょっと伏せカードの警戒をした方がいい。ブラフかもしれないけど、逆に言えば魔法の筒やミラーフォースかもしれないでしょ?」 ボク、いつも言ってるじゃない。遊戯に言われて十代はしょんぼりと頷いた。十代はその生まれ持ったデュエル・センスがあまりにも卓越し過ぎているためにそれに頼りがちな傾向があると度々二人の遊戯に指摘されているのだ。気を付けているつもりではいるのだがこう肝心なところで無防備では意味がない。 「徹底除去しろとまでは言わないけど、勝ちを焦らないでカウンターか何かを仕掛けておいた方が安定するんじゃないかな。ま、もう一人のボクも十代くんみたいに突っ込むプレイングを結構するから、きみだけの問題じゃないけど」 『て、手厳しいな相棒』 「本当のことだからね。……でも、何はともあれリーグ優勝五連覇おめでとう十代くん。引きの調子は今回も安定して良かったね」 「仲間達のおかげです。俺はデッキを信頼していて、デッキも俺を信じてくれる。だから俺はもっと強くなれる」 『くりくりっ!』 十代の言葉にハネクリボーが力強く賛同した。ぱたぱたと羽ばたいている毛むくじゃらの精霊は撫でてやるとくりくりと嬉しそうに鳴いた。 「ハネクリボー、元気そうだね」 「はい。ハネクリボーも俺と同じぐらい遊戯さんのことが大好きですから!」 にこにこ笑う。この屈託のない、純粋そのものの青年のことを二人の遊戯はとても好ましく思っている。彼は夢みる少年がそのまま大人になったような、そんな青年だ。いつまでも夢を追いかけている。ワクワクして、ドキドキして、世界のうつくしさに憧れを抱いている。 けれど時々、そのままの人間で良いのかと疑問に思う時もある。十代に分別が足りないわけではない。だけどどうしてだか、彼はもうちょっと大人びた青年だったのではないかと思わずにいられない時があるのだ。 「師匠、遊戯さん、今度はどのくらい日本にいるんですか?」 『相棒次第だな。もうしばらくはじーちゃんに顔を出していたいし、まあ次のリーグまで多少時間があるからどこか行くにしても十代、お前を連れてになるだろうが』 「そうだね。海馬くんともなかなか落ち着いて話す機会がないから今度のお誘いは断らないつもりだったし……一週間ぐらいはこの町にいようか」 「わかりました。あの、そしたら、今度はどこに行くんですか?」 十代がきらきらした目で聞いてくる。ははあ、これはおねだりのサインだなと感じて遊戯はくすくすと目を細めて笑った。子供が旅行に行きたがっている時にねだる態度と、よく似ている。 「行きたいとこ、あるかい」 「えーっと……あ、あそこ、ヴェネツィアとか。イタリアの」 『イタリアか、そういえばそっちはまだ行ってないな。美術館も多いし悪くないんじゃないか』 「ふふ、いいよ。でも珍しいね十代くんが自分から志願するなんて」 「なんか、急にぽっと出てきて。あそこに行ったら何かあるんじゃないかってそう思ったんです」 「そっか。何かあるといいんだけどねえ」 遊戯が弟子の十代を連れて世界中をぶらぶらしているのには理由がある。一つは世界中で経験を積ませる武者修行のためだ。そしてもう一つ、一番大事な目的が「名前の手掛かりを手に入れる」ことである。 武藤遊戯と共存しているもう一人の遊戯――太古のファラオの魂には名前がない。神を束ねる名前が失われてしまっているのだ。遊戯は彼の名前をもう何年もずっと探している。しかし手掛かり一つ掴むことが出来ずに既に十年近くが経過してしまっていた。パズルが組み上がるのにそもそも数千年が掛かっているのだから気に病むことはないと名を喪失したファラオたる彼はそう言うが、責任を感じずにはいられないらしい。 「……名前、早く見つかるといいですね」 『ああ』 それを知っている十代がぽつりと言うと、もう一人の遊戯が頷いた。だがその隣で遊戯はなんだか寂しそうにでもね、と首を傾げる。 「もう一人のボクの名前を、本当はもう知ってるんじゃないかってボクは時々不安に思うんだ」 ◇◆◇◆◇ 「あなたのお父さんから出掛けに手紙を預かったわ。一応、目は通してあげてちょうだい。あなたのことを心配してくれているのだから」 「……。その辺に置いておいてくれ」 「駄目よ。今開けなきゃあなた、ずるずると開封をしないでその内ゴミ箱に入れちゃうもの」 学生服のアキが聞き分けのない幼馴染に手紙をずいと押し付けている。押し付けられている方の遊星は嫌そうに眉を顰めていたが、封筒の鋭い角がいつ頬の皮膚を切り裂くかもわからないという懸念に負けて渋々彼女からそれを受け取った。監視されながら嫌々封を開ける。中に入っている手紙には決して汚いわけではないがしかし綺麗とも言い難い手書きの文字で文章が綴られていた。 『パパの大事なゆーくんへ。近頃連絡がないのでパパはすごく寂しいです。お金に困っていたりしませんか。何か騒動に巻き込まれていたりしませんか。ご飯はちゃんと食べていますか。睡眠は毎日五時間は取ってください。アキちゃんに優しくしてあげること。友達と喧嘩したら謝ってね。たまにはお家に帰ってきて欲しいです。パパはすごく寂しいです。また手紙を送るよ ゆーくんが大好きなパパより 追伸、最近ママが冷たいです。倦怠期?』――すごくどうでもいい手紙だと心底遊星は思った。 ぐしゃぐしゃに丸めて速攻でゴミ箱に投げ入れる。軽い音を立てて丸まったゴミは箱の中にストレートで入った。後は見向きもしない。いつもこんなものだ。 「またそんなぞんざいに扱って」 「母さんには定期的に連絡してる。それで問題ないはずだ。自立して収入も得ていて、やりたことをやっているんだ。父さんにあれこれ言われたくない」 「気持ちは、わからないでもないけど……」 アキは溜め息を吐いて幼馴染の青年を見た。彼、不動遊星は大抵の場合バイクを弄るかコンピュータに向かうかの日々を過ごしているメカニックだ。職業は何でも屋。エンジニアとしての資格は山程持ちあわせているし大学博士号も特殊カリキュラムを利用して取得していて、その上家柄も悪くないエリートなのだが父に反抗してこんな生活を送っている。実家のあるトップスを飛び出して学生時代の仲間達とつるみ、現在はWRGPに向けて資金調達とD・ホイール、それからデッキの強化に明け暮れている。 中学校に上がった頃から、思春期に突入したのか遊星は自分にだだ甘い父親に反抗的になっていった。甘えているよりはいくらもましだとは思うがしかし遊星の反抗は時々度を過ぎていると思う。学生時代はチームを組んでワルぶっていた時もあった。尤もチームメイトが皆根のいい人間ばかりだったので非行に走っているつもりで治安維持ごっこをしていたに過ぎなかったのだが。 アキは遊星と生まれてからの付き合いになる。親同士に縁があり、住居が近かった二人は兄妹のように育てられた。遊星はアキの面倒を見るように言い付けられていたしアキは遊星と一緒にいるようにと言い付けられていた。不動家の嫡男は頭脳明晰で人あたりもよく、出来た子供だったし言われたから仕方なくといったふうでもなく自然にアキに接してくれた。サイコ・デュエリストの能力が暴走した時も遠巻きにせず身を挺して助けてくれた。 アキは遊星が好きだ。高校に上がって告白して了承を貰い、今は彼と付き合っている。ゆくゆくは、結婚もしたいと考えている。だが遊星にはまだその気がないらしく、それとなく尋ねた時には「アキが大学を出たら、反抗気も潮時かもな」などと言っていた。確かにこの生活ではアキの父に下げる頭もないだろう。遊星が大のお気に入りのあの父なら彼が気にしているほど職業にはこだわらないような気もするが。 「たまには顔を出してみたらどうなの。時々うちのお父さんにも愚痴ってるらしいのよ、あなたのお父さん」 「面倒だ。いい年して、いい加減に息子離れの一つもしていない方がどうかしてる。母さんには会っているし電話もしているし」 「あなたそれじゃ、ただのマザコンにしか見えないわよ」 アキはもう一度溜め息を吐いた。不動父子の溝はそこそこ深い。 「ゆうせーい、あれっアキ姉ちゃん。何々、遊星また博士の手紙捨てちゃったの?」 「あら、二人とも今日は学校早かったのね」 「うん。ホームルームがいつもより早く終わったのよ」 アカデミアの制服を翻して双子がガレージの階段をとんとんと下って来た。トップスに住むこの幼い双子は、遊星が学生だった頃に学区が一緒で色々と面倒を見ている内にすっかり懐かれてしまって、遊星が卒業してしまった今でも放課後にはちょくちょくとこの場所に遊びに来る。基本的に面倒見の良い性質であるために遊星は子供に懐かれやすいのだ。 「今日は二人しかいないの?」 「クロウはバイトで、ジャックは試合だ。ブルーノはパーツが欲しいと言ってジャンク屋に出掛けて行った」 「ふうん。ねえ遊星、過保護がイヤなのはわかるけどたまには声ぐらい聞かせてあげなよ。両親がいるってそれだけで幸せなことだよ」 「……急にどうしたんだ。まるで両親がいないみたいな口ぶりだぞ龍亞」 「え? あれ? えっと……」 勿論、双子は優しい父母の元で庇護養育されている。だが今の龍亞の言い方は「両親がいなくて寂しい子供」だと言われればなるほどそうなのかもしれないと納得出来てしまいそうな声音だった。しかしそう言った龍亞自身、少し混乱しているらしい。首を捻ってうんうん唸ると、わっかんない、と肩を竦める。 「……なんだろ。なんとなくそう思っただけ、かな。パパもママもいなくて龍可と二人っきりなんて俺、やだし……」 「そうね。私も兄妹二人だけは嫌だわ。でも、時々ね、不思議に思う時があるのよ。あれっ、私と龍亞って二人で暮らしてたんじゃなかったかな? って。ヘンな話だけど。もしかしたら並行した世界のどこかでは両親がいないのかもね、私達」 「パラレル・ワールドか。最近そういうファンタジー小説でも読んだのか?」 「少しね。龍亞が読んでたSF小説、面白そうだったから――あ、ブルーノが帰って来たみたい」 振り返ると、重たそうな紙袋を抱えたブルーノがえっちらおっちらと覚束ない足取りで階段を下ってくる。こいつはこぼすな、とあたりを付けて遊星はデスクから立ち上がったが遅かった。ずるりと足を滑らせ、盛大な音を立ててパーツがガレージの床にばらまかれてしまう。 「買い込みすぎよ」 「言わんこっちゃないよ。ブルーノっておっちょこちょいだよなあ」 「手伝う。何を買って来たんだブルーノ」 「え、えへへ……ごめんね遊星。エンジン用の制御チップとモーター、ちょっと奮発して新しくいいやつ買ったんだ。あと試作用のギア山程とコンピューターの方のカスタムパーツも買ったよ。それから……」 「大体わかった。まずは床を綺麗にしよう……帰って来たジャックやクロウに文句を言われないうちにな」 「うん。ありがとう遊星」 チームの二人目のメカニックにしてエンジニア、ブルーノは柔和な笑みで遊星に答えた。 WRGP出場エントリーをするにあたって旧知の仲で組んだチームがこの「チーム・ファイブディーズ」だ。エントリーしている選手が控えのアキとブルーノを含めて五人共ドラゴンをエースカードとしていることからこの名前が付けられている。ピットクルーの双子もドラゴンのカードを(龍亞のカードは機械族だが)持ってはいるが、試合に出ることはないのでとりあえずファイブだ。 不動遊星のスターダスト・ドラゴン、ジャック・アトラスのレッド・デーモンズ・ドラゴン、クロウ・ホーガンのブラック・フェザー・ドラゴン、それから十六夜アキのブラック・ローズ・ドラゴン――この四体は学生大会などで散々その名を轟かせある意味で大会荒らしも行ってきた名の売れているカード達だ。特にスターダストは抜群の知名度を誇る。二代目以降空白が続いていた「決闘王」の称号を僅か十八歳で掻っ攫い、そしてあっさりと返上したからだ。 その一方でブルーノの操るTG‐ハルバード・マシンナーズ・ドラゴンは様々な経緯から世に一度も出たことのないダークホースにあたるカードである。その五体を総称してファイブ・ドラゴンズというわけだ。勿論ハルバードのポテンシャルも他の四体に勝るとも劣らぬものである。 「遊星、そっちの出力は? どう?」 「遊星号問題なしだ。エンジンが大分軽くなっている」 「ホイール・オブ・フォーチューンは?」 「やや甘い。軽量化のし過ぎで逆にバランスに誤差が出ている」 「うわあ、それじゃやり直しだね……ごめんジャック」 「納得のいくものを作るためだ。試行錯誤なしに出来る方が稀だろう」 「そう言って貰えると、気持ちが楽になるよ。……じゃ、遊星はクロウの方をお願いするね」 ポッポタイムのガレージ中にエンジンの騒音が鳴り響いている。永久機関であるモーメントが作り出すクリーン・エネルギーであらゆる機械が動く時代で本当に良かったと龍可は思わず考えた。モーメントが実用化される以前に用いられていた化石エネルギーを原動力にしたエンジンだったらこのガレージ中がもくもくと吹き出したガスに占拠されて大変なことになっていただろう。音だけで済むことに感謝したいぐらいだ。 今日は珍しく昼間から全員がポッポタイムに集まっていた。いつもはバイト漬けのクロウや、日を問わずプロ活動のスケジュールに追われているジャックも丸一日オフらしい。アキに伴われてやって来た双子は差し入れのケーキが入った箱を抱えて、大声で叫んだ。 「ねえみんな! ケーキ持ってきたけど、冷蔵庫に入れとく?!」 「だから、このモーターはこっちのプログラムで……ん? どうした?」 「ケーキ! どうしよっか!」 空いている方の手をメガホンみたいにしてもう一度叫ぶと、ようやく声が伝わったようだった。遊星とブルーノが示し合わせてエンジンの駆動を停止させる。騒音がガレージから消え去って広い屋内に正常な音量が返ってくる。男四人は重たそうな腰を上げてアキと双子の方へ向き直った。遊星がゴーサインを出す。 「折角だ。テラスに出て今、食べよう」 「さっすが遊星。話わかる!」 「クロウ、ジャック、テーブルを出してやってくれ。キャンプ用のパラソル付きのやつ」 「了解了解。お前らはちゃんと機械類片付けてから来いよ、データを盗まれちゃ洒落になんねえからな」 「わかってるさ」 クロウに釘を刺されるが、遊星とて元よりそのつもりだ。用心に越したことはない。 「この前テレビでやってたお店が美味しそうだったからさ、アキ姉ちゃんに連れてってもらったんだ。苺のとか、チョコとか、葡萄のとか、色々買って来たよ。どうかな」 「目移りしちゃってなかなか決まらなかったのよね。今度また、今日買えなかったも買ってくる」 色とりどりのケーキが大きなテーブルに並べられる。アキとブルーノが紅茶とフォークを配り終えると同時に「いただきます」の声が誰からともなく上がった。龍亞はお目当てのチョコレートケーキを譲って貰ってご満悦の様子である。双子の兄妹の微笑ましい遣り取りに遊星は微笑んだ。この二人とも長い付き合いで――彼らが幼稚園に入っていくらか経った頃だったように思うからもう八年になるだろうか――時々、まるで自分が彼らの兄であるかのように感じる。勿論双子だけじゃない。クロウやジャックとの仲はもう腐れ縁で小学校の頃からの付き合いだしアキに関しては言わずもがなだ。唯一ブルーノだけは出会って一年にも満たない付き合いだが、そんなことを感じさせない程彼とは呼吸が合う。 この七人のチームは遊星を中心としたファミリーだった。家族共同体だ。全員が同じ屋根で暮らしているわけでもないし血の繋がりもないが、七人で家族だった。家主のゾラもその考え方には大いに頷いていたものだ。 「龍亞、龍可、俺のも一口食べるか」 「えっ、いいの?!」 「ああ。代わりにそのチョコレートケーキを一口交換、ということでどうだ」 「うん。じゃあ遊星、先に取って」 雲があまりなく、空は綺麗に晴れ上がっていた。作業中は空調をがんがんにかけてしまうからあまり気にしていなかったが日中は随分と暑かったらしい。そんなことをアキや龍可が話していてふと空を見上げる。夏が近く、時刻は四時近かったがまだまだ明るかった。 「……ん?」 見上げた先で何かが光ったような気がして、遊星は目を細めた。訝んで何度か瞬きをしているうちにどうやらそれが見間違いの類ではなさそうだということがわかってきた。光ったように感じた何かが重力の力で落下速度を増して、みるみる内にこちらへ向かって墜落してくる。そう思った瞬間に体が動いて、気が付いた時にはその何かを受け止めていた。身構える暇もなかったが、衝撃や痛みはなかった。 「遊星!」 仲間達が駆け寄って来る声や音がどこか遠い場所のものであるように感じられた。腕の中に抱え込んだ何かに視線が吸い寄せられていく。赤だ。赤い服を着た人だ。身長は低くもないが高くもない。茶色い髪をぐったりと降ろし、目を瞑っている。成人男性だろうか。だが、大きさと重さが釣り合っていないのだ。まるで紙のように軽かった。もしかしたら天使なんじゃないかと、ありもしない考えが脳裏を過った。 喉元まで声がせり上がってきていて、しかしつっかえてしまっている。げほ、ごほ、と噎せ返るとその声はすうっと無散して消え失せてしまう。何がつっかえていたのだろうか。自分は、何を言おうとしていたのだろうか。わからない。答えが見当たらない。どこかへ消えてしまった声は、もはや取り戻せそうにない。 (なまえ……) 「……ゆうせい?」 思考に覆い被さるようにその人が瞳を薄く開き、唇を震わせた。酷く透き通った声だ。美しいアルトの声音だった。なんでだか無性に懐かしくなった。こげ茶色の綺麗な眼球が遊星をぼんやりと見上げてきている。遊星の藍色の瞳とかち合うと、その人はぼおっとした表情のまま「あのさ」、と遊星に尋ねた。 「ここはどこだ?」 「……ネオドミノシティです」 「俺は……誰なんだ?」 遊星は首を横に振った。それはこっちが知りたい。 代わりに今度は遊星が尋ねる。 「何故俺の名前を」 「え? あぁ、ゆうせい、遊星、不動遊星……そうだ。君の名前は不動遊星。俺はそれを知ってた。知っていてここに来て……」 手のひらを遊星に向かって伸ばして、その人は遊星の頬に触れる。壊れものに触るような、生まれたばかりの命に恐る恐る触れている時のようなそんな手付きだった。優しい温度が皮膚越しに伝わってくる。どきりとする。何かタブーを犯しているようなそんな気分になっていたたまれず、遊星は彼に目線で指を放すように訴える。 「俺はきっと、きみにあいにきたんだ」 その人は遊星の懇願に気付く素振りもなくふわふわとした口調でそう言った。 |