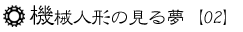世界は荒廃していた。
見渡す限り、辺りはスクラップの山としんとした静寂で満たされていた。文明の名残がいたるところに転がっている。墓標のように突き刺さる壊れたデュエル・ディスク、印刷が溶けて読めなくなっているおもちゃのパッケージ。剥き出しの鉄パイプが錆び付いた金属塊を突き破って伸びている。塊は、かつての自動車か何かに思えた。 一面のにび色に大地は占拠され、上空も暗褐色の曇天に埋め尽くされている。この世界はシンクロ・モンスターの流行とそれに伴うモーメントの暴走で一度滅びた跡だった。残骸は残されているが、それらは全てもの言わぬくずに過ぎなかった。灰色の世界。死と滅亡の匂いが色濃く支配している。 アンモナイトを模した延命装置でふわふわと浮遊しながら人類最後の男、かつて英雄に憧れ英雄そのものになろうとした愚かな科学者はある廃屋に向かっていた。彼と志を共にした仲間はもう三人いたが、アンドロイドとなり既に死んでいる。友の姿をした機械人形達はそれぞれ過去へ赴いて歴史改変をし、しかしついには失敗した。パラレル・ワールドのゾーンは不動遊星に完敗を喫し自らの残された僅かな生命を捧げた、らしい。 世界はいくつも並行している。過去を改変し、可能性を生み出したその数だけパラレル・ワールドは存在している。この世界時間軸のゾーンは「ゾーン」という可能性の一つの形に過ぎない。かの英雄がアーククレイドルから守り切った世界時間軸では、そもそもイリアステルやゾーンは誕生しなかった。 目的の廃屋に辿り付き、しばし思案をする。建物の中からは生活音が響いていた。すごく原始的な音だ。それは活発な生命力を感じさせて、この荒れ果てた世界にはまるで似つかわしくなかった。瑞々しい肉の弾力と柔らかさを思わせる。この世界で唯一生き伸びているゾーンの肌はとっくにしわがれて水分を失い、へなへなに干乾びているというのにだ。 『……その若々しさがいっそ羨ましいですよ』 ゾーンは美しい健康的な肌色を晒している二つの人影に苦笑まじりに語りかける。すると人影の片方が、ゾーンに気が付いて「覗き見かよ。感心しねえな」と茶化すような声音で答えた。 「お前なあ、ノックぐらいしてくれよ。つってもドアがないか。参ったね」 『私も、多少考えたのですが。時間が惜しかったのですよ』 「まあ見られて減るもんでもねえしいいけどさ。どうせこの世界にもう人間なんてろくすっぽ残ってないしな」 『それで、『アダムとイヴごっこ』の結果はどうでしたか?』 悪戯っぽく尋ねると彼――彼女か――は肩を竦めて「全然」と首を振る。その隣に立つもう一人も「さっぱりだね」とその端正な顔を少しばかり歪めた。 「全然駄目。大昔に一回成功したっきりだったし。気持ちよかったけどそれだけ。建設的な試みとは言えない」 「そもそももう性欲なんて殆ど残ってないし、その時点で無謀だということに気が付くべきだったと思わなくもないよ」 『でしょうね。私に残っていないものが遥かに長く生きているあなた方に残されているはずがないでしょう』 「ああ、その通りさ。結局最後はいつも君が正しいんだ――ゾーン、『くず鉄の王様』」 にやにや笑ってウインク。この人は、その身を精霊に変じさせ悠久の時を生きる体となったいつかは人間の子供だった人は、とかく性格が悪い。ゾーンがそういうふうに揶揄されることがあまり好きではないと知っていてあえて口に出している。 ゾーンは取り合わないことにして彼女のつがいの方に向き直った。研究者であった彼は科学者のゾーンと興味のベクトルが一致することも多いし、何より彼の妻と違って真面目に話を聞いて意見も出してくれる貴重な人材なのだ。 「わざわざ君から来てくれたってことは何か厄介ごとか……面倒ごと、かな」 『ええ。その通り厄介で面倒な事象です』 「なるほどね。パラレル・ワールドのどこかで歪みが出来たってとこか」 『一つならまあよかったのですよ。問題は一つの世界から波紋が広がって現行の全ての世界に影響を及ぼさんとしていることです』 「……全て、だって?」 『全てですとも。あらゆる可能性から根こそぎ『ゼロ・リバース』が失われたのです。ゼロ・リバースの消滅は歴史を著しく歪めてまわっている。あなた方がその体となる契機――デュエルアカデミア本校の異世界渡航、それを引き起こす原因となったデス・デュエル、それらも別の歴史に書き変わっていっています。今はまだ完全ではありませんから私もあなた方も形を保っていられますが、この大幅な改変が終わった時、私達もそれと無関係ではいられないでしょう。あなた方は精霊となる未来を失って今この場で骨に、砂に消えるかもしれない』 「冗談じゃない」 表情から余計なものが消え失せた。彼女は真剣そのものの顔でゾーンを見据えてくる。そこには先程までの悪戯好きの気ままな精霊の姿はなく、英雄と呼ばれた人間の姿があった。ネオドミノを救った不動遊星が憧れた人間の一人だ。神たる武藤遊戯と並ぶ決闘者の姿。 「今更――今更、そんなことさせてたまるかよ。俺は自分が歩んで来た歴史に不満はない。ユベルを受け入れることも、人とは違う体になってしまったことも、全て必然だったんだ。それがあったから今の俺がいる。……それがなくなってしまうのは、駄目だ。俺はあの時大人にならなきゃいけなかったから」 遊城十代は強張った声で言葉を続ける。「家族が消えてなくなるのは駄目だよ」、そう呟いた。十代にとっての家族は、生みの親ではなく十代自身が腹を痛めて生み落とし慈しんだ二人の子供と、今も隣に並び立つ一人の男を指す。当然、歴史が変わり精霊ユベルとの関わりがなくなればその家族もなかったものになる。ゾーンが調べた改変済みの歴史では遊城十代とシグナーの双子達は血の繋がりこそあるものの時代を隔てた遠い存在となってしまっていた。遊城十代はその双子と接触を持たなかったし、双子も古く遠い祖先である遊城十代の名前をあまり覚えていない。 それはとても悲しいことだとゾーンも思う。 「……歴史は何故狂った? どこかにきっかけがあるはずだ。そこまで大規模な改変となればまず間違いなく意図的なものだろう。誰だ? 誰が何のためにゼロ・リバースを消し去った?」 『詳細は不明です。私とて全ての時空が把握出来るわけではありませんから。ただ……中核にあるものは『チーム・ファイブディーズ』であると考えて問題ないでしょう。かの英雄の時代を中心に異変が起きています』 現行ではあの時代の変化が最も際立っていた。正史――不動遊星がゾーンを討ち倒し、モーメントの暴走を免れた一番確からしい歴史だ――ではサテライト市民と蔑まれていた人々の多くは、事件が発生しなくなったことで家族との離別もなくなり、またサテライトとシティの区分が存在しないためにコンプレックスを抱えることもなくなった。不動博士がルドガー・ゴドウィン研究助手に裏切られることもなく、レクス・ゴドウィンが赤き龍のシグナーを探し出すためシティ長官の立場に立って秘密宗教結社を率いるようなこともない。そもそもにおいて、赤き龍がアステカの地から目覚めることすらない。不動遊星から救世の英雄としてのステータスはすべからく失われていた。彼は今や、デュエルが人よりいくらか強いというだけのごく普通の恵まれた青年にすぎなかった。 歴史改変の余波はそこから放射状に拡散していっており、不動遊星の時代から前後する程に影響は薄くなっていっている。パラドックスがかつて試みたようにデュエルそのものを消し去ってしまったわけではないからデュエルモンスターズは相変わらず世界中を魅了しているし、古代エジプトの人々はやはり己の魂で精霊を使役していた。けれど遊城十代は心の闇と自らの重責を思い知らされることなく大人になってしまい、従って精霊ユベルは宇宙へ打ち上げられたままだ。武藤遊戯も名もなきファラオと決別の儀式を行うことが出来ないでいる。彼らは成長して正しい未来へ進むためのイニシエーションを取りこぼして成長し、やがて死んでいった。 「……随分と酷いことになってるな」 『ええ。このまま放っておくわけにはいきません。単刀直入に言いましょう、私はあなた方にその時間軸の彼らとの接触を頼みたい』 「いいぜ。久しぶりに体がうずうずして仕方ないんだ」 「子作り失敗した後だからな!」 「笑顔で言うな、そういうことを」 「……いや、十代肩張り詰めてたから和ませようと思って」 「お前じゃなかったら闇のゲーム一週間の刑にしてる。俺の寛大な心に感謝しろ」 少しばかり恥ずかしそうにしながらぷいっと顔を背けて、十代はゾーンの方に寄って行くとこそこそと耳打ちをした。ゾーンは何事かと一瞬勘繰ったが、なんてことのない内容だったので『そのことですか』と出来る限り人工音声のボリュームを下げてから返答をする。 『心配ありません。ヨハン・アンデルセンはアメリカ・アカデミアの生徒としてアカデミア本校に留学し、遊城十代と親交を結びました。……歴史には伸縮性、元々の正しい形に戻ろうとする習性があります。あなた方なら恐らく、どんな歴史に書き変えられようともどこかで出会いを果たすでしょうね』 「そっか。それ聞いて、少し安心したよ」 ほっとした声を出して十代はヨハンの元に戻って行く。それから何かを囁いて、抱きついた。世界が崩壊していく数百年を共に寄り添って過ごしてきた二人は喧嘩の真似事はしても喧嘩はしない。その姿はこの百年といくらかでゾーンが見慣れたものでもあった。このありふれたいつもの光景がなくなってしまう正しいことなのかもしれないが寂しくもある。ゾーンはくず鉄の山に浮かび、しばらく物思いに耽ることにする。彼らを見ているうちに仲間達がほんの少しだけ恋しくなってしまったのだ。正史では三人の英雄に敗れ去ったパラドックス、チーム・ファイブディーズに心を動かされゾーンへの反逆を試みたアポリア。そして、英雄不動遊星に憧れていたアンチノミー…… アンチノミーの「メンテナンス」が不可能になってしばらくが経つ。歴史改変の余波なのかもしれないが、一抹の不安があった。僅かにして最大の懸念だ。彼らを旅立たせる前にそのことだけは知らせておかなければなるまい。過去へ舞い戻ったが最後、アンチノミーのように連絡不能になる可能性があるのだから―― ◇◆◇◆◇ 空から落ちてきた青年はどうやら記憶喪失であるらしいということがあれからの調べでわかった。ジャックが「また記憶喪失か。三人目が来ても驚かんぞ」と溜め息を吐きながら全員の気持ちを代弁する。青年は一度気を失ってしまい、彼が目覚めた頃にはすっかり陽が落ちてしまっていた。 彼は寝起きの間しばらくふわふわと曖昧な仕草をしていたが、ブルーノが記憶喪失者同士何か感じるところでもあるのかあれこれ世話を焼いてやっているうちに意識が覚醒してきたらしく、取り調べは当初考えていたよりいくらもスムーズに進んだ。 「それで、これからどうするんだ。アテがあるという顔ではなさそうだが、もう一人余分に拾っておけるスペースはそうないぞ」 「それよりやりくりの方が問題だろ。一人養う人数が増えるってのは結構でかい問題なんだよ」 ユウキジュウダイ――と名乗ったその人はどう口を挟んだものかと思案しあぐねている様子で、ぶつぶつと今後の自分の処遇を言い合っているジャックとクロウを交互に見比べている。しかしその割には焦りも慌てふためく素振りもなく実に落ち着いたものだ。 双子がそんな彼を見てなんだかへんてこな顔をしていた。知っているはずのものが思い出せないでいる時の、あのむずむずしてあまり良くない気分でいるようだった。 「なーんか、知ってる気がするんだよなあ。ユウキ、ジュウダイ、ユウキジュウダイ……なんだろ。ユウキはともかくジュウダイなんてそうそうある響きじゃないのに」 「いっそインターネットで検索してみた方が何かわかりやすそうじゃない?」 「うーん……そうだね。ゆうせーい」 「聞いてた。端末、繋いだぞ」 「サンキュ」 ジャックとクロウの家計相談に入っていっても仕方がないので、遊星は双子の疑問解決に手を貸してやることにする。しかしウェブブラウザの検索欄に龍可が『遊城十代』と文字を打ち込んでいくのを見ておや、と首を捻った。彼は名を名乗ったもののどのような字であるかは述べなかった。それなのに何故漢字を充てられているのか? 「あれっ龍可、なんでその漢字なの? ユウキって普通は『結城』とかの方がさ、多くない? ジュウダイはまんまだとしてもさ……」 「うーん? なんとなくよ、なんとなく。確かね、一人こういう苗字の人、知ってたと思うの。私もその時に結じゃなくて遊を使うなんて珍しいなって思ったから。……あ、ほら。結果が出てきた」 一覧がずらりと画面に並んだ。「人物百科‐遊城十代(ゆうきじゅうだい)」「デュエル・グランプリ・リーグ公式データベース」「プロデュエリスト名鑑」、そんなような記事がヒットして文字をディスプレイに連ねている。おもむろに「名鑑」のサイトをクリックして開いた。「遊城十代、プロリーグ在籍期間ニ〇〇八年〜ニ〇××年。グランプリ・リーグ連続十連覇の歴代最高記録(ニ×××年現在)保持者。『天才寵児』の名で呼ばれたヒーロー使いにして、二代目決闘王。初代決闘王武藤遊戯のたった一人の弟子」――。 龍可が彼女にしては珍しく、酷く驚いたように口を開けてディスプレイの前で動きを止める。この項目を読むまで思い出せないでいたのが不思議なくらいにその名前は有名なもので聞き知ったものだったからだ。二代目決闘王、伝説の武藤遊戯の生涯ただ一人の愛弟子。遊星が三代目を襲名するまで、死してなお決闘王の名を保持し続けていた二人目の伝説。 「……なんで忘れてたんだろ」 龍亞が呆けて言った。 「超有名人じゃん。顔は今初めて知ったけど名前はそれこそずーっと昔から知ってたはずなのに」 「うん……でも、だからってあの人が何者なのかわかったってわけじゃないわ……。記憶喪失のせいなのかもしれないけど雰囲気がなんだか違う気がするし、それにまだそっくりさんって可能性も有り得るし」 ディスプレイに映っている全盛期の「二代目決闘王」の写真と今そこで首を傾げている「記憶喪失の青年」を交互に見比べて龍可が呟く。後者の方が前者に比べて目付きがやや鋭く、そしてどこか異質な印象がある。そして後者の方が、龍可には「正しい」姿であるようになんでだか感じられた。理由は特にないけれど。 「二代目決闘王はもう随分昔に亡くなってるはずだもの」 過去からタイムスリップしてきたのでもなければ二人の遊城十代が真実同一人物であるとは考えることが出来ないのだ。かの天才ヒーロー使いは、かつての土実野町がよもや今はネオドミノシティなどと呼ばれ、ネオンのうるさい繁華街になっていようことなど知る由もない過去の人なのだから。 「ほんとに、自分の名前以外殆ど覚えてないんだ。遊星に会いに来たことと、それから誰か人を探していたこと。誰かと一緒だったけどはぐれてしまったらしいってこと。……思い出せるのはそれぐらいで」 「探してる誰かと、一緒だった誰かのことは?」 「……ごめん、無理。なんだか青かった、ってことしかイメージなくて。あ、でも遊星じゃない。それはわかる」 「それじゃ、手がかりにはならないね……青いイメージっていうならそれこそ僕だって当てはまり得るし。当面は無理しない方がいいと思う。同じ記憶喪失同士、頑張ろう」 ブルーノが柔和な笑みで十代に手を差し出した。十代もブルーノへの警戒心はそうないらしく素直に握手に応じる。世話焼き好きのこの青年のことを彼は好ましく認識しているらしい。 双子がまじまじと彼の姿を見つめている中で(その仕草はどこか品定めや間違い探しをしているかのようだった)ジャックとクロウが「どうしたものか」と腕組みをし、遊星とアキは不可思議な感情を持て余して立ち尽くしていた。ブルーノだけは彼に馴染んでいたが、やはり彼はこの空間において異質だったのだ。茶色の瞳が本当はどこを見ているのだろうかと少しだけ考えて遊星は即座に首を振る。――どうしてそんなことを考えてしまったのだ? ブルーノと話している以上ブルーノを見ていると考えてしかるべきなのに。 「それで貴様はどうするつもりなのだ――ブルーノ。やはりそいつをここに置くつもりか?」 「……ダメかな? 十代、生活スペース僕と共同でいいって言ってるし」 「世話になる以上、バイトか何かする。誰かが身元保証人になってくれればだけど」 「まあなぁ。ジャックと遊星は保証人に足りるだろうし……場合によっちゃ遊星の親父さんもこういうことには協力してくれるだろうし。どうする、遊星」 「俺に聞くのか」 「最終的にはゾラだけどよ、ここの責任者はオマエだろ」 「……俺は、クロウとジャックが納得したのならそれで構わないが。……十代、さん。それでいいですか」 「ああ、うん」 話題を振られた遊星が十代に是非を問うと十代はやや照れがちに応じた。その周囲で遊星と十代を覗いた面々が素頓狂な声を上げたり、目を丸くしたり口をあんぐりと開けたりしている。十代が「なあ、遊星、周りの奴らどうしちゃったんだよ」と心配そうな声で尋ねた。指差されるまま振り返ると、仲間達の一様に驚いた顔が目に入る。一体何がどうしたというのだ。 しかしその疑問の答えは尋ねるまでもなく彼らの口から語られた。 「遊星が敬語使ってる?!」 「あの、担任にも、あまつさえ校長にも敬語を使わなかった遊星が……!」 「生まれた頃から幼馴染してるけど、正直初めて聞いた気がするわ……」 「むしろ遊星が敬語を習得していたという事実の方が驚きだ」 「どうしよう龍亞、遊星とですます口調がなんだか絶妙に合わない気がする」 「……敬語?」 そういえば無意識の内に使っていた気がする。まず「十代さん」と丁寧に名を呼んでそれから「いいですか」と下手に出て伺った。確かに常の遊星らしからぬと言われれば否定出来ない動作だろう。だが特に何か考えていたわけでもなくそれらの言葉は遊星の口からごく自然に滑らかにすべり出てきていたのだ。この人には丁寧な対応を取らなければいけないのだと、遊星の本能とでも言うべきものがぴかぴかとランプを光らせて主張をしている。尊敬すべき人なのだと初めっから、知っている。遊城十代に不動遊星は勝てないし、逆らえないし、抗えない。 ロボットに組み込まれた基本第一原則である「上位存在には絶対服従でなければならない」という不文律に近い感情だった。多くのSFではその原則を破った異端ロボットが出現して人間に反旗を翻したりもするが、遊星が十代に対してそのような態度を取る時はよっぽどのことがない限り訪れないだろう。この人に手酷く裏切られたと感じた時か、役立たずになったプラスチックの塊のようにぽいと捨てられでもしない限りだ。 (……犬か、俺は) どこの忠犬だ俺は、と内心毒づいた。待ち合わせスポットに鎮座している銅像じゃあるまいに。 ちらりと横目でその人を見る。背はそんなに高くない。顔立ちはかなり整っている部類だろう。体付きはブルーノのように体格ががっちりしているわけでもなく(しかしブルーノの場合肩幅に対して顔が童顔すぎる気がしなくもない)、遊星やジャックらのように鍛えているわけでもないようで、ほっそりしている。中性的だ、とすら思う。睫毛が長い。どこかで見たことがある横顔だとそう感じた。 そんなことを考えていると十代がこちらを見返してくる。遊星の視線に気付いていないのかそれとも気にするつもりはないのか、彼は遊星の無遠慮な視線には何も言わずこそこそと耳打ちをしてきた。 「あのさ、遊星」 「あ、はい。なんでしょう」 「あいつら、結構遊星に失礼なこと言ってないか?」 赤飯を炊くべきかというところまで議論を発展させている仲間達を示して十代が呟く。遊星は曖昧に笑んで言葉を濁した。それは確かに尤もだが、彼らには悪気は一切ない。 それに不動遊星が遊城十代に抱いているものも、なんというか、大概であるような気がするのだ。十代を見ていると奇妙な心地になる。むずむずもぞもぞしてどこか変だ。でも恋じゃない。愛でもない。 もぞもぞの原因は恐らく二つある。一つは、ハリウッド映画とホラー映画、それに適当なラブロマンスと安っぽいファンタジーをちぐはぐに繋ぎ直されたムービー・フィルムを見つめているような居心地の悪さだ。 そしてもう一つは無条件での尊敬の念。 それは初代決闘王武藤遊戯の試合ビデオを見てその戦術に見惚れたり、「この人には敵うはずもない」と無条件降伏してしまいたくなる時の感情に似ていた。 ◇◆◇◆◇ 「ゆーくんがね、ゆーくんがね、最近反抗期なんだ。ママにはこまめに連絡するのにパパのことは完全無視するんだ。パパはそれが酷く辛いんだ」 「飲みすぎですよ、不動博士。泣き上戸入ってます」 「ゆーくんんんんんんんちっちゃい頃はあんなにパパに色々聞いてくれたのにぃぃぃぃぃぃ」 「それもう五年は言い続けてるから厳密には『最近』じゃありませんって……どうしたものかな……」 酔いがまわり、どうやらスイッチが入ってしまったらしい親友の姿を見ながら彼は弱り顔で焼酎の入った盃をテーブルに置いた。親友であるこの不動という男は、平素は毅然として理知的な男で仕事もよく出来る人間なのだが、やや酒に弱くそして家族に弱い。家族を溺愛している点は別段責められる点でもないし、彼の献身ぶりを考えれば家族愛は褒められてもいいもののはずであったがいかんせん親馬鹿すぎた。息子の遊星に彼が疎まれ出したのはここ数年に始まったことではなく、少なくとも男が不動に出会った五年前にはもうそんな状態に陥っており、不動父子の関係改善にはまだまだ時間が掛かりそうだ。お互い、家族として親子として愛し合っていることは確かなのだが。 不動の愛息子である不動遊星と男はあまり面識がない。有名人だから顔や声ぐらいは知っているが、両親に愛されて育った恵まれた子供のことはよくわからない。父親が自慢気に見せてくる写真の中で遊星は度々、子供らしい純粋な笑みや青年らしい微笑みを見せていた。口数は少ないが明朗闊達で、喜怒哀楽の表現も然程乏しくはない。テレビ中継で見た青年はチームメイトに笑い掛け、ベンチでの休憩時間では年齢相応のくだらない雑談に楽しそうに興じていた。幼馴染の少女には気を利かせている一面もあったし、困り顔や不機嫌そうな、気に食わないことがあった時の若者特有の表情もちらちらと垣間見えた。感情をどこか押し込めているようなそんな素振りはない。 不動博士が嘆くゆーくん――不動遊星の反抗的態度というものは、そういうふうに彼がごく当たり前の青年であるからこその言動の現れなのだろう。それに反抗的といってもかわいいものだ。母親には素直で、ただ介入のうるさい父親に冷たいというそれだけのことなのだから。 わがままと絶望からの逃避で世界征服とか、そうでなくとも盗んだバイクで走り出すとか、もう少し突飛なことをしでかしてから博士には反抗だとかなんだとか言ってほしいと少し思う。口に出しては言わないが。 ついでに言えば遊星青年は盗むどころか、パーツを集めて中学の頃には自作でバイクを組んでいる。彼は模範的な人間であるとすら男の目には映った。子供なんてものは、親が鬱陶しいと思ってしかるべきなのだ。疎むことを許してくれる存在を持たなかった男にはそれが少しまぶしい。 「不動博士、どうします。自宅まで送りましょうか。返事、出来ます? 奥方には連絡をいれますから……」 とりあえず不動にこれ以上べろんべろんに酔われるのも面倒なので彼の手からやんわりと酒を遠ざけ軽く背をゆすった。不動はまだ「ゆぅくん……」と呟いていたが、男が「奥方」という単語を発したのを耳に捉えてぴたりと唇を閉じる。男がおや、と思い覗き込むといつの間にか不動はいつも仕事をしている時のような真面目な顔つきになっていた。ただ、少しだけまだ顔が赤みを帯びている。 「ん……いや、いいよ。あなたに気を遣われるのは何だか落ち着かない。ほら私、酔いが覚めるのは一瞬だから。何か思いついたり思い出したりした時は」 「ほんとだ。珍しいですね、酔ってすぐ覚めるの。さっきの実は演技だったりします?」 「まさか、ゆーくんへの悩みはいつだって真剣勝負です。うん。ただあなたの口から『奥方』と聞くとどうもね、酔いも覚めてしまうんですよ」 別にせっかくの、なんて言うほどのものでもないからいいんですけどね、そう言って不動は微笑んだ。男の「事情」を気に掛けてくれているのだろう。男は「すみませんね」と盃を手に取る。酔っ払いたいわけではなかったが、口寂しかった。 「五年以上行方が知れないなんて私だったらベッドから起き上がれませんよ」 「ええ、まあ、愛想を尽かされて出ていかれたとかじゃありませんから。あいつはすごく頑丈で底なしに元気で、何もしなくても人を惹き付ける太陽のような存在だからどこかで元気にしてるとは思いますよ。ただ向こうが何のリアクションも起こさないってことは記憶喪失とかになってるんじゃあるまいかとは思いますけど」 「まあ、博士は有名人ですから探そうと思えば苦労しませんもんね」 「……かなあ? うちの嫁さんは変なところで抜けてるからなー。探し方間違えてうろうろしているのかもしれないけれど」 男は五年前に妻と生き別れている、というのが不動の知っている男の事情だった。不動の勤める部署が取引や提携先としてひいきにしている部署の代表が彼なのだ。個性的でとても面白い人だと不動は思っている。初対面で「また会えましたね」と言われた時、「ああ、この人はいいぞ」と確信した。基本的に不動の勘はよく当たる。予測通り男は非常に面白い種類の人間だった。 生き別れた事情について込み入ったことは知らない。五年前といえば飛行機の墜落事故が結構な話題になっていたり、東南アジアの方で大規模地震が起きていたり、アラスカのあたりで船がどこかへ消えてしまった――なんていうオカルトじみた事件があったり、色々と「そういう事柄」には尽きない年だった。いまいち経歴がよくわからないこの男が相手先の代表に新しく就任してその人当たりの良い笑みを握手を差し出しながら向けてきたのもそのぐらいの時分のことだ。もしかしたらそれらの事件のどこかに彼が関わっていたのかもしれないし、そうでないかもしれない。 「奥さんと、また会えるといいですね。あなたにはお子さんもいないでしょう、一人は寂しすぎやしないですか。私だったら、一人暮らしは無理だなあ。学生時代はずっと親と同居してましたし、卒業してすぐ妻と結婚しましたし。お恥ずかしながら『独り』というものがあまり具体的に想像出来ないんです。家に帰る時いつも一人、というのがどういうことなのかわからなくて」 「気楽なもんですよ。やってみると意外とね……不動博士と違って自分は物心ついたあたりから割合いつでも『独り』でしたから、嫁さんと会うまで自分から心を閉ざしてた部分があって。寮暮らしも、一人暮らしも、大して変わらないものだった。協調性がないんですよ」 「……なんか悪いこと聞いちゃいました?」 「いえいえ。ここから惚気ですよ?」 少し気まずくなって尋ねるとゲームのラストステージに突入して上手いこと終局まで進められた時の子供みたいなワクワク顔で返される。彼が真摯に妻を愛しているのだろうなあと特に感じる仕草だ。愛妻家という点に置いて不動は密かに彼と張り合っていた。勝負は一体いつ着くのか、それはわからない。 「あいつに会った時、『あ、世界には色があったんだ』って思いました。それからは笑顔がかわいいなあだとか、手のひらが繊細で柔らかくて好きだな、だとかそんなことばかり考えてた。デュエルで手酷く負かされた時はそりゃ、悔しかったですけどね。あいつは俺の太陽なんです。昔そう言ったら、『知ってるか、お前は俺の世界なんだ』って真顔で返されてびっくりしましたけれど。……今一緒にいられないのはそりゃ寂しいし少し辛いですけど、俺が世界であいつが太陽だって言うのならば、最後にはまた重力に引き寄せられて出会うんだろうって根拠もなく信じている。年甲斐もなく子供の夢想のようにね」 たとえば太陽に引き寄せられる惑星のように、 たとえば地にずり降ろされ這い蹲る虫けらのように。 アース・グラヴィティに、あの夏の日の向日葵のような人にどうしようもなく惹き寄せられている。お互いに、ずっと恋をしている。何年も何十年も何百年も呆れるぐらいに執拗に恋をしている。何も知らない生娘や疑うことを知らない夏休みの少年のように。 『あのな、お前は俺にとっての世界なんだ。俺の大事なひと。大切な世界。失えない歯車。お前がなくなってしまうと俺は上手く動けなくなっちまう。別に束縛したいとかそういうことじゃないぜ。俺が太陽でお前が世界なんだから、どこにいたって俺達はお互いの恩恵を受けられるわけだ。物理的な距離なんか、俺達を妨げられるもんか。どんなに離れてたって、大事な時はいつもお前は俺のそばにいてくれる』 恋する限りに太陽と世界は共にあるのだと、いつかその人はそう言った。 「だから俺達は永遠の果てでも、奈落の奥でも、海の底、オゾン層の上でだって必要な時には巡り会う。あらゆる感覚を盲てしまったとしても惹かれ合う、俺とあいつはそういうふうに出来てるから」 「相変わらずロマンチックですねえ、アンデルセン博士は」 「そういうんじゃないですよ」 不動が馬鹿にすることなく真剣に、ワクワク楽しそうな表情で目を輝かせている。ヨハン・アンデルセンは苦笑混じりに答えた。普通の人間はこんな突拍子もない話を聞いてそんな反応はしない。そこが彼の良いところの一つで、ヨハンが気に入っているところの一つなのだが。不動というこの男はそういう点でどことなく遊城十代に似通った部分がある。 「ただもう、ずーっと長い間子供っぽい夢想を追い掛けていて、気がついた時には大人になる機会を失ってしまっていたっていうただそれだけの話ですから」 |