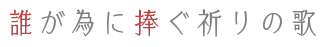
※22歳のレオと暮らす記憶喪失の泉/シリアス/未来捏造
プロローグ:目覚めよと呼ぶ声が聞こえ/序曲
――主よ 召しませ 祈りの歌を
――いのち 言祝ぎ 生誕の歌を
誰もいない部屋の中央で、一人の青年が明朗に歌い上げている。旋律はもの悲しく、はりつめて厳かで、その声は硝子のように美しい。
なんて透明な歌声だろう、と朱桜司は思った。
なんて残酷な歌声だろう、と朔間凛月は思った。
なんて健気な歌声だろう、と鳴上嵐は思った。
そして月永レオは、世界でいちばん儚い歌声だ、とそう思った。
「……美しい曲ですね」
司が小さく漏らす。たまらず震えてしまった唇を手のひらで覆い、感嘆の息を吐きながら。
「そうだね……でも」
司の肩を抱き、凛月が囁いた。彼の紅の瞳には、ただ真っ直ぐな眼差しが宿っている。凛月先輩、と訊ねかける司の唇を、凛月はそっと塞いだ。降ろされた司の手のひらを嵐が掴む。それで一瞬、四人の周囲はしんと静まりかえった。あたりに響くのは、彼の歌声だけ。はりつめて玲瓏で、今にも壊れてしまいそうな、硝子の城の独唱曲。
「悲しい歌」
そう呟いたのは、一体誰だったのか。
分かっているのは、ぐしゃりと楽譜を握りつぶした音が、その言葉を遮った事実だけだ。
◇◆◇◆◇
瀬名泉は月永レオと同居している。泉の体感で言うと、一ヶ月ほど前から。「泉の体感」という注釈がわざわざつくのは、それがどうも、実際の年数とは異なっているから、らしい。
「セナ? 起きてる?」
「……起きてる。今行く……」
おたまがフライパンを叩くリズミカルな音に呼ばれ、ふらふらとベッドから降り立った。寝室にはダブルサイズのベッドが一台だけ置かれていて、その事実に、ひと月が経った今でもなかなか慣れることが出来ずにいる。
「おはよ、セナ。今日のセナはお寝坊さんだな〜」
「うるさいよ。打ち上げ飲みも、仕事のうちでしょ。それでも終電までには帰って来たんだから……」
「わはは、まあなっ。俺たちもうとっくに高校卒業してるんだから、『打ち上げでジュース以外を飲むべからず』とか、『原則二十二時には現場を切り上げること』とか、そういう夢ノ咲の規則に縛られる理由なんて、もうないもんな」
「まあ……そう、かな」
寝間着のままダイニングに着き、対面に盛られているお揃いの朝食をぼんやりと眺めた。レオは三毛猫と灰色の縞猫が描かれたエプロンをしていて、それを見る度、「こいつ料理なんかする男だっけ?」という疑問にいつも苛まれてしまう。でもまあ、きっと年月が人を変えることもあるだろう。何しろ五年の月日が経っていると聞く。月永レオは今年で二十二歳になる。車の免許も持っているし、朝ご飯にサニーサイドアップも作るし、泉と同居を初めて数年になるという。
(そんな実感ないんだけどな……)
盛りつけが終わって席に着いたレオと向かい合い、いただきますをしたあと、サラダ菜をフォークで滅多刺しにしながらそう考えた。実感はない。何もかも。未だにレオが車を出すというとびっくりしてしまうし、この男にエプロン姿は似合わないと思うし、一緒に何年も暮らしているなんて言われても信じられない。
でもなにより信じられないのは、レオが二十二歳になっている以上、同い年である泉もまた、二十二歳になっている、という事実。
(俺はまだ十七歳だったはずなのに)
卵にフォークを突き刺すと、半熟の黄身がとろりと零れ、真っ白なディッシュプレートをべたりと汚した。生娘の呻きみたいだと思った。望むと望まないとに関わらず流された破瓜の涙。
ぐちゃぐちゃに刺し殺された黄身は、ほどなくして全て泉の胃袋の中に収まる。レオの作るサニーサイドアップは、いつも黄身の溶け方が天才的だ。その他の料理はからきしできないんだけど。
「ねえれおくん、今日の予定は?」
「今日は一日オフ!」
「じゃあ、またどこか出掛けるの」
「セナさえよければ。……いつもみたいに、セナにゆかりがある場所に行こっか」
問いかけに答えるレオの声は、慮るようで異様に優しい。
泉は「そう」と小さく答え、プレートに載っている食べ物を残さず平らげた。この男の優しい声を聴くのはなんだか複雑で、微妙な気持ちになる。
人間って変わってしまうのかな。五年も月日が経てば。
泉の知っているレオはもっと傲慢だった。もっとわけのわからないやつだった。泉にいちいち、「セナがよければ」なんて聞いてきたりしなかった。なんでも独断専行で決めてしまうし、気付いた時にはやらかしたあとだし、その尻ぬぐいは大抵泉がやることになっていたし、だけど楽しかった。青春の全て。まぶたを閉じれば、ついこの間にも、そんなふうに若気の至りからきた馬鹿をやっていた光景が思い浮かぶのに。
(だけどそれはもうずっと昔のことなんだよって、世界中みんなが口を揃えて言うんだもんね)
溜め息を吐き、苦いコーヒーに唇を付ける。
瀬名泉は記憶喪失だ。
高校二年生の秋から以後の記憶が、まる五年分――すっぽりと全て抜け落ちてしまっている。
◇◆◇◆◇
レオに手を引かれ、川べりをとぼとぼと歩いていた。もうじき昼に差し掛かろうという時間だが、日が出ている割に風が冷たい。東風が染みる季節。季節感覚は、泉の記憶とぴったり連続して繋がっている数少ないものだ。ほぼ唯一の慰めに近い。
泉の手をしっかりと握り込んだレオの温もりは、記憶にあるものよりも、幾分か低く落ち着いていた。あんなに子供体温だったのにな。一ヶ月一緒に暮らしている限り、奇想天外で子供っぽいところが完全に失われたわけではなさそうなのだが……それでもなんというか、月永レオは、大人になった。
こうやって手を引いている姿も、何と言うべきか、弟妹を守って先導しているような趣がある。「セナ、手離すなよ、はぐれちゃうから」というのが、ここ一ヶ月の彼の口癖だ。レオはとにかく泉の手を握りたがった。「離したら魂ごとどっか行っちゃう気がして」なんて、名作ゲームのコピーみたいなことさえ口にした。だけどその意味がわからないほど泉だって愚かではない。レオは、泉の中にもうひとり、別の瀬名泉を見ているのだ。たぶん……。
記憶喪失になる前、レオと泉は?同棲?していたらしい。
ただの同居ではなく、同棲。嵐も凛月も口を揃えてそう言っていたので、本当なのだろう。つまり今手を握ってくれているレオは、二十二歳の泉と付き合っているのだ。なんだか全然実感がわかないけれど。彼には恋人がいるのだ。
……恋なんて、まるで無縁のやつだと思ってたんだけどなあ。
いつも騒がしくて、子供っぽくて、赤ん坊みたいに純粋で。俗な言い方をすれば、穢れた欲求なんかひとつもない善良な生き物だった。十七歳の瀬名泉が知っている月永レオは、三大欲求の定義が歪んでいて、七割の作曲欲と二割の食欲、そして残り一割を辛うじて睡眠欲に捧げているようなところがあった。
綺麗で美しい魂。だからあんなに、心に響く旋律ばかりを紙に書き留めていられたんじゃないだろうか。
そんなあいつが、恋だなんて……。
あまつさえ、その相手が泉だとか言われても、にわかには……信じがたい。
(確かにれおくんは、臆面もなく大好きだって何度も言ってくれたけどさ)
けれど泉が思うに、月永レオは、みんなのことが大好きなのである。世界を平等に愛している。みんなが好きで、みんなが愛おしい。レオは泉に好きだと言ったその唇で妹への愛情を謳うし、同じ舌先で見知らぬ誰かへのパッションを語る。あいつの特別になんかなれるもんか。月永レオは天才で、奇才で、鬼才だ。化け物みたいなものだ。凡俗な泉ではとても釣り合わない。
(この前だって、『瀬名は月永の友達なんだから〜』とかなんとか言われて、そんなんじゃないって言ったばっかり。……あ、この前じゃないのか……)
五年前か、と自戒をするのと同時に、くしゅんとくしゃみが口から飛び出した。するとレオが立ち止まり、「大丈夫か?」と振り返る。泉が何かを言うより早く、レオは自分のマフラーをとって、泉の首に付け直した。マフラーは青地に白で模様が編み込んであり、端っこに、Knightsのエンブレムであるナイトの駒と、レオのイニシャルが編み込んである。
「……これ、どこで買ったの?」
ファンクラブか何かで生産したもののサンプル品をもらったのだろうか。そう思って軽い気持ちでレオに訊ね、そしてすぐに、そのことを後悔した。
「高校三年生の冬に、セナに編んでもらった」
レオの唇から、白く濁った吐息が漏れ出ていった。ああ、まただ。また、泉の知らない五年間の話。こんなマフラーを、自分が編むのか。泉はその事実に単純におののく。友人へのプレゼントでこんな凝ったマフラーを? いや、自分なら、出来なくはないと思うけれど……でも間違いなく、嵐や凛月のぶんは、作っていない。だってこんなの何本も作れない……。
「毎年ずっとつけてるよ」
セナは手先が器用で編み物が上手だもんな、とレオが笑った。泉は胸が締め付けられるような思いがして、顔を俯かせてしまう。
(この人は俺の知ってるれおくんじゃないんだ)
ちょっとだけ低くなった体温で、再び手を握り締められた。指先はどうしようもなく優しく、そのぶん余計に泉は傷付く。二十二歳の月永レオは、泉に、恋人のような振る舞いを決してしない。「同室に暮らしている友人」以上のことをしてこない。だけど世間はふたりを恋人同士だという。
レオは今、我慢しているのだ。見た目は完全に二十二歳の瀬名泉を前に、何かを我慢させられている。それを思うとたまらなく悲しくて、己の無力さにうちひしがれてしまう。レオの優しさに漬け込んで甘えているみたいで、対等じゃないみたいで。けれど恋人の扱いをして欲しいのかと聞かれれば、それはそれで、恐ろしくていやだ。
十七歳の瀬名泉は、いつだって月永レオと対等な友人同士でいたいのに。
どうして世界は、それを許してくれないのか。
「……ごめんね、れおくん」
「ごめんなんて言うなよ、セナは何も悪いことしてないのに」
「ううん、だけど」
「いいから。……思い出せないことを気に病まなくていい。今度はおれがセナを守って、助けてあげるって、約束したんだ」
「……誰と?」
「二十二歳のセナと、それから、魔法使いに」
そんな話をしたあたりで、レオの足取りが止まる。つられて足を止めると、そこには、古ぼけた教会が建っていた。屋根はぼろぼろで、嵐の日は雨漏りが酷そうだった。「中に入っていいの?」訊ねると、レオが頷く。「ここには神父様がいないから」。
「神父様のいる教会だと、形式のなっていないおれはお祈りしづらいし――」
それに好き勝手歌ったりも出来ないしな、とレオが言った。泉は彼の手に引かれるままに廃教会へ入っていった。じめじめして、かび臭くて、いかにも、神さまに見放された土地……という臭いがした。
メッキの剥げ落ちた聖像の前まで歩み出て、さびれた偶像を拝む。知らない場所だけれど、「セナにゆかりのある場所」の一つらしいので、二十二歳の泉はここがお気に入りだったのかもしれない。いや、なんで? という感じではあるんだけど。たった五年で自分の潔癖症がなくなるとも思えないので、絶対好きじゃなかったと思うんだけど、こんな場所。
(きっとこの場所で忘れられないことか何かがあったんだろうな)
隣の男が両手を合わせているのを見て、慌てて泉も手を合わせた。二人とも基督教にはまったく興味関心がなかったはずだし、見ている限り今のレオもさりとて熱心な信者に宗旨替えをしたというふうでもなかったが、どうしても、この場で祈らなければいけない気がした。
泉はまぶたを閉じ、神に祈るかわりに、まったくの他人である「二十二歳の瀬名泉」へ訊ねかける。おお、二十二歳の瀬名泉。あんたは一体、れおくんの何だったの。何者だったのかなあ、未来の俺は。恋人だったの? 好きだったの? ねえ、キスした? それよりもっとすごいことは? 欲望もなにもかも人間の醜いもの全てを取り払った純真な生き物に、どんな薄汚い欲を求めたの……?
(きらい……二十二歳の俺なんて……)
組んだ手が震える。どれほど厚顔無恥でいれば、そんなことをレオにねだれたのだろう。泉は自分と同じ顔をした悪魔がレオにしなだれかかっている姿を想像し、あまりのおぞましさに、苦い顔をして生唾を飲み込んだ。胃袋の中身全部引っ繰り返りそう。あの生娘の呻き声みたいな半熟の黄身も、ぜんぶ、吐瀉物になって出ていってほしい。そんなことをしてもなんにもならないけれど。なればこの身は既に穢れていて、指先は血に染まり、唇は嘘に塗れているというのに。
(大人になんかなりたくない)
――吐き気がする。
泉はその気持ち悪さを振り払いたくって、手をほどき、胸を押さえると、大きく息を吸い込んだ。
「……主よ召しませ、祈りの歌を――」
汚れを洗い流すように、唇から知らない歌を紡ぎあげた。主よ召しませ、祈りの歌を。いのち言祝ぎ、生誕の歌を。泉はこの歌のことをよく知らない。歌詞もメロディも全部暗記しているけれど、何の歌なのかまったくわからない。歌詞を検索してみたけれど、何一つ引っかかりはしなかった。これは世界中の誰も知らない曲。泉とレオだけが知っている、不思議な歌。
「主よ赦したまえ、憐れみたまえ、愛しい人への子守歌――」
きっとこの歌の意味は、二十二歳の瀬名泉だけが知っている。
澄み渡った歌声を響かせ、泉は最後まで知らない曲を歌い上げた。神さまに見放された場所で信じてもいない神へ許しを請う出来損ないの賛美歌を、大人になってしまったレオだけが、目を逸らさず、一瞬一秒を永遠に縫い止めるが如く、冷徹に見守っている。
(返して。俺の青春を、俺の子供時代を、返してよ……)
歌が終わり、唇を閉じると、レオが何も言わずにまた手を取ってくれる。二人で出掛けると、いつも泉は、何かに衝き動かされるようにこうして歌わずにはいられないのだった。人がたくさんいる場所の時は、口を手で覆い、小さな声で歌った。この歌を手放しちゃだめだ。だから歌う。これは記憶を取り戻すための手がかりだから、そういうふうに、脳の奥で誰かが泉にそう囁く。
「ねえ、れおくん」
「ん、どした?」
「二十二歳の俺は、どうして記憶喪失になっちゃったんだろう。れおくんと同棲してて、仕事もうまくいってて、アイドルとしてもモデルとしても脂ののった時期でさ。何も悲しいことなんかないじゃん……なのにどうして、今ここに取り残されてるのは過去の俺なんだろう……」
「……もしかしたら、セナは本当は、幸せじゃなかったのかもしれない」
「俺たちが大人になっちゃったから?」
「どうだろ。おれは、大人になってよかったと思ってるけど。もし今のセナが大人になりたくないって願っているのなら、そうなのかもな」
大人になりたくないならそれでもいいよ、とレオがなんでもないふうに言った。だけど繋いだ手のひらがきゅっと震えたことを泉は見逃さなかった。
うそつき。信じてない神様にやり方もわからないまま祈ってまで、本当は取り戻したいくせに。
昔より低くなった生ぬるい体温が、そんな感傷を泉に助長する。うそつき。れおくんはうそつきだ。本当は恋人の瀬名泉に帰ってきてほしいんでしょ。こんなちんちくりんの、大人になんかなりたくないと蹲っている、十七歳の青臭い男の子なんかじゃなくって……。
「俺に優しくしてくれなくたっていいんだよ、れおくん。俺はさ、あんたの知ってる瀬名泉じゃないの。あんたが付き合ってたらしい男じゃない……ただの醜い、小さな餓鬼だよ。いいんだよ、無理して、慣れないことなんてしなくても……」
医師の診断では、泉の記憶喪失は、心因性の部分健忘であるのだという。要は過度のストレスが原因で、嫌な記憶を全部消し去ってしまった状態だと。あの頃に戻りたいと願って、自ら記憶に蓋をした状態で、治るかどうかは正直わからない、と。
「それでもおれはセナのそばにいたい。おれはセナが好きだから。セナがくれたものを、ちゃんと返しきるまで、おれはずっとセナのそばを離れないって約束したんだよ」
レオが嘯く。握り合った指先から臆病者の温度がする。本当のことを言ってないのはどちらだろう。泉は自嘲気味にそう考えて唇を歪めた。大人なんて嫌いだ。誰も本当のことなんか言いやしない。いつだって自分の気持ちに正直で、本能のままに生きていて、自由で何者にも囚われない月永レオでさえ、子供を脱ぎ捨てて知らない男になっていく。
――このれおくんは、俺と「そういうこと」をしたいのかな。今も、本当は我慢しているのかな……。
泉はかぶりを振り、唇をきつく噛みしめた。最低。最悪だ。そんなことレオに言って欲しくない。レオだけはきれいなままじゃなきゃ。いつまでも子供みたいに無邪気で、明るくて優しくて、ごみためみたいな世界に差した光だったのに!
……だけど、なにより。
そんなふうに考えてしまう自分自身の醜さが、泉は一番いやだった。