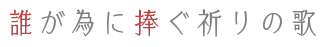
01:醜いアヒルの恋
あの日からずっと夢を見る。あの、目覚めてすぐ、「おまえはもう十七歳じゃないんだよ」と宣告された一ヶ月前の朝から。見る夢の内容はまちまちだ。知らない場所にいる夢、学院でレッスンをしている夢、大勢のお客さんたちのまえでライブをしている夢、そのへんで猫とじゃれているだけの夢……。
それら、一見無秩序な夢の中に、たった一つだけ共通点がある。
月永レオがいつもそばにいることだ。
『あ……ぁ、うぅん、おう、さま、そこ……やだあ……』
『セナ? ?王さま?なんて他人行儀な呼び方はやめろよ』
『ん……わかったぁ、れお、く、あぁああっ!!』
――だからって。
……だからってこんな夢は、さすがに、あんまりじゃないだろうか。
『やだ……れおくん……そんなふうに、ぁ、しな、いで……』
十七歳の瀬名泉は、地獄の最下層を見せられた聖職者のように泣き腫らし、両の手で顔を覆った。娼館に売り払われた箱入り娘みたいな、人間の感情の最底辺の気持ちだった。
目を逸らしたくて仕方がない。だけど釘付けにされたみたいに視線が動かない。人間の醜悪な営みから目が離せない。
『うん、セナ、気持ちいい?』
見慣れたダブルベッドの上で、二十二歳の瀬名泉が、犯されていた。甘ったるい猫なで声を上げ、男に自ら肢体を絡ませ、淫蕩にふるまい、うわごとのように男の名前を呼んでいた。嫌だ、嫌だ、嫌だ! こんな汚いもの見せないでよ。泉は叫ぶが、抵抗は何の結実も招かない。世界はなにも変わりやしない。
ただ、だらしない顔の自分が男に組み敷かれ、猥らな喘ぎ声をあげているばかり……。
『れおくん……すき……すきだよ……』
もうやめて。こんなもの見たくない。
『大好き……ずっと、こんなふうに、めちゃくちゃにされたかっ――』
「――やめて!!」
泉は羞恥と辱めとで真っ赤になった顔でなりふり構わず叫んだ。
「最低」
恨み節は、呟いた自分自身ぞっとするほど低く怨嗟の念に満ちている。ああ、このみっともない人間の屑が、きっと五年後の自分なのだ。己こそが、そう遠くない未来に、恥も外聞もなくこんなことをレオにねだるのだ。最低、最低、最低! こんなものが失われた未来の記憶だというのなら、忘れてしまって、よかったのだ。こんな醜態……十七歳の泉は望んだりなんかしない……。
「やめて……れおくんは俺のぜんぶなの……青春で……はじめての友達で……大切な人……美しい感情を綺麗なままでいさせてよ……!」
ああ、恋なんて、醜い。
なお最低なのは、二十二歳の泉がどうしてこんなことをレオに求めたのか、理解が及んでしまうこと。
――この醜い感情を恋と呼ばぬのなら、瀬名泉には恋なんて分からない。
◇◆◇◆◇
記憶喪失になった泉だが、芸能人としての仕事を何もかも放り出すわけにはいかない。世間的には記憶喪失になった事実を隠しているし、詳細を把握しているのはKnightsとマネージャー、その他一握りの人間だけだ。夢ノ咲学院の同期たちには、会うとばれてしまうやつらが何人かいるのだが……そういう手合いには、リーダーであるレオ直々に頼み込む形で箝口令を敷いている。十七歳の泉が選んだのは、何事もなかったかのように「二十二歳の瀬名泉」として振る舞う道だった。
レオはあまり泉に仕事をさせたくなかったようなのだが、泉の選択を尊重し、代わりに一つだけ条件を付けさせてくれ、と言ってきた。それが、「一人で出歩くな」というものだ。外出時はなるべくレオが付き添い、スケジュールの都合でレオが空いていない時は、他のKnightsメンバーがそばにつく。一人で放っておくと、うっかりして何が起こるかわからないというのが彼の言い分だった。一理あると考え、これには泉も素直に従った。
そんな感じで、あとはバラエティ番組など露出が多い仕事だけ調整してもらい、モデル仕事や日々のレッスンは、これまで通りにこなしている。五年の間に増えた曲に対する踊りなんかはなんとなく身体が覚えており、割合なんとかなっている。「求められている瀬名泉像」の演技は上々だ。付き添いが必ずいる以外に変わったところはない。プライドの高い泉は、そう見えるように心血を注いでいる。
……だけどたまには、うまくいかない日だってある。泉の事情を知っている人間しかいない、レッスンの時間なんかは……特に。
「あー……しんど……」
一通りのレッスンを終え、荒い息を吐きながら、泉は壁にもたれかかった。今日はどうも調子が良くない。足が重たいし、気分が優れない。おかげでステップをとちるし、ソロの歌唱で詰まった。いいことなんか一つもない。
そんな泉の様子を見かねたのか、同じくレッスンを終えた凛月がタオルで顔を拭いながらこちらへ寄ってくる。
「おい〜っす、セッちゃんお疲れ〜。どしたの? 今日、調子悪い?」
「ん、ちょっとね。夢見が悪くて」
「ふうん。夢見ねえ……。あんまし、よくない兆候だなあ……」
スポーツドリンクを飲み干し、そっかと凛月が頷いた。何かしら思うところがあるらしい。そういえばこの朔間兄弟、自分たちを吸血鬼だとか言って売り出している関係で、オカルトっぽい領域に専門職ですみたいな態度をよく示すのだ。兄の零がたびたびそういう素振りを見せているのは、十七歳の泉でも与り知るところだった。
そうやってレッスン室の隅で話し込んでいると、ぱたぱたと軽妙な足音を立て、一緒にレッスンをしていたもう一人が駆けてくる。赤い髪のまっすぐな目をした男の子……朱桜司だ。
彼は泉が高校三年生に上がった春からKnightsに加入した後輩なのだ、と凛月たちからはそう聞き及んでいた。「セッちゃんはねえ、ス〜ちゃんのことがたいそうお気に入りで、みっちりしごいてあげてたんだよ」なんて繰り言つきだった。だけどやっぱり、その実感はない。申し訳ないのだけれど。
この一ヶ月で彼が裏表なく泉を慕ってくれていることはわかってきたが、それでもどこか、他人行儀じみてしまう。彼の存在も、泉がバラエティの出演を断っている理由である。
「え、瀬名先輩……いえ、瀬名お兄さま。やはり、ご体調が優れないのですか? それはTerribleです、ゆゆしき事態です! 朱桜かかりつけのお医者さまをご紹介いたします!」
「ああ、いいから……朱桜くん。大丈夫、別に風邪とかじゃないし。本当にただの気分の問題なの」
朱桜くん、と呼びかけると、司は途端にしゅんとして悲しそうな顔になった。あ、やってしまった。この子はどうも自分の氏に誇りを持っているようなので、そこを尊重してあげようと名字で呼びかけてしまうのだが……二十二歳の瀬名泉はあだ名で呼んでかわいがっていたらしく、呼び間違える度、こうしてがっかりさせてしまう。
「あうぅ、お気軽に?かさくん?とお呼びくださいと再三申し上げておりますのに〜! 事情は存じておりますが、それでもやはり、他人行儀で寂しく感じてしまうのです。その分私がお兄さまと呼び慕うことでバランスを取ってはいるのですが! うう、わがままな司は悪い子でしょうか?」
「え、いや、そんなこと……ないけどぉ……」
上目遣いで訊ねられ、泉はうっと息を詰まらせた。かわいいふうに言われても、自意識が十七歳の泉にとって、二十歳になる司は年上の認識だ。いや泉の身体は二十二歳なんだけど。ともかく意識が十七歳なので、そんなふうにされると困ってしまう。年上の子に甘えられているみたいで。
甘えてくる同輩年上は、レオだけで十分というか、手一杯なのである。
そこまで考えてから、今一緒に暮らしている「二十二歳の月永レオ」は甘えてくるどころか泉の世話に命を賭けている節があることを思い出し、つと首を横へ振った。そう。俺の知っているれおくんは、もうこの世のどこにもいないんだ……。
「そうそう、そんなことないよお。かわいいかわいい。ス〜ちゃんはいい子だねえ……♪」
「ひゃあ、凛月先輩……☆」
「仲良しか。ともかく、おほん……?かさくん?」
「はい!」
「……気遣ってくれてありがとね」
「……はい! 瀬名お兄さま!」
考えを切り替え、兄ぶって司の頭を撫でてやる。すると司は尻尾を振る子犬のように喜び、楽しげに笑った。
(はあ。この世界で俺に求められてるのは、結局、二十二歳の瀬名泉なんだよねえ。わかって提供してやることにしてるんだけどさ)
自嘲気味に胸中で呟く。そう、誰も、十七歳の瀬名泉なんか望んでいない。司も、凛月も、嵐も、レオも、ファンの子たちも……みんな二十二歳の泉だけを欲しがっているのだ。きっとそうに決まっている。
だけどそのことを考えると、気落ちせずにいられない。だって今の泉にとって二十二歳の瀬名泉というのは、恥の象徴みたいなものなのだ。
泉は今朝見た夢の内容を思い出し、とびきりナーバスな気持ちになった。
「最悪……」
「ねえ、そんな酷かったの、今日の夢」
「そうだよお、今すぐ忘れちゃいたぁい! 二度とあんな夢見たくない」
「わあ、深刻だなあ。ちょっとそれは、放っておけないね」
凛月がずいと泉の顔を覗き込んでくる。無遠慮にじろじろと見てくる距離感のなさに、こいつこんな奴だったっけ? と疑問を浮かべながら、泉は凛月の視線にじっと耐えた。今の泉にとって、凛月はよく寝ている変なやつ……以上の認識ではないのだが、五年もユニットを組んでいれば、竹馬の友になっているなんてこともあるのだろうか。適応しなければいけないのは多分泉の方だ。
凛月はしばらく泉のことを観察していたが、数分経つと用事が済んだらしく、仰々しく頷くとおもむろに司を手招きした。
「ス〜ちゃん、悪いんだけどセッちゃんのこと連れてってくれる? 今日、二人はこのあとフリーでしょ」
「え? はい、ご用命とあらば。しかしどこにです? 朱桜かかりつけのお医者様であれば、ここかLeaderのご自宅にお呼びしますよ?」
「ううん、お医者さんじゃなくて占い師さんとこ」
「占い師…………ああ! 逆先先輩のところですね。お任せください!」
司がどんと胸を張って応える。「ちょっと」意思確認を放棄してどんどん進んでいく話に、泉は割り込んで異を唱えた。「何の話してるわけ?」。
「え、いや何、占い師って」
「逆先夏目……一個下の学院の後輩。高二のセッちゃんだと、まあ記憶にはないかもね。あの子がユニットを組んだのはセッちゃんが高三になってからだったし」
「そうじゃなくて……いや、それもそうなんだけど、なんで占い師?」
「それはねえ、あの子が魔法使いだから。あと、?五奇人?だしね、夏目くんは」
兄者と同じ、?夢ノ咲の怪物?として括られた子たちの一人なんだよ、と凛月が人差し指を唇にあててそっと呟いた。
奇人。十七歳の泉でも、ギリギリ、聞いたことがある単語だ。いつからか、誰からともなく呼ばれるようになった、夢ノ咲が誇る天才たちの総称。生徒会長を務めていた朔間零や、同じクラスで顔見知りだった芸術家の斎宮宗、演劇の申し子日々樹渉、ほぼ不登校だったので何者かよく知らない深海奏汰……。彼らは同学年なので一応聞き知っていたのだが、一年生にもう一人いたのか。
「奇人、ねえ。確かにみんな突出した天才だったけど、なんだったんだろ、あれ」
「まあ、過去にエッちゃんが行った悪行に関しては割愛するとして……。王さまと並ぶ才能の固まりだったよね、みんな。そう、王さまと同じ……」
「……何? その顔」
「ふふふ、何でもな〜い。とにかく、行っておいでよ。セッちゃんが記憶喪失である限り、あいつらと無縁では、多分いられないし」
凛月が意味深長に微笑む。本当、何を言っているんだろう、この男は。「五奇人」なんて集団、絶対に縁なんかないと思うのだけど。凡俗である瀬名泉には、天才なんてお呼びじゃないだろう。レオだけは、何故か気に入られてしまったので例外としても……それでも異次元の住人だなあという気持ちがあるのだ。
今でも正直、レオと一緒に住んでいるのが信じられない。あの、音楽に愛された稀代の天才が、自分のためにサニーサイドアップを焼いてくれているとか、夜は一緒に眠ってくれるとか、時々掃除機を掛けてもくれるというのが……現実味がなさすぎて夢なのではないかという気がしてきてしまう。
おまけに泉の恋人……。昔のレオを思い返して並べると、悪い冗談みたいな響きだった。レオが音楽以外を特別に愛するなんて理解出来ない。だけど確かに、あのレオは泉に何もかも奉じて尽くしてくれる。十七歳の月永レオと二十二歳の月永レオの間にある乖離が、いつも泉を戸惑わせる。
姿は、まだ見知ったものだ。どうやら身長は五年間の間にろくすっぽ伸びなかったらしい。声も聞き慣れたものだし、顔も、あの女の子みたいにかわいい華奢なつくりをしたまま。
だけどあの生ぬるい体温と、無条件に与えられるだけの優しさが、十七歳の泉に警鐘を鳴らし続ける。――信じちゃだめ。この人はもう俺の知ってるれおくんとは別人。大人の俺に汚染されちゃったあとなんだから。
泉は表情を曇らせ、唇を噛みしめた。それを見て、凛月が「だいじょうぶ?」と背中をさすってくる。凛月の手のひらの冷たさは昔と何も変わらない。五年前と一緒。「ま〜くん」とかいう幼馴染みの話ばかりするのも、全部一緒。
世界もレオもこのぐらい不変だったらよかったのに。どうしてこう、ままならないんだろう。
「ねえセッちゃん、これだけ今聞いてもいい?」
帰り支度を始めた泉の背に、凛月が訊ねかける。泉は顔を向けもせず、「なに」とだけ小さく声を返した。すると凛月は鋭くこんなことを問うてくる。
「今のセッちゃんにとって、二十二歳の自分ってどんな存在?」
泉は一瞬、手を止めて押し黙った。脳裏に、あの醜いエゴのかたまりがちらつく。征服者に絡みつき喘いでいた、汚らしい男の姿。
「…………。汚らわしい屑だよ、心底……嫌い。大嫌い」
「ふうん。それじゃ、二十二歳の王さまは?」
やっとの思いで振り絞るように答えると、間髪入れず凛月が畳み掛けた。泉は、夢の中で、請われる通りに優しく泉を犯していた男を思い浮かべた。それから、いつも手を握ってくれるあの温度を。
二つは線で繋がり、泉の思い出と交わることを拒絶する。あんなれおくんは知らない。俺の大切な友達とは違う。れおくんはセックスなんかしない。性欲なんかない。だからあれは、
「知らない男のひと……」
唇から漏れ出た声は、驚くほど震えて力なかった。通り魔に強姦された生娘の声みたい。脳裏には、まだ、穢らわしい二匹の大人が交尾している図がこびり付いている。
◇◆◇◆◇
司に連れられてやって来た場所は、人気がなく、ひっそりしていた。アンティークな内装と調度品の趣味が、「いかにも」といった感想を抱かせる。泉は前に進むと、この館の主に「どうも」と一礼をした。
「やあ、待っていたヨ、瀬名先輩。ようこソ、逆先夏目の占いの館ヘ……☆」
「……随分静かなところだね、ここ」
「わざわざ人払いしておいたんだヨ、デリケートな話みたいだシ。君が記憶喪失になっていることハ、世間様には内緒なんでしょウ? それに配慮しているのサ」
「はあ、そうなの」
促されるままに腰掛け、夏目の顔をまじまじと見る。眼差しは、一瞥で心の奥を見透かしてしまいそうに鋭い。そうか、この子も天才と呼ばれる化け物なんだ。泉がそんなことをぼんやり考えていると、夏目がトントンとテーブルを叩いて本題に入っていく。
「じゃあまず、現状と夢の内容について教えてくれるかナ? 守秘義務は守るヨ」
「……わかった……」
泉は生唾を飲み、今自分が置かれている現状を少しずつ夏目に話していった。記憶喪失になった日から、毎日、レオとの夢を見ること。今朝の夢が特に生々しい内容だったこと。記憶喪失は自分の心が負荷に耐えられなかった結果だと聞いているので、もしかしたら夢の中に、失われた記憶を取り戻すヒントがあるのではないかと考えていること……。
それから、時間さえあればレオと二人で出掛け、辿り着いた先々で不思議な歌を歌ってまわっていることも伝えた。その歌のことは一切わからないが、歌うといつも切ない気持ちになる。これもきっと記憶に連なるものなのだと思う……と告げると、夏目は深く頷いた。
「話は概ね分かったヨ。最大の手がかりハ、瀬名先輩が思っている通り、歌だろうネェ。単に手続き記憶として残っているものというよリ、エピソード記憶の引っかかりに近そうだシ。たダ、その歌の意味がわからないのデ、トリガーとしてはっきり機能していないんだろうネ」
「じゃあ歌の意味がわかれば、記憶は戻るかもしれないってこと?」
「恐らくはネ。正しい意味でなければいけないけれド。で……目下の問題ハ、そっちじゃなくて夢の方カ。単刀直入に聞くけド、これ、悪夢なんだよネ?」
「今朝のに限って言えばそうだよ」
「ふうん……」
いまいちしっくりきていない様子で夏目が唸る。こんなもの、悪夢以外の何物でもないんだけどなあ。泉が不服そうな顔をすると、それに気がついたのか、夏目が「ああ、ゴメンネ」とひらひら手を振って唇を開く。
「深い意味はないヨ、申し訳なイ。……まず基本の話をしておきたいんだけド、夢というものは原則、『願望の表れ』なんダ。この法則ニ、例外はなイ……人間の脳はネェ、自分が知っていること以上の情報を開示することハ、出来ないからネ。だからこの法則に則って考えるト、月永先輩にそうされたい、と瀬名先輩自身が心の何処かでは願っていることになル」
「……そんなの、信じたくない。どっちかというと……二十二歳の俺の記憶を再生してるだけって言われた方がしっくりくるけど」
「フム、まあそのセンも有り得ないわけではないと思うけド……」
夏目がペンを取り、紙にさらさらと何かを書き記した。夢占い学では、好意的な相手との合意の行為は、運命の好転や幸運の兆しとして捉えられる。単純な占いごとで考えれば、ちょっと気恥ずかしい吉兆程度に捉えておけばよい。夏目のペンが一旦そこで止まる。
「でもネ……」
もし、泉が言っていた通り、夢の内容に起きてから嫌悪感を示し、なおかつそれが今失われている本来の記憶だとするならば。それは月永レオという人物への深層心理下での拒絶を示す可能性がある、と夏目のペンは文字を紡いだ。
「俺がれおくんのこと嫌いってこと?」
「人格に対する好き嫌いというよリ、存在そのものに対する忌避感だネ。――瀬名先輩、いわゆる『天才』って存在に対して引け目があるでショウ?」
「……それは、ある、けど。俺は天才じゃなかったから。天才の気持ちが分からないって、いつも思ってる……」
二十二歳になった俺がどう思ってるのかは知らないけど、今は少なくともそうだ。そう答えると、夏目は何かに納得したようで、ペンをかたりと置く。
「にいさんたちに比べたラ、ボクなんか大した天才でもないんだけどネ、それでもこれだけは明確に言えるヨ」
「……何?」
「天才本人は、自分のことをさりとて特別に思ってはいないということサ」
それから夏目は物々しい声でそう告げた。声にはありありと実感がこもっていて、その言葉の真贋は疑いようがなかった。
泉は息を呑む。
「嘘。だってあいつ、自分のこと天才だって言って憚らないんだけど」
「それもネ、周囲の人間に言われ続けている『こだま』を反芻してるだけだと思うヨ、それ以外に自分を表す言葉を知らなかったんじゃないかナ。……ボクら?五奇人?だっテ、別に自分たちで名乗り始めた訳じゃないサ。他者にそう貶めらレ……迫害されることデ、ボクらは出会っタ……。決して天才同士で寄り集まってサバトを開こうなんて思っちゃいなかったんだヨ。
世の中、確かに天才鬼才のカテゴリ分けは存在していル、けド、そのレッテルを貼り付けるのはいつだって外野のやつらだヨ」
「……天才同士惹かれ合うみたいなのも、なかったわけ?」
「それこそ謂われのない妬みサ。宗にいさんが聞いたら憤慨するネ、あのひとは芸術を大衆へ伝導することに心血注いでるんだかラ。自分の歌を聴かない聴衆に対する怒りも激しいけド、別にそれモ、天才じゃない人を罵倒したいって訳じゃあなイ。たとえ相手がどれほどの天才だろうと話を聞かない奴には怒るっていうだけのシンプルな理屈だヨ」
ボクらも紐解けばけっこう単純な生き物なんだヨ、と夏目が言う。誰かに満たされたいと願ったり認められたいと祈るばかりの、皮に包まれた骨と肉の集合体に過ぎないのだと。根本のところで、天才とそうでない人の区別は無意味だ。だってみんな人間なんだから。
「……嘘だ」
「嘘じゃないヨ。……月永先輩のことハ、ボクもそれなりに知っていル。ボクなんかよりあのひとを最後の五奇人に数えたほうが相応しかったんじゃないカ……なんて考えたこともあるからネ。まァ、ボクが思うニ……あのひとが奇人構想から外されたのハ、彼が皇帝・天祥院英智の数少ない友人だったからというそれだけの理由なんだろうけド。ともかく、あのひとは天才だけド、それは決して普通の男の子としての権利を手放したって意味にはならなイ」
だから身勝手に変化するし、誰かを嫌うし、憎むし、愛して恋をしたりもするだろうネ、と占い師は言い聞かせるよう静かに言い放った。
「まず前提が間違ってるんダ。月永先輩が瀬名先輩に優しくするのっテ、そんなにおかしいことなノ? 夜毎の夢は、そのことを問いかけているのかもしれないネ。月永先輩と瀬名先輩が恋をしたことハ、本当に穢れの象徴なのかナ」
「あ、当たり前じゃん。あんなの……だめだよ……れおくんは綺麗じゃなきゃ、俺が汚しちゃ駄目なのに……」
「ああ、そウ……。じゃあ、これだけ覚えておいテ?」
それでも言いよどむ泉に、夏目が一つ息を吐く。それから彼はすうと目を細め、語調を変え、声音を変えた。そして魔法をかけるための言葉を囁く。
「人を変えるのは、いつだってその人自身だ。もし月永レオが変わってしまったというのなら、それは月永レオの決断であって、君の関与するところではない。君の変化もまた、君自身の責任だ。――彼を変えてしまうなんて思い込みは、驕りだよ」
「……え、」
「まずは余計なレッテルを剥がしテ、瀬名先輩自身の目で確かめてみるべきじゃないのかナ。月永先輩が本当に変わってしまったのカ。瀬名先輩自身がそのひとをどう思っているのカ。自分の気持ちがわからないのニ、真実なんて見えやしないヨ」
魔法をかけ終え、夏目が立ち上がった。
泉はぽかんとして、彼の言葉を胸中で反芻する。レオは、勝手に変わっていく。勝手に誰かを嫌うし、誰かに恋する。……本当だろうか? 本当に? あの、きれいなものしか知らない、純粋無垢な赤ちゃんみたいな、男の子が……?
心臓の位置を、きゅうと撫で回した。泉の手のひらは冷や汗でぐっしょりと濡れている。鼓動がいやに駆け足で鳴り続けている。自分の本当の気持ち。そんなのわからない。レオの考えていることもわからないし、五年間にあったことも何一つわからない。世界の全ては不親切で、縋れるものは二十二歳のレオが伸ばす指先ばかりで、この手を本当に取って許されるのかさえ、誰も教えてくれないのに。
「……シンデレラに掛けられた魔法はネ、永久に続いてはくれないんダ。ハッピー・エンドを願うなラ、ガラスの靴ぐらい自分で取りに行くことだヨ」
最後に、逆先夏目は泉を真っ直ぐ見てそう告げた。泉は目を瞑った。あんな夢を見ておきながら今日の夜もまた抵抗なくあのダブルベッドで眠りに就こうとしていた自分の気持ちなんて、考えたくもない。浅ましい。
◇◆◇◆◇
「ね、王さま。聞いたよ、十七歳のセッちゃんからしたら、二十二歳の王さまは『知らない人』みたいなもんだってさ。自分に優しい王さま、よくわかんないみたい」
「うう。そう面と向かって言われると、おれも結構傷付くんだぞ、リッツ。いやまあ……毎日毎日、距離置かれてるな〜警戒されてるな〜って思いながら暮らしてるから、薄々気付いてたけど〜……」
控え室でお菓子をかじりながら、凛月がなんとはなしにそう言った。ふたりで、この次のラジオ収録を待っているところだった。メインパーソナリティが凛月の番組で、レオがゲストの回を収録するのだ。
凛月が差し出してきたポッキーを受け取りながら、レオが露骨にへこんでみせる。この一ヶ月、記憶喪失の泉と一緒に暮らしてきたが、泉の記憶が戻る素振りはない。それは別にいいのだが、記憶がない泉はレオの存在について常に懐疑的なので、厚顔無恥には自信のあるレオでも、つらいことはつらい。
凛月はそんなレオを見ると、まったく悪びれることもなく、あははと笑った。レオの反応を楽しんでいる。まったくこの男は悪魔だ。いや、吸血鬼なのか。よくわからないけど似たようなものだとレオは思った。次の新曲は、「悪魔に小突かれるセナ」にしよう。
「それにしても回りくどいことするよねえ。なんで? 王さまってマゾなの?」
「そんなことない! ……と、思う。たぶん。おそらく。希望観測的に!」
「歯切れ悪すぎない?」
「へへ……犯した罪に自覚的な良い子だから!」
「良い子は犯罪に手を染めないよ、王さま」
まあ、王さまはそこそこ良い子の方ではあると思うけどね。凛月はポッキーを咀嚼しながら呟いた。そう、月永レオは善良で子供っぽくていい人だ。ただし自己完結が早いしプロセスをろくに踏まない。計算式をすっ飛ばして答えだけ書いた紙を提出しがち。泉が記憶喪失に陥ったのも、突き詰めればそのあたりの積み重ねが原因なのではなかろうか。
……まあ、責任問題の話をすると、もれなく凛月……というかKnights全員が共犯になってしまうのだが。
そこは素知らぬふりで押し通し、レオに自供を促す。
「セッちゃんをあんまり困らせないであげてね」
「わかってる。……おれはね、単に、セナにもらったものをちゃんと返してやりたいんだ。セナのことを守ってもやりたい。壊れたおれをそれでも待って許してくれたセナだから。それだけ。それがおれに出来る唯一の恩返しなんだよ」
「うわ、重……」
ポッキーを嚥下しきると、凛月はあからさまにどんびいて見せて、やだやだ、と手のひらを振った。
「歪んだ愛情だよねえ、それって」
「……そうなのかな」
「うん。ス〜ちゃんには、ちょっと見せられない。修羅場すぎるので」
「……そうなの?」
「そうだよ。でもしょうがないか。王さま、誰かを好きになったの、セッちゃんが生まれてはじめてなんだもんね……」
初恋の相手があの高嶺の花みたいなセッちゃんじゃねえ、と凛月が他人事みたいにぼやく。恋に気付くのが遅すぎたよね、ふたりともさ。だからってこんな仕打ちを強いるのは、お互いに不健康だなと思ってるけど。
「王さまの愛し方は、ちょっとむごいなあと、思わないこともない」
凛月が、やや冷ややかな声でレオを糾弾した。レオはその言葉に甘んじた。それでもレオは、泉のそばにいたかった。泉を手放したくないし、責任を取るとしたら、自分しかいないと思っている。
泉に好意を告げられたあの日から、その気持ちはずっと揺るがない。
「けどさリッツ、これが最善だよ。セナには優しくしたい。セナには幸せになってほしい。だけどそのふたつが両立出来ないっていうのなら、おれがいる限りセナが傷付くっていうのなら、どちらか片方は痛みを取り除いてやるしかないだろ」
「そうだねえ、俺もま〜くんを愛してるから、その利己的な愛を否定はしないよ。博愛主義者じゃなくなった王さまってこんなにめんどくさいんだ……ってひたすら引くだけ」
「ええ〜……?」
「いつだったっけ、ステージ上でセッちゃん捕まえてさ、『おれのセナ!』って堂々と言った時は、正直放送事故になるかと思ったし? ま、セッちゃんが自らを磨き上げたのは、それを見つけた王さまのためだって知ってるので、不問としたけど。正直きわどかったよ〜」
炎上しなくてよかったよね、本当。まあちょっとは燃えてたけど。凛月は遠い目をしながら次のお菓子に手を伸ばす。
――はあ、それにしても、十七歳か。
(よりによって巻き戻ったところが恋を知る前のセッちゃんとは。好きって認められてないぶん、絶対しんどい。かわいそうだけど、それがセッちゃんの好きになった男なんだよね……)
レオの方をちらちら見ながらお菓子を貪る。泉はしきりに「レオが優しくて怖い」「十七歳のレオはもっと傲慢で我が儘で子供だったのに」ということを凛月に話してくれるが、凛月に言わせれば、二十二歳のレオは十七歳のレオと変わらず、傲慢で我が儘でお子様だ。
(……早くあの歌が悲しい歌じゃなくなるといいな……)
凛月がそう考えていることに気付いているのか、いないのか。
気がつけばレオは、泉が先々で歌うあのはりつめたメロディを、誰に聞かせるでもなくハミングしていた。