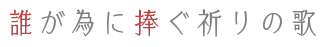
エピローグ:目覚めよと呼ぶ声が聞こえ/終曲
「What!? 瀬名先輩、お助けを! Leaderが……Leaderが、私をまったく離してくださらないのですが!!」
「ああ、それねえ、なんか罪滅ぼしのつもりらしいから。悪いけどもう少しだけそうさせてあげてくれない?」
「ええっ、そんなあ……うう、は、離してくださいー。あったかくて優しくて、このままでは司は駄目になってしまいます……」
司が観念してじたばた暴れるのをやめると、レオは調子に乗って頬ずりをはじめ、「ごめんなスオ〜、ほんとにほんとに、スオ〜のこと大好きだぞ……!」と熱っぽく囁く。
まったく調子がいいのだからこの男は。泉は溜め息を吐くと、司を助けてやるため、レオをがばっと引き剥がした。「ああっ!? セナの薄情者!! お母さんは我が子がかわいくないのか!?」とわけのわからないことを言っていたが、黙殺。お母さんではないし、司も子供ではないが、かわいいに決まっているだろうが。なにせこんな先輩達をずっと愛してついてきてくれる、たった一人の後輩なのだから。
あれから医師の診断をもらい(奇跡的に全治した、まるで魔法のようだという診断書が出たのでちょっと笑った)、一ヶ月あまりにわたった記憶喪失の日々は完全に終わりを迎えた。そのことをKnightsのメンバーに伝えると、誰からともなく、じゃあ快気祝いのパーティをしようという話になり、今、レオと泉が暮らすマンションに五人全員が集まっている。
「Leaderのおうちと聞いてちょっと身構えていたのですが、思いの外綺麗ですよね。壁に落書きもないし」
「それセナも言ってたな〜。みんなおれのことなんだと思ってるの?」
「五歳児、かな……」
「あら凛月ちゃん、アタシは三歳ぐらいかと思ってたわ」
「なに〜っ!? おまえら、王さまに向かってだいぶ不敬じゃないか!? がるるるっ、おれだってものの分別ぐらいつく!! ナルやリッツより、随分先に大人社会に出てたんだからな!!」
頬を膨らませるレオに、冗談よォと嵐や凛月が笑いかける。いつも通りの光景。ピリピリしてないし、変な気遣いもないし。みんな自然体で楽しそうだ。
「本当、王さまの暴走のせいで大変だったんだから……。かさくんには、特に負担かけたよね。深海が言ってたんだけど、あんたに『お兄さま』呼びさせるのも、王さまの悪巧みの一環だったらしいじゃん。慣れないことさせたでしょ。……ごめんね」
「あっ、いえ! 瀬名先輩のことをお兄さまと慕う気持ちは、本当にありますので。鳴上先輩も、凛月先輩も……みんなみんな、私の自慢のお兄さまたちです。い、嫌でなければ、これからもお兄さまと呼ばせていただいても私は構いません……♪」
「えっスオ〜、お兄さまの中におれが入ってなくない?」
「あんたは家長でしょ。ともあれ、今まで通り『瀬名先輩』でいいよ。そのほうが慣れてるしさ」
頭をくしゃりと撫でてやると、司が無邪気にはにかんだ。何か、聞いた話(何故か千秋経由で奏汰から電話が掛かってきたのだ)では、泉を取り逃したとかでレオにこっぴどく叱られたらしいのだが、思ったより元気そうで安心する。
無論、司に激烈に冷たく当たった(と電話口の向こうで奏汰がぷんぷん怒っていた)らしい件については、すでにみっちりとレオを説教したあとなのだが……それで反省したせいなのか、今度はレオが司にベタベタ構い出すし。あれはあれで教育上よくない気がする。いや司も、もう二十歳なのだが。奏汰も言っていたが、手がかかってかわいかった子ほど、いつまでも子供扱いしてしまうのは年長者の悪癖だ。
凛月たちが来る途中で買って来てくれたオードブルなんかを広げ、オーブンからメインディッシュをテーブルに運ぶと、とたんに美味しそうな臭いがダイニングにたちこめた。すっかりお腹が減ってしまい、五人で席につくなりそぞろに乾杯、そのまま仲良く食事に入る。最近の仕事のこと、今度やる何度目かのワールドツアーのこと。様々な雑談に話を咲かせている最中、思うことがあり、泉はフォークにラザニアを突き刺したまま不意に訊ねた。
「で、結局あんたたち、どこまで何を知ってたわけ?」
「何って、ああ……セッちゃんが王さまと別につきあってなかったこととか?」
「面と向かって言われるとなんか微妙な気分になるけどぉ……まあそうかな」
「うーん、まあ、大まかなところまでね」
さすがに、お家がバラバラだったことは知ってたしねェ。嵐が呟く。かさくんも? と訊けば、末子はハムスターみたいにもぐもぐ頬を動かして口の中のものを全部嚥下し終わってから、「よくわかりませんが、とりあえず記憶喪失になったので安全のためにLeaderが身柄を預かられた……と聞いてましたよ」という返事を寄越す。
ああなるほど、この子は殆ど何も知らされていなかったんだな……。一人合点がいって泉が頷くと、凛月がちいさく息を吐いた。
「そうそう。ス〜ちゃんはそのへんのつめが甘いから、俺が占い師さんのとこ連れてってって頼んだ時も、『Leaderのご自宅』って言ってたしね。正直、王さまの嘘がいつバレるかひやひやもんだったよ? セッちゃんが昔から王さまのこと好きなのと同じぐらい、バレバレだったし……」
「あ、やっぱりそうなのですね……。ちなみにお兄さま、一体いつからこのCrazyな方を……」
「出会った時からでしょ」
「最初からよねェ」
「ちょっとかさくん、もうお兄さまはいいってば」
そんな、姉に彼氏が出来た弟みたいな、初心な反応をされても。不覚にもかわいい。かわいいけどその反応もちょっといかがなものか。
あう、とかなんとか言いながらサラダを頬張る後輩の頭をぽんぽん撫でてやると、対面の嵐と凛月が微笑ましそうにこちらを見てくる。レオと泉で司を挟む並びになっているのがやたら面白いのか、異様に楽しげだ。
泉がなんだなんだと視線をやると、それに気がついたのか、嵐がひらひらと手を振った。
「ま、なにはともあれ。収まるところに収まったって感じで、よかったわよねェ。泉ちゃんのいないところで、王さま……デュエルに明け暮れていた頃と同じかそれぐらい、怖い顔してたし。もう王さまのあんなピリピリした顔見るの、や〜よ? ハッピー・エンドがずっと続くのが、一番よォ」
「あ、ここにもハッピーエンド症候群。まあ俺は、どっちの言い分もわかるよ。俺だってま〜くんに何かあったら、自分が何するか予測つかないもん。――でセッちゃん、王さまとのキスはどうだった?」
「はぁ!?」
「え。だって記憶戻ったのって、王さまとキスしたからでしょ?」
ちがうの? 凛月が犬歯を見せて笑い掛ける。いきなり投げ込まれた剛速球に、泉はすっかり動転してしまい、勢いで司の顔を手で覆った。「ええっ!? 瀬名先輩!? 瀬名先輩〜!? 司は瀬名先輩がLeaderとき、き、Kissをしていても、変わらずあなたのかさくんです!!」とかなんとかもごもご言っていたが、無視。
「あ、あんたねえ、かさくんの前で何言ってるの!」
「だって本当のことじゃん? ていうかス〜ちゃん、セッちゃんに比べたら全然動揺してないし。もう一人前だもんね〜、セッちゃんが初物じゃなくなったみたいに」
「へ? 初物? それはどういう意味ですか、凛月先輩?」
「ちょっとくまくん!!」
「ふふん。吸血鬼は血の匂いでそういうのがわかっちゃうのだ。な〜んて……実は悪い子の王さまから聞いたんだけどね。あ〜あ、シンデレラだったセッちゃんが、大人の階段上っちゃったなあ……」
古い流行歌を口ずさみ、凛月がけらけらと小悪魔のように笑った。まったく、どいつもこいつも泉をシンデレラにたとえやがって。確か……夏目と零もそんなことを言っていたような気がする。
とはいえこれ以上凛月の相手をしてやっても喜ばせるだけなので、泉は溜め息を吐くとぱっと司を離し、キッシュを口の中に放り込んだ。
シンデレラが務まるほど自分はうつくしい生き物ではないと自負している泉だけれど、呪いに掛けられた日々が、ガラスの靴が見つからないまま彷徨っているように心細かったのは本当のことだ。五奇人がちょっかいを出してきたのも、大方、彼らが心優しい生き物だからなんだろうし。そう思うと、記憶喪失の日々も、全てが悪いことばかりではなかったのかもしれない。自分が見失っていたことを、人との関わりの中で見つけることが出来たのだ。
特に、あの歌が……本来であるならば引き出しの中に秘めた悲しみとして埋没していくだけだったラブソングが、ちゃんと日の目をみてレオに届けられたのは、五奇人連中のおかげと言えないこともない。そのあたりの悲喜こもごもを一言で奇跡と括るわけではないけれど、怪我の功名みたいなところはあった気もする。
「そういえばあいつら、やたらあの歌のこと褒めてくれたっけ。何でだろ、ある意味生き恥晒してるみたいなものなのに」
「ふふ、秘めた恋心ほど美しい芸術もそうないわよォ、泉ちゃん。アタシもあの歌、好きよ。ね、よかったらまた歌ってちょうだい。最初に聞いた時はね、健気なほどもの悲しい歌だなって思ったけど、今なら違うふうに聞こえるんじゃないかなってワクワクしてるの」
呟くと、嵐がウインクをして寄越した。そういえば最初にこの歌を歌ったのは、記憶喪失だとわかってすぐの、練習室でのことだったように思う。一人で口ずさんでいたつもりだったのだが、聞かれていたのか。
それにしても健気とか芸術とか、ろくでもないことを言うものだ。
「な〜るくん、なに斎宮みたいなこと言ってるの。ってか、嫌だよ。なんかあの曲歌うと、五奇人の連中が出てきそう。病み上がりだからさあ、まとめてあいつらの相手してる余力なんてないし」
などと言ってしまったのが、運の尽き。
次の瞬間、部屋中に、突如として高層マンションの窓ガラスを派手に突き破る音が響きわたった。
「――呼ばれて飛び出て、Amazing! あなたの日々樹渉と愉快な仲間達ですよっ……☆」
「って嘘ぉ、で、出た! 本当に出た! ちょっとどうすんのこれ、収拾着かないんだけどぉ! ってか、ここ、何階だと思ってるわけ!? 非常識にもほどがある……!!」
「この日々樹渉の辞書に『不可能』の文字はありません。何らかのトリックを用いて、必ず現実にしてみせましょう! あなたがたに愛と驚きとAmazingを! 受け取っていただけますか?」
「いらん、ていうか窓ガラス直しなよぉ!?」
人が入れそうな巨大なプレゼントボックスごと飛び込んできた渉が、「おや、少々お待ちを!」と右手を振ったとたん、粉々に砕けていたベランダの窓が一瞬で修復する。いや、これは最早魔法だろう。泉は呆然と非常識な光景を見るほかなかった。タネと仕掛けがわからなければ奇術は魔法と変わらない、天祥院あたりと意見が被りそうなのは癪だけど、実際、隣で司が泡を食ったような顔をしているし。
Knightsの面々が固まりきっていると、その隙にプレゼントボックスからひょいひょいと五奇人連中が這い出てくる。みんなそこそこいい体格をしているのに、どうやって詰まってたんだろう。泉は己が蓮見敬人と共に箱詰めにされた過去を一瞬思い出し、そしてゴミ箱に放り込んだ。しかし二つ隣のレオが、「わはっ、昔のセナみたい!」とはしゃぎはじめたので、その試みは失敗に終わった。
「いや、ていうか、本当に何しに来たのあんたたち」
落ち着け。こういう時は、心を無にするのだ。
司の背を通り越して後ろ手にレオの腕をつねりながら、泉は淡々と訊ねる。すると渉は底抜けに明るい笑顔で大仰に盛大に身振り手振りを交えて話し始めた。
「『おめでとう』を言いにです、騎士さん、王さま♪ 本日は我ら一同、はなむけに参りました……☆ ああでもご安心を。それが終わったらすぐに退散しますので!」
「え〜、日々樹くん、せっかくじゃし長居して行かぬか? 我輩ふつうにお腹減っておるし。美味しそうな匂いもしとるし。月永くんがさんざん、瀬名くんの料理は絶品だとかのろけておったし〜……」
「フン、相変わらず品性の欠片もない行為をしているのだねッ、月永は。瀬名……この男に対して度し難いとか付き合いきれないと思ったら、いつでも逃げ出してよいのだよ。月永はなんというか、お子様だからね? 予測不能で、直情径行で、本能にばかり忠実で……そこがまあ、腹立たしいところに芸術家として秀でた部分を生んでもいるわけだが」
「チョット……宗にいさん、落ち着きなヨ。……あ、一つだけ弁明させてもらうとネ、ボクは一応反対したんだからネ。あんまり大人数で押し掛けようなんていうのは美しくないシ」
「ふふ、おめでたいひは、『ぶれいこう』ですよ、なっちゃん。ちあきも、つねづね『たのしいのがいちばん』だっていってます。ぼくは、みんなで『おいわい』をできたら、とっても『たのしい』なっておもいます〜♪」
「……ええい、一斉に喋るな! この摩訶不思議ちゃんどもが!!」
わらわらと喋り始めた五奇人を叱りつけると、渉がわざとらしく肩をすくめて、指を弾いた。途端にプレゼントボックスは立ち消え、ダイニングテーブルについていたはずのKnights五人ともが、リビング側に拉致される。慌てる泉の前に、零がずずいと歩み出た。彼は唇に人差し指を添え、なんだかあざとい表情をすると上目遣いで泉に迫る。
「で、歌ってくれるのかえ? 瀬名くん。我輩久しぶりに瀬名くんの歌が聴きたいのう、零ちゃんチーム時代のことも思い出してくれたのじゃろ、そのよしみで、な」
「いや、思い出したけど……あの時あんた俺のこと散々おちょくって結局王さま見つけてきてくれなかったじゃん。なんの恩義もないけど」
「おうふ、痛いところを突きよる。凛月や〜、凛月からもどうか口添えしておくれ」
「やだ」
「Knightsのみんなは我輩に辛辣じゃのう、悲しい! あとは斎宮くんにパスじゃ」
「ふん……零の言葉にのってやる場面でもないような気はするが、瀬名の歌をもう一度聴きたい気持ちは、僕も同じだよ。……瀬名、どうか歌ってはくれないかね。無論僕たちからも、とびきりの贈り物を用意している。だから……」
「ふふ〜、ぼく、『きしさん』のうたはまだきいてないので。すっごく、たのしみです……♪」
「あ、ボクも聴いてなイ。にいさんたちが口を揃えて褒める歌ダ、後学のために聴いておきたいネ」
零をかわしても第二・第三のおねだりが泉を襲い続ける。泉は頭を抱え、深く深く溜め息を吐いた。もうこれ、歌いたくないと言っている方が疲れる。一曲歌って満足してくれるのなら、その方がよっぽど楽だ。
そう思ってちらちらとKnightsのメンバーを横目で見ると、レオと目が合った。レオは諦め始めた表情の真意を敏感に悟ると、目をつむってぶるぶる顔を横へ振った。
「セナ〜、別にあれ、聴かせてやることないぞっ。……ていうか、どうせ歌うなら、別の曲があるし」
「……ああ。あれのこと? まだあんまり練習してないんだけど……」
「あらあらっ? 泉ちゃん、王さま、何の曲?」
「ん。おれが最近書いてたセナのための新曲!」
言われてみれば、そんなのもあったっけか。
何かと言うと、この前レオが「恋の歌」とか言いながら作曲していたあれである。アップテンポで、かわいい旋律。ちょっと早いリズムに、ポップでキュートな、幸せそうな曲……。
記憶が戻ったあとでわかったことなのだが、なんのことはない、あれは元々泉のソロ用にと書いていたものらしい。レコード会社側から「そろそろまたKnightsのみんなでソロを発表したい」と打診されたのが切っ掛けなので「いちおう仕事」みたいに答えていたそうで、紛らわしいとちょっと怒ったあと、嬉しくなってすぐ歌詞をつけた。わりと、出来たてほやほやだ。
「ふうん、その歌、そんなにすごいノ?」
「当たり前だろ、なにしろ、恋を知ったおれと愛を受け入れたセナで作った、最新最高のラブソングだぞっ……☆」
「えっマジで……? 王さま、セッちゃん、子供の前でそういうことしないで。情操教育に悪い」
「凛月ちゃん……あなたついさっき司ちゃんももう一人前とか言ってなかったかしら」
「凛月は二枚舌の天才じゃからのう、そこがまあ小悪魔かわゆいところなんじゃが……」
「――ああもう、チョ〜うるさぁい! 全員黙って! これじゃいくら俺が歌ってあげたって、聴こえないでしょお!!」
十人もいるので、泉が突っ込むより早く、会話が乱立して場が混沌としてゆく。パン、パン、と強めに両手のひらを叩くと、全員が一斉にびくりとして、静かになった。司や奏汰たちが、ものすごく期待した目でこちらを見てくる。渉なんか、鳩をばさばさ飛ばしてどこからともなくフラワースタンドとマイクを取り出す始末だ。
「だから、耳の穴かっぽじってよく聴きなよねえ。まだレコーディングもしてないやつ、あんたたちにだけ特別に聴かせてあげるんだから……」
渉からマイクを受け取り、スイッチをオンにする。レオがいそいそとノートパソコンを取ってきて、スピーカーに繋げるとデモ音源の準備を完了させる。
それは恋を知った二十二歳のレオが書いたかわいい曲に、自分の恋心を受け入れた二十二歳の泉がつけた愛の歌。ちょっと気恥ずかしいなという気持ちがないわけではないが、泉はこれから、この歌を世界中のお姫さまたちに聴かせるのだ。それを思えば、この一ヶ月、騒動に関わっていた彼らに恋心を開帳するぐらい、大したことではない。
泉は大きく息を吸い込み、それから、澄み渡って玲瓏な声で、密やかに告げた。
「曲名は――……」
/誰が為に捧ぐ祈りの歌