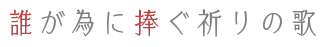
06:わが青き春のすべて
※R-18シーン含みます。高校生以下の閲覧はご遠慮ください。
主よ 召しませ 祈りの歌を
いのち 言祝ぎ 生誕の歌を
あなたの愛を讃えましょう あなたの夢を偲びましょう
どうして力は 優しいあなたを苛むのだろう
そのことを胸に描くたび 私の心は 地に墜ちる
嗚呼 罪深きかな 罪人の調べ
けれど 愛おしき 主への懺悔
主よ赦したまえ 憐れみたまえ
あなたが今日は 眠れるように
この歌はすべてあなたに捧ぐ
愛しい人への子守歌
「〜〜♪ 愛しいあなたへ、夢よりも確かに――……」
雨ざらしの中、泉は歌い続けた。旋律はもの悲しく、はりつめて厳かで、声音は硝子のように繊細だった。
その場の誰もが、泉の歌を夢中で聴いた。元々泉はそれほど歌がうまいわけでもなくて、たゆまぬ努力でなんとか一定水準より上の歌い方を習得しただけで、天才のレオや渉が持つ才能に及ぶべくもない拙い歌唱だったけど、その歌は間違いなく世界で一番美しいと、その場の誰もが直感していた。
「……それが、セナの答え?」
独唱が終わり、泉が顔を上げる。目の前でレオがぽかんとした顔で蹲っている。こんなに雨に濡れてそんな間抜け顔をして、ああ、なんだか本当におかしい。泉が何も答えないでくすくすと笑い出してしまったので、レオは困ったふうに首を傾げ、「セナぁ」と甘えたな声を出す。
「おれのこと怒らないの」
「そうだよ」
「……どうして? おれ、かなり酷いことしたじゃん。おれはね、一応知ってて、記憶を奪おうって決めたんだ。セナが嘘は嫌いだとか、あと、その……おれに抱いてほしいっていう言葉の意味とか。後者は……あとから、レイとリッツにくどくどと説教されてわかったんだけど……その、セナの好意は……最初からなんとなく知ってたから」
「はあ? あいつられおくんに何教えてんの? あとで絶対シメる」
「ふ、ふたりとも悪くないって! わからんから教えて〜って聞きに行ったのはおれだし! リッツんち行ったらレイも出てきて、そのまま……うん、ちょっと、気恥ずかしくはあったけど!」
泉の前で、レオが子供のように慌てふためく。会話の内容はだいぶあれなはずなのに、真っ赤になってあわあわぱたぱたと手を振るレオの姿は、赤ちゃんみたいでかわいかった。醜い欲望をぶつけられて、その意味を知っていても、月永レオは、瀬名泉にとってかわいいひとだ。たぶん死ぬまで、ううん死んでも。
何も変わらないんだ。レオがもし変わることがあるとすればそれはレオ自身が選び取った変化で、泉の怒りや悲しみや憎しみを受容しようと決めたのもレオで。もしも彼が瀬名泉のために大人になることを決定したのだとしても、それは月永レオという男の子の意志でしかない。それに対して「自分の欲望が彼を穢した」なんて言い分は、かえって傲慢なのではないだろうか。
同じ場所まで堕ちてくることを選んだのがレオだというのなら、「れおくんは違う」なんて言わないで、それを尊び愛してあげたい。泉は微笑み、レオの身体へ体重を預ける。
「怒らないよ。怒ってなんかやらない。あんたは確かに、俺から記憶を奪ったのかもしれない……だけどそれが何? あんたが俺を守ろうとしてくれたその気持ちは、本物じゃん。だからもういいんだよ、れおくん」
「でも、」
「これ以上言わせないで。あとは、そう……れおくんの愛って俺が思ってたより随分重かったんだなあって、そのぐらいだよ」
だけど嬉しかったよ、と泉は囁いた。そのぐらいレオに大事に思われていたことが、嬉しかった。たとえ虚偽でも恋人だと言ってくれて幸せだった。一緒に暮らすのは楽しかった。キスはしてくれないけど、手しか握ってくれないけど、その先をくれない理由が泉を傷つけたくないからだと知ってしまえば、それらの事実が生む感情は、寂しさから愛おしさに変わっていた。
「記憶なんか戻らなくてもいいよ」
一生このままでもいい。たった五年間の記憶が失われたぐらいで泉の恋心は変わらなかったし、穢れも消えない。むしろ、喪ってはじめて気付いたことの方がいくらも多くて、大変だし辛かったけど、もしかしたら得をしたんじゃないかと思う部分さえある。
「呪いが掛けられたままでもいい……れおくんが俺を大事にしてくれて、そばにいてくれるなら、なんだっていいよ」
泉が耳元で流し込むようにとろとろと喋ると、レオはちいさく頷き、泉の額にキスをした。
――思えば臆病者同士、腫れ物に触れ合うような恋だった。
五年間にわたって秘められた恋心は一度ぐちゃぐちゃにぶちまけられたけれど、それをレオは全部拾い集めて瓶に詰めて入れてくれた。
少し前に、自宅で作曲をしていたレオの言葉を思い出す。「好きになったのは、セナがおれのこと好きだって言ってくれたからだよ」。「それって全部さ、セナがくれた愛のおかげなんだ。そのことに気付いた時が、おれにとっての恋のはじまり」。「セナが愛してくれたからおれはセナに恋したんだよ」。
ばかだなあ。泉が口にした言葉は、本当は、「俺のこと抱いてよ」という惨めな追い縋りだったのに。
レオはその言葉をこの上なく綺麗に解釈して、泉の願いに寄り添ってくれたのだ。それも泉が傷付かないように腐心しながら。「れおくんはやらしい目で見ないし、キスもしないし、汚らしいことはしない」という言葉を遵守するため、同じベッドで寝ても何もしないし、一緒にシャワーを浴びても何もしない。
その代わり、ただいっぱい、抱きしめて大好きだよと教えてくれた。
「ねえれおくん、俺のことまだ好き? こんな俺でも愛してくれる? 手を繋いでキスをして、俺のこと抱いてくれる……?」
上目遣いに訊ねると、レオがごくりと唾を呑む音が聞こえてくる。レオはちょっとだけ目を逸らし、それから、微妙に赤くなった頬で、泉に向き直る。
「……本当はね、セナが思っていたよりずっと、おれは最初っから、醜い生き物だったんだよ」
レオが辿々しくそう言った。
「だっておれも人間だし。作曲する機械じゃないし、人の心がない化け物でもない。宇宙人にさえ、なれはしない……おれはどこにでもいる普通の、人間の、男の子だよ」
泉がそう教えてくれたから。泉が、レオのことを「天才」ではなく「れおくん」と呼んでくれたから。識別記号ではなく愛称で、血の通った声で呼んでくれたから……いつの日からかレオは普通の人間の男の子になった。
もちろん、人間であるのはいいことばかりじゃない。一緒にいる泉の願いを叶えたくて、その結果他者の悪意に利用されて押し潰されて、一時は、生き甲斐である作曲が出来ないところまで落ちぶれてしまった。人の愛を知ったから月永レオは憎悪に負けた。自分に向けられた感情を理解できるようになってしまったから針のむしろに気付いて死んだ。他人を蹴落として屍の山を築き、戦って傷つけることばかり続けて、疲れてしまった。だけど……。
それでも泉がそばで歌ってくれたから、泉がKnightsのみんなをよりあつめ、家族になって待っていてくれたから、月永レオは帰って来た。人間だから、人間の愛で立ち直ることが出来た。
「だからおれは、自分がただの男の子であることを、誇りにさえ思ってる」
恋してるんだよ、あの日からずっと、とレオが呟いた。
ぱち、ぱち、ぱち。
ともなく、拍手の音が鳴り響く。「五奇人」日々樹渉から、見届けた舞台へ敬意の拍手だ。音に気付いてレオと泉が振り返ると、渉は優雅に一礼をし、ぽんとあたりに花を咲かせた。アザレアと、季節外れの黄色いヒヤシンス。花言葉は「恋の喜び」と「あなたとなら幸せ」。
「答えは出ましたね?」
渉が人差し指をぴんと伸ばし、唇に当ててそう訊ねた。
彼の言葉にレオが頷く。
「うん。――あのさ、やっぱりおれたち、最後はハッピーエンドがいいな。野獣の呪いが解けなくても、ガラスの靴を見つける前にシンデレラの魔法が消えてしまっても、それでもおれたちが幸せだって言い張るなら、『めでたしめでたし』に書き換えちゃっても、いいのかな」
「もちろん。結末を決める権利はあなたがた自身にあります。誰がどう言おうと」
「……『悪い魔法使い』も?」
「英智は、そうですねえ、きっと面白そうに笑ってくれるでしょう。元来、あの人もハッピーエンド症候群の患者なのでね。あなたが自分を頼ってくれたことに、ちょっと喜んでる節がありましたし? 同窓生の決めた幸せにあれこれ口を挟むほど暇人でもありません」
ぽんぽんと花をしまい、代わりに傘を差しだして渉が呟く。幸せの定義はいくつもあり、困難や苦難に出会わないことが幸せだという人もいれば、それを乗り越えた先にあるものしかそうと認めない人もいる。二人がそれで納得しているのならそれでいいんですよ、と日々樹渉は優しく言った。呪いが解かれなくても、真実を乗り越えて傷付くことを怯えなくて済むようになるのなら、それは十分ハッピーエンド足りうるのですよ、と。
「幸せになる権利は誰にでもありますよ」
それこそ、一度は醜悪な怪物として討伐された我らのように。微塵にすり潰して殺された奇人たちは、それでも、人間の愛と夢に触れて蘇った。奇跡は何度起こったっていいし、愛はいくらあふれてもよい。「だって私たちはアイドルなのですから!」日々樹渉が謳う。幕引きの裏側でウインクをして、楽しそうに。
「そう、私たちはアイドル。夢と希望をふりまき、喜びや幸せを分け与え、愛してくれたひとたちの人生をほんの少しでも輝かせる……愛の星。さあ、笑って……Amazing☆」
この舞台は閉幕です、と渉が言った。だからおうちへ帰りましょう、カーテン・コールが鳴り止む前に。幸せな物語を「おめでとう」で締めくくりましょう。
それから渉が、座り込んだままの二人に「もしよければお送りしますよ」と提案してくる。レオと泉は顔を見合わせ、彼の申し出に甘えることに決めた。色々あって、もう、くたくただ。
立ち上がると、渉はウインクをして最後にひとつ、おまけで魔法を掛けてくれた。
「僭越ながら、我ら五人を代表して祝福を。――Have a nice dream♪」
◇◆◇◆◇
雨ざらしの教会で濡れ鼠になってしまったため、帰宅してまずふたりが行ったのは、急いで順番にシャワーを浴びることだった。レオが頑なに譲らないので先にシャワーを使い、身体を乾かして、一台しかないベッドの上で彼の帰りを待った。
――結局、記憶は戻らなかったな。
今まで毎晩、何も起こらなかったベッド。そういえばどうしてこんなサイズのベッドを置いていたんだろう。以前のレオは一人暮らしだったという話だし、泉の荷物なんかは天祥院の力で前の住居から持って来たんだろうとしても(冷静に考えるとそれはそれで恐ろしい話だが、今回は考えないことにする)、このベッドはどこから出てきたのか。
(……れおくん、在学中はこんなばかでかいベッドじゃなかったよねえ。ふつうの一人用のやつだった。一人暮らしになって無闇に大きいやつ買ったのかな……寝相悪いし……)
考えてみるが、答えはわからない。ううん、こんな埒のあかないことを考えていたって、仕方がないのではないか。そう考えていると、寝室の戸が開いてレオが戻ってくる。
「――セナ……」
レオは何故か熱っぽい声で泉を呼んだ。そして入り口で何か戸惑ってみせたあと、おずおずと泉のそばへ寄ってきてぽすりと隣に腰掛ける。
明らかに挙動不審だ。一体どうしたというのか。
「……れおくん? どうしたの」
「いや、その〜……」
「もう、なにそれ、はっきりしなよ。せっかくいろいろ踏ん切り着いたってのに、あんたねえ、そんな思春期の子供みたいな態度、し、て……」
小言を垂れていた泉の言葉が、そこで急に途切れる。レオの身体がよりこちらに密着して、挙動不審の理由に気付いてしまったからだ。
「あ、あんたまさか」
泉はひっと喉の奥を引きつらせて違和感の正体に手を遣った。
スウェットを履いたレオの中央、股間部分が、布の上からでもはっきりわかるぐらい張り詰めている。
「勃ってる……」
口から漏れた声は、泉自身げっそりするぐらい冷ややかだった。
「す、すまん〜! なんかその、ごめん、もうこれでセナに隠し事しなくていいのかって思ったら、気が……ゆるんで……」
「えっなに、あんた逆に言うと今までずっと気を張ってたわけ?」
「まあ……。一緒に寝起きしてたら、セナの寝顔がかわいいし、そういう気分になっちゃうこともあったんだけど……。ばれないように朝早く起きて処理したり、その――努力してたんだぞ。えらいだろ!」
レオの言葉が途中からしどろもどろになり、視線はあらぬ方向を彷徨って、迷走した挙げ句「えらいだろ」とか言い始める。泉はびっくりしてぽかんと間抜けな顔をさらしてしまった。確かに、この一ヶ月レオは基本的に早起きだった。だいたい、先に起きて朝食を作り、泉が起きるのを待っていてくれた。
しかしその裏にはこんな理由があったのだ。
泉は手のひらで顔を覆った。こんなことを言われたら我慢出来なくなってしまう。
「やめて……かわいいとか思っちゃうから……」
「かわいいのはセナの方だろ!」
「そういうんじゃなくて。あんた、あはは、いじらしいとこもあるんじゃん」
笑いながらレオの股間に手をやる。するとレオはびくりと身体中震わせて、中学生の男の子みたいに顔を真っ赤にした。ああ、かわいい。本当にかわいい。からかってしまいたい。
第一、何をためらうことがあるのだろう。
だって泉はずっとそうされたかった。キスより先のこともレオとしてみたかった。レオにそういう欲求がないならと我慢をしていただけで、レオの方にもその気があるのなら、話は別だ。
泉は悪戯を思いついた猫のような顔をして、レオの方に身体を傾ける。
「ねえれおくん、俺たち恋人なんでしょ? 俺は今もそのつもりなんだけど……れおくんは?」
それとも恋人と思っているのは俺だけだったの? そう意地悪く訊ねると、レオはぷるぷると首を横へ振り、がばりと立ち上がって泉の手を取った。股間が膨らんでいるせいでちょっと間抜けだったけど、なんでもいい。
「ん……んぅ、は、む、ふ……」
下穿きを全部脱いで半身をさらけ出したレオの中央に顔を埋め、泉は懸命にレオのものを舐め回していた。泉にはそういった経験はもちろん一度もなかったが、献本でもらった女性誌の隅になんだかそういういかがわしいコーナーがあったことをなんとなく思い出して、まずはそこに書かれていることを実践してみようと思ったのだ。
ぱんぱんに膨れあがった男性器を、根本から丁寧に舐め上げていく。こんなところ、汚いだけとばかり思っていたけれど、レオのものだと思うと、愛おしくていくらでも舐めていられる。
筋をなぞるたび、竿が熱く、かたく張り詰めて、レオが鼻から甘ったるい息を漏らすのが特によかった。泉は夢中になってレオの陰茎を頬張った。顔に見合わずけっこうなサイズに膨らんでいたので、全部を飲み込むことは難しかったけど、頑張って奥まで口の中に咥えた。
そんなことを続けていると、そのうち頭頂部からとろとろと液が漏れてくる。それを舐めるついでに口をすぼめて亀頭を吸い上げると、苦くて変な味がする。
「……なにこれ」
じゅぽん、と口を離して訊ねると、レオがふるふると左右へ首を振る。
「し、知らん」
「ふうん? 精液じゃないのかなあ……」
「うぅ、おれ王さまなのになんにもわかんないんだな……」
真っ赤になったままがっくり項垂れてしまったレオを見て、そんなことないよと言ってあげる代わりに、竿にちゅうと触れてキスをした。するとレオの身体全体がびくりと跳ね、男性器が震える。どうしたんだろう、と泉がぼんやりそれを眺めていると、「あ、」とレオが呻き、ほどなくして、先端から勢いよく白い液体が吹き出て泉の顔をべたべたに汚した。
射精したんだ。顔中をしたたる生臭い白濁液を指ですくい取り、泉は陶然とその場にへたり込んだ。誰かが射精するところを見たのは初めてだった。
「わ〜っ、ごめんセナ、出ちゃった……」
一方射精したほうのレオはというと、言いかけた「ごめん」の続きを、泉の顔面を見た途端にどこかへやってしまったようだった。レオはごくりと生唾を飲み込んだ。レオが今まさにしたたかに吐き出した精液が、泉の顔いっぱいにぶちまけられ、重力に従ってぽたぽたと滴り落ちている。そのなんと卑猥なことか。泉の整った容貌に、己が出したものがたっぷりかかって糸を引いているさまは、絶景だ。
「セナ、えっろ……」
それで思わず、脳味噌からじかに言葉が出してしまう。すると泉は、何故かむっとしてレオを睨んだ。
「顔いっぱいに掛けるやつがある? 堪え性なしか?」
「だ、だってセナがいっぱい舐めてくれるから〜! おれも男なんだよ、気持ちよくなったら出ちゃうの!」
「ふうん……気持ちよかったんだ」
「うん。セナの口あったかくて好き」
他意なくそう言うと、泉はか〜っと顔を赤くして「バカ!」とか言い始める。デコピンまでされたので、ちょっとむっときて、えいと泉を押し倒した。仰向けになった泉の上に覆い被さり、彼の下穿きに手を伸ばすと、既に泉の陰茎もゆるく勃ちあがって先走りに濡れている。
「セナだってえっちな気分になってるじゃん!」
下穿きをずるりと脱がせると、「やだぁ」とか言いながら手の甲で顔を覆われる。何が嫌なもんか。レオの性器を舐めているだけでこんなふうになっているのだから、本当は嫌の逆に決まっている。泉はあまのじゃくだ。
「素直じゃないなあ……そこもかわいいんだけど……」
泉の腹を撫でさすりながら呟き、いつの間にか立場が逆転していることに気がついた。最初は泉のほうがかわいいとかなんとか言っていたのに。でもレオから見た泉はとびきりかわいいんだから、まあ、仕方がない。たぶんお互いに本当のことを言い合っているだけなのだ。レオはそんなふうに自分を正当化して、泉を撫でる指先を、徐々に腹から下部へ移していった。
男同士のセックスに対して殆ど知識のない泉と違って、実はレオは、なにをどうしたらいいかは、一通り知っている。知っているというか馬鹿正直に「セナに抱いてって言われたんだけどどういう意味?」と聞いたら、朔間兄弟がしばらく顔を見合わせたあと本を一冊貸してくれた。本の内容はわりと真面目な指南書だったのだが、童貞かつ基本殆どの欲求を作曲に持って行かれがちで性欲の薄いレオにとっては、かなり衝撃的なものだった。
「セナ〜、あのさ、今のセナって、このあとどうしたらいいかはわかる?」
「えっ? ううん……? 言われてみれば、夢の中でも、そのあたり判然としなかったような……」
「ん? 夢の中?」
「――どうでもいい話だから忘れて。えっと、たぶん、よくわからない」
「そっか。じゃあおれがやるから、セナはいい子にしてろよ」
できるだけ怖がらせたくないのでにこりと告げ、泉の身体を固定する。ベッドサイドの引き出しから指南書のおまけでもらったローションボトルを取り出し、新品だったのでラベルを剥がして開封し、中身を自分の指先に垂らした。そのままぬるぬるした人差し指を尻に添わせ、入り口に掛けてから窄まりの中に押し入れる。
すると泉の口から「ひっ!?」と声が漏れる。「ここに入れるから」と宣告すると、さらに「えっ」みたいな声が飛び出てくる。
「な、なに、そんなところ触らないで……ぎゃあ!」
「うわ、色気のない声……」
「うるさ、だって、変な感じする……!」
「う〜ん、なんか、声のわりにゆるいような……。もう一本いけそうかな?」
ぎゃあぎゃあ言ってあばれそうになる泉の身体をもう片方の手で押さえつけ、中指とあわせて二本の指を尻たぶの中に突き入れた。ローションを奥に塗り込むようにぐちぐちと動かし、直腸の中をまさぐり続けていると、そのうちある一点を掠めたところで「ぁ、」と甲高い声が上がる。あまりに扇情的な声に、レオは驚いて手を止めてしまった。出会ってからずっと泉のことを見てきたけれど、彼のこんな声を聴くのは、初めてだった。
「……え、なに、今の声。まさか俺? 俺が出したの?」
初めては、泉の方も同じだったらしい。彼は鳩が豆鉄砲を食ったような顔をし、一瞬息を止め、「うそ」と頼りない声を漏らす。
「な、なんで? なんでこんな声出ちゃうの」
「え〜っと、たぶん、レイに借りた本によると……前立腺? とかいう場所を、擦ったせいかな。ふうん……じゃ、セナはここが気持ちいいんだ。ここが好きなんだ?」
「おい待て朔間あの吸血鬼れおくんに何てものを読ませて……ひゃんっ!?」
「おお……なんか面白くなってきた☆ 一曲作れそう……♪」
「バカ! ふあ、あっ、……」
少し入り込んだ先にあるしこりを擦ったり弾いたりすると、泉が面白いぐらいに反応を示す。がちがちに固まっていた身体がほぐれ、頬を赤らめてきゅっと目を閉じ、時折びくりと身を震わせる。
「セナ、もっと声聴かせて」
「やっ、あ、ん、ぁ、そこ、ばっか、やめて……んんっ、」
「なんで? じゃあどこがいいの? おれはセナにもっと気持ちよくなってもらいたいな……あ! そうだ」
身をよじらせていやいやと首を振る泉の身体を押さえつけ、いいことを思いついたとばかりに、彼の胸に口を近づけた。赤くて小さな乳首が、もうぴんとたって硬くなっている。そこにキスをして、乳頭を啄む。すると泉は雷にでも打たれたみたいに甘い声を上げた。
「うん、セナ、気持ちいいな」
「や、ぁ、おしり、と、いっしょにされたら、あたまおかし、なる――」
「いいよ、頭おかしくなっても。このセナはおれだけの秘密」
右乳首を吸い上げ、前立腺を執拗に擦る。左乳首に口を移す頃には、吸い尽くされた右乳首が、すっかり腫れ上がって真っ赤になったあとだった。隙を見て後ろを弄る指も三本に増やす。ローションで濡れそぼった窄まりは、少しつっかえたものの、ほどなくして三本目の指も飲み込んだ。その状態で指を曲げたり広げたり、あるいはばらばらと動かしてやると、泉は次第に声を上げることも忘れ、未知の感覚に身を任せた。
「は――ぁ、あぁ……」
唇を離し、ちゅぽんと指を引き抜く。一時解放された泉は、身体を小刻みに震わせ、一糸まとわぬ姿でベッドの上に打ち上げられていた。息を呑むほど卑猥な光景だった。散々慣らした窄まりは、控えめに、けれど確かに口を広げ、ひくひくと収縮して、雄を誘っている。
「きれいだ……」
我を忘れて、レオは泉の裸体に見入った。
「きれいだよ、おれのセナ」
ああ、血液が、下半身に集中していく。泉と暮らしていた一ヶ月間、トイレでこっそり抜くことは何度かあったけど、こんなに全部の意識を下肢に持って行かれた経験は一度もない。ふつふつと、原始的な欲求がわき上がってくるのを感じる。零に借りた本が正しければ、きっとこれが「抱きたい」という気持ちなのだ。この何もかもめちゃくちゃにしてやりたいという気持ちが。泉の大切なところを暴いて征服してやりたいという気持ちが。彼を自分だけのものにしてマーキングしたいという気持ちが。だけど大切に抱きしめてあげたいという気持ちが、全部全部ひっくるめて、「抱きたい」という本能に集約されるのだ。
「セナ」
怒張して上向いた陰茎を手で押さえ、ゆっくりと、先端部分をひくつく後口に宛がった。ゴムをつけるのも煩わしくて、そのまま肉と肉をぬちぬちと擦り合わせてやると、期待するように入り口部分が蠢く。いいよな、と訊ねる代わりに彼の目を見つめた。目尻に涙が溜まっている。こわいの、と聞くと、すこし、と彼が言う。レオは泉の目元に顔を近づけ、彼の涙を舌ですくう。
そうして顔を離すと、泉の熱に潤んだ瞳が、まっすぐにレオを見ていた。
あの美しい海色の目が、愛欲にまみれ、レオだけを映し込んでいる。その中に見え隠れする自分の顔を見て、レオは驚いて目を見開いた。そこには、獲物を前にした肉食動物の姿が映り込んでいた。こんな顔をするのか自分は、と思ってびっくりしたけれど、でもまあ、仕方ないかな、いっぱい我慢したし、とも思った。
「なあ、抱いてもいいか?」
訊ねると、「やさしくして」、と泉が言った。
駄目元で「やさしくして」なんて言ってはみたけど、多分無理だろうなあ、というのはなんとなくわかっていた。だってレオは今までどんなライブでも見せたことがないというぐらい雄臭い顔をして泉の上に覆い被さっていたし、一方彼の目に映り込んだ泉の方はというと、今か今かとそれを待ちわびるはしたないけだものの表情をしていた。
いちおう、恐怖はあった――だって彼の性器はわりと大きかったし、赤黒く変色したグロテスクな陰茎が丸出しで、コンドームをつけようという気配さえ見えなかったし、今からこれで串刺しにされるのかと思うと心臓が縮み上がりそうだったし――けれど、レオが自分を求めてくれることへの喜びはそれに勝るとも劣らず大きかった。
「あ、あぁっ、痛、あ、ぐ、ぅう、ぁ――!」
ぬぷ、ずぷ、と怒張しきった陰茎が少しずつ掘削するようにして、泉の尻を穿っていく。秘めた場所を割り開かれる度、今まで味わったことがないような感覚が泉の全身を駆け巡った。まずはじめに無理矢理巨大な質量をねじ込むことによる痛みが生まれ、ゆるやかにそれが侵入を進めていくにつれ、信じられないような圧迫感が生まれた。自分の中に自分ではないものが入りんでくる違和感。どうしても身体に力が入ってしまって、食い締めているせいだろう、レオも少し辛そうな顔をしている。
「セナ、息吸って、おれの顔みて、だいじょうぶ、だいじょうぶだから」
「う、うぅ、ふ、ぁ、れおくんの、おっきいよ、も、むり、はいんない……!」
「大丈夫だ。たぶん入るから」
何が多分入るだ。その自信と根拠はどこから出てきてるんだ一体。
なんてことを問うことも出来ず、ひたすら、挿入の圧に耐える。レオはゆっくりと腰を進め、着実に泉の中へ侵入を果たしていた。そのうち、硬く張り詰めた先端部分がある箇所を通過してこする。
その瞬間、泉はだらしなく空いた口から絶叫を漏らした。
「やっ――あ――あぁっ……!」
腰が浮くような感覚。お尻から背筋を駆け上がってわけのわからない感情が脳天へ到達する。ああ、ここ多分、気持ちいいところなんだ。さっきレオがしつこく弄っていたような。
泉がそう理解するより早く、レオの方が異変に気付く。彼はきょとんと瞬きをして(悔しいけどかわいいなと泉は思った)、その直後、にっと笑うと舌なめずりをした。一瞬でもかわいいと思った自分が馬鹿だと思った。この男はそんな生やさしいものじゃないのに。だってこの子ライオンだもんね、本で読むまでセックスの仕方をよく知らなかったりしたけど、だけどやっぱり、男の子なんだ。
不意に、レオの両腕が泉の腰をがっちりと掴む。そのままレオはずるずると自分の陰茎を引き摺り出し、完全に抜けきるその手前でぴたりと動きを止めた。嫌な予感がした。抜けないでほしいと入り口が彼を食い締めていることも衝撃的だったが、その次に起こるであろうことがなんとなく予想できて、泉は歯を食いしばり、
「い、ぁ、あっ――!!」
でも駄目だった。
泉の腰を掴んだまま、レオが勢いよく、性器を抜いたり差したりしはじめたのだ。ぐっと押し込まれたかと思えば、ずるりと引き抜かれ、何か物足りないような寂寞感を覚えたところでまた戻される。その繰り返し。出たり入ったりを繰り返す肉の塊に、腸壁のひだが絡みついているのが、なんとなく、わかった。最初に泉が唇と舌でそうしたように、身体の内部が、レオの男性器を舐めしゃぶっている。
肉が引き攣れる音。それから入り口が泡立つだらしない水音。抜き差しをする度にぐぽぐぽとはしたない音がする。ああ今セックスをしているんだと意識するごとに、泉の感覚は研ぎ澄まされて鋭敏になっていった。身体の中に埋まる質量のあるものを、こんなに大きくて怖いのに、愛おしいと思った。彼が身を引く度に行かないでと泣きたくなった。帰って来てくれると安心した。いつの間にか痛みは感じなくなっていた。本当はまだ痛いはずなんだけど、たぶん、どこかで何かが麻痺してしまっていて、レオに抱かれている多幸感で上書きされてしまっているのだと思った。
「れおくん、れおくん、れおくんっ……!」
腕を伸ばす。自分を犯す男を両腕で抱きしめ、為す術もなく喘ぐ。今この瞬間ふたりでひとつになっていると思うと不思議な気持ちがした。この男にも性欲がちゃんとあって、泉に対して興奮を覚え、猿みたいに腰を振るのかと思うと、天上人みたいに思っていた月永レオが本当は瀬名泉と同じ卑しい人間の男の子なんだということに、どうしようもなく納得がいった。
「セナ、セナ、セナ、すきだよ――大好き、ずっと……」
レオが口にする言葉の全部がこんなに信じられることもそうないだろうというぐらい、あらゆる声が嬉しかった。俺も好きだよと言おうとして、でもうまく口がまわらなくて、突き上げられる快楽に合わせ、みっともない喘ぎ声を垂れ流した。繋がっている場所から感覚がなくなっていく。ふたりを隔てていたものがなくなる。この男に抱かれたら絶対絶望すると思っていたのに、いざその段になってみると、そんなことは全然なくて……ただ、悦びだけが泉の全てを支配する。
それでも足りないの、と泉は喉を鳴らしてレオに訴えかけた。これだけじゃ足りないの、もっと奥に来て、いちばん深いところまで、レオにだけ教えてあげる、ゆるしてあげるから、もっと来て。熱い眼差しで訴えかけると、レオが捕食者の瞳をして答える。
「うん、いいよ」
レオが囁いた。
それはマイクを持ってステージで歌う時の声よりずっと扇情的でエロティックで、死にかけていた泉の心臓を鷲掴みにして、一気に破裂させてしまった。
「いいよ。セナの足りないもの、全部おれが満たすよ」
ぐっ、とひときわ奥深くに、強引に陰茎が挿入されていく。ごりごりと押し進めて、全てを咥えこませたあと、全部入ったな、えらいなセナ、とレオが泉の肩を撫でた。身体があつい。これからくる「何か」を察して、エマージェンシーを上げている。
「何……する、の?」
訊ねるとレオは男の子のいじわるな笑みを浮かべ、耳元で低く囁く。
「セナの、中に。ぜんぶ……ぜんぶあげるから、受け止めて」
それからレオが、勢いよく、泉の中で射精した。
「――ッ……!」
泉は歯を食いしばって衝撃に耐えようとして、だけどいなしきれず、甘い吐息を漏らした。泉のからだの奥の奥まで、こってりとした液体が吐き出されていく。いっぱいになる。何も考えられない。
びゅくびゅくと勢いよく吐き出される精は、最初に顔にぶちまけられた時よりずっと、長くねちっこく感じた。一体どこにそれほどの醜い欲を隠していたのかというぐらい、レオはたっぷりと精液を吐き出し続けた。あつい。きもちいい。れおくんで魂まで全部満たされて、ほかのことが何も考えられない。それに呼応するみたいに、泉の腰が跳ね、いつの間にか勃起していた先端部分が震える。
「れお、くん、おねっ……ぁ、が、い、」
泉は最後の力を振り絞って、レオにおねだりをした。それが一生に一度のお願いになってしまっても、よかった。
「なに、セナ」
すると泉を支配する男が顎を引いて訊ねる。舌なめずりをして、征服者の目をして。
「おまえの王さまに言ってみて?」
ああ、なんて傲慢で横暴で、我が儘。最低の暴君だ、そのうえ育児放棄も宣言するし。
だけどこれが泉が愛した男なのだからしょうがない。
十七歳の泉も、そしてきっと二十二歳の泉も、この男のそういうどうしようもない部分を含めて好きになってしまうのだ。
こいつが天才とか、そういうところを全部すっ飛ばして、ただこの純粋で美しい生き物を愛してしまったのだ。この男の子を守ってやりたいと思った。剣となり盾となり、冠となり鞘となり。全てを捧げても構わないと思った。
天才作曲家なんかじゃなくて、ただの人間の男の子に恋した。それが十七歳の頃からずっと続く、瀬名泉の初恋だったのだ。
「キスして……!」
だから泉はねだった。
汗と唾液とあらゆる体液にまみれたぐちゃぐちゃの顔で、みっともなくても、穢れていても、人間だから幸せになりたくて、レオの愛を請うた。
頷く代わりに、レオが顔を近づける。大好きな男の子の唇が間近に迫る。そのさまに息を呑むより早く、食い荒らすように、レオが泉の唇を奪った。触れ合わせるだけのキスに留まらず、どこで覚えたのか知らないけどちゃんと舌を割り入れて歯列をなぞり、唾液を交換し……そして泉の舌を引っ張り出すとそれを絡め合った。
(――あ)
恍惚の中、泉はふと、走馬燈のように過ぎる数多の記憶を見た。
はじめの記憶は、ガーデンテラスではじまった。制服を着た月永レオが、五線紙にペンを走らせている。リトル・ジョンを抱きながら泉は彼に尋ねかけた。それ、何の曲? 恋の歌だよ、と彼は答えた。
次の記憶は、ドリフェスの舞台の上だった。ふたりっきりのKnightsで、ジャッジメントと称して数多の敵対ユニットを葬り去った。レオの作る楽曲は最強の武器で、それさえあればどんなユニットにも負けなかった。そんなことを続けているうちに凛月や嵐と出会い、とうとうふたりは、「チェス」を相手取る最後のジャッジメントに挑み、そして不戦勝を決めた。その日が全ての凋落の始まりだった。
その次は、荒れ放題の部屋でレオが死人のような顔をしている記憶だった。彼の私室からは異臭がして、身体中包帯や絆創膏だらけで、あんなにきらきらしていた両目は死んだ魚のように濁っていた。「ルカを泣かすなよ」唸り声は掠れきって弱々しかった。もうこいつは死んじゃったんだろうなって思った。無性に儚くって、本当は言ってやりたい文句が十や二十や三十はあったんだけど、全部どうでもよくなった。死人を鞭打つ趣味はないから。ご飯ぐらいちゃんと食べなよと言い棄てて、振り向きさえしなかった。
さらに次は、レオがいない日々の記憶だった。帰らない王を、世界で一番無力な生き物になってしまった男を、それでも泉は待ち続けた。そんな薄暗い日々の中、落ちぶれていたKnightsをわざわざ選んで入って来た司の存在が、泉の心を慰撫した。彼の真っ直ぐさにどこか救われる気がして、まあまあお気に入りになって、ちょっと厳しく指導しすぎたところもあった。凛月に笑われた。嵐にも。でもふたりとも嬉しそうだった。レオも帰って来たらいいのに、きっとあいつだってこの子を気に入るに違いないと、いつもそう思っていた。
そのさらに次の記憶。季節は少し飛んで夏の終わり。月永レオが帰って来た。そしてめちゃくちゃに泉たち四人を振り回し、決して、自分は舞台に上がらなかった。そのことに泉はかんかんに腹を立て、泉に似通った気質を持つ司もぷんすか怒り、果てに何故かレオはジャッジメントを言い渡した。これが五人のKnightsで行った最初で最後のジャッジメント。騎士殺しをひっさげたレオのやり方は苛烈で容赦が無く、泉たちは苦戦を強いられた。この男は本気で殺しにかかってきている。それが悲しくもあったが、それよりずっと、むかついた。――今更のこのこ帰って来て偉そうにするな! 泉たちは辛くも勝利を収め、レオを取り戻した。
そこからは――どうにも、楽しい記憶ばかりが続いていた。『ナイトキラーズ』との戦いのあとも何度かレオはふらっといなくなったり仕事をドタキャンしたりして小さなハプニングはなくならなかったが、おおむね、全ては順風満帆に進んだ。年明けの武道館ライブも大成功を収めたし、卒業後のワールドツアーも楽しかった。五人のKnightsが、レオと泉をいつも繋いでいた。子はかすがいねえと冗談交じりに嵐が言ったのを覚えている。家族みたいであったかかった。みんなのことが愛おしい。全て満たされて、それで十分幸せじゃないかと、何年も自分を宥めすかして過ごした。だけどそれも長くは続かない。
最後の記憶は、二十二歳の誕生日。レオがひとつの曲をくれた。誕生日プレゼントに、と言って渡された五線紙には、彼の直筆で美しいメロディが綴られている。おまえのためだけの曲だよ、と彼が言った。その曲に歌詞をつけてくれ、とも。泉は頷き――いくらかの時間を掛け、賛美歌の歌詞を綴った。それは長く泉が秘めてきた、レオへの恋慕を秘めたものだった。それが完成すると、どうしてか酷くもの悲しくなって、ひとりで泣いた。こんなつらい曲は忘れてしまいたいと思って、だけど忘れられなかった。レオが書いた曲に泉が歌詞を付けることはこれまでにも数限りなくあったけれど、その曲はとりわけ特別だったから。
つまりそれは瀬名泉の青春の全て。
彼へ捧げた恋心の終焉。
実るはずのない想いがかたちになった、今にも壊れてしまいそうなラブソング。
それから数日経って暴漢に襲われた時も、泉の頭の中では、その曲が鳴り響いていた。
(――思い、出した)
唾液を吸われ、深い口づけを交わしながら、泉ははらはらと泣き出した。セックスの最中に流していた涙とは違う、悲しみと喜びがすべてないまぜになった、感情のかたまりだった。
(全部思い出した……)
けだもののように己を貪るレオの舌遣いに翻弄されながら、頭だけが、すっきりと晴れて明瞭になっていく。今まで靄が掛かっていた部分が全て解き明かされ、十七歳の泉の中に、レオによって殺された二十二歳の泉が帰還する。
奇跡は何度起こってもいいのですよ、と微笑む奇術師の声が蘇った。それから、古来より呪いは王子さまのキスで解けるものじゃん、という友人の声が。愛はいくら溢れてもいいし、瀬名泉は幸せになるべきだし。誰かの声が無数にこだまする。それを呆然と聞いていると、不意に白昼夢が泉の視界を埋め尽くす。
真っ白い世界の中で、二人の瀬名泉が、向き合っていた。
――もういいの? この恋心は、無駄じゃなかった?
二十二歳の瀬名泉が、どす黒く汚れたみじめな心臓を抱きしめてそう訊ねた。
――いいんだよ。醜い感情も、きれいな感情も、全部ひっくるめて恋だった。だからね、もう、泣かなくたっていいんだよ。
十七歳の瀬名泉は、静かに答えて大人になった自分自身を抱きしめた。ふたりはほどなくして光の粒子になり、一つに混ざり合い、たった一人の瀬名泉の姿になる。
白昼夢が終わる。視界が、またレオの顔でいっぱいになる。すると示し合わせたようにレオが唇を離し、長い長いキスが終わった。泉は奪い尽くされた酸素を取り戻そうとして大きく息を吸い込んだ。
「――王さま」
そう呼びかけただけで、レオは全てを察したように、大きく目を見開いた。
「……セナ? もしかして……何か、思い出したのか……?」
「うん……全部ね。なんだか、今更って感じだけど。だって記憶なんか戻らなくても生きてけるって決めたあとなのにさ。だけど……悪くはないかな……」
こんな状態で言うとちょっと間抜けだけど。着るものもろくに着ないで、身体はまだ繋がったままで、泉はレオにがっちりと組み敷かれていて。だけど泉がそう言うと、なんで? どこも間抜けなんかじゃないよ、とこの綺麗な魂の持ち主は笑った。笑うとやっぱり赤ちゃんみたいだった。
「どんなかたちでも一緒に生きていけるんだもん。もう全部夢でもいいよ」
「えっ、それは困る。幸せなことは現実じゃなくちゃ。おれはさ〜、一回死んだようなもんだから、尚更そう思うんだよな。セナとリッツとナルとスオ〜で、五人揃ったKnightsじゃないと満足出来ない。だからセナの記憶を奪ってでも引き留めようとしたわけだし。おれってわがまま?」
「それこそ今更でしょ」
「わはは。憎まれ口叩けるなら元気だなっ!」
レオは豪快に笑い、もう一度、泉の唇にキスをしてくれた。
そのあとは、ふたりでごろりと寝転がって、幸せな気分に包まれたままピロートークみたいなことをした。
別れ際に渉がかけてくれた、おまけの魔法のこととか、とりとめもなく話をした。キスで呪いがとけたのか、泉の感情に決着が付いたあとだから思い出せたのか、それともキスさえしていれば記憶はもっと早く帰って来ていたのか……そのあたりは謎が残ったが、今が一番記憶が戻るのにいいタイミングだったという結論になり、疑問は放置された。
「ねえこのベッド、どうして買ったの?」
その次に、ふと気になっていたことを訊ねる。するとレオはちょっとだけ恥ずかしそうに頬を掻いて、だけどまっすぐ泉を見つめて、こっそり耳打ちをしてくれる。
「……一緒に住むことになった日に、セナとふたりでずっと暮らせるならこれがいいなって思ったから……」
そして照れたふうにへへへと笑う。まったく、何を今更恥じらっているのだか。恋人ごっこを一ヶ月やりおおせたとわかった今では、何を言われても驚かない。
「はいはい。しょうがないなあ、あんた危なっかしくて心配だし。一生面倒見てあげる」
感謝しなよね、とちょっと顔を背けて言ってやる。
だけど逸らした頬が赤らんでいることは、何故かレオには全部お見通しで。
「あはは! ありがとな。……セナって、ほんとに素直じゃないなあ。でも……そういうとこも大好き。ほんとにかわいい」
レオは赤らんだ泉の頬を何より愛おしそうに撫でさすり、世界で一番幸せだよと呟くように、ふたたび、泉の唇にキスをした。