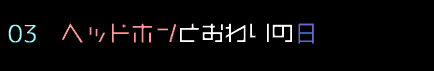
イヤホンがなくなった。
十二月一日。月が切り替わって師走。師も走るほど忙しい、それはまあいいんだけどイヤホンが走ってどこかへ行ってしまうなんて聞いてない。本当に、どこへ行ってしまったんだろう。自室は勿論隅々まで探したし、心当たりという心当たりには全て訪れたのだ。ベルベットルームにまで行った。そうしたら、エリザベスに、「ございませんわ」と首を振られた。
昨日まで確かにちゃんと身に着けていた。銀色のイヤホン、それなりに磨き上げてあって、使い込まれていて、僕が戦闘に際してあちこち動き回っても取れてなくなったりしないでちゃんと僕の肩に掛かっていたそのイヤホンがなくなるということを僕は少しも想定したことがなかった。付けたまま無防備に眠ることもあったけど、まさかなくすなんて思っていなかった。
あのイヤホンが僕の前からいなくなるなんてことはないと思ってたのに。
綾時からマフラーが取れたぐらいの喪失感だ。なくなったことに気がついたのが二限の後の中休みで、その日はもう、それからずっとそわそわして落ち着かなかった。
「餌が欲しいハムスターみたいだね……」
「あ、やべ、それすごいいい感じだわ。ピッタリナイスー……って、茶化せる感じじゃなさそうだな……。おーい、リーダー、リーダーってば」
「……」
「……マジで落ち込んでる」
「そんなの最初から、見ればわかることじゃないか」
綾時にしては珍しく理に適ったことを言って僕の肩に手を置く。順平が「リーダー、ジョーダン、通じねえんだよなぁ……」と困った顔をしてどうしたもんかと腕組みをしていた。どうしたもんか、って、僕の方こそ気軽に言えたら良かった。
別に両親の形見だったわけじゃないし(十年前にあんなイヤホンは存在しなかったし、そもそも、僕はそれほど両親について頓着していない)、こっちに来る前に保護者をしてもらっていたおじさんに適当に買って貰ったやつだった。ただ、なんでだろう、すごく気に入っていたし僕によく馴染んでいた。おじさんは、「俺のピアスみたいなもんだな、きっと」と言って僕とイヤホンを撫でた。
イヤホンは僕の身体の一部に等しかった。喪失感。これはきっとそういう名前をあてられている感情だ。
「あれ、君のお気に入りなんだよね、きっと。同じモデルのってまだ売ってるかなぁ。確かに……あれがないと落ち着かないの、僕にもわかる気がする。湊君は湊君なんだけど、何か少し欠けてしまっているっていうか」
「まあなぁ。正に肌身離さずってやつか……そういや俺、リーダーがイヤホンしてないとこ見たの、修学旅行の風呂の時ぐらいだわ。夜でも外さねえもんな。……なあ、ジャストフィットの一台の代わりになるかはわかんねえけど、放課後買いに行こうぜ、せめてさ」
「それがいいね。うん、そうしようよ湊君。僕も選ぶの手伝うから」
「……綾時が?」
「僕でよろしければ。いいものが見つかるといいね」
にこりと、屈託のない笑顔。ああ、なんだろう、癒されるな、これ。ちょっとだけ気持ちが楽になって「ありがとう」と手を握ると綾時がはっとした顔つきになって、順平に至ってはぎょっとした顔をした。「何」とぶすっとして訊ねると順平があわあわと変な動きをする。
「そ、そのー、有里サン」
「……何その、後ろめたい態度みたいなの」
「い、いやあハハハ……」
「びっくりした。君ってあんな顔するんだねえ。なんだかちょっと気が緩んでる感じの顔。僕なんかかわいいものを見るとしょっちゅうだけど、どうしたの、お空にウサギさんでもいたとか?」
空にウサギがいるのだとしたら綾時の頭がちょっとやばいんじゃないだろうか。
僕は綾時の頭をぽすぽすと撫でるように叩くと立ち上がって、机の下から教科書を取り出した。五限は音楽室に行かなきゃいけない。教室移動の準備、いつもならとっくに済んでいる頃なんだけど、落ち込んでいたからまだしていなかったんだ。
手短に済ませてから二人の方に向き直ると、順平はまだしっくりこない顔をしているし綾時は子供みたいにきらきらした顔でるんるんしている。僕はなんだか調子が狂ったような気分になって溜め息を吐いた。
「よくわかんないけど、そんな、僕の表情なんかでいちいちそんな反応するなよ。調子狂う。順平はお化けでも見たような顔するし」
「いやあ……ある意味お化けよりよっぽどレアだわ。あー、写真! 写真とっときゃ良かったッ!!」
「…………順平。僕は写真を撮られるのはあんまり好きじゃないし、それが順平の小遣いの足しにされるのはもっと不本意なんだけど」
いつもより低い声のトーンで眉間に皺を寄せて言うと「スミマセン」と蚊の鳴くような声で順平が返してきた。いつもの遣り取り。いつも通り、変わらない、僕らの日常。赤色の秋が通り抜けてもうすぐ純白の冬が訪れようとしている季節の境目、僕達の青い春はそうして幾つかの季節を通り過ぎていこうとしている。
◇◆◇◆◇
ポロニアンモールからちょっと外れた、巌戸台駅方面にある大型家電量販店のオーディオ設備の売り場で僕達は四人でああでもないこうでもないとイヤホンの音比べをしている。昼間約束をした僕と綾時に順平、それから四人目はアイギス。アイギスには放課後に捕まった。綾時が一緒に行くのに、順平だけじゃ心許ないから「私も同行させてもらうであります」というのが彼女の言い分だった。
アイギスと綾時は何故か仲良くなれない。青い瞳の彼と彼女は僕からしてみれば結構似通った部分が多くて、アイギスの警戒心させもっと薄ければきっと二人はもっと歩みよれると思うんだけども、アイギスは頑なにそれを拒絶する。あの修学旅行先での、美鶴先輩の「処刑」の後の遣り取りを思い出す。綾時が苦手だというアイギス。違和感が残り、しこりのように彼女の思考回路を遮って、まるで人間のようにかぶりを振る。
近頃アイギスはすごく人間らしくなってきた。最初の頃、屋久島で出会ったばかりの彼女はもっとメカメカしくて、考え方が僕達と少しずれていた。だけど今は違う。人間と同じように「答えのでない疑問」に思い悩み、苦悩し、「わからない」と首を振ることが増えた。機械にとって、答えが選択出来ないというのは致命傷と成り得るバグのようなものだ。だけど彼女は平然とその事態を受け入れて今も活動を続けている。答えの出ない、「理由がわからないけれどダメ」な綾時のすぐそばでヘッドホンをあれこれ手にとって試している。
「アイギスさんは、イヤホンよりヘッドホンが似合うね。この赤色のなんてどうかな。今のと、デザインがちょっと変わるんだけど……」
「折角なのですが、これは性能がいまいちです。私の眼鏡に適うものがあまりありません。風花さんに改造して貰った方が私の場合は早いのかもしれません。それより、湊さんのイヤホンはどうなのですか」
「うん。大体目星がついて、三択ぐらいまで絞れたんだって。残念ながら完全に同じモデルはなかったらしくって、後継機にするかそれとも少し路線を変えるか迷ってるみたいで……」
「そうですか」
「らしいぜ。そんで一人で考え始めちゃったから俺らは邪魔しない方がいいかなってアイちゃん達の方へ」
「順平さん。何故だか、貴方にその『アイちゃん』というあだ名で呼ばれることを好ましく思えません。そうですね……美鶴さんのようにブフが使えたら、あなたを氷漬けに……」
「わーっタンマタンマ、勘弁してくれアイギス!!」
たとえばだけど。今の彼女のこの反応、これは、もうプリセットされた感情の閾値を超えてるんじゃないだろうか。イヤホンを試着して少しだけ音の遠くなった世界で僕はぼんやりとそのことを考えた。Aを入力されたらAを答えて、1+2を問われたら3を返すのが機械の役目だ。機械はルールに従って正確に稼働しなければいけないから、1+2の答えを気分で「今日は2.5ぐらいですね」とは答えない。「思い切って5にしましょう」とも言わない。機械にとって1+2はあくまで3ではなければならない。
だけど彼女の反応はそうじゃない。彼女にとって綾時は「ダメ」なもので、それが機械としての定義なのだとしたら3は永遠に二進数の「11」でなければいけないのに、綾時に対する態度がぶれるのだ。確かに僕はアイギスに「もう少し仲良く出来ないの」と一度言ったことがあるけれど、……それではいそうですねと簡単に修正が行えるのは人間だけだ。機械に修正や学習をさせたいのならば上位の権限で彼女の認識を書き換えなければいけない。
当然僕はそんなことはしなかった。出来なかったというのもあるし、したくないという気持ちが強かった。彼女の永久機関《パピヨンハート》で動いている頭脳はそんなことをしなくとも大丈夫だと思ったからだ。心に干渉したくない。僕は、アイギスには心があると、信じていた。
そして実際に、彼女の認識は少しずつずれてきているようだった。アイギスと綾時の距離が縮まって、こうして普通の会話が成り立つことがあるぐらいにアイギスは「ぶれて」いる。
それはあたかもヒトではないものが人になっていくかのような。
(Far in mist a tower awaits, Like a merciless tomb devouring moonlight……)
そうやって根気よくものを教えたり待ったりする感覚を僕は知っていて、だから無意識に重ねているのかもしれなかった。
あの子も、初めのうちは、そうだったから。
『ねえ、よかったら、僕とトモダチになってよ』
はじめのうち、ファルロスにとって有里湊という人間は、「興味対象」でしかなかった。可能性を感じるんだ、面白そう、だから君を見ていたいな。ファルロスはそういう思惑を隠そうとしなかったし僕もそれはそれで別に構わなかった。あの不思議な子供は、多分人間ではないんだろうなとは薄々分かっていた。それでもよかった。
それでもいいから、僕は、あの子に何かを教えてあげなきゃって信じていた。
(I rush straight ahead with a sword in hands……Cold touch of my trembling gun……I close my eyes to hear you breathe……)
十一月四日の朝に僕の元を訪れたファルロスの表情をよく覚えている。『たとえ今日が最後になっても』と言った君が僕に何と言ったのかを僕は忘れない。『絆が僕らをいつでも繋いでいる』と言った君の安らかに伏せられた瞼を、僕は、ずっと、
多分、えいえんに、
「湊さん」
「湊君!」
わっ、と両耳から急に大きな音がして僕はびっくりして目を見開いた。「随分長いこと考え事をしていたようですが」とアイギスの声。「決まった? どれにする?」と更に綾時の声。
「まだ聞き比べ、終わってない? それとも甲乙付けがたくて迷っちゃったとか。どうだい」
「……どれがいいかなって、ぴたっと決まらない。あと少しなんだ。だけどそのあと少しが半端でしっくりこない」
「うーん。それじゃ、もし良ければだけど僕が選んでしまってもいい?」
君の中で決着が付かないのなら一つの案としてだけど、と注釈が続く。この場合は三択だけど、四択を二択に減らすフィフティ・フィフティ、クイズ番組の選択肢の一つみたいだねって言うと、綾時は「それなんて番組?」と小首を傾げた。
「君は本当になんでもよく知ってるね。僕、テレビはあんまり見ないんだ。お母さんがそういう人だったから」
「別に、僕も自分からは見ないけど。おじさんが好きだったからさ。友達が司会だったんだって」
「へえ、友達が」
「そう、友達が」
二人で何故だか「友達」という部分を妙に強調して、それからぷっと顔を見合わせた。綾時の手がひょいと伸びてきて僕の目の前にずらずらと並んでいる棚からケースを一つつまみ上げる。僕が以前使っていたヘッドホンと同型の後継機種。色合いは殆ど同じで、値段も、確かそうこのぐらいだったはずだ。おじさんが「お前はお目が高い。いい値がするものを選びやがって……」と言っていたからこの程度には高かったはずだ。「これ、どう?」と手渡された箱を手にとって僕は小さく頷いた。さっきまではどれにしようか、正直どれでもいいようなそんな気もしていたのにいざこうして綾時に選んで貰って手渡されると、もうこいつじゃなきゃいけないような気がしてきて頷く他なかった。
「これにするよ」
「わあ、本当かい。僕の選んだものを君が使ってくれるってなんだかすごく嬉しい」
「僕も。綾時の選んだものがどうせならいいなって思った」
レジに向かってすたすたと歩き始めると後ろに綾時がくっついてくる。あんまり大人数で行ったって仕方ないと思ったのか、順平とアイギスは綾時にはならわずその場で留まったみたいだった。その代わりに僕が購入を決意したイヤホンが掛けてあった棚に近寄って値札をを確認して、そして順平が頭をガンと殴られたような衝撃を受けていた。
「友達に選んで貰うっていうのも悪くない」
僕がぽつりとそう零すと綾時は「へ」と一瞬本当にすごく間抜けな顔をして、それから自分のことを自分で指さして僕へ訊ねたりなんかする。「ねえ僕、君の友達?」だっておかしなことを聞くんだなって思いながら僕は「そうだよ。そうじゃなかったら、何なの。他人じゃ、ないよ」とだけ答えてやった。
一番最初に屋上で「友達になってよ」って言ったの、綾時はもしかして覚えてないんだろうか。そんなまさか……いや、でも、どうだろう。綾時なら有り得る気がする。僕は綾時の友達だから綾時のことはある程度知ってるし、そんな感じがした。
帰り道、綾時と二人でイヤホンをシェアして道をてくてくと歩いた。ペタワックでテイクアウトしたポテトを行儀悪く二人で食い歩きしながら、僕の携帯音楽プレイヤーに入っている曲を聴く。綾時が修学旅行の帰りに「君みたいだね」と言った曲。「Burn My Dread」。
「もうこの曲は、君のテーマソングだねぇ」
綾時が実に暢気な声で言った。
「でもやっぱり君ってこういう感じがする。君は強い人だ。君達はみんなそれぞれにとても強いけれど、君は特に」
「そう?」
「友達の僕が言うんだからきっと間違いないさ」
てくてく。てくてく。歩く僕達を、順平とアイギスが遠巻きに見ている。順平は何とか話題を見つけようと間を探っているみたいだったけど、結局僕らが寮に帰り着くまで上手い具合に何かを切り出すことは出来なかったみたいだった。
アイギスは注意深く観察するように前を歩く僕ら二人を見ていて、その視線には恐らく綾時も気が付いていたはずだと思うんだけど、僕も綾時もアイギスの方を振り返ろうとはしなかった。
そのまま三人は寮の中へ入り、いつものようにお茶でも飲んで行くかと誘ってみたんだけども綾時は珍しく首を横に振ると、ちらりとアイギスの方を伺ってマフラーを巻き直すと通りの向こうへ消えていく。アイギスが「イヤホン、良かったですね」と小さく言った。後は、特に何か記すようなことはない。
それが僕と綾時が最後に出かけた日のこと。
◇◆◇◆◇
「私は対シャドウ制圧兵装のラストナンバー。取り返しの利く命。だから私が皆さんを守らなければいけないと信じていました。それが私の役割でした。出来ると思っていました。私には人間と同じ意味での死は存在しません。死んではいけない皆さんの代わりに……私が。私があの人にとどめを刺さなければいけないと考えていました。それが十年前にあなたにしたことへの、償いにならないのだとしてもせめて、と……」
アイギスが長い空白の後に寮に戻ってきて、その夜、彼女は密かに僕を呼び出した。寝静まって誰もいない談話室で僕達はぽつりぽつりと話をする。話題に上るのは「彼」のこと。望月綾時。十三番目の存在しないはずのシャドウ。死の宣告者。だけどあいつは僕の友達だった。
約束の日はもうすぐそこまで迫ってきていて、アイギスもそのことは把握していたから、「こんな時間にすみません。だけど今しかないと思ったから」というふうに僕に頭を下げた。「あなたは……いえ、皆さんは先程ああ言いましたけれど……」と言葉を濁して、最後に「ごめんなさい。私自身も、もう、よく、わからないんです」と締める。アイギスがわからないこと。ああ、そのことか、と僕はすぐに察した。
「望月綾時」というものの認識についてだ。
「でもダメでした。私には出来なかった。確かに《デス》は、存在するはずのない十三番目のシャドウは、忌むべきものです。殺さなくてはなりません。でもあの人は……《望月綾時》は……」
あの人がシャドウとして、宣告者として桁違いに強かったことも一因ではあるのですけど……と釈明のように前置きする。「機械の本能は、心の底からその存在を忌避しました。圧倒的な上位者の存在を、機械の本命を全うすることを阻む怨敵を恐れました」そこまで述べて、アイギスは「だけど!」と首を振る。感情を露わにして隠そうともせず、僕の胸ぐらを掴まんとするぐらいの勢いで叫ぶ。
「私の『心』がその認識を忌避したんです。確かに皆さんを守りたいという気持ちは心も強く支持していて、その与えられた命令を遂行するためには綾時さんを倒さなければ、殺さなければならなかった。だけど私にはそれが辛かった。……心のどこかで迷いが生じたんです。機械には、本当はそんな『誤作動』はあってはならないものだったけれど」
「……続けて」
「彼は……人間でした。少なくとも私の目に映る『望月綾時』は、私が守ろうとした皆さんと、本当は、何も変わらなかった」
「そう」
「私はあの人と交戦して初めて理解したんです。あの人は、綾時さんは、あなたに育てて貰ったんですね。たくさんの感情をロードしました。私も同じだから、すぐにわかりました。綾時さんの抱いていた湊さんへの感情」
綾時。あの子は結局、僕の胎内で育ち、成長したシャドウだったのだと自分を示してそう言った。「僕は人間じゃないんだ。ごめんね」と言う綾時の顔はすごく辛そうで、見ている僕は、胸が張り裂けてしまいそうなぐらいその顔が嫌だった。
「あれは母親と慕う誰かへの憧憬でした。勿論、彼が母なるものだという、ニュクス……大いなるもの、などではなく」
人間になりたかったシャドウ、それは、なんて残酷なことなんだろう。シャドウは皆「母体」に戻ろうとする習性があり、その法則に則って彼も戻ろうとしたけれど彼は人工的に造られた、死の写し身だ。彼には本当の意味での母体はニュクスの他ない。
でも、と綾時は言う。「でもね、湊君。僕にとっては、君が」。
人間に焦がれたあの子は僕から手に入れた人間性で「半分人間」になり、《望月綾時》になる。人間と同じように感情を表し、痛みを覚え、涙を流す。それってもう人間だってことと同じじゃないの? って僕は訊ねた。あの夜部屋に二人きりになって、僕にだけは綾時が殺せるんだって言い聞かされた前の日に、そういうふうに。
綾時は首を振った。「だって人間だったら僕はこの運命を嘆いてきっと自殺していただろうね」って。
死ねない死が、まるで人間みたいなことを。
「湊さんがイヤホンを新しく買いに行った日、私、あの人と話をしました。あの人の空色の目と逃げることなく真っ正面から、私は彼と会話を持ちました。言葉の遣り取りを通じて、お互いに魂の根源を探り合うような、二人で『知りたい』と言って手を伸ばし合うような、そんな会話でした。湊さん、……あの人は、」
「アイギス?」
「私の目を見てこう言ったんです。『僕のお母さんの色だね』と」
アイギスが一際強く、逃がすまいとするみたいに僕の腕を掴んだ。アイギスの目。アイギスの瞳。空色のアイ・レンズ。綾時と同じ色をした、あおいろの世界。僕の好きな色。綾時のお母さんが好きな色。それらが今僕の中で緩やかな等式を描き出し、やがて、イコールで結ばれる。
僕の好きな色は綾時の世界。
「綾時さんが慕った母親は、湊さんです」
アイギスの空色が僕を捉えた。綾時のあおいろに覗き込まれているかのような気分だった。僕の愛する尊い色は、こうして僕を束縛する。
「私が十年前にあなたの身体に押し込めたシャドウは、あなたを、母として焦がれたんです……」
考えてみればそれはとても単純で簡単な図式だった。
かつて僕の中に綾時がいて、それはアイギスが十年前に仕留めることに失敗したデスで。でも、ならば、あの子はどうやって人間性を獲得したのだ? 僕に与えられたと彼が言う人間性、だけどそれは散り散りになったシャドウの破片を集めたから手に入ったものじゃないだろう。僕が一つ一つ教えて与えていったのだ。どこで。どうやって。
一つしかない。
あの、夜の子。
「ファルロス」
綾時が転校してくる直前に朝日の中で別れを告げた僕の友達、僕に愛情を教えてと願ったあの子は、綾時と同じあおいろの目をして泣きぼくろを持ち、僕にたくさんのことを教えて貰った、とはにかんだ。
そして望月綾時は同じように、「母親にたくさんの物事を、そして愛情をも教えて貰った」のだとそう僕に言った。
僕は黙ってアイギスの手を握り返す。ファルロス。僕は君に正しく愛情を伝えられていただろうか。「ファルロス」を「綾時」にしてしまうぐらいに。
僕の愛は君に伝えられていたのだろうか。
「僕はまだ綾時に、伝えてないことがあるんだ」
「……それは、どのような?」
「泣きぼくろ。僕の右目の下にも……お前と同じ、左右対称の、アシンメトリの、泣きぼくろがあるんだって。いつか言ってやらなきゃと思ってたのに」
もしも僕のこのつたない感情を君がちゃんと受け取ってくれていたのだとして、それを、君が受け入れてくれたのだとしたらそれはどんなに素晴らしいことだろう。「お母さん」の話をする時、いつも綾時は世界で一番大切でうつくしい人の横顔を語る眼差しをして僕にその話をしてくれた。その話をする綾時こそが、僕にはとても尊いものに思えていて、だから僕は、彼の母親の話を聞くのがむずがゆいけれど嫌じゃなかった。
「……ではあなたは綾時さんを殺さないのですね」
アイギスの声音は静かで、凪いで、決まり切ったことを反芻するように淡々とそれを訊ねる。大晦日の選択。望月綾時を殺害して仮初めの平穏を手にするか、望月綾時を生かして絶望の中で足掻き続けるかという二者択一。そうだね。答えは決まり切っているから、アイギスのその訊ね方は極めて正しい。
「僕にはそれは出来ないよ」
「けれど、湊さんにしか出来ないことです」
「それじゃあ世界中の誰にもそんなことは出来ないんだ」
「いいえ。あなたには、出来ます。……湊さんに心さえなければの話ですけれども」
アイギスが悪戯っぽく笑った。
アイギスにはわかっている。綾時に心があり、僕に心があること。アイギスにも心があるから知っている。望月綾時とアイギスはそれぞれに、僕から心を受け取ったのだということを、そうして少しずつ「人」になっていったのだということを、理解している。
「でもきっと大丈夫だって、そんな気がしているんです……」
「そうだね」
「綾時さんはお母さんを心から愛していました」
「うん」
「……それって、とても、素敵なことですね」
アイギスのアイ・レンズは、遠く澄み渡る水の色をしていた。
「私も湊さんのことが大切です。だから、その日まで、私にお手伝いさせてください。あなたが綾時さんに伝え忘れることがないように」
——本当は。
アイギスと綾時はよく似ていたから、きっと、素敵な友人になることが出来ただろう。何と言っても僕が分け与えた二人だ。アイギスが人間を守るよう命じられた機械で、自立して思考する兵器で、綾時が人間に憧れたシャドウでさえなかったら、もし二人が人間だったら。
でもしか論を考えたって仕方ないんだけど、僕はそう考えずにはいられなかった。僕達のあおい世界、その中で生きていた二人がこんなふうにしか出会えなかったことが悔しかった。僕は綾時と友達でアイギスとも友達だったけれど、最後まで、アイギスと望月綾時は友達ではなく「敵」だった。
ぶわりと、空間が切り替わるような感覚と共に十二月三十日の影時間が終了を告げる。空の色は戻り、星が空へ帰って来る。そう言えば君は星空を見て大はしゃぎしていたね。僕が君に見せたいものの一つだと言ったことを、きっとどこかで覚えていてくれたんだ。
影時間の終了は即ち暦の変更を意味している。「今日が大晦日です」アイギスが再確認のために口を開いた。「また、会えますよ。あの人と」。
「嬉しいですか? 悲しいですか?」
どちらですか。今、僕の両手の平の天秤にはとても重大な決定が秤にかけられてぷらぷらと揺れている。世界を終わらせるかどうかの、イエスかノーかの選択肢。僕の針は片方に傾いている。世界の終わり、それに対する「NO」。
「……どっちも」
だから答えは、どちらも、だ。
綾時に会えるのは嬉しいし、ずっとそう出来ることを待ち望んでいた。許されるなら僕は彼を抱き締めるだろう。僕の青い夜の子を、精一杯抱擁する。
だけど彼の甘い毒のような提案だけは蹴ってやらなきゃいけないから、それはあの子とその根底にどんな意思があるとしても、一度決別の形を見るということだ。あの子のことが大事だからそうするのだけれども、道を違えねばいけないというのは、やはりあまり気の進むものじゃない。
「僕達きっと今、最高に青春してるんだろうね」
「……急に面白いことを言うんですね」
「だってそうだ。こんなに思い悩んで、泣きそうになって、それでも、前に進むしかないなんて……それってすごく。『青い春』って言うに相応しいやつなんじゃないかな……」
「私も、そうなのでしょうか?」
「勿論、アイギス」
それで僕達の秘密の夜の会話は終わった。
コーヒーカップをシンクに置いて、彼女におやすみを言う。彼女もまたおやすみ、と言って僕に応える。
機械人形で戦闘兵器だったはずの彼女を、その時僕は心から人間らしい存在だと感じた。死ぬのが怖い機械の彼女になら託せる気がした。
なんとなくわかってる。けれど僕は、人間の彼や彼女達と一緒になら戦う覚悟があるし、綾時に全てを伝える決意もある。
心と心の間で繋ぎ、築き上げた物がある限り。