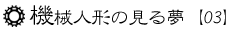「ええ、それじゃ十代ってデッキ持ってないの? デッキ。それって大変じゃない?」
「ああ、どうもなくしちまったみたいで。しかも何のデッキ使ってたのかも一緒に忘れちゃったんだよ」 『くりくりぃ』 「今残ってるのは相棒のハネクリボーだけ。でもあんまり天使族デッキ! って感じでもないし」 羽根の生えた茶色い毛玉が十代の隣でくりくり鳴いて同調している。龍可の持っている「クリボン」にどことなく似通っている十代のそのモンスター、「ハネクリボー」をまじまじと見つめて龍亞は首を捻った。龍亞は妹の龍可と違って本来は精霊を見ることが出来ない。今ハネクリボーを眺めていられるのは単純にハネクリボーが実体化しているからだ。 どうやらハネクリボーのマスターである十代はアキに似た、精霊を実体化させる能力の持ち主であるらしい。しかしサイコ・デュエリストとは違いデュエル・ディスクを通す必要がない。だから似た能力。アキ自身は、「彼の能力は私の能力なんかよりもよっぽどずば抜けて珍しく強い能力だわ」と言っていた。チーム・ファイブディーズの面々もそれには多いに頷いている。 「でもさあ、デッキないとこの先困るよね。だってここネオドミノだよ。天下の聖地だよ? デュエルが出来ればあとはなんとか、って感じがあるし……」 「そうね。デュエルが趣味程度でも嗜めないといろいろやり辛いのよね。逆に強ければそれ程武器になるものもないわ」 「うんうん。ね、十代ってどのくらい強いの? デッキなくしたってことはなくす前は結構それでデュエルしてたんでしょ?」 期待と興奮が隠せない少年らしい高揚した声で龍亞がねえ、と尋ねてくる。十代はこの可愛らしい少年の疑問に大真面目に付き合ってやって、もやがかかって茫洋とした記憶を懸命に手繰り寄せてみた。デュエルが、とにかく楽しかったことは覚えている。仲間達と力を合わせて結束して、勝ったら大喜びで。そう、デッキのモンスター達は十代にとっては大事な仲間だった。あいつは家族だって言ってたけど、仲間。 「……あいつ?」 呟いてからはっとして首を捻る。デッキに入っているデュエル・モンスターズの精霊達が家族なんだと目を輝かせていた「あいつ」のことが上手く思い出せない。声も、姿も、何もかもが曖昧でぼうっとしていた。手を伸ばしたら霧散してしまいそうだった。 「十代、どうしたの?」 「ん、いや、ちょっとな……デッキの中のモンスター達を『家族』だって言ってた奴がいたような気がするんだ。でも思い出せない。もしかしたら、そいつ俺の友達だったのかな」 「友達どころか、十代が探してる人かもね。断片的にでも覚えてるってことは、とても印象深い人ってことでしょう? ――でも、家族、か……。精霊のことを家族って呼ぶその人になんでだか今親しみを覚えちゃった。そんな人知り合いにいないのにね」 「龍可にとってクリボンは家族みたいなもんだろ? 親近感だよ、きっと」 龍可のまわりをふわふわ漂っていたクリボンをわしゃわしゃと撫でて実体化させる。龍亞が「クリボン、いたんだ!」と姿を現した小精霊に手を伸ばした。ハネクリボーもつられたのかそちらに寄っていく。二体の小精霊と幼い双子が戯れている様は愛らしく、確かにどこかしら家族然とした空気があるようだった。 微笑ましく見遣ってから今一度デッキの内容に思いを馳せる。仲間である精霊達の数は結構なものであったように思う。種類も、一つに統一されていたわけではなく結構ごちゃごちゃとしていたはずだ。対戦相手に「カテゴリがそんなに入り混じっていてよく手札事故を起こしませんね」と純粋に驚かれたようなそんな覚えがある。それも一人や二人じゃなかったから、メイン・デッキに複数のカテゴリが投入されていたのだろう。 ファンシーな魔法使いや、遊星やブルーノのようにかっこいい機械族(遊星のモンスターには結構な確立でどう見ても機械族にしか見えない戦士族モンスターが存在していたが)、アキのような見目麗しい植物族、クロウのテクニカルな鳥獣族、ジャックの力強いドラゴン族――思い当たる順にぱっ、ぱっ、と種族を頭の中に並べていくがどれもいま一つしっくりこない。そもそも自分は機械とかいう柄ではないのだ。植物でも鳥獣でもドラゴンでもない。しかし、ハネクリボーの天使族もぴんとこない。あと、出てない種族は爬虫類に炎に雷、岩石、悪魔――まだあるけどどれも何かが違う。 「ああでも、ジャックのリゾネーター・カテゴリモンスターは可愛いよなあ。悪魔族だっけあいつら」 「ジャックがどうかしたんですか」 「あ、遊星」 「丁度あなたの声が聞こえて。考えごと、邪魔しましたか」 「ん、いや。むしろ丁度いいよ」 通り掛かったらしい遊星が相変わらず丁寧な物腰で十代に尋ねてきた。理由は知らないが、どうやら十代はこの青年にとってのヒエラルキーのほぼ頂点に君臨している、らしい。そのようなことを遊星の彼女であるアキに苦笑混じりで話された時はぽかんとしたものだが、なるほど数日付き合っているとその言葉の意味が徐々にわかってきた。 不動遊星は基本的に他人を尊敬しない。いや、それは決して傲岸不遜であるからだとか、そういうことではないのだ。敬うべき相手にはそれ相応の態度で臨んでいる。ただ、その「相応の態度」の中でも十代に対するものが頭一つ飛び抜けて丁重なものであることは明白な事実だった。どうも、遊星の中で自身でもよくわからぬ内に十代への絶対格差が生じてしまっているようなのだ。 「龍亞と龍可がさ、デッキがないままだと苦労するから、作った方がいいって。それで以前のデッキを思い出せないものかと思案してたんだけど」 「ああ……それはそうですね。十代さん、バイト先のアテは見つかりましたか」 「アテ? あそこいいなーってとこは一つあるけど。シティ中央部のカフェテリア。制服のセンスが好みでさ」 「なら尚更デッキがあった方が有利です。腕が良ければ面接にプラスが入ります」 「……なんつーか、徹底してデュエル脳社会だな」 「ネオドミノですよ、ここは。他でもない伝説の聖地です。この土地においてはデュエルが全てを左右すると言っても過言じゃない」 さらりと言う。この自信もそれに見合う実力もある男に、「十代さん」と名を呼ばれることがむず痒くも心地良い。不動遊星は男である自分から見ても非常に魅力に溢れた青年だ。優良物件ってレベルじゃないよなこれ、と内心で呟いた。アキは果報者だ。尤も、アキ自身も容姿端麗頭脳明晰の高嶺の花だからこれはこれで上手い具合に釣り合っているのかもしれないが。世の中上手く出来ている。 「そんで、遊星は強いのか? そういうことをなんでもないふうに言えるってことはさ。そのシステムで今まで苦労してきたこと、ないんだろ?」 「え」 「あ、気分悪くしたんならごめんな。ちょっと思っただけ。遊星はさ、すごいなって」 「――でも、」 「ん?」 茶色い毛玉と戯れている双子を見て目を細めながら特に他意なく漏らすと遊星は虚を突かれたようになって、息を呑んだ。不審に思って振り返る。社会的な地位も明るい未来も約束されている青年は整った顔を僅かに歪めて十代を見つめている。どきりとした。このような表情を十代は知っている。 誰かを敬愛してやまず、崇敬し、崇拝する時の表情だ。 「俺は、あなたには敵わないんです。絶対に」 昔十代自身も誰かに向けていた表情だった。だが誰に? やはり、思い出すことは出来ない。 ◇◆◇◆◇ シティ繁華街のカード・ショップで龍亞が背伸びをしてあれこれと十代に言っていた。ショウ・ケースに陳列されている高額カードを眺めながらふんふんと相鎚を打つ。見覚えのないカードがわんさとあって見るもの見るもの目新しい。 白枠のシンクロ・モンスターが特に強く十代の目を引いた。この時代では最もポピュラーでスタンダードな上級モンスターの召喚方法なんだそうだ。十代が一応「儀式は?」と尋ねると「えー、うん、まあ、リチュアってカテゴリが強いかな……」と言葉を濁された。わかりやすい。 「汎用魔法罠はさ、俺らの余りで多分なんとか出来るよ。奈落の落とし穴とか神の警告とか。十代はどういうの採用する?」 「馴染み深いような気がするのは攻撃の無力化、神の宣告、聖なるバリア‐ミラーフォースあたりかなあ。激流葬あたりも一応……」 「じゃ、大丈夫。クロウとかジャックに聞かなくても多分俺の余りで足りるよ」 「おう、サンキューな。しかしデミスドーザーが大したことないなんてすげえ環境だな」 龍亞が言葉を濁した儀式系デッキの控えめなパーツコーナーを見付け、感慨深げに陳列されたごくわずかなカードを見る。終焉の王デミス特価百円。サウザンド・アイズ・サクリファイス特価五十円。なかなかに衝撃的だ。 「十代、何見てるの? あ、それ禁止カードだよ。買ってもしょうがないって」 「禁止っていうか、これペガサス会長のじゃん。遊戯さんと戦った時の秘蔵のカード。レプリカ出てたんだ……」 「ペガサス会長?」 龍可が変な声を出す。聞き覚えがないらしく誰それ、という顔をしていた。勤勉な龍可が知らないということは、この時代において適切な人物ではないのだろうか。十代は自分が元いた時代にも実のところ確信が持てない。もしかしたら未来から来たのかもしれないし過去から来たのかもしれない、そういうふうに遊星に言われてそれもそうかなと頷いた。 儀式パーツコーナーから右に進むと紫枠の融合パーツコーナーにラインナップが変化する。儀式よりはいくらか広く間取りが設けられていて、十代はワクワクしながらそれを一つ一つ見た。シンクロ・モンスターももちろん見知っているが融合モンスターの方がワクワクして心踊る。だから多分記憶を失う前の自分は融合デッキ使いだったのだと十代は考えている。そう考えると確かに、フュージョン・ゲートなんかは覚えのあるカードなのだ。 指で順々にカードを追っていくとメモ書きが目に入った。曰く、『ヒーロー、サイバーはレプリカ特設コーナーへ』。レプリカカードというのは、世界に一点しかないレア著名カードをレアリティを落として生産された一般向けコモンカードのことだ。例えば先に見かけたサウザンド・アイズ・サクリファイス。元々あれは一点ものの激レアカードなのだが、レアリティをウルトラレアからスーパーレアやらにランクダウンして大量生産したのだろう。見分けるのは簡単で、レアリティでも見抜けるが左下の「レプリカ」表記を見るのが一番手っ取り早い。 「なあ龍亞、レプリカ・デッキって普通に組めるのか?」 「え? うん、出来るよ。ただレプリカはコレクションで買う人が殆どでデッキに入れたとしても普通は一枚二枚ぐらいだけど。ああいうのってクセが強いから本物の持ち主以外は同じレシピでデッキ作っても上手く回せないんだ。なんか気になるの、あったの」 「ああ。ヒーローがちょっと気になってさ」 「ふーん……」 足早に向かったレプリカカードのコーナーは思いのほか広かった。武藤遊戯のブラック・マジシャンやブラック・マジシャン・ガールが目に入って思わず値札に視線を向けてしまう。――『一枚五万円(レプリカ)』。流石としか言いようがない。 レッドアイズ・ブラックドラゴン、黒竜の雛――それらも負けず劣らず高い。そういえばレプリカとしての一般販売は基本的に一度っきりなのだったか。元々、物によっては少量限定生産になってしまいがちな商品だったような気もするし、レプリカモデルが作られるのはそもそもが人気プロデュエリストなんかのメインカードに限られているから販売から時間が経つとこういうことになってしまうのだろう。 そのまま視線をスライドさせていくと、お目当てのカード郡はすぐに見付かった。ヒーロー・モンスター。E・HERO、D‐HERO……それなりに数がある。見覚えのあるものばかりだな、と思った。見覚えはある。だがテキストは思い出すことが出来ずぽっかりと欠落してしまっている。 「エレメンタル・ヒーロー」 「あっ、それ? 二代目決闘王のカードシリーズだから、結構高いよ。決闘王ってだけで大人気だもん。遊星のスターダストもいつかレプリカになったらそのぐらいの値段になったりしてね」 「案外有り得るかも。スターダストは綺麗だしとっても強いもの」 双子の言葉を右から左に流しながら十代は食い入るようにカードを見つめた。ネオス。フレイム・ウィングマン。エッジマン。マリンドルフィン。ミラクル・フュージョン。ヒーロー逆襲。 「大体一枚ずつかな……全部ぶっこんでも、まあ回るだろ。コンバート・コンタクトとホープ・オブ・フィフスで上手くドローして、あとバブルマンと壺と施し……なあ、悪夢の蜃気楼って今禁止か?」 「そうだけど。って十代、本気で二代目決闘王のコピーデッキ組む気なの?!」 「うん。一番気に入った」 こともなげに言う。双子は度肝を抜かれてしまってあんぐりと口を開けた。レプリカ・デッキは揃えるのに大金がかかり、その割に上手く使いこなせない。本物の持ち主のクセが強く、高度なテクニックとセンス、そして大概の場合はそれに上乗せして並々ならぬドロー力、すなわちリアルラックが求められるからだ。それを説明してやったつもりだったのだがもしかして言葉が足りなかったのだろうか。 しかし十代は双子を一瞥するとにやりと笑んで「言いたいことはわかってる。大丈夫だから」と言って壁の貼り紙を指差す。慌てて内容を流し読んだ。『レプリカ・カードを四十枚以上購入の際にワンチャンス。当店が用意したプロキシカードを用いて店長に勝利した場合、全額から九十パーセントオフ!!』……無茶苦茶だ。 「合計六十枚で総額十五万円ぐらいだから、勝てば一万五千円だろ。そのぐらいなら払える」 「そのぐらいなら払えるって、無茶だよ! ここの店長すごい強いんだから。元プロデュエリストであのサイバー流の後継者で、遊星だって負けたことあるんだよ! 何年か前に一回だけど」 「大丈夫大丈夫。俺負けないから問題ない。カードの精霊達はな、信じれば応えてくれるんだぜ」 「……十代、水を差すみたいで悪いけど使えるのは持参のカードを除けばプロキシ、コピーカードよ。その辺のコピー機で作ったコピーカードじゃいくらなんでも精霊は宿らないわ」 「そいつはどうかな。やってみなきゃわかんないぜ? ――すみません、店長にこのデュエル申し込みたいんですけど!」 まるで聞き入れる素振りもない。唖然とした表情の双子に手招きをして十代は足取り軽やかに駆けていく。負けた時どうなるのかは考えたくもなかった。十五万円といえばそこそこの大金だ。最悪遊星につけておこう、という悪い考えが一瞬脳裏を過った。 終わってみれば、それはいっそ残虐なまでに一方的なデュエルだった。清々しい程に十代は強かった。強すぎた。遊星とジャックがデュエルを始めたばかりのジュニアスクール生を相手取るよりも歴然とした実力差がそこにはあるように思えた。 「サイバー・エンド・ドラゴン使っててアタック八千止まりとか、サイバー流の名が泣くぜ。未来融合オーバーロードフュージョン、リミッター解除で初手一万六千ぐらいは余裕だろ? 仮にもプロだったんならさ。――速攻魔法、『決闘融合‐バトル・フュージョン』。自分フィールド上に存在する融合モンスターが戦闘を行う場合、そのダメージステップ時に発動出来る。その自分のモンスターの攻撃力はダメージステップ終了時まで戦闘を行う相手モンスターの攻撃力の数値分アップする。更に手札から『オネスト』の効果発動、自分フィールド上の光属性モンスターが戦闘を行うダメージステップ時にこのカードを手札から墓地へ送る事でエンドフェイズ時までそのモンスターの攻撃力は戦闘を行うモンスターの攻撃力の数値分アップする」 淡々とつまらなそうに効果説明をする声がしんとした店内にいやによく響いた。最初は興味本位で集まってきていたギャラリーも、すっかり静まりかえってこの勝負の行末を見守っている。十代が「アタック」と短く攻撃宣言を上げ、相手の店長が「参りました」と敗北を認めるとざわざわとギャラリーにざわめきが波及し出した。やれ、まさかあの店長が負けるだなんて、だの何者だあいつ、だの。 十代のデッキは龍亞が貸した数枚の汎用魔法罠を除いてデッキのほぼ全てがプロキシカードだった。かたや相手方は正真正銘本物の開祖直伝サイバー流デッキだ。数十年を共にしてきた魂のデッキをプロキシの寄せ集めで抵抗の余地なくずたずたにされた店長の心持ちの方が龍亞としては心配になる。 店長の引きだって決して悪くなかった。サイバーエンドを僅か数ターンで召喚し、リミッタ−解除で一気に決着を着けようとした。十代の場には「シャイニング・フレア・ウィングマン」と伏せカードが一枚のみ。効果でアタックが上昇していたとはいえ三一〇〇だ。八〇〇〇のサイバー・エンドなら一撃で勝利をもぎ取れるだろうと誰もがあの瞬間は確信していた。 しかし実際には決闘融合とオネストでシャイニング・フレア・ウィングマンのアタックが一九一〇〇まで跳ね上がり、逆に店長の側が一撃でオーバーキルされてしまった。その姿は圧倒的であり、しかし華麗であった。 「ガッチャ、筋は悪くないぜ、うん。ただちょっとドロー力と構築が甘かったな。折角のサイバー流なんだから保身はほどほどにしてオーバーキルをメインに据えた方が構築としては面白いと思うよ」 「いやはやこうも完膚なきまでに叩きのめされるとは……参った。九十パーセント引きと言わず全額無料で持っていってくれ」 「おっマジで? それは助かる」 「……いや、マジでって言いたいの、こっちの方だけど」 「龍亞」 あまりのことに何と言っていいか途方に暮れている龍亞の姿に気が付いて十代がどうした、と手を差し伸べてくる。綺麗に整ったこの指が今の今まで圧倒的な実力差を演出していたとはとても思えないが事実だ。ここの店長がプライドの異様に高い人間であったりしたら恐らく非常に面倒なことになっていたのだろう、そんなことを思う。 「な。俺は負けないってそう言っただろ」 「……うん。おっそろしく強いってことはよくわかったけど……」 ギャラリーを指し示して言外に「これ、どうするの」と尋ねる。彼らは皆一様に無名の超強力デュエリストに興味を示している様子だった。どこから聞きつけてきたのか耳の速いタブロイド誌の気者まで紛れ込んでいる。さっさとポッポハウスに帰りたいがそれが簡単に出来る状況だとは思えない。 双子は遊星達とずっと一緒にいたから、好奇の目には慣れている。しかし十代がそうであるとは限らない。少なくとも彼にこの事態を穏便かつ早急に解決出来る手腕があるとは考え辛い。 危機感のなさそうな十代の顔をちらりと見て双子はお互いの顔を見合わせる。どうしたものか、と溜め息を吐いたその時、ギャラリーの後方からどよめきが起こった。ずかずかとそれを掻き分けて、誰かがこちらに向かって来る。 「しかしあんた、冗談抜きに強いな。プロ・リーグでも滅多に見ないレベルだ。その上二代目決闘王のデッキを使いこなすとはとんでもないタマだ。あのお人のデッキはとにかくクセが強くてな、ほぼそのオリジナルレシピで挑んで来た時はこりゃカモだなと思ったもんだが……逆にカモられちゃざまあないな」 「いや、店長さんも強かったですよ。ただ俺の知ってるサイバー流使いには劣るかなって」 「ほう、そりゃまた大きく出たなあ。時に、名前を教えて貰っても構わないかね。自分を負かした相手の名前ぐらいは知っておきたいもんでね」 「ああ、そんなこと。俺の名前は――」 「言わなくていいですから、十代さん」 「……あれ」 思いっきり「遊城十代」と名乗ろうとしたのであろう十代の口を遮る手があった。ギャラリーのどよめきが更に凄まじくなる。そりゃ、あの不動遊星と謎の挑戦者が知り合いだと分かれば野次馬連中も興奮するというものだろう。何といっても不動遊星は三代目決闘王、現行タイトル保持者なのだ。 「遊星。なんでここに」 「シティのカード屋が騒がしいとクロウに教えられて慌てて来ました。案の定あなたでしたか」 「なんだよその言い方。俺、別に悪いことはなんもしてないぜ」 「悪事でなくとも、目立つことをしていたのは確かですよ。というか挑んだんですかこの勝負」 テーブルに散見出来るデュエルの名残りを見て流石の遊星もやや眉根をひくつかせる。 「うん。勝ったけど」 「……あなたには負けます」 「どうかなあ。これでデッキも手に入ったし、そういうのはやってみるまでわからないもんだ」 「そういう意味ではなく。デュエルでも勝てるとは思いませんが」 立ってください、携帯の契約をして帰りますよ、と言って遊星は十代にこの場からの退場を促す。店長からレプリカカードを一揃い受け取りながら十代は「携帯?」と露骨に不思議そうな顔をした。そんな謂れはない、という表情だ。 店長が遊星の姿を認めておや、と声を出す。 「遊星君じゃないか。そこの彼と君は知り合いだったのかね?」 「……父の知り合いで、訳あって今来て貰っている。俺の、師です。他に何か?」 「ああいや。カード、大事にしてくれよ」 「言われなくとも。カードには心があるからな」 十代はマイペースに頷いて双子を拾い、遊星に「携帯、マジで要るの?」と不満そうな顔で尋ねた。遊星の先導でモーセの川渡りのように開いていく道をずんずんと我が物顔で歩いていく。遊星は「こればかりは譲れません」と強固に主張をした。龍亞と龍可は何がなんだかいまいちよくわからないまま駆け足で二人にくっついて店を出る。 この出来事がそれからしばらくまことしやかな噂となって囁かれたのは言うまでもない。『あの不動遊星に、凄腕の師匠がいるらしい』、と。 ◇◆◇◆◇ 「へえ、そんなことがあったんだ」 メンテナンスの手を緩めることなく動かしつつ顔だけをこちらに向けてくる。ブルーノはまるで子供が隣の家の飼い犬と仲良くなったという類の話を聞いた母親のようににこにこして「それは、良かったねえ」などと何も考えてなさそうにのたまった。途端にクロウとジャックが噛み付く。 「良かったの一言で済むものか。あれ以来ここ周辺に妙な野次馬が増えてかなわん」 「ま、ジャックと遊星が住んでるから野次馬自体はそもそもいたんだけどよ。不動遊星が師事する超凄腕ヒーロー使いってんでもう盛大に噂が一人歩きしてやがる。二代目決闘王のデッキを使いこなしたってとこから再来だの生まれ変わりだの尾ヒレが付いてるし、その時店にいたらしい奴らの目撃情報も派手に装飾されて絶世の美男だかなんだか……ひでぇ奴だと不動遊星にボーイッシュな超美女の師範とかいうのもあったぞ。ゴシップ誌の三流ライターが食い付いてたからしばいといた」 「事前に面倒ごとの芽を詰んでくれてありがと」 「ああ、まあそんな噂が立ったらお前が面倒なことになるのは目に見えてたしよ……」 アキが聞き捨てならないといったふうにクロウに視線を向ける。クロウとて彼女との付き合いがそう短いわけではないから、わきまえるところはわきまえているのだ。嫉妬した女性ほど扱いに困るものもない。経験則である。 防衛戦からジャックが帰ってきて数日ぶりにメンバーが揃ったチーム・ファイブディーズの面々が誰からともなく切り出したのはやはりこの話題だった。十代はあの後受けた面接で受かったカフェテリアのバイトに出ていてここにはいないので、デュエルの様子なんかは必然当時そこに居合わせていた双子が解説することになる。龍亞が非常に大雑把な説明をする傍らで龍可がちょこちょこと補足を入れ、訂正をし、おおよその流れが掴めたところで今に至るわけだ。 「しっかしあいつ、マジでタダもんじゃなさそうだな……遊星がフルネームを名乗らせなかったのは正解だと思うぜ。噂を信じるわけじゃないが、本物の再来ってのもあながち有り得なくはなさそうだし」 「本当に過去から来たのかもしれないってそういうこと?」 「ああ。今時二代目決闘王を敬して子供の名に『十代』と名付けるのはそう珍しいことでもない。だがフルネームが丸々一致して、容姿も似通いクセの強いデッキを苦もなく操る……となると、非現実的だがそのセンを無視するわけにもいかないだろう」 「何しろ空から落ちてきたわけだしね……」 ブルーノは浜辺に漂着していたらしいが、十代の場合は空からの落下だ。あの時タイムリーにヘリコプターか何かがポッポタイム上空を飛びでもしていたのなら話は別だがまずそんなことはないだろう。 ファンタジーみたいな、不思議な人だ。 空から落ちてきた青年は捉え所も掴み所もない、自由人である。子供っぽい所作も多いが時折驚くほど老成した仕草を見せる。デュエルは滅茶苦茶に強かった。腕っぷしはわからない。精霊と特殊な結び付きを持っている。数え出すと際限がない。 「そう……精霊よ」 龍可が何か思い出したらしくはっとした顔をする。 「私、あの時確かに見たわ。あのね皆、十代がデュエルに使ったのはプロキシの安っぽいコピーだって話、したでしょう?」 「ああ。それと精霊に何の関係が?」 「デュエルモンスターズの精霊ってね、全てのカードに宿っているわけじゃないの。持ち主に大切にされたカードには宿るけど、その逆はないのよ。放置されたカードは何も応えてくれないか怨霊化して人に害を及ぼすかのどっちかなんだって。後者は滅多にないけど……とにかく、思い入れのないものに精霊は来てくれないの。たった今刷ったばっかりのプリンタコピーの紙っぺらなんてものには尚更よ。でも、十代が触ったプロキシには確かに精霊がいたわ。十代が『頼むぜ』って言った時にシャイニング・フレア・ウィングマンの精霊がコピーの上で十代に会釈してた。……ディスクも何も使ってなかったからソリッド・ヴィジョンは関係ないと思う」 「つまり十代が触れたからコピーに精霊が宿ったということか」 「うん。そうとしか思えないもの」 人指し指を顎に添えて憶測だけどね、と結んだ。十代本人はとても面白い人だし、人柄も悪くない。ただブルーノ同様やや常識が欠落しているためにちょっとばかり浮き易い。そんな状態でバイトなどして大丈夫なのだろうかと少々思わなくもなかったが居付く条件として十代の側が提示してきていることもあるし、断るのも野暮だ。第一何と言って止めればいいのか。「危ないから」なんて言っても大爆笑されて終わりだろう。何せデュエルは絶句する程強い。 危なっかしい人だが、それと同時に何故か無条件の信頼を置けるようなそんな人だった。出会ってまだ一月経っていないがその見解に関してはチームの全員が一致している。 「でも、十代にそんなに色々噂がたってるなんて僕知らなかったなあ」 ブルーノが依然、カチャカチャと部品を弄りながらのんびりと呟く。ポッポタイムのスペースには限りがあり、結局記憶喪失者同士でルームシェアをすることで落ち着いたため、自然とこの建物の中で最も多く十代と時を過ごしていることになるのはかのブルーノだった。何しろ十代は基本寝る時と食事を取る時以外はポッポタイムにいないのだ。双子のお守りをしているのか双子にお守りをされているのか、物珍しそうにあちこちをきょろきょろ見回してシティ観光をしていたりバイトに勤しんでいたり、アキと連れだって食材の買い込みに行ったりと彼は随分精力的に種々の活動を行っている。 ポッポタイムにいてもごろんと転がっていることは少なく、ジャックを上手いことおだてて現在の環境や流行りの戦術をあれこれ解説させていたり、アキやクロウを手伝って食事を作ったりする姿がよく見受けられた。記憶を失う前から台所に立つところが多かったのだろう、料理はなかなかの腕前で双子など「なんかよくわかんないけど、家族の味って感じがする」と絶賛していた。記憶を失っても体に染み付いたものはなくならないというから、案外誰かのために料理を作っている人だったのかもしれない。草食系男子ってやつなのだろうか。 「一緒に部屋にいても十代はいつも寝てるし、そんな話聞いたことなかったし。バイト先で女の子と間違われてナンパとかされてたら、ちょっと洒落にならないよね」 火のないところに煙は立たないって言うし、と軽い冗談みたいな口調でブルーノが言う。美女とされていた噂を示しているのだろう。確かに十代は中性的な整った顔立ちをしているから、服装如何によっては女性に化けることも可能かもしれない。 しかし。 「流石にそれは問題ないでしょ。男物の制服着てるってこの前俺と龍可に楽しそうに話してくれたよ。写真見せてもらったけど普通にイケメンだったし」 「遊星が無理矢理携帯持たせたし、心配ないわよ。ちゃんと毎晩帰る前に定時連絡入れてるって」 「え、そうなの? 僕家電当番だけどそんな電話取ったことないよ」 ブルーノが不思議そうな顔をする。双子は言われて初めて、そういえばポッポタイムに電話をかけた時に「もしもし」と応対するのが九割以上ブルーノであったという事実に思いあたった。ごく稀に遊星やクロウが出ることもあるが、きっとその時はブルーノが外出中なのだろう。 「ブルーノが取った覚えがないのは当然だろう。十代さんには俺の携帯にメールをくれないかと頼んである。時間の記録になるし電話より確実性が高い」 「……遊星が?」 「連体でパック契約したから俺宛てだとメール代が無料なんだ。……そんな目で見ないでくれアキ。自分でも過保護気味かもしれないとは薄々思っている」 じっとりとした目付きを向けてきたアキを自らの胸中に抱き寄せ頭を撫でてやって遊星が溜め息混じりに言う。アキはまんざらでもなさそうな顔で「男に嫉妬するほど私だって狭量じゃないわ」と嘯いた。ついさっきまでそんなふうじゃなかったくせに、と場の誰もが思うが怖いので口には出さない。 「でも、そういえばまだ今日は連絡ないよね」 「まだ七時だろ。シフト中なんじゃないのか」 「うーん、どうだろ。十代のシフトって結構不規則っていうか、合間を縫って人手の薄いところにねじ込んでるみたいでバラバラなんだよね。この前三時に来たらいなかったよ。逆に、夜最後のシフトの時もあるって言ってたし」 「あ、今日十代が仕事に行って来るって僕に声かけたの、お昼ぐらいだったよ確か。僕の分もご飯作り置いていってくれたもん」 「……昼?」 「うん。お昼」 何も変なところはなかったけど、と付け加えてようやく工具を手から放す。ブルーノがそうして見上げた遊星の顔はものすごく心配そうな妙な表情に染まっていた。娘を心配する父親というよりは、仏陀が新しいことをし出した時の慌てた信徒だったりイエス・キリストが不可解なことを言い出した時の十二使徒の表情に近いのではないかと、そんなものを見たことはないけれどそう思った。 多分干渉したいのだがそれを阻み止まらせようとする自分の中の何かに諭されている真っ最中なのだ。遊星は別に十代の保護者ではないのだから。 |