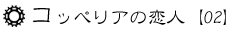生温かい粒に濡れていると、ふっと意識が薄らいでいくような錯覚を覚えた。ジェットバス完備のバスルームはポッポタイムの風呂よりいくらも金がかかっていそうな造りで、インダストリアルイリュージョン社の給料はやっぱり相当良いのだろうかと邪推をする。ミルク色のタイルを伝って排水溝へ流れていく水、室内に満ちる蒸気。ゆるい人肌の温度が緊張を溶かしていく。
こういうゆったりしたバスタイムは、ポッポタイムではなかなかないものだ。何しろあそこは男五人世帯で、風呂はさっさと入らないとつっかえる。洗い場もさして広くないし湯槽に湯を張ることもない。水道代が馬鹿にならないので夏は張らない、という取り決めが遊星達の中にはあるらしい。 ジャックがプロで稼いでいる資金はそれなりにあるが、当のジャックが贅沢志向なので生活費にはそう回ってこない。遊星も実家は裕福だが親馬鹿の父から一切の援助を断り何でも屋の収入だけで家計の足しにしている。食費もかかるし、従って優雅な生活など望むべくもないのである。別にしたいわけではないからいいのだけど。 寝室やリビング、キッチンもそうだったがバスルームも全体的に統一されたインテリアになっていて、ヨハンはセンスのいい奴なんだろうなと少し羨んだ。十代のセンスは基本人並、たまに並以下、だと思う。そう思うと無性に切なくなってきて生まれた土地とか育った環境の差かもしれないと自分を慰めた。ごちゃごちゃした都市の団地育ちだ。ハイセンスを求められたって困る。 「ああも、湯槽つかってやる」 「どうぞどうぞ。シャンプーとコンディショナー、どっちがどっちかわかるか?」 「まだ使ってな……ってなんで入ってきてるんだよ!」 「いや俺も昨日風呂入ってないから」 「そういう問題じゃなくて!」 背後からするりと腕が伸びてきたことに面食らって思わず声を張り上げた。屈む姿勢を取るものだから胸板のあたりが背中と擦れてかなわない。脇を抜けていく二の腕は顔の印象よりも随分と逞しく鍛えられていて男らしかった。ついつい自らの二の腕と見比べて若干へこむ。それなりに体力には自信があるのだが、遊星やヨハンに比べるとまるで大したことがない。 第一ヨハンは、かわいい顔しているくせになんなのだこの体格は。ブルーノと同じタイプか。体付きのバランスに対して顔が童顔すぎるのだ。着ている服の印象で誤魔化されがちだが、絶対に、アンバランスだと思う。遺伝子の神秘だ。 とりあえずなおもはばかることなく十代に自らを密着させている無遠慮な男にきっと睨みながら向き直る。ヨハンは十代の睨み顔を見ると手を添えてくすくすと笑った。無性に腹立たしい。 「十代、かわいい」 「男にかわいいって言うのは賛辞にはならない。取り敢えずそこどけ、近いんだよ距離!」 「えー?」 「えーじゃない。暑苦しい。汗臭い。ヘンだ、そんなの」 「昨日の夜は俺の胸に顔を埋めて寝てたのに、汗臭いはないだろ。だとしたらいくらかはお前の汗だ」 にっこりと告げられる。言葉の内には、僅かな悪意が含まれていた。ヨハンの言葉を反芻して、温まってきた体が精神的な問題でさっと冷めていくのを感じる。男の胸に、顔を埋めて、一晩寝こけていた? 「俺は人肌恋しかったからいいけど」 「俺がよくない。精神衛生上非常によろしくない」 「でもよく眠ってた。結果オーライってことで手を打ってくれ」 結果オーライというか、十代は割合どこにいてもよく眠れる性質だから体のいい枕代わりにされていたに過ぎないのだが。男に胸枕にされてむしろお前の方は何も感じないのか、そう思ったが問うまでには至らなかった。嫌な顔一つしないでヨハンがシャンプーの液を手に取り、おもむろに十代の髪にそれを擦り付けてきたからだ。 ぬるりとした冷たい液が他人の手で頭に擦り込まれていく。抵抗する暇もなく、わしゃわしゃと頭皮から毛髪から何から何までを擦られ、泡立てられ、頭部がいい匂いの泡に塗れていく。 「な、に、し、て、ん、だ!」 「親切心をちょっと。髪の毛もうちょっと気を遣いなさい、パサパサさせておくのは感心しない」 「風呂はほぼ毎日入ってる!」 「コンディショナーしてないんだろ。十代は髪の艶が綺麗なんだからそれを殺してしまうのはもったいないよ」 お前は俺の母親か何かか! とシャンプーが目に入らないように堅く目を閉じて喚くと曖昧に言葉を濁される。「ま、母親じゃないことは確かだが」、そういうふうに苦笑いの声で言って十代の頬に触れた。目を閉じているから何も見えずにただ他人の皮膚が自らの皮膚に触れる感触がダイレクトに感覚に響いてくる。柔らかい皮膚だった。優しい手のひらの感触が、悔しい。 コックを捻るキュッという軽い音がして、一旦止められていたシャワーの雨がノズルからまた降り注いでくる。丁寧に洗い流されてそのままコンディショナーを付けられた。抵抗するのは、阿呆らしくなってもう止めた。目に染みたら嫌だし、向こうがやりたがっているのだから、もう好きにさせておけばいい。楽ちんだし。 「大人しくしていると、人形みたいだ」 黙っていると、不意にヨハンが漏らした。 「それは聞き捨てならないな、どういうことだ」 「文字通りにね。十代に限ったことじゃない、この世界の人間はどこか人形のようだ。確固たる意志があるようでいてその実ふわふわしてる。強靱さが足りない気がする。牙をもがれた獣のような――誰かが夢見ている物語のロールプレイ・キャラクターのような。夢から醒めた夢、とでも言うのかな。世界はあまりにも幸せすぎるんじゃないかな、って」 「……何言ってるのかわかんねえけど、仕事疲れなら病院行った方がいいぞ」 「うん、それは大丈夫」 おしまい、と最後にもう一度髪を流してやってからヨハンは軽く十代の肩を叩く。つるつるした素肌は相変わらず若々しく、瑞々しい。アンモナイトを模したあの男に報告したら溜め息を吐かれそうだなと思った。 「湯槽、入ったら。そう言うと思って起きてすぐにスイッチ入れておいたからもうわいてるよ」 「ああ、わり。お前は入らないのか」 「うん。うちの祖国じゃ入浴の習慣があまりないんだ。十代がどうしても密着したいっていうのなら検討するけど」 「じゃ、出てなんか冷たいの用意しとけ」 「他人をこき使うことへの抵抗のなさはいっそ清々しいくらいだな。風呂出たら携帯見た方がいい。遊星君から大量に着信が入ってるから」 言い捨ててヨハンは十代が言葉を発する前に風呂場から出ていく。慌てておい、と声を投げるが聞き入れる素振りもない。本当に聞こえてないのかもしれない。ヨハンはぐいぐい引っ張っていく上にマイペースだ。こっちの都合なんかお構いなしに十代を連れていく――どこか遠いところへ、ひょっとすると本人も意図しないままに。 それにしても、と湯槽で手足をぱしゃぱしゃと遊ばせながら十代は考えた。遊星から着信が山程入るのは仕方がないことだ。だがそれなら携帯がうるさく何度も鳴っていたはずだし、着信音に気付かない程自分が鈍感であった覚えはない。加えて、何故あの男はその相手が遊星だとわかるのだろう。どうして遊星のことを親し気に「遊星君」などと呼ぶのだろう。 わからないことばっかりだ。 「そりゃ、一度目の着信で目を覚ました俺がサイレントモードに変更しておいたからさ。俺はしつこい着信音に眠りを妨げられるのが嫌いだし、十代はべろんべろんで爆睡だし、人肌恋しかったし」 「いや待て。色々と言いたいことはあるが、待て。俺携帯にはパスコードロック掛けてたはずなんだけどなんでお前がそれを解除してモード変更を出来るんだ」 「四桁のパスワードに誕生日を設定するのは懸命な判断じゃない。知人だったら開けられるってことだ」 「……なんで知ってるんだよ」 冷たいもの、としてレモネードを用意していたヨハンの手からそれを奪い取るなり詰問するとヨハンはけろりとした顔で答えた。この男との間柄が果たして知人と呼べるほどのものなのだろうかという疑問がまずある。昨日会ったばかりで、家に連れ込まれる形になってしまってはいるが別に親しくもなんともない相手のはずだ。今日以降何かのきっかけがあって交友が深まる可能性もゼロではないが、少なくとも今日までは単なる他人である。ましてや教えもしない誕生日など知られる理由がない。 「なんでも何も、パスワード、俺と同じなんだよ。ゼロ・ハチ・サン・イチ。一年で一番に好きな日だ。次が自分の誕生日」 「……考えるだけ馬鹿を見るような気がしてきた」 「そりゃ結構なことで」 自分のグラスにもレモネードをとぽとぽと注いで一息にあおる。本当に時折、見惚れるぐらいに美しい所作をする男だ。気にくわない。 開いた携帯の着信履歴はびっしりと遊星で埋まっていて、更にはメールも何件か入っていた。一件目、「すみません。今、何をしているんですか?」午後十一時。二件目、「どこにいるのか連絡をください」午前一時。三件目、「無事でしたら返信をお願いします」午前四時。段々と心配をエスカレートさせていく遊星の焦燥した顔が目に見えるようだった。この男の徹夜はいつものことだが、今日はそういうことでなく寝不足になってしまっているに違いない。うっかりで連絡を入れ忘れていたのだ。非常に悪いことをしたと思う。 ヨハンがレモネードの瓶を冷蔵庫にしまいに行くのを横目で見ながらコールをすると、コール音が三度も鳴らない内に遊星の声が電話から聞こえてきた。 『――十代さん!』 無事ですか、怪我は、何か不快なことは、そう捲したてるように続いた声を遮って「落ち着け」と返してやる。すると十代の声が聞こえてきたことへの安堵の息がスピーカー越しに聞こえてきた。 「悪かった、連絡もなしに外泊して。お前が心配しているようなことは何もないからとにかく深呼吸でもして落ち着いてくれないか」 『はい。はい、すみません、取り乱して』 「謝らないでいい。俺が全面的に悪いんだし……ともかく今日の昼ぐらいには帰るよ」 『いえ、十代さんが無事なら俺はいいんです。あの、ところでつかぬことを聞きますが』 「うん」 『外泊ってどこに』 「俺んち」 電話の向こうで遊星が声を引きつらせる音が聞こえてくる。十代はぽかんと口を開けて乱入者の顔を見た。相変わらずすました顔で、……いやそれは嘘だ。口端でニヤニヤ笑っている。純情な青年を弄ぶ嫌な大人の顔だと思った。張っ倒してやりたい。 第三者の、それも男の声が突然聞こえてきたことに動揺していた遊星が深呼吸を数度繰り返しているのがわかる。小さく「遊星どうしたの?!」という声も聞こえてきた。これは多分ブルーノだ。 ブルーノが驚いた様子で遊星の背を擦っている光景が思い浮かんだ。遊星が今浮かべている表情をあれこれ想定していると何かいたたまれない気持ちになる。何か欲しいものを聞いて買って帰ってやろうか。それともヨハンに奢らせるか。そんな思考を巡らせる。 しばらくすると再び遊星の声が聞こえてきた。どことなく震えていて、信じたくない現実を突き付けられた子供のようだった。 『……誰ですか、あなたは』 探りを入れているのかぎこちない敬語だ。ヨハンは十代の手から掠め取った携帯を顔に当てて、素晴らしい笑顔で「やあ、久しぶり遊星君」とにこにこしている。遊星が久しぶりという単語に困惑してあの、と聞き返した。心当たりがないんですがという律儀な言葉に十代は溜め息を吐く。それは多分ミスリードだ。 「君のお父さんにはいつもお世話になっています。俺はインダストリアルイリュージョン社のヨハン・アンデルセン。十代は昨日飲み屋で潰れたので家に連れて帰りました。……動揺しない、別にやましいことは何もないし」 『動揺してません。アンデルセン博士が一体十代さんとどのような接点を持っているのかは知りませんが、父に関しては、いつもこちらがご迷惑を』 「いや、君の父さんに迷惑をかけられたことはないから大丈夫だよ。彼は飛び抜けて面白い奴だと好ましく思っているし」 『はあ』 「それに十代とは酒を飲んで寝て風呂に入っただけだから特に心配しなくていい」 「なんだその言い方」 あからさまな含みと牽制を含んだ物言いに疑わしげな顔付きになる。大体「寝た」という一言で済ませるのもどうなのか。口ぶりが誤解を招きかねないというか、むしろヨハンは誤解を招かせようとしているふうですらある。 いや、男同士だから、遊星にはその手の発想には至って欲しくないが。 十代が変な顔をしていることに気付いたヨハンは、口端のにやにや笑いは止めないままで器用にぶすくれているのだという感情を表現して十代の腰に手を回した。何が起きたのかと認識するよりも早く人肌の感触を皮膚が感じる。途端に猛烈な閉塞感に教われてもがき、息が自由になって初めて唇を塞がれたのだということに思い当たった。 顔が熱い。真っ赤なんだろうなと思う。今鏡を覗き込んだらきっと茹で蟹も真っ青になってしまうぐらいに赤い顔をしているのだ。 「――ヨハン!!」 「何?」 「おまえ……!」 「うん、口にパン屑付いてたから」 だから取った。いけしゃあしゃあとそう言ってはばからない口が憎い。その唇が今さっき自分の唇に触れていたという事実がたまらなく恥ずかしい。十代の唇は未だ湿っていた。ヨハンの温度に温もっている。 「奥さんいるんだろ、馬鹿」 「うん。でもうちの奥さんは十代にキスしても絶対怒らないから大丈夫」 「ばか、そういうんじゃなくてよ、お前は誰にでもこういうことをするのか」 「誰にもってわけじゃない。当たり前じゃないかそんなの」 だって俺は十代が好きだから、と厚顔無恥にも続く。殆ど初対面で一晩一緒だっただけの男に「好き」とはこいつは一体どういう神経をしているのだろう。そういう手の人種なのか、とも勘繰るが別段そういうふうには思えない。 ヨハンは優しい人間で、懐が広くて、なんでも受け入れてしまうような馬鹿で、だからきっと十代のことも、最後まであいしてくれる。見捨てないでくれる。ずっと永遠に味方でいてくれる。根拠もなく唐突にそう思った。失われてしまった過去の記憶が訴えてきているみたいで少しだけ頭が痛い。じくじくする。 「……どういう、つもりだよ。エイプリルフールは大分先だと思うけど」 「どういうも何も、だって好きなんだ。一目見た時に『いい友達になれる』って思った。……嘘じゃ、ないぜ。だからさ……」 今度は遊星にもはっきり聞こえるように「好き」と繰り返す。 電話の向こうで、ガタン、という音がした。 「君が遊星君に懐いているのを見ていると、なんだか面白くない気分になるもんだから」 なんでもないように、それが当たり前のことであるように、胸を張ってけろりと言う。だが嫌だとは思わなかった。思えなかった。ヨハンの関心を一心に受けているような気すらして、心臓が少しだけ鳴った。 ◇◆◇◆◇ 『何をやっているんですかあなたは』 一言目に溜め息混じりのお小言が飛んできた。だって、と口を尖らせると馬鹿ですか、とオブラートなしに直球で言われる。ぐさりときてコーヒーを零しかけた。彼には配慮が足りないと思う。かの英雄をコピーした結果というより、意図的なものに思えるから性質が悪い。 『記憶を失っていることに関しては確かに不可抗力です。しかし接触をしたのなら手早く記憶を元に戻してしまえば良いでしょう。それが何故ああなるのか私には理解しかねる』 「青春の甘酸っぱい思い出の追想ってやつさ。君には情緒が足りないぜゾーン」 『時間がない、というのは理解頂けているでしょうね』 弁明の余地もない。ヨハンはからかう方向には持って行けないなと判断してそれ以上の反論を止めた。ゾーンは正史の英雄不動遊星を人格や思考パターンまでコピーしているために考えがところどころお堅いというか真面目すぎるきらいがある。そんな彼をからかって自分のペースに持ち込めるのは、ヨハンの知るところでは十代ぐらいのものだ。十代はゾーンのコピー元である遊星その人も自分のペースに引き摺り込んで頷かせてしまうような手合いだから、これは致し方ないのだと思う。ゾーンとしても不可抗力のようなものなのだろう。今回の十代の記憶喪失みたいに。 「わかってる、わかってるさ。時間がないからこうして俺達は過去へ来たわけだ。正真正銘イリアステルの人間として歴史修正をしにな。思わぬ誤算がいくらかあるが」 『ええ、まさかあなた方がはぐれてしまうとは思いませんでした。記憶喪失の可能性はゼロではなかったので危惧してはいたのですが……それも本来ならば限りなく低い可能性の、起こり得ないことでしたから。今となっては机上の確率論に過ぎませんがね』 「俺だって好きではぐれたわけじゃないんだ。いやまさかさ、情けない話だけどくしゃみを抑えるために手を離した隙になんて思いもよらなくて」 ゾーンの手引きで二人揃って過去へと飛び出したヨハンと十代は、手を繋いで時空の波にもまれていた。とにかく密着するなりして体を繋いでいないとあっという間に座標を見失ってしまうからだ。それには十分留意していたのだが、ふとしたアクシデントではぐれてこんなことになってしまった。 結果、ヨハンは予定通り過去に到着しイリアステルの持つあの手この手のコネで現在の環境を手に入れることに成功したが十代はまず予定から五年遅れ、座標も違えてしまいご覧の有様だ。それでも不動遊星のすぐ傍に出現出来たことに関してはもう運命の悪戯か或いは執念とでも他に表わす言葉がない。 「それでさ、十代の居場所を掴んだと思ったらあいつ記憶喪失で遊星と仲良くなってて、一つ屋根の下だってさ。まあ遊星には彼女がいるわけだけど、あの入れ込みようは俺の嫉妬心を煽るには十分だったってわけだ」 『並行世界の影響を受けた刷り込みに近いものですよ。世界関係が歪な故に彼は遊城十代へああいう態度を取らなければならないと思い込んでいる。それだけに過ぎません。確かに不動遊星は遊城十代を尊敬していましたが……』 「それに俺じゃなくて遊星のそばに落ちて来たってのもある。俺だって十代をお姫様抱っこで受け止めるぐらい出来るのにさ」 『あなたは今までに散々やってきたでしょうに。遊城十代が単に仕事に忠実だっただけではないですか』 「複雑な夫心ってやつ。わからないかなあ」 今回のメインターゲットは異変の中心にいるチーム・ファイブディーズだ。当然、チーム・ファイブディーズの面子の中で一番重要なのは不動遊星となる。だから十代が遊星に接触し、上手いこと取り入って仲間として受け入れられた事実はイリアステルとして考えればまたとない好機であるわけなのだが、それを理解していてもヨハンはどこかで納得出来ないでいる。まだまだ嫉妬出来るぐらいの若さが自分の中には残されていたらしい。びっくりだ。 「遊星のことは嫌いじゃないし、むしろ好きなんだけどな。いい子だよ、彼は。家族と仲間のことを愛している。それはきっと彼が不動遊星である限りどこの世界でも変わらないことなんだろう。十代も、仲間として定義されてそういうふうに大事にされてて、それだけなんだろうとは思うんだけど」 『多少はそれ以外のものもあるかもしれませんがね。正史の不動遊星は遊城十代が母だと知らされていましたから。ただこれだけは断言しますが、彼が遊城十代に対してやましい思いを抱くことはありませんよ。あなたとは違います、ヨハン・アンデルセン』 「どういう意味だいそれは」 『正史の彼もまた遊城十代に惹かれ敬していましたが、しかしそれだけだ。遊城十代を許容し許容されるのはあなただけです。ですから出来るだけ手早くことを進めていただきたい』 「残念だが、君の希望に添うのは難しいなあ。ロマンが足りないし、何より俺はこの千載一遇のチャンスを逃す気はない。――十代と俺が、もう一度恋をすることが出来るんだぜ。しかもゼロからだ」 その言葉にゾーンが遠慮のない嘆息をわざとらしく寄越してくる。しかし彼はそれを咎めることなく『本当に仕方のない人達ですね、あなた方は』と漏らした。自然とヨハンの頬も緩む。依頼主の公認を取り付けられたわけだ。 「悪いな。恋したいお年頃なんだよ、俺は」 『とても妻子持ちの齢数百歳を数えようかという人間の言葉とは思えませんね。恋をしたからあなたは遊城十代と連れ添っているわけではないのですか』 「うん。恋、はしたことないかもしれない。恋を自覚する暇がなかった。俺達はきっと出会った時から愛をしていた。恋愛はしていたかもしれないけど」 まだ武藤遊戯が健在だったあの時代に、デュエルアカデミア本校で出会った時のことを思い出す。もし二人で恋をした瞬間があるとするのならばきっとそれは出会って握手を交わすまでのほんの数分に満たない時間のことなのだ。デュエルをして、再び隣り合って歩いた時にはもう心が完全に通じ合っていた。完璧なツーカーだった。恋はとっくに終わって、二人が抱いているものは愛になっていた。初めは友愛と見分けが付かなかったけど、そういうことなのだ。 アカデミアを出ていくらか経った頃には、それはもう間違えようのないものになってしまっていてそれから随分と長い月日が経つ。 「今の十代は人形の一体だ。記憶を失い、チーム・ファイブディーズというぬるま湯に浸かって過ごしている。俺はねゾーン、そんなあいつの姿もかわいいなって思うわけ。――コッペリアに恋するフランツ青年の気分さ。まあこの場合スワニルダも十代なんで、ちょっとややこしいわけだが」 『それでは、コッペリウス博士は誰なのです?』 「君ではないね。世界からゼロ・リバースを消し去ろうと身の程知らずにも願った誰かだろうさ」 今はともかくコッペリアと仲良くなることを考えないと。それを最後にゾーンとの通信を切ってヨハンは携帯のアドレス帳をスクロールした。や行に「遊城十代」の名が燦然と輝いている。それは十代が寝ている間にこっそりと交換しておいた、十代の携帯のアドレスデータだった。 ◇◆◇◆◇ 「……ただいま」 「あ、お帰り十代。ねえ遊星がすっごい落ち込んでるんだけどさ、十代なんか知らない?」 双子の片割れが帰宅した十代に気が付いて、二人でぱたぱたとこちらに駆けてくる。十代は「しってる」と疲労の滲み出た声音でぼそりと答えた。ぐったりだ。 「ブルーノが修羅場だとかなんとか言ってたけど。修羅場ってどういうこと?」 「うん、俺がな、外泊だったろ今日」 「あ、そうなんだ」 「そうなんだ実は。色々あってさ。朝方遊星に電話したらすっげえ心配されてて、それなのにヨハンの奴妙な言い方してさあ。さあ誤解しろって言わんばかりの。しかもさ……」 そこまで言ってはっと口元を抑える。朝方の出来事を思い出すとまた無性に恥ずかしくなってしまって、とてもじゃないが続きをこの子供達に言う気にはなれなかった。よもや男に唇を合わせられて真っ赤になっていたなんて、恐らく遊星はそれに対して複雑な感情を抱いているのだろうなんて、言えるはずもない。 その上そのことに特に嫌悪を感じていないなどとはとてもとても。 「――ヨハンの奴が馬鹿やらかしたんだ。それだけ!」 いたたまれなくなって、適当に叫んで割り当てられた自室に駆け込む。ばたんという音と共に勢いよく扉が開閉してすぐに十代の姿は双子には見えなくなった。 「……行っちゃったね」 「……どうしたんだろ」 双子がお互いに顔を見合わせて小首を傾げる。何やら口走っていたが龍亞も龍可も「ヨハン」とかいう人物のことはさっぱり知らないから、結局よくわからないままだ。その人が一体何をやらかしたら遊星があそこまで落ち込むのか。上手く想像が付かない。 「うーん、でも龍亞、私思うんだけど」 「うん。何?」 「十代が『ヨハン』って名前を呼ぶのはすごく自然な気がするわ。しっくりくる。アキさんが遊星を呼んでる時とか、ママがパパのことを呼び止めた時みたいなそんな感じ」 龍可が不思議そうに言った。 |