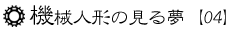「ネオスでダイレクトアタック。俺の勝ちだ」
「参りました!」 「うむ精進せえよ、もっともっと強くなって、プロリーグまで来いな!」 少年と握手を交わして、十代はひらひらと観客席に手を振りながらステージ裏に歩いていった。バックヤードには十代の師匠である遊戯が立って、にこにこしている。お疲れと労いの言葉を貰うと十代は破顔した。 「はい! ちっちゃい子達とデュエル出来て俺も楽しかったです。あの中から将来俺の後輩やライバルになる子達が出てくるのかなー!」 「うんうん。ボクもきみにハネクリボーを渡した時はそんな気持ちだったよ。あの頃のきみは危なっかしかったねぇ」 『遅刻遅刻、と騒ぎながら往来を走っていたな。アカデミアに受かったのは正直奇跡的なことだったぞ』 「ひ、酷いですよ師匠。そりゃ確かに筆記は壊滅的だったけど」 『受験者最低点だ。合格ラインより遥か下だったな』 「うぐ、でも俺ちゃんと卒業してプロになりましたよ!」 「ま、デュエルは理屈と理論だけじゃ上手く行かないからね」 『ああ。そこにかけてはお前は圧倒的なまでに天才だ。右に出るものはそうそういないだろう』 目付きの鋭い方の遊戯が霊体の手のひらで十代の頭を撫でる仕草をする。実際に触れてはいないのだが十代は目を細めて幼稚園児のように嬉しそうな顔をした。十代にとって、この二人の遊戯は師匠であると同時に兄と慕う相手だ。だから遊戯もまた十代のことを弟のように思っていた。時折、子犬よろしく思えることもあったが何にせよ可愛く大事に思っていることには違いない。 その大切な愛弟子が、子犬の目をして「もう一人のボク」に師匠、師匠と名を呼ぶ姿はかつて魔導士見習いの少女がお師匠サマ、と目をきらきらさせて次の術の伝受をせがんでいた時のそんな様子を喚起させる。微笑ましくてくすりと笑むと幽体の彼が耳ざとく振り返った。 『どうした、相棒』 「うん。ブラック・マジシャンとブラック・マジシャン・ガールの遣り取りに似てると思ってね」 『言われてみれば、そんな気もするな』 手を顎に当てて頷く。十代は「そうなんですか、師匠?」と小首を傾げた。 十代は武藤遊戯のことを「遊戯さん」、もう一人の遊戯――名もなきファラオのことを「師匠」というふうに呼び分けている。「だって、『もう一人の遊戯さん』じゃあなんだか長くて呼び辛いしまだるっこしいじゃないですか」とは彼の言で、師と呼ばれた方も『フフッ、悪い気はしないな』と乗り気だったのでそういうことになったのだ。 かつてラフェールやドーマの者達に「名もなきファラオ」と呼ばれた通り、もう一人の遊戯には名がない。名無しの死者。言い換えれば亡者だ。武藤遊戯という人間の体を間借りしてこの世界に存在している。 今は遊戯自身の賛同を得て失われた王の名を求める旅に出ている最中だ。とはいっても、もうその旅も随分と長く続いていて、だというのに名前が見付かる兆しはないのだった。かつてファラオであったらしい現決闘王の魂は名を持たぬまま放浪を続けている。……無様にも。 「さて、ペガサスの依頼はこれで達成出来たし一度宿に帰ろうか。もう夕方だしね。十代くんはそろそろお腹が減ってきて仕方がないんじゃないかな?」 「うーん、それは山々なんですけど。俺ちょっと約束があって」 『ほお? 珍しいな。食事よりも優先したい用事か。プロのマッチにも食い物を頬張りながら来るのにな』 「師匠! 恥ずかしいですからそういうことは言わないでくださいよぉ!」 『イタリアだぞ。日本語を完璧に理解出来る人間は少ない。お前のファン達にバレることはないさ』 しれっとして言う。十代はもー、だとかかなわねー、だとかぼやいて腕組みをし弟子をにやにや見ている遊戯を上目に見上げた。時折意地の悪い姿勢を見せるのがこの師の困り所であり、しかし愛すべきところであると十代は考えている。彼のこの意地悪さというのはおしなべて親愛ゆえの表現だった。何とも思っていない相手にそういうことはしないのだ。だから少し嬉しいし、こそばゆい。 ただ、同じようにもう一人の遊戯に一貫して意地悪い態度を取られている海馬瀬人にも親愛――信頼があるのだろうということは、思っても口に出さないことにしている。海馬は遊戯と「お友達」扱いされるのが大嫌いなのだ。彼曰く遊戯は宿敵であり、討ち倒すべき相手ではあるが仲間ではないらしい。 『そんな心配より、時間は大丈夫なのか十代。待ち合わせなんだろう』 「うーん、大丈夫だと思うんですけど……あいつ方向音痴だからいつも遅れてくるし。ルーズな俺に溜め息吐かないでくれる唯一の同類です」 「……それはそれでどうなんだい?」 「だから俺、あいつのこと好きなんだよな」 「ふーん。何が理由で俺が好きだって?」 突然背後から伸びてきた手がひょいと十代の上着を掴んだ。声に驚いて振り向くと、そこには馴染んだ悪友の姿がある。方向音痴の悪友は目を細めて「なあ?」と繰り返した。十代はやや顔をひきつらせて、しどろもどろになりながらたどたどしく理由を述べる。 「……方向音痴で、俺とおんなじぐらいルーズだから……」 「奇遇だな。俺もお前のルーズさは嫌いじゃない」 ぱっ、と十代から手を放してそいつはにこりと綺麗な笑みを浮かべ遊戯に会釈する。十代は自由になった首や肩を一回り回転させてそいつに向き直り、アイコンタクトをして笑いかけた。 「こんなところで会えるなんて思ってなかった。『方向音痴のヨハン』」 「その方向音痴のおかげで、待ち合わせ場所に辿り着くより先に十代の居場所に辿り着いたってわけ。……あとさあ十代、よりによって遊戯さんの前でそういう説明の仕方するなよ! 泣きたくなってくるだろ!」 「えー……」 「えー、じゃない」 撤回を求める、と『宝玉獣のヨハン』はいつになく真剣な顔で言った。 ◇◆◇◆◇ 「きみのことは知ってるよ、ヨハンくん。十代くん一番の悪友ってきみのことだったんだねえ」 『話に聞いていたより、随分と真面目そうな男じゃないか。うちの弟子が迷惑を掛けていないか?』 「……どういう話をしてたんだよ十代」 「普通に親友なんだって説明してただけだぜ。遊戯さんも師匠もリーグとか興味ないから、そういうとこチェックしてないんだよなぁ」 成り行きで三人(もう一人の遊戯は精霊のような存在なので、遊戯と人格交代を行わなければ普通の人間には目視出来ない)で夕食を取ることになり、ヨハンの案内でレストランに入った。なんだか保護者同伴で遊びに来た中学生のように思えなくもなかったが気にしたら負けかなと思い努めることにする。フォークとナイフがかちゃかちゃと擦れ合う音やら遠くのテーブルから聞こえてくるワイングラスがぶつかり合う音、老若男女様々な人々の談笑、そういったもので店内は溢れ返っていた。 「エビフライねえの、ここ」 「エビフライは基本日本にしかない。あれは洋食じゃなくて正しくは洋風創作料理に近いんだ」 「へー。いっつも思うんだけどさ、なんでお前の方が日本人の俺よりも日本文化に明るいんだろうな」 「そりゃ俺が聞きたいよ」 ヨハンはフォークとナイフを手に持ったまま器用に肩を竦めてみせる。前に同じようなことを聞いた時は翔や剣山に「アニキが知らなさすぎるだけっす」「アニキにも問題があるドン」などと言われて腑に落ちない思いをしたものだ。十代に言わせればヨハンの方が明るすぎるのである。そこらの日本人よりもよっぽど日本に詳しいこの北欧人は、そういえば秀才の類だったなということを思い出した。 きっと十代がデュエルにのみ捧げてきた有り余る熱情を、彼は日本の言葉や文化を学ぶことにも向けていたのだろう。だがその努力があるからこそ今の親交があるわけで、それについてとやかく言う気も深く考える気も今はない。 十代はグラスに入った水を飲み干すと次の話題をヨハンに振った。 「そういやヨハン、待ち合わせをイタリアにしたのは確か理由があるんだったよな? たまたま俺がそこで仕事入ったからとか、そういうんじゃないんだろ」 「ペガサス会長から十代が仕事で来るって聞いたのが理由の一つなのは確かだけどな。……最近、このへんで事件が多発してるんだが、知らないか?」 「……初耳」 首を横に振るとヨハンはだと思った、と言って箇条書のメモを取り出した。「あんまり色んな人間に聞かれたい話じゃないから」と小声で補足が入る。なるほど、適度に騒がしい大衆食堂を場所に選んだのにはそういった意図も含まれていたのか。素直にメモを捲って几帳面な日本語を追い掛けていく。一通り目を通し終わって、十代は眉を顰めた。 「本当なんだな、これ」 「嘘吐いてどうするんだよ。会長から直々に頼まれて動いてるんだぜ、これでも」 ヨハンは世界に一つしかない「宝玉獣」デッキを受け取ったことをきっかけにペガサス会長との個人的な親交を深く持っていた。プロとしての彼のバックに付いているスポンサーはインダストリアルイリュージョン社傘下の会社だし、度々会長本人と歓談する機会もあるらしい。「父親みたいな人なんだ」と昔ヨハンは言っていた。ヨハンは孤児で本当の両親は生きているか死んでいるかもわからない。 不思議そうな顔をしている遊戯にメモ書を回して十代は左隣に座っているヨハンに向き直る。遊戯も、もう一人の遊戯とメモを覗き込んでざっと内容に目を通してから顔を上げた。 メモの内容はおおまかにはこうだ。最近、ヴェネツィアを中心にイタリア、いやヨーロッパ広域でカードが消滅する怪事件が相次いでいる。カードはある日突然、忽然とデッキから姿を消している。いくら探してもなくなったカードは出てこない。その上消失はデッキからに限らない。デュエル中の手札から消えたり、コレクションケースから消えることも珍しくないという。 なくなるカードの種類に統一性はなく、言語フォーマット・カードの種別・レアリティ、それら全てに関係なくカードは失われていった。一見したところでは無作為な選別に思えるために調査は難航しているらしい。 「レアリティに関係しないってことは、高額カード目当ての盗難じゃないってことか?」 「中には高額カードも含まれてるからカモフラージュかもしれない。断定は避けるべきだな。一応言っておくと、一番被害額が大きいのは『混沌幻魔アーミタイル』、三幻魔の融合先モンスターで一点物、会長が個人所蔵してたやつだ。逆に軽微だったのが『ジェリービーンズマン』、なんてことのないありふれたバニラモンスターカードだよ。パックでもよく出る量産品。とある少年の持ち物だ」 「アーミタイル? 幻魔の関係カード? 俺そんなの知らないぜ」 「お前が影丸会長と戦った時にはなかったんだってさ。ペガサス会長があの後……丁度俺が留学に来てた頃に、インスピレーションを受けて作ったらしい。会長本人もどうしてデザインしてしまったのかはよくわからなくて、ただ『作らなきゃ』っていう強い意志があったんだそうだ。……俺は、そのカードの作成時期がキモじゃないかなって思ってる。ジェリービーンズマンは確かに量産カードだけど、第何刷でいつパックに詰められて市場に出回ったかにはいくつかのタイミングがあるんだ。ジェリービーンズマンのカードは今までに何度か刷られてるが、その内の一回がアーミタイルの製作時期と被ってる」 「じゃ、他のも」 「恐らくは」 失われたカード達が生産された思われる時期はおおまかに言って、十代とヨハンがアカデミア本校に三年として在籍していた間の一年前後だ。とはいってもその期間に作られたカードを全て把握すること、ましてや管理しようなどということは不可能に近い。デュエルモンスターズのカード生産量は年間数億枚に及ぶ。一々カウントしていてはきりがないので、今のところは呼び掛けだけに留まっている。 「十代も気を付けろよ。デュエリストの実力に関係なくこの現象は起こってる。この前、エドのカードも消えたんだ。楽観視出来る状況じゃない」 「エドが?! あいつまでか!」 プロ仲間でアカデミア後輩のエド・フェニックスといえば相当な腕の持ち主だ。そうおめおめと消失盗難を許すような実力ではないし、性格でもない。 「遊戯さんは、カード、大丈夫ですか?」 「うん? ボクともう一人のボクのデッキには、基本的にそんなに新しいカードは入ってないからね。たまに入れ替えるけど禁止制限改訂に合わせて調整するぐらいだよ。もう一線を退いてるからメインデッキは問題ないかな」 『問題があるとしたら、あれか。十代用の手加減デッキ』 「でも汎用カードが多いから万が一なくなってもそこまで大変なことにはならないと思うよ」 「……て、手加減デッキって」 「しょうがないだろ! それでも勝てないんだよ!」 じゃあお前なら勝てるのかよ! と噛み付くとヨハンはとんでもないというふうにぶんぶんと首を横に振る。原初にして至高、頂点にして生ける伝説――この前のチャレンジマッチで司会が言っていた言葉を思い出した。多少飾りたてすぎなような気がしたが、しかしそのどこにも偽りはない。 十代は機嫌を損ねたらしく頬を膨らませてドリンクのストローに口を付ける。その様が子供っぽく、口に出しそうになったが止めた。その代わりに自分のメインディッシュを一口「食べるか」と差し出してやると、機嫌はあっさりと直った。 「そういえば師匠、どうでもいいっていえばどうでもいいんですけどちょっと気になったことがあって」 『なんだ』 「師匠ってエジプトのファラオなんですよね」 『そうらしいな』 実感はあまりないが、もう一人の遊戯がと頷く。 「ヨハンが日本語出来るのは勉強したからだけど、師匠が生きてたらしい時代にはそもそも日本語がないでしょう。やっぱり遊戯さんと会ってから勉強したんですか?」 『いや……』 もう一人の遊戯は首を捻って過去を回想する。武藤遊戯が千年パズルを完成させて自分は目覚めた。目覚めてしばらくの間は自らの存在がどういうものなのかをいま一つ理解しておらず、自分は武藤遊戯の第二人格か何かだろうかと考えていたような気がする。別人だと知らされたのはバトルシティ開催前の博物館でのことで、そこから少しずつ遊戯と自己の区分けが進んでいった。 あれから十年以上が経っているが、記憶の中のどこにも日本語以外の言語を思考に利用していた瞬間が存在しない。 『最初から、日本語で思考し喋っていた。恐らく宿主である相棒の思考回路や記憶を共有しているのだろう』 「え」 「なんかズルいよねえ、それ。ボクはヒエラティック、全然知らないのにね」 ヒエラティック? と目を白黒させていると横からヨハンが補足を入れてくる。古代エジプトで使われていた文字の一つで、神聖文字のヒエログリフを崩した神官が用いる文字らしい。それを更に崩したのが民用文字のデモティック。 「三幻神のカード・テキストは神官文字で書かれてるから俗にヒエラティック・テキストって呼ばれてるんだ。バトルシティの決勝トーナメントのビデオで遊戯さんが神を呼んだ時もマリクがラーを呼んだ時も何かブツブツ言ってただろ。あれがそれ。理論上亡国の言語であるヒエラティックの発音表記は確認しようがないからマニアの間でアレはオカルトか何かで処理されてるけど、ほんとにファラオの魂なのなら読めてもおかしくないよな」 「ああ、あのうにょうにょしたよくわかんない文字」 「見たことあるのか?」 「一回KCのカードデザイナーがラーの翼神竜のコピーカード作って、魔法カードで無理矢理縛り付けて召喚したのを相手取ったことあってさ。その時少しだけ見た。本物はなんか怖くて見せてくださいって頼めたことないなあ」 なんだそれ、といぶかしがられたので十代はかいつまんで説明してやる。デザイナーのフランツが自らの能力を認めたがらない、と一方的にライバル視していた隼人の故郷アカデミア島にまで逃走してきて、暴走を止めるためにデュエルをすることになった。「神縛りの塚」で召喚されたラーのコピーカードが泣いていることに気付き、最後は墓地に落ちたラーを蘇生して止めを刺した。その場で立ち合っていたペガサスにコントロールを奪ったラーのカードを返却する際にテキスト部分が見えたのである。 「ラーも、複製された上に無理矢理縛り付けられて嫌だったんだよなきっと。俺はそのヒエラティックとかよくわかんないけど、精霊が泣いてたのはわかった。やっぱ、遊戯さんとか、神のカードはちゃんと選ばれた人間が使わないと。少なくとも縛り付けて道具みたいに扱うのは駄目だよ」 「ふうん……」 ヨハンは曖昧に頷いた。三幻神のレプリカが研究用にI2本社に保管されているという話はペガサス本人から聞いたことがある。「たとえ写し身だとしても、非常に気難し屋のカードなのデース。遊戯ボーイや海馬ボーイ、一部のデュエリストを除けば残念ながら人間に扱える代物ではありまセーン。せいぜいが、研究用の資料止まりデース」……かつて神という強大な精霊をカードに閉じ込めたカードデザイナーはそう語っていた。 神のカードは本物だ。三幻神、三幻魔、それらには確かな人智を超えた力が宿っている。神の怒りはソリッド・ヴィジョンを飛び超えて現実に干渉を及ぼす。 「神のカードがこの騒動に巻き込まれたら大変なことになるだろうな」 「遊戯さんが持ってるのにそんなわけないじゃん」 「万が一、さ。そしたら、カードを盗んだりした奴は下手すると死にかねないんじゃないかって」 墓荒らしの報いを受ける盗賊みたいに。ヨハンがそう呟くと、テーブルの向こうで遊戯がぱちぱちと瞬きをした。何処か心当たりがあるような、ないような、不思議な表情だった。 ◇◆◇◆◇ 「ねえそれ、何見てるの」 大量に出力されたプリンタ用紙の束を手に取って珍しく大量の活字を追っている兄に龍可は不思議に思って尋ねた。龍亞は文字を読むのがあまり得意ではない。難しいことや面倒なことを考えるのが苦手で、だからびっしりと活字で埋められた本を読ませると大概は数ページも進まない内に寝入ってしまうのだ。 覗き込むと、どうやって手に入れたのか聞くのも憚られるような個人情報が整理されないまま無作為に羅列されていて、龍可を訝しませた。異様なまでに詳細なデータが出されていることからしてこれを調べたのは恐らく遊星なのだろうが(ブルーノが一枚噛んでいる可能性も捨て難い)、それにしても、そんなものを紙媒体に残すのもどうなのか。 「ちょっと遊星。何これ、こんなこと印刷していいの?」 「問題ない。……オープンソースになっていたものが殆どだし、知られて本人が困るような情報はない。気味が悪いぐらい完璧だ。偽造履歴だと思いたくなるぐらいに」 「なにそれ」 出力された情報は「ヨハン」――ヨハン・アンデルセンという男のものだった。十代がこの前口にしていた名前だ。生年月日、出身地、これまでの経歴。加えて主観的なメモが書類中に散見出来る。 デンマーク出身で全寮制のアカデミア・アークティック校に幼稚舎から通いエスカレーターで進学。その後ケンブリッジに進学し博士号を取得、インダストリアルイリュージョン社に就職。現在同社の重要職に就いている。簡潔に纏めるとこんな感じだ。一切においてそつがなく、確かに嫌味なぐらいに綺麗に整った経歴ではある。一体どういう接点でもって十代と知り合ったのかが不思議になるような内容だ。 遊星の父との交友関係についても、聞き込みの結果のような箇条書が出されていた。五年程前に仕事の取引先相手として出会い、今は酒飲み友達だという。性格は明るくおおらかで、やや大雑把。大概のことはにこにこと笑顔で応対し、結構な人格者であるらしい。 経歴を不審に思ったのか、その後付けを確かめたものも出てきた。だが結果はオールグリーン、なんらおかしなところはなかったようだ。未だモニターと睨めっこを続けている遊星は納得のいかなそうな渋い表情をしていた。 「気にすると面倒だぞ、龍可。遊星の悪い癖だ。以前に十六夜にストーカーもどきが付いた時もあいつは似たようなことをやって、犯人を社会的に抹殺しようとしていた……半殺し程度で思い留まったようだが。あの女なら遊星が手を下さずとも自力で打ちのめして帰るぐらいはしそうなものだがそれはともかく」 わざとらしい咳払いが台詞の途中に入る。見るとジャックの背後にどこからともなくアキが現れて薄ら寒い笑顔を浮かべていた。ジャックがもう一度咳払いをすると、組まれた腕が下ろされる。 「放っておけ。そのうち飽きるだろう」 「それもそうなんだけど、ちょっと気になることがあるのよね」 「何がだ?」 「うん。どこにもデュエルのこと書いてないなあって」 アカデミア系列の学校を卒業しインダストリアルイリュージョン社に勤めているのにまったく出来ないとは思い難い。デュエルの腕が相当にからっきしであったのならともかく。 しかも遊星の情報が正しければ居住はこのネオドミノ内だということになる。ならば尚更、ちっとも出来ないなどということは考え辛い。コミュニケーション手段がそもそもデュエルに取って代わられているような場所なのだ。……自宅の住所を遊星が如何様な手段で割り出したのかについては考えないことにする。 「デュエルは、『家族』以外とはしないことにしているんだそうだ」 不意に遊星がモニタから目を離し、龍可の心の疑問を聞いていたかのように丁度よく答えた。作業が一区切りしたらしく、立ち上がって両腕をぐっと伸ばしている。それに気付いたブルーノが台所へ消えていった。恐らく彼は数分後に人数分のお茶を持って戻って来るだろう。まめに気配りが出来る男なのである。 「それ、どういうこと」 「父さんが、……俺の父がアンデルセン博士という男と友人らしいことは知ってたんだ。五年ぐらい前だったか、夕食の席で楽しそうに話していたのを覚えている。曰く、I2の新任に面白いのがきたと。それ以降個人的に付き合いを持っていたようだったから昨日面倒を全部呑み込んで連絡を取ったんだが」 「遊星って、そういう時には手段を選ばないというか手間を惜しまないよね」 「色々聞き出したところ、そういうことなんだと。アンデルセン博士は丁度その五年前に奥方と生き別れているらしい。子供は、いるようないないような曖昧な態度でわからないと」 家族と、デュエル。ふと十代がデッキを買いに行く前に言っていた言葉を思い出す。デッキの中のモンスターを家族なんだという誰かのこと、そして自身は家族というより仲間として見ているということ。遊星の説明だと、人間の家族としか、つまり内輪でしかデュエルをしないというふうに受け取りがちだがそういうふうに捉えることも出来る。本来のデッキを失くしてるんじゃないかということだ。 「遊星、もしかしてその人は私と同じように精霊が見えるんじゃないかしら」 「……らしいが。どうしてわかったんだ?」 「確証はないんだけどね。直感かな……だとしたら十代に興味を持つのもわかるし」 精霊が見える人は珍しいから、と続けて龍可は遊星を見上げた。遊星はむっすりとして、「それはそうかもしれないが」と返す。まだ疑って、勘繰っているようだった。 「納得がいかないんだ。何がこんなに引っ掛かっているのか自分でもわからないが、納得出来ない。何か、大事なことを忘れているような……」 「おいおい、これ以上記憶喪失が増えるとか洒落にならないぜ。冗談はもっとわかりやすいモンにしろよ、実は女でしたー、とかさあ!」 ブツブツ言う遊星の背をクロウの手が無遠慮に叩いた。遊星が目を見開き、それに気付いたクロウが「おい、大丈夫か?!」と慌てる。遊星は咳こむことなく「大丈夫だ」と答えて更に「その発想は、なかった」と締めた。その場に居合わせた一同に疑問符が浮かぶ。 「十代さんが実は女だったとし」 「ねーよ! なんでそうなるんだよ!」 「いや、だとしたら、辻妻が合うと思って」 クロウばかりでなく、ジャックやアキ、双子に至るまでが顔を変な風に歪めて「もしかして遊星は病気になったのではないか」「変なものでも食べたんじゃないか」「このまま放っておいたら症状が悪化してしまうかもしれない」「いっそここで殴ったら直りはしないだろうか」、そんなことを考える。ブルーノだけは、何が悪いのかいまいちわかっていないらしくいつもののんびりした顔のままだった。 遊星は仲間達の表情の変化を気に掛ける気がないのか、いたって真面目な顔をしている。それが逆に嘘臭さを排していて恐ろしい。 「それに、電話口の向こうから聞こえたんだ。アンデルセン博士が十代さんに『好き』だと囁くのが」 今度は場が一斉に凍り付いた。ブルーノは相変わらず何もわかっていなさそうにきょろきょろしていて、浮いている。しかし空気を読むことは出来たようでわからないからと安易に何かを尋ねることは控えることにしたようだ。口をぎゅうと結んで声を出さぬよう努めていた。 しばらくの間居心地の悪い沈黙が辺りを満たしていた。転機は、クロウが堪えきれず口を開いたことによって訪れた。 「……あのよ」 「なんだ」 「……それがマジだったとしたら、そのー、確かに十代は危ないかもしんねえけど。身の安全とか……とか……。で、でもよ、親父さんの話によると奥方がいるんだろ? なあ?」 「十代さんがその見付からない奥方に似ていたりしたら、どうなると思う」 「最悪だ」 「……今のは仮定だ」 一応な、と補足が付く。カップの中に残っていたコーヒーを一息に飲み干して遊星はカップをブルーノが手に抱えたままだった盆に乗せると資料を引き払って自室の方へと歩いていった。後に残された面々はお互いに顔を見合わせる。 「なんだか、迂闊に口出ししづらいわ」 「ああ、まあ、なあ。遊星の思い違いか聞き違いなんじゃねえかって俺は思うんだが」 「うーん、でもね」 「うん。この前昼過ぎに帰って来た時に十代が『ヨハンの奴が馬鹿やった』って言ってたよね」 「正直その報告はいらなかった」 ジャックが困惑の滲んだ声で首を横に振る。自然、皆々の口から溜め息が漏れた。 遊星を欠いたメンバーで顔を見合わせ、それからワンテンポおいてようやくのことで室内の妙な緊張が解けていく。なんだか脱力してしまいそうな空気だ。十代本人がこの場にいないこともあってまだ判然としないこともある。そういえばと思ってブルーノを見ると、彼は何か考え込んでぶつぶつ呟いていた。 「……ブルーノお前、今の会話の意味わかったか?」 「うーん? 十代のことが好きな人がいるんでしょ? しょうがないことだけど十代ってまだ交友関係が狭いからそれっていいことなんじゃないかなって僕は思ったんだけど、そうでもないのかな」 「いや、まあ、それはそうだな。いいよわかんねえならわかんねえで」 「あと、遊星が十代のことをすごく心配してるってこともわかったよ。……本人に言ったら嫌がられそうだけど、ああいうとこ見てるとお父さんに似てるんだろうなって思うよ」 「過保護を嫌がってるわりに、そっくり似たような態度取ってんじゃぁしょうがないよなぁ。ま、善意なんだろうってのもそうしたい気持ちもわかるが、にしても妙な入れ込みようだよな」 アキがストーカーに付き纏われた時に遊星が行動を起こしたのは、まあわからなくもないのだ。十六夜アキは幼馴染で彼女の両親とも浅からぬ縁があり、そして女性だ。彼女の場合はサイコ・デュエリストとしての強大な能力があったから放っておいても事態は解決しただろうが、そこに介入してしまう気持ちは同じ男として理解が出来た。女の子は守ってやらなきゃ、という観念だ。 今回、確かに女だとか男だとか関係なしに警戒腰になってしまうのは仕方ない状況だとはいえ、十代はあの時のアキと違って学生でもない。見た目はひょろっとしているが、腕っぷしはそんなに悪くない。いざとなったら彼だってモンスター達の力を借りて身を守るぐらいのことはやってのけるだろう。 デュエルだって鬼のように強く、遊星が連敗記録を打ちたてているぐらいなのだ。何故そうまでして入れ込むのかはわからない。 「なんか、あんまり調べてる奴のこと好きじゃなさそうだったよな。いつもの無関心とは違って、純粋に気に食わないっていうか」 「言われてみれば確かに、敵対心みたいなのはあったかもしれないねぇ」 「ああ、そっか。珍しく、普通に嫌ってるっぽいんだな」 博愛主義者ではないから遊星にも好き嫌いはある。ただ彼が明確でどうしようもない理由なしに誰かを嫌うことは殆どない。学生時代に差別主義の教師とは真向から対立して批判していたが、その程度だ。感情的な好き嫌いというのは本当に珍しいものなのである。父親のことは感情的に疎んでいるのだろうが、外野から言わせて貰えばあれは愛情表現の一種に過ぎない。根本的に不動父子は趣味が似通っているから話が弾む時はとことんまで白熱させている。 「でもね、私その人は悪い人じゃないんじゃないかなって思うわ」 クロウが一人で頷いていると龍可がぽつりと言った。 「だって十代は嫌いだって一言も言わないもの。本当に嫌いなものには容赦しないから、十代は」 「そういえばこの前ものすごい勢いでゴキブリ潰してたね」 「蚊を叩く速度も目にも止まらぬ速さだったわ」 「でもネズミとかはつまんで話しかけてるんだよね。なんか、よくわっかんないぁ」 龍亞も妹に同意して頷く。十代は好き嫌いがはっきりしている人なのだ。興味のあるなしもはっきりしている。さばさばして明快で、わかりやすい人だ。よく双子の頭をかわいいかわいいと撫でてくれるが、その時は明確に好意を示されているのだと感じる。面倒なことを頼んだ時は、渋々やってくれたとしても明らかに嫌そうに顔に出すのでなるべく十代ではない人に持っていくように決めた。良くも悪くもすっきりしている。単純と言うと聞こえが悪いが、しがらみがないとも取れる。 「十代本人が嫌がってるわけじゃないんだから、好きにさせておけばいいのにね。十代はもう大人なんでしょう? 何をどうしたって、十代の自由なはずじゃない」 「感情はそう大人しくはいかないんだろ。そんなことは遊星ならわかってるさ」 わかったふうな口ぶりでクロウが双子の頭をぽんぽんと撫でた。 「結局、あいつはそういうところでわがままなんだよな。貪欲っていうかさ。一度手に入れたものを失うのが怖いんだろ――大事なものを失ったことがないから」 |