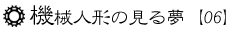ふあぁ、という間の抜けたあくび声を上げてからごしごしと目を擦り、まだ眠たげな瞳でぼんやりと部屋を見回した。普段なら通路を挟んで向かいのベッドで行儀よく掛け布に収まって寝息を立てているルームメイトの姿が今日はない。あまり街に出る予定のない彼に珍しく外出予定でもあったのだろうかと考えてみるが、前日までにそんな話をしていた様子もない。
適当に着替えて洗面台へ向かう途中で、ガレージの扉が開く音が聞こえてきた。ポッポタイムのリビング兼倉庫、D・ホイール置き場として使われている広いガレージの正面扉が開くのはD・ホイールで誰かが出掛ける時、換気をする時、D・ホイールの整備をしっかりとやる時――頻度の順でこのぐらいだ。となると今日はお出掛けの日か、ジャックの仕事日なのかもしれない。 「おはよ……こんな朝から誰が出掛けるんだ?」 「ああ、おはよう、十代。クロウが今配達から戻ってきたところでね、それと入れ違いに遊星が出てったよ」 早々に姿を発見出来たルームメイトは器用に結ばれたエプロンの紐を後ろ手に解いているところだった。ふぅんと適当に相鎚を打ちながら朝食にめぼしいものを物色する。買い置きの食パンを手に取ってトースターに放り込み冷蔵庫を開けた。手前で存在感を主張しているベーコンのブロックには手を触れずに奥のプロセスチーズを取り出す。ベーコンエッグを見るとなんだか微妙な心持ちになってしまうので、あれ以来ベーコンは口にしていない。 「遊星はどこへ」 「トップス。アキさんと龍亞くん龍可ちゃんを迎えに」 「わざわざ迎えに? 珍しいな」 「デートなんだよ、おデート」 ライダースーツのジッパーをだらしなく下ろしながらクロウが投げ遣りにそう言ってこちらへ寄って来た。顔には非常にわかりやすい羨みの感情が浮かんでいる。長年つるんできた仲間内で彼一人だけ特別な女性がいないから、というのは一緒に暮らし出してわりとすぐにわかったことだ。 「デートなら双子は拾いに行かない方がいいんじゃないかなぁ」 「本人には自覚がねぇからな。双子は遊星もアキもちっこい頃から面倒見てきたから邪魔な部外者ってカテゴリに入ってないんだろ、多分」 「妬み嫉みにしか聞こえないぜクロウ。現役プロのジャックと現行タイトル保持者の遊星がモテるのはもうしょうがないじゃん、そういうものとして諦めろよ。俺もブルーノも彼女いないし、ほら」 「お前ら女に興味ないだろ」 「「うん」」 「つまり、そういうことだ」 盛大な溜め息を吐いてから脱いだスーツをブラックバードに投げ掛け、椅子にどかりと座り込む。十代としては、そんなに悩むことなのかと思うぐらいのことなのだがクロウにとっては長年続いている少し悲愴なこと、であるらしい。十代個人はクロウの場合出会いのなさがその原因なのではないかと思うのだが、以前にそう言ってやったら学生時代を挙げられて否定された。 勿論彼も彼女云々が全てではないと理解してはいるのだが「わかってるのと、虚しさとか羨ましさとかそういうのは全然別物」と断言されては返す言葉もない。確かにアキも、それからジャックの相手であるカーリーも、かなり献身的なタイプだから興味がないといっても少しぐらいは同意しなくもない。でも少しだ。 「十代、朝飯作ってんのか」 「ん。チーズスクランブルエッグ」 「余分に頼む」 「オッケー、卵いくつ追加する」 「……二個」 配達後だからいいよなうん、という小声での釈明が続いてくすりと笑んだ。チーム・ファイブディーズに混ざってのこの生活は一々が面白くて、十代はそれがとても気に入っている。なくしているらしい記憶のことが然程気にならないのももしかしたらこの生活のためなのかもしれない。 リーダー格の遊星を主としたチームメンバー達は皆気さくで個性豊かで、居候の身のブルーノと十代にも本当によくして貰っている。この空間は非常に居心地が良いのだ。「ファイブディーズは家族だから」とにこにこしていた龍亞の言葉がよくわかる。役割だとかそういうものはないが、チーム・ファイブディーズは確かな絆で繋がったファミリーだった。そこには無条件の信頼と愛情が存在している。十代にとってはどこかこそばゆく、懐かしく、むず痒い。 手早く混ぜて完成させたスクランブルエッグを大皿に盛って自身も食卓に着いた。ブルーノもコーヒーマグだけ手に持って椅子に座り込む。どうやら今日は暇らしい。 「十代はほんとに料理上手だよねぇ。十代が来るまでは、クロウが一番上手かったんだよ。アキさんもほら、頑張ってクロウに習ってるでしょ? クロウはなんというかお母さんみたいだよね。裁縫も掃除もクロウが一番効率良く綺麗に出来るんだ」 「……褒められてるはずなのにいま一つ嬉しくないのは何でなんだろうな……」 「なんだよ素直に喜べばいいのに。今時家事の出来る男はもてるんだぜ」 「だといいよな。サンキュー、十代」 家事が出来るというのならば、十代も相当に出来る男なのだ。ブルーノの台詞通り料理はクロウ以上だし、適当そうな性格に反してそこまで部屋が汚くなることもない。几帳面な遊星よりはいくらか雑な面が見られたが、ただ時折、女性めいた性質が少しばかり彼の中には垣間見えた。 それは本当に些細なものだ。振り返る挙作がもたらす印象だとか、エプロンを着けて台所に佇む後ろ姿、双子に接している時の声音、優しい手付き、それらの中に僅かな違和感が見え隠れするというその程度の問題に過ぎない。 多分、遊城十代は母親めいているのだ。 「あのさ、ブルーノ」 「うん。ジャックならまだ寝てるよ」 「あ、じゃあ余分にもうちょっと作っておけばよかったかな……ってそうじゃなくてさ。見たところブルーノって今日暇っぽいよな?」 「そうだね。特に用事はないよ。……どうしたの?」 「じゃさ、どっかに出掛けないか」 気を利かせ過ぎてやや斜めの回答を寄越したブルーノに苦笑しながらそう切り出す。「うんいいよ、どこに行こうか」とにこにこ嬉しそうに返すブルーノの声でクロウは思考の中から現実に引き戻された。思わず妙な間抜け声が口から漏れ出してしまう。 ブルーノと十代が二人で出掛ける? この不思議ちゃんと不思議ちゃんが? 記憶喪失故に二人がところどころで常識欠如気味だったりするのはもう既にはっきりしていることだった。勿論当たり前に日常生活をする分には問題ないし、人格に異常があったりするわけでもない。ただ時折明らかに時代錯誤な発言をしたりするのだ。そしてあまり人目を憚ったりしないからいい意味でも悪い意味でも目立ち易い。 これは一体どうしたものなのか。止めるのはやぶさかではない。放置して問題を起こされても面倒だ。 「……まぁ、こっちはデートじゃねえしなぁ」 二人でもそれ以上でも対して変わりはないだろう、と自身の中で結論付けて一人頷いた。 十代のことを母親めいていると思っている一方で、クロウ自身が保護者というべきか母性のようなものを持っていることにクロウ本人はあまり感付いていない。 ◇◆◇◆◇ 「るかー、るかぁ、龍可ってばぁ。着替えに時間掛けすぎだよ、もうすぐ遊星が来る時間になっちゃうよ」 「それまでには間に合わせるから、部屋の中覗かないで!」 扉の隙間を縫うように飛んできた枕をひょいと慣れた動作で避けて、龍亞は「はいはいわかったから急いでね!」とドアを閉めた。リビングの方から両親の談笑が聞こえてくる。龍亞が性懲りなく龍可に枕を投げられているところを見ていたのかもしれない。 「昔は同じ布団で寝てたんだし、そんなに気にすることもないと思うんだけどなぁ……ていうか、なんであんなに着替えに時間掛かるの?」 「女の子は何かと要り用なの。そんなこともわからないなんて、ほんと、龍亞ってお子様よね」 腕を組んでぶすくれていると背後から妹の澄ました声が飛んでくる。振り返った先の龍可は龍亞と目が合ったことを確認するともう一度「お子様ね」と繰り返した。その物言いにかちんときて自然、龍亞も愚痴みたいな言葉を漏らす。 「お子様って、龍可だって俺と年変わんないじゃんか! それはそうと準備出来たんなら早く行こうよ。さっきアキ姉ちゃんから遊星と合流したってメールがきてさ……」 「アキ」「遊星」と今日の同行者の名を挙げるとほんの少し陰っていた機嫌をあっという間に治して、龍亞は龍可の手のひらを握って後ろ手に引きながら走り出した。引かれながら龍可は、やっぱり龍亞はわかっていないというふうに首を振る。 こんなのだから、いつまで経っても成長しないのだ。きっと、もっと歳を取って見た目だけは大人になっても、龍亞は龍可のそばにいるだろう。だからまた龍可も、龍亞のそばにいるのだと思う。 「……誰かさんと一緒ね」 そうぼやいてからはたと首を傾げた。知り合いにそんなふうな人達が、いたっけか? 「龍可、どうかした?」 「あ、ううん……」 なんでもないの、と返事をすると龍亞は変な顔をする。だがチャイム音が鳴って玄関口に待ち人が訪れると、龍亞の興味はそちらへと動いてそのことはすぐに頭のどこかへ行ってしまった。 『不動です。そちらに……』 「おはよう遊星! こっちは準備万全だよ、待ってね、今出るから……」 インターホン越しに姿を確認して外へ出ると、アキを隣に立たせた遊星が双子を待っていた。いつも着ている作業着でも昔着続けていた制服でもない普通の私服だ。基本的にファッションに無頓着な遊星らしいシンプルな装いだが、ところどころに彼らしからぬアレンジが入っている。多分、アキに見立てられて言われるままに着ているのだろう。折角の美形を適当な服で埋めておくのが勿体ないとか、そういう心理だ。 「待たせたか、龍亞、龍可」 「ううん、大丈夫。どっちかというと俺は龍可のことずっと待ってたよ。もう最近着替えとかの時間が長いのなんの」 「そんなの、女の子なんだから当たり前じゃない」 「そうなの? わっかんないなぁ……」 「心配するな。俺もその理屈は未だによくわからないでいる」 訝しむ龍亞の頭をぽんぽんと撫でて遊星が同調してやると女性陣二人がくるりと振り向いて、じっとりとした目を向けてきた。慌てて「努力する」「もうちょっと頑張る!」と答えると二人は「そう」「頑張ってね」と冷めた答えを返して寄越す。 「ね、ねえ遊星、今日海馬ランドに行くんでしょ? 何かイベントとかあるの?」 「ん、あ、ああ。俺としてはいくらか気が早い気がしないでもないんだが、今日からハロウィーン・イベントがあるらしい」 「へー、仮装とか出来るのかなぁ」 ごく無邪気にそうはしゃいでからちらりと女性陣を眺め見て、「……アキ姉ちゃんと龍可の機嫌が直ったらね……」としょんぼりして呟くとアキと龍可はくすくすと笑った。二人とも、そんなに本気で怒っていたりするわけじゃないのだ。 かの海馬瀬人社長がその生涯を賭して建設したことで知られている海馬ランドは、学生が長期休み前後に繰り出す先や、またカップルやファミリーの定番行楽スポットとして高い人気を誇るアミューズメントパークだ。運営元の海馬コーポレーションはインダストリアルイリュージョン社と提携してデュエルモンスターズの公式大会を開催したり、関連商品の展開を一括で管理している。その規模たるや、世の中のエンターテイメントを牛耳っているといっても過言ではない程である。 そんなわけもあって現在はアミューズメント事業でよく知られている同社が、技術開発を主とする複合企業であることはあまり周知されていない。そのルーツが創業当時は兵器事業に携わっていたことにあることも、一部の社員にしか知られていない。夢の国に軍需産業、なんてイメージは当然好ましくないものであるからそれは当然の帰結なのだが。 「相変わらずすごい人だよね。夏休みよりすいてるけど」 「でも私は人が多くて活気がある方が好きよ。その、鬼柳さんには悪いけど……」 「……それは仕方ない。俺も、あの町がどうしてああ世紀末というか……西部劇チックというか……ああなのかはわからない」 鬼柳京介、職業町長。彼は、昔遊星達が伝説のチーム「サティスファクション」を結成して在学中のデュエル・アカデミアを飛び出して良くも悪くも大暴れをしていた時のリーダー役の青年である。口癖は満足。大都市のネオドミノからそう離れていないのに何故か人気の少ない町を統括している。 生家は十六夜の家には劣るもののそこそこ裕福な良い家柄で、ルックスもデュエルタクティクスも頭脳も悪くない。そんな彼が町長になるまでには紆余曲折艱難辛苦の出来事があったらしいのだが、それに関わっていた遊星は頑として、双子やアキ相手には口を割ろうとはしなかった。 「とりあえず、ブルーアイズコースター乗ろうよ」 「相変わらず龍亞って無計画。効率とかちゃんと考えなきゃ」 「まあまあ、好きなふうに回ればいいじゃない。いつでも来れるんだから」 「ほら、アキ姉ちゃんもそう言ってるじゃん。龍可が乗りたいのから回るからゆっくり行こうよ。龍可、ぎっちぎちスケジュールで一日制覇したがるんだもんなぁ」 「単にそれが好きなのよ、誰かさんがルーズだから。……でもそうね、今日はアキさんと遊星に引率して貰ってるわけだし……」 ちらり、と兄を眺め見てから思わせぶりに呟く。龍亞は文句を言いながらも龍可に妥協することが多く、なんというか妹に弱いのだった。わがままをしたいわけではないが、龍可は割合主張がはっきりしている方だからこういう小さなことではよく龍亞と対立してしまう。大筋ではぴったりと意見が一致するから、きっと好みの問題なんだろうなぁとは思っている。結局のところ、龍亞と龍可は疑いようもなく双子の兄妹なのだ。 「アキさんと遊星の好きにして貰うのがいいわよね。パパとママじゃないもの」 ぱっと手のひらを返して見せると遊星とアキが揃って苦笑した。家族共同体に似たチーム・ファイブディーズのメンバーの中でも、特にこの四人がいわゆる「家族」に近いことを受けているのだろう。 「仲が良いな」 「遊星とアキ姉ちゃんもね。で、何乗る?」 「そうだな……アキ」 「それじゃ、左回りで行きましょ。ハロウィーンの写真撮影スポットがあるんですって」 アキが簡潔にまとめて提示すると、双子は賛成、と手を上げて頷いた。 元気良く走り続ける龍亞に、後ろから雑踏を縫うようにして龍可の少し怒った声が響いてくる。それを無視して高揚した気分のままに走り続けていると、とうとう遊星とアキも龍亞を見失いかねないと判断したようで二人分の声が龍可の呼び声に加わった。 「あー、流石にまずいかも」 一人ごちて、急ブレーキをかけるように踏み止まる。その途端に勢いよく何かと衝突して龍亞は盛大に倒れ込んだ。 「あ、ごめん、すみません!」 ろくに前後確認しないで走っていたために、思いっきりぶつかってしまったらしい。跳ね飛ばされるように地面に尻餅を付いてしまい龍亞はいてて、と呟きながら起き上がった。慌てて謝りながら反射的に閉じてしまった目を薄く明ける。途端に視界に入ってきたのは、赤色だった。 どことなく嫌な感じのする色だった。褐色めいた、多少彩度の落ちたその色に龍亞は言葉を失ってしまう。このどうしても好きになれなさそうな色を昔どこかで見たような気がする。乾き出した不健康な血のようなそんな色を。 「……誰?」 問いながら、凍り付いていくのに似た感覚を覚えた。さあっと冷えていく。気分が悪い。怖気がする。 「よお、お前に会うのは、結構久しぶりかなぁ? ああ、わかんないって顔してる。そうだよな、こっちじゃ初めてだもんな。はじめまして龍亞君。今日は顔見せに来ましたあ。……なぁんてな、おいおいなんだよその顔」 ケッサクだぜ、それ。目がちかちかして拒絶してしまいたくなる赤色の少年が龍亞を指差してケタケタ笑った。腰まである長い三つ編みがそれに合わせて揺れている。 龍亞は蒼白な顔で呆然と少年を見ていた。世界中の時間がまるで凍り付いて止まってしまっているかのようでぞっとしない。いや、ような、というわけでなく時間は本当に止まっているみたいだった。通行人は皆、カメラフレームの中でピンぼけしたまま切り取られてしまった静止画みたいに生気がない。龍亞と少年、そして少し離れた位置にいる老人と青年、遊星、アキ、龍可だけがブレずに視界の中で姿を保っていた。しかしぴんと張り詰めた糸のように彼らもまた動き出す気配はなかった。 赤毛の少年はにたにたと嫌らしく口端を吊り上げる。 「声も出ないって? キャハハハハハハハッ、向こうの方がもうちょっと筋あったんじゃねーのォ?! そんな顔すんなよぉ、お前の大ッ好きな龍可ちゃんには今回は用なんかないしさあ。お前にもないけど。まあ単に僕がお前のこと気に食わないってそれだけ」 「……嫌いだ、お前」 「なんだ喋れるんじゃん。奇遇だね僕も嫌いだよ。大ッ嫌いさ。『あいつら』の子供ってだけで反吐が出そうになる。……あーこっちじゃ違うんだっけ? やっやこしいなぁ……」 心底かったるいというふうに頭を掻く。姿形も声質も所作もつくり物のように完璧で精緻なバランスを取っていたが、それらが組み合わさって動き出すと歪つなつくり物のぎこちなさと相容れなさを産み出していた。ちぐはぐのロボットみたいだった。綺麗なものと綺麗なものを、歪んだ黒い意思で繋ぎ合わせたマネキンがあったとしたら恐らくこんな感じなのだろう。 悪意を寄せ集めて、煮詰めて、丸め、剥き出しにしてぶつけられている気持ちだった。 「ほんっと胸糞悪いよねぇお前は! そっくりなんだよ。そっくりすぎて、バラバラにしてやりたくなる。むかーし僕達を否定した《母さん》と《偽善者》まんま。気持ち悪いったらないね、見てるだけで腹が立つ。キレイな戯れ言ばっかでさ、そういう意味じゃチーム・ファイブディーズそのものが似たり寄ったりなんだけど!」 キャハハハハハハッ、ああもうほんッとむかつくよね! そうきちがいのように笑い転げて少年は龍亞に純然たる悪意を投げ付けてくる。いわれのない敵愾心、憎悪、どす黒い感情。鋭利な刃のように鋭くそれでいて鈍器のように重たく龍亞にのしかかり、押し潰してこようとするそれが龍亞にはとても恐ろしく思えた。 だがそれと同時にその狂的に笑う少年がどうしてだか酷く哀れめいて見えるのだ。 彼を憎み返すことはどうしても出来ないのだろうと直感的に知った。かわいそうなこどもを憎むだなんて。嫌うだなんて。それのどこに意味があるのか龍亞にはわからない。 しかしその眼差しが気に触ったのだろう、少年は「憐れんでんじゃねーよ。そんな目で見るな、馬鹿の分際で」と吐き捨てた。 「愛してくれるものを失った絶望。愛するものを失った絶望。愛さえ要らなくなった絶望。それだけでも、酷かったのにさ。……この身すらままならぬ絶望。わかるかい? わかんねーよな。結局どの世界にいたってお前達は恵まれた子供なんだ。何も知らないくせに。何も知ろうとしないくせに。……嫌いだよ。嫌いだ。だから僕はお前を……!」 唇のかたちが平仮名一つ分だけを形作って、しかしそれが音を成すことはなかった。饒舌だった唇が嘘みたいにきゅうと固く結ばれ、彼は音を喉の奥に飲み込む。妙に生々しい音と共に吸い込まれて戻っていった言葉はだから、その時龍亞の耳に届くことはなかった。 だが龍亞には、わかる。 この自分を憎んで憎んで仕方ない少年は、きっと「ころしたい」と、そう言おうとしたのに違いないのだ。 あけすけな殺意を隠そうともせずに。 「……残念、時間切れだ。《母さん》が来る」 憎々しげに「母さん」と呼ぶ少年の顔は苛立ちに歪んでいた。皮肉っているのだ。そう呼んだ相手のことを母親だとはこれっぽっちも思ってやいない。道端に落っこちているボルトナックに世界一嫌いなものを投影して「母さん」と呼び、そうすることで蔑んでいるような感触だ。がらくたを弄んで握り潰すみたいに。 しかしそこで頑なに母さんという名でもって形容しようとするのは、憎悪の裏返しに似ていた。 「芋づるにあのふざけた男に出てこられても対処に困るし。今はまだ《母さん》の所在をばらすわけにはいかないんだよねぇ。あいつ本当馬鹿の塊だから手に負えないっていうか。あいつの血族はみんな嫌いだね」 お前もだよ、と急に少年が龍亞の胸ぐらを掴み上げる。華奢そうな見た目に反して、異常なまでの握力で掴まれて息苦しさに喘いだ。腕一本で龍亞を吊り上げている右腕を龍亞は自身の両腕で掴んで引き剥がそうともがくがまるでびくともしない。 しばらく必死の抵抗を続けていると飽きがきたのか、実験動物を見るような目で睨まれた後ぽいと放り出された。今日二度目の尻餅をつく。痛みは先の比ではない。じりじりと嬲るように持続する痛みはそのまま少年の性質を映し込んでいるようでもあった。蛇のようだ。少年の瞳をもう一度見上げてそう思う。 「こんなことしてる暇ないんだった。……感謝しろよ、仕事だからしょーがないし、これだけは教えといてやるよ。敵の名前を知っとくって、存外大事なことなんだぜ」 少年は川べりに落ちていた漫画雑誌を読み上げるようにだるそうな声で言った。 「……てき」 「そうだよ。お前さぁ、こんなにわかり易くマイナスの感情をぶつけてくる奴が味方だと思うか? モーメント・エネルギーじゃないんだよ。僕には悪意がある。それが全てだ」 「……そういうもんなのかなぁ?」 「そういうふうに出来てるんだよ。僕は不合理がお前らの次ぐらいに嫌いだし。――『イリアステル』。それが僕達、有史以前からこの世界を操ってきたこの組織の名前。覚えておきなよチーム・ファイブディーズ――ま、君達、色々素っ破抜けちゃってるみたいだけど」 僕の名前、ちっともわかんないんだろ。薄っぺらい声音で問い掛ける。忘れちゃったんだろう。そう続いた声に呼び起こされるようにして脳の奥で一瞬だけ、閃いたものがあった。走馬燈のようなフラッシュバック。真っ白なノイズ。その向こうに三つ編みで、デュエル・アカデミアの男子制服を着た少年が立っている。 「あんまりさぁ、がっかりさせんなよ」 「……あのさ、俺、お前と知り合いなのか」 「さあね」 赤毛の少年は龍亞の問い掛けをはぐらかして酷薄に笑った。冷たい声音が遠くなっていく。龍亞は震える手のひらを今一度見つめた。汗が酷い。 「バイバイ龍亞。また今度」 ◇◆◇◆◇ 「なんだか大世帯になっちゃったねえ」 「いいじゃん。俺は、人数多い方が好きだぜ」 面子を見回してそう漏らしたブルーノに十代が素直な笑みで返した。シティ観光を兼ねたジャンクショップ巡りに、今日はメカニック以外の人間も付いてきているのだ。その最たるのは恐らくジャックだろう。そもそも有名人だからというのはあるが、彼は平素面倒がってパーツ屋なんぞには出向かない。 「でも本当に珍しいよね。クロウは何度か着いてきてくれたことがあったけど……」 「遊星に荷台として駆り出されてな。今回は、お前ら二人っきりで野放しにして何されるかわかったもんじゃなくてほっとけなかったんだよ」 「ジャックはこういうところに来るの、初めてじゃない?」 「遊星に荷物持ちに使われて何度かある。学生の頃の話だが」 「遊星荷物持たせすぎじゃね? どんだけ買い込んだらそういうことになるんだよ」 D・ホイールそのものに疎くパーツからなにからさっぱりの十代がそんな感想をこぼした。 チーム・ファイブディーズの面々、というよりむしろネオドミノシティの住人は全般的に機械に強い傾向がある。モーメントシステムの実用化と、海馬コーポレーション本社膝元の企業城下町であることが手伝って、そういったデバイスや知識の普及率が非常に高いのだ。デュエル・アカデミアでも必須科目にデュエル実技や論理と並んで情報工学が入っていたというからすごい。 お互いに素性のよくわかっていないブルーノと十代だが、こと情報機械の分野においては両者の実力に天と地ほどの差があった。何しろブルーノは遊星に並ぶ、ひょっとしたら凌ぐ程の超天才メカニック。一方で十代はネオドミノ外の一般人に毛が生えた程度の知識技術しか持ちあわせていない。 携帯やパソコンを日常的に使う分には特に問題がないが、一歩踏み込んだ内容となるとてんでダメだ。これに関しては、触れただけで電子レンジを爆発させるような音痴でなかったことを喜ぶ方針にしよう、と十代の実力の程を計った後で遊星が言っていた。二人連続で凄腕メカニックがどこからともなく現れるなどという幸運があるはずがないのだから。 「十代が行ったことのない場所がいいだろうし、今日はちょっと遠出してダイダロスブリッジより向こうに行こうか」 「ダイダロスブリッジ……っていうとあのおっきな橋? 真中が指輪みたいになってる」 「うんそう。でも十代がD・ホイール持ってないから今日はモノレールだね。モノレールもね、結構すごいんだよ。無人運転だからシティの外からの人には結構珍しがられるんだ。僕としては、いつか運転席をバラして内部構造を見てみたいんだけど」 「へー、無人運転か。ネオドミノってそういうの多いよな」 そもそも、ネオドミノでは住民全員が住基IDで管理されるシステムになっている。旅行者などの臨時滞在者も出入管理センターで一時滞在用IDを発行して貰い、そうすることでようやくシティに足を踏み入れることが出来るようになる。不法滞在者や、犯罪者などの取り締まりその他諸々に利用されているIDはシティ生活における要と言っても過言ではなく、万が一このデータに何らかの障害が起ころうものなら大混乱は必須だろう。 出自不明なブルーノや十代も、シティに住む以上どうしてもこのIDが必要になってくるので発行元のセキュリティ・シティ市政管理局に口を利かせて発行して貰ったものを用いていた。少々アレな手段だが不正偽造ではなく単なるレアケースだ。発行元が正しいのだから問題などない。 そういうわけで、ネオドミノシティはまさしく「機械の街」であるのだった。或いはネットワークの街か。徹底管理された電子の街。十代の価値観からすれば、一つ手のひらを返すだけでどこか薄ら寒いものを感じるようですらある。利便性と紙一重で危機感の麻痺を差し出させられてやいないのかと。 便利なことには確かだ。だがこの方式は、上層部からの監視を容易にすることもまた意味するのだ。 「わっかんねえなぁ……」 しかし「それで、だからどうしたって言うんだ」と問われてしまえばそこでお終いである。犯罪抑止能力としては確かに有効に働いていたし、生活が便利であることも間違いない。IDパスさえ持っていれば電子マネーで簡単に支払いが済ませられるから財布が嵩張ることもない。十代は首を振って、考えることを止めた。十代の脳味噌ではこれが限界だ。 「……なあジャック」 「……なんだ」 「話変わるんだけどさ、さっきから時々刺さってくる視線って、やっぱジャックがいるからかなぁ?」 代わりに、ついさっきから気になっていたことをストレートに尋ねた。プロデュエリストのジャックは相当な有名人で、ずぼらだったり色々と問題のある性格がわからなければ文句なしのイケメンだ。当然女性ファンも多い。彼女がいることを彼は公言しているのだが、それでも多い。 街を歩くだけでキャーキャー言われるとはこのことなのだろうか、というぐらいに黄色い声が今現在ジャックに向けて寄せられていた。ジャックが変装する気も見せずにトレードマークの白いコートを翻しているのも、目立つことに拍車を掛けている気がするのだが。 「いつもこんな感じなのか、ジャックが出歩くと」 「まあそうだな。全盛期のチーム・サティスファクション時代に比べればまだマシだが……あの頃は悪名も高かったしなー……っとこの話遊星にはするなよ。若干黒歴史らしいから」 「大体そんなものだ。だがまあ、今日は一段とうるさいな。理由は知らんが」 「遊星がいないからかもな」 そう言ってクロウは横目で十代を見た。ジャックとクロウの会話を聞いている整った横顔は、素直に美しいと賞賛出来る類のものである。クロウとしては大変悔しいことに、十代は遊星と同じ自身の分かり易い長所に気が付いていないタイプの人間だった。自分の容姿の良さをいま一つ理解していないのだ。遊星がきれいだ、うつくしい、と褒めるのも世辞だと思っているらしい。 「……あとさ、もしかしたら十代も要因の一つになってるかもしんねぇ。ほらよ、見馴れない顔だろお前。アイドルグループに新規メンバーが参入した時を想像すると分かりやすいんじゃねぇかな」 それから、彼が少し中性めいていることも、問題の一端を担っているだろう。熱心なジャック・アトラスファンの中には十代を女と取り違えるのが出てくる可能性もある。尾ひれが付いてあることないこと噂になるのは考えられないことではない。現に遊星が十代をカードショップから連れ帰った時にそういうことになりかけた。 「自覚ないかもしんねぇけど十代もそれなりに目立つ方なんだからな。覚えといた方がいいぜ。遊星がまた妙な本気を出し始めても面倒だしさ」 「ふーん。……あ、わり、着信きてる」 クロウの言葉が注意になってから頭半分に流し聞いて適当に頷いていた十代は、断ってからぶるぶると震える携帯を手に取って開いた。ディスプレイには「ヨハン」と着信相手が表示されている。その文字の並びに十代は眉を顰めるが、しかしメールを送ってはきてもこいつが電話を掛けてきたことだけは、あの日以来一度もない。 胡散臭いが、であるのならば何らかの緊急事態が発生したのかもしれない。そう判断して仕方なしに通話ボタンをタップした。 「なんだよ、電話なんか掛けて何の用だ」 『推測は出来てると思うけど、緊急の話だよ。残念なことに今は君の声を楽しんでいる余裕がない。――いいか十代、海馬ランドに行くんだ。イリアステルが遊星君達と接触した』 「……は?」 『ご丁寧に十代も俺もそばにいないタイミングを見計らってだ。こっちもまだ正確には事態を把握出来てない。今すぐ遊星君と合流してくれ、何かあってからじゃ遅い』 「あ、おい、待てよヨハン――!」 十代の言葉を待つことなく電話は一方的かつ唐突に切れた。海馬ランド、遊星、イリアステル――単語が頭の中でぐるぐると渦巻いて氾濫している。四人が朝から出掛けている先が海馬ランドなのだろうということは数秒掛けて理解した。だが、イリアステルとは一体何なのだ。 インダストリアルイリュージョン社で働いているはずのあの男はどうしてそんなことを知っているのだ? 「……わけわかんねえ。でも、」 「イリアステル」という単語が何かとてもよくない響きを持っていることは直感的に伝わってきた。肌がぞわりと粟立つ。 「十代、どうしたの。電話、誰から?」 「……せい」 「えっ?」 口の中がからからして落ち着かず、思わず生唾を飲んだ。心配そうなブルーノの顔が十代を覗き込んでくる。 十代はそれを栗色の瞳で見返して手短に旨を告げた。 「遊星のところに行かなきゃ。龍亞と龍可もだ。何かとてつもなく嫌な予感がする」 |