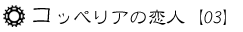「……なんだってこんなことに」
夕飯の買い出しをする主婦達に紛れて買い物籠に食材を放り込みながら十代は深く、深く溜め息を吐いた。周囲の目には一体自分はどういうふうに映っているのだろう。一人暮らしの買い出しに解釈されていればいいが、好きもののおばちゃんに妙な事を考えられていてはたまったものではない。何故なら、現実問題としてこの買い出しの後赤の他人の男の家に向かうことになるからだ。 気が重い。 電話の後に渋々メールを送って、最終的に取り交わされた約束はこんなものだった。曰く、夕食と朝食を共にして抱き枕になれと。なんなのだろうあの男は、疑うべくもなく、ただの変態趣味なのだろうか? かっとなって条件を呑んでしまった後で「これは遊星が危険視しても確かにしょうがないのではないか」と遅ればせながら気が付いたが既に後の祭である。十代は一度結んだ約束を破ることが好きではない。 そんなわけで出掛けから精神的な疲労に苛まれているわけなのだが、疲労の原因は実のところそれだけではなかった。 「十代さん、考え直してください。それは自殺行為です。飛んで火に入る夏の虫だとか、ライオンの棲み家にわざわざシマウマが出向いてやるだとか、そういうことと変わりません。危険すぎます」 「いや落ち着け、目が据わってる。どっちにしろ情報切れで行き詰まってるんだろ? このぐらいで手に入るんなら安いもんじゃないか。滅茶苦茶に厳重な情報なんだから。それにお前の親父さんの知り合いなんだから身元も確かだ、一応」 「俺の父の知り合いだからこそ心配なんです。類は友を呼ぶと言う言葉を知っていますか、アンデルセン博士は間違いなく変人です。そうに違いない」 「……お前、今さりげなく一言で複数人を馬鹿にしたよな」 今回の遊星は異常なまでに強硬だった。十代が渋々「明日から明後日にかけてヨハンと情報交換してくる」と告げるや否や遊星はガタリと立ち上がって一言「駄目です」ときっぱり言い切ったのだ。そのあまりの剣幕にチームの他の皆も若干椅子を引いて遊星と十代から距離を取ったぐらいだった。何かに取り憑かれていたんじゃないかとすら思える。 その晩、アキや双子達が家に帰った後になってもまだ遊星は頑として譲ろうとしなかった。ついには十代だけでなくブルーノやクロウもほとほと困り果ててしまい、しかし尚もあちらに諦める気配がない。これは一体どうしたものかと半ば諦めた時に動いたのはそれまで黙りを決め込んでいたジャックだったのである。 「――見苦しいぞ遊星」 ジャックはぴしゃりと言い放った。 「ジャック! しかし……」 「遊星、お前はこいつの父か母にでもなったつもりか? なんだ、さっきから聞いていればみっともなくぐだぐだと。不安になるのがわからんわけでもないが」 「え、なんでジャックも不安になるんだ」 「話がややこしくなるからお前は黙っておけ。――とにかく、成人した『赤の他人』の決定と行動を妨げる権利はお前にはない。十代が大丈夫だと判断したのならそれに任せておけ、好きにさせろ。どうしてそれが出来ないなどと言う? おい、十代、別段お前は脅迫されているわけではないのだろう」 「ああうん。あいつは遊星を敵に回すのは嫌だって言ってたし。遊星が何を心配してるのか知らないけど、ヨハンは変なやつだけど危ないやつじゃないと思う」 妙な好意は受けているがそれだけだ。嫌いに感じたことも不快に思ったこともない。ヨハンは不思議な男だった。彼に触れられることを、気持ち悪いと感じることはどうしてだかなかった。 「嫉妬か、馬鹿馬鹿しい。か弱い女子供ならばともかくこいつは強い。デュエルでも実力排除でも、今のお前よりは余程上手くやるだろう。頭を冷やせ、虚けのままでは困る」 「ジャック、言い過ぎじゃ……」 「いーや、これはジャックが正しい」 「クロウまで」 「でも、僕もそう思うよ。遊星はなんでだか、十代のこととなると落ち着きがなくなるよね」 とうとう遊星の味方はゼロになった。遊星は唇を噛んで皆の言葉を聞いていたが、やがて「……ああ、少し、熱くなり過ぎた」と非を認める。ジャックの手が十代を遊星からぐいと引き剥がして、彼は十代にやや複雑そうな面持ちで最後にこう言った。 「行け、十代。こいつは一度冷静になる必要がある。そしてその情報とやらを出来る限りふんだくって帰って来い。いいな」 「しかしなあ……」 ヨハンが電話で言っていた「遊星脳内劇場」のことを嫌でも思い出してしまって苦虫を噛んだような顔になる。一体遊星の中でヨハンはどういう人間に映っているのだろう。ヨハンのことをそういうふうに卑下して見られるのは我慢ならなかった。優しいただの善人なのに、なんだってあんな野獣みたいな扱われようをしなければいけないのかがわからない。 籠に豆腐を放り込んで悩ましげに息を吐く。ヨハンが「十代のご飯ならなんでもいいけど敢えて言うなら日本食がいいな」とにこにこ顔の絵文字付きでメールを寄越していたので、今晩のメニューはすきやきだ。後は朝食用にめざしと納豆。和食ではなく日本食と言ったのが運の尽き、外人は納豆嫌いが多いが十代は好きなのでちょっとした仕返しの意も含めて無理にでも食わせようというそういう魂胆なのだった。世の中美味い話ばかりではない。つまりそういうことだ。 「……寂しいのかな、あいつ」 意地の悪いことを考えていると少し同情心がわいてきてそんなことを思う。五年前からずっと、二人で暮らすための家で一人っきりで生活しているというのが本当なら、それは相当にわびしいものだろう。あの家にはあらゆる調度が「二人分」揃えられていた。皿もグラスも二つあったし、ソファはそれこそ子供がいても余裕そうなファミリーサイズだった。スリッパもエプロンも、明らかに客用ではないものがペアで揃えてあった。ベッドだけは一人身には大きすぎるぐらいの気持ちで済むかもしれないが、それにしたってずっと二人で使ってきたのだとしたら喪失感を喚起させて仕方ないだろう。嫌ではないのだろうか。 そうして、いつも「いないもう一人」の存在に圧迫される家が、あの男は嫌ではないのだろうか。 「まあそれが免罪符になるわけじゃもちろんないんだけどさ……」 最後に生鮮食品コーナーで野菜を籠に入れてレジへ向かう。たまにはあの一人には広すぎる家でせめて二人で過ごしたいという気持ちには賛同してやらないこともないし、そのぐらいしてやってもいいかなと寛容に思える。別にベッドが一つでも、そんなことは大した問題じゃないだろう。ヨハンはそういう目をしていなかった。ただ、大事で壊したくないものを見る顔をしていた。 「……なんだよ、これ。恋人ごっこかっての……」 恋人ごっこ。恋人のふり。恋人の代わり。ヨハン・アンデルセンのいずこかへと消えてしまった奥方の代替。そう考えると奇妙なものだったが不思議とその関係性を嫌悪する気にはなれない。どんなふうにヨハンが十代に接してきてもあの男の中で「奥方を想う気持ち」は決して揺るがないのだと根拠もなく言い張れる気がしてくるのだ。 あの男はきっと、馬鹿が付いてしまうぐらいに生真面目で、誠実なのだろう。親友の不動博士のように。 だから恋人ごっこでもいいかなと十代は思った。流石に、突然何の前触れもなく平然と風呂に入って来られるのは勘弁願いたいが。 『るび、るびー!』 『くりくりー!』 面倒な認証手続きやらなんやらの末辿り付いたその家の玄関戸を開けると真っ先にルビー・カーバンクルが飛び出てきて、待ちわびたというふうにハネクリボーにじゃれついた。一通りごろごろし終わると尻尾と羽根を触れ合わせて挨拶を交わしている。微笑ましく思って下を向いていると不意に頭頂部に触れられて、驚いた勢いで跳ね上げてしまった。 「お帰り十代」 「あ、ただいま……って違うだろ! それはそうと鍋でっかいのある?」 「あるある。どうぞ好きに使ってくれ」 「じゃあ出しとけ。適当にやるから、なんか手伝えよ」 「了解」 スリッパに履き替える際に床に置いたスーパーの袋を手に取ってヨハンがすこぶる機嫌良く頷く。今にも鼻歌を歌い出しそうなぐらいに上機嫌だ、などと思っているうちに本当に歌い始めた。十代もよく知っている。ふわふわして少女めいたメロディラインには馴染みがある。あの日遊星号に乗って十代も口ずさんだものだった。 「……旅に出たくなるよな、その歌」 「うん? 俺は郷愁の念を思い起こすけどね。俺の好きな人がよく歌ってくれた。『私のお気に入り、マイ・フェア・べィビィ』ってね」 「ベビー?」 「昔ね」 はぐらかしてヨハンは曖昧に微笑んだ。また、寂しい笑顔だった。通り過ぎた過去を懐古して冷えた木枯しを浴びているような表情だ。郷愁の念、というのは単に口を突いて出た言葉というだけではないのだろう。 十代は追求をしないことにして、それからエプロンを着て振り返った。以前にも身に着けた赤いエプロンは、買い出しの荷を置いて自らも青い紐を後手に蝶々結びにしているヨハンのエプロンと同じデザインで、「またペアルックなのかよ」と冗談めかして言うと彼は「まあね」と目を細める。 「さて、調理はどうすればいいのかな。シェフのお任せコース? 見たところ、この材料だとすきやきあたりが出来そうに見えるけど――うん、まさかと思うけどめざしと納豆を鍋に放り込んだりはしないだろうな」 「お前一人が食うんならナイスアイディアだと手を叩く所だけど、俺も食べるからな。そんなゲテモノ調理はしない。闇鍋ってろくな鍋にならないんだ」 「ああ、序盤からショートケーキとか入ると壊滅的だな。じゃあ俺はネギでも切ってるよ」 「妥当なとこだな」 それぞれに食材とまな板、包丁を用意してシステムキッチンに並んで立つ。言うまでもないが、どう見積もってもキッチンは一人暮し用の慎ましい設備には見えなかった。四つ並んだIHコンロ、広々とした流しに作業空間。人が二人ぐらいは並んで作業出来ること前提にデザインされている。 ヨハンの手が十代の腰に触れて、そしてすぐに離れた。緩く結ばれていた紐がしっかりと結び直されたのだろうということはそれなりにすぐわかった。 ◇◆◇◆◇ 「うわぁ……なにこれ。遊星がマジだぜ……」 メインモニタの他に、普段は使われていないサブモニタが無数に壁に吊られている。恐ろしいことにその全てが別々の映像を映していて、見るからに合法的に手に入れられそうな映像ではなかった。 学校や大通り、ダイダロスブリッジモノレールの駅舎内、ショッピングモール、デュエル・アカデミアエントランス、その他おびただしい数のネオドミノシティ内部映像を次々と映し変えているサブモニタ群のうち、割合中央に配置された一枚だけが映像を切り替えずに定点で一ヵ所を追っているようだった。なんてことのない、ありふれたチェーン店のスーパーだ。「毎日が大特価!」と書かれた紅白ののぼりがぱたぱたと風に揺れている。 「おー、面倒なとこに来ちまったなぁ。遊星はご覧の通りだ、何か用があって来たんだったら諦めてくれ」 「ううん、特にこれといった用はないからいいんだけど。遊星は何をどうしたああなっちゃったわけ?」 「今ここにいない奴がいるだろ」 「ジャック……じゃないよね。大抵仕事でいないし。ってことは、十代?」 「遊星が異常なまでに敵視している例のアンデルセン博士のところに泊まりにいくんだと。情報交換をしにな」 「へー」 昨日十代が受けていた電話の結果なのだろうということは龍亞にもすぐわかった。だから交換して来る情報というのはつまり未知の組織《イリアステル》に関連したものだろう。上手くいけば一時凍結ということで落ち着いた作戦会議を再開出来るかもしれない。十代は友達と何かやって帰ってくるのだろうしいいことばかりだ。 しかしクロウは「そいつは楽観的過ぎるな」と龍亞の想像を一秒の躊躇いもなく綺麗に一蹴した。 「駄目だ、ああなると。聞く耳持たないって奴だ。十代がヨハン・アンデルセンのことを友達だと思っているのか、その逆がどうなのか、それは俺にはわからないがこれだけは断言出来る。不動遊星にとってのヨハン・アンデルセンは忌むべき敵であり得体の知れない不審者であり変態だ。真実は知らないが」 「よく知らない他人にすごい言い草じゃないそれ」 「理由はわからねぇがどういうわけか、遊星は十代に心酔してる。飲み潰れた十代を自宅に連れて帰ったところで対応は決まったらしい」 「……なんか、もう、どうしようもないね?」 「ああ。どうしようもない。アキですら五分で説得を諦めた」 暇そうに遊星の傍に立って緩慢にディスプレイを眺めているアキを後手に指差す。暇を持て余した主婦がワイドショーのゴシップをどうでもよさそうに見ているのに似た光景と、高速で鬼のように監視システムを組み上げる遊星が隣りあっている様はなんというか非常にシュールだ。まるで噛み合っていない。 ここまでくれば、遊星があんなにたくさんのディスプレイを用意して一体何をやらかしているのかということも自ずと推測が付いてくる。恐らく遊星は十代の行動を逐一回線越しに追い掛けているのだ。ある意味ネットワークストーキングである。流石に龍亞もちょっとばかり引きそうになった。 「……聞くの怖いんだけどさ、あの映像って……」 「パス、技術方面のことは俺に聞くな」 「あ、それなら僕が答えるよ。理屈はそんなに難しくないんだ。龍亞、ネオドミノは街中至るところに監視カメラが設置されてるって知ってるでしょ?」 タイミング良く現れてブルーノが解説を始める。彼はそのへんに置いてあったタブレット端末を起動するとペンを引き抜いてイラストアプリをアクティブにした。そのままさらさらと図を描く。本人の人柄が反映されているのか妙に可愛らしい図柄だ。しかし内容はまるで可愛いものじゃない。 「その監視カメラの映像はね、通常セキュリティの詰め所に送信されてるんだ。ものすごい量だから専門の部署があって、常時たくさんの監視員が交代交代でリアルタイムにチェックしてるわけ。並行して試験ロボAIも同種の作業に従事してるんだけどね……遊星はそこに堂々とハッキングを仕掛けて、映像データを傍受してるんだよね。それで通常十人ぐらいでやる作業を一人でやってるんだ。延々と」 「それさぁ、バレたら逮捕物じゃない?」 「普通はね。なんか、不動博士のスーパーアカウントでやってるらしいよ。あのシステムの開発者が不動博士なんだって。ここにスパコンが設置してあったのって、こういうことをやるためだったのかなぁってちょっと邪推しちゃったよ」 「あー、否定はしねぇ。昔片っ端からきなくさい組織を潰していった時に便利でなー……向こうのセキュリティを覗いたり乗っ取ったりウイルス流したりなんだり……」 うわあ、という声とうへえ、という声が重なって微妙な空気が三人を取り巻いた。遊星を敵に回すということはつまりそういうことなんだろうなと思う。対企業レベルの行動を取られた件のアンデルセン博士には御愁傷様としか言いようがない。これじゃあ、プライベートも何もあったものじゃないだろう。サイバーテロだ。不動遊星という男は、その気になれば世界規模のネットワーク・ハザードを引き起こせるんじゃないかと龍亞は考え、しかしすぐにその思考を追いやる。怖すぎてこれ以上考えたくない。 中央の十代を追尾しているモニタに映る場所が、スーパーから人速で移動を始める。十代の移動経路に沿って高速で映像を受信するカメラを切り替えているらしい。 そこで飽きがきて龍亞は一旦モニタ周辺を離れたのだが、二十分程経った頃にアキが「マンションに着いたみたいだけど、見る?」と気怠い声で手招きをした。 「アキ姉ちゃん、見る? ってそれいいの?」 「そんな見られて困るようなこと、十代に限ってないでしょう。遊星は何言っても止めないし。そうこうしてるうちに野次馬根性が出てきたって言うか……」 「えぇ……」 「でも、ちょっと気になるわよね」 「龍可まで何言ってるんだよぉ」 龍可がアキに賛同する姿勢を見せて「まあ、龍亞にはわからないよね」などと言う。途方に暮れる龍亞にクロウが「仕方ない、諦めよう」と声を掛けた。こういう物事への興味関心の差が分かり易く男女の差を表しているようだった。色恋沙汰が好きなのは昔から男よりも女の方と相場が決まっているのだ。 マンションのエレベーターに設置されたカメラから通路のカメラ、と切り変わって最後にモニタは室内映像に切り変わった。高級マンションによく設置されている室内完全監視カメラだ。外出で家人がいなくなる時などに一定のパスワードで起動させることが出来る防犯カメラの一種である。勿論平素は起動オフにしておくのが普通だ。これもネットワーク経由でハッキングして不法に起動オンさせたのだろう、どうやら遊星はセキュリティ不正アクセスのかたわらで民間警備会社にも侵入をしていたようだった。そういえば、海馬コーポレーションにもその手の部門が存在していたからその辺か。 モニタの向こうで、十代が軽くなった腕を伸ばしながら我が家を歩くような自然さでキッチンに消えていった。ヨハンはその後ろを代わりに買い物袋を持って追っていく。 遊星は無言で微動だにせずモニタを真正面に据えていた。天井に設置されていると思しきカメラは上アングルから、仲良く並んで作業をするヨハンと十代を映していて、その並びにはいくらも連れ添ったパートナーであるかのように違和感がない。仲の良い男友達というより、これではまるで、 「おしどり夫婦ってやつ?」 龍可に言われた言葉に思うところがあったのか、結局モニタを見ることにしたらしい龍亞がそんなことを言った。 「それか、カップルとか」 「それは男と女に使う形容でしょ! ……でも、そうね、私も否定はしないわ」 そんなに鮮明でない音声がスピーカーからぼそぼそと聞こえてくる。『あれ取って、あれ』『ああ、これね』『うんこれ。じゃ、そっちにさ……』モニターの向こうの会話はそんな調子で続いていて、音声だけでは要領を得ないものだった。代名詞だけで滞りなく会話を成立させようというのは並大抵のことではない。よっぽど息のあった者同士で、互いを完璧に把握していないとそれは難しい。例えば龍亞と龍可なら大体はそれでまかなえるだろうが、遊星とアキだと全てにおいてそうはいかないだろう。こういう調理の場面ならともかくアキには遊星がどんな工具をどんな工程で必要とするのかが分からないことの方が多い。 モニタの中の二人は手際良く調理を進め、それほど時間を掛けずに鍋の下準備を完成させて食卓に着く。それまでの間に数回、「カチッ」という冷たいクリック音が遊星のいる辺りから発せられた。その音が鳴るのはヨハンが十代の頬に付いた液体を拭い取っている時であったり或いは食材を受け渡している時であったり、更には何の気なしに横を向いて二人の顔の距離が息が掛かりそうなぐらいに近くなった時であったりもした。 「……で、これ、いつまで続くの? もう五時過ぎたけど」 俺お腹減ってきちゃったんだけど。学生服のままの龍亞がぼやく。学校帰りでポッポタイムに寄ったから龍亞も龍可も、ついでにアキも制服姿のままなのだ。普段ならまだ夕食を気にする時刻ではないが、目の前で匂いこそないものの湯気をあげ始めた料理を見ていたために龍亞の胃袋はそう大人しくしていられないらしい。 「ねえ龍可、帰んない? どんどん腹ぺこになってきたんだけど」 「わかってないなあ、これからいいところなんじゃない。ご飯食べたいんなら龍亞一人で帰ってよ」 「やだよ、直帰ならともかく遊星のとこに寄ったのが明白な時間に一人で帰るとママにどうして龍可が一緒じゃないのかって怒られるんだもん。ねえ龍可ぁ」 「今日はポッポタイムに泊まるからって言っておいてよ。どうせ明日は学校お休みだし」 「るーか!」 「困るんだってほんと!」と弱り顔で言うが龍可が聞き入れる様子はない。見かねて遊星に干渉しないために敢えてコンピューターから距離を置いていたらしいブルーノが耳ざとく龍亞の方へ寄ってきて肩を叩く。 「じゃあご飯作るから、龍亞手伝ってよ。もし泊まるのなら二人一緒に泊まっていくって、ちゃんと僕や遊星の方からご両親に連絡しておくし。どうせ今日はベッド一つ、空いてるしね。クリーニングしておけば十代も怒らないよ」 「あ、うん。ありがと、ブルーノ」 「遊星はともかく、アキさんと龍可ちゃんはそのうちお腹が減ってきてモニターから離れる時があるだろうしね。ちょっと多めに作っておこうか。それがいいよ」 「なんか今日のブルーノ、すごい頼もしく見える。いつもの何倍も頼れる感じ」 ブルーノの提案に龍亞は目を輝かせた。ブルーノは、「いつもは頼れないと思ってるの?」という質問をぐっと喉の奥に押し込む。 今はきっとそれがいい。 ◇◆◇◆◇ いただきますの声と共に二人で手を合わせて、それから箸を取った。ヨハンはそこらの若い日本人よりも大分綺麗な手付きで箸を操っている。日本びいきの外国人というものはまず箸の持ち方を外すことはないとどこかで聞いたような気がするとぼんやり思った。日本の子供は箸の修練を嫌がるが、ヨハンのような手合はまったくの逆なのだ。 「それで、本題に入ろうじゃないか。教えてくれるって言ったよな。例の『イリアステル』とやらについてお前はどこまで知ってるんだ? あいつら、何者なんだよ」 「せっかちだなぁ……もうちょっとゆっくり食事を楽しもうって気はないのかい?」 「俺はお前と飯を食いに来てるわけじゃない。それは情報提供の見返り。交換条件」 「……作ってる時は楽しそうだったのに」 「作ってる時はそういうこと考えてねえもん。余計なこと考えて作ったら美味しくはならないだろ」 真顔で言ってやると何故かくすりと笑まれた。嬉しそうな表情だ。今のやり取りのどこに喜ぶ要素があったのかわからず、十代は怪訝な顔になる。ヨハンは遠い過去を懐かしむように対岸の十代に視線を寄越した。今の、記憶喪失の十代には奇妙なバランスで二つの「十代」が入り混じっている。 彼の外見はもう随分と長いこと変わらない、「異世界の後の遊城十代」、寂しい大人になってしまったあの青年のものだった。しかし精神の有り様はその限りではない。少なくない箇所に「無知であった在りし日の遊城十代」、よく笑う子供だった少年のままの部分が散見される。それは大人になった彼が自らに課した戒めの反動として損ねられたものだ。彼が失った記憶にはそういったものが含まれていたから、その過去と今が混ぜ合わさったかのような不可思議な姿が形成されたのかもしれない。 「どっちにしろ可愛いことに変わりはないけどな、うん」 「……は?」 「ん、一人言。ところでちょっと口を開いてくれないかな」 「え、ああ、うん」 特に何を疑うこともなく豪快に口を開く。ヨハンは鍋の中から火の通った肉を摘むと割って混ぜたばかりの卵が入っている自分の椀に通して十代の口まで運んだ。意図に気付いた十代の目が非難がましく変わって、威嚇するように睨んでくる。その眼差しを可愛いなぁと感じる自分がいて、ヨハンはもう病気だねこれはと内心呟いた。十代を好きになった日から、多分ヨハンは今までずっと病を患っている。恋患いなんてものよりももっと性質が悪くて、しかし純粋なものだ。 「なんだよそんなに嫌? 恥ずかしがることないのに、ほら、あーん」 「馬っ鹿なんじゃねえの?! いきなりこの展開に付いてこいとか、傍若無人にも程ってのがだな、」 「そうだな、自由人とはよく言われる。それより肉が冷めるから早く食べてくれよ」 「なんで赤の他人の、それも男の箸から食わなきゃいけないんだよ! それはお前が食えってば、自分で飯ぐらい食えるから」 「諦めが悪いなぁ」 ア段を発音して一際大きく口が開いた隙を見計らって箸先をその中に押し込んだ。変なところで律儀な性格のこの青年は、ほんの少しでも一度口を付けたものは押し返してきたりしないはずだ。期待通り、十代は観念したような顔をしてヨハンの箸から肉を飲み込んだ。じっとりとした瞳で、しかし頬は薄く上気している。恐らく羞恥からくるものだ。昔から十代はこういうあからさまな惚気に似た行為が好きではなかった。 「もう二度とやるな」 咀嚼し終えた十代の言葉は棘が立っていた。 「食べ物を粗末にするのは嫌だから食ったけど。俺は、……お前の恋人でも奥さんでもないんだ。一晩ぐらいなら多少は代わりになってやってもいいかなって思ったけど。それだけで」 「悪かったよ。もうやらない」 「でも今わかった。本気じゃなきゃ失礼だ。俺はお前と友達にならなりたいって思うけど代役は多分もう無理だ。今のでわかった」 「誰も十代に『誰かの代わり』なんてさせようとしないさ。君の代わりも、君が代わりを出来る人間もどこにもいない。そうだろ?」 「……わかってるんならああいうことやるなよ」 「出来心だった。悪かったって」 ひらひらと手を振る。「反省してないだろ」と凍り付きそうに低い声音で問われるがそんなことはない。心外だ。 仕方なしにヨハンはそれで口を噤むことにして、前振りの説明だけをして十代にお伺いを立てることにする。 「イリアステルの話だけど、資料も出したいしご飯が終わってからでいいかな。あんまり、楽しい話じゃないし。せっかくの手料理を不味くしたくは君だってないだろ」 「……なら片付けも終わってからな。お前のその言い分だと、話が終わった後に洗い物とかする気分にはなれなさそうだ」 「話が早くて助かるよ」 「必要なことはな。きっと昔からそうだったんだろうさ。あんま覚えちゃいないけど、俺はきっと昔っからああいうふうなおふざけは嫌いだったんだよ」 ぶっきらぼうに言う。驚いたことにヨハンはそれに大いに頷いて、十代を肯定した。十代は目をぱちくりさせる。この男のことだから、多分また何か言い返してくるのだろうと踏んでぞんざいに言ったのにこれじゃ拍子抜けだ。しかしヨハンの顔はとてもふざけている様子ではなくて、十代に肉を食わせようとしていた時の表情と比べると何倍も厳しかった。 思わず息を呑む。この高低差は、十代の見知ったものだと不動博士のものと良く似ている。 「そう。君は君でしかない。遊城十代は遊城十代でしかないんだ」 ヨハンの口調は言い含めるかのようだった。自分自身にじゃない。――十代にだ。 食事の後、ダイニングからリビングのソファに場所を移して二人で並んで座っていた。例のファミリーサイズのソファだ。ヨハンがぴったりと詰めて座ってくるものだから、両サイドに結構な空きスペースが出来てしまっていた。割合密着しているから手を動かすと腕同士が触れてしまい、少し気恥ずかしい。 ソファの正面には大型のテレビが設置されていて、今はさらにそこにノートパソコンが接続してあるらしい。ヨハンが膝の上で操作している機械のモニタと正面のモニタには同じ映像が映っていた。遊星も似たようなことをよくやっているが、このような技術の認識にはまだ慣れない。コードで繋がっているのならまだしもワイヤレスだ。やっぱり、この時代の人々と自身の中には技術認識の差があるようにしてならない。 手持ち無沙汰になって、足を意味もなくぶらぶらしているのも行儀が悪いからと黙って操作をしているヨハンの顔を身を屈めて下から仰ぐように覗き見た。かちんと目が合う。エメラルドの瞳。いつか見た海の色のような。 「もうちょっと待ってて」 「具体的に」 「三分前後」 小気味良い返事を受けたはいいものの暇であることに変わりはない。十代は横を向いたままヨハンを眺めていることにする。やっていること自体は作業中の遊星とそう変わらないはずなのに、そこから受ける印象はいくらも違っていて新鮮だった。 機械弄りをしている遊星というのは、いつもどこか少年めいた印象を持っていた。玩具遊びが楽しくて仕方ない少年のような気配が大なり小なり彼の背からは感じられたのだ。機械が好きで好きでたまらないというイメージだ。十代からすると機械と向き合っている不動遊星はどこかしら可愛いと思える存在だった。たとえどんなに高速でキーを叩き込んでいたとしても。 一方で機械に向かっているヨハンの表情はそういったものではなくて、仕事をしている大人の表情だった。眼鏡を掛けているせいもあるかもしれない。モニターに向けられている眼差しが凛々しいなぁとぼんやり思う。 (俺のこともそういうふうに見ればいいのに) 黙ってそうしている分には、ヨハンという男は申し分のない、美しい顔立ちの男だった。一度唇を開いてしまうと駄目だが、閉じていれば、嫉妬するぐらいに整っていた。日本人特有の野暮ったさがないからそれだけでスマートに見える。前回見た限りでは洋服の下はそう単純ではないみたいだが。あれはスマートと言えばそうなのかもしれないが、まじまじと見つめることが憚られる程にしっかりと鍛えられていて見るに耐えないのだ。十代の方が恥ずかしくて根負けしてしまう。 (変なやつ) 本当に、心底、なんて変なやつなんだろうと思った。馬鹿みたいににこにこして十代に手を振るくせ、いざ相対すると酷く寂しそうな顔をする。理解の付かない行動を取るのに、話させてみると理路整然として頭の良さそうな話をする。いなくなった奥さんをずっと待ってると言ってるのに十代に妙に積極的に好意を向けてくる。だけど彼は何も偽っていない。ヨハン・アンデルセンは彼の伴呂を愛していてなおかつ遊城十代に微笑み掛けるのだ。 (……どうして) そこで思考を振り返って十代は愕然とするのだった。途端に訳がわからなくなって、もつれてくる。判然とせず、自分がわからなくて、頭を抱えたくなる。隣にいる男は――そう、男だ、紛うことなく――妻を持っていて、そして十代は記憶喪失のどこから来たかもわからない男なのだ。 異邦人だ。出自もわからず、今のところ以前までに送っていた生活への手掛かりもない。 (ああ、でも) でも全くのゼロではないような気がする。度々ヨハンはかつての自分を知っているふうな素振りを見せることがあって、さっきもそうだった。思えば初めて声を掛けられた時もかもしれない。 「ああ、やっぱり」「記憶喪失か」と少し落胆したように、思い返してみれば確かに彼は口にしていた。 「準備、出来たぜ。前見てくれ」 「あ、ああ」 「イリアステル、の語源は遊星君あたりが教えてくれただろ。世界の始まりから終わりまで全てを知っている世界の摂理のことだ。彼らはある種の皮肉の意味を込めて自分達をその名で呼んでいる。……十代、イリアステルはな、未来人なんだ。平たく言えば」 まずモニターに映し出されたのはどこかのウェブサイトだった。《イリアステル》という項目名の下につらつらとやたらと難解そうな文章が記されている。十代は目にして三秒でその読解を諦めて視線を下に動かした。次の項目には《ウロボロス》とあり、どうやらあいうえお順でその手の専門用語が連ねられているようだ。 ウロボロスという単語はイリアステルと違って聞き覚えがあった。いつだったかのカード・パックのタイトルだ。「破滅の邪龍ウロボロス!!」、キャッチ・コピーは「闇に染まりし三匹の禁断の龍が破滅をもたらす」。パック最大の目玉カードが「ヴェルズ・ウロボロス」という効果モンスターで、確か禍々しい黒い三つ首の龍が描かれていた。 モニターの画面が切り変わってウロボロスが十代の視界から消え去る。ヨハンの中ではこれは然程重要なワードでもないらしい。 「それでこれが当日の海馬ランドの監視カメラ映像。不動に頼んで出して貰ったやつ」 ムービーが再生を始め、音割れしたガヤがスピーカーから流れてくる。ハロウィーン装飾が施された園内でごった返している人混みの中から見知った双子の片割れが飛び出してきて、誰かと勢いよく衝突した。赤毛の少年だ。長い髪を三つ編みにして束ねている。 少年が龍亞に何か話し掛ける。次の瞬間、あっと思った時には龍亞は街路の壁に打ち付けられて座り込んでおり、赤毛の少年は画面から消え去っていた。 「該当する監視カメラ映像はここで終わり。このすぐ後に君が到着して、後は俺より君の方が詳しいだろ」 「あの、龍亞とぶつかった奴はどこへ消えたんだ」 「わからない。カメラには龍亞と衝突したその前後数秒しか映ってないんだ。どこからともなく現れて一瞬の後消滅した。人間の技じゃない。かといって、龍亞と接触している以上幽霊ってわけでもない。わかるだろ?」 「いや、わかるだろ、ってしたり顔で言われてもさ……突然幽霊ってなんだよ。オカルトって、俺、あんまよくわからない」 「なんだろう……十代にそう言われると俺はとても自信がなくなってくるよ……。でも未来人、っていうのは間違いなく確かなんだよ。現に彼らは時間を止めているんだ」 「お前、頭おかしいんじゃないのか」 「いやぁ、それほどでも。あのな、技術ってのは常に最先端が民間に解放されてるわけじゃないんだ。時間操作は不可能な技術じゃない。KCでもその辺の研究は進められてる」 そう言いながらヨハンは画面に何やら資料らしきものを表示した。グラフや専門用語が乱舞する難解そうな文章がずらっと並び、画面を埋めて圧迫してきている。十代はくらっとくるような眩暈を覚えて目蓋を閉じた。こういうのは苦手だ。すごく。 「結論だけ言うとだな、時空渡航は可能なんだ。で、検証の過程は色々あるわけだがそこを更にかいつまんで言うと先の結果になるってわけ。イリアステルは未来からの使者であり、そしてここからは憶測になるがパラレル・ワールドの存在である可能性が高い」 「……あ、」 『あいつは多分、俺のことを知ってた。龍可のこともチームの皆のこともきっと知ってる。……世界を操ってきた、って言ってたけどそれってもしかしたら歴史を弄るってことなんじゃないかなあ? 俺は知らないのに向こうが知ってるってことは、パラレル・ワールドから来たのかもしれないじゃん』――龍亞の言葉が甦る。ヨハンは無言で頷いた。全てを見透かしているように。 「龍亞は、他に何か言ってた?」 「えっと……」 昨日、海馬ランドでまだ少し震えながら龍亞が口にした言葉を記憶の中から手繰り寄せる。『名前はわかんない。変な奴だった』『信じられないかもしれないけど、時間を止めて……』『俺のこと、すごく憎んでるって』。得体の知れない少年を恐れていたその言葉の次に、龍亞はこう続けたはずだ。 「『あいつらの子供だから嫌いだ』って言われたって」 恐れながら、しかし不思議でたまらないといったふうに龍亞は言ったのだ。自身の父と母が何故そのように糾弾されなければならないのか、理不尽でどう反応したものか対応を決めかねているようでもあった。 それきり黙り込んで、俯いてしまう。龍亞の表情に浮かんでいたわかりやすい怖れとそれから憐憫。――『それから『敵だ』って言った。でも、あいつ、なんか可哀相で』――龍亞は赤毛の少年を憐れんでいた。少年を可哀相がる龍亞も、可哀想と思われる少年も、不自然で歪で嫌だった。 口を閉ざしてしまった十代を眉を顰めてヨハンが覗き込んでくる。反射的に体を起こすと鼻と鼻がぶつかりそうなぐらいに近くなって、慌てて距離を取る。ヨハンは名残惜しそうに目を細めて、しかしそれに関して何か言うことはせずに指を機械に戻した。 「で、それ、確かなのか」 平坦な声で横目に尋ねられた。 「龍亞の聞き間違いじゃなきゃ確かだよ」 「……うわ、そういう理由なのか」 がっくりと溜め息を吐きながらヨハンはまた画面を操作する。「チーム・ファイブディーズ」と注釈の付いたスライドが現れ、そこにはチームの皆の写真が行儀良く整列して収まっていた。 写真の中には、揃いの青いブレザーを着て並び歩いている遊星やジャック、クロウ、それからまた別の写真にアキや双子も写っている。十代が知らない姿だった。当たり前だが遊星にも学生であった頃が存在したのだ。ジャックにも、クロウにも。 恐らくヨハンにも。 「この写真で一体何を説明するつもりなんだ」 「いやぁ、まあ……あのさ、違和感、ないか? デュエル・アカデミアは基本的に資産家の子女が通う学校だ。よっぽどの才能があるんならまた別だけどな……『この写真の』遊星君はその双方の条件を満たしてこの学園に幼稚舎から十五年在籍して一昨年卒業したわけなんだが、」 「それのどこが変だって言うんだよ。大体お前、どこでこんなもん……あ、不動博士か」 ブレザー姿の遊星を見ても特に思うところなどない。敢えて言うのならば、同じ青であるのに今彼が着用している作業着より似合っていないように感じるぐらいたったが、それは馴染みがないせいだろう。 十代の言葉が途切れると、接続を切ったらしく唐突に大型のテレビディスプレイが映し出す画面が一瞬ぷつんと切れたように真っ黒になって、すぐに別の映像を流し出した。オーケストラによるクラシック演奏がスピーカーから流れてくる。横を向くとヨハンは何やら一人で納得してうんうんと頷いていた。 「そっか。それなら、それでいいんだ」 「……いいって、何が」 「こっちの話。――イリアステルに関しては未知の情報が多いから今のところはこんなもんだな。少なく感じるかもしれないが、ま、我慢してくれ」 「最初から魂胆はなんとなく見えてたから別に今更少ないとかは言わない。いいよ。お前は嘘を吐いたりはしないだろうから」 「そう思う?」 「なんとなく」 十代の「なんとなく」を繰り返すように口先で呟いて、ヨハンはそのエメラルドの双眸でじっと十代を見つめた。どきりとする。それから彼は「うん。そっか」と言って幸せそうにはにかんだ。嬉しくて仕方ないといったふうだが、しかし手放しで喜んでいるわけでもないようだ。口元にそこはかとなく緊張が浮かんでいた。今までヨハンが緊張して喋る様子というのを見たことがなかったから新鮮に感じる。ヨハンはなんでも自信満々に言い切ってそしてやり遂げてしまう、そんな印象があったからだ。初対面で十代を強引に誘った時だってどこにも緊張の色なんてなかった。 「それじゃ、もう一つ話を聞いてくれないか? 別に難しい話じゃないんだ。イリアステルとは関係ないけど……俺にとっては大事なことで、そしてすごく単純明快ななことさ。君はただ黙って聞いていてくれれば俺はそれで構わない」 「ふぅん。別に、付き合ってやってもいいぜ。言えよ」 緊張の色が伺えるだけでなく、今度は躊躇いがちに言葉を紡いだりなんかする。少し面白くなってきて、十代はよく考えもせずに二つ返事でオーケーを出した。ヨハンがほっとしたように安堵の色を表情に乗せる。 「うん、本当に簡単なことだよ。俺が好きな人の話だ」 「……へえ?」 ヨハンが好きな人、それはつまり彼が愛しているらしい例のいなくなった奥方のことだろうか。しかしそれで十代に対して緊張する理由がわからない。何となく妙な予感がして十代はソファに備えてあるクッションを強く引き寄せて握り締めた。隣に座り込んでいる男はその様子に何も言わず淡々と話を続けている。 真横に置かれたルームランプの明かりに浮かび上がるヨハンの横顔に既視感を覚えた。いつか見た、触れそうなぐらいに近い横顔。だけどこの前一緒にいた時に目にしたわけじゃない。もっと、ずっと、昔に―― 「俺はその人のことを五年前に離れ離れになってしまってからずっと探していた。長い間手掛かりの一つもなくて、俺には指輪一つだけが残された。それでもまあどこかで生きていればまた会える時もあるだろうと構えることにしてたんだけど、望みは薄かった。それが最近、ふとしたきっかけで、再会が叶った。その人は俺のことをまったく覚えていなかったけどまあそれも想定内ではあったからそんなにショックではなかったかな。とにかくこれはチャンスだと思ってさ。もう一度恋をしようと、恋に恋する少女のように馬鹿みたいに純粋な恋愛がしたいと俺はそう考えたわけ。 幸いその人はその手の話に疎かったから俺の知らないところで恋人が出来ていたりとかそういうことは一切なかった。どころか興味ゼロだったみたいで、ああ変わんないなぁとか安心したもんさ。ただ嫉妬はしたかな。だって俺がいなくてもまるで何も変わらずに楽しそうにしてるんだぜ。うんまあ俺のこと忘れてるんだからしょうがないんだけどな。そこで俺はこいつはまっとうにアプローチをする必要があるなと踏んで行動に移ることにしたわけだ。幸い絶望的なまでに嫌われてるってことはなさそうだったし。……さて、それで俺の好きな人が誰かって言うとね……」 ヨハンは十代の方に向き直って一度口を閉じる。 そしてすぐに口を開いてまるで気負うことなく、明日何を食べようか、そう恋人に問う気軽さで言った。 「そう、十代、君のことだよ」 |