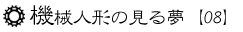静けき夜 巷は眠る
この家に 我が恋人は かつて 住み居たりし 彼の人はこの街すでに去りませど そが家はいまもここに残りたり 一人の男 そこに立ち 高きを見やり 手は大いなる苦悩と闘うと見ゆ 汝 我が分身よ 青ざめし男よ などて 汝 去りし日の 幾夜をここに 悩み過ごせし 我が悩み まねびかえすや 「ドッペルゲンガー」‐ハインリヒ・ハイネ(遠山一行 訳)
十六夜アキは不動遊星を愛しているのか? ――イエス。 不動遊星は十六夜アキを愛しているのか? ――これも、イエス。 不動遊星は遊城十代に恋慕しているのか? ――わからない。 ヨハンは遊城十代を真実愛しているのか? ――たぶん、イエス。 遊城十代は「彼」の、何でありたいのか? ――知りたくもない。 アキに連れられるままに足だけはせこせこと動かすかたわら、そんなことを思った。今一番考えたくないと思っていたことだった。向き合いたくなかった問題だ。遊星のそれを一過性と片付けることが出来ても、ヨハンのそれをそうと扱うことは出来やしないのだってことは十代が一番よく知っている。 アキは道中、沈黙を守っていた。彼女なりに複雑に思うところがあるのかもしれない。アキは近頃十代に異常な執着を見せている遊星の、正真正銘の彼女であり人生の殆ど全てを共にしてきた幼馴染だった。 やがてアキが「着いたわ。ここにしましょう」と十代に声を掛けるまで、漠然としたとりとめのないことばかりが頭の中を過ってはどこかに消え落ちていった。何を考えていたのか、後になってからではもうろくすっぽ思い出せそうにもない。 「座って。何か適当に頼んでちょうだい。多分話は長くなると思うから、それなりのものにした方が効率がいいと思うわ」 「お、おう」 「急いで連れて来ちゃったけどまさか無一文ってことはないわよね。ここ、結構するから」 「持ってる持ってる、パスならそこそこ残額入ってたはずだし! 流石に女の子に奢らせるとかさ、そういう情けなさ過ぎる真似は出来ねーって……」 「女の子、ねぇ……」 アキは意味ありげに言葉端を止め、値ぶみするように十代を眺め回して、 「ま、いいわ」 一人で納得したらしく、メニューを手に取って開いた。 ようやくのことでアキが足を止めたのはシティ繁華外のカフェで、昼過ぎということもあってか随分と賑わいを見せていた。十代もアキにならってメニューを開き、まず値段を確認する。貧乏人の性ってやつだ。今は遊星達に助けられて(そもそもチームの皆は出自が裕福なのだ)それなりの生活を送っている十代だが、身に付いているこういった習慣やふとした折に出てくる倹約術なんかを鑑みるに、記憶喪失前の生活はさほど余裕のあるものではないようだった。着のみ着のままが普通に有り得るんじゃないかという勢いだ。 だからそこそこ張るらしい値段に正直戦々恐々だったのだが、幸い、学生が背伸びをするぐらいのものだった。そういえばアキはまだ高校生なのだ。 「アキちゃんってさ、時々すごく大人びてるっていうか……なんだろな。遊星の保護者みたいだって思うよ」 「一応褒め言葉として受けておくわ。そういうあなたは、よくわからない人ね。子供みたいにはしゃぐかと思えば、生き字引のご老人ばりの年月を感じさせることもあるのよ。さっきみたいに男としての矜持を気に掛ける時もあればまるで女の子みたいな表情もする。いくつもいくつも顔があるみたい。仮面やマスクを次々付け替えていくように」 「……そうか?」 「だけども、その全てを集約させて、包み込み呑み込んで、それが『遊城十代』なんだわ。遊星にはそれが見えてないの。あの人、まだ自分にとって都合の良いとこだけ見てる。まるで子供だわ――私、そこも好きなんだけど。ところで注文は決まった?」 「……ああ」 ウェイターを呼んで注文をする。営業スマイルを貼り付けたウェイターの姿に、まあ自分にも仮面の一つや二つはあるだろうなと思った。十代も仕事をする時はああいう顔だ。 「話っていうのはね、他でもないあなたのことよ。ちょっと悪いとは思うんだけどね、昨晩あなたの動向をモニターさせて貰っていたの。でも遊星は責めないであげて。あなたに責められたら遊星は固まってしばらく使いものにならなくなると思うし」 「へ。モニターってまさか……」 「ええ、カメラ越しに全部。ああでもあなたが彼に告白を受けた辺りでカメラが壊れちゃったからその後は知らないわ。安心して」 「いやいや待って全然安心出来ねーし?!」 「遊星は、責めないであげてちょうだいね」 アキが凄みのある笑顔で念を押した。十代は気圧されて押し黙る。 「それを前提で話を進めるけれど――ねえ考えてみて十代。あなた、彼のこと、好きなの」 「……知らない」 「そういうの、いつまでも目を背けてるとどんどん面倒になるわよ。夏休みの日記みたいなものよ、そういう意味では。あのね、十代。少なくとも私には……」 唇をきつく結んでアキの顔を対面から見ていた。面白がっているふうでもないし、過敏になっているふうでもない。彼女はただ純粋に、まるで女友達の恋愛相談に乗るみたいな顔をして、当たり前のようにこう言った。 「あなた、恋をしている女の子みたいだって、そういうふうに見えたわ」 自棄食い用にケーキをもう一つぐらい頼んでおけば良かったとそんな思考が一瞬流れて、しかしすぐに掻き消えた。 ◇◆◇◆◇ 「少しは落ち着いたか。まったく、お前は、本当に……」 「すまない」 「馬鹿だ。頭脳は悪くないが、どうしようもなく阿呆で愚かだ」 「……すまない」 「血迷ったか遊星。あの男に何故そうも入れ込む? 十代は確かに見所のある男だ。加えてあの光景を見せられては俺とて警戒心がわくのはわからんでもない。だがそれにしても、なんだ、あの無様な姿は。餓鬼か」 「……」 「ふん。お前はいつもそうだ。昔から……上辺を取り繕うことばかり上手くなりおって。遊星、俺は何もお前を責めて終わりにするつもりはない。十六夜がいなくなって丁度いい、この件に関しては今この場ではっきりさせるぞ。俺達の精神安定の為にな」 腕組みをして尊大に立ち、ジャックは遊星を見据える。クロウとブルーノも頷いた。正直十代絡みのことになる度毎度毎度ああでは、たまったものじゃないのだ。遊星がどことなく惨めに映るようでもあった。 「見ていられん」 「ジャック」 「寝癖はどうでもいいから席に着け。話は、それからだろう」 バン、とテーブルを叩いて席に着けと示して見せる。《絶対王者》ジャック・アトラス、プロ・リーグの頂点に君臨する若き天才。レッド・デーモンズ・ドラゴンとともに広く知られている彼の二つ名を、今のジャックの所作は想起させた。チームの中である意味一番の発言力を持っているのは遊星を尻に敷いているアキなのだが、その彼女がいなくなった今、この場で最も迫力を持っているのは確かにジャックであると言えた。 ジャックはジュニアスクール時代からの遊星の腐れ縁だ。遊星が入学して初めて出来た「ともだち」だった。あの当時から尊大で、「いつかキングになる」と公言してはばからなかった彼はキツい物言いも多く、他者を見下す発言も時には不用心に飛び出した。それでも一度認めた人間には彼なりの礼節をもって接していて、遊星はその中でもライバルとして一目置かれているようだった。 そのジャックが、こうして遊星の身の振り方に対して怒って見せることはかなり稀なことだった。ひょっとすると以前に一度大喧嘩をした時ぶりのことではないだろうか? 黙って席に着くと、クロウが動作だけで臨席の伺いをジャックに立て、ぽすんと椅子に収まる。空気がどことなくぴりぴりしていていたたまれない。視界の端に十代が持ち帰って来たデイパックが映った。アンデルセン博士の家で、彼の所持品がかの場所の匂いを吸ってきたのだと考えるといやな気持ちだった。 いつから、こんなにみみっちい人間になってしまったのだろう。遊星は首を振る。わからない。性格は昔っからで、今になって急に発露したものかもしれない。 「……なあ、遊星」 「……なんだ」 「お前のそれは、一過性の病に似ていると、そう思う」 ジャックは開口一番にそんなことを言った。不自然に途切れる言葉からして彼なりに気を使って選んだものなのだろうということはすぐに知れた。 ブルーノが台所から人数分のコーヒーを持ってきて分配し、自らも席に着く。 「そうか」 「そうだ」 「俺は、やはり、変なのか」 「安心しろ。お前が変なのは昔からだ」 「そうか」 かたりと、少しだけ口を付けたコーヒーマグをテーブルに戻す。それから奇妙な居心地の悪い沈黙が辺りに訪れた。遊星は目を伏せって押し黙っている。他の三人は言葉を選びあぐねて思案しているらしい。クロウが顔を顰める。ブルーノも落ち着かないふうにそわそわしている。 かつての、チーム・サティスファクションの集まりだったならばこんな沈黙はそうそうなかった。あの頃遊星達は今よりももっと子供で、そして鬼柳京介という男がまず沈黙を許さないお祭気質の騒がしい男だったからだ。チームの誰一人として今みたいにうじうじとしていなかった。良くも悪くも、若気の至りという名前の暴力じみた実力行使が全てを解決してくれると無条件に信奉していた。 だが、あの好き勝手に暴れ回った日々から脱却して大人になったのかと聞かれるとそれには頷ける気がしない。結局遊星は本質のところでもう何年も立ち止まったままで、両手のひらで顔面を覆い立ち尽くしているんじゃないかとそんなことを思う。 子供のまま体だけ大人になっていく。チャイルディッシュで、怠惰なモラトリアム。挫折も苦難も試練も知らない甘やかされた自分。まだ終わっていない反抗期。中途半端だ。何もかも、あらゆる全てが。 遊星の顔から表情が消えていく。それを受けて静寂を破ったのは、やはりというか然るべきというか、ジャックだった。 「いいか遊星、よく聞け。性別を一度置いておいて話を考えるとする。例えば、だ。十代が恋をすると仮定するだろう」 「……」 「一つだけ断言出来ることがある。遊城十代という人間が、いつか誰かに恋をする時がくるとして、その相手は絶対にお前ではないだろうということだ。何故なら、お前は遊城十代にまっとうに恋していないからだ。お前のそれは酷くいびつで不完全な――崇拝感情だ。憧れをこじらせた、性質の悪い何かだ。たまにいるんだ、そういう奴は。向けられた好意に舞い上がって境界線を見誤ってしまう。盲目になってそれに気付きもしない。そういう意味ではまあ、恋に似ているかもしれないが。断言出来る。十代は不動遊星という男を『家族』『きょうだいのようなもの』『仲間』それ以上には捉えないだろう。それを、本当はお前だって知っているはずなんだ」 ジャックの言葉にあの日の父の言葉を思い出す。『きっとね、彼はいずれ遊星の前から姿を消すよ』『わかっているだろう? 彼は、君のものじゃないんだ』。 あの時それが酷く恐ろしい言葉だと思った。恐れたのはそれが事実だからだ。遊城十代は、あの太陽のようなひとは、不動遊星のものにはならない。宣告は呪いじみていた。悪夢に近かった。鋭利に研ぎ澄まされた、それは針のような釘だった。 心臓を今にも貫かんとする致死量の劇薬に似ていた。 「なんだか遊星、今酷い顔してるよ。有害薬物を摂取し過ぎて泡を噴く寸前みたいな表情。……心底怖がってる人の顔だね。そんなに怖いの、君は十代のことが」 「――死に至る病に似ていると。それだけ思った」 「うん?」 「絶望が人を殺すのならば、俺を一度殺すのは十代さんなのかもしれないと、予感がする。根拠はない。ただの勘だ。……あのな、ジャック」 遊星の瞳が珍しく陰って、申し訳なさそうに細められている。憂いる横顔に似ていた。それにジャックとクロウは顔色を変える。 遊星の「予感」はよく当たる。それはテストに出そうな単元、という簡単なところから、どこどこの方面に嫌な予感がするといった事故の想定まで幅広く、とかくよく当たるのだ。その遊星がそんな不吉なことを言う。遊城十代が不動遊星に絶望を与えると。その言葉の羅列は妙な生々しさを伴ってその場の人間の胸の内に迎え入れられた。冗談の類ではなく、本当に起こり得るものごととしてだ。 遊星の予感は予言と同質だった。 「俺の十代さんへの感情は、恋じゃあ、ないんだ。そういう手合いの愛情でもない。俺は、アキを見ると可愛いと思うし、守ってやりたいとも思うし、きっと人生を添い遂げるのだとしたら彼女とだろうという確信がある。でも十代さんにはそうじゃない。お前の言う通り恐らくは崇敬して――いるのだろうと」 「……ほう? それでお前の導き出した結論は何だ、遊星」 「崇拝している偶像に己を否定された時、俺は多分、死ぬんだ。一度」 表情とは裏腹に声音は淡々としている。色がない。分かり切っている事実を機械が復唱するように無感情だ。 「あの人がもしアンデルセン博士のものになったとしたら……」遊星は原稿を読み上げるニュースキャスターのような調子で言った。「いずれ、あの人は俺を拒絶する」。 拒絶の後、不動遊星の固定概念は粉々に破壊され尽くす。砕け散って壊れる。信じていた世界は瓦解する。覆されてなくなって最後には消滅する。ジ・エンドだ。 「だから、あの人をアンデルセン博士に渡したくない。アンデルセン博士は全て見透かしているだろうから。あの人は、何か『へん』だ。それは十代さんに執着しているということではなく、存在が異質であるよう、思う。これから起こることが全部わかっているみたいに迷いがない。攻略本を読んでいるプレイヤーが操作しているRPGの主人公みたいに」 「それじゃなんだ、遊星はアンデルセン博士を未来人か何かだって思ってんのか」 「似たような何かである可能性は否めないと、割と本気で思っている」 「……マジかよ」 「大真面目だ。そうでなきゃ、こんなに恐れるものか」 その言葉は尤もだった。 ジャックとクロウが口を閉ざす。ブルーノだけは曖昧に頷いて、伏せ目がちにテーブルとコーヒーマグの間とで視線を行ったりきたりさせている。遊星が「ブルーノ」と声を掛けるとぴくりと肩を揺らしてすごく慌てたふうに「う、うわ、ごめん!」と反射的に謝罪の言葉を口から出した。 「もう昼だ。龍亞と龍可が多分、ここに出るに出られなくて困っていると思う。二人を外に連れ出してくれないか。遊園地でもショッピングモールでもなんでも。……話も、もうじき終わる」 「あ、う、うん」 「すまない」 「別に、全然構わないよ」 両手をひらひら振って「大丈夫」と笑って見せる。ブルーノのその表情に、今日初めて遊星は僅かにはにかんだ。「じゃ、声掛けてくるね」と席を立ったブルーノを彼と十代との相部屋の方へ手を振って送り、ジャックとクロウの方にもう一度向き直ると二人は肩凝りが酷そうな顔で溜め息を吐いている。 「ちびどもには悪いことしたかもなぁ」 クロウが言った。 「ま、でもこれで確かにお前が十代に執着する理由はわかったよ。ヨハン・アンデルセンを毛嫌いする理由は若干想像とは違ったみてーだけど……」 「まったくだ。もっとわかりやすい嫉妬か何かだとはじめは思ったぞ」 「いや、嫉妬は多少あるぞ。だが彼のように十代さんに接したいかと聞かれるとそれは違うな。あの人は十代さんのことを俺がアキを見るように見ている。俺には、とてもそんな真似は出来ない。あの人を守ろうとしても結局俺が守られてしまうに違いない。それを軽々とやってのけるアンデルセン博士が少し羨ましくて、そしてやはり苦手なんだ。あの馴れ馴れしい人は俺のことを父さんと同じような目で、きっと見ている」 子供扱いしてるに違いない、とぼやく。遊星を溺愛している父親の博士が息子をどのように思い、扱っているかは周知の事実であったから二人はああ、と若干同情めいた声を漏らした。不動博士は重度の親馬鹿だ。息子が成人した今でも「パパのかわいいゆーくん」「ゆーくんはパパの宝物なんだよ!」「ゆーくんパパとお出かけしようよ」などと言った言動を衆人環視の中で行うことをまるで憚りもしない。こればっかりは遊星が辟易するのもしょうがないことだと常日頃から思っているのだ。ジャックの親も、クロウの親も、高校に上がった頃から干渉が少なくなっていって今はよっぽどのことがなければ心配はしてくれるが、文句は付けてこない。 不動博士の過剰スキンシップアピールに比べればありふれた干渉の方が対処に困らないものかもしれないが。 「……十代さんは、怖い人だな」 「ん?」 「とてつもない力で人々を引き寄せるが、その視線はどこか一箇所にしか向かないんだ、結局のところ。そしてそれ以外の人間の価値観や信じていたものを気付かない内に滅茶苦茶にしてしまう。あの人は悉く他者を変革させてしまうんだ。良い方にも悪い方にも、引っ張っていく」 不意に遊星が零す。自分も既にその「毒牙」に掛かっているのだということを自覚して、自嘲めいていた。十代に変えられてしまうということは、つまりそういうことだ。十代に選ばれる人間というのは逆に彼を改革してしまえるようなそういう人間なのだと思う。モニター越しに見たヨハンの顔を思い出す。ヨハン・アンデルセンは間違いなく十代を変えてしまう側の存在だった。あの人を何度も何度も動揺させて、顔を赤くさせて。そんな芸当が出来る人間があとどれくらいいるものか。 二人が二人とも、他者を振り回さずにはいられない性質なのだろう。ただそれが、お互いに向け合ってみるとヨハンのベクトルが十代のベクトルよりもいくらか強力に出来ていたとか、そういうことなのだ。 そんなことをすらすらと思い描いてはっとして、だからこそ、今「怖い人」だとそう思った。 「遊城十代は――あのひとは、いつもそうだ。いつだって容易く俺の常識を粉々に打ち破っていってしまう。俺はきっとそれを知っているんだ。……でも、何故だ? 何故そんなことを『知っている』と俺が思うのか、それがわからない。だけど俺は十代さんのことを本当はもっとずっと昔から知っていたような、そんな気さえしている。一昨日龍亞が言っていたように。今、パラレル・ワールドが架空の理論ではないと言われたら簡単に頷いてしまうと思う。……教えてくれジャック。この思いは俺だけの思い過ごしなのだろうか」 「……遊星?」 「どうして俺は、こんなに『幸福』な生活を送っているんだ?」 今しがた気が付いてしまった「それ」が本当に純粋に不思議でたまらないというふうに遊星は言葉の鎌首をもたげた。 背筋を氷のように冷たい手のひらがなぜる。ジャックもクロウも瞬間立ち尽くし、目を見開き、それからかぶりを振った。答えなど持ち併せようがなかった。遊星は濁りのない深い藍の瞳でじっと二人を見据えている。その瞳は良く出来た硝子玉のように、ぞっとする程、うつくしい。 ◇◆◇◆◇ 「私の目に映るあなたはね、恋をする女の子のような顔をしてた。ライクかラブか、決めかねて迷っている女の子よ。男と女って恋の仕方が違うのね。そういう意味で、あなたの彼を見る視線は紛れもなく『女の子』のものだった。……自覚、ないかしら?」 「言ってる意味がそもそもわかんねえ」 「あら、言葉の通りよ。あなたが例の彼に恋してるように見えたってそう言っただけ」 アイスティーが入ったコップのストローに口を付けて、アキが有無を言わせぬあの視線を投げ掛けた。ぐっと言葉を詰まらせて視線を泳がせる。彼女のこの視線は、あることないこと洗いざらい全て吐かされてしまいそうで苦手だ。 アキは堂々とした少女だった。それは「十六夜アキ」という自己を拠り所にする確かな自信からくるものだ。今の十代にはそれがない。異邦人で、誰かに肯定をして貰えなければあっという間に崩れ落ちてしまいそうな脆い土台の上に立っている。それでもブルーノ程気弱ではないのは、恐らくは昔の自分がアキのように自信を持っていたことがもたらしたサブリミナルに違いなかった。 その「自信」がまぶしい。それさえあれば、迷いがこんなになければ、或いはヨハンにももっとはっきり答えを返せていたかもしれないと思う。 「恋とか、そういうの、形のない口約束みたいだ。アキちゃんが遊星にしている恋はもっとずっと強固な愛だけど、俺が? 自分が何者かもわかってない俺がそんな不確かなこと、思わないよ」 「少なくとも、アンデルセン博士は本気ね。私が遊星に向けるものに負けないぐらい、ひょっとしたらそれよりも余程強力に愛しているのだと思うわ。――彼のあなたへのそれは恋ではなく愛よ。私の両親や、遊星のお父さんとお母さん、そういった人達が抱いている稀有な感情。あの人、きっと十代が死にそうになった時は顧みずに飛び出すわね。そういう顔だったもの」 「……モニター越しで、随分しっかり見えてたんだな?」 「マンションのセキュリティがとびきり高解像度の海馬コーポレーション製だったことが逆に仇になったな、って遊星が」 「ああ、そういう……」 それはもう、はっきりくっきり見えてしまったことだろう。室内監視カメラをハックして強制起動させ、映像を傍受するとは恐れ入る。 それなら、とふとその可能性を考えた。ヨハンの左手薬指に嵌っているあの赤みを帯びたプラチナ・シルバーの結婚指輪。丁寧に磨き込まれた、優しい歳月を感じさせるものだった。一年や二年そこらのものではない。 「アキちゃん、それならあいつの薬指、見えただろ。あいつの結婚指輪だよ。後生大事に抱えてる誓約の形だ。俺なんかお呼びじゃない」 「あなたがその対になる一方を持ってたんじゃないの。空から落ちて来る前に」 「まさか。あの指輪は相当年季が入ってる。俺の年とじゃ計算が合わない」 「それを言うならアンデルセン博士の外見年齢もね。二人して二十代前半みたいな見た目してるじゃない。思ってるより年を取ってるってだけかもしれないわ。……それに、今のではっきりした」 「何が」 「十代、あなたやっぱり彼のこと気になってるのよ。だってそうでなきゃ指輪の状態なんてどうしてそんなに気に掛けなきゃいけないの? 少なくとも、私には今まで経験のないことよ」 だって遊星は指輪、してないもの。当たり前のようにそう述べる。彼女の琥珀の瞳にぎくりとした。見て見ぬふりをしていたところを一息に貫かれたような痛みが胸中を襲って、知らず冷汗が垂れる。 「しかも、性別ではなく年齢で否定をした。拒絶はしないのね、彼の好意を」 追い撃ちは止まる様子を見せない。蓋を次々剥ぎ取られて抉られていく、そんな心地だ。胸の痺れのような痛みが断続的なずきずきにとって替わられる。物理的な痛みでなく、甘い疼きのような精神的な痛みであることが辛い。 誘導尋問のようだった。成すすべなく袋小路に追い詰められて、いやいやとかぶりを振ることも許されずに目を背けていたものと直面させられるのだ。「好き」の反対は「嫌い」じゃない。反対は「無関心」だ。どうでもいいという消極的な感情だ。歯牙にもかけず視界にすら入らず、意識なんか毛程もしない、そういうことだ。 本当は知っている。 「だって。拒絶出来ないんだ。絆されてしまいそうになる。触られるの、嫌いじゃないし……」 「でも、好きじゃないのね。――あのね、別に好きだって無理に言わせたいわけじゃないの。『友達としては好き』なのか、『それ以上に好き』なのか、それが知りたいだけ。だからそんなに困った顔しないで。私が悪いみたいな気分になるわ」 「悪いとは言わねえけどさ、どう考えてもアキちゃんが絶対上位だろ、この状況……遊星がアキちゃんに弱いというか甘い理由、すごくよくわかったよ」 「嬉しいようなそうでもないような難しいこと言うのね、あなた……」 アキが溜め息混じりにぼやいた。でも本心だ。 咳払いを一つして、テーブル向かいの少女の機嫌を伺う。彼女はそれを見こしていたみたいに頷くと「そのことは別にどうでもいいから」、と続きを促してくれた。 「じゃ、例えばの話をするけど」 「ええ、どうぞ」 「仮に、俺がヨハンとくっついたとしてさ」 十代はゆっくりと、アキと自分二人に言い聞かせるように言葉を選ぶ。喉が乾いてからからしてくる。アップル・ティーソーダの入ったグラスは殆ど手付かずで、しかしここで飲む気にもならず、唾を呑む。 「もう散々にした気もするけど、キスしたり手を繋いだり、デートしたりしてさ、二人で一緒にいる、みたいなことになるわけだ」 「そうね。別にそういった行為の積み重ねが愛情表現の全てだとは思わないけれど、私が見た感じアンデルセン博士は好きそうね、そういうの」 「うん、俺もそう思う。……でもアキちゃん、それって変じゃないかなあ? 俺もあいつも、変えようもなく男でさ。若さ任せにしちまえる程子供でもなくて。あいつは真剣だし、俺はよくわかんないし……それでもアキちゃんは恋をしてるって、そんなことを無責任にも俺に言うのか」 「変、ね。それは確かに、変なことなんでしょうけれども……でもどうしてかしら、私の中でそれが変だって気がしないのよ。ずっと前から二人が一緒にいたみたいにふと思うの。それに別に無責任に、例えば遊星があなたに取られそうだからって口から出任せ言ってるわけじゃないわ」 「それは知ってるよ。アキちゃんはそういうことをしないし、第一遊星がアキちゃんから離れるってことがまず有り得ない」 近頃、遊星は十代に妙な執着を持っているのだという。クロウに言われたことだ。ヨハンに言われたことでもある。クロウ曰く、それはアキやジャックの立場からしても傍目に明らかなことであるらしかった。だがそれでも、不動遊星が恋をしているのは真実十六夜アキただ一人だけで、遊城十代ではないのだという自信がある。彼が十代を追う視線というのは、子犬が母親を慕って追い掛けたり、小鳥がよちよちと必死になって親にくっついていく姿に似たものだった。インプリンティングだ。まるで何かの条件付けを施されて、それをそうと思い込まされたみたいに。 インプリンティング、というのならば十代もそうなのかもしれない。ヨハンの声だとか、においだとか、果ては皮膚の温もりに至るまで、彼のどこをとっても拒絶の要素というものが見当たらないのだ。知っている、と触れられる度いつも思った。 そしてこの男は自分を絶対に裏切らず、最後の最後まで彼の全てを掛けて愛してくれるだろうと。 でも、と十代は心中で首を振る。そんなまやかしのように根拠のない思いに縋ってはならないと誰かが警告を発していた。愛されることは悪いことだと声高に主張をしている。ましてやあんな優しい人間の心をがんじ絡めにして独占しようだなんてあってはならないことだ、といきりたつ誰か。『知ってるんだ』、誰かは言った。『哀れで残虐な末路ってやつ』。 目を瞑る。「それに」、と切り出すとアキが瞬きをした。 「俺は誰かの特別になりたいとは思わない。駄目なんだ、そういうの」 「どうして?」 「だって、俺が――、俺が好きになって欲しいと思った人達は、皆……」 そこで突如言葉端が濁り、みるみる口の中で萎んでいく。アキが訝しんで怪訝な顔をするが、一度閉じてしまった唇をもう一度開くことは出来そうになかった。はたと思い当たることがあって立ち止まってしまう。意識が現実から遠くなる。 そう思うと不意に幻が現れて、十代の意識と視界の中をいっぱいに広がって満たした。アキの顔やカフェの内装、ついさっきまでそこにあった世界が消え失せて代わりに要領を得ない不鮮明な映像がフラッシュバックする。走馬燈のようだった。次から次へと右から左へ流れては消えていく。 頭が割れそうに痛い。きいん、と一際甲高い音が頭蓋の中で響き渡ると顔の一部が虫に喰われたようにぽっかりとなくなって削げ落ちた子供が現れて徐に口を開いた。 『俺が好きになった人、みんな、不幸にしちゃうんだ』 薄茶けた虫食いのフィルムの中で、幼い少年が誰に言うでもなく呟いている。がらんどうの頭部にはあるべきパーツが足りていなくて、空洞の中に唇だけがぽかんと浮かびあがりもぞもぞと形を変えて喋っていた。よく見ると欠けているのは頭部だけに留まらないらしく、左腕や右太腿、脇腹、そういった箇所にこれもやっぱり虫食いのように食まれた穴が空いていた。 『父さんも母さんもあんまり幸せそうじゃないし。オサム兄さんも、俺にデュエルしようって言ってくれた子達も皆駄目だった。例外なんかないんだ。翔も、明日香も、万丈目も剣山も吹雪さんもカイザーもエドもジム、オブライエン、みんなみんな俺が不幸にした。不幸な目に遭わせた。だからさ……』 独白を続ける少年の身長がぐんぐん伸びていって今の十代と同じぐらいになりそこでぴたりと止まる。振り返った青年の姿は少年のように酷い虫食いに苛まれてはいなかったが、代わりに哀愁を帯び、諦観していて、儚げで寂寞としていた。 十代とよく似たライトグリーンとオレンジのオッドアイが涙を流してちぐはぐに光っている。 『だから俺は、きっとヨハンも不幸にする』 遊城十代自身が十代に語り掛ける。『お前、本当の本当に信じているのか?』互い違いの瞳が「記憶喪失の十代」に向き直って言葉を投げた。目蓋を閉じる。聞きたくない、と反射的に思った。脳味噌にちくちくした痛みが走り、頭を抱えてしまいたい衝動に襲われる。 だれかたすけて、と泣きそうな子供が呻いていた。先程セピアの残像の中で泣いていた少年だ。今度はがらんどうの闇ではなく子供らしい幼いパーツで構成されたまともな顔を持っていて、ちぐはぐの瞳を持つ青年と隣り合って顔を腫らしている。失われた記憶の中のドッペルゲンガー達。過去の遊城十代の残像達はよく見ると檻の中にいて、今の十代とは隔絶されている。 『犠牲もなしに幸せになんてなれるわけがないのに。馬鹿なやつ』 光彩異色症の青年が言った。 『でも、ヨハンのこと好きなんだ。ばかみたい』 子供がとうとう、涙声になってそう言った。 走馬燈のような光景が終わり、また、雑踏のカフェテリアに戻ってくる。アキが名前を呼んで十代の前で意識を確かめるように手を動かしていた。余裕がなくて、酷く心配そうな顔をしている。 知らず、声が漏れた。すとんと胸につかえていたものが落ちていくような感触を覚える。吹っ切れたみたいに清々しく、しかしどうしようもなく苦しい。 「――あ、……そっか。そうなんだ……」 胸が痛くて、堪えきれずに目を瞑った。この感傷は初めてのものじゃないんだということを胸の痛みは告げているようだった。 「わかった……わかったんだ……」 「……十代?」 「少しだけ、昔のことを思い出した。はっきりした事柄じゃなくて曖昧でもやもやした気持ちの欠片だけど。俺、さ」 二人のドッペルゲンガーは知っていた。遊城十代が何を恐れなければならないのかを。犠牲と代償、絶望と覚悟、傲慢と愚鈍、そういったものたちがないまぜになって胸を圧し潰していく。 「ヨハンの、大事な人になるのが怖い」 そうしたらまたあの男を失ってしまうに違いない。そんな確信めいた予兆があってそれが恐ろしくてたまらない。 |