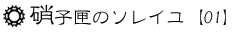「この世にはいくら考えてもわからない、でも、長く生きることで解ってくることがたくさんあると思う。
君たちも大人になればわかるさ。ある意味で、大人は子どもよりももっと子どもみたいになることがあるんだよ。」 スナフキン‐トーベ・ヤンソン
「オーゥ遊戯ボーイ、十代ボーイ、お久しぶりデース。先日は我が社のイベントに協力いただきありがとうございマース」 「ボクは何もしてないけどね。十代くんは大張り切りだったよ」 「いやー仕事ですから! 子供達と触れ合うのは好きだし。なんせ未来のライバル候補だもんな」 「頼もしい台詞デース。時に遊戯ボーイ、本題に入りましょう。本日ここに集まっていただいた理由なのデスが……」 「うん、聞き知ってるよ。ヨーロッパで起こっている『連続カード消失事件』だね。理由も見境もなく次々とカードが消えていく。ヨーロッパ連合、及びI2他名だたるカード産業関連企業は特別チームを発足させてこれの捜査にあたっているけれど目ぼしい成果はなし。被害は拡大する一方で現在の推定被害総額は数億にものぼろうとしている……『混沌幻魔アーミタイル』もそうだけど、『毒蛇神ヴェノミナーガ』や『ダークネス・ネオスフィア』はまずい、というか厄介だね」 「ブリリアント、素晴らしい情報収集能力です。私から説明するまでもありませんでしたね。――それで遊戯ボーイ、ユーのアンサーはいかがデスか?」 「この件には何者かの思惑が関わっているはずだ。奪われたカード達が悪用される恐れもある。ボク、武藤遊戯は捜査チームへの協力を表明します。十代くんは」 「勿論、俺も行きます。いいですよね遊戯さん、師匠」 十代が身を乗り出すようにして許可を求めた。遊戯とそばに控えた霊体のもう一人の遊戯が快く頷く。「うっしゃー!」とガッツポーズを決めた親友を、ペガサスの側に立って眺めていたヨハンは瞬間呆気に取られて、それから口で手を押さえながら大笑いした。本当にこの悪友は、あの頃から何一つ変わっていない。 彼は昔から喜楽を大袈裟に表現するきらいがあって、しばしば今のようにガッツポーズを取ったり飛び跳ねてこけることがあった。ムードメーカーであり、時にはペースメーカーともなった彼の回りにいつも人が絶えなかったことを覚えている。そのおかげで在学中は十代のそばにいると「また一緒なの?」と盛んに尋ねられたものだ。寄って来ているのはお互いさまだと思うのだけども。 ヨハンの視線に気が付いたのか、十代が掲げた右手を慌てて引っ込める。それから彼は遠慮がちに辺りを見回した。事態がそう軽々しいものでないにも関わらず軽率な行動を取ってしまったことを恥じているのか、或いは単純に居心地が悪くなって萎縮しているだけかもしれない。 今回、ヨハンがペガサスの側――遊戯に捜査協力を依頼するホスト側に立っているのは彼が既に捜査チームの協力者の立場にいるためだ。I2社の社長というしがらみや制約の多い立場にある彼が最も気兼ねなく動かせるのが、彼をパトロンとしており内々に養子縁組を組んでいる《ペガサスミニオン》のうちの一人、現在寵児達の最年少にあたるヨハンだったのである。パトロンと言ってもプロデュエリストのヨハンは若干立ち位置が複雑で、カード製作の本家本元がプロのバックスポンサーを公然と行うわけにはいかないので子会社が表向きには立っているのだがそれはさておき。 「聞いた通りだよ。ボク及びにもう一人のボク、それから十代くんは捜査に最大限の便宜と協力を図ろう。ペガサスの方からコンタクトは取れると思うけど、必要なら海馬コーポレーションの方にも話を……」 「アー、海馬ボーイには既に話自体は通してありマース。彼が乗ってくるか否かは全くの別問題ですがね。実を言うと、ここだけの話」 不審がる遊戯にペガサスは防音、防犯に十分以上に気を配っているはずの支社社長室であるに関わらず声を潜めた。よっぽど誰かに盗み聞きされたくないらしい。遊戯は耳をそばだてる。これはかなり大事な話だと直感が告げている。 「海馬ボーイのブルーアイズ・ホワイトドラゴン、ならびに城之内ボーイのレッドアイズ・ブラックドラゴンも既に失われてしまっていマース。海馬ボーイは大層憤慨していまして、私には手に負えそうにありまセーン……」 「海馬くんと城之内くんまでもが」 「イエス。彼らは高い実力を持つデュエリスト。事態は相当に深刻を極めています」 「そっか。それじゃ確かに海馬くんに協力を仰ぐのは難しそうだね」 「理解が早くて助かりマース」 「え、なんでですか。自分のカードが無くなったとなれば海馬社長は尚更……」 『尚更協力体制なんてものは望むべくもなくなる。あのプライドの高い海馬のことだ、独自行動で行くとこまで突っ走るぜ。ま、現場で鉢合わせってのなら十分に有り得る未来だが』 十代の疑問にもう一人の遊戯がスムーズに答えて茶化すように「お手上げ」のポーズを取ってみせた。十代は力なく「は、はあ」と声を漏らす。ライバルであり犬猿の仲にも近しい彼の言うことだから、恐らくそうなのだろう。 「途中で上手く合流出来るといいけどねぇ。それでスタッフは今どのくらいかな。ここにいる三人だけ?」 「今のところは。皆忙しく……しかし、ここにいるヨハンが十分な働きを見せるはずデース。月行や夜行もヨハンをいたく気にいっていマース。それに何より、彼が見せる十代ボーイとのコンビネーション。あれ程までに息のあった連携はそうそうないと私自らが保証しましょう」 「それは頼もしい限りだ。改めて宜しくね、ヨハンくん。きみ、《ミニオン》の一人だったんだ。月行くんや夜行くんは相変わらずかい」 「遊戯さん、月兄と夜兄のこと知ってるんですか」 「勿論さ。天馬兄弟は有名人だし、彼らとは個人的な親交もあるし。それにしてもあの二人に認められているなんて流石は十代くん一番の親友と言ったところかな……っといけない、話を進めよう。ペガサス」 「オウケーイ、ヨハン、用意したものを」 「イエスファザー。遊戯さん、十代、これを」 ヨハンがペガサスに指示されて書類を手渡してくる。十代達の前では「ペガサス会長が」「会長」、と他人行儀に彼を呼んでいたヨハンだが、本人の前では「ファザー」呼びらしい。十代が目線でそのことを尋ねるとヨハンは歩み寄り、小声で「兄弟達のように『ペガサス様』って呼ぶのは、なんか違うんだよ」と打ち明けた。ミニオンのことをよく知らない十代は首を傾げたが、その隣で話を盗み聞いていたもう一人の遊戯は合点がいったらしく頷く。 《ペガサスミニオン》というのはそもそも、シンディアを失い子供をもうけるチャンスを喪失したペガサスが自分の後継者を養成するために世界中から集めた優秀な孤児達の集団を指す言葉だった。《ペガサスの寵児》の名で呼ばれた彼らはあまり恵まれた出自の者がおらず、そのためそれまで夢に見たこともなかったような上等な食事、上等な教育、上等な生活環境を与えてくれたペガサスは彼らにとって神にも等しい存在であったのだそうだ。それ故ミニオン達はペガサスの期待に応えようと常に努力を重ね、成果を出し続けた。大抵のミニオン達にとってペガサスは養父という名の絶対上位存在なのである。 しかしヨハンの場合はケースがやや異なる。十かそこらでまとまって集められ、奇妙な連体意識の中で成長した「兄」達と違いヨハンは自我意識がある程度固定されてきた十五の歳に孤児院から(正確には奨学金で在籍していたデュエルアカデミア・アークティック中等部所属預かり名義から)引き取られ、「弟」としてミニオン達のライバル意識ではなく庇護欲や愛情を注がれる生活を送った。それがために彼はペガサスを「様」ではなく「父」と呼び、外でおおっぴらに彼との関係を吹聴するのを良しとしないのだろう。本人にはともかく、他人には兄達と比べた際の引け目があって自信を持ってそのように紹介出来ないのかもしれない。 いつか月行と夜行が遊戯に聞かせた台詞を思い出す。――「先日ミニオンに一人少年が増えたんだよ。まだまだ荒削りだが将来有望な子だ。歳が離れているからか、兄弟皆が気にかけて、頻りにデュエルを申し込んだり自主的に家庭教師を買って出たり、とにかく大人気だよ。素直でかわいい。いい子だと私も思ってる」「遊戯さん、私達はね、ようやく海馬瀬人の気持ちというものが少し理解出来たような気がするんです。『兄弟』とは良いものですね。何せ、私達は長いこと『兄弟のように近しい好敵手』或いは『同じ神を崇拝する信徒』しか知らなかった。慈しんで面倒を見ることなんて初めてで戸惑うこともありますけれど。兄弟とはああいうものなのでしょうか。私と夜行は双子の兄弟だけども、慈しみ合う相手というよりは二人でひとつの片割れだから……」 初めての「弟」に頬を緩める天馬兄弟は喜びを隠そうとせず穏やかに微笑んで「最年少の彼」のことを語った。一人っ子の遊戯にはしばらくその言葉の意味は推して計るしかなかったが、後に弟のように親しい弟子を持って真意を自ずから悟った。 「それは調査報告書兼申し送り事項デース。現在はっきりと判明している失われたカードと所持者のリストアップは巻末にありマース。ユー達にはまず、通りがかりに消滅現象が頻出する傾向にあるサンマルコ広場へと向かっていただきたい。消滅する時は予備動作として発光現象が起こるとの報告が上がっていマース。しばらくは地味な仕事になるでしょうが、ユー達ならば何かのはずみで犯人の姿を認められた場合に捕縛出来る可能性も低くない。連合との話は既に付けてありますから、もしそのような事態に遭遇したならば遠慮なく立ち回ってください。補修の必要が生じても全額我が社が持ちましょう。奪われたカード達の総額に比べれば、大した額にはならないはずデスから」 ――それが昨日のことだ。 「しばらくは地味な仕事になるって、それもうまったくの期待外れじゃんかよぉ! あーくそっ、サイバー・エンド・ドラゴンまで持ってかれてたなんてそんなの聞いてないぜ、なぁカイザー!」 「『しばらく』は地味だっただろ。二十四時間保たなかったけど……サイバー・エンド・ドラゴンは昨日の段階ではリストになかった。つい先頃に奪われたと見るべきだ」 「それにしても……失われたカードが人を、それも実体化して襲うなんて初めての事例だ。今までは疑問程度だったけどこれで黒幕が存在してるってはっきりしてきたね。コントローラーなしにモンスター間でここまでの連携を見せるのは難しいよ。ブラック・マジシャンとブラック・マジシャン・ガールのように特別な繋がりを持つ精霊ならまだしも」 遊戯は上空を瞬間ちらりと見遣る。現在サンマルコ広場に現れて遊戯らを追い回しているモンスターは二体。カイザー丸藤亮のエース「サイバー・エンド・ドラゴン」並びに海馬瀬人の魂のカード「ブルーアイズ・ホワイトドラゴン」だ。二体の接点はドラゴンという共通した文字を名前に持っている以外にないに等しい。種族もアタックディフェンスもかすらないし、何より持ち主同士に直接の面識があるかどうかまず不明だ。 サイバー・エンドが機械の口腔を大きく開いて「エヴォリューション・バースト」を放ち退路を塞いでくる。そこですかさずブルーアイズが「滅びのバーストストリーム」で援護を入れ、上手いこと進路に攻撃を直撃させた。慌てて回避防護の態勢を取るが、立ち込める粉塵による被害を免れるのは不可能だった。視界が奪われ、足が僅かに止まった隙を突いて二体のドラゴンは滑空し三人を挟むように降り立つ。 『追い詰めたつもりか、くそ』 「でも打つ手がないのは事実だ。まさか実体化して襲ってくるなんてね……厄介極まりない。さてどう対処したものか」 『こちら側には対抗手段がないときた。一体敵は何者なんだ?』 二人の遊戯の会話を横に聞きながら十代とヨハンは背中合わせに立ち尽くしてそれぞれに眼前のドラゴンを見上げていた。巨大な機械の龍、滑らかな表皮を持つ至高の白龍。そのどちらもが圧倒的な質量を伴って君臨し、三人の人間を圧迫している。最早後退るスペースもない。十代は生唾を飲んで働こうとしない脳味噌に必死に呼び掛けた。 二体のドラゴンが取った行動パターンは奇妙なものだった。極力建物には被害を出さぬように時折不自然な迂回や蛇行が動きに含まれていたように思えるのだ。今だって、サンマルコ広場の開けたスペース中央に鎮座していて地面はともかく建物の損傷は軽微なものに留まっている。この明らかな法則性はドラゴンを操っている黒幕の指示によるものなのだろう。そこまでは、十代の頭でも考えが追いついた。だが目的が読めない。 「八方塞がりなのは変わんねーし……!」 「ああ。街に被害を出さないようにしてるのと、俺達に重傷を負わせる気があるかどうかはまるっきり別問題みたいだしな。……なあ十代、どのくらい手加減してくれれば死なないで済むと思う?」 「知るかそんなもん。エヴォリューション・バーストはソリッド・ヴィジョンでも喰うと結構キツいんだ。それが生とか、ああもう考えたくないって」 「滅びのバーストストリームもなかなか厳しいものがあるよ。まずすごい眩しいからフラッシュで視界がね――」 「遊戯さん冗談言ってる場合じゃないです!」 『真面目な話、目潰し対策に目を閉じていた方がいいかもしれないぞ。この後無事に逃走経路を確保したいのならな』 もう一人の遊戯がぞっとしないことを言う。しかし十代がその内容に反論することはなかった。その余裕もなく、二体の――アタック四〇〇〇と三〇〇〇の光線が――生身の人間三人を襲った。 反射的に瞑った目をしばらくの間十代は開くことが出来なかった。きつく目を閉じたまま不意に体が空へ浮き上がるような感触を覚える。確かに地に付けていたはずの足が投げ出されてぶらりと所在なさげに揺れる。体に痛みはなくて、ああ、なんだ俺結構無事に生きてるのかなと漠然と思考した後、数テンポ遅れて疑問符が踊り出た。 恐る恐る目を開く。まず視界に入った自分の手足は殆ど無傷で、せいぜいがかすり傷程度のものだった。ゆっくりと頭を動かして見渡す。十代の周囲にあるのは広場の建物群ではなく晴れ渡った青色で、それが雲の少ない空であることを理解するのに少々の間を要した。 「へ? 浮いてる……なんで」 「伏せろ、十代!」 ヨハンの手に押されて伏せた直後、後を追って上昇してきたらしいサイバー・エンドとブルーアイズが放った咆哮が飛び抜ける。回避し損ねた頭髪の端がじゅっ、と笑えない音を立てて焦げたことで十代の思考は急激にクリアになった。二体のドラゴンと対峙する形で今現在十代達を乗せている足場――恐らくは実体化したモンスターも翼を広げて威嚇しながら飛行をしている。 「レッドアイズ・ブラックドラゴン。なくなったって聞いてたけど……」 「おい遊戯! ぼさっとしてる場合じゃねぇんだよ、手を貸せ!」 ぽつりと漏らした遊戯に第三者の声が飛ぶ。遊戯は振り返って目を見開いた。そこには見知った人物の姿があって、彼の胸元で呪術めいた金属が揺れ、存在を主張していた。千年リング。遊戯の友人を宿主としている闇の人格。 バクラだ。 「バクラくん?!」 「余裕ねえんだよ、とっとと王サマに代わりな! そこのガキ共を守りたいと思うのなら今すぐにだ。こいつは闇のゲームだ……お前の手に負えるもんじゃない」 「どうして、きみは……」 「急げ、早く!!」 バクラの怒号に合わせたかのようなタイミングで再びブルーアイズ・ホワイトドラゴンが吼える。こいつを海馬くんが見たら怒り心頭だぞ……と考えながら遊戯は「もう一人のボク」へと語り掛けた。彼は『ああ』と小さく頷き、すぐに人格の交代が行われる。 「――バクラ。貴様が何故ここにいるのか、レッドアイズをどうやって手に入れたのか、そもそもオレ達を手助けする目的は何か、問い正したいことが山程ある。だがまずは状況の立て直しが先決だ。この局面を切り抜けたら説明をして貰うぞ」 「勿論、王サマ」 バクラは意地悪い声でにやりと応えると四人を乗せたレッドアイズに攻撃命令を下した。 ◇◆◇◆◇ 「ホラよ。城之内にはお前から返してやれ」 ようやくといった様子で席についた遊戯にバクラがカードを投げて寄越した。右手で挟み受けたそのカードは紛れもなく、城之内克也の所有する「レッドアイズ・ブラックドラゴン」だ。カードの重みはかつてバトル・シティで彼から預かり受けた時と何ら変わらぬものだった。ひとまず腰のホルダーを取り出し、丁寧にカードを収納する。バクラは遊戯の所作に関心がないらしく、無事手に渡ったことだけを横目に確認すると慣れた手付きでコーヒーメーカーを起動させた。 サンマルコ広場から離れ、なんとかブルーアイズとサイバー・エンドを撒いた後にバクラが一行を連れて訪れたのは郊外にあるマンションの一室だった。表の表札には「R.BAKURA」と記されている。バクラの宿主である獏良了はどうやら今現在イタリアに居を構えているらしい。 玄関の鍵を開鍵し、「入れ」と素っ気無い声で招き入れられた室内はシンプルというよりは殺風景なレイアウトであまり生活臭がなかった。必要最低限の寝床、及びに休息場所といった感じだ。元々獏良自身が何か一つのことに熱中し出すと生活を疎かにしてしまいがちなタイプだったから生活臭を求めても仕方ないのかもしれないが。 (……今もまだ、バクラくんと獏良くんは……) 人数分のコーヒーを用意して適当な受け菓子を見繕うバクラの手付きはこなれていて、動作に無駄がない。天然でぽーっとした性格の持ち主である宿主とは正反対にてきぱきと手を動かしている「千年リングに宿る闇の人格」をぼんやりと見る。借りものの体、意識を奪い取り乗っ取って使っている器を彼が本当に大事に扱っていることをなんとなく遊戯は気付いている。自分とよく似た境遇でありながら異なる関係性を持つ二人の「バクラ」。二人はまだ会話を持たないのだろうか。バクラにとっての獏良はそれでもまだ利用価値のある肉体に過ぎないのだろうか。 (……でもそれはボクが口を出すことでもないし、出してどうにかなることじゃない) 遊戯はそのことに関する思考を止めた。今はそれよりももっと大事なことがある。 「何はともあれ、ありがとうバクラくん。それで良ければなんだけど、このカードをどういう経緯で手に入れたのか教えて欲しいんだけど」 「別にやましいことはしてねえよ。元々、そいつもさっきの二体みたいにオレ様を追っ掛けてきてな。要は嗅ぎ付けた邪魔者排除用の使いっ走りだ。めんどくせえからコントロールを奪ってやって、一際派手に騒動が起きてる方へ飛ばした。そうしたらお前らとご対面、ってわけだ」 「コントロール奪取? どうやって?」 「簡単だぜ。『精神操作』で干渉してやってチョチョイだ。遊戯、いや王サマ。千年アイテムを持ってるんだからちっとはそれを使っとけ、『光の護封剣』でもそいつの力を借りて発動しときゃ時間稼ぎにはなったはずだろう」 コーヒーを配膳し終えたバクラが腰に手を当てて情けないとばかりに溜め息を吐く。反論することが出来ないので遊戯は黙って頷いた。バクラの溜め息顔が呆れ顔になる。 「相変わらず素直だねぇ。史上最強の決闘王ともあろうお方がまあ殊勝なこって……ククッ、そう苦い顔しなさんなよ王サマぁ。それが武藤遊戯の美徳だろーがよ」 『……話を濁すな。レッドアイズの入手経緯は理解出来たが、お前がこの件に関わる理由がまだだ』 「そう焦んなよ……答えは単純だ。獏良了もまたこの一連の事件の被害者に相違ないからさ。要するに宿主サマのお気に入りがなくなっちまったんだ。ある日唐突に、光になって消え失せた。目の前でそいつに消滅された後の反応ったらひでぇもんでよ……」 カードそれそのものはさしてレアなものでもない。デッキにおいて重要な役割を担っていたわけでもない。効果はそれなりだが召喚に手間のかかる最上級モンスターで、重たすぎてまともに使えたもんじゃなかった。それが原因で事故って負けたことだって一度や二度じゃないというのにそれでもそのカードをデッキから抜こうとしない獏良の姿は、バクラに言わせれば酔狂以外の何者でもない。しかし固執する理由を理解してやることは出来た。そのために代わりに飛び回ってやることも。 「天音の……死んだ妹の形見なんだと。それ以来宿主は意気消沈しちまって飯もロクに食わねえ。それはオレ様にとっても不都合なんでね、代わりに生活してやってんだよ。そうでもなきゃこいつは死んじまう」 形見を失ったのだということを悟った獏良の有様は本当に酷いものだった。バクラに拭えない焦燥を与え、危機感と使命感を覚えさせる程に獏良の精神は急激に衰弱した。呆然自失の状態に陥った獏良はその時手に持っていたカードを全てぽろぽろと取りこぼして、ただ一言蚊の鳴くような声で「あまね」と妹の名を呼びくずおれた。泣き虫な宿主、とからかってやることすら出来なかったのだ。何故なら、獏良了は涙を流すことさえ忘却していたのだから。 様子を見る、という選択肢はバクラには与えられなかった。その場を動こうとせず食事も忘れて座り込むその姿に彼は立ち上がり、宿主の意識をまどろみに押し込み、そしてそのまま一度も人格を元に戻すことなく今に至る。 『驚いたな』 「柄でもねえってか?」 『否定はしないが、もう少し別のことにだ。オレ達は肉体を借り入れているもう一人の自分を守らなければならない、それは自明のことで一応の言い訳としては受け取っておける。オレが驚いたのは獏良くんの方だ。彼は確かに何かに依存しやすいきらいがあるが、そこまで取り乱したのか』 「デリケートなんだよ、オレ様の宿主は。なんのかんの言ってタフな貴様の相棒とは違って繊細に出来てんだ」 『相棒を侮辱する気か』 「いーや滅相もない。ただ、一つ言っておくがな、宿主に関してはオレ様が一番よくわかってるんだよ。口出しはなしといこうじゃねえか」 「わ、わかったわかった、ほらもう一人のボクも下がって……さっきから十代くんとヨハンくんが所在なさげにぽかーんってしてるんだ。彼らもわかるように話してあげなきゃ」 もう一人の遊戯とバクラがいがみあいを始めたのを受けて遊戯は慌てて仲裁に入る。充満する剣呑な空気に気圧されて、常はお喋りな口をぴたりと閉じている十代とヨハンをこれ以上放っておくのは忍びなかった。しかしそれでもなおもう一人の遊戯は威嚇体制を崩そうとしない。仕方なしに笑顔で「怒るよ、ねえもう一人のボク」と囁いてやるとようやく彼はそれを止めた。バクラの顔が引きつっていたが気にしないよう努める。 「バクラくん、話続けて」 「あ、ああ。つっても特にオレ様から説明することはそうないだろうし……ちなみに遊戯、このガキ共はどうしたんだ? ただのハナタレならお人好しにも拾ったのかと納得してやるところだがそういうふうでもなさそうだ。なんたって噂の《天才寵児》に《ミニオン》の秘蔵っ子だ、ペガサスの野郎に子守でも押し付けられたか」 「捜査チームのスタッフ。二人とも戦力として十分な実力を備えてる。きみ、《ミニオン》のことなんてどこで知ったの」 「裏まで潜らずとも有名人だろう、ヤツらは。政治経済デュエル全ての世界にあまねく影響力を持つ組織だぞ。天馬兄弟に睨まれたが最後、一生元の立ち位置には復帰出来なくなるってのはまことしやかに囁かれている『通説』だ。善良な宿主サマがオレ様のミスでペガサスミニオンに目を付けられでもしたら参っちまう」 「その時はボクが取りなしてあげるけど……しかしすごい情報網だなぁ。彼が天馬くん達と兄弟だってボクでも知らなかったのに。それで、きみはそのネットワークを駆使してここイタリアが怪しいと狙いを付け、結果敵さんにもマークされちゃったってワケか」 「ドジ踏んだぜ、どうやらあちらには見境なんてもんは求められそうにないしな。オレ様一人じゃ分が悪い。そこでだ遊戯、ここは一つ共同戦線ってヤツを結んでおかないか。先に王サマに聞かれた『助けた理由』ってのはそれさ。オレ様は情報と戦力を提供し、お前らに協力をする。指揮系統を決めて貰えばそれに従うぜ。見返りは一つしか求めない。宿主の宝物を取り返すことに関してだけは最大限便宜を図って貰う。悪い取引じゃあないだろう」 『まっとうすぎて裏を疑いたくなるぐらいだ』 「そうだね、悪くない。ボク達はその申し出を受けるよ。指揮系統が必要になる時はボクが取る。それでいいかな」 まだ若干御機嫌斜めらしいもうひとりの遊戯を牽制するように返答を出してとうとうかちんこちんに固まって萎縮しきってしまった十代とヨハンに「ゴメンネ」とアイコンタクトを送る。十代が反射的にコクコクと頷いて応えた。動きがゼンマイ人形みたいにぎこちない。 (うわぁ、なんだかすごく悪いことをしちゃった気がするなぁ……) まるで茶色と蒼の小動物が並びたって、怯えた目でちんまりと、眼前で展開される肉食動物の争いをおどおど眺めているようだった。ハムスターとかによく似ている。すごく可愛くて、庇護欲をかきたてられて、頭を撫でてやりたくなる。 「……こーゆーこと考えると、ボクももうオジサンだなぁって、なんかさみしくなるなぁ……」 「ゆ、ゆーぎさん」 「うん。ほんと忍びないや。……あれ、ヨハンくん、それ光ってない? ケータイ」 「あっ、ほんとだ。今サイレントにしてて……すみません、ちょっと電話出てきます」 青い着信ランプを点滅させている携帯を手に取り、ヨハンが席を立つ。「もしもし」と出方を伺うような声で受けた直後、緊張に染まっていた顔がすぐにパッと明るいものに変わった。憧れの人に声を掛けられたようなその表情はヨハンが人間の「家族」、敬愛する人達に向けるものだ。 「……あ、月兄、うん……」 「――つきにい? おい、まさかそいつ、天馬月行……」 「……ああ。今? 酷い目に遭ってさ、サンマルコ広場からは大分離れたとこにいるよ。……うん、十代も遊戯さんも一緒……わかった」 「冗談じゃねえ」と呟くバクラに気付く素振りもなく、ヨハンは会話を続けている。先の台詞からバクラがなるべく天馬兄弟と関わりあいになりたくないと考えているのは確かだったから、まあそのうろたえようもわからなくはなかった。《ペガサスミニオン》。それは掛け値なしに世界有数の影響力、コネクション、権力、そういったものを有している集まりなのだ。 「あの、遊戯さん」 「月行くんからボクに用事が?」 「はい。夜兄も一緒に話がしたいって。なんでも」 ヨハンは通話の途切れた携帯を手に遊戯に向き直る。 「黒幕の人間を誘き出す算段が立ったらしくて」 |