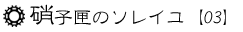※長丁場のデュエル前半戦となります。オリカ・原作効果・OCG効果入り乱れていますがご容赦ください。 「あれぇ、パラドックスじゃん。D・ホイールなんか用意してるってことは仕事なわけ?」 「ああ。正史の私がへまをした場所へ。因果律が妙な値で固定されてしまったらしく、あの時代のあの場所にだけは私が存在している必要があるのだよ。修正された歴史の《英雄因子》達がそのことに気付く可能性は決して低くないと試算が出ている。或いは一手交えることになるだろうとも」 「ふーん。ま、せーぜー頑張りなよぉ? スクラップになったら僕がネジは拾ってやるからさぁ」 「まさか。相手は手のひらの上の人形達だぞ。武藤遊戯はともかくとして――名もなきファラオがいようがいまいが、あの《英雄》だけは脅威として君臨し得る――遊城十代は最早ただの抜け殻だ。亡骸といっても差し支えない。あの程度で何が出来る? 遊城十代を真に英雄たらしめていた要素が、まるっきり、ごっそり、剥奪されているというのに。笑えるな。この世界では不動遊星ですらただの恵まれた傲慢な子供に過ぎない。本当に笑える」 「不動遊星、ね。サーキットの時は便利だったんだけどなー、こっちじゃ確かに期待出来そうにもないね。あの偽善者に嫉妬してるよ、それこそ子供みたいにさ」 「ヨハン・アンデルセン……気付いたのか、奴は」 「僕もホセのじじいもプラシドの馬鹿も多分捕捉された。あいつは阿呆だけど脳味噌は悪くないし、何かしらのプランは取ってるんじゃないのお? でもまあそれはいずれ通る道だよ……どうせ最後にあいつは全部知ることになる。それが多少遅いか早いか、それだけ」 ルチアーノが面倒臭そうにぼやいて「どう足掻いても……」その言葉の後に唇を閉ざした。パラドックスは眉を顰めて「何かあったのか」と問い掛ける。少し、と返ってきた彼の口調は複雑な色相を帯びていて、パラドックスは彼が何をして来た帰りなのかを悟った。 「遊城の子供達に会ったのか。それとも、《聖女》か」 「両方。龍亞の奴、僕のことなーんも覚えてないんだ。ほんッと笑えるよ。大爆笑。母親がそばにいるのに気付きもしない。確かに血縁を遠くしたのは僕達なんだけどさぁ!」 「彼女の方は何を?」 「別に、いつも通りだよ。相変わらず白馬の王子様なんか夢見ちゃってさ、へらへらしてる。その間も汚いこと腐る程やらされてんのにいつまでもいつまでも来やしない男のことを待ってる。《母さん》はいっつもそうだ。夢ばっか追いかけてる。星辰が揃う日まで? ハッ――どんなに待ったってあいつは来ないんだよ。ヨハン・アンデルセンは、僕の嫌いな人種の男は自分の片割れに夢中でくず鉄で出来たなり損ないのことなんか知ってすらいないんだ。馬鹿だ。馬鹿だよ。ばかみたいだ。『私のお気に入り』を口ずさんだって耳障りな電子音にしかならないのに。あの音は人間の脳味噌をいかれさせるだけなのにさぁ、なんだってあんなに嬉しそうに……」 海底神殿で「いつかは人間のかたちをしていたものども」に崇拝され、夢を見ながら待っている、憧れの男が好んだ歌を歌おうとして呪いの賛美歌を謳っている怪物のことを思い返しながらルチアーノは俯く。あの恥知らずな「同じ穴の貉」はそれでも信じているのだ。ルチアーノの頭を母親ぶって撫でながら子守歌のつもりで愛を謳っている。永遠を鼻で笑ってしまうのにそのくせ「不変」を盲信している。 ルチアーノが、アポリアが幼い頃に失い「そんなものは有りもしない」と気付いたものを未だに信奉して、気を狂わせる電波を唇の形をした穴から垂れ流している。 滑稽だと思っていた。ハッピーエンドも何もない敵役の玩具に慈悲が与えられるいわれがないのだ。惨めなものだった。愚かな神の偽物。 「随分と入れ込んでいるようだな、《マザー》唯一の成功作は」 「そーいうんじゃねーし。単純に嫌いなだけ。見てるとイライラすんだよ。あいつはまるで、身の程知らずって言葉を形にしたみたいだ」 人間に恋するコッペリアじゃ、まるで報われない。フランツ青年は結局のところコッペリアが人形であることを知って見限り、スワニルダの元へ行ってしまうのだ。どんなに願ったって望むものは手に入らない。 欲しいものは目の前で壊れて粉々になって、或いはそもそも目通りも叶わぬまま消えてなくなる。 「分不相応の夢は首を締めるだけ。愛が欲しいと願えばやがては愛さえ要らなくなる。残されるのは絶望、絶望、絶望……三度の絶望で僕達は生まれたんだ。だから僕はもう何にも期待なんかしない。ホセにもプラシドにも、アンチノミーにもパラドックスにもゾーンにも、僕自身にも」 ましてやあいつになんて。 ルチアーノの横顔にはいびつな感情が発露していた。強烈なコンプレックス。それは恐らく、暴走したモーメントとの争いの最中で両親を失った少年期を模した人形の持てる「母なるもの」への執着の表れだ。ホセは執着すら失せ、プラシドは恋人に執着を見せ、ルチアーノは両親に執着を見せる。アンチノミーが不動遊星に今でもきらきらした憧れという幻想を持っているように……。 「悪いね、引き留めて。仕事には早く行きなよ。回収の方は調子いいんだろ?」 「一応な。数が多いのでまだ全てではないが。人間三人の運命を狂わせただけでこの誤差だ、英雄というのはまったく手に負えない。歴史を、世界そのものを変革し得る英雄因子の持ち主か。私は決して、あのようなものになりたいとは思わないな」 「僕もだよ。あんなのまっぴらごめんだ。嫌んなるよ……」 その《英雄》になろうとした愚か者のことを思って二体の機械人形は押し黙った。共通の友にして偽りの造物主。くず鉄の王様、英雄崇拝の狂信徒ゾーン。 彼は自らを英雄に造り変えんとした。不動遊星のパーソナルデータをスキャニングで全て複製し自らにその思考パターンすらも転写した。パラドックスもアポリアもアンチノミーも、ゾーンが名もなき科学者だった頃のことは何も知らない。知っているのは英雄になり損ない、贋作の限界に直面した「ゾーンと名乗る不動遊星の劣化コピー」だけだった。 科学者が何をもって英雄になろうなどという願いを抱いたのか、それだけはついぞ尋ねられずにいる。尋ねるのが恐ろしかったのかもしれない。アンモナイトの形をした生命維持装置で無理を重ねて延命を続け、その果てに、救われる歴史を拒絶し人類に断罪を下さんと決意したその生々しく醜悪な「人間の心」に触れることを忌避しているのだ。 ルチアーノはゆっくりと顔を上げ、首を横に振った。 「ともかく、さ……人間ってやつを、あんまり見下すと最後に痛い目見るぜ。正史のプラシドの話、してやっただろ? ――多分さあ、僕達は元々人間だったってことを忘れちゃあいけないんだよ。それを忘れるから人間に負けちゃうんだ。プライドばっかりたっかくなった鼻っぱしらは折られるように世の中なってる。嘘吐きピノッキオの驕りたかぶりみたいに、チョッキン、ってさぁ?」 ◇◆◇◆◇ 別段驚くような要素はなかった。名もなきファラオと遊城十代は元々この時代の人間だ。出しゃばってきてもおかしいことはない。ならば正史の不動遊星の分の埋め合わせに、その知り合いがくっ付いてきていてもおかしくはないだろう。 (データベースによると……ヨハン・アンデルセンは照らし合わせるまでもないな。獏良了……盗賊王バクラ、か。盗人が財宝の持ち主であるファラオと肩を並べようとはまあなんとも荒唐無稽なことだ) 一つだけ驚くとすれば、それは呪術結界が一帯に施してあることだった。千年アイテムを触媒にしてあるだけあって、強度と再現率は極めて高い。誰が術者なのかは知らないが、呪術的である以上パラドックスの持つマシン理論ではたち打ちが出来ないということだけは確かだった。最後の最後まで逃がしてなるものか、という名もなきファラオの声が聞こえたようなそんな錯覚を覚える。 パラドックスが正史で敗北を喫した「英雄」達と比較して遊城十代はやや幼く、武藤遊戯は随分と成長している。頼りなさげな小さな体躯はそれなりに逞しい青年のものに姿を変え、人格が交代してファラオが主導権を握っているだけあって強烈な威圧感を生み出していた。名もなきファラオとその器たる武藤遊戯は二人でいる時にこそ最高のポテンシャルを発揮する。ファラオをくだし冥界へ送り届けた正史の武藤遊戯は強靱な精神力と卓越したゲーム・センスこそ保持していたが、かのファラオの如き苛烈な攻め方と神を並べる力は往年程残されていなかった。 (警戒すべきはやはりファラオ、か) 神三体をそのデッキに組み込みなおかつ展開し得る可能性を持っている。遊城十代とヨハン・アンデルセンのコンボも過去の経験から多少恐ろしくはあったが、それは正史の人智を超越したものどもの持つ驚異だ。生身の人間にどうこう出来るとは期待していない。 「ルールは変則サバイバル・ルールで墓地フィールド除外ゾーンは俺達四人で共有する。各人ライフ四〇〇〇で、ただしお前だけはハンデとして一六〇〇〇だ。全員が一ターンを終えるまで攻撃は出来ない。いいな。――先攻はこちらが貰う」 「よかろう。私のデッキの前に全員ひれ伏させてやる。どうせ君を倒さぬ限りここからは逃れられないのだろう?」 「ああ、そうだ。勝利はオレ達がお前のライフを削り切るかお前がオレ達全員を倒した時に決する。――行くぞ。デュエル!」 高らかなドロー宣言をして遊戯がカードをデッキから手札に加える。正史ではイシズ・イシュタールをして「望むカードを意のままに引き当てることが出来る」と言わしめた王者の一手。 遊戯は横目でドローカードを確認すると特に何のリアクションも取らずに細く整った指を手札に掛けた。 「手札より『魔導戦士ブレイカー』を召喚。魔導戦士ブレイカーの効果発動、魔力カウンターをこのカードに一つ乗せる! よってブレイカーの攻撃力は一九〇〇となる。更にオレはカードを一枚伏せ、ターン・エンドだ」 「それじゃ、次はオレ様が行かせて貰おうか。手札より魔法カード『封印の黄金櫃』を発動。デッキの『ネクロフェイス』を選択して除外し二ターン後手札に加える。更に除外されたことでネクロフェイスのモンスター効果が発動、お互いにデッキの上から五枚のカードを除外ゾーンに置く!」 ネクロフェイスの効果処理で除外ゾーンにそれぞれ五枚と二十枚のカードが送られる。ネクロフェイスのもう一つの効果は「召喚された時、除外されたカードの枚数×一〇〇ポイント攻撃力を上昇させる」というものだ。確かにこの特殊ルール下でこの戦術は大いにその威力を発揮するだろう。 だがそれも二ターン後のことである。その間に勝負を決められたら意味がない。寧ろバクラ以外のプレイヤーにとっては予想外の損失だ。 「更に手札から『苦渋の選択』を発動。オレ様のデッキから五枚カードを選択し、貴様に一枚選んで貰うぜ。オレ様が選択したのはこの五枚! さあ、どれを取る?」 「……『ダブルコストン』を選択する」 「なるほど? そんじゃ残りの四枚は墓地行きだ。ありがとよ」 バクラは「馬頭鬼」「ゾンビ・マスター」「ヴァンパイア・ロード」「不死王リッチー」を墓地に置きにやにや笑った。バクラが選択したカードは全てアンデッド族のモンスターカードだ。やるだろうことは目に見えていた。 「こいつはさっさと条件が揃って楽でいいな。オレ様は墓地から三体のアンデッドモンスターを除外し、手札より『ダーク・ネクロフィア』を特殊召喚するぜ。更に手札からダブルコストンを守備表示で召喚してターン・エンドだ」 しかし想定内だ。たかだか攻撃力二〇〇〇台のモンスターなど如何ようにも処理が出来る。 「私のターン、ドロー。手札よりフィールド魔法『sin World』を発動。更にデッキから『青眼の白龍』を除外し――」 「あっ、まさかそれ海馬さんのブルーアイズかよ?!」 「いかにも。私は手札より『sin青眼の白龍』を特殊召喚する!」 歴史上の名だたるカード達を略奪し罪の名の仮面の元縛り上げた「sinモンスター」がフィールドに現れ雄叫びを上げた。驚きに目を見開く十代とヨハンの隣にバクラは無表情に立ち、遊戯は眉を顰めている。好敵手の、友のカードだ。だから遊戯はあからさまに表情を苦いものにしたが、それでも正史でsinレインボー・ドラゴンを呼び出した時に遊城十代にぶつけられた視線に比べるといくらもましだとパラドックスは思った。 あの苦々しく正義漢じみた怒りに満ち、忌わしげな色を隠そうともしない金の眼。覇王のまなこだけは何度見ても慣れることがない。 「手札一枚をコストに『死者への手向け』を発動。『魔導戦士ブレイカー』を破壊する」 「チェーンして速攻魔法『ディメンション・マジック』を発動! 自分フィールド上に魔法使い族モンスターが表側表示で存在する時、一体をリリースして手札から魔法使い族モンスター一体を特殊召喚する。現れろ、我が最強のしもべ『ブラック・マジシャン』! これによって『死者への手向け』は対象を失い無効、よって破壊される!」 「かわしたか。だがお目当ての破壊効果は使えずじまいだったな。私はカードを二枚伏せてターン・エンド」 「そう悪い結果でもないぜ。ブラック・マジシャンを呼び出すことが出来たからな」 遊戯は自信に満ちた表情でほくそ笑む。その背後で半透明の幽霊のようになって、器の遊戯が彼を支えるように触れていた。 「よっしゃ、俺のターンだな! ドロー、手札から魔法カード『E‐エマージェンシーコール』発動、『E・HEROエアーマン』を手札に加える。『E・HEROエアーマン』を召喚、効果発動。『E・HEROフェザーマン』をデッキから手札に加える。更に手札から『融合』発動、手札のネクロ・ガードナーとフィールドのエアーマンを融合して『E・HEROエスクリダオ』を特殊召喚! 俺はこれでターン・エンド! ヨハン、頼んだぜ」 「オッケー。俺のターン、ドロー。『宝玉獣サファイア・ペガサス』を召喚。モンスター効果発動、デッキ・手札・墓地から宝玉獣と名の付くモンスターを一体選択して永続魔法扱いでフィールドに置くことが出来る。俺は『宝玉獣ルビー・カーバンクル』を選択。『サファイア・コ−リング』! これでターン・エンド」 ターンが一巡して遊戯に戻ってくる。十代とヨハンはきらきらした目で遊戯を仰ぎ見て、「師匠」「遊戯さん」と促すように名を呼ぶ。 「ああ、任せろ。ようやく攻撃に移れるというわけだ。――俺のターン!」 弟子に尊敬と期待の念がこもった声を掛けられて師匠の遊戯がふっ、と笑う。「デュエルはワクワクするものじゃなきゃいけない」という十代の信念をよく知っている彼はいつもそうであるとは限らないことをよく知っていたが、その分、十代の願いを熟知している人だった。 だから出来ればこのデュエルも彼にワクワクさせてやりたいと思っているのかもしれない。パラドックスのことも、逃がさないように結界を張りまでしたのはもしかしたらデュエル後に首尾よく改心させて手と手を取り合って握手――だなんて都合のいいことを考えているからかもしれなかった。 「ドロー! ヨハン、きみの力を借りるぜ。フィールドの『宝玉獣サファイア・ペガサス』を生贄に『ブラック・マジシャン・ガール』を召喚!」 決闘王武藤遊戯のデッキの中でも特に高いファン人気を誇る「ブラック・マジシャン・ガール」が師の隣に現れ、一言二言言葉を交わし合う。ソリッド・ヴィジョンの理論を超越した「精霊の絆」がわかりやすく形になっているのだ。精霊の声を聴くことが出来る十代とヨハンにはブラック・マジシャン・ガールが『お師匠サマ!』と声を弾ませるのもそれにブラック・マジシャンが『行くぞ』と応えるのもしっかり聞こえていた。 「魔法カード『黒・魔・導・連・弾』を発動! 『ブラック・マジシャン』と『ブラック・マジシャン・ガール』を選択して発動。このターン、『ブラック・マジシャン』の攻撃力を二倍にする! 行くぞ、バトルだ! 攻撃力五〇〇〇になった『ブラック・マジシャン』で『sin青眼の白龍』に攻撃!」 「トラップオープン、『攻撃の無力化』。攻撃を無効化しバトルフェイズを強制終了する」 「チッ……ならばこれでターン・エンドだ。『ブラック・マジシャン』の攻撃力は元に戻る」 ブラック・マジシャン・ガールがしょんぼりと肩を下げて師と共にすごすご下がって行く。パラドックスがせせら笑うような表情をするのが見えて、決闘王は不機嫌そうに皺を寄せた。 「なんだよ。何がそんなに可笑しくて笑ってるっていうんだ? おい」 「大したことではない。何と平凡な応酬かと思ったに過ぎない。……弱いな、君達は」 「……そいつは、聞き捨てならないな」 遊戯の表情が剣呑なものになる。しかし実感として、パラドックスの知るものよりも目の前の「人形」達は弱々しかった。脆弱なデュエル。かつて並行世界のパラドックスが敗北を喫した二人に比べても、また別の世界でイリアステルの妨害をしてその異常性を見せつけたつがいと比べても、ひ弱で頼りなくて、姿形を真似た子供だましのようだ。 圧倒的暴力で立ちはだかる敵を薙ぎ倒した世界一強靱ないきものと比較するのが可哀想なぐらいに、眼前の遊城十代とヨハン・アンデルセンは、苦労を知らない儚く幸福な道化だった。 「私の知っている遊城十代はもっと大きな驚異だった。ヨハン・アンデルセンはもっと攻撃的で、恐ろしく天才的な男だった。決闘王武藤遊戯はそれこそ伝説や神話のように語り継がれていた。絶対無敵の不敗伝説だ。だがそうではない。歴史一つ狂わせただけでこのざまだ。目に余るな」 「パラドックス貴様、十代達を侮辱する気か――」 「待て、王サマ。安い挑発に乗ってんじゃねえよ。王サマは身内のこととなるとそうやってすーぐ熱くなっちまいがちなのが欠点だな。ここはオレ様に任せな」 声を尖らせる遊戯をバクラが制する。遊戯は実に意外そうに目を見開いていつも通りの風体で立っているバクラに目を向けた。バクラが苦笑いをする。遊戯がそういう顔をすることはわかっている、というふうに息を吐いて彼はディスクに手を掛けた。 「……バクラ」 「オレ様にも思うところがあるんでね。さて、オレ様のターンだ。ドロー、……バトルは見送る」 「ほう? 威勢よく任せろと言った割に、やることはそれっぽっちか? 私は君のバトルフェイズ終了にチェーンして『終焉の焔』を発動、黒焔トークンを二体特殊召喚する。元より期待などしてはいないが、期待外れだ。酷い肩透かしだな」 「自爆特攻したって仕方ねえだろうがよ。オレ様はその程度の挑発でかんかんになったりしないぜ」 「挑発ではない。事実を言ったまでだ。奇妙なことだな、いや、喜劇めいたと言った方が良いか。幸福な人生を与えられた結果、ここまで弱くなる。皮肉なものだ――人形は実に愚かだ」 「……はあ?」 バクラが「意味がわからない」というふうな表情をしてパラドックスを見る。バクラだけでなく、他の三人もパラドックスの発言を理解し損ねてぽかんとしていた。 挑発で手元を狂わせる戦術にしてもどうも言葉が変だ。喜劇めいた幸福。それはまるでありふれた幸せを享受している人々を無知だなんだと嘲笑っているようで気分の良いものではない。 カードを繰る指を止めてバクラはパラドックスの言葉を問い正すように反芻した。 「人形、だと?」 「言葉通り、君達は皆すべからく神の手のひらの上で踊る人形に過ぎないということだ。君なら分かるんじゃあないかね。人形は知恵を付けるべきでない。林檎を食べて賢くなるべきではない。人形は人形のまま、御しやすい愚者のままが良い。そうだろう。そう思わないか――バクラ? もっと平易に言ってやろうか。君の宿主のように、だ」 パラドックスが厭味ったらしく、悪意を含ませた声音でそうカードを握るバクラに囁きかけた。 パラドックスの言葉はねっとりと絡み付くように悪質な響きを伴っている。明らかにバクラ一人を狙ったその羅列はまるで悪意の蛇のようだ。それは丁度皮肉にも、知恵の実を食べるようにはじまりの人間に唆したエデンの蛇に似ていた。 それまで冷静だったバクラの表情が変わる。一瞬だけさっと青冷めて、それからすぐに別の表情に染まった。それは非常に分かり易い憤怒の色だった。遊戯にも、どころか事情をよく知らない十代やヨハンにすら理解出来てしまう程のあけすけな怒りの感情だ。 バクラの顔が陰りを帯びる。カードを持つ手が、心なしか少し震えているようにも見えた。 「……おい。てめぇ、今、なんつった……?」 「君の宿主のように、と言った。違うのか? 私の記録にはそう残っている。正史で君は愚直な宿主の獏良了、お人好しの彼を利用するだけ利用して……最後には棄てたと。理想例だ。人形は、マリオネットはそうあるべきだ。一喜一憂して踊らされているのが彼らの幸福だという理念に君は賛同してくれると、データベースからは判断したのだが」 バクラの手の震えが酷くなる。パラドックスは心外そうに肩を竦めて「何がそんなに怖い?」と無感動な声で問うた。わからない、と顔に書いてある。この明白な怒りの感情を本当に上手く汲み取れていないのか、わざとなのかは遊戯には判断出来かねた。その動作はあまりにも人間らしくなかった。 バクラが面を上げる。歪んだ双眸が、パラドックスを睨めつけている。 「……ざけんなよ。貴様に何が分かる」 「なんだ。この期に及んで否定か。都合がいいな、利用しているのはこの歴史においても確かな事実だろうに」 「ふざけんな。ふざけるなよ。宿主を……了を……人形なんぞと、呼ぶんじゃねえ!」 そうして響き渡ったのは絶叫だった。 バクラの全身から怒気が発せられている。それでようやく、パラドックスもバクラの抱いている感情に理解がいったようだった。遊戯は二人で素直に驚いてその光景を見ている。 これ程までに激昴するバクラの姿を見るのは遊戯にとっても初めてのことだった。それも自分の目的が狂ってなどの理由からではない。今この闇人格は寄生して上手く騙し込み、利用しているとばかり思われていた宿主の為にああも眉をつり上げて喚くように叫び立てているのだ。それは感嘆に値する事実であり、また、奇妙なまでに納得のいく光景でもあった。 確かに、これまでにもその片鱗は見えていた。殺風景な獏良の部屋、使い込まれた家具、その風景に馴染んでいる「バクラ」。妙にこなれた手付きでコーヒーメーカーを操作する姿。気力を失った獏良の為に彼は自ら遊戯に協力体制を申し出までした。それはやはり、大昔にTRPGをやったあの時の千年リングの人格からは考え難い姿だ。 十年を超える年月がバクラを絆したのかもしれない。もしくは、獏良が歩み寄ろうとしたのかもしれない。そのどちらでもあるのかもしれない。しかし事実は一つっきりだ。 彼が甘くなったというその一言でしかない。 「宿主を人形扱いされちゃ黙ってられねえな。了はオレ様の千年たった一人の最高の器だ。今までのどの体よりもオレ様によく馴染み、オレ様に反抗的で、それでいてオレ様に甘い。この体は一つしかない。これまでもこれからも、オレ様の『お気に入りの宿主』はひとつしかない」 「愛情か。クルエルナの亡霊もさぞかし落胆することだろう。盗賊王に未だにそんな、脆い感情が残っていたなどとは」 「愛? 情け? 憐憫? ハッ、なんとでも好きに言え。オレ様の行動はんなもんじゃ括れねーよ。貴様のような玩具に何がわかる? 今分かったぜ、玩具人形よぉ。知らねえなら教えてやるぜ、オレ様を理解出来るのは世界で唯一! オレ様ただ一人だ!」 「……玩具、だと?」 「見抜けないとでも思ってたか。貴様からは『魂』を感じねえ。どんな人間にも纏わりついているはずのエクトプラズマーがない。死霊デッキは趣味だけで選んだわけじゃないぜ。宿主はともかく……オレ様には全て視えてんだよ。王サマの偽善ぶった魂も、そこのガキ共の甘ちゃんで夢みがちな魂も。貴様の空っぽの張りぼても! なあ、そうだろアンドロイド野郎」 バクラの仕返しのような挑発に今度はパラドックスの表情がひきつる番だった。酷く醜い顔だ。急速に彼の周囲の温度が下がっていくような錯覚と共に、動きの少ない表情が見る間にさめて、文字通りの能面になっていく。 「張りぼてだと」、と彼は抑揚のない声でわなないた。「玩具人形、と言ったか?」唇が震えている。 「……バクラ。私を人形と呼ぶか。造られた歴史の中で踊り狂う人形風情の分際で」 「何言ってやがる、その機械みてえな面ぶら下げた貴様こそが『人形』だろうが。魂ある人間は利用こそ不可能じゃないが、完璧で従順な駒にはならねえ。魂引っこ抜いて意思を奪ってしまえば別だがな。オレ様も流石にマリクの野郎みてえなことは出来ないね。ククッ」 マリクが千年ロッドの力で洗脳し、オシリスを使わせ遊戯に敗北をした「人形」のことを思い出してか鼻で笑う。瞳に光なきものをこそ「人形」と人間は呼ぶのだ。獏良了は、だから人形などではない。左腕の反逆を思い返しバクラは唇をぺろりと舐めた。 バクラから見て、パラドックスは紛れもなく人形だ。ボディは魂のない空洞に過ぎず、瞳にも光……光彩がない。バイクで空から降りてくるような輩だ。あれ程精緻な機械仕掛けの人形であったとしてもさして驚きはしない。むしろ、あれがもし人間のなまものの体だったら、という方がぞっとした。マリクの造った人形とは比べものにならない程に上手い具合に動くのだ。そういったものを造り出す手法は概ね一つしかない。 「神」を崇拝させることだ。信仰だ。バクラが嫌いなものだ。 「私を怒らせたな。人形だからと多少は優しくしてやっていたが……盗賊王バクラ。私を侮辱したことを命ある限り後悔させてやろう。せいぜいその大事な奪いものの体が死なないように祈るがいい!」 「はん、好きにしな。――オレ様はリバースカードを一枚セットしてターン・エンドだ。さあ、来やがれ。お前は最後に宿主を――人間を侮辱したことを後悔するだろうよ。例えこの場でオレ様をいくら傷付けようとも、オレ様を物理的にこのデュエルから降ろそうとも、だ。オレ様の宿主サマは大層頑張り屋のいい子ちゃんでね。そうそう簡単には死なねえとオレ様に約束しているのさ。『信じる人達が戦っているならせめて役割は果たす』ってね!」 「偽善者め。友情も親愛も脆いものだということを重々刻み付けてやろう。まずはお前からだ盗賊王、愛しの宿主様と共に眠らせてやる。……私のターン!」 パラドックスが宣言してターンが移行する。彼はドローしたカードを手札に加え、残虐な瞳を隠そうともせずに唇で薄く笑った。 「魔法カード『手札断札』を発動。お互いに手札を二枚捨て新たに二枚のカードをドローする。更に『トレード・イン』を発動。手札のレベル八モンスター一枚をコストにカードを二枚ドローする。更に手札から『闇の誘惑』を発動、カードを二枚ドローしてその後闇属性モンスターを一枚除外。私は『sinパラレル・ギア』を除外する! そして私は第一の悪魔を召喚する――慄くがいい。フィールドの『sin青眼の白龍』と二体の『黒焔トークン』を生贄に捧げ! 降臨せよ、『邪神ドレッド・ルート』!」 パラドックスはバクラの挑発返しでどうにも冷静ではいられないようだった。この「邪神」の召喚がその証拠だ。遊戯はこっそりと舌打ちする。この暴走が良い方に働くのか悪い方に働くのかはまだ読めない。 横目にちらりと見たバクラには既に先程の苛烈な怒りは見られなかった。千年リングに指で触れて撫ぜている。蹲って声一つ出さない獏良と心の部屋で少しばかり向き合っているのだろうか? それとも、パラドックスを逆上させることに成功した時点で、彼はもう目的を一つ果たすことに成功したのか。 パラドックスの宣言と共にフィールドを異様な圧力が付加される。地響きを伴って天を裂くようにして、一体の悪魔がそこに顕現した。邪神ドレッド・ルート。その姿を認めたヨハンは、冷汗を垂らしながら叫んだ。 「なんで……三邪神は、会長が……父さんがカードとして作るのを断念した禁断のモンスターだ。お前がカード泥棒だとしてもないものは奪えない! なんでそいつがそこに……」 「無論、作られた世界からこれを回収して来たまでの話。三邪神もまたこの歴史には不要なものだからな」 「馬鹿な。父さんが作らなきゃ誰がそんなものを作れるものか」 「決まっている。お前の心酔する天馬月行と天馬夜行だ。一つの歴史で盗賊王に殺されたペガサス・J・クロフォードの死後、天馬兄弟は暴走した。人間とはそういうものだ。お前の敬愛する兄君達もたがが外れればその程度の生き物でしかない」 「――兄さん達を馬鹿にするな!」 ヨハンが邪神を睨みながら言った。 「哀しみが人を狂わせることがあるとしても……お前なんかにそのカードを使う資格なんかない」 「資格? そうか、お前はカードの精霊をことのほか強く信奉していたな。だが、所詮精霊などというものは……」 ヨハン・アンデルセン、自らを愛してくれる父とたくさんの兄達を手に入れた「幸福な青年」を一瞥してパラドックスは彼の矜持を踏みにじる。世界最後の四人となった生前のパラドックス自身はお世辞にも恵まれたとは言い難い不幸で惨めな人生を送ってきた。毎日が地獄のようだった。食べるのにも困窮し、機皇帝の襲撃に怯え、ゲリラ兵のような生活を送った。 パラドックスは、いや、あの世界で生きていた人間は誰一人としてデュエルモンスターズの精霊などという不確かで曖昧なものは信じないだろう。彼らが信じられるものは確固たる形を持った役に立つオブジェクトそれのみだった。精霊が何の足しになるものか。彼らは人間を助けてはくれなかったのだ。 「まやかしにすぎない。私にとってはな。『天よりの宝札』を発動し、お互いに手札が六枚になるまでドローする。更に『強欲な壺』を発動してカードを二枚ドロー。そして私は手札から永続魔法『血の代償』を発動!」 「手札からトラップ?! そんなの出来るわけが……」 「いや、出来なくはない。しまったな、先程手札断札で捨てていたのは『処刑人‐マキュラ』か!」 「その通りだ。私はライフポイントを五百支払って『幻銃士』を通常召喚しモンスター効果発動、フィールドに存在するモンスターの数まで『銃士トークン』をフィールドに特殊召喚する。更にライフを五百支払い、『幻銃士』と二体の『銃士トークン』を生贄に捧げ第二の邪神『邪神イレイザー』を通常召喚!」 今度は二体目の邪神だ。二体の邪神が共鳴し合って、地響きが酷い耳鳴りをもたらした。耳がきんきんする。思わず耳を塞いだが不快感が肌から消えていかない。 パラドックスの手はそれでも止まる様子を見せなかった。彼は勢いのままにカードをディスクに叩き付け、最終宣告に踏み切ろうとする。 「まだだ。私達を穢したお前には最大の恐怖でもって叩き潰させて貰う。魔法カード『邪神降臨』を発動、このカードはフィールドに二体の邪神が存在する時に発動することが出来る。フィールドに『邪神の殉教者』トークン三体を攻撃表示で特殊召喚。『血の代償』の効果を発動し、ライフを五百支払うことで最後の邪神を召喚。絶望をその身に焼き付けるがいい。降臨――『邪神アバター』!!」 巨大な、絶望や悪夢で塗り潰したかのような漆黒の球体がフィールドに顕現した。 ぶよぶよとしたその球体は徐々に形を変え、「ドレッド・ルート」の姿を模した黒い像のようになる。アバター、つまるところの「神の写し身」。それがこのおぞましい「邪神」の能力なのだろう。 「……遊戯さん。『三邪神』は、昔父さんが『三幻神』を抑え込もうとしてデザインしたカードなんです。三幻神が強大な力を持っていて、そして製作の過程でそれに関わった人間が次々まるで呪いのように突然死を遂げていった……っていう話は遊戯さんならご存知ですよね。そのカードの力をなんとかして制御しようと試みて、試作段階の三邪神には三幻神に匹敵する能力が与えられました」 「……なるほどな。まさに邪なる神、か……三幻神も決して扱い易い存在じゃない。ペガサスが製作を断念したということは、そいつは……」 「三幻神クラスじゃなきゃ、恐らくたち打ち出来ない」 生唾を呑む音がやけに大きく響いた。十代とヨハンは焦燥を隠し切れていない。遊戯も思案顔だ。ただその中で唯一バクラだけが腕を組んで泰然と構えている。 バクラの目には迷いも恐れもなかった。揺るぎない信頼がその瞳の奥に見えたように、遊戯には思えた。 バクラの手が腕から離れ、指差しするようにすらりと伸びてパラドックスを示す。 「いつまでオレ様を待たせる気だ? 来いよ。オレ様を待たせていいのは宿主だけだぜ」 「死に急ぐような発言だな。ああ、その目は私が嫌いなものだ。絶対を盲信している。不確かなものに追従している。そんなものは全て全て幻でしかないということを知らない者のする瞳だ、それは。大切なものを奪われるまでそのことに気付けない。……ならば私がこの手で完膚なきまでに奪い尽くしてやろう。魔法カード『サンダ−・ボルト』を発動、相手フィールド上のモンスターを一掃する。行け、邪神よ――『邪神イレイザー』『邪神ドレッド・ルート』『邪神アバター』でバクラにダイレクトアタック!」 雷の強烈なエフェクトが発生し、フィールドいっぱいに広がっていた五体のモンスターが魔法効果で吹き飛ぶ。がら空きになったフィールドめがけて邪神達がその体躯をのっそりと動かした。邪神イレイザーの攻撃力は遊戯達のフィールドに残る二枚の伏せカードを参照して二〇〇〇。邪神ドレッド・ルートは神の名に相応しい四〇〇〇。そして最高位の三幻神「ラーの翼神竜」をモデルにデザインされた邪神アバターは、フィールドで最も高い攻撃力のモンスターを写し常にそれより高い攻撃力を持つように調整されるため現在は四一〇〇だ。防ぐ手立てがろくにないこの状況では、バクラのライフはもたない。 だが、この状況下でさえバクラは微動だにしなかった。目を閉じることもせず、ただじっと、哀れな邪神達の拳が迫って来るのを待っていた。 「バクラ!」 「何故そんな顔をする? 王サマよぉ。上手いこと攻撃をオレ様に集中出来て万々歳じゃねえか」 「だが――!」 「安心しろ。倒れてもこれは維持する」 「そういう問題じゃない! オレは……」 「宿主の体なら死守するぜ。問題ない。オレ様の精神はそんなもんで磨耗し切る程ヤワじゃない」 邪神イレイザーの攻撃がバクラにヒットして、彼は衝撃に退けぞった。ギリギリのところで耐えて、憐れみの目を向けたまま彼はパラドックスと邪神達から目を反らそうとせず態勢を立て直す。 続いて邪神ドレッド・ルートが攻撃モーションに入る。バクラのライフは最早二〇〇〇しか残されていない。 「墓地から『ネクロ・ガードナー』のモンスター効果を発動! このカードを墓地から除外することで、このターン一度だけ相手モンスターの攻撃を無効化する!」 十代の宣言に呼応して現れた姿が透けたネクロ・ガードナーが、バクラとドレッド・ルートの間に割って入りシールドを形成する。ドレッド・ルートは攻撃を弾かれてそのまますごすごとパラドックスの前に帰って行った。しかしそれも一時凌ぎに過ぎない。すぐさまパラドックスの指示に従って邪神アバターが攻撃に移った。もうこれ以上の防御策はない。 「バクラ! きみは――」 「うるせえ! 王サマ、貴様は黙って見てな。ガキ共もだ。オレ様にも意地ってもんがあるんだよ!」 千年リングを手に持って鳴らし、バクラはにやりと笑った。遊戯が再び口を開きかける。だがそれは実体なき器の遊戯の無言の腕にすんでのところで阻止され、彼がもう一度バクラの名を呼ぶことは叶わなかった。 遊戯が魂の器、半身にも等しい全幅の信頼と愛情を寄せる相棒に戸惑いの視線を向ける。それに静かに首を振って諭すように武藤遊戯は言葉を紡いだ。 『ねえ、もう一人のボク。ボクはきみに言ったはずだ』 「相棒」 『ボクは、バクラくんを信じている』 半透明の遊戯は、強く固い信念を感じさせる眼でパラドックスを見据え、確かな声音でそう言い切った。 邪神のダイレクトアタックを受けてバクラが大仰に吹き飛ぶ。猛烈な勢いで跳ね飛び、そのまま彼の肉体はビルに激突した。土煙が上がりコンクリートが崩れ落ちる。まともに巻き込まれたらまず助からないであろう規模だ。どころか、命すらも危うい。 十代とヨハンは蒼白な表情で土煙が晴れて段々と被害が顕になっていくのを眺めている。やがて一帯が晴れ渡ると、人間の体が現れた。体中擦り切れて酷い怪我だ。だが命に関わる程ではないようで、それは彼を起点とする結界が滞りなく維持されていることが証明していた。 遊戯が息を呑む。バクラの胸元では千年リングがひとりでにざわついて、何か感情を示しているようでもあった。 「……ふん。千年リングの力で死は免れたか。害虫のようにしぶといな。だが――もうその男にターンは回ってこない。私はカードを一枚伏せてターン・エンド」 「師匠、遊戯さん、バクラさんは……!」 『十代くん、ボクがもう一人のボクに言ったこと、聞こえてなかったかい? 彼を信じて。彼は、彼の守るべきものの為にその言葉を守るはずだ。彼は大丈夫。とても、強い人だ。バクラくんも、獏良くんも』 目を細めて美しく微笑む。「わかりました、あなたがそう言うのなら」、と十代は頷いた。一先ずバクラは、それでいい。 だけど問題は信じていれば解決出来るわけじゃない。聳え立つ三体の邪神達はその厄介極まりない固有能力を余すことなく保持して存在感を放っている。息が苦しくなるような威圧感だ。一体これを、どうしたらいいというのか。 「さあ、君達のターンだぞ。仲間の仇打ちでもなんでもやるといい。私のこの、三邪神に勝てるというのならな」 パラドックスがまるでもう勝負は決まったとでも言いたげに勝ち誇った声で言った。それに苛立ちを覚えないでもないが、この圧倒的アドバンテージ差は否定しようのない現実だ。こちらのフィールドには既にバクラが残した伏せカードが一枚と結晶化したルビーしか存在していないのだ。 気分はあまり優れない。もう、どうにもならないのかもしれないという最悪の予想すら脳裏を過った。 ヒーローになりたい。自らが操る精霊達のような正義の味方になりたい。でももし自分の力が及ばなかったら、奇跡でもなんでもいい、誰か助けて、そんなことを思う。絶望に全てが変わる前に希望を与えてくれる、力強い誰かを十代は今待ち望んでいた。だけど、そんなことは起こりっこない。有り得ないってことは分かっている。そんなことは重々知っている。 それでも願わずにはいられなかった。神様、今まであんまり信じたことのない神様。もし不信心な俺の願いを一つだけ聞いてくれるのなら、俺に誰かを守る勇気をください。 だけど神様なんていないから、いくら祈ったって仕方がない。 「――十代さん!」 そのはずだった。 力強い声がした。どこからともなく唐突に、こいつなら絶対になんとかしてくれるって、そういうふうに思える声がだ。振り向くとそいつは空から急に現れたみたいで、へんてこな赤い龍のようなもやに包まれて、これまた真っ赤なバイクに跨っている。ヒーローに憧れる子供のように混じりっけなく純粋に「かっこいい」とそう思った。かっこいい。青いジャケットを翻して、ものすごい勢いで地面に向かってくる。 着地に失敗するかなと思ったけどどうやらそんなことはなかったみたいで、青年はふわりとバイクを地に着けてだっとこちらに駆け寄って来た。「十代さん、」と彼はまた十代の名前を呼んだ。「遊戯さん、ヨハンさんも」それから共に戦っていた人達の名前もだ。青年は一先ずの安堵の息を吐いてきっ、と仮面の男を睨み上げる。 「君は……」 「赤き龍とシグナーの痣。お前は《正史》の不動遊星か。何故だ? 最もゼロ・リバースの影響が強い不動遊星の時代は真っ先に消滅して然るべきだというに」 「答える義理はない。どの道お前はここで終わる。……あの、大丈夫ですか。俺の名前は不動遊星、この世界から見て百年と少し後のパラレル・ワールドからやって来ました。パラドックスにこの時代を改変させるわけにはいかない。助けになります」 「え、いや、それよりなんで名前……」 「《決闘王》武藤遊戯、《HERO使い》の遊城十代、《宝玉獣》のヨハン・アンデルセン。俺の時代でもその名は伝わっています。もう一度あなた方に出会えて……間に合って本当に良かった」 遊星がはにかんで見せる。この青年のあらゆる所作は堂々として英雄じみていた。においが、空気が確定的に違う。この男はまず間違いなくこれまでに幾多もの危機を救って来たのだ。世界の英雄だった。紛れもなくだ。 「今は一分一秒が惜しい。まずはあの男を倒すのが先決です。それから、少しでもお話がしたい。――伝えたいことがあるんです、とても大事な」 「遊星」 「パラドックス。ライフを四〇〇〇足せ。俺は初期手札を五枚ドローしバクラさんのターンを引き継ぐ。異論はないだろう、それともまさか、俺が怖いのか?」 「大丈夫です、俺に任せてください」と十代に返して遊星はパラドックスに宣告する。パラドックスは苛立たしげに頷いた後好きにしろ、ならば私も好きにやらせて貰うまで、と言ってライフを加算した。遊星の口端が僅かに釣り上がる。まるで獲物を見付けて「かかったなぁ?」と舌なめずりをする肉食動物のようだとそう思った。 |