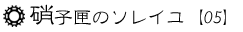「やどぬし」 しんと張りつめた静寂の中で、ある時突然にその言葉が真暗な心の部屋の中に響き渡った。声音にはいつものような覇気がなく、酷く疲弊して掠れている。だが、優しい声だった。獏良にはそう思えた。 「宿主。頼みが、ある」 バクラの声を聞くのは獏良にとっては本当に久方ぶりのことで、だから余計に優しく耳をくすぐったのかもしれない。ゆっくりと振り向いた先にいたバクラは声の通りぼろぼろになった体をなんとか気合で立たせているといったそんな風体だった。肩で息をしている。 獏良はまずなぜ、と首を傾げた。こんなふうにバクラを傷付けられる奴なんてそうそういない。 「バクラ、どうしたの。なんでそんなふうに傷付いて……」 「悪い。お前の体を綺麗なままで守り切れなかった。闇のデュエルでのダメージをもろにくらっちまってる。だがまあ、命には別状ない。……オレ様も流石に少し、だりぃ……」 「少しなんてものじゃないじゃないか。全身ずたずただよ。それに闇のデュエルっておまえ、一体」 「王サマに貸しを作りたくない。……頼む。行って助けてやってくれ。残した伏せカードを発動出来りゃ、王サマもやり易くなるはずだ」 息も絶え絶えといった声で、だが眼光に宿るプライドの鋭さは失わずに千年リングの闇人格は言葉を繋ぐ。バクラはいつも強気だ。 だけど獏良も、自分が納得出来ないことに対してはそれなりに強情なたちだった。だから頷く前にまず、疑問を彼にぶつけた。 「ねえ、そういえばボク、いつからここにいるの? 全然、最近何してたか思い出せないんだ。最後にご飯を食べたのはいつ? 誰かと喋ったのは? そもそも、おまえとこうやって顔を合わせるのだっていつぶりか……」 「ぴったり二十日だよ、宿主。天音の形見を失ってお前はここに引き籠もっちまった。その間の食事諸々とスケジュール管理はオレ様がやっておいたから今負った怪我以外は健康にも日常生活にも支障はないはずだ。今は、パラドックスとかいう歴史を変えようとしてるイカれチート野郎と変則四対一デュエルの最中で、あと一手が足りてない。遊戯も弟子とその連れのガキも追い詰められて結構焦ってるな」 「――天音の」 獏良は小さな声でわななくように反芻する。途端に忘れ去っていた記憶が返ってきて息を呑んだ。目の前で形見のカードが光になって消えた、あの焦燥。目を瞑ったが、幻はまぶたの裏に焼き付いて消えようとしない。 それを見たバクラが辛そうにまなじりを下げた。 「まだ思い出したくなかったか」 「……うん。でも」 「なんだ」 「バクラが言ったってことは、必要な時なんだね、今が」 「ああ」 「それなら、ボクはそれに応えないといけないって、そう思う」 起き上がって腰を払う仕草をする。もう納得したから素直に頷いてバクラの手を握った。すり剥けた表皮が少しささくれだって、まだ止まっていない血が浅いかすり傷からぽたりと垂れている。血の色は赤かった。それは獏良の体が流す血の色だったかもしれないけれど、少なくとも獏良は彼が言葉よりも人間じみて情というものも持ち併せているのだということを信じている。 気安めにしかならないが、傷口をひと舐めしてやるとバクラはなんだか少し困ったような表情になってやれやれと頭を横に振った。 「行くよ、ボク」 「……そうか」 「友達のピンチなんだ。ボクやみんなのために遊戯君が戦ってくれてる時に、バクラがこんなに傷付いてボク一人だけ何もしないのは嫌だな」 手を握ったままそう言ってやると「ばかな宿主」と溜め息混じりに苦笑して、擦過傷だらけのちょっとばかり汚れた体で、全身でハグをしてくれる。「現実で怪我してるのはお前の体なんだからな」と言い含めるように耳元で告げたバクラに「わかってる。大丈夫」と気丈に返してくすぐったい温もりに甘んじた。 それから少しして、不意に皮膚と皮膚が離れ離れになる。すかすかした冷たい空気が今まで触れ合っていた部分をあっという間に冷ましてしまうこの瞬間が獏良はいつも物寂しくて仕方なかったが、だけどそういうものだからどうしようもないのだといつかバクラは視線を寄越さないままで言っていた。 「墓地にブラック・マジシャンが落ちてる。リビングデッドの呼び声を残してあるから、タイミングを見て蘇生してやれ。あの用意周到な王サマのことだ、何かしらコンボを用意しているだろうよ」 「了解バクラ」 「ああ。頼んだ、『了』」 バクラは笑んで、そして瞳を閉じ倒れ込んだ。心の部屋の床がつるつるのフローリングや冷えびえとした大理石でなくて良かったと心底思う。獏良のつかみどころのなさをそのまま表したようなふわふわの地面は、今のバクラに一番必要な休息のための寝床としてとりあえずは機能するはずだ。 内緒の話をするように彼の元に歩み寄って、耳打ちをする。彼と仲間達のためならなんだって出来ないことはないというようなそんな気分だった。 「おやすみバクラ。今度はボクの番だ」 バクラはすぐに意識を手放してしまったのか、獏良の声に反応することなく端正な顔を覗かせていた。 『解けたのか、結界は』 鼓膜に届いた音と、アンドロイドがさっきまで横たわっていたはずの場所を確かめて霊体の遊戯がぽつりと尋ねた。それに遊星が無言で頷く。レンチボックスからあぶれたネジまきの工具がぼんやりと地面に転がっている。 獏良は千年リングを撫でて見知らぬ青年である遊星のことをじっと見つめていた。 「あの……バクラの指示通り、ボクがこれを鳴らしたら解除されたみたい。逃がすの、まずかったのかな……」 「でもバクラくんがそう言ったのなら、問題ないんじゃないかな。必要な限りは死守するって言ってたもの」 「問題ないです。むしろベストなタイミングでしょうね。これ以上長引かせたら最悪回収係ともう一戦連続でやりあうはめになっていたかもしれない。連中は機密を守るために少し躍起になっているように見受けられる」 「れ、連中?」 「パラドックスは単独犯ではないんです。俺のいる未来では『イリアステル』と名乗りましたが……今は、もう『ヴェルズ』と呼んだ方がいいかもしれない。歴史修正を目論む組織ですよ。太古の昔から歴史に介入し都合の良い形に管理してきた、そういう奴らです」 『ドーマと似ているな』 「相違は未来をシミュレートした上で強引に修正をかけようとしているか否かだと。イリアステルは全ての『最終結論』を知っていた。人類が滅ぶ未来を」 工具をきっちりと仕舞い込み、遊星が立ち上がる。それと同時にコール音が鳴り響いて騒々しい電子サウンドをまき散らした。――流行のアイドルの得意曲。ヨハンの携帯だ。 「あ、それ今人気絶好調のデュエル・アイドルの」 「この前みたいに切っとけよミーハー……」 「だってデュエル中に掛かってきたらそれじゃ気付けないだろ。もしもし? 夜兄?」 敬愛する兄からの電話であったらしく、声のトーンが「兄に甘える弟」のそれに少しだが変化を見せている。十代がこれ見よがしに聞かせている溜息にもお構いなし、気付く素振りがないからひょっとしたら聞こえていないのかもしれない。彼にとって家族というものはそれ程に大切なものなのだ。デュエルモンスターズの宝玉獣達も人間のミニオンらもどちらも同じぐらいに絶対だった。 それがなんだか面白くないような気もするけれど、すっきりしない気持ちの正体はいま一つ掴めない。 「うん……うん、ちょっと待って……あのさ、遊星、うちの兄達……I2の技術者なんだけど……が君と話がしたいって。ここのモニタリングして貰ってたんだけどどうも君に興味を持ったみたいでさ」 「構わない。その方が俺も都合がいいかもしれない。この時代の技術者に情報を直で残せるチャンスは貴重だ」 「了解。じゃ、そういうことだから夜兄、スピーカーフォンにしておく」 ホログラフモニタが遊星の前に投影される。ソリッド・ヴィジョン・システムを応用して小型携帯機に組み込んだ天馬兄弟の試作品だ。 知識でこの時代ではかなりレアなものだとわかったが、遊星の時代では別に珍しいものではないため遊星は反応を特に返さず「どうも」と会釈して何か話があるのなら早くしてくれと顎で促した。何しろ時間がない。こうしている今も刻一刻とタイムリミットが近付いてきているのを遊星は感じていた。 「天馬兄弟、あなた方のことは一方的に知っている。俺の時代のKCでも時々名前が出るので……自己紹介は」 『いえ、必要ありません。不動遊星博士、でいいんでしょうか。先程までの話も盗み聞きみたいだけれど全部見せて貰っていましたから』 「……博士と呼ばれるのは好きじゃない。それは俺の父を指す言葉なので」 『それは失礼。ところできみはさっき興味深いことを言っていましたね。タイミングがどうというやつです。それはボディの回収と量りにかけて遥かに厄介な出来事だったと?』 にべのない断りに特に構うふうでもなく月行が質問を投げ掛けてくる。遊星は頷いた。待機していたのはアポリアの一体、恐らくはルチアーノだろう。ルチアーノは容姿こそ少年のものだが、残酷な性格と激情しにくい性質を兼ね備えていて少なくともプラシドよりは厄介な相手だった。あれに出てこられたら、連戦で勝利してポイントを維持出来たかは怪しい。 かといって何の防御策もなしにさっさと回収されてしまっていたらそれはそれで交戦が発生していた可能性があるし何よりパラドックスが置き土産に話を語って聞かせる機会と必要なものを手に入れそびれてしまっただろう。結果オーライだ。 「折角守った歴史の交錯点を強欲で潰すわけにはいかない。だが結界が機能している間に時間稼ぎは出来たから、参考に部品のいくつかはパラドックスのボディから失敬している。問題はない」 ぱっ、と開かれた遊星の手袋に覆われた手のひらの上で小さなモーターのような部品が踊る。「補助モーメントです」と事もなげに言い放って見せられたそれが一体いかような役割を果たすものであるのか十代にはよくわからなかったが、誠実そうな見た目に反して意外と手癖が悪いのだなということはわかった。 『未来技術を駆使したオーバーテクノロジーの塊ですか。技術者達が喜びそうだ』 「一応基本原則というものがあるから、あまり多くの目には触れさせたくない。解析を頼みたいのはやまやまだが、厳格にセクションを守って貰えると助かる。……俺達自らの手で歴史を誤らせるわけにもいかない」 『わかりました。信用のおける者数人で行いましょう。海馬兄弟あたりが見解の一致するところかもしれませんね。我々は解析から先、どこを目指せば?』 「時空渡航理論の構築と実践レベルまでの実用化を百年で。その時代に技術が確保されていないと敵方を追い掛けることが出来ない。こちらの世界では赤き龍の力を借りることはどうやら出来ないみたいだからな。この先数十年で技術のインフレが起こるから、多分不可能じゃない」 モーメントの実用化がなされると同時に技術は空前絶後の大発展時代を迎える。遊星の時代で後に「第三次産業革命」と呼ばれるようになったそれはモーメントによる破滅を前提としてイリアステルに設計されたこの世界ではまず間違いなく訪れるだろう。それを回避するために技術進化を促進させるというのも皮肉な話だが、そうなって貰わねば遊星が骨を折った甲斐もないというものだ。仕方がない。 『きみが手に入れたパーツは何に役立ちそうですか?』 「製作年代を割り出すことで座標を特定するのに使えるはずだ。時空渡航の技術を手に入れただけじゃどうしようもないからな。メモリチップを内蔵しているモーメント・エンジンがあれば時間が掛かっても解析は可能だと俺は考える」 天馬兄弟と遊星の専門的な会話においてけぼりをくらった面々はよくわからないという表情を露にしていたが、構う暇もないのでそこから更に込み入った説明を続けるとやがて夜行がなるほど、よくわかった、と言って礼を述べた。 それで一区切りがついたと見たのか、遊戯がほうと息を吐く。 「なんだかすごいねえ。遊星くんは、そういうの、詳しいんだ」 「一応、KCの技術開発部門に勤めているので。だから本来は俺が解析にあたるか、そうでなくとも協力をしていくべきなんでしょうが、すみません。説明だけして丸投げする形になって」 「……そういえばきみは、ここに現れた時にも十代くんに時間がないと言っていたね。それに関係のあることなのかい? さっきから説明も急ぎ気味だ」 遊戯が鋭く尋ねる。遊星はほんの少しだけ押し黙って、それから「……はい」と申し訳無さそうに肩を下げた。 「俺は、間もなく存在が消滅する」 ◇◆◇◆◇ 遊星の住む街が突如として様相を違え、崩壊を始めたのは陰鬱な雲が空をいっぱいに覆った昼下がりのことだった。ここのところ不吉な空の色が続きますね、と部下達が不安がってよく話題に出していたことを気にも留めていなかったことは多少後悔している。だがあの時後悔していても何かが変わったわけではないのだろうということは、今はもう理解していた。 一瞬だった。崩壊は前触れも何もなく訪れ、ネオドミノどころか世界全域を覆い尽くし、ゼロ・リバースなど目でもないような陰惨凄絶な結果を遊星に突き付ける。――世界は滅亡したのだ。 硝子が弾け飛ぶよりも呆気なく脆く、遊星が守ってきた世界は終わりを告げた。インク壺が引っ繰り返ったみたいに視界がくろぐろと染まっていく。『世界は終わった』聞き覚えのある声が遊星の耳元で囁いた。『貴様が守ろうとしたものはもうどこにもない。消えろ、不動遊星。邪魔者の英雄』昔遊星が戦い、打ち倒し、壊れたはずのアンドロイドの声だ。 「アポリア! 何故だ!」 叫んだが、それすらも空しくブラックホールに吸い込まれていく。赤き龍の痣があれば、と縋るような思考に走った自分に気が付いて情けなくなり、唇を噛む。暗闇の中で遊星は孤独だった。出口の見えない巨大な蛇の腹の中に呑まれて、惨めにも生き続けて、死を順列だてて待たされている気分だった。 それから気が滅入るような長い間、その中で身を丸めていた。一ヶ月よりも長く感じたが、実際は三日もなかったかもしれない。議論に意味はない。 ある時ふと光が差した。なにぶんずっと暗闇にいたものだから酷く眩しかったが幸いにも視力を損ねることはなく済んだ。 『――不動遊星!』 「誰だ?!」 『あなたを起点として歴史の改竄が開始されている。そこを脱してターニング・ポイントへ向かってください。あなたなら出来るはずだ』 「無理だ。何をどうやったらここから出られる。俺はここで消える他ない」 『可能です。あなたの存在はあなたを守護するアステカの神によって保たれていますが、しかしそれもどうやら殆ど限界のようだ。神を呼んで過去へ向かってください。詳しい話はまたその時に』 「待ってくれ。赤き龍が俺を守護していると言ったな? では他のシグナーの仲間達は」 必死になってそう問い正す。一縷の望みを託した問いかけだったが、返答は冷たいものだった。 『残念ながら。あなた一人をなんとしても守り抜くために全ての力を結集させたようです。この時空の前後百年での生存者はあなた一人だ』 「……本当なのか」 『ええ。ですから、時間がないのです。私を信用してくれますか、正史の英雄よ――私はあなたとは別のパラレル・ワールドに存在するZ‐ONE。あなたに焦がれた愚かな科学者の、また別の末路です』 暗闇の中でゾーンはそう薄く笑んで言って聞かせる。生唾をごくりと呑み込んだ。藁をも掴むような話だったが、ここでただ漫然と死を待つよりはいくらも有意義だ。 「……いいだろう。その言葉を信じよう、ゾーン。俺が戦ったお前も、俺を謀るようなことだけはしなかった」 気力を取り戻したことに反応でもしたのか、背に熱いものが走り、ぼんやりと赤い光をあたりに生み出す。遊星に残された仲間達との絆の証、シグナーの痣の完全形。 奇跡を起こすための意志の力だ。 「話を聞かせてくれゾーン。これから俺が何をすればいいのか、どうしたら、俺の世界を取り戻せるのか」 『……適応が早いですね』 「父さんにまた叩かれるのは御免だ。思い出したんだ、あの時俺はもう二度と絶望しないとそう決めたんだと」 現れた赤き龍に頼み時空間のひずみへ抜け出す。懐かしい青いジャケット、遊星号、そして馴染みのデッキ。賭けるに足る全てが揃えられていて、妙な感心を覚えた。 『……では、お話しましょう。私の知ることを全て』 ゾーンが言った。 「……どういうことだい、それ」 「俺がパラレル・ワールドから来たことは話しましたよね。……元々、あなたがたの存在しているこの世界はあってはならないものなんです。歴史を強引にねじ曲げて、摂理を破壊し、無理矢理に出来上がった世界。それに圧迫されて元々の正しい歴史が消え去ろうとしているのが現状です」 信じられないでしょうが、と遊星は眉根を下げる。それから「すみません」と小さく謝罪の言葉を口にしてまっすぐに遊戯を見つめた。 「……俺のいた世界の歴史では、『決闘王武藤遊戯』は既に一人でした。十代さんに教えて貰ったことがあります。名もなきファラオ、もう一人の遊戯さんは武藤遊戯自らの手で『光の中に還った』のだと。遊戯さんが高校生の時です。共に過ごした時はほんの一年そこらで、……だがそれが最良にして恐らく最後のタイミングだった」 まるで己の失態を恥じてでもいるかのように遊星の表情が翳りを帯びる。ヨハンと十代が話にうまく付いてこれずにいる中で二人の遊戯は悲しむでも嘆くでもなくただじっと遊星の言葉に耳を傾けていた。遊星がこれから言うであろう言葉を予期して、ただ、静かだった。 「厳しいことを言いますが、恐らくあなたはもうこの歴史では名前を見つけることは出来ない。そういうふうに歴史が歪められてしまった以上……この座標が本来の歴史を守る為の最後の砦であることは確かで、言い換えればそれは他の座標は既に改竄されてしまった後に他ならないということになる。名もなきファラオの神を統べる王の名は歴史に埋没したまま……普通の人間である武藤遊戯は生涯を終えファラオの魂はまた千年パズルの中に戻ることを余儀無くされる。だから、俺は傲慢を承知であなたに頼みたいことがある」 『いいぜ。遠慮しないで言え』 「ここからもう百年程先の未来でこの世界での俺……不動遊星が生まれる。未来の俺へ伝言を。甘ったれで腑甲斐無いとは思いますが、なんとかサポートしてやって欲しい。パラドックスは最後に俺に願ったんです、友を救ってくれと。……そしてそれが可能であるのは大幅な介入が発生して恐らくは彼ら歴史改変者達の思惑から最も外れたルートに入っている本来の俺がいる時代、ネオドミノが栄華を極めたあの場所であると」 なりふり構うことをせずそのままストレートに遊星は懇願した。その姿に十代が目を丸くする。デュエルの最中に遊星を英雄のように堂々としている、なんて言っていたからショックを受けているのかもしれない。遊星にもそのショッキングさは覚えがあった。あの凛々しくて力強く誰よりもヒーローじみていた憧れの人が双子の母だと知らされた時のショックは多分もっと手酷かった。 顔を上げろ、という凛とした声が諌めるように降ってくる。名もなきファラオは腕組を解いて『そうされるといたたまれない』と首を振った。 『何を気にしているのか知らないが、もう少し堂々としていてくれ。やりづらくてかなわない。きみの願いは聞き届けるし、そのために尽力を約束するぜ。俺は嘘は吐かない』 「遊戯さん、でも、いいんですか」 『おいおい、きみが頼んできたのにいいんですかはないだろう。きみは俺を特別視しすぎていないか? 弟子入り前の熱が上がっていた十代みたいだぜ』 「……遊戯さんは俺の背中を押してくれた人なので。特別なんですよ、どうしても」 『へえ?』 気になるな、と口にして彼はふむふむと頷く仕草をする。その時のことは、遊星の体験の中でも一際鮮烈な体験として記憶に刻まれていた。何しろあんなふうに力強く答えを真正面からくれたのは後にも先にも彼だけで、遊星にそうやってまっすぐな自身を他意も汚れもなく示せるのが武藤遊戯と名もなきファラオに限られていたのかもしれない。 スターダスト・ドラゴンを奪われて焦燥していた遊星に彼が与えてくれた言葉と、それに連なる華麗な戦術のことを遊星は忘れないだろう。たとえこの身が世界から滅ぼされても。 「昔も、まだ俺がもう少し子供だった頃にああしてパラドックスと戦ったことがあるんです。十代さんと遊戯さんと一緒でした。俺はその時遊戯さんに言われた言葉に胸を衝かれたような思いがして……あの日から一度だって忘れたことはない」 「もう一人のボクがかい? なんて言ったの」 「はい。『そうさ遊星……オレ達は、前に進むしかないんだ』と、そう」 はにかんで確かな声音でそう言った。見やると、問い出した当のもう一人の遊戯が空中で少し照れている。 遊戯はこくりと頷くと遊星の手に自らの手を重ね合わせた。 「そっか。もう一人のボクらしいね。うん、そうか……前に進むしか、ない……。遊星くん、きみがこの時代に来ることはともすると後ろ向きの遠回りに思えなくもないのだけれど、これは君にとっての『前向き』で間違いないんだね」 「はい」 「安心したよ。それならみんなで気持ちよく納得してきみの頼みを請け負えるからね。伝えたいことは、これで全てかい? ――そろそろ時間なんでしょ」 遊戯の手のひらは柔らかく、傷の無い美しいかたちをしていた。遊星の無骨な工具汚れやまめのある手のひらと比べると一目瞭然だ。遊星の知らない幸福な家族の母親の手のひらというものに似ている。あの、遊星が敬愛していたアンデルセン一家の母にあたる人もこんなふうな大事に守られている指先を持っていた。 「わかったんですか」 「わかるさ。さっきから少しずつ、爪先から薄くなってきているもの。ボクね、観察力は結構あるんだよ。そうでしょ?」 「そうですね。……限界です」 怯えるふうでもなく、淡々と答えた。 「もうあと数分ももつかどうか」 「やっぱりそうか」 遊戯は驚かなかった。遊星も表情を変化させずにいる。中途半端なかたちで父の元へ行ったら何か言われるだろうか、それはあまり楽しくないことだなと思ってはいたがそれだけだ。 実のところ、消えることへの恐怖はあまりなかった。仲間達ももうとっくにこの虚無のあかりに呑み込まれて消えていってしまって、あの時代の人間で生き残っていたのはそもそも遊星一人だけなのだ。 赤き龍を叩き起こして、最後の役割だけは果たし終えた。改革された歴史に真実を伝える橋渡しの役目だ。傲慢で身勝手な願いかもしれない。歴史を正せば、この世界で培われた全ては消えてなくなってしまう。 だけど遊星の願いを彼らが断ることはないだろうという確信は持っていた。 武藤遊戯も、遊城十代も、不動遊星にとっては変わることのない不変の英雄だった。 「遊戯さん、十代さん」 『……ああ』 もう一人の遊戯が消滅して行く遊星の肉体を眺めながら返事を寄越す。「お願いです」ともう一度頭を下げると遊戯の指が手のひらから離れて遊星の頭を起き上がらせた。 「俺は、あなた方を信じています。世界中の誰よりも尊い憧れの俺のヒーロー達。お願いです。俺の言葉を、俺自身に、」 『勿論だ』 「パスワードは……」 遊星が耳打ちをすると、もう一人の遊戯が彼の頭を撫でるように透き通る幽霊の手を翳す。遊星の体はもうしゃがみ込んでいた下半身の殆どが半透明で、爪先は消滅していた。「誰よりも尊い憧れのヒーロー達」と口にする唇には蓄積された疲労が見え隠れしている。 遊星の姿は戦い続けてきてようやく安楽の場所へと行こうとしているヒーローの姿のそれだ。傷つき、しかしそれでも希望を失わず、足をもがれた最後には希う未来を誰かに託して繋げようとしている。 綺麗でまっすぐな魂の色だ。 『全部わかってる。きみはもう、眠っていい。後は全部任された』 「……ありがとうございます」 薄く透けた体で笑う遊星の姿は、今までに十代が見たどんな人間の姿よりも儚くて、でもどこかでほっとしているように見えた。肩の上にずしりと積まれた責任や後悔、焦燥、そういった重荷から解放されてようやく、初めて彼はまぶたを閉じることが出来たのだ。 『おやすみ遊星』 名もなきファラオが愛おしむように言った。民を慈しむ王のような、それでいて我が子を労る父親のような、厳格だが確かな愛情がそこにはある。 『尊き未来の英雄、俺はきっとまた、『きみ自身』と出会える日が来るとそう信じているぜ』 存在しなかったものとして粒子になり消えていく遊星が、最後に小さくあの謙虚な声で「はい」、とそう答えた幻を、十代は垣間見たようなそんな気がした。 |