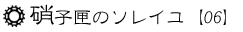くず鉄の城に王はいなかった。無機質な回廊をがらくたに成り果てた同胞を抱きながら一人で歩いていると、ふとセンチメンタルな気分というものを想起してしまって気分が悪い。生前のデータからプリセットされた感情の真似ごとにしかすぎないというのに、眼球のあたりが無性にごろごろして嫌なのだ。ままごとで涙を欲するのは、もうたくさんだった。 この前も同じことを思ったばかりなのにまただ。人間みたいにすぐ激情的になるのは短絡なプラシドだけで十分なのに、でもきっとこの感傷はまた幾度もやってきてはルチアーノを襲いたてる。 「馬鹿な奴。本当にネジを拾わせにいくとか、どーいうつもりだよ。母さんのとこ持ってったってもう完全蘇生は出来ねーぞ」 気分を紛らわせようとするみたいに声を掛けたけれど返事はなかった。返事なんかもう来ないってことはわかっていた。パラドックスは『壊れた』。単にそれだけのことで、それ以上でもそれ以下でもなく、そういう事実だった。 偽者の機械人形達のつくりものの生命、モーメント・エンジンが回転することで生み出されていた思考の劣化コピーが止まる時が彼に――いや、それに訪れたのだ。 いつかはルチアーノも辿るであろう末路は言葉なく雄弁に語り掛けてきていた。 「忌々しい英雄ども。いつもいつも、これだ……しかも正史の不動遊星だって? ちゃんちゃらおかしいよ。でもまぁ、あいつももう消えちゃったんだけどぉ」 動かない人形が安置されている装置はまるで棺桶のようだった。破壊されたパラドックスのボディを受け取ったシステムアームがそれを容れものに安置して、見た目だけはきっちりと整えていく。腕を綺麗に組まされて造花の白百合を容器いっぱいに埋められていく様子を見ていると死化粧を眺めているようで滑稽だ。 血の通わない頬は青白い。オイルさえも奪われて、所在地の足が付きかねないパーツだけは死守したけれどいくばくかの内蔵部品も抜け落ちて。ミイラの方がまだまともに死者ってやつをやっていただろう。機械人形は結局葬儀に至っても機械のまねごとに過ぎないのだった。 「嫌いだ、嫌い、嫌い、大ッ嫌い。どいつもこいつも……あいつもだ。信じない、許さない、僕に心なんてない。僕にあるのは造物主への裏切り防止プログラムと何もかもが計算の上に成り立ってる人工知能だけだ。プラスチックの安っぽいイミテーションでしかないんだよ。なあ《母さん》、あんたはいつか僕ら人形にも心が、誰かを愛する気持ちを持つ資格があるって言ったけど……」 棺桶の透明な蓋がスッとオートメーションで閉じられる。パラドックスの表情はとても穏やかで、丁度人の言うところの安らかな死に顔というべきものを表していた。それもAIが神経コードに伝達してかたちづくらせたものだ。 だけどルチアーノにはどうしても、それが機械人形の嘘真似には見えない。 「僕はそんなの信じないね。嘘っぱちさ。その証拠にいつまで経ってもあんたの待ち人は来ないし、そしてパラドックスは壊れたんだ」 ひとりだけ満ち足りた顔をしやがって、と嗚咽のような掠れ声がひっそりと続く。幸福の青い鳥を知らないんだな、と笑った《聖女》の声が脳裏でこだましていた。『チルチルとミチルが幸福の青い鳥を探しに行く話さ。二人はそれをずっとずっと遠くまで探しに行くんだけど結局見つからなくて家に帰ってくる。そして気付いたんだ、青い鳥がどこにいたかってこと』……彼女はそう、耳障りな声で嬉しそうにさえずるのだ。『青い鳥は、ずーっと二人のそばにいたんだ』。 ルチアーノにはわからない。世界が幸福になった分の不幸まるごと全てを押し付けられているような彼女がどうしてそんな顔をしているのか、わからない。 「……龍亞、待ってなよ。もう一度僕自ら、お前に会いに行ってやるから」 ルチアーノは誰に聞かせるでもなく天蓋を仰いで唇を歪めた。その背景でセキセイインコの剥製が古ぼけて染みのついたポピュラー・ミュージックを延々と歌い続けている。神の居城《アーククレイドル》、くず鉄の王ゾーンが組み上げた最後のアルカディアの片隅からひっそりと設えられたカタコンべに響き渡るそのメロディは陽気で愛らしく、今この場においてはちぐはぐだった。 ルチアーノはこの曲の名前を嫌という程聞かされていた。だって彼女が嬉しそうに口にするのだ。――《ルルイエの聖女》が大好きな、その、恋の歌をだ。 ◇◆◇◆◇ 「バクラくん、もうよくなったの」 「おかげさまでな。宿主も形見が返ってきて随分良くなった」 「そういや消えたカードも全部元の場所に返ってきたんだっけ。パラドックス一人がやってたのだとしたら、彼って実は結構な大仕事を任されてたんだね。同情は、しないけどね」 《伝説の初代決闘王》がとぼけた声でそんなことを言う。未だにあどけない顔つきをしているくせにその内実は老成しきっているのがこの男の特徴だった。一番よく周囲を見渡していて的確に痛いところを突いてくる。学生時代からそれは変わる兆しを見せない。 柔和な眼差しでバクラを見据えるその隣には相変わらず幽霊状態の名もなきファラオが浮かんでいて、彼の相棒に比べると幾分も厳しい目付きで半ばバクラを睨んできていた。彼はあからさまな不信感を隠そうとせず、『何故獏良くんが元気なのに人格を交代しているんだ』と問い掛けてくる。それに胸元にぶら下がった千年リングが焦ったように反応して揺れた。 「オレ様が表に出てちゃ都合が悪いってか? 大抵のデュエルの度にしゃしゃり出てくる王サマに比べちゃ、オレ様は大人しい方だと思うんだがねえ。……おっと怖い顔しないでくれよ。事を構えるつもりはないんでね……」 『ほう。オレにはとてもそうは見えないな』 「もー、二人ともすぐそうやって喧嘩腰になるんだから……一触即発のハブとマングースじゃないんだからさ。……リングが揺れたってことは獏良くん、閉じ込められてるわけじゃないんでしょう?」 「ああ。どっちかといえばこれは宿主の意志だな」 「獏良くんの?」 「オレ様からきちんと感謝を伝えろとよ」 またリングがしゃらしゃらと揺れる。同意と催促を表している音にバクラは仕方ないというふうに舌打ちをしてから「ホラよ。あん時は助かった」と軽く頭を下げた。二人の遊戯の表情が一方は驚きに変わり他方は訝しむものに変わる。 『……随分聞き分けがいいんだな』 「他ならない宿主サマの頼みだぜ。名もなきファラオともあろうお方が一宿一飯の恩義を知らないとはまさか言わないだろう」 「なんかそれ、ちょっと違う気もするんだけど……うん、そうだね。ねえバクラくん、きみってば随分と丸くなったね。ボクはそれがちょっと嬉しいんだ。一番はじめの、きみ達とTRPGをやっていた時のことを思い出すと特にね」 「……前々から思ってたんだが、遊戯お前、存外しつこいな?」 「昔を忘れられないんだよ。思い出に縋るおじいちゃんみたいでなんだか情けないでしょ? ふふ……そうだ。一つ思い出したことがあるんだよ。これ、きみに預けておこうと思って」 言うなり遊戯が懐のデッキケースから丁寧に梱包されたカード大のものを取り出し有無を言わせぬ手付きでバクラに手渡してくる。あまり良い予感がせず、遊戯の顔を見返すといいから黙って開けろとでも言いたげな柔和な表情が貼り付いていた。何も言い返せる気がしない。 仕方なしに包装を開く。現れたのは三枚の、ついこないだバクラが触れる機会のあったものだ。だが手渡される謂れはないし、覚えもなく、また欲しくもない。 「あのね、イシズさんにタウクで視て貰ったんだ。そのカード達はきみが持ってくれている方がいいって。いつかまた必要とされる時のためにね」 「オレ様なんぞに渡していいのかよ。これは三幻神に匹敵する極秘レアカードのはずだろうが」 「うん。だってボクきみのこと信じてるもの。今の獏良くんへのきみの接し方を見てればわかるよ」 「……はあ」 『言っておくが、オレは反対したし今でも賛成はしていないんだからな。ただ相棒がどうしてもというから渋々こうやって……』 「いや、ややこしいから王サマはちっと黙っとけ」 三枚のカード、一度エナジードレインで世界中のカードや人々に多大なる悪影響を及ぼした三幻魔はバクラの手のひらの中で奇妙な存在感を放ってそこに収まっている。先日結界の触媒に使用する際に触れた時よりも軽かったが、ただの紙きれとしては異常なまでに重々しかった。 「遊星くんが言ってたでしょ、もう一人のボクは名前を見付けられないって……イシズさんはそれを伝えたら、『それならばバクラ、彼もまた同じ運命でしょう』って言った。きみともう一人のボクは一蓮托生なんだって……おかしいでしょ。でもねバクラくん、ボクはそれにも意味があってそしてそれはとてもとても大事なものだとそう思ってる。ねえ、きみは笑ってしまうかもしれないけどね、ボクは運命って言葉信じてるんだよ」 笑うことなど出来ようもなかった。武藤遊戯、名もなきファラオの器たる三千年にただ一人のファラオの唯一無二、生ける伝説となった《初代決闘王》。そいつがこうやって確かな眼差しでもって何かを語る時、その言葉はいつだって正しいのだ。筋がきちんと通って、整然とした彼なりの説得力を確かに持っている。 それを一蹴するのは実のところそう難しいわけでもない。ただ、最後には蹴り飛ばした方が突き付けられた現実に蒼白になることになる、それだけが決まりきっていた。 「運命っていうと、すごく不確かで漠然としていて、頼りのないものみたいだけど。ボクが千年パズルを完成させてもう一人のボクと出会ったこと、そこから始まっていったこと、それら全てはボク自身が選択し続けてきた『運命』に相違ない。運命って決して予定調和のことではないんだ。バクラくんが獏良くんを選んで、交わしてきた十年間もきっときみ達二人にとっての運命なんだね。ボク達もそう」 『……相棒』 「きみが三幻魔をここでボクに突き返しても受け取っても、きみの選んだその選択が最後に運命になるんだ。願わくば、ボクはその選択が遊星くんの残してくれたものに繋がる一手であってくれれば嬉しいとそう思ってる。イシズさんがもう一つ言っていたことがある。『三体の幻魔は、近くて遠い未来の赤と青が必要とするだろう』、これが彼女の二つ目の預言。そのカードを彼らに手渡すのはきみだとボクはそう予感してる」 「決闘王サマ直々のお使いってワケかい」 「平たく言えばそうかもねえ。でもボク、多分その頃には死んじゃってるもの。信頼出来る人に頼んでおかなきゃいけないよ。もう一人のボクには遊星くんのこと、だからきみには、伝えるべき二人のことを」 お願いだよ、遊戯の眼差しが名もなきファラオとバクラを射抜く。現世にしがみついている二人の亡霊はその瞳に否を告げることをしなかった。名もなきファラオは本当は、三千年前に死すべきだった。それに紐づけられている千年リングの闇人格も、であるならばもう死者でなくてはいけないのかもしれない。 だが不動遊星はそれが叶わないのだと言う。レールを曲げられて不当な歴史に追い込まれたこの世界では、死者が死者になる理すら断絶されてしまったのだと言う。 遊戯にはそれがどうしても良いことだとは思えなかった。幽霊は現世への未練を断ち切って新しく生まれなければいけない。そう思っている。 「ボクがしわくちゃのおじいさんになって、獏良くんもいなくなって、いつかきみ達を置いてどこかへ行ってしまう時がいずれ来るんだ。だからボクは、もう一人のボクの心の中にボクを残していく。それはきみにとって重たいことかもしれない。それを申し訳無いと感じているけれど……」 『構わないさ。立場が違えばオレもそうする。オレはお前を責めない。お前をいつだって信じて……愛してる』 「うん」 差し伸べられた手のひらに遊戯が少し泣きそうな顔で笑った。ほんのりと赤みの差した目尻はいつか目立たずいじめられていた頃の遊戯と似ているようで全く違う、強い人間の持つ美しさをたたえている。 「それでもボクは、願わずにはいられないんだ」 祈るような声でそう紡いだ。武藤遊戯のその姿は人間臭く、だがそうであるだけ美しい。 ◇◆◇◆◇ 「……寝てるのか、十代」 「ん……あ……?」 どうやら来客用のソファで眠りこけてしまっていたらしい。十代は緩慢な動作でもぞもぞと何か声を漏らしそして寝返りを打つ。子供のように警戒心がなく、頬が緩んでいる。それを見ていた月行がとうとう堪え切れなくなってくすりと笑んだ。 「月兄、笑うことないだろ」 「いや、そういうつもりじゃないんだ。ヨハン、きみの友達はとても良い子だね」 ヨハンがきょとんとしてしまったので月行と夜行が微笑みながら顔を見合わせる。モニタリングをしていたこの一件を通じて、遊城十代という少年のことを二人はとても高く評価していた。少年らしいナイーブさを棄てられずにいるが、その芯の強さは傍目からしてもはっきりと際立っていていっそ美しいと言える程だ。 「彼が遊戯さんの弟子でさえなかったら、我が社にスカウトしていたところなんだけどね」 「遊戯さんのたった一人の愛弟子に手を出すわけにもいかない。ヨハン、彼との絆を大事にするんだよ。きみと彼は不可思議な縁で結ばれていると私達はそう思う。決してないがしろにしていいものじゃない」 「まさか、俺が十代のことをないがしろにしたりなんかするもんか。十代は俺の一番の友達なんだぜ」 「ならばそれでいい。優しい子だ、私達の弟は」 ミニオンはとても特異な集団だ。選り集められた優秀な素体に専属教育による種々様々な英才教育を施して育てられたため、ヨハンを除いて彼らには学校教育を受けた経験がない。 だから必然的に友と呼べる存在には疎くて、そのくせなかなかミニオン同士でうまく家族になることも出来なくて、いつもぎくしゃくしていて心の休まるところというものが持てていなかった。猜疑心や嫉妬が入り混じって優しい気持ちから遠く離れて生きてきたのだ。 「兄さん達だって優しいじゃないか」 「いつも言っているだろう? ヨハン、それはきみが教えてくれた気持ちだ。きみは幸せものだが、私達もまた同様に幸せものなんだよ。……遊星くんがこの歴史は間違ったものだと、そう言っていたが。だとしても私はこのかけがえのない幸運を確かに喜ぼう。ヨハン」 「何? 月兄」 「愛しているよ、私の大切な家族」 「――、」 不意にぽたり、と水滴が落ちた。 ぽつ、ぽつ、と落ちて服に染みを作っていく。ヨハンははじめそのことにびっくりしてきょろきょろと辺りを見回し、それが自身の涙であるのだということを徐々に悟った。 「え、俺、泣いて……?」 水滴は止まらない。そのうちこま切れの滴からしたたる流れのようになって、じんわりと染みを広げていった。正面の月行と夜行は微笑んでいる。ただ呆然として、ヨハンは涙を拭うことも忘れて佇んでいた。 「え、えっと、」 「ゆっくりでいい、ヨハン」 「兄さん達が俺のことを大事だって言ってくれるの、すごく嬉しくて……それを当たり前に受けられることが、すごく……」 「うん」 「ありがとう。俺も、愛してる。父さんも兄さん達も、家族を、俺を迎えてくれた全てを」 頭の中に次々と大切な人達の姿が思い浮かんで流れていく。義父のペガサス、一番上で一番良く面倒を見てくれた月行と夜行の双子の兄。素行は荒っぽいが信念を持ってヨハンに教えてくれたリッチー、寡黙で多くを語らないけれど、とてもまっすぐな言葉をくれたデプレ。たくさんの兄達、そしてもう一つの家族である宝玉獣達…… それらに続いて最後に脳裏を過ったのは十代の姿だった。天真爛漫な少年が思い出の風景の中を駆けて行く。彼はヨハンに手を振って手招きをした。だけどすぐに消えてしまった。 その代わりに別の十代が現れて強い風の吹く場所に立つ。かつて彼が身に纏っていた赤い制服のジャケットが翻って、彼の姿を隠した。大人びて儚い。寂しそうだ。そいつは唇で何がしかの言葉を作り出し、小首を傾げ、まなじりを下げる。 『おまえは、しあわせになってくれよ、ヨハン』 それきり幻は掻き消えてもう見えなくなってしまっていた。本物の十代はヨハンのすぐ後ろのソファで丸まっているし、兄達も目の前でやはり優しい微笑みをヨハンにくれている。はっとして慌てて涙を拭うと夜行がハンカチを貸してくれた。慌ててそれを借り受ける。 ヨハンは今のままで十分に幸せだし、愛する家族、愛してくれる家族、愛がある幸福、それらに包まれてこれ以上に望むものなんかないと思っている。大事な親友もいる。だけど遊星の話を聞いて以来、奇妙な違和感が消えてなくならない。ちりちりと燻ってヨハンを苛んでいる。 おまけに今の幻だ。変な気持ちだった。大切なものがぽっかりと抜け落ちて、盗まれて、それが何であるかも思い出せずにいるかのような。 「幸せってなんなんだろう。遊星、俺には何が間違っていて何が正しいのかわからないよ。……だけど」 十代はまだ眠っているようで、ヨハンの言葉には答えなかった。幸せそうな寝顔だ。不幸とは、少なくとも無縁そうに見える。遊星も十代達、彼曰くの「曲げられてしまった歴史」を生きる人達を不幸だとは言ってはいない。 『しあわせになれよ』と告げた、ヨハンの知らない十代の幻。なんとなくヨハンにはそれこそが遊星の知っている遊城十代の姿なのだろうなと思えた。共通するスタンスが両者の中に見えたからだ。どこかくたびれたヒーローの背中だ。みんなの期待を一心に背負っていつだってそれに応えようとしてきたもののもつ背中。 「一つだけわかるのは、きっと俺は十代を欠いてしまったら上手に幸福にはなれないんだろうってことだ。だから俺は十代のそばにいられればそれでいい。でももしこの歴史がまかり通るせいで俺と十代が離れ離れになってしまうのだとしたら……」 ぐっと息がつまる。言葉にするのが無性に恐ろしくて声にならない。だけどもそう考えてしまうのは事実だし、きっとそれが正しいのだとそう感じる。 だってそうだ。ずっと誰かが見ている夢が永遠に続くだなんて――そんなことがあっていいはずがないのだ。 夢はいずれ醒めなきゃいけない。 醒めない夢は、決して本当の意味での幸せをもたらしてはくれないのだから。 《硝子匣のソレイユ/END.》 |