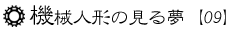愛することを恐れる気持ちを、知っていた。 少女は父のことを愛していた。だけれども、初めてデュエル・ディスクを付けて行ったデュエルでその父を傷付けてしまって。父は少女のことを畏れるような瞳で見た。その中に確かに映り込んでいた恐怖と拒絶、痛ましいそれらの感情を聡い少女は一瞬で見抜き、そして顔を覆った。 自分が愛した分だけ、誰かを傷付けてしまうのだとその時信じていた。大事に思えば思う程に世界を傷付けてしまうのだと疑いもしなかった。だけどそうじゃないんだと、少年は少女の手を取って言い聞かせてくれた。 『アキ。もしアキの手が俺を傷付けてしまう、傷付けたいと願っていると言うのなら思いっきりそうしてしまえばいい。でも俺はアキを恨まない。俺は、アキがそんなことをしたがらないと知っているから。……アキ、怖がらなくていいんだ。願えば、アキはその力を破壊ではなく、もっと素晴らしいことに使える』 少年はただの少しも少女を恐れたりしなかった。カードが作り出した薔薇の棘にいくら傷付けられようと血を流そうともその紺碧の眼を揺らがせることなく、少女の瞳からまっすぐに心を覗いていた。偽ることなんか出来ない本当の気持ちがある場所。そこだけを一直線に見つめていたのだ。 だから少女はその日から、威嚇するはりねずみのように棘を突き出して縮こまり、世界じゅうを敵に回すような目で眺め恐れることを止めた。 その必要がないということがわかったから。 肘を付いた上に顎を乗せて、アキは項垂れたままの十代の顔色を伺う。栗色の髪の隙間から漏れる彼の表情は、アキがよく知る「恐れ」のものだ。彼は恐れている。ヨハン・アンデルセンを傷付けてしまうこと、壊してしまうこと、そして失ってしまうことを。 「大事なのね」 「……」 「恋よりも愛に近いものだわ。男だとか女だとか、そういう些細なことを飛び抜けた本質的な気持ち。驚いた。十代、あなたって随分と献身的なものの考え方をしているのね」 「……献身的?」 「だってそうでしょう。あなたは今、愛されることを、そうすることで彼を失うことを怖がって彼のために身を引くと言ったのよ」 十代が顔を上げる。わかりやすい動揺と怯えが見て取れて、不謹慎にも子犬のようだと思った。小さな柴犬。おどおどと自信なさげで、認めていいのか悪いのか必死に悩んでいる。 「……そっか」 それからややあって、十代は絞り出すように蚊の鳴くぐらいに小さな言葉を漏らした。 「俺、やっぱり、ヨハンのこときらいじゃないんだ。恋じゃないけど。失くしたくないって思うのは確かで……」 手のひらを無意識に握り込んでぽつぽつと喋る。あの人肌の温もりに包まれていると酷く安堵する。優しい声に泣きそうになる。昔手のひらから零れ落ちてしまった大事なもの。一度手が届かないところに行ってしまって、叫んで、泣き喚いて、世界を呪うぐらいに狂乱して、 「俺はヨハンを知ってるんだ。昔一回、失いかけたことがある。俺が大事に思っていたせいでヨハンは俺の前から姿を消した。俺が親友だと思ってたから、ヨハンは俺を信じて、自己犠牲を遂げて……」 「十代。それは、あなたが失っていた記憶?」 「だけどわかったのはここまで。それ以上のことは何も思い出せない。ただ、その時の気持ちはわかる。俺は絶望してた。ヨハンのいない世界に絶望して、自分をこっぴどく責めたてて、後悔ばっかり胸の中で大きくなっていって。気が付いた時には何も見えなくなってた」 そこまで並べ立てて思い知らされる。絶望して呪う程までに、かつての遊城十代はヨハンを愛していたのだ。二人のドッペルゲンガーの言葉が蘇った。「犠牲もなしに幸せになんてなれるわけがないのに。馬鹿なやつ」「でも、ヨハンのことが好きなんだ。ばかみたい」。 ヨハン・アンデルセンは幸せでなければならない。それは十代の中でとり決められた絶対で、揺るぎないものだ。そして十代はヨハンを不幸にするから、どんなに欲しくても渇望したとしても彼の隣にいることは出来ない。 ヨハンは誰か器量が良くて気だてもいい女性を見付けてその人と温かい人間の家庭を築けばいいのだ。半端ものの十代じゃなくてもっとちゃんとした人が、彼なら見付けられるはずだ。 それなのにヨハンは十代が大事なんだって言う。十代でなきゃ嫌なのだと言う。五年もの間ずっと独りぼっちで、自分以外帰ってきやしない家の中で二人分の調度に囲まれて寂しく待ち詫びている。 「すきだ」 おおばかやろう、という意味を込めて吐き出すように呟いた。十代じゃなくったって幸せになれるはずなのに、むしろその方がよっぽどいいはずなのに、ヨハンは幸せになれる権利を放棄して疫病神の十代なんかに手を差し伸べている。いつもそうだ。ヨハンという男はいつもそうなのだ。十代の心をぎちぎちに縛りあげて、やっとのことで突き放したと思ったら次の瞬間にはまた十代の手を握っている。 そうして彼は自信満々に「絶対君のことしあわせにしてあげるから」とか言い出す。一体どこからそんな台詞が沸いてくるのかわからない。十代が幸せになる前にヨハンが散々な目に遭って不幸になって、最後には見限るのがいいとこなのに。 どんなにそう言ってやってもヨハンは諦めなかったし、耳障りのいい言葉、温かな指先、十代が望んでいた優しさの全てを与えてくれた。いつしかそれを好きになっていく自分がいた。 いいや、いつしか、ではないのだ。 十代は最初からヨハンを愛していた。その感情に気が付くのに時間がかかってしまっただけで。 「おれだってしあわせになりたいよ、ヨハン」 頑張って自分に言い聞かせて拒絶したけれど、本当は誰よりも彼の温もりを欲していた。幸せになりたかった。だけど幸せになっちゃいけない。どうして? ――どうしてそれが許されない? アキの琥珀色の眼が十代をじっと見据えている。馴染みのある色だということを今になって思い出した。ヨハンの家族の色。トパーズ・タイガー、兄貴分のきっぷのいいやつ。 ヨハンの家族は他にもいた。父親のようなサファイア・ペガサス、母に似たアメジスト・キャット。エメラルド・タートル、コバルト・イーグル、アンバー・マンモス、そしていつも肩に乗っていたルビー・カーバンクル。七体のデュエルモンスターズの家族達。連鎖的に記憶が蘇っていって、しかしそれはある地点で隔絶されてぴたりと止まってしまう。精霊の家族達はそれで合っているけれど、ではヨハンの人間の家族はどんなふうだったのだろう? 彼にも人間の家族がいたはずなのだ。そう確信して懸命に記憶を手繰り寄せると浮かんでくるヴィジョンがあった。子供の姿だ。幼稚園ぐらいの身長の子供が二人、白衣のヨハンに駆け寄って何か言っている。 名前は何と言ったか。思い出せない。すごく大事なことなのにちっとも出てくる気配がない。 「十代」 アキの指が十代の顔に触れ、リアルな感触にはっとして意識が思考の海の底から返ってきた。アキは丸い瞳を鋭く細めたまま溜め息を吐いている。カフェテリアのテーブルに乗ったアップルティーソーダは、氷が解けて薄っぺらいビールみたいな色合いに透けてしまっていた。 アキがかぶりを振る。 「帰りましょう。あなた、一度家に帰った方がいいんじゃないかしら。こんなところで長時間無防備になられたらたまらないもの。そろそろジャックの話も終わった頃でしょうし」 「ジャックが何か話してるのか?」 「遊星によ。もうそろそろ限界がきてるって顔をしてたから、私がいなくなったタイミングで何かしら話してたと思うわ。あの二人が幼馴染なのは知ってるでしょ。遊星が行き過ぎた時にストップを掛けるのはいつもジャックの役目だったの。これまでそうだったんだから、きっとこれからもそうね」 はっきりした口ぶりで言いながら彼女は既に手際よく荷物を纏めている。グラスの中の薄まったドリンクにちらりと目をやって、けれど今更それを口に付ける気にもならなくて、十代ものろのろと用意を始めた。昔も、こうやってしっかりとした口調で喋って十代を気に掛けてくれた女の子がいたような気がした。アキと少し似ているように思う。 でもやっぱり、名前はさっぱり思い出せそうな兆しがない。 ◇◆◇◆◇ シティ中央部の繁華街は当たり前のように混雑していて、私達は雑踏を縫うように上手いことかい潜ってその中を歩いていく。少し離れたところから、ブルーノの「待って、ちょっと待って」という間伸びした声が聞こえた。でも私も龍亞も速度を緩めないでぐんぐん前へ前へと進んでいく。 私達が目を覚ましたのは十時を少し過ぎた頃のことで、ポッポタイムにはもうアキさんも十代もいなくてガレージでは問答が行われていた。ジャックの厳しい声が扉を擦り抜けて途切れ途切れに聞こえてきて私は首を傾げる。珍しく、ジャックは遊星に対して怒っているみたいなのだ。 『死に至る病に似ていると、それだけ思った』。遊星の声が耳に入ってくる。死に至る病、キルケゴールの唱えた絶望の末路。遊星はやっぱりちょっと変だなあ、と二人で顔を見合わせる。十代にべったり、どっぷりで。 十代は遊星のことを弟みたいにしか思っていないってことを私達は知っていたし、彼が惹かれるとしたら遊星が大嫌いなヨハンという男なのだろうということを薄々勘付いていた。あの監視カメラの映像の中で、隣り合う二人は長い間連れ添った夫婦みたいにぴったりと調和していて、口では否定していた十代自身も満更ではないふうで。少なくとも遊星のつけいる隙はないなあということが見てとれたからだ。 それに遊星の十代への眼差しは傍目からもいびつに映った。ジャックの言葉が遊星に追い討ちをかけていく――遊城十代は不動遊星には振り向かないしこれっぽっちもなびかないのだと。 断片的な会話を盗み聞きしているうちに時刻は正午を回り、気を利かせたらしいブルーノがノックをして部屋に入ってくる。「出掛けよう」という誘いに一も二もなく頷いた。そういえば私達はまだ朝ご飯も食べていなくて、お腹はぺこぺこで背と腹がくっついてしまいそうなのだ。 「ブルーノは、何を話してたのか誤魔化そうとして教えてくれないし。どうせいくらかはばれてるんだからさあ、そんな律儀にしなくたっていいのになあ」 「でも、仕方ないわ。遊星のプライドに関わることだし。……ここのところ、遊星ったらまるで十代にとてとてくっついてく子犬とか雛鳥みたいよ。本当に、変だわ」 「なんなんだろうなあ。あんな遊星今まで見たことないから調子狂いそう。そりゃ十代はなんか凄いから憧れるのはわかるんだけど……遊星のは俺の憧れと微妙にズレてる。ヒーローを追っかけてるみたい」 龍亞が腕を組んで唸る。私達よりも幾分も背が高い大人達の人波に揉まれて、適当に流される方向へ歩いている龍亞はすごく危なっかしい。でも考え込んでいる龍亞はその危険性をあまり考慮していないようで、ぶらぶらとたゆたいながら唸り声を上げ続けている。 「十代も十代でヘンなんだけどさ。アキ姉ちゃんみたいな顔、時々してるんだ。ねえ龍可、近頃おかしなことばっかりだと思わない? 十代が来てから、遊星が変になって十代も変で、おまけによくわかんないまま襲われたりして」 「それは十代への文句?」 「まっさか。俺、十代のこと大好きだもん。十代の傍って不思議と安心するんだ」 龍亞が妙に誇らしげに言った。本当の家族よりも手に馴染む充足感を時折十代から得るのは私にしても確かな事実で、向日葵みたいに笑う彼の背中からはどこか母親めいた匂いを感じるのだ。よく晴れた日に干した洗濯ものの、お日様の匂い。いつか触れたことのある母性。 でも実の所は、トップス最上階に住む私達の衣類は潔癖症のママの手によって完璧に室内クリーニングされてしまっているのでお日様の匂いなんかちっともしやしないのだった。嗅ぎ取れる匂いはいつも、柔軟剤の合成化学臭剤のわざとらしい造花の香りだ。 「そりゃ、私も十代のことは好きよ。チームの仲間だもの。一緒にいると安心出来るし……」 「あ、それ俺も思う。十代の手ってさ、遊星よりもちっちゃいのにすごくしっかりしててあったかいんだ。ほっとする。龍可の手に似てる」 「私に?」 「うん、そう」 ブルーノはいつの間にかその気もないのにまいてしまったようで、ふと振り向いた時にはその姿を確認出来なくなってしまっていた。でも多分携帯電話を持っているからなんとかなるだろう。いざとなれば遊星がGPSからあっという間に場所を割り出すことが出来る。 それからまた少し歩いていると、真昼のメインストリートの往来にいるというのに進むにつれて不思議と人の量が少なくなっていって、私はそれを不安に思いながら龍亞の足取りを追いかけていた。あんなにぎゅう詰めだった知らない人々の集団がこんなにもまばらになって、十人、五人、三人、二人、一人……じわじわと数を減らしてとうとう私達二人だけになる。それなりに幅のある通りがこんなにがらがらになるのは平日でも珍しいことで、流石の龍亞もそこではたと足を止めた。 「……いやな感じがする」 私も黙ってそれに頷く。よくよく見渡すと、通行人達は別にいなくなったわけじゃないってことが理解出来た。彼らはずっとそこにいる――ただし、ホログラム投影されたかもしくはよく透き通った氷の彫像にでもされたかのように薄くなってだ。 ぶるりと身震いする。がくがくと足が震え、膝が笑っていた。予感がして顎を上げる。 「あれぇ、どんなに馬鹿になっても勘だけはいいんだ? それとも元から勘以外てんでからきしの馬鹿だったっけ。きゃははっ、なんて顔してんだよ! その顔何回見てもチョーウケる!!」 通りと通りに挟まれた四叉路に設けられた信号機の上から耳障りで甲高い声が降ってくる。顔を上げて確認するよりも早くその声の主に私達は思い当たった。あの日龍亞を傷付けた子供。イリアステルを名乗る得体の知れない敵。 赤毛の少年は足をぶらぶらさせながら高慢な顔つきで私達を見下ろしてきていた。龍亞の足がすくんで、小刻みに震えているのが伝わってくる。私達は手を繋いだ。手のひらはお互いに、酷く冷めた体液に塗れていた。 「また出たな……」 「なんだよ人を幽霊みたいに。あー、っても僕別にニンゲンじゃないんだけどぉ! だからお前らじゃあ、僕に傷一つ付けられっこないってわけ!」 「うるさい! そもそも俺は……」 「うるさい? ねえお前さあ、誰に向かって口きいてると思ってるわけ?」 けらけら笑っていた少年がさっと顔色を変えて、冷え切った温度で龍亞を遮る。龍亞が言い淀むと彼はあからさまに不機嫌そうな表情を隠そうともせずに侮蔑の視線を私達、特に龍亞に向けた。まただ。また、混じりっけのない悪意と敵意、害意、明確に龍亞を忌み嫌い呪う声。剥き出しの鈍重で研ぎ澄まされた黒い感情の塊。 でも今度はそれだけじゃない。以前の純然なものと違って今度はそこに僅かな不純物が含まれている。自らへの苛立ちと、それから誰かへの…… 「だからさぁ……」 だけど私の思索はそこで強制的に切られてしまった。 少年が、パフォーマンスでもするみたいに右腕をゆっくりと振り下ろす。さながら神の宣告のように。絶対者の勅命のように。傲慢に、緩慢に、冷酷に無慈悲にその暴力的な言葉を投げて寄越す。 「死んじゃえよ」 凍りついた時の中で、トラックだけが猛烈なスピードで動き出した。 視界が真っ暗になる。目をぎゅっと瞑る。どうやら私が目を瞑ったのと同じぐらいに、かちこちに固まっていた世界が動き出したらしいということが耳をつんざく悲鳴の合唱でわかった。うるさい、だけどそれに反応することも出来ない。少年の笑い声が悲鳴を縫って耳に刺さった。 私達、このまま死んじゃうのかな。 トラックはまっすぐに私と龍亞めがけて走って来ていた。意識が遠くなってスローモーションの世界の中で排気ガスとけたたましいクラクション、それからエンジンの音が迫ってくる。すごく怖い。龍亞の手を強く握って私は終わりを覚悟した。この状況じゃ、どうやったって助かりっこない。やっぱり私達は死んでしまうんだ。 本当に心からそう思った。 だけどその「終わり」は、どうしてか私達兄妹の脇をすり抜けてどこかへ行ってしまったのだ。 「――龍亞! 龍可!」 突然、本当に何の前触れもなく唐突に暗闇の向こうから私と龍亞を呼ぶ声が聞こえてくる。男の人の声。でも遊星でもジャックでもクロウでもブルーノでも、十代の声でもない。全然知らない人の声だ。 それなのに、私はその声を聞いて目頭が熱くなるのを感じた。泣いてしまっていた。ぼたぼたみっともなく涙が零れ落ちていくのにも全然構わないで、手放しでその声と巡り会えたことを喜んでいた。 私はその声を、ずっと、ずっと、探していた。 ふわりと体が浮き上がって、そのまま急激に横へ。さっきまでと違って恐怖はなかった。私を支えてくれる誰かの温もりと隣り合う龍亞の体温が私に安らぎをくれている。 けたたましいクラクションが私から少し離れたところを通り過ぎてゆく。急ブレーキの音。ざわざわと、人々の声。誰かが歓声を上げるのが耳に入った。それに続いて舌打ち。信号機の上の赤毛の少年の声だ。でも急いで見上げた頃にはそんな人影はいなくなってしまっていた。もしかしたら時間が止まっている間にトラックだけけしかけて雲隠れしてしまったのかもしれない。 「大丈夫か、怪我はどこかしてないか? あと少しで跳ねられるところだった。助けられてよかった」 がっしりした腕にだき抱えられて、私はゆっくりと目を開く。排気ガスもエンジンの音もどこかへ行ってしまっていて、通行人は遠まきに私達兄妹とそれを抱き締める男の人を見ていた。体を起こして男の人をまっすぐに見やる。 見たことのある顔だ。ほんの数日前に私はその顔をモニターで見ていた。ヨハン・アンデルセン、遊星があんまり快く思っていないらしい人。無遠慮だということも忘れてじろじろと見入ってしまう。それは彼の姿を見知っていたからというよりは、目を疑うような事象が目撃出来たからだった。 ヨハンの背中に、羽が生えている。 「え……」 純白の翼だ。お話の中の天使か、ひょっとしたらそれ以上の神々しい翼。でも瞬きしている間にその翼はふっと掻き消えてしまう。もう一度確認したヨハンは普通の人間でありそれ以外の何者でもなかった。 「よかった、本当によかった……」 彼は心底安堵したように息を吐いている。まるで世界で一番大事なものを見るように、それこそ私のパパとママが私達を見るよりもそれらしく、その人は私達を愛おしんで見ていた。強く抱き寄せられる。私はそれが不思議でたまらない。 なんだってこの人は、今初めて会ったばかりの赤の他人にそんあふうな優しい表情を出来るのだろう? 私達は全くその人と血の繋がりのない赤の他人で、その他人が子供を往来の真中で抱き締めているというのに道ゆく人々は誰もそれを疑問に思っていないようだった。一歩間違えたら犯罪者扱いされてもおかしくないと思うんだけど。 それは私達がその人を拒絶しないで信頼する親しい人にそうするように体を預けているからかもしれない。その人が身を挺して私達を助けたという事実があるからかもしれない。……それからもしかしたら、私達とその人の面だちが似通っているから、かもしれなかった。 (……パパ?) そうだ。私達三人は、血の繋がった親子なのだと説明されたらきっと殆どの人が納得してしまうだろうってぐらいによく似ていた。青みの強い緑色の髪。目鼻だち。ぱっちりした瞳、二重まぶた、それらがかたちづくる全体の雰囲気。だからかもしれない。私が口の中で呟いた言葉の響きに違和感はなくって、ただ、昔に失ってしまった大切な人の幽霊に呼び掛けているみたいなすかすかした気持ちがあった。 龍亞がヨハンをじっと見ている。多分私と同じことを考えているのだ。私達双子はいつだって同じことを考えている。私が悲しい時は龍亞も悲しいし私が嬉しい時は龍亞も嬉しい。喜びも痛みもあらゆる全てを私と龍亞は共有していた。私達はそうやって生きてきた。 ヨハンは同じような表情をしている私達を見て少しだけ驚いたように目を見開いたけれど、すぐに元の優しい顔色に戻って「ああ」、と柔らかい声をくれる。それにほっとしてまた目を瞑ると、彼はとても小さな声で、自分一人にこっそりと言い聞かせるように、「あいしてる」、と口にした。 「いつだって、ずっと、あいしてる……龍亞、龍可、俺の大切な……」 「え……?」 「いいや。なんでもないよ。きっとまた会おう、龍亞、龍可。いつまでもここで固まっているわけにもいかないしな……十代によろしく言ってくれ」 私が疑問を口にすると気まずい表情になって言葉を噤み、かぶりを振る。それが彼の中での区切りになったのかヨハンが私達から手を離してすっと立ち上がった。私を包んでいた、知り得る限り誰よりも優しくて力強い手のひらが離れていく。帰ってしまう。どこかへ行ってしまう。 「元気にしてるんだぞ。……家族を、大切に」 そんなことを言ってひらひらと手を振った。おかしな気分だ。ぽっかりと空洞が空いて、私の中で強烈な違和感が膨れ上がって胸中を支配していく。すごくすかすかした気持ちだった。何かが足りなくて何かが間違っている。私達とその人がバラバラに別々の方向へ歩いていくということがどうしようもなく気持ち悪い。 ぐちゃぐちゃだ。 「……嫌。行かないで」 だから私は、反射的にその腕を握り締めていた。龍亞が驚いたように目を丸くしておどおど慌てふためく。ヨハンも龍亞と似たような瞳で私を見ている。ほら、また、親子みたいに。二人は揃って、「龍可がこんなことを言うなんて」という顔をしているのだ。顔にそう出ていてばればれだ。 「る、龍可」 「こんなの嫌。変よ。ねえ龍亞、私達、この人とこのまますれ違っただけの赤の他人じゃいけないと思うの。だって名前も知らないのよ。それだけじゃない、何か、大切なことを……」 「でも、龍可、」 「忘れてるわ。十代みたいにぽっかり、全部なかったみたいに」 何としても逃すまいといきおい強く強く袖を握り込んだ。その振動が伝わって髪の毛が揺れて、ヨハンのにおいが私の鼻腔をくすぐる。十代とそっくりだ、と思う。 十代と同じにおい。 ヨハンは心底困ったというふうに肩をすくめて首を横に振り、今にも頭を抱えてしまいそうな弱り顔で私に言い聞かせるように口を開いた。「いいかい龍可」、父親じみた声音が聞こえてくる。「女の子はもうちょっと危機管理能力を身につけるべきだ。誰かに教えて貰えなかったのか?」 「そういう問題じゃないわ。それに、皆がいるポッポタイムに一緒に行こうって言ってるだけだからその手の心配は要らないと思う」 「ぽ、ポッポタイムって遊星君が住んでるガレージのことか」 「勿論、そこしかないもの。……どうしてそんなに震えているの」 「だってさ……遊星君はたぶん俺のこと、好きじゃないぞ」 口をすぼめて言うさまは悪戯を見咎められた子供に似て体躯には似付かわしくないが不思議と違和感はなかった。ヨハンはそういう人なのだという確信がある。子供らしい純粋さを失わないでまだ持ち併せているに違いないという根拠のない確信だ。 子供が好きな人だった。誰かを愛する気持ちを大切にする人で、世界じゅうを、このうつくしい世界のありとあらゆる全てを慈しんでいた。 「俺が彼の前にのこのこ出でもしたらそれはもう面倒なことになる。多分だが、何かこう、埋め難い溝のような確執があるに違いないんだ」 「だったら尚更話すべきよ。遊星は目を背けてる。怖いものから逃げてる。――私達、きっと前に進まなきゃいけないの」 私は言った。強く、強く、力強く。龍亞が呆けた顔をしている。 ヨハンが首を振った。彼がやんわりと首を振って溜め息を吐いた時、それが諦観の合図に他ならないのだということをどうしてだろう、私は確かに、知っているのだ。 |