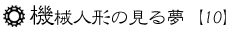「なぁんだよォ、ぼけっとしちゃってさあ。何がおかしいって思うの? 時間が止まってること? 僕やお前だけが動いてること? ……それともさあ、もしかして、自分が何もわからないこと……?」 少年は謳う。聖女が繰り返し聴かせたものに似せて、祈りの代わりに告発を、優しさの代わりに悪意を、慈しむ代わりに宣告を。 悪意の讃歌は鳴り止まない。心にもない言葉を連ねて最後に忌むべき呪いを吐き棄てる。Kyrie eleison;Christe eleison;Kyrie eleison――しんでしまえ、愚か者。 「《主よ、憐れみたまへ》――」 少年の唇が、連なった皮膚が、ひきつり歪んだ。口裂け女のように見境なくめりめりばきばきと。「憐れみの讃歌」を紡ぐその唇は汚れ、塗れ、毒に犯されて一人を追い詰めようとする。 「ばっかじゃないの。お前が! その手で! 人口細胞で出来た偽者の唇で! 願ったんだろォ?! 『やさしい』世界を。不動遊星を手放したくなくて! ――機械人形の分際で!!」 「ちがう!」 「何が違うもんか。何も違わないんだぜ、なあ、××××……」 指が撫ぜる。喉から縮れて凝ったような掠れた嗚咽。少年の光彩の欠けた瞳が意地悪く射抜く。思わず後退った。怖い、こわい、触れていたくない。 大切なことを思い出してしまいそうな気がして怖い。 ◇◆◇◆◇ 双子とブルーノを見送ってシャワーを浴び、こざっぱりした恰好でリビングルームにあたるガレージに戻ってきた遊星は恥も外聞もなく、あんぐりとだらしなく口を開け文字通りに目を丸くした。もしかしたら疲労による幻覚か何かかもしれないと考えて幾度か瞬きをしてみたが結果は変わる兆しを見せない。それでもにわかにはその光景が信じ難くて、遊星は最後の抵抗として思いきりごしごしと目を擦った。しかしそれでも結果は変わらない。無慈悲だ。 「あー……やあ」 男がきまり悪そうに笑った。その隣で龍可が直立不動の姿勢に立っているものだから腰を猫のように丸めて浮かない顔をしている彼は余計に目立ってしまっていた。遊星は首を捻る。どうしてこの人がこの場所に存在しているのだろうか。 遊星が立ち尽くしていると男がやんわりと龍可の方を示して見せる。龍可は落ち度や問題など何もないというふうな澄まし顔でつんと遊星の抗議をつっぱねていた。こうなると龍可は強情なのだ。まず他人の言うことは簡単に聞いてくれなくなる。 「……龍可」 「私が連れてきたわ。遊星には対話が必要だと思ったの。その人のことをよく知りもしないで嫌ったり批判したりするのは、駄目よ」 「……。ブルーノ、何故許した」 「ブルーノは責めちゃ駄目だよ、ねえ遊星知ってるでしょ? 龍可はこういうところ頑固なんだ。もうそっくりなんだよ」 龍亞が既に諦めのついた声でぐったりとした様子を見せた。遊星は生唾をごくりと飲み込む。声の一つでさえぱりぱりに乾き切ってしまってまともに出そうにない。 遊星はその男が大の苦手で、憎む程ではないにせよ、嫌っていた。生理的に受け付けないのだ。優男然とした顔でいるくせに男として求められる大抵のもの(例えばそれは地位だとか、財産、その他コネクションといった経済力を象徴するものから容姿に人付き合いの良さなどといったものまで)を備えていたし、何より彼は十代を愛して、また彼に許容されていた。それが許し難くて、恐らく遊星は嫉妬しているのだった。 ――わかっている。 本当は、これがただの醜く子供じみて馬鹿げた嫉妬に過ぎないのだということを、遊星はわかっている。 「まあ……そう警戒しないで貰えると嬉しいかな。せっかくだから話をしてみよう、遊星君。確かに、俺も一度君と話をしておくべきかなとは思っていたんだ。今後のためにもね」 「今後って」 「いろいろさ。そう、いろいろと……本音を言うと今接触するのは時期尚早のようにも思うんだけどね、まあほら思い切りってやつがいつだって大事なんだ」 十代が言ってたよ、そう言って笑う。ヨハンは「十代」と彼の名前を口にする時、酷く嬉しそうに愛おしそうに目を細める。だけどそれもやっぱり、遊星には気にくわない。 双子やブルーノが怪訝な顔をしているのが視界の端にちらちらと映り込んだ。歯ぎしりする。爪が手のひらに食い込む。口腔内で滲む鉄の味が、鼻から僅かに生臭い匂いとして抜けていく。ジャックの叱咤が重なって泣きそうだった。遊星が一番気にくわないのはヨハン本人じゃない。それに振り回される遊星自身だ。 いつまでも終わらない少年時代。永遠に続くモラトリアム。もうとっくに大人になっていて然るべきなのに、ずっとずっと幼い少年の無知をその身の中で飼い続けて、そしていつか飼い殺しになっていく。 「……アンデルセン博士。俺は、あなたがきらいだ」 「だろうね。知ってた」 「だけどそれが本当に幼稚で馬鹿馬鹿しい感情だってことも薄々勘付いてる。父さんへの反抗と同じだ」 「不動への? 内心で、君はそれを恥じているってわけか。別に俺は反抗も嫉妬も、通るべき道だと思うけれどね。……無理をせずにまっすぐ生きている君は少年らしくていい」 「……そういう、何でも見透かしてるって態度は素直に嫌いだ」 「十代にも言われたよ。君達はどこか気質が似通ってるんだ……それはどこでも一緒だな」 そうして遊星の父によく似た横顔を見せた。外見年齢にそぐわない老成した物言いはけれど空言でなくはっきりとした実感を伴っている。遊星は眉を顰める。たった一言で「反抗と嫉妬」まで全て見抜いてしまうこの男の鋭さは父が「ゆうくん」とふざけずに「遊星」と名前を呼ぶ時と同じものだった。あの、現実を突き付けようとする時の。 似たもの同士、類を呼ぶというやつだ。不動とアンデルセンの両博士はその変人気質や奇人特有の波長というものでひかれ合って親しくなったに相違ない。けれどその理屈でいくと、十代もまたある種の変人で遊星もそうなのかもしれないという気分にさえなってくる。その辺りの真偽はどうあれ遊星が変人カテゴリの父を持つ事は変えようのない事実だ。 「さて、だとすればだ。君は十代にどうして拘るんだい? 一体君は十代の何を知っているって言える? 君は十代に何を望んでいる? 俺はそれを知りたいな。それこそが核心だと確かにそう考えられるからね」 「……俺が望むこと?」 「イエス、ちなみに俺は結婚を前提にした付き合いを望んでいるんだけど保留された」 後で龍可が小さく「当たり前じゃないそんなの」と胡乱な目付きでぼやくのを確認してヨハンは苦笑いをする。世界が変わって血縁関係も変化し、彼女はもう「この世界のヨハンの遠縁の子孫」でしかないのだが、ばっさりときつい言葉を吐いて捨てる性格は変わらないらしい。 反射的に飛び出して双子を腕の中にかき抱いた昼の時に、いつか娘が自分を見詰めていた時の裏表のない瞳を思い出した。ヨハンを「パパ」と呼ぶその少女は母親に似て厳しい物言いをする子供で、度々母が父にそうするように双子の兄を困らせたりたじろがせたりしていた。女系が強いのだ。兄は妹に弱かったし父は母に弱い。 ヨハンは家族を愛していた。だから、この先もずっと子供達が死んだ日のことを忘れられそうにない。それは彼らが生まれて生きていたことと同じぐらいに確かなことなのだと、こうしてまた別の可能性の中で生きている姿を見ると強く感じる。 「その場で斬って棄てられなかっただけ望みがあると俺はそう考えているけどね。君は? 君は何になりたい?」 「……わからない」 「ふむ、なるほど」 「少なくとも、結婚とか付き合うとか、そういうのは微塵も……」 「俺は、その、ノーマルだから」とか細く続いて不謹慎にも噴き出しそうになった。ノーマルとアブノーマル、その思考と見えざる境界線。なるほどヨハンは確かに彼らチーム・ファイブディーズの面々からしてみれば疑いようもなくアブノーマルな性癖を持つホモセクシュアリズムの気を持つ危険人物なのかもしれない。ヨハン本人は性別で人を愛することはないと断ずるが、正史の遊星ですら初めはそれに戸惑いを隠せずにいたのだからありふれた青年にはちょっと理解し難いだろう。 十代に恋した経緯というのはちょっとどころでなく複雑なものなのだ。引力のように惹かれ合って何も知らない子供から汚水を許容出来る大人に引きずり降ろされて、それでもやはり愛をせずにはいられなかった。体が欲しかったわけじゃない。心を独占したいとも言わない。ただ見て欲しかった。 こんなにもあふれるぐらいに、世界中に氾濫しているラブソングのように愛してるということを伝えたかった。 使い古された、ありふれて安っぽい言葉しか渡せなかったけれど。 遊星は言葉を詰まらせて俯いている。少しばかり意地悪い質問だっただろうか。捻くれて以来相当に意地悪くなってしまった人間と長い時を共にしてきたせいか少し感覚がずれてしまったようだ。「俺は、」不動遊星が切れ切れの息を吐いている。「おれは……」 「思い込みや錯覚の類だ」 ぶつ切りの言葉をぴしゃりとした声が遮った。見ると、いつの間にか現れた男が尊大に腕を組んで壁にもたれている。ジャック・アトラス。テレビでは何度か見かけたが実際に目にするのは実のところ本当の意味でも初めてだ。 ジャックは遊星を一瞥するとカツカツと歩み寄ってきてその怜悧な眼差しでヨハンを一直線に射抜いた。侮蔑は一切なかったが、代わりに値踏みといくらかの好奇心、それから嘆息の色が宿っていた。 「遊星に代わって俺が答えてやるが、こいつのそれは憧れと崇敬をこじらせた倒錯の感情だ。本人も認めている。どうしようもないヒーローへの憧憬に過ぎん」 「ジャック。その言い方は、遊星に酷いよ」 「しかし事実だ、仕方あるまい。事実は変えようがない」 遊星は押し黙っていた。無言の肯定が表すものは親友への信頼なのか、或いはやり込められたお手上げのサインなのか。こんな時、昔の十代だったらユベルの力で容赦なく心の中を読んでずけずけと他者のプライベートゾーンに土足で踏み入ったのかもしれないが、ヨハンはそれをやろうと特に思わないし簡単には実行出来ない。十代の持つ精霊の力は並外れて強力なのだ。ユベルのねちっこさが結実したに違いなかった。 「ヒーロー願望だ、結局のところ。龍亞の憧れと同じ、延長線どころか成長してもいない。むしろ退化している。遊城十代という人間が落ちてきて以来、遊星は父親に反抗を始めた中学生の頃に逆戻りだ」 「ジャック!」 「いや、いい。ブルーノ」 立ち上がったブルーノを押さえる手がある。ブルーノはいつもは柔和な瞳を珍しく憤りに変えて「どうして止めるの」と強い語調で遊星に問う。義憤によく似ているが、どこか責任を感じているようにも見えた。ヨハンを連れてきて問題を間接的に誘発させてしまったことにだろうか? 「お前が怒るようなことじゃない。すまない」 「僕別にそういうつもりじゃ……」 「いや、結局そうなんだ。ジャックがぴりぴりしているのもクロウの溜め息が増えるのも、ブルーノがそうしてつっかかるのも、今この場の不和の原因は全て俺だ。知っている。分かっている。俺はアンデルセン博士には勝てないし、なりたいとも思わないし、違うとも思っていて……ただ単に、あの人のことを知りたいだけなんだ。俺が強く惹かれる理由を、あの人が何者なのかを」 その場の視線がやんわりと遊星に集中した。遊星は近くて遠い過去を回想する。 十代が空から落ちてきたあの日に感じた鮮烈な懐かしさ、羽のように軽い肢体、中性めいた容姿が与えた違和感。無意識のうちに植え付けられていた遊城十代を上位存在と定義して疑わない自身の思考の異質さも、何もかもきっとそこに起因しているはずだ。 そうでなければおかしいのだ。遊城十代という存在にはブラックボックスが多すぎた。彼のプロフィールはその殆どが「UNKNOWN」で埋められていて、遊星がどれだけ手を尽くしても何一つ情報が出てこない。こんなことは初めてだったのだ。かつて遊星をこのように挫折させ得たのは当代のローマ法皇のプロフィールを面白半分に割ろうとして、危うくお縄に掛けられそうになった時以来のことだった。ただの一般人の個人情報が何故そこまでやっても出てこないのか。 そこに答えがあるはずだと遊星は信じていた。ヨハンもそうなのだろう、彼は先程からただの一度も他に目を向けることなく、遊星だけを見ていた。遊星の美しい青まなこを、硝子玉のように精緻で繊細な、傷つくことを知らないその在り様をともすると、舐めるように執拗に見続けている。それがさも重要なことなのだと言うように。 「英雄願望ね。君は、どちらかというと昔の十代に似ているな。偶像崇拝めいた無条件の強烈な吸引力に抗えないでいる。実に少年らしい」 「十代さんが、あの完璧な人が、そこまで強い憧れを他者に抱くものなのか」 「『完璧』、ねえ」 遊星の言葉を摘みあげてヨハンはくつくつと笑う。おかしくてたまらないといったふうだ。ヨハンの中で「遊城十代」と「パーフェクト」という名詞はどうしてもイコールでは結び難い事象であるらしい。 遊星がむっとした顔になった。尊敬する人を鼻で笑われていい気はしない。 「何がそんなに……」 「いや、おかしくてさ。あのな、一見した人間はその眩しさに目を潰されてそう言いたがるが、十代は完璧とは程遠いやつだよ。遊城十代程パーフェクトと縁遠い存在もそういない。あいつは常に変動して新しくなっていくし、ついでにズボラで不器用だ。それに、十代は十代で武藤遊戯をいつまでもアイドル視していた。どこにでもいるミーハーないちファンそのものだ」 「だったらあんたは何を知っていると言うんだ?」 つい反発して食ってかかっていた。出そうになっていた手を、すんでのところでブルーノが押し留めている。今度はさっきと図式が真逆だ。双子が落ち着かない様子でヨハンの方を見遣るがヨハンはヨハンで、非常に涼しい顔をしていた。余裕しゃくしゃくである。 「知っていることは、そりゃ知ってるさ。あいつとももう長い付き合いだからな――君の数百倍は知ってるぜ、遊星君。信じるも信じないも自由だが」 「そういう押し問答がしたいんじゃない」 「でもあんまりなんでもかんでも包み隠さずってわけにもいかないんだよな。歴史を曲げ変えてしまうことになる。いわゆる禁則事項ってヤツだ……」 ぽりぽりと背中を掻きむしりながら遊星の様子を伺っている。彼は目を細めて、「焦るなよ少年」と上から目線でにやにや薄く笑った。その態度にかちんとくるが、ぐっと堪える。ここで手を出すのはまずい。 ヨハンがそれでようやく満足そうに頷いた。この男はそうやって自らを試していたのだと、遊星は遅まきに悟る。 やはり、父と同じだ。どうやら二人を結びつけたのには奇人変人の要素のみならずいたちのような性格も一役買っていたらしかった。 「まあ、龍亞が狙われ出してるしな……そろそろひた隠しにするのも難しくなってきているのかもしれないな。教えてあげられることを伝えるのはまあ俺としてもやぶさかじゃないし、それじゃあ……」 「――待て!」 話を始めようか、と言い掛けたヨハンの声を上塗りして玄関口から荒い息遣いの声がガレージ中を満たしてまわった。 その場の誰もが、ヨハンを除いて一斉に振り返る。タイミング良く(或いは、悪く)帰宅したらしい件の遊城十代がそこに立っていて、顔にありありと「だから嫌な予感がしてたんだ」と書き殴ってあるような表情を浮かべている。肩で呼吸をしていた彼はまだ息が整い終わらないうちに移動を始めてヨハンのところまでずかずかと進むと胸ぐらをわし掴みにした。それを引き止めようとした遊星は後ろから現れたアキに掴まれて身動きを封じられる。 ヨハンは酷い態勢に甘んじたまま爽やかな笑顔で「やあ、十代。また会ったね」だなどと悪びれもせずにのたまう。十代は眉間にしわが寄るのを自覚した。なんという腹立たしい男だ。 「こんなことだろうと思ったんだ。帰る最中にものすごい嫌な予感がして、ああこれはヨハンだなって思ったらまさにその通りだったな。その爽やかな顔、すごいむかつく」 「いや光栄なんだけれどもそろそろ首の辺りが少し苦しいかな……あのさ、十代笑顔笑顔。遊星君が新たな境地に目覚めようとしている気がする」 「ともかく、俺のいないところで俺の話をするな。ヨハンなら、否定が入らないのをいいことに歯の浮くような嘘を平然とさも真実みたいに織り混ぜてくるに違いないんだ」 ぎりぎり首を締め上げていると流石にギブ、ギブ、と苦しそうな声が上がる。十代は憮然とした顔のまま言い放ってぽいと椅子にヨハンを落として棄てた。痛みにか、流石のヨハンも笑顔が歪んでしまったようで絵面が非常にシュールだ。 そのままどかりと座り込んで無情にも続きを促す。ヨハンはむくりと起き上がると心底痛そうに頭を擦って「あー、じゃあ、微妙に逸れた気もするけど始めようか」とやや不機嫌そうに小声で言った。龍可と十代の視線が冷たい。 気を取り直すためにか、彼は深呼吸をした。びりびりと突き刺さってくる視線。まるで親子喧嘩の後のごめんなさいの時間みたいで、ヨハンには懐かしい。 やにわに口を開く。もう何度も回想した過去の記憶は、鮮明に輝きを失わず、すらすらと口から滑り出てくる。何もかもが懐かしい。あの頃に戻りたいと思ったことが一度か二度はあった。でも生きていけるのは今だけだ。 「昔話だ。その頃遊城十代は、アカデミア本校をなんとか卒業してぶらぶらとあてのない旅を続けていた。俺は、卒業以来その足取りが掴めなくて少しもやもやしてた」 ◇◆◇◆◇ よく晴れた夏の日のことだった。その頃遊城十代は一も二もなくヨハン・アンデルセンを避けてまわっていたようで、カードの返却でさえ彼はヨハンの前に現れようとしなかった。何かどうしようもない用事があると必ず間に人を立てて動いた。 でも原因は薄々ヨハンの方でも勘付いていて、それはわりと仕方のないことで、ある意味で救いようがなかった。 「俺達はデュエル・アカデミア本校の同期で、まあ俺は分校からの留学生だったんだけどもとにかく生粋のデュエル馬鹿同士ですごくうまの合う親友だった。二人とも精霊が見えて、それぞれに彼らを家族や仲間として捉えていたんだ。同じ価値観を持つ同類の出現に舞い上がった俺達はすぐに旧来の仲と言われても疑う余地のないような友になった。それに、俺は自惚れていた。どんな危険も顧みず俺を助けてくれる十代は俺が何をしても受け入れてくれるはずだと根拠もなく盲信していた。 それがやっぱり良くなかったんだな。アカデミア本校の卒業式の日に、ちょっとその、若気の至りってヤツだ。金輪際の絶交を言い渡されて然るべきことを俺はやらかした。そのことについては重々反省しているし、当時も当時で散々に罵られたので何か思うことがあっても勘弁して欲しい。とにかくだ、それ以来十代は俺を避けていたわけなんだがとうとうそんな俺達に再会する時がやってきた。にわかに蒸し暑くなってきた葉月の頃のことで、あの日は本当によく晴れ渡っていた。いやになるぐらいに」 天上院吹雪の元に相談で訪れていたヨハンは懺悔と十代への思いを告白し、また数日後に来るように言い渡される。そうして言われた通りにやってきて目にしたものは泣き崩れる遊城十代の姿だった。アカデミアで誰からも英雄視され、奉りあげられていたヒーローがありふれた人間の弱さを吐露し、曝け出す姿。 でもヨハンが愛した人は本当は完全でも無欠でもないたった一人の人間で、だからそれは正しいことだったのだろう。本当に泣きたい時に泣けなくなった時、ひとは人間であることを放棄してしまう。それは大人になるだとかそういうこととはまったくの無関係に訪れる真実で、今なおヨハンが信じている真理だ。 十代は泣いていた。叫んでいた。失いたくなかったと、どうしても欲しかったのだと、無我夢中でそう口にした。 その時たまらなく嬉しかったことを覚えている。十代に必要とされていたこと、嫌われていなかったこと、そういったことを諸々ひっくるめてそれは疑いようのない幸福であった。 「久しぶりに再会した十代は随分と様子がおかしかった。聞くと、こう言った。腹の子供が流れてしまったのだと」 「……は? ヨハン、頭がいかれたのか?」 その言葉に一番に反論をしてきたのは十代だった。他の面々は意味が飲み込めずにいるらしい。まあそうだろう。ヨハンがもし彼らの、例えばクロウ・ホーガンの立場だったら考えることを放棄するに違いない。 でも事実は事実だ。奇しくも先にジャックが言ったように、変えようがないし曲げようがない。 「俺の頭はずっと正常だよ。十代は流産していたんだ。あー、俺の過ちに関しては、あまり深く考えないでくれ。龍可、俺は今すごく泣きそうな顔をしているはずだ。……ともかく」 それから幾らかの月日を経て再び十代は妊娠する。丁度春先の頃だ。そこで少なくない事実をヨハンは知らされ、蓋をされていた過去との対面を行った。覇王十代とその大虐殺の話。翔の声を聞いているだけで悲鳴と怨嗟がヨハンの耳に流れ込んでくるような思いだった。まさかあの十代が精霊を傷付けるものかと思う半面で十代なら確かにやり遂げただろうと確信する自分がいて、ヨハンは最後に、それを受け止めることをもう一度確かめた。 十代は強い。強いが、それ故に、酷く脆い性質を備えていた。彼の世界の一部を否定されること、また奪われること、破壊されること、そういうことに対して尽く無力だった。仕返しに彼が行ったものは虐殺であり略奪であり暴虐であり或いは陰惨極まりない種々のものごとであったりした。覇王は手段を選ばなかった。あらゆる圧倒的な暴力を用いて、超融合を作り出した。 ヨハンのため、だったのだという。 「そこから色々あって俺達は和解したってわけ。元々、別に喧嘩とかしてたわけじゃないんだけど。そうして、ある日俺達は二人で旅行に行くことにしたんだ。だけどそこで想定外の事態に遭った。殆ど不可避の事故だった」 「なんで勿体ぶるんだ?」 「別に勿体ぶってるわけじゃない。十代、君は今それをすっかり忘れてしまっているんだな。でもその方がよっぽど幸せなことなのかもしれない。……俺と十代は飛行機事故に遭ったんだ。調べれば出てくるんじゃないかな。死者二百余名を記録した、『五八七号便』事件だよ」 そこで表情を変えたのは十代ではなく遊星だった。遊星は信じられないといったような顔をして立ち尽くしている。それから交互にヨハンと十代の顔を見比べ、もう一度、話をしているヨハンを見た。 「……あんたは人間なのか」 「さあ、どうだろうね。これでも殴られれば痛いし皮膚が切れれば血は流すんだぜ」 ヨハンは首を振った。遊星は未だに信じられないといった様子でまるで幽霊でも見るかのように目を見開いている。幽霊でなければ、化け物だ。何か得体の知れないものを差別する時の目の動き方。 ヨハンに馴染みのある青年は決してしない目だった。だがそれは、目の前の青年がこのお膳立てされた世界では確かに幸福であるのだということを証明している。 「二人とも何の話をしてるんだよ。ヨハンは人間だろ。当たり前の、普通の、人間じゃないか。なんでそんなことを」 「……十代さん」 「ヨハンが好きじゃないのは知ってるけど、そんな言い方はないだろ。俺の友達を悪く言うな」 「ともだち」 遊星が口の中でもごもごとその響きを繰り返した。遊城十代がついぞ不動遊星には与えてくれずにいる言葉だった。 「遊星。その、云々は後にしてあなたが気付いたことを私達にも教えてちょうだい。一人で納得されても困るわ」 「だってさ。彼女の要請には応えてやりなさい、あんまり俺も詳しく言いたい話じゃないしね」 「……。『五八七号便』は、乗客・乗組員併せて二百三十五人が機体ごと行方不明になった墜落事故だ。当時記録されていた観測反応から墜落事故ではないかと言われているが、真相は迷宮入りしてしまい面白半分にバミューダ・トライアングルに呑み込まれたのだと言う輩もいる。――二〇〇九年三月十一日に起きたこの事故には、ただの一人も生存者が存在しない。死体すらも」 手短に、躊躇いがちな声が説明を終えると思わず背筋が凍ってしまうような冷たい空気が辺りを通り抜けた。死体一つ引き揚げられなかったという生々しさが余計に恐怖を駆りたてる。しかもそれだけじゃない。 「待てよ……二〇〇九年って今から百年は昔じゃねーか。そんなに長い間生きてるわけねーだろ……」 「ううん……説明がつかないことはないんだ。バミューダ・トライアングル内部は時空が歪んでいるらしいから、そこを経由して出るとどこに飛ばされるかわからないんだって。すごい未来に出ることもあれば、遠い過去に出ることもある。勿論これは信憑性のない伝承を信じれば、ってことだけど。確かに類例は出ているんだけど、科学的には、もしこの数々の遭難が事実だとしてもメタンハイドレートによる発火爆発現象が原因じゃないかって言われてるんだ。遊星なら知ってると思うけど、つまり大爆発による強烈な誘因力と電磁波の発生で海底に沈められちゃうんだって」 「だとしたら生きて帰れるはずがねえじゃんか」 「いや、別にバミューダ・トライアングルだって決まったわけじゃないし僕に言われても……」 「そうだな。それにあの事故、少なくとも俺の世界ではそんな摩訶不思議ファンタジーの類じゃなかったし。わりと普通の墜落事故だったよ。ただ、運が無かった。不時着を試す暇もなく全員海の藻屑になって、パン、だ。葬儀を上げられちゃったから戸籍がなくなって面倒だった」 ヨハンがそう言うとブルーノとクロウも押し黙る。最早何を信じたものか、そう雄弁に瞳が語っていた。 「まあ、それから先にも色々あったのさ。結婚して子供が出来たり、普通に暮らして、普通に幸せだった。……俺の世界では不動は既に故人だった。遊星君はそれを長いこと気に病んでいたが、ある時、大きな事件を乗り越えて博士号を取得しモーメント・エンジンに携わる職に就いた。父親の遺志を継いで、仲間達の帰るべき場所になるのだとそう言っていた。……さて、ここまで話せばもうわかったんじゃないか。俺達がどこから来た異邦人なのかってことが」 「異世界……」 「うんまあ、そんなとこだ。平行世界、パラレル・ワールド。無数にあるそれらの残された最後の《正史》から俺と十代はやってきた。信じて貰えないかもしれないけどね。イリアステルを知っているのはそのため。歴史を狂わせたのは大方奴らだと思ってる。……遊星君、龍亞、龍可、それから他の皆も」 よく聞いてくれ、と唇に指を添えてヨハンはその言葉を口にする。ひそひそ話をするみたいに。内緒の約束をする子供のように。サンタクロースにどんなプレゼントをお願いしたのか無邪気に両親に耳打ちするキッズスクール生のように―― 「この世界は、ほんとうは存在していてはいけないんだよ」 |