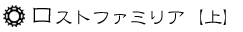――この世界は、ほんとうは存在していてはいけないんだよ。 私の頭の中で、ヨハンのひそやかな言葉が反響する。私達が住むこの世界はあってはならない。捻じ曲げられた、破滅を前提にした世界。彼の言葉はそんなふうにその後続いたのだけれど、チームの皆はそれを上手く受け入れられなかったようだった。 「冗談は、冗談で済まされる範疇のものにしてくれ」 ショックによる沈黙と静寂から一番に立ち直ってまず口を開いた遊星がヨハンに告げたのはその冷たい一言だった。遊星の顔には失われた平静さと憤り、それから払拭し切れない不安が同居している。でもそれは他の皆も同じだ。漠然とでも受け止めることが出来ているのは私が見る限りでは十代と、それから私達双子だけだった。 「悪質と言うのも憚られる程には荒唐無稽だ」 「だから言っただろ。信じるも信じないも君達の勝手だってね。それに君達が生きているうちに何かが起こるわけじゃない。世界が破滅するのは君達が死んだもっと後の時代のことだ」 「だとしても。あまりにも……」 そうして首を振る。きつく目を閉じて、迷いや恐れを無理矢理に振り解こうとしている。でも、それも叶わなくて怖くてたまらない。遊星はそういう顔をしていた。ヨハンはそんな遊星を冷徹とも言える程怜悧に見ている。 「……ねえ、龍亞」 「る、龍可。何?」 「龍亞はどう思う?」 「どうって……」 ヨハンのこと、とひそひそ声のまま続く。私が小さく頷くと龍亞は考え込むような仕草を取ってからもっと小さな声で「でも、嘘吐いてるとは思えないよ」そう耳打ちした。私の考えも、龍亞と同じ。ヨハンがこういう嘘を吐く人だとは私にはどうしても思えない。 不動博士の友達らしいし、不動博士みたいなちょっとふざけたところや、他愛ない冗談はむしろ言うタイプの人だとは思う。だけど大事なことだけは絶対に偽らない。そういう人だ。私の中には理由のない確信があった。 「でも、遊星達は信じられないみたい。俺も……正直、信じたくはないし、その気持ちはわかるよ。だけどあいつのことを思い出すんだ。あいつが、俺に『名前、ちっともわからないんだろ』って言ったことを忘れられない。そう思うと並行世界も普通にありそうだと思うし、それにさ、俺達のことをああやって助けてくれたのにヨハンが悪いやつなわけないよ」 「私もそう思う。遊星には、ちょっと悪いけど」 「ああ。俺もそれには同意する」 「え……十代?」 びっくりして振り向くと、私の隣で十代が神妙な面持ちをしている。彼はヨハンと少し距離を置きたがっていたような気がしたから少しだけ驚いたけど、でもすぐにその驚きはどこかへ消えていった。十代の顔には、確かにヨハンを信用しているとそう書いてあったからだ。 「実はさ、前に泊まりに行った時にも同じこと言われたんだ。あの時ヨハンは決して嘘を吐くような目をしていなかった。それは今も同じだ。……可能性から目を背けちゃいけない。ゼロでない限り、なんだってあり得る……」 つかつかと十代が歩いていく。その先にいたのは糾弾するかのような目付きの遊星と、それに甘んじているヨハンだ。十代は二人の間に割って入り、どうどう、と遊星をいなした。 遊星が怪訝な顔になる。 「どういうつもりですか、十代さん」 「どうもこうもねえよ。まず疑ってかかるのはいい癖とはいえないな。俺は、ヨハンを信じるぜ。それから、龍亞と龍可も」 「……俺は同意しかねます」 「今すぐ賛同しろって言ってるわけじゃない。そんなの、遊星に限んなくてもアキちゃんもジャックもクロウもブルーノも、無理だろ。ただ最初っから有り得ないって決めつけるのを止めないかって言いに来たんだ。……お前、俺が今止めなきゃヨハンになんかぶつける手前だっただろ?」 「ッ……!」 「図星だな。あのさ、ちょっと頭冷やせ……とは言わないから、もう少し前向きに考えてくれよ。とりあえずヨハンを遊星とこれ以上同じ空間に置いとくのはまずいだろうし、俺が外に連れてくからさ。ついでに、龍亞と龍可も」 ぽんぽん、と頭を撫でる。「こども扱いしないでください」、と遊星が蚊の鳴くような声で漏らした。遊星は十代の前では、どうも調子が出なくて子供みたいな泣き言になってしまうらしい。「ぶざまだ」、と唇だけで呟くのが見えた。 遊星が口を閉ざし、アキさんもジャックもクロウもブルーノも私達に(或いは遊星に)掛ける言葉が見付からないのかだんまりを決め込んでいる。十代はぐるりと辺りを見渡してそれを確かめると有無を言わせない強さで私と龍亞の腕を掴み、それからヨハンにアイコンタクトでサインを送ってガレージの玄関口へ向かってすたすたと歩いていく。淀みない挙作で動く彼に、私は半ば呆気にとられながらも一方で安心感を覚えていた。 ヨハンも十代の決定には一切異を唱えず、彼を信頼してその判断に従うつもりのようだった。ヨハンが手招きをして、十代の腕から私を引き離してそのまま自分に引き寄せる。一瞬、抱き上げられるのかと思った。なんでだろう。私はもう抱き上げて貰うような年じゃないのに。 「夕方には帰ってくる。ごめん」 十代が言った。遊星はそれに応えない。 アキさんだけが、わかったわ、と了解の意志を示してくれていた。それが強張った空気が充満するガレージの中で唯一の救いのように私には見えた。 ◇◆◇◆◇ 「らしくないな。焦ってるのか、ヨハン」 十代の声に同調するみたいに、カモメが鳴きながら飛んで回っている。ネオドミノの端にある海浜公園にやってきた私達は高台のベンチに四人で並んで腰かけていた。訊ねられたヨハンははじめ「さあね」とはぐらかすふうに返事をしたのだけれども、十代の「正直に言え」という一言ですぐに態度を改めた。 「ばれてたか」 「バレバレだ。ああやって遊星を揺さぶるやり口ははっきり言ってヨハンらしくない……気がする。しかも遊星だけじゃない、チームの他の皆も。俺は異邦人だし、龍亞と龍可は純朴な子達だし、だからまだ固定観念なしで話を聞こうって気持ちになれたけど遊星達はそうじゃないってこと、お前ならわかるはずだろ」 「まあね。ただ、そうやって先延ばしにしてる場合でもないかもしれないと思ったんだ。イリアステルが攻勢をかけてきてるだろ。この前龍亞が襲われたことだけど……なあ、龍亞」 「えっ?! あっ、うん!」 「十代から聞いたんだけど、はっきりと名指しで龍亞と龍可の親を示したんだろう?」 「そうだよ。あいつらの子供、って言って俺を襲ってきたんだ」 「つまり、そういうことなんだ」 目配せをする。私も龍亞も意味をはかりかねて目をぱちくりさせた。十代は曖昧にうんうん頷いていたけど、多分半分ぐらいしかわかっていないと思う。 ヨハンもそれを見抜いていたみたいで、「わからない時は安易に頷かないでくれ」と子供にするように十代の頭を撫でた。 (……あれ) 首を傾げる。てっきり十代はそれに反発するかと思ったんだけど、俯いて顔を赤らめるぐらいで嫌がる素振りがない。アキさんと二人で出掛けている間にどんな心境の変化があったのか、聞きたいような――でも聞けないような。 「龍亞と龍可の両親って言っても、今の両親のことじゃないんだよ。龍亞と龍可の場合、俺達がいた方の元々の世界での両親はこっちとは違う人間なんだ。ちょっと色々あって……遊星君とか、アキちゃんとかはどっちも変わらないんだけど。……ごめん。突然そんなこと言われても困るか」 「別に。俺もなんとなくそんな気がしてた。パパもママも誰かの恨みを買うような人じゃないもん」 「そ、そうか……」 目に見えてヨハンが落ち込む。もしかしなくとも、あっちでの私達の両親はヨハンに近しい人だったのだろう。もしかしたら……まさかね。ヨハンは若すぎる。 「まあ、そういう意味では確かにあいつの恨み……もっと根源的で強大な、憎悪と執着を買ったんだろうな。だからあいつは特に龍亞に執着する。力関係の差で親の方にはなかなか勝算がないって言うのもあるし、龍可のことを個人的に気に入ってるらしいっていうのもある。龍可はあいつの母親に少し似てるんだ。だから、余計に龍亞のことが嫌いなんだろう」 「なにそれ。俺滅茶苦茶とばっちりじゃん!」 「っていうか、あの子にも親がいたの?」 「人間だった頃に。あのぐらいの年頃でゲリラ戦に巻き込まれて天涯孤独になってる。それが三つの絶望の一つにして機械人形としての最たる原動力、『愛してくれる者を失った絶望』なんだと」 それきりヨハンは口を閉ざしてしまった。十代がふぅんと、今度こそ理解が追い付いたように頷いてヨハンに双眸を向けている。私と龍亞は顔を見合わせて首を横に振ったり、身振り手振りで意思疎通を図ったりした。ヨハンの言葉には相変わらず妙な重みがあって私達を戸惑わせていた。 「人間だった頃に」、両親を失ったらしい赤毛の少年。ヨハンは彼を「機械仕掛けの人形」なんだって言う。遊星の言葉を借りるならばそれはとんだ荒唐無稽な設定だったけど、でも直に少年と相対している龍亞はそれに納得しているらしい。時間を止めたり、また尋常じゃない力で握られたことを考えるとむしろその方が自然だと考えてるみたいだ。 でもそこで行き詰まってしまう。「ねえ」、私はヨハンに訊ねてみた。「ヨハンは、どうしてここに来たの?」 「……何かな」 「ヨハンは、どっちの世界での私達も知っているのよね。それなら、きっとヨハンが目指している世界を上手く元に戻す方法に私達チーム・ファイブディーズが関わっているのかもしれないってところまでは私でも考えられるわ。十代にしつこくアプローチを掛けてくるのも、一緒に来た協力者を連れ戻そうとしてるのかなあって考えればまだ大分自然だし……結婚云々は知らないけど。だけど、私と龍亞を気に掛ける理由だけわからないの。さっき、私達をあんなに必死になって助けてくれたことも。正義感だけじゃなかった。ヨハンは、すごく必死になって、それこそ世界で一番大事なものを守ろうとするみたいに……」 ヨハンは否定をしない。私の言葉を真剣に受け止めて、そのうえで、私達兄妹を特別扱いしていることを無言で肯定している。 それで確信した。彼が私と龍亞を見る目に私は見覚えがあったのだ。 「……十代に対するのと同じぐらい、なんじゃないかな」 「まさかお前……ロリータコンプレックス……」 「違う違う違う、十代、お前は一体俺をどういう性癖の人間にすれば気が済むんだ」 「私もそういうのじゃないと思うわ……ヨハンは、多分、私達のことを重ねているんじゃないかしら」 「何に?」 「そりゃ、勿論――」 人さし指を伸ばして私は十代にその言葉を口にしようとする。でも出来なかった。私の言葉はヨハンでも十代でも龍亞でもないものに遮られて、口の中に押し留められ凝って凍り付いていく。 私たち四人が形づくっていた空気が一瞬で弾け飛んで、冷たい緊張が辺りを支配した。嫌。怖い、怖い、助けて、ねえ…… でも駄目だ。祈りも虚しくその少年が口端を歪めた。 爆発音。それから、爆炎。土煙を巻き込んで炎がまき上がる。咄嗟に身構えたけど、当たり前だけどそんなもので身を守れるはずがない。私の両脇すれすれに硝子の破片や木材の切れ端が飛び抜けて行った。遠目を凝らすと、レトロ調の電話ボックスが破壊されて粉々になっている。さっきまで私達が座っていたベンチも似たような有様だ。 「トパーズ・タイガー! アンバー・マンモス、サファイア・ペガサス!!」 ヨハンが私を庇いながら名前を叫んでいる。するとそれに呼応して何処からともなく彼らが現れ、『ヨハン!!』と主の名前を呼んだ。デュエルモンスターズの精霊達だ、ということはすぐにわかった。どうやら実体化しているらしく、彼らの下には影が出来ていた。 十代がそれに倣って精霊達を呼び出す。彼が持っているのはショップで買ったレプリカ・カードのはずで、だから精霊なんか本当は宿りそうにないものだけど関係ないらしい。ネオスとフレイム・ウィングマンが呼び出されてヨハンの精霊達と並ぶ。精霊達は独自に確認を取り合い、少年に向かって飛んで行った。 「邪魔だよ。どけよクズども」 精霊が弾かれて地面に投げ出される。私を守るヨハンの手が、龍亞を守る十代の手が同じように強く握り締められた。私達兄妹は何も出来ず守られてばかりいる。どうしてだろう。私にも何か本当は、出来るはずなのに。 「ヨハン……」 「いいんだ。子供は、大人に守られてるもんだよ。余計なことは考えちゃいけない。俺と十代は絶対に死なないから、龍亞と龍可は生きることだけを考えるんだ。いいね」 「でも! 逃げ出すだけだなんてそんなの私は嫌よ!」 「大人の言うことは素直に聞くものだよ。パパとママにそう習わなかったのか」 「――そんなの習わなかったわ!!」 「そうだな。俺もそんなことは、教えてなかったな、そういえば」 ヨハンが言った。鈍痛が走る。また視界のあちこちで爆発が起きる。ヨハンの言葉の意味を深く考えようとする前にあの耳障りな甲高い笑い声が響き渡って私の思考をかき乱した。下卑て、でもどこか哀れな少年の嘲笑だった。 「つーかさあ。家族ごっこも大概にしときなよ。一応、今回は仕事だからガキ共には用はないんだよね。俺が潰したいのはお前らだけ。なあわかってんだろ、《母さん》――それからそこの胸糞悪い《偽善者》」 「信用ならないな。お前らは高度な機械人形だ。嘘を吐ける機能が搭載してあることぐらいは知ってる」 「その言い方が僕としても気に食わないんだよねえ。だから余計にお前を嫌うんだよ、ヨハン・アンデルセン。いいの? 大事な片割れが死んじゃうかもしれないってのにぃ?」 「十代は簡単には死なない。それは俺が一番良く知ってる」 「どーだか。遊城十代を人外足らしめている悪魔の力こそが、記憶を奪う核として抜き取られてるんだって言ってもお前、そういう顔してられんの? ……キャハハッ! ほんっと、見ものだよねぇ!」 「なんだって?」 「聞こえなかったあ? 今の遊城十代には忌むべき悪魔の力が殆どない……つまり精霊が出せて多少死ににくいこと以外はまるっきり、ただの、生身の人間だって言ってんだよ。なあ化物!!」 庇われている私には届かないように手加減された攻撃が、ヨハンの背中に直撃する。でもヨハンは少し呻いただけでそれに耐えきって、特に支障がなさそうな感じだ。遅れてしゅうしゅうという音が私の耳に届く。……それが、SF映画なんかでありがちな皮膚が再生する音だと気が付くのに少し時間がかかった。 超再生能力。私にも龍亞にも、遊星にもない修復機能。少年が「化物」と形容したのは精霊を実体化させるからだとかそういうまだありふれた異能のことではなく、間違いなく人間には有り得ないものをヨハンが持っているからなのだ。私は怖くなった。ヨハンがじゃない。 そういうふうに、一切の躊躇いなく誰かを傷付けようとすることが出来るその子が、怖かった。 「再生能力も人間並み、悪魔の力も使えない、おまけに龍亞なんかを庇ってる。絶望的じゃん? それってさ……」 また嫌な笑い声。どうしてこの子は、こんなふうに歪んでしまったのだろう。アンドロイドとしてそういうふうに設計されたから? 違う気がする。もしそうだとしてもそう設計される理由があるはずだ。ヨハンがさっき言っていたことを思い出した。彼には親がいないのだ。 羨んでいるのだ。そして、恐らくは欲している。 「むしろ龍可なんかよりあっちを庇った方がいいよお前はさぁ。ほら、こんなふうに、僕が殺しちゃうからさ! キヒャヒャヒャヒャヒャ!」 「十代! 十代ッ……!!」 「キャハハハハ! まあ精々頑張りなよォ!!」 少年が歪んだ笑みをひっきりなしに洪水みたいに垂れ流す。何が起こったのだろう。私には、何も見えない。 気が付いた時には十代は気絶していて、龍亞と引き離され、精霊達と同じように地面に投げ出されていた。ヨハンが弾かれたように走り出す。私に小さく謝罪をして、一目散に十代に駆け寄っていった。十代はぐったりとしなだれ落ちていて、瞳を開かなかった。 十代を両腕でお姫様のように抱え上げ、ヨハンが俯く。 「ルチアーノ。子供だから何をしても許されるわけじゃない。特にお前は子供の姿で作られたアンドロイドだ。埋め込まれた倫理観しか作用しないということを加味しても、俺の知っている限り、製作者のゾーンは必要なものは全てプリセットしているはずだ。やっていいことと悪いことの区別ぐらいはつくように」 「はぁ? 何寝ぼけたこと言ってるわけ」 「子供達は、狙わないんだったな」 それはぞっとするような酷く低い声音だった。 私が今までに聞いた中で、一番怖い声だ。怒りを押し殺そうとして、でも上手くいかなくて、噛み殺せなくて発露してしまって、そういうものが滲み出ている。 一歩歩を進めるとその代わりにルチアーノと呼ばれた少年が後ずさる。「約束しろ」ヨハンが醒めた声で言った。 「俺達は好きにしていい。子供達に手を出したら、世界全てをぶち壊す」 「……きちがいじみてる。いくらなんでもさぁ……」 「出来るってことは知ってるだろ? 十代がユベルの力を使えなかったとしても、俺一人で十分だ。この世界だけじゃない、存在するありとあらゆる可能性を根絶やしに出来る。脅迫じゃない。警告だ」 「さぁ。どう――だか!」 二人が地を蹴って飛び出す。 ヨハンの背中には、私が幻視した天使の羽が生えている。 「龍亞、龍可、今の内に逃げるんだ」 私も龍亞も、それに答えられずに立ち尽くしてしまった。 前にも、確か同じことがあった。 私と龍亞が襲われて、二人が身を挺して必死に私達を守ってくれる。二人って誰だっけ? 私はその人達のことを決して「十代」や「ヨハン」と名前では呼んでいなかったはずだ。急激に脳内に光景が甦る。フラッシュバックしたあるはずのない私の記憶に映る後姿は間違いなく十代とヨハンのものだったけど、そうじゃないもっと特別な呼び名があったはずなんだ。 『龍亞! 龍可! 父さんと母さんに構わず逃げろ――ネオドミノの中央部へ。早く!』 「遊星君のところへ行くんだ、早く! 龍亞、龍可、誰かを困らせたり悲しませたりするんじゃない!」 記憶の中で私達に振り返った「パパ」の焦燥した顔と、今現実で振り返ったヨハンの顔が重なる。そうだ。思い出した。 思い出してしまった。 「パパ……私の、大切な……」 恐る恐る口にした言葉が確かな説得力を伴って私の中にすとんと落ちていく。今思えばヨハンが私達のことを妙に気に掛けて優しかったのも何もかも当たり前のことだったのだ。 ヨハン・アンデルセンは並行世界での私のパパ。遊城十代はママ。私達は彼らのたった二人の子供としてこの街で生まれて育てられた。すれ違うこともあったけれど、離れ離れになったこともあったけれど……パパとママは私達兄妹を愛してくれた。 私達もパパとママを愛していた。 「急げ! ルチアーノの気が変わらないうちに逃げるんだ。俺はもう、子供達が死ぬところを見たくない」 パパはずっと私達に嘘をついていた。私達を守るために、パパは親子だってことを言わなかった。だってこっちの世界のパパとママは二人とは別にいるんだもの。混乱しか生まないってわかってたから黙って、こっそり私達を見守っていてくれたのかな。パパがルチアーノをレインボー・ドラゴンの力でなんとか抑え付けようとしているのがわかる。私のパパは精霊と魂を分けあったからそういう超常能力を持っているのだ。 でもルチアーノも未来のアンドロイドだからパパの精霊の力にそう簡単に負けないで攻撃を仕掛けて来る。腕の中に気絶してしまったママを抱いているパパはどう考えても不利だった。ママの体は羽根のように不健康的に軽いのだけど(遊星も言ってたし、それは多分記憶喪失になっている今も変わりない)、それでもパパはママを絶対に落としちゃいけないと気負っているから、どうしても色んなものが疎かになる。 「邪魔するなこの偽善者……目障りなんだよ、龍亞は。お前らそっくりだ。僕のことを憐れんで――バカにして――蔑みやがって。殺してやる……」 「誰がそれを赦すか。そんな子供の癇癪で子を殺されて親が黙っていられると思うのか? お前達には確かめたいことがまだまだあるが、それとこれとは別に俺はお前を破壊してしまうかもしれない。引け、ルチアーノ。俺は出来ればお前のことも壊したくなし、世界滅亡なんて馬鹿げたこともやりたくはない」 「ハァ? だっからお前は偽善者だって言ってるんだよ。胸糞悪いったらないね、ヨハン・アンデルセン! お前のその小動物を憐れむ視線が僕は大ッ嫌いなんだよ! 龍亞と同じぐらいに!!」 パパの説得はルチアーノの怒りの火に油を注いだだけみたいだった。確かそうだ、ルチアーノは子供の頃に愛してくれる両親を失った絶望を元にして作られた姿だからきっと親というものに強烈なコンプレックスを抱いているのだ。父親も母親もいないから、よりどころがもうないから、それを持つものやそうであるものに嫉妬を隠さない。 両親に庇われている私達はルチアーノからしたら恰好の獲物……鬱屈した感情の吐き出し場所だろう。彼は私達のことが憎くて憎くてたまらない、理屈としては全然、わかる。 でも元よりパパには説得出来るつもりなんかさらさらなかったみたいで、だろうな、とかぶりを振った。 「俺もそういう意固地なところは好きじゃない。子供は子供らしくいるべきだ」 「どの口で言うわけ、それ。余裕ぶってられるのも今のうちだから。生憎さぁ、お前の知ってるゾーンと僕達を調整したゾーンは別物なんだよねえ。だから、お前が思ってるより僕は強いんだよ?!」 「なっ……?!」 「死んじまえよ! 塵ひとつ残らず、痕跡一つ残らず、僕が消してやるよ――!!」 ルチアーノの目が狂気に見開かれる。開き切った瞳孔に、口裂け女のようにつった口。鬼気迫る、という言葉では表しきれない。ルチアーノのその時の表情には怒りも憎しみも哀しみも慟哭も絶望もあらゆる感情が詰め込まれていて、一つに溶けてぐちゃぐちゃになって、おぞましかった。 拮抗していたバランスが傾いてパパがルチアーノの暴力に晒されてる。パパが落ちる。 地面のないところへ落ちていく。 「いや――!!」 そのままぼちゃん、という不吉な音を立ててパパの姿は見えなくなった。海の上の空には、ルチアーノだけが浮かんでいた。 カモメの一匹もいなかった。 パラレル・ワールドでの私の記憶が私を苛む。きっと思い出さない方が良かったし、正しいのだろう。私は愕然として、涙も零せずに立ち尽くしていた。唇が震える。かたかた、がたがた、振動が次第に大きくなっていく。 パパは海に落ちた。ママを抱えたまま、ルチアーノに突き落とされた。不自然に盛り上がった海面がトラバサミのような鮫のような大口を開けて二人を呑み込んだ。ルチアーノが海面を操作したのだ。だとすれば、普通に水底へ落ちていくだけじゃ済まされないだろう。 もしかして、二人は、死んでしまったのだろうか? 「いや……いやよ……パパ……ママ……」 そんなことあるわけない、と首を振る一方でルチアーノの明確な悪意と敵意をもってすれば確実に死ぬよう仕向けてあると考えるのが確かだろうと冷静に分析する自分もいて。龍亞が私の名前を呼ぶ。それから、私と同じようにパパとママを呼んだ。龍亞も思い出したみたいで、その声の中には複雑な感情がこもっていた。 「やっとまた会えたのに。私まだ、二人にパパとママって呼び掛けてもいないのよ。何も、伝えられていないのよ……」 「俺も。俺も龍可とおんなじ。やっと思い出した。パパとママのことも、ルチアーノのことも……エンシェント、パワー・ツール」 龍亞がつめたい声で私達のシグナーの龍の名前を呼ぶ。あっちの世界で龍亞はパパとママから、精霊をこの世界に呼び出す力を貰って生まれたのだ。やり方を思い出してさえしまえばそれは造作もないことだったようで、龍亞の声に従って私達のシグナー龍は姿を顕した。でも違う、と思う。 二つの精霊には私が知っている程の感情や喜怒哀楽がない。世界が違うから精霊も別物なんだ。 「あぁ……向こうと同期しちゃったんだ。めんどくさ……」 「答えなさいよ。パパとママを、どこへやったの」 「ここじゃないとこだよ。世界と世界の狭間……どこでもあってどこでもないゴミ捨て場。お前らは確か、《バミューダ・トライアングル》とか呼んでた」 「どうして? 何がしたいの? 私達を殺したいのなら、私達にしなさいよ!!」 「天秤にかけたんだよ。そもそも優先排除命令が出てたのはあいつらであって、木偶人形のお前らじゃないし。記憶が戻ったってお前らが人形であることに変わりない。結局皆ゾーンの手のひらの中で踊らされてるんだ」 私と龍亞の激昂に反して、ルチアーノには先程までの覇気はこれっぽっちもなかった。ただ疲れ切ったように眉間の皺を深くして、似合わない神妙な面持ちで……それはどこか、ママが疲れた時にする顔に似ていた。 「顔も見たくない。行けよ、見逃してやるから。僕は……僕は……」 疲弊がありありと伺える。逃げる気だ、すぐにわかった。私達に報復の機会も残さず、ルチアーノは逃げる気なのだ。 それは彼にとって正しい判断だったのだと思う。ルチアーノはパパを無理矢理処理したことで相当に消耗していたみたいだし、私の見間違いでなければ少し感傷的になっているようだった。 その状態で私達を相手にするのは得策ではないと判断したのだ。それは正しい。とても正しい。 私達兄妹は、今にもルチアーノを壊してしまいそうな顔をしていたから。 「大嫌いだ。お前らなんて」 捨て台詞と共にルチアーノの姿が掻き消える。入れ替わりにカモメが戻ってきて、パパとママが呑み込まれていった海の上で鳴いていた。 やり場のない怒りだけがそこに残される。私は、どうしたらいいのかわからなくて龍亞の手を握る。強く。食い込んだ爪が血を流してしまいそうなぐらいに。 「龍可、遊星に伝えなきゃ。信じて貰えなくても、俺達の知ってること、教えてあげなきゃいけない」 龍亞が、自分も怒りが収まらなくて内心がたがた打ち震えているというのに精いっぱいお兄ちゃんぶって、出来るだけ平静を装った声で私に言う。ばればれだ。パパも龍亞も、男の子は皆嘘を吐くのが下手で困る。 でも、龍亞が気丈に振る舞って私を安心させようとしてくれたことは確かに救いだったのだろう。パパがママの背をさする時、きっとママもこんな気持ちだったはずだ。 「パパとママは、嘘吐きなんかじゃないし遊星のことを心配してたんだって。……それで、俺達を守って連れ去られちゃったんだって……」 龍亞は決してパパとママが死んだとは言わなかった。 私も同じ気持ちだ。どんなに手を尽くしたって、あの二人が、世界で一番強靭な十代とヨハンが、いつだって世界のピンチを救ってきた私達のパパとママが―― 死ぬはずがない。絶対に。 だけどカモメは何も言わないし、海面も知らんぷりをして穏やかな水面を見せている。 記憶を取り戻した私達の目に映る世界はこんなにも無慈悲だった。 |