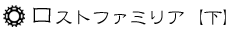『恋の歌だよ。ルチには、やっぱわかんないかなぁ』 いつだったか、そんなふうに《聖女》が言った。 『おれたちは、星が生まれて死んでいくのと同じぐらい確かに、恋をするんだって。そういう歌だ』 少し、遡って。 ――気分が悪い。 パラドックスが壊れた時も、確かこんな気分だった。プラシドと言い合いになった後とは違うこの倦怠感は、いつも訪れる度にルチアーノを苦しめる。 「くそ……」 力無く悪態をつくがそれに構ってくれる相手もいない。記憶を同期させて、明確な敵意でもって自分を睨んできていた双子の子供達の姿が脳裏を過った。大したことがない、どうせ思い出したところで――そう思うが反面でそれは過小評価だろうと捉える自分もいて、ルチアーノは混乱している。 双子は血縁関係にねじれが生じたあの世界でさえも、反吐が出る程に遊城十代と似通っていたしヨハン・アンデルセンと似通っていた。どう足掻いても奴らの子供は奴らの子供なのだ。どうしようもなく、絶望的なまでに絶対的に愛されていた。世界中に祝福を受けていた。 ルチアーノが随分と昔に欲しがっていたまぼろしだ。 双子の前から逃げるように立ち去ったという事実がルチアーノの憂鬱を更に色濃いものにする。逃げたのは本能によるものだ。逃げなければいけないと思った。情けないこと極まりないが、あの時ルチアーノは心底怯えていたのだ。「こわされる」と直感的に感じた。遊城十代と相対した時と同じように。 「……ばかじゃん」 馬鹿馬鹿しい。そして腹立たしい。再生産に適応した唯一の成功作として、今のルチアーノはチーム・ファイブディーズと戦った件の歴史に存在する機体よりも優秀にチューニングされている。あんな子供達に敗北するわけがないのに。なのに何故こんなにも、恐ろしいのか。 (あの、むかつく視線か) 憐れみの眼差しを向けた双子の兄の顔が記憶領域から鮮明にロードされて、一ビットの狂いもなく正確な姿を思考野に再現する。妹と並んではしゃぐ姿、学校で眠たそうに頬杖をつく姿。それからあの日ルチアーノを見ていた少年の姿。ヨハン・アンデルセンと同じ目をして呆然と、だが確かに憐憫の情を向けていた。 まっぴらだ。子供に同情されるだなんてことは。それも持たざるものの不幸を知らない子供に。ルチアーノは反芻する。自らの醜い憎悪を反芻して、しなだれかかるように棺桶に覆い被さる。 パラドックスの残骸を納めた棺桶からは相変わらず美しい白百合の花が咲き乱れてその花弁を硝子の蓋の下から覗かせていた。アーククレイドルの片隅に存在するこの部屋の天蓋もまた硝子製であることに、その時ふと気が付いて知らず身震いする。円形の大ホールのそこらで咲き誇りきついフレグランスを撒き散らしている百合の花達。設えられた六つの棺桶。その中に一つのアンドロイド死体。五つの空箱。 ドームの上空に繋ぎ留められたセキセイインコの剥製、鎮魂歌の代わりに流れ続ける《聖女》の愛したラヴ・ソング…… 「ゾーン、まさかあんたは……」 ドームから続くガレリヤの全面硝子には失われた太陽の代わりに人工太陽の光が当てられていて、そのせいでより一層強く破滅のイメージを見るものの中に想起させていた。本物の代わりに偽者を。不動遊星の代わりに《Z‐ONE》を。遊城十代の代わりに《聖女》を。そうして、平穏の代わりに―― 棺桶に囲まれた中央の巨大なパイプオルガンは錆びついて久しく、その音色を今まで一度としてルチアーノは聞いたことがない。 出来るならばこのゼンマイ仕掛けのつくり物の命が終わるその瞬間まで聞きたくないと思った。聞いてしまったが最後全てが壊れてしまう気がする。 もう壊せるものなんかないのに、それでも破壊され尽くしてしまう。 「母さんのところへ行こう」 震える唇でその言葉を絞り出した。 馬鹿げた夢想が思考を過る。とても信じたくはないのだが……ゾーンは、あの歪み切った英雄願望の成れの果ては、いつか《聖女》が死んだらその姿をイコンにして、パイプオルガンの上に飾るのではないだろうか? イエスの母マリアを崇めるように、聖女崇拝のように、しかしその中にいくばくかの倒錯した処女崇拝を混じらせて、オリジナルが信じた神の模造品をデッドコピーの出来損ないが拝しているのではなかろうか。 ルチアーノには、それを否定する術がない。 ◇◆◇◆◇ どんなふうにわだかまりを抱えていてもルルイエは変わらずきちがいじみた場所だったし、はびこる異形どもも何も変わっちゃいない。くさくさした気分のまま歩き続けるとやがて聖堂が見えてきた。趣味の悪いオレイカルコスの緑石製だ。アーク・クレイドルの硝子の聖堂より悪趣味だが、神聖さはこちらの方が勝っていた。彼女を祀っているからかもしれない。どんなに馬鹿げていても彼女は仮にも《聖女》なのだ。 「《母さん》」 訪れたそこで、彼女はやはり歌を歌っていた。相変わらず酷い声のラヴ・ソングだ。ルチアーノが声を掛けたことに気が付いたらしく彼女の歌声がぴたりと止まる。そうして振り向くと、無垢な子供のように笑った。 『おー、なんだぁ、ルチ』 「その中途半端に略すの止めろ。僕の名前はルチアーノだって言ってんだろ」 珍しく十字架から降ろされて、裸体を隠しもせずに晒している《マザープラント》、ゾーンの信じる神をかたどって造られた《ルルイエの聖女》にルチアーノは溜め息と暴言を投げ付ける。 この歪んだ意思のもと造り出された機械人形を憐れな同類だと思いこそすれ母親だとはこれっぽっちも思ってはいない。ただルチアーノを再調整して「第二次出産」を担っただけの、それは生産工場に過ぎないからだ。第一こいつには恥じらいというものが丸っ切り欠如している。乳房から何から何まで露出して、ここが地上だったら単なる痴女だ。 しかしここは地上ではない。海底都市ルルイエ。創作神話クトゥルーから名を取って付けられ(或いは、それに名を与え)た「時空の迷子」だ。バミューダ・トライアングルに呑み込まれたもの達が辿り付くごみ集積所にして《大いなるクトゥルー》を崇拝するものどもが呻き這う場所。最悪の場所だ。この地で《聖女》は会ったこともない、オリジナルのつがいにして最愛の「ヨハン・アンデルセン」を夢という牢獄の中で待ち続けている。 『今日は何の用で来たんだ? 見たとこ、メンテが必要ってわけでもなさそうだし』 「なあ。僕さあ、一度聞いてみたかったことがあるんだけど」 『なんだ? 珍しいな、ルチアーノがそういうこと言うの』 「あんた、嫌になったことねーの。体のいい化け物の量産工場にされてさ。いっつもニコニコしててぶっちゃけさぁ、気持ち悪いんだよ」 唐突な言葉を投げかけられても、それでもやっぱりニコニコしている。彼女はルチアーノの頭をひと撫ですると諦観したような顔で寂しく笑った。母親がそうしてやるように。 『だってしょうがないじゃん? 所詮オレはゼンマイ人形に過ぎねえもん。オレの腹から何が生まれようがそれは工場が玩具のスライムやらを造ってるのとなんも変わんない。オリジナルに同じことさせたら倫理的にまずいかもしれないけどさ、オレは表皮一枚捲ったら全部つくりもんの機械のパーツなんだ。ゼンマイとネジと金属の塊。血なんて一滴も流れてない。流れてるのは全部オイル』 「でも、あんたはそれでも信じてるんだろう。僕に聞かせるぐらいには、オートマタの僕らが誰かを愛せるとふざけたことを言うからには……」 『そう、信じてる。――だからオレはなんだっていいよ。オリジナルとヨハンがそれで守れるのなら偽者の神様に祀りあげられたって、延々と出来損ないの化け物を造り続ける機械として扱われたって、全然いいんだ。何を悲しむ必要があるって言うんだ? ――機械は、そうやって目的に沿って使い続けられる為に生まれてくるんだろう?』 《聖女》が心からそう信じていると、肩を竦めて見せる。この高度に発達した機能を持つ神もどきの偽物は、オリジナルによく似てたちの悪い存在だった。偽善者だった。自己欺瞞が、自分に嘘を吐き続けて納得したふりをすることが、得意だった。 反吐が出る。腐ってやがる、と思う。これが母親役かよ、と思うといつも泣きそうな気持ちになった。でも涙なんか出やしない。プリセットされた人間だった頃の「泣きたい」という感情コードをロードするだけで、どうしてそんな気持ちを感情記憶野から引っ張り出してきてしまうのかもわからずにいる。 「機械仕掛けの神……デウス・エクス・マキナ、ね……」 ルチアーノは吐き棄てるように言った。 「救われない」 聖女もそれを否定しない。自分が救いようのない機械人形であることを彼女はわきまえていて、それでもやっぱり、あのいけすかない優男を愛しているのだと謳うのだ。 『うん。ルチから見たらオレ、ほんとに救いようがないんだろうな』 「誰から見てもそうに決まってる」 『そうかな。でも、ヨハンも、きっとそう言うんだろうな……ゾーンですら同じだもんな。だけどな『ルチアーノ』。オレは、オレだけは自分のこと惨めだとも可哀想だとも救われないとも、絶対に思っちゃいないんだよ』 そう断じてルチアーノの言葉を遮り、彼女は次の歌を歌い出す。耳障りの悪い合成機械音。でも、何故だかいつもより声音が透き通っていて、儚くってぞっとしない。 偽者が本物に近いことをやってのける時、それはいつだってロジック・エラーによる終焉を指し示している。一番はじめの歴史でゾーンが不動遊星の物真似で世界を救えると感じたあの時と同じだ。その贋作は理を乱した為にもうじきに破滅してしまうのだ。 「……なに、それ」 『恋歌だよ。ヨハンが結婚したあとオリジナルの遊城十代に教えてくれたんだ。恋する誰かのための歌なんだって。人間は、こうやって恋をするんだって』 《聖女》は柔らかく柔らかく微笑んでルチアーノの頭を撫でた。体温の設計されていない人口皮膚の冷たい感触に顔を顰める。今日の彼女は変だ。 「なんでそんな話をするんだ」 だから問うた。恐ろしい予感が、している。 『ん。なんでか、って? ルチは頭のいい子だからもう気付いてるかもしれないけど……多分今日が、おれがルチに会える最後の機会なんだ。恋する気持ち、そういう優しさを出来ればルチに知って欲しくて』 「最後ってどういうこと。ここで祀られている限り、《母さん》が壊れるはずがないのに。墓場だぞ、ここは。何が辿り着くって言うんだ。ゾーンが執着してるあんたのことは、僕達機械人形は絶対に穢さない」 『ルチ、ごめんな。でもオレはこれからもうすぐに壊れるだろうし、その訪れるだろう最期がちっとも怖くないんだ。だってオレは、ずっとその時を待っていたから』 彼女はとても美しく安らかに笑った。 固唾を呑む。その《聖女》の表情で、どういう終わりが彼女に訪れるのか、どういう末路を彼女が望んでいるのかを理解してしまったのだ。そしてルチアーノは本当に聡明な機械人形だったから、もう一つ知らなくていいことを知ってしまった。 「あんたは……」 『ごめんな。あいしてた。オレのこどもの、ルチアーノ』 「あんたは、ヨハン・アンデルセンに自らを破壊させる気だな……?」 『ほんとに、あいしてたよ。――ヨハンの次に』 「エゴの塊みたいな女だね、ほんとにさ!」 『うん。オレ、多分オリジナルの一番嫌な女の部分を色濃く抜き出して造られてるから。遊城十代の半身の悪魔ユベルを核エネルギーとして、ってそういうことだろ?』 だから泣くなよ。オレなんかの為に、もったいないぜ。聖女が言う。優しく怖気がはしる程になめらかな声で。愛しているという単語がゲシュタルト崩壊して、ルチアーノの中で音を立ててボロボロに崩れて消えていく。 「どうしろって言うんだよ、僕にさ……」 『ごめん。困らせるつもりじゃなかったんだけど。でも、どんなふうにねじ曲がってしまってもたとえばオレがアンドロイドだったとしてもそれでもオレが『遊城十代』である限り』 「もういい。やめてくれよ」 ああ、偽りの神よ、造物主気取りの我らがゾーンよ。 ルチアーノは懺悔した。本当は誰よりも母の愛に焦がれていたことを、ずっと前からこの人形に執着をしていたことを、 『オレは、『俺』は、どうしようもなくヨハン・アンデルセンに恋焦がれてしまうんだ』 ゾーンの信仰する神に恋をしていたことを、どうするあてもなく懺悔した。 ◇◆◇◆◇ そうして、時を戻して。 ――再び訪れた《ルルイエ》は廃墟だった。 祀るべき神を失い、その機能を奪われた祭壇の残骸はただおちぶれてみすぼらしく、これといった感慨もルチアーノにはもたらさない。輝きを失ったオレイカルコスはその場所が役目を終えたことを如実に指し示している。泉は枯れ、鉱石には罅が入っていた。 蠢く異形どもはエネルギーを断たれて死骸になっている。ようやく死ねたのか、良かったな。あの《女》ならばそう言ったのだろうか? 「それで、マジで壊してもらったんだぁ?」 あの女としてのエゴイズムを隠さなかったアンドロイドの成れの果てがそこには残されていた。また安らかな死に顔だ。パラドックスと同じ、人間みたいな顔をして機械のパーツを剥き出して十字架の足元に転がっている。 愛する男の手に掛かって死ねたのだ。さぞや幸福だっただろう。機械の死、突き詰めればジャンクになったにすぎないその事象をそういうふうに表していいものかはわからないが、ルチアーノがそれに複雑な心境を覚えていることは確かだった。 光の残り香がする。あの強烈で吐気をもよおす正義の匂いだ。水底に叩き落としてやったヨハン・アンデルセンの横顔を思い出した。双子によく似た顔立ちの彼らの父は酷い偽善者で、《聖女》と《オリジナル》が愛した男で、遊城十代の同類だった。 「あんたは、あの最後の一瞬までは頑なに僕のこと子供だって言わなかったな。女でいたかったのか? 母親は、嫌だったか……?」 答えはない。亡骸をすくいあげると驚く程に軽い。プラント機能の大部分はヨハンによって跡形もなく壊されてしまったらしい。 「だけど僕は、『イリアステルのアンドロイドであるルチアーノ』は、あんただけを母親だと思ってたらしいんだよ。チョーウケる。マジでさ、馬鹿すぎてもう笑うしかないっていうか……」 恋するコッペリアは彼女が愛したフランツ青年の手によって破壊される。そうして彼は元通りスワニルダの方へ戻っていくのだ。記憶が分散して二体になっていたコッペリアは、二人で元通りに合わさってスワニルダに戻る。コッペリアは死んだ。もはや地上にもルルイエにも存在してはいない。 「かあさん」 皮肉な話だ。 「僕は、もしかしたらもう少し甘えてたかったのかもしれない」 今になってよくわかる。遊城十代に焦がれた不動遊星の気持ちが、両親を守ろうとした双子の眼差しが、出来やしないとわかっていても盲信したものを造ろうとしたゾーンの思いが。愛だ。ルチアーノが奪われ、プラシドが取りこぼし、ホセが最後に棄て去ったアポリアの未練。 アポリアが忘れてしまった誰かに愛され誰かを愛するという気持ちを、確かに機械人形もこの高度に発達したAIであたかも持ちあわせることが出来るのだというふうに錯誤が可能だと、ルチアーノは愛していたものが壊れてから気が付いた。 指先で目蓋をひん剥く。人造皮膚の下から現れた眼球パーツはもうあのオッドアイではなく、ありふれた茶色を示している。動力の核として起用されていた悪魔ユベルがあるべき場所へ還っていったのだ。遊城十代はもう間もなく偽りのモラトリアムから解き放たれるだろう。悪魔の力を取り戻してつがいの男と共に、不動遊星が敬した「最強の赤いヒーロー」として蘇り、イリアステルの前に立ち塞がるに違いない。 「かあさん。あんたのへったくそな歌、僕けっこー、好きだったんだぜ」 遊城十代が蘇る。でも、だからなんだっていうのだ? 「……あのさ。僕が、かあさんの子供として定義されるかもしれない理由」 赤いヒーローが復活したとして、それはあの幸福な双子の母親であり、ルチアーノが執着したオートマタの《聖女》ではない。あれがなりたくてなれなかった本物は、だけど本物であるがゆえに偽者には近付けない。違うものだ。違う。聖女は死んだ。 「がらくたの《聖女》から生まれた僕はまかり間違っても神の子とかにはさ、なれっこないし……なりたくもないけど。あいつらを、潰すだけのものはそれでも僕はもらったつもり。僕はマザープラント唯一の成功作だから」 ルチアーノの虹彩が互い違いにうっすらと光った。オレンジと黄緑。このルルイエの地で造物主ゾーンが拝じた悪魔の力の断片がその中には残されている。悪魔の全てとその魂を一つにしたオリジナルと比べたら微々たるものだろう。だがそれでも持っていることに変わりはなく、アドバンテージであることにも違いない。 ルチアーノは双子が嫌いだ。ヨハンに似ている龍亞、そして聖女に似ている龍可。あの二人が、たまらなく憎たらしくてそして、 「おやすみかあさん。またね」 どうしようもなく惹かれている。 聖堂の真ん中に安置された棺桶にこのジャンクを入れなければいけない。パラドックスと同じように白百合の花の中に、純潔と死を司るカサブランカの海に埋めてやるのだ。それから少しだけ祈りの真似事をして、また出掛ける。双子のいる世界へ。最後に残された、破滅の未来をゾーンによって与えられた世界に出てこの体を動かす。 「《イレイティスの眠る地》へ――いずれ僕も、行くことになるだろうから」 何の為に戦うのか。双子を殺すため? 世界を終わらせるため? それとも、敵でもとるために? わからない。機械人形の思考システムはその答えを与えてはくれない。 もしも。 血の通わない、涙も流せない人造アンドロイドが電気羊の夢をみたり、水が命をうみだすように森が息をするように星が生まれ死んでいくように、恋をしたりするのだとしたら。 ろくでなしの神がどうしようもなく哀れな人形達を作り出したことにも意味があったのかもしれないと、信じてやってもいい。 ゾーンが遊城十代に焦がれてやまないことが、呆れ果てた恋なのだとするのなら。 ルルイエを覆うドームの上で無数の魚達が泳いでいる。光の差さない深海を泳ぐ彼らは地上に憧れ、或いは地上すらも知らず引力に引きずられてこの場所を彷徨っている。 まるで機械人形達のように。 青い英雄の光に焦がれた人形や、コッペリアに魅入られた人形達の如く。 《ロストファミリア/END.》 《モラトリアム・END》 |