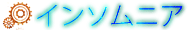私のパパとママは年をとらない。本当はとてもとてもゆっくりと年をとっているらしいのだけれど、私達からしてみればそれは止まっているのと同じくらいにゆったりとした速度だった。昔はもっとさくさく、人並に成長していたらしいのだけれど年々その速度が落ちていってしまっているらしい。 だからいつの日か、私達兄妹は当たり前に、両親よりもずっと早くこの命を終えてしまうのだと思う。そしてその時も、きっとパパとママは今とそんなに変わらない姿でそれを見看ってくれるのだろう。昔そのことを知った時に私は随分とびっくりしてしまって、一回だけ尋ねてみたことがある。パパとママはそれが辛くないのかって。子供達に先に逝かれてまた二人になってしまうことが嫌じゃないのかって。どうしてそれでも私達を生んでくれたのかって。 そうしたら二人は揃って首を振って、それぞれ私と龍亞を抱き締めておでこにキスをしてくれた。それは昔、もっとずっと子供だった頃にパパとママがしてくれた「おはよう」や「おやすみ」のキスに、とてもよく似ていた。 ◇◆◇◆◇ プロ・リーグ専門誌のタイトルマッチ一覧に記された上半期のマッチ予定表を見せて龍亞がママにピースサインをしている。龍亞は昨日の夜遅くに遠征から帰ってきたばかりで、実家にこうして顔を見せたのは私が覚えている限りでは二週間ぶりのことだった。 予定表の半ばぐらいの場所に「チャレンジマッチ・不動遊星(現決闘王)VS遊城龍亞《R》」と印字されている。Rはライディングデュエルの略字だ。遊星がライディングデュエルの公式戦に出るのはもう三年ぐらいぶりのことなんじゃないかとぼんやり思う。スタンディングにしたって、現役デュエルキングの称号を持っていてもプロではなく研究職に就いている遊星が公式戦に出るというそれ自体がレアなことで、彼は今や一部のチャレンジマッチ以外では姿を見せない生ける幻みたいな扱いの人になってしまっていた。 「やー、龍亞も随分と立派になったなあ。遊星と並んでライディング・デュエルなんて羨ましいぜ、母さんもいつかは手合わせ願いたいもんだ」 エプロンを畳みながらママが感慨深げに龍亞を見てそんなことを言った。朝ご飯のパン屑をぱしぱしと払っている龍亞の姿はなんだか八年前、遊星と出会ったばかりの子供だった頃とあんまり変わってない気がするけどママから見ればそれでも「立派に」なっているのだろう。龍亞はにょきにょきとたけのこみたいに身長を伸ばして、あっという間にママを追い抜いてしまった。パパはまだ抜けないみたいで、二人が並ぶとちょっとだけパパの頭が上に出ている。 「どーかなあ。遊星、ママとはあんまりデュエルしたくないって言ってたよ」 「え、なんで」 「『十代さんとデュエルだなんてそんな恐れ多い』だってさ。ママ、一体遊星に何やったんだよ?」 立ち上がった龍亞が溜め息まじりにそう問う。するとママは「ええ……?」と本気で心当たりがないというふうな表情をしてそれから「……フュージョンゲートワンキル?」空恐ろしいことを平然と言った。 「それか、遊星の切り札を速攻俺のHEROの融合素材にしたことか……」 「なにそれ……大人気なさすぎ……」 「だって悔しいじゃん、後輩に負けるとかさあ……」 「それにしたって酷いわ。そりゃ、遊星だって、嫌になるわよ」 「あーうんそれは十代が悪い。大体お前はピンポイントでメタを仕掛けすぎなんだ。信じられるか龍亞、お前の母さんは父さんが折角召喚したエースを情け容赦躊躇一切なく自分の素材にしたんだぞ。しかも二人で世界を救った時に使った思い出の、絆の象徴に、ただの野良デュエルで」 「野良じゃない。真剣勝負にならざるを得ないアンティの勝負だった」 「晩飯を中華にするか仏料理フルコースにするか、ぐらいの話だろ!」 パパがちょっとだけ怒ったような声になってママを叱るような目付きで見る。でも、私と龍亞はそれが本気じゃないって知ってるから別に心配とかはしない。パパはいつだってママにべたべたに惚れていたし、それはママも同じなのだ。パパとママは子供の私達がちょっと引いてしまうぐらいに仲が良くて、喧嘩の真似ごとはよくするけれど、喧嘩をしているところは一度だって見たことがない。 ママがわがままを言った時は、大抵パパが折れてママの言い分を飲み込んでしまうのだ。龍亞がすぐ私に言い負けてしまうのとちょっと似ていた。 「ま、なんにせよ精一杯頑張れよ。遊星に勝てたら、なんか龍亞の好物作って待ってるよ」 「えー、どうかなぁ、遊星滅茶苦茶に強いしなあ……普段仕事ばっかりでデュエルしてないって本人は言ってたけど今のところジャックもクロウも全敗らしいよ。そりゃ、俺も頑張るけど。勝ちたいし」 「そこは元気よく頷くとこだろ?」 「だって遊星ほんとに強いんだよ」 「弱気になるなよ。パパとママの息子なんだから」 ママはちょっとむくれたふうに頬を膨らませるとそんなことを龍亞に言う。パパとママは遊星に引けを取らないぐらい、ううん、それよりもうんと卑怯なぐらいにデュエルが強いのだ。私はパパとママに再会するまで遊星よりもデュエルが圧倒的に強い人というのを見たことがなかったから、初めて本気の二人を見た時はかなりびっくりした。 あれは、チームの皆と離れて二年ぐらい経った時のことだったように思う。ママの全力とパパの容赦のないデュエル捌きは、相手に同情したくなるぐらいに苛烈で恐ろしいものだったのだ。二人の本気は危険なんだってことがすぐにわかった。遊星の、ゾーンと相まみえた時のデュエルもそう言えるかもしれない。強すぎる力は一定のラインを踏み越えると脅威にしかならない。 もしかしたら、それが二人が「ふつう」でなくなってしまった原因の一つなのかな、って一度思ったことがある。でもとてもじゃないけどそんなことは聞けなかった。 私はパパが好き。ママが好き。龍亞が好き。家族が好き。 だから、そんなふうに家族を困らせるようなことは、聞いちゃいけない。 「元気に生まれてこんなに大きく育ってさ。二人ともパパとママの自慢の子供達だよ。だからほら、自信持てって。ママが付いてる!」 「わかったよ、ママの超ドロー力の加護付きで当たって砕けてくる」 「おいおい龍亞、砕けちゃ意味ないだろう」 パパが小さな子供にするのと変わらないように、龍亞の頭をぽんぽんと撫でた。どこにでもいる、幸福な家族の光景。私達がなくしたくないもの。 今まで何度か、私達はばらばらに引き離されてきた。今までもこれからも、私達はその度に必死になってそれを取り戻そうとするだろう。当たり前の幸福を甘受することを、私達が少しばかり変わっているからって許されない道理があるだろうか? だから私はパパを苦しめようとするものが嫌い。ママを追い詰めようとするものも嫌い。龍亞を迫害するものは許さない。 私はただ、家族と一緒に幸せに生きて、そうして幸せに死んでいきたいと、それだけを願っている。 「生まれた時はあんなにちっちゃかったのになぁ」 ママが言った。アルバムで見た生まれたばかりの私達双子は確かに小さくて、割と小柄なママの腕でもすっぽりと覆い尽くしてしまえるぐらいの大きさだった。 「そりゃ大きくはなるでしょ。生きてる人間なんだから、ママもパパも昔はそのぐらいちっちゃかったんだよ?」 「はは。全然もう覚えてないけどな! ああでも、シスターに見せて貰った小さい頃のパパの写真はそりゃもう可愛かったぞ? こういう時西洋人は実にずるい。人形か何かみたいな整った顔立ちの子供が、お仕着せの綺麗な洋服に着られて立ってるんだ。さまにならないはずがないもん」 「ちなみにその時俺は腹が減って仕方なくて、その日の夕飯のことばかり考えてぼーっとしてたんだけどな。丁度いい。今日は特に予定もないし、ちょっと昔話でもしようか。龍亞、龍可、アルバム取ってきてくれ」 「ええ、やだよあれ重いし。そんなことよりデュエルしようよデュエル! 死ぬまでにはパパとママに勝つっての俺の目標なんだから」 「死ぬまでにはな。残念だが今の龍亞じゃワンキルで返り討ちだ。まずは遊星君に勝つことだ」 龍亞は不服そうに頬を膨らませたけど、パパにもママにもさっぱり敵わないことは事実なので渋々承諾して、徐に私の手を取る。龍亞の手は体温が高い。形だけは昔よりもいくらも大きくなったし、頑丈にもなったけれど、その子供っぽい熱だけは昔と一緒だった。 納戸に入って分厚いアルバムがずらりと並ぶ書棚の列の前に立つ。パパの手書きの文字で綺麗にラベリングされたちょっと尋常じゃない数のアルバム達。何十冊もあるこれを全部持っていこうと思うと私や龍亞が何人いても足りないので、順繰りに全てが納められている正規ナンバリングではなくより抜きベストの方を数冊手に取った。ついでに、赤い革表紙の古ぼけたやつも。昔遊星達と覗いた時にこのアルバムの中身がパパとママの小さな頃の写真だってことを私と龍亞は確かめている。 それからずっと聞こうに聞けなかった。でも、今日なら二人はそのことも教えてくれそうな気がする。 遊城十代とヨハン・アンデルセンがどんなふうに出会って、どんなふうに、生きていくことを決めたかってことを。 リビングルームに戻るとソファに腰掛けたパパとママが手招きをしてくれる。一番番号の若い一冊を手渡すと、ママは満足気に頷いて手に取った本を開いた。 「何となくその古っぽいのも一緒に持ってくるだろうなって思ってたよ。でも、それは後回しな。色々、本当に色々な思い出がその一冊にあるんだ。両親の昔話なんてさ、退屈かも知れないけど……出来ればよく聞いておいて欲しい。いつか必要になる時が来るかもしれないから。こいつは勘なんだけど」 アルバムの一ページ目にはゆりかごの中で丸まった私と龍亞が大写しになっている写真が綺麗な飾り模様の下に貼り込まれている。生まれたばかりのしわくちゃの私達。ママの指が写真の中の子供達を優しくなぞった。家事の一切を担当している割にママの手は節くれ立ったものもあかぎれも殆どなくて、妙に綺麗だ。 「俺達家族はどうしたって厄介ごとに巻き込まれちまう運命にあるらしいんだよなあ。俺やヨハンの単体のそういう性質がしっかり遺伝しちゃったみたいでさ。だからもしもどこかで二人が俺の子供じゃなくなったとしても――」 「私は何があったって二人の子供よ。世界がいくつ変わったって」 「お、俺も俺も! 俺達のパパとママは一人っきりしかいないんだから」 「たとえばの話だって。とにかく、もしそういうことがあったとしても二人ともきっと大きな出来事に巻き込まれちゃうんだろうな。それはもう、本人の意志とは関係なく否応なしに」 二ページ目。マタニティを着たママの写真。昔遊星がうっかり目にしてしまってすごい顔をしたのは確かこの写真に対してだった。一目で身ごもっているとわかるぐらいに大きく膨らんだお腹を抱えたママが、カメラの向こうのパパに笑っている。 添えられたメモ書きはナンバリングと同じ、パパの丁寧な日本語で書かれていた。ママはこういう細かな管理が苦手だから、アルバムの制作はきっと何から何までパパが仕切っていたのに違いない。「七ヶ月」という表示に続いてそこにはこう書き記してある。――「三度目の妊娠。かなり久しぶり。久々すぎて十代はその期間の注意点を忘れていたが、この頃ようやくリズムを取り戻す。お腹の子供の名前はもう決まっている。この子達が、今度こそ元気に生まれてきますように」。 「私達の前に、妊娠したことがあるの?」 「うん。二回な」 「でも、俺達に他に兄弟がいないってことは……」 「そ。二回とも死産だった。だからどうしても、俺は三度目の正直でお腹に宿った命を失いたくなかったんだ。アルバムを作ろうってヨハンに話したのもそのせいだった。ちょっと重たいかなあって思ったんだけど、ほら、日本って思いの丈は届くみたいな考え方あるだろ?」 八ヶ月目のメモ。「母子共に今のところ順調。大徳寺先生にレアケースだから人間の医学が全て当てになるとは限らない、と忠告された。少しぐらい変わっていてもいい。俺達も精霊が見えるのだから」。その隣には九ヶ月目のメモ。「ルビーとハネクリボーが十代のお腹に触りたがる。二つ分のいのちがそこにあることを、ちゃんとわかって祝福している」。 「それで、とうとう出産の日がやってきた。予定日より何日か早かったんじゃなかったかな。よく晴れて、気持ちのいい日だった」 昔を懐かしむ目でママが言う。私は知らず、生唾を嚥下する。龍亞もだ。寂寞を語るようなママは、私達があまり知らない顔をしている。 「二人が生まれた日は、庭の向日葵が丁度咲き揃ったあたりのことだった」 パパが言った。 |