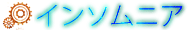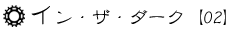その年は酷い猛暑が続いていて、その日もお日様が何かに怒りをぶつけようとしているかのようなかんかん照りだった。ミーンミンミン、というぎらついたアブラゼミの鳴き声。それを窓の外から聞きながら、ヨハンは祈るような面持ちで控え室に立っている。 大昔に教会で習ったように十字を切り、目蓋を閉じ黙して神に祈りを捧げる。こういうふうに敬虔な気持ちで神に祈るなんてことはもう百年近くしていなかったような気もするし、そもそも今のヨハンはもう宗教の神をあまり信用出来ないたちになっていたから、祈る相手は多分デュエルの神様か何かだ。遊城十代が信じているもの。今は亡き武藤遊戯。 「……よく考えたら遊戯さんに失礼だよな……」 十代は遊戯にとてもよく懐いており、ヨハンから見た二人は兄弟や親子のような関係そのものだった。武藤遊戯は遊城十代をとても近しい家族同然の存在として大切にしてくれていた。あの人は十代とヨハンが結婚した時もそうやって祝福をくれたのだ。 もしあの人がまだ生きていたら、きっと初孫や姪甥が生まれたかのように喜んでくれただろう。 十代とヨハンは半人半精の特異な存在である。 そのために二人はとても子供が出来にくい体質をしており、事実やっとのことで受胎が叶った一度目と二度目に妊娠した胎児は生まれる前に流れ落ちてしまっていた。大徳寺はしきりにこう言ったものだ。「生まれることそれ自体が奇跡のようなものだから、落胆しすぎても期待しすぎてもいけない」のだと。 二度目の流産から百年近くが過ぎて、あの頃はまだ人間だったヨハンもそうではない十代と同じものになった。それを指して、大徳寺からは「二人の希望は、今後更に困難を極めるですにゃ」と冗談の通じなさそうな声で「警告」を受けている。だけどヨハンは信じている。確かに二度あることは三度あるのかもしれないが――三度目の正直が起こったっていいはずだ。 一度でいい。自分達の血を継いだ子供達をこの腕に抱いてみたかった。例えこの体がもうまっとうな人間のものでなかったとしても。この血が、子供達に何か辛い命運を宿命付けてしまうのだとしても。愛する人との子を育て、何に代えても守り、慈しみ、「世界で一番あいしてる」のだと教えてあげたかった。 愛してくれる親を持たなかった自分達だからこそ、強くそう願うのだ。 それはほんの少しだけ、エゴイズムの表れなのかもしれないけれど。親は子を愛おしく思うものなのだと、めいっぱいの愛情を与えてその中で健やかに育ち、知って欲しい。 「遊城さん、中へどうぞ」 「ああ、はい」 扉が開いて看護師がヨハンを中へ入るよう促す。連れられるまま恐る恐る訪れた室内では十代が帝王切開施術を終え、ぐったりとしていた。看護師が「だっこしますか」と聞いてくるので茫洋と頷くと布にくるまれた二人の赤子を手渡してくる。受け取ると、ずしりと重かった。まだ水気の多い体で、すやすやと眠り心臓を動かし血を巡らせている。 「おめでとうございます。元気な双子のご兄妹ですよ」 看護師がにこりと笑って告げた。十代が「だるい……いたい……」と呻いている。「ああ……」ヨハンは感極まって子供達を抱いたまま俯いた。 「生まれたんだ」 ようやくのことで訪れたその日は、ヨハンと十代にとって最も幸福な日であり忘れがたい日だった。あいする子供たちがこの世に生を受けた日。家族が出来た日。儚く短い、永遠のような一瞬が始まった日。 そうしてたった一度だけ、世界のどこにいるともしれないかみさまに二人が感謝をした日だった。 ◇◆◇◆◇ 男だったら、龍亞。女だったら、龍可。双子だったらその両方。 ゼロ・リバースが起こったその日に二人でそう決めた。ヨハンの友である不動博士が眠る大地に立ち、厳かな表情でヨハンがそう言ったのだ。名前をここで決めよう。生まれた子供達には、「龍」の名前を付けたいと。 「遊星は、人と人とを繋ぐ遊星粒子のようにって名付けられたんだよな。だから十代、俺は子供の名前に『龍』って入れたい」 「なんでまた。龍の子供だからってか?」 尋ねるとヨハンは首を横に振った。それだけじゃない、もっと特別な運命を感じる。だから。 双子が生まれるより七年昔のことだった。不動遊星が天涯孤独になったその日、半人半精のつがいはやがて遊星と巡り会う運命を信じてそれを取り決めた。 十代が両手の平を合わせて口を開く。小さな、震えるような声音。世界中で誰よりも強靱な肉体を持っている彼が、しかしそんなこととは無関係にいのちを願ってその尊さと美しさに息を呑んでいる。 「生まれてくる子供達が誰かを守れる人間になりますように」 十代は祈るように言った。まるで小さく無力な、ただの人間のように。 「遊星みたいな、優しくて強い子になりますようにって」 「面と向かってそういう話をされると何か気まずい……というか恥ずかしいんですけど。十代さん」 「なんだよ」 「驚きました。あの日、貴方はあそこにいたんですね」 遊星にそう問われて頷く。ゼロ・リバースの爆心地であるモーメント一号機「ウル」。その膝元に確かに十代とヨハンは立っていた。たくさんの命が埋もれた、あの不動博士の亡骸さえ呑み込んだ大地に立ち、死を踏みしめ、次のいのちを繋ぐことを決めた。 生き残っているというのはそういうことだと信じていたから。 「俺はずっと、爆心地の生存者は俺一人だと聞いていました。でも実際はそうじゃなかった?」 「どっちつかず。確かに俺達は不動が君をカプセルに入れて逃がすという話をした時はあそこに残っていたが……不動に、どうしても逃げないのか、俺達なら逃がしてやれるって三回訊いたからな……その後、爆発から逃れるためにけっこうな上空へ避難した。だからまあ、俺達もあの瞬間を肉眼で見た一人ではある。おぞましく、ぞっとしない、うつくしい死の光だったよ」 「……父さんは、逃げなかったんですね」 「そうだ。不動は頑としてそこを譲らなかった。開発者である自分一人だけおめおめと逃げるわけにはいかないってね……暴発させたのはルドガーとそれを操っていた市の急進派だ。俺はお前がそこまですることないって言ったんだが……」 「いいんです。父さんはそういう人なんだって、俺はそれを誇りに思います」 穏やかな表情で父の名を口にする。今年二十歳になる青年は、ヨハンと十代が最初に出会った時よりも随分と大きくなり、心身共に大人になった。たくさんの苦難を乗り越えて、彼は今父親の意志を継ぎ「仲間達の帰る場所」としてたった一人ネオドミノに残り活動を続けている。 ヨハンが「遊星君は偉いなぁ」と行儀悪く頬杖を付いて嘆息した。 「初めて見た時はこの子が本当に世界なんか救っちゃうのかって驚いたもんだ。小さな体で、一生懸命に母親の乳を吸って生きようとしてた。今の君みたいにいつもクールな顔してなかったし、年相応に赤ん坊って感じで実にかわいかった。十代が子供が欲しいってまた言い出したのはそういえば君を見てからだったな」 「え……?」 「あー、そうそう。俺達が不動博士と親交があったのは今の流れでわかっただろ。うん、だからちっこい遊星も見たことあるんだ。俺達、実は二十年前から会ってたんだよね」 まあ俺は百年ぐらい前から遊星のことは知ってたんだけどな! と豪快に笑い飛ばす。彼にとっての百年前というと、丁度遊星にとっての二年前の出来事のことだ。パラドックスが各時代から強力なカードを奪って逃走していたのを三人がかりでとっちめたやつ。 「両親揃って多忙だったから、俺が代わりにおむつとか替えてやったこともあったぜ。遊星、顔真っ赤。ま……それはまた今度な。そんで、龍亞と龍可のことだろ? 他に何が知りたいんだ?」 「あ、いえ……具体的にこう、とかはないんです。ただ、仲間達のことを知っておきたくて。プライベートを詮索するとかでなくて……俺達のルーツを知りたかった。絆を」 「ふーん。絆か。君を象徴する言葉だな」 十代が感慨深げに頷いた。 コーヒーカップを空にしてテーブルに置き、「んー」と軽く唸る仕草をする。「絆」というのは遊星の藍色の瞳を覗き込む度に思い返す言葉でもあって、そうすると自然と昔のことを思い出してちょっとだけセンチになる。寿命で先に逝ってしまった多くの親しい人たち。友人。先輩。尊敬していた人。憧れていた人。ヨハンを除いて彼らは皆自然の摂理に導かれるままその生涯を終えていった。今でこそ彼らの死に目に立ち会えたことに感謝しているが、当時はそりゃあ落ち込んで彼らとの間にあった「絆」をほんの少しだけ恨めしく思った。 こんなものさえなければ苦しい思いはしなくて済んだのかもしれないと、浅はかにも。 今はそう思っていないし、絆をともすると信奉しているような青年にそれを言う必要はどこにもない。十代はそのことを押しやって言葉を紡ぐ。 「ご覧の通り、龍亞と龍可は一卵性双生児なんだ。男女の双子で一卵性になることは、相当なレアケースだけどあり得ないことじゃないらしい。大徳寺先生には、『君達は確率学を無視しすぎですにゃあ』って言われたっけな。奇跡みたいな存在だった。あの子達は神に愛されていると、俺は思った。柄にもなく」 遊城十代とヨハン・アンデルセンの愛する子供達は二人が持ちうる限りの奇跡を結実させたような存在だった。半人半精の体からごく当たり前の人間として生を受け、精霊達の祝福を受け、世界中のありとあらゆるうつくしいものの寵愛を受けた。そのまま健やかに成長し、けれど人間として成熟するに足るだけの苦難を仲間と共に乗り越え、今に至る。「おれには出来すぎた子供達だよ」十代がぼそりと呟いた。 「俺みたいなドロップアウト・ボーイのおちこぼれには勿体ないぐらいに本当にいい子達だ。天使みたい」 「でもそれは十代さんが愛したからでしょう? 俺が父と母を愛しているのも、父母が俺を愛してくれたからです。マーサに抱く感情も同じように。子供は、親に愛されたことを覚えている。……俺も、子供だから。分かる気がする」 「ん。二人が初めて覚えた言葉さ、龍亞が『ママ』で龍可が『パパ』だったんだ。その次は『はねくりぼー』と『るびー』。二人でいつも一緒なのに、言葉だけは別々に覚えていった。龍亞は俺のこと、龍可はヨハンのこと。……あの子達はきっと二人でひとつなんだ。時々本当にそうなんじゃないかって思える時がある。龍可が痛い時は龍亞も痛いし、龍亞が悲しい時は龍可も悲しい。未分化された存在みたいに、ひょっとするとシャム双生児のように。俺はそれが愛おしくもあり、恐ろしくもある。遊星、俺はな」 「……はい。十代さん」 「俺は、とても残酷なことをあの子達に強いようとしているんだ。あの子達に、当たり前の人間として、普通に生きて普通に眠って欲しいんだ。両親に看取られるのがどういうことか、わかってるつもりだけどこればっかりは譲れない。いつの日かあの子達がしわくちゃのおじいさんとおばあさんになる日が訪れたとして、俺達はまだこのばかみたいに若い外見のままだけど、ありがとうって父と母として伝えたい。生まれてきてくれた愛しい子供達に」 十代はそこまで一息に述べたてて口ごもった。口の中が乾いてしまったようで、空っぽのコーヒーカップを弄んだ。 本当に、なんて残酷なことなんだろうと、告げられてようやくゆっくりとした感慨が遊星に訪れる。人間の子供達と半人半精の両親。ヨハン・アンデルセンと遊城十代は永久の時を生きる。だから簡単には年老いない。でも遊城・龍亞・アンデルセンと遊城・龍可・アンデルセンはそうじゃない。精霊に愛されているだけの、言ってしまえばそれだけのありふれた人間だからやがて両親よりも先に年老いて、寿命を迎え、死んでしまう。 愛した子供達に先に逝かれてまた二人になることと、子供達にそのような宿命を背負わせてしまったそのどちらにも十代は怯えているのだった。子供達と過ごす時間は最初から有限に定められていて、そしてその時間は彼らの長い長い生涯の中で数えればほんの一瞬の出来事に過ぎないのだ。 幸せな思い出は残されたものを縛り上げる。死に別れた夫、妻、恋人、そうして先立たれてしまった子供達。彼らは一際美しい形で生者を束縛する。残されている無限にも等しい時間をその思い出を抱えて生きていけというのは、確かに拷問じみていた。 「俺はそのことであの子達に恨まれてしまうのがすごく怖い。もし龍可に『どうして私達が先に死ななきゃいけないの?』って目で見られたら? 龍亞に『俺達まだ死にたくなかった』って言われたら? そしたら、俺は一体どうすればいい?」 「十代。龍亞や龍可はそんなことは言わないよ。あの子達は、全てをわきまえている。受け入れてくれている」 「でも。俺は……この体であの子達を産んだからわかるんだ。きっと俺が望めばあの子達を普通の人間よりいくらも長く生きる体に生むことも出来た。どっちが良かったのかはわからない。ただ深層意識下で当たり前に生きて欲しい、普通の子供として、人生を楽しんで欲しいって願ってしまった。俺はあの子達に選択するチャンスを与えてやれなかったんだ」 「十代」 「十代さん」 「……ごめん。変なこと、言って。遊星の前でこんなに取り乱しちまうとかダッサイよな。ただ……思ったんだ。俺にとっての絆って言葉の持つ意味を」 十代が結んだ絆の殆どは、形のない約束としてどんどんと彼に絡まっていくものたちだった。彼らが望んだわけでも、十代が望んだわけでもなかったけれどそれは必然的に不可抗力的に訪れる不可避の現実だった。丸藤翔。前田隼人。万丈目準。天城院明日香。丸藤亮。天城院吹雪。早乙女レイ。ティラノ剣山。エド・フェニックス。ジム・クロコダイル・クック。オースチン・オブライエン。藤原優介。鮫島校長。トメさん。ペガサス会長。数え切れないもっとたくさんの人たち。不動夫妻。そして、武藤遊戯。彼らと結んだ絆はやがて彼らが遺していった絆に変化していく。遺物となり、目に見えないものになる。 遊星の藍色の、絆の色をした目をまた見た。今は遊星達も生きているけれど、やがて彼らも老いて眠り、遊星との絆も過去のものになる。 同じことが、龍亞と龍可にも訪れる。 だから遊城十代にとっての絆という言葉は酷く重たいのだ。 「なあ……遊星。あの子達は」 声音は、自然と赦しを請うようなものになった。遊星がぎょっとして十代を見返してきていた。 「おれのことを、ゆるしてくれるだろうか?」 ◇◆◇◆◇ 「それで、遊星はママになんて言ったわけ?」 私は呆れ顔でポテトチップスを口の中に放り込んだ。龍亞も同じような顔でポテトチップスをばりぼり食べている。ママは非常に釈明がましい顔をして、あのな、と言葉を続けた。 「まず『十代さん、すみません。ヨハンさんも』って言った」 「ふぅん。次は?」 「殴られた。平手で、綺麗にぱしんって」 「あー、だろうね」 「痛かった。めっちゃ痛かった。大分手加減してくれたのはわかったんだけど、遊星に叩かれたっていう事実が痛かったんだな、今思うと。そりゃあびっくりしたよ。だけど遊星の奴、真顔でこう言うんだぜ。『見るに堪えない』。ひでーよな」 「だが十代、正直俺としても見るに堪えなかった」 「うっせ。ヨハンは俺の情けないとこなんてもっといくらも知ってるだろ。まったく……」 アルバムに手を添えてぶすくれている。写真の中で、幼い私達が手をしゃぶってカメラを物珍しい目で見ていた。「七ヶ月。もうすっかりハイハイを覚えて、いろんなものに興味津々」。 「その上『俺の知ってる十代さんはそんなことでくよくよしたりしません』ときた。お前の理想像を押しつけるなよって思った」 「あー、それは遊星の良くない癖ね。遊星はママのこと、ヒーローだと思ってるのよ」 「そうそう。ママってこんなにおっちょこちょいなのに遊星の話だけ聞いてるとすごい完璧超人みたいに聞こえてくるんだよ」 「俺だって遊星が初めて会った時からは年取ったんだよ。百年も前の若気の至りの時なんか持ち出されても困るってのに」 「十代は今でも十分若い。いっつも無茶苦茶して」 パパが溜め息混じりに言ってママの頭を撫でた。多少不満げな表情をしながらも大人しく撫でられているママは、ちょっと離れてみると人形のように整った姿形をしていて、ちょっとだけ遊星が憧れる気持ちも理解出来なくはない。 ママは遊星にとってスターダスト・ドラゴンを武藤遊戯と一緒に取り返してくれた命の恩人なのだ。多少補正がかかってしまうのも、まあ仕方ないんだと思う。 本気のママはかっこいい。パパも。子供の私が言うとペアレント・コンプレックスのように聞こえかねないけど事実だ。 「あのね、ママ。遊星って意外と喧嘩っぱやいんだよ。大抵の場合手段をデュエルにしてるから穏便に見えるんだけど……ジャックが言ってた。昔の遊星はなんか理不尽な感じにアグレッシブだったって」 「そうそう。遊星が鬼柳さんに負けて落ち込んでる時、気が付いたら殴り合いになって最後に二人でスカッとして笑い合ってたって言ってたわ。スポ根みたいよね」 「あと足技とか、体術スキルすっごいんだ。クロウがね、昇竜拳から着地キャンセルでワン・ツーコンボを決められるとかなんとか……」 「あー、はい、その話はまた今度な。話が逸れちまう」 遊星の武勇伝を途中でストップされる。パパの「二人は遊星君のことが大好きなんだなぁ」という拗ねた声。そんなふうに言わなくったって、私達はパパとママのこと、大好きなのにね。おかしい。 遊星は私達双子にとってとても身近なヒーローで、お兄ちゃんなんだもの。そりゃあかっこいいし好きよ。パパとママとは違うふうに、私達は彼に憧れているのだ。 ママが確かめるようにパパとママに挟まれて座っている私達に触れる。 「ま、そんな感じで俺はえらいびっくりしたってわけ。でも今は遊星が叩いてくれて良かったと思ってるんだ。――あのさ、龍亞、龍可、一つだけ聞いてもいいかな?」 「うん。なあに、ママ」 「二人は俺達のこと、恨んでる?」 ああ、急に私達の手を取ったのはこのためね。私はくすくすと笑ってしまう。そんなふうにしなくたって、私も龍亞もママを傷つけたりしない。冗談でも、絶対に。 横を確かめると龍亞も同じように困った顔をして笑っていた。ママが遊星に昔言って聞かせたように、私達双子の心はこうやってたいていの場合シンクロしている。 「まさか。ちょっとは不満もあるけど、恨んだことはないわ」 「俺も。パパとママの子供に生まれることが出来てほんとに良かったと思うんだ。例え俺達がパパとママよりもうんと早く死んじゃうんだとしてもね」 「……龍亞、龍可」 「ほらな。だから言ったんだ、俺とお前の子供がそんなこと言うわけないって」 私達が口を揃えてそう言うとママは感極まってぷるぷると震えていた。大袈裟なんだから。ママはこうしているとまるっきり子供みたいで、でもパパは基本的によく出来た大人だったから子供が三人いるみたいになることがある。だからママの子供時代はなんとなく想像が付くけど、パパの子供時代って全然わからない。ママにわがままを言うパパなんてもってのほか。大体いっつも、ママの方が欲張りでわがままで、パパを振り回しているからだ。 そんなママがパパは大好きなんだって言う。私達も、そういう童心を忘れないようなママが好きだから、パパの好みがきっと遺伝しているんだと思う。 「ママ、次、このアルバム見ようよ。俺達が幼稚園ぐらいのやつ。ほら……」 「ああ……」 アルバムを手に取るなりママがアンニュイな表情になる。そんなに思うところがあるような内容だっけ? と首を傾げ、ママが開いたページを見てすぐに理解した。それは丁度私達に一番最初の転機、事件が訪れた時期のもの。 パパも痛ましい表情になる。あの決断を、二人がまだ心の中で悔いているのだとすぐにわかった。 「龍亞の精霊との繋がりを断ったのはこの頃だったな」 精霊暴走が起きたのは、そのあたりの時期のことだった。 |