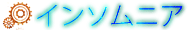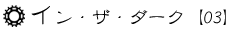精霊暴走、と一部の有識者の間で呼ばれているその事件は、不動遊星がサテライトでくすぶり「チーム・サティスファクション」を結成し大暴れをしていたぐらいの時期にシティで起きたちょっとした「怪事件」だった。突如として、直径およそ十キロ圏内という恐ろしく広い領域でデュエルモンスター・カードの実体化現象が始まったのだ。レベルひとつふたつの下級モンスターから、果てはレベル十を超える超上級のモンスターまで見境も区別も一切なくその現象は襲いかかった。等しく精霊達はこの世に実体を持って呼び出された。 龍亞の能力がある原因によって誘発暴走した結果であり、そうして精霊と深い関わりを持つ彼ら家族が全世界にその存在を知らしめてしまった理由でもある。 「龍亞は悪くないの。龍亞は私を庇ったの。だから、龍亞を怒らないで……!」 幼い龍可が両親にそう懇願する。彼女の後ろには力を使い果たし、能力のオーバーフローで意識を失った龍亞がぐったりした姿で倒れ込んでいた。酷い高熱を出し、体中が汗ばんでいる。 非常に幸いなことに、一家はネオドミノシティ・インダストリアルイリュージョン社・海馬コーポレーション、それらの権力を持った組織にパイプラインを保有していたがそれにしても情報操作には限界がある。ヨハンと十代は、龍亞や龍可を叱る気など毛頭なくもっとおぞましい可能性に心を痛めていた。 「龍可、落ち着いて、いいかい……父さんも母さんも二人を責めたりはしない。エクスクルーダーが教えてくれた。決して、二人が悪かったわけではないのだって」 「パパ……」 「家に帰るんだ、龍可。それから、家族で話をしよう」 ヨハンは娘を抱き締めた。幼く小さな体は可哀相なぐらいに震え、怯えていた。両親に糾弾されるのではないかという怯えと、それからもっと直感的な怯えだった。龍可は本能的に理解している。龍亞の能力暴走が「とてもよくないこと」だということをだ。 十代が龍亞を抱き上げ、気を失っているその頬にキスをした。動悸がほんの少しだけ治まって表情が安らかになる。母親の愛情には叶わないな、とヨハンは内心で独りごちた。 「ママ……龍亞は……龍亞はどうなるの……? パパとママが、怖い顔をしてるの、わかるわ……。パパとママは龍亞をどうするつもりなの……?」 ベッドに横たわる龍亞を伺いながら龍可が尋ねてくる。十代が首を振った。 「龍亞は、精霊が見えなくなる。精霊界にも行けなくなる。勿論、精霊をこちらに呼び出すことも出来なくなる」 「――どうして?!」 「その方が龍亞のためになるからだ。龍可、母さんもな、ほんとはこんなことしたくなんかないんだ。でも、龍亞がその能力をコントロール出来ない限りまた同じことが起きてしまう。何度も、何度も、何度も……子供達を危機に晒すわけにはいかない。龍可、分かってくれるか?」 「そんなの……そんなのいや……わたしには、わからないわ……」 「龍可」 告げられた事実に愕然として、絶望の表情で龍可は両親を仰ぎ見た。双子にとって精霊は家族同然の存在だった。ヨハンが常からそう標榜していたし、十代も、精霊達は仲間だといつも言っていたからだ。 龍亞と龍可は精霊達の「特別」だったから、二人は常に精霊に囲まれて育ってきた。寂しい時には精霊が慰めてくれたし、うまくいった時は精霊が褒めてくれた。時には忙しい両親の代わりに叱ってくれる精霊もいた。エンシェント・フェアリー・ドラゴンなど、よく龍可を言い含めたものだ。 龍可の世界から精霊が欠けるなんてことはあってはならないのだ。龍亞の世界からも。それが双子の世界を占める比重の大きさは計り知れない。 「龍亞から精霊を連れてっちゃうなんて、そんなのだめよ」 「でもな、龍可。例え奪うと言われようと俺達はそれをやらなきゃいけない。もしも……家族が離ればなれになってしまった時のために……」 「離ればなれ……?」 「そうだ。龍可、謝ったって仕方ないかもしれないけど、ごめんな。二人にきっと寂しい思いをさせてしまうと思う。辛い思い、嫌な思い、俺達を恨むようなことも……あるかもしれない。許してくれなくていい。それでも、父さんと母さんは二人をずっと愛しているから」 「パパ……? なんて言ってるのか、わたし、全然わからないわ」 「龍亞の能力が暴走して、悪い奴らが父さん達に気が付いてしまったんだ。父さんと母さんには、二人を守るために自らを差し出す以外に選択肢はない」 きっとね。ヨハンが悪戯っぽく笑う。十代がその後ろですまなそうにまなじりを下げた。龍可の怯えが酷くなる。わからない、と口先で言いながら、聡明な少女は両親の言わんとする意味を解してしまっていた。 自分達の前から愛する家族がいなくなってしまうということを、理解した。 「パパ……」 「いい子にしてるんだよ。不自由はさせないから」 「ママ……」 「大丈夫。二人には、いずれ頼もしい仲間が出来る」 「いや……いやよ……いや……!」 「龍亞と仲良くな。お前達は、たった二人の兄妹なんだから」 「いやよ……パパとママのバカッ……おおうそつき……!」 「うん。ごめん」 十代が右手を掲げる。普段は綺麗な焦げ茶色をしている両目が、オレンジと黄緑の互い違いに発光した。それは龍可にとって初めて目にすることになる、母親が本気で精霊としての能力を行使する姿だった。 龍亞の隣で同じく力を使い果たし眠っていたミニチュア状態のライフ・ストリーム・ドラゴンが十代の側に吸い寄せられる。そのまま十代がもう片方の手に持つカードの中に吸い込まれ、ライフ・ストリームは世界から消え失せた。上位精霊の能力で封印されたのだ。龍可が駆けて、母親の手からカードをひったくる。「パワー・ツール・ドラゴン」。シンクロモンスター、機械族土属性星七。 しかしすぐにカードを十代に取り替えされてしまい、龍可の手の中には惨めな空虚さが残された。 「十代、こっちは終わった。後は龍可だ」 「ああ。サンキューヨハン」 「返して! 返してよ……!」 「駄目だ。聞き分けの良い子になれとは決して言うつもりはないが、こればっかりは母さんも父さんも譲るわけにいかない」 その時母親がしていた表情が、父親が向けた眼差しが、とても怖かったことを龍可はずっと大きくなって、両親と再会した今になって思い出す。二人は覚悟を決めていた。それは遊星が最後の戦いに赴いてアーク・クレイドルへ消えていった時の、死さえも厭わないようなそういう表情によく似ていたのだ。 意識が糸を断ち切ったみたいにぷつりと落ち、そうして再び目を覚ました時には、龍可は龍亞が精霊と深い結びつきを持っていたこと、彼らと触れ合うことが出来たことを忘れていた。回復した龍亞の方もそれは同じだったらしく、それ以降、度々龍亞は「龍可はいいなあ。精霊が見えてさ」と口にするようになった。 そればかりではない。二人ともが揃って、精霊は家族であるという信念を喪ってしまっていた。両親が精霊と強い結びつきを持っていたことも、果ては、両親が使っていたカードの精霊達がどんな姿をしていたのかさえ。 十代とヨハンはその欠落について何一つ教えてはくれなかった。ただ黙って、胸をなで下ろし、子供達を抱き締めた。 それから数日後、双子の両親は家に帰って来なくなった。 ◇◆◇◆◇ 「今ならまだちょっとはわかるの。パパとママの気持ち。でも、やっぱり釈然とはしないんだけど」 「うん。エクスクルーダーも、何か見たらしい遊星も詳しいことは教えてくれなかったからさ。パパとママが嫌がるからって……」 「まーな。子供に喋りたくないことの一つや二つはあるさ、そりゃ」 ママのアルバムを捲る手が少しだけ止まった。私と龍亞のアルバムに刻まれている空白の五年間。写真を撮ってくれる人がいなくなったから、その期間は学校の集合写真とかそういうのしか記録に残っていない。 「今思うとね、私達、あの頃は随分とちっちゃな世界の中で生きてたなあってそんなふうに感じるの。私達には家族しかなかったのよ。パパと、ママと、それから精霊達が殆ど世界の全てだった。友達はいたけどね。だから、あの五年間もきっと必要なものだったんだわ」 「そういうふうに言えるなんて、龍可は強いなぁ。俺だったら駄目だな。ヨハンがいなくなったらと思うと……ゾッとする。ていうか無理だ。絶対無理」 「ママはパパに依存しすぎなのよ」 「そうだな。それはもう全然まったく、否定出来る気がしない」 さっぱり自慢にもならないことを偉そうに言う。そんなママを見てパパが「本当に変わらないな」と苦笑いをした。 「変わらないって、いつぐらいから?」 「うーん。会ってすぐぐらいから。昔、パパとママが高校三年生だった時にそれはもうえらいことがあって……それ以来だな。自惚れでなければ」 「へー。それってパパとママの馴れ初めってやつ?」 「平たく言うとそうなるかな」 パパが観念したように革表紙の赤い古っぽいアルバムを手に取った。「わかったよ。この中身が見たいんだろ?」と溜め息を吐いてやれやれと頭を振る。流石に話が早い。 昔見たこのアルバムの中には、ごく少ない二人の写真が納められていた。写真が嫌いそうなパパと、写真が苦手そうなママの子供時代の肖像達。私達はそうでもないけど、パパとママは本当に写真が嫌だったみたいで、心から楽しそうな写真というものはあまり納められていなかったように思う。 「父さんは孤児だった。だから両親の顔を知らないで育ってきたし、大人になってからも特に調べようとかは思わなかった。実際のところ、親に対する未練ってのがそんなになかったからな。孤児院でもまあ当たり障りなくやってたけど……シスター達から見れば相当嫌な子供だったと思う。協調性が殆どないくせ、大抵のことはそつなくこなしちゃうんだからな。ある種の問題児だった自覚はあるよ」 「うそ。パパってむしろ優等生っぽいのに」 「そうそう。問題児ってママの方じゃないの?」 「うるさいな。高校じゃ、確かに俺は問題児でヨハンは優等生だったよ」 ママがぶすくてれてぷいっとそっぽを向いた。パパの方を持ち上げられると、大抵ママはこうやって不機嫌そうなポーズを取る。そうするとパパが甘やかしてくれるからだってことを私達は知っていた。 「問題児だったともさ。十代の方がわかりやすい分かわいい問題児だったと思うよ。俺は、子供の頃は基本的に人間を信用してなかったからな」 「それって、人間が嫌いだったってこと?」 「……そうだな。あんまり子供に当てられて嬉しいもんでもないけど」 アルバムのページが切り替わる。「アカデミア・アークティック高等部入学式」という日本語の添え字。写真の中に書かれている言語はぱっと見英語でもないみたいで、私にも龍亞にも読めない。多分パパ以外にはわからないのだろう。「デンマーク語。父さんの母国語だよ」とパパが教えてくれた。でもやっぱり、発音は良く聞き取れなかった。 「人間が嫌いだった。でも表面上はうまくやっていく方法っていうのを、高校に上がる時にはすっかり身につけてたから特に苦労はしなかった。……そんな顔したって教えないぞ。知らなくっていいんだから」 そう言って困った風に私達を見ると、パパは私と龍亞の頭をくしゃくしゃと撫でた。 パパの写真がなくなって、ママの写真群に移り変わっていく。おどおどして自信がまったく感じられないこの子供がママの昔の姿なのだと言われると違和感があったけど、確かに目鼻立ちに面影はあった。ママは自信が肉体を持ったらこうなのだろうってぐらい自信に満ちあふれた顔をしているから、不思議で仕方ないけれどこの子がママなのだ。その子は二色の茶色のツートーン・カラーの髪の毛をして、泣きそうな目でカメラの向こうから私達を見上げてきていた。 「男の子みたいだよね」 「男の子なんだよ。遊城十代は紛れもなく日本男児だった。泣き虫だったけどな」 「ママなのに?」 「そう。色々あったんだ。色々あって、父さんは母さんが好きになった。性別とかどうでもよかったし、側にいてくれればよかった」 「俺は、最初は戸惑ったけどなぁ。でもこうして今龍亞と龍可を授かることが出来て、あの時の判断は間違ってなかったって確かにそう思える」 私達の疑問をはぐらかすふうにママが笑った。パパはとても神妙な顔をして、私達三人の顔を順々に眺め、最後にママの顔をまじまじと見つめる。ママが「なんだよ、急に」と怪訝な顔をする。パパの手がママの頬に伸びた。 「恋してたんだ。きっと」 「お、おう」 「じゅうだい」 「……ヨハン?」 「ありがとう」 謝罪するような声音だった。ずっと抱えてたものが堰を切ったような、そういう顔色をしている。私達はパパとママの出会いに何があったのか知らない。だけど、このやりとりから分かったことがある。結婚を申し込んだのは多分パパの方だ。 パパがママを口説き落として、そうして私達が生まれたのだ。それを自覚すると何か気恥ずかしかった。 「俺、十代に会えて本当に良かったって、そう心から思うんだ」 神様に祈るみたいにパパが言った。 ◇◆◇◆◇ ヨハン・アンデルセンは敬虔なクリスチャンだった。過去形だ。ある日あるきっかけでああ神様っていないんだということを知り、ヨハンは信仰をやめた。平たく言えば日本人のような考え方になった。だいたい、遊城十代の影響だ。 「意外ですね。あなたは、なんと言うか……ばりばりのクリスチャン、といったふうな容貌をしているように私には見えたから」 「おいおいそりゃどういう意味だ? 俺自身は、ごくごくありふれた西洋人の容貌だと思ってるんだけど。そんな、特別敬虔な信仰心を持つ人間がこんな胡散臭い職業なんかやってるもんかね」 「まあ、日本人特有の偏見だと思って聞き流してくださいよ。あなたは『そんな感じ』の横顔で、よく、どこかを見ている。そんなふうに思ったものですから」 不動博士がコーヒーマグを片手にニコニコ笑ってそう言った。博士の人柄の良さを知っているので、そんな塩梅でなあなあに流されるとどうも「しかたないなあ」という気分になってしまう。つくづく彼は得な性質の人だと思う。 「君の父さんは、実にずるい性格をしているぞ……遊星。苦労するんだろうなぁ……」 「止してくださいよアンデルセン博士。うちのゆーくんが変な言葉を覚えてしまう」 「いーや。君の息子は優秀だ。きちんとこの子はわかっているよ。自分の父親がずるい奴だってことをね。そんな顔をするな不動、俺は褒めてるんだ」 赤ん坊の遊星が、不思議そうな顔でそんなよくわからない会話をしている大人たちを見上げてきていた。父親譲りの意志の強い瞳でじっと見つめている。「この子は強い子になるな」ヨハンは懐かしむように言った。「俺が初めて会った頃の十代と、顔がちょっと似てる」。 その言葉に不動博士の目がきらめいた。 「あ、奥さんとのなれ初めですか。是非聞かせていただきたいですねえ」 「誰も話すなんて言ってないぞ。ただちょっと懐かしくなっただけで……ああ、うん、わかった。わかったから俺の裾をそんなに引っ張らないでくれ遊星、頼むから」 「おや。ゆーくん、おいたはいけないよ。でもよくやった」 「そうやって甘やかすのは感心しないなぁ俺は」 「必要があればきちんと叱りますよ。迷っている時に、手を差し伸べるばかりではなく叩いてあげられる優しさが必要だというのが私の持論です。ねえ、ゆーくん」 大きく溜息を吐く。不動博士というのは、決して計算づくで動く嫌味な男などではないが、こういういい意味での計算高さを備えている人間だった。ヨハンは、そういう手合いには結構弱い。 十代もそういうところがあったし、聞いた限りでは、成長した未来の遊星にもそういう気質が受け継がれているらしい。無意識に人を動かし得るものたちの、きっと素養みたいなものなのだろう。 「……。なれそめって言ったって、そんなに面白いことなんかいくらもないぞ」 「私にとってはなんでも興味深いんですよ。勿論、根掘り葉掘りプライバシーを詮索したいわけではありませんが……ご自慢の奥方との出会いはさぞかし運命的なものだったのだろうなあなんて考えたりはしましたね」 「出たな。研究者の悪い癖だ」 「それを言うのならあなたもでしょう、博士」 不動博士が人の悪い笑顔になって言った。遊星がそれにびくりと体を震わせ、今にもぐずりだしそうな顔になる。 「遊星が泣きそうな顔してるぜ、不動。それじゃ、手短に、さわりだけな。あんまり赤裸々に話すことでもないし、それほど内容もない。……高校三年生の秋だった。俺達が出会ったのは。校舎の屋上でさ、俺、道に迷ってて」 「ああ。博士は方向音痴ですものね」 「そう。しかも着いたばっかりの知らない土地だぜ。迷わないほうが難しい。でも、それに関してばかりは自前の方向音痴に感謝してる。だって、十代と出会えたんだからな」 遊星の頬を撫でながらヨハンははにかむ。小さな命に触れていると、いつも決まってあの瞬間を思い出すのだ。ヨハン・アンデルセンの世界に色が付いた時を。 あの頃遊城十代はまだ子供で、自らが持たされた命運のことを何も知らなかったし、ワクワクするデュエルさえ出来ればそれでいいと思っているぐらいの、考えなしだった。彼は無知で、それゆえ美しかったがそれは恣意的に形作られた姿でもあった。ユベルを奪われていた少年は、とても呑気に笑ってヨハンに手を差し伸べた。 彼の温もりに触れ、そうして初めて、ヨハンは「世界」を知った。 「きっかけは簡単なことだったんだ。俺達はお互いに超が付くぐらいのデュエル馬鹿で、デュエルを愛していた。デュエルさえあれば人と繋がれた。ただ、その中で飛び抜けて俺達は似通っていた。さも、そういうふうにデザインされていたんだと言わんばかりにな。――結局、同じ穴の貉だったのさ。俺達は同族だった」 やがて家族が欲しいという感情を知った。愛する人が生まれてきた世界を守りたいという思いも知った。十代と触れ合ううちに、ヨハンは「精霊が見えることで何かとのけ者にされがちだった」少年は人の愛を知り誰かを守りたいと切望することを知った。 「生まれて初めて、命に代えても守りたいって思える人だったんだ、十代は。それまで俺にとっては宝玉獣達だけが全てだった。びっくりしたよ、自分でも。ま、無茶したせいでそのあと十代にはこっぴどく怒られたんだけど。怒られたっていうか、心配させすぎて逆に十代がまいっちゃったんだっけ。懐かしい。何もかも、もう、懐かしい」 若さが十八歳の遊城十代とヨハン・アンデルセンを突き動かす全てだった。二人は若かった。紛れもなくだ。それ故に愚かしく、無力だった。今よりももっともっと無力でそのくせちっぽけな両の手でなんだって救えると信じて疑わなかった。 自分がまるで正義のスーパーマンにでもなったかのように、錯覚していたのだとそう思う。ヒーローに憧れていた青年はいつだったか言っていた。「信じる限り、なんだって出来るはずだって盲信していた。アメリカン・コミックのヒーローみたいに」。 たくさん失敗して、傷ついて、すれ違って、わけもわからず泣いたこともあった。苦しみがなかったわけではない。ただそれでも、たった一つ、明確な事実があったからヨハンは今もこうして生きている。 「何が正しくて何が正しくないのかなんて関係なかった。愛してた。それが全てだ。十代が愛する世界を守らなきゃって思った。あいつが息をしている世界を、遊城十代がうつくしいと尊んだ世界を。不動、俺はな、ご立派な博愛主義者なんかじゃないから、世界中全ての人を愛してなんてそんな御大層なことは言えない。だけどほんの一握りの、大切な人たちがいる世界は守りたい。それは本当にちっぽけな願いかもしれない。でもだからこそ強く祈るんだ。……おかしいよな。神様なんて信じてないって、言ったばっかなのにさ」 「おかしくなんかありませんよ。アンデルセン博士、あなたは確かに偶像として祀り上げられた神を信じることを止めてしまったのかもしれませんが……これは、私自身が無神論者だから言えることなんですけどね……」 不動博士が声をひそめて、内緒話をするように口元に手を寄せる。ヨハンも耳を彼の口元に近付けようと動くと、間に挟まれた遊星が少し苦しそうに目を細めた。 「我々の信仰――信じる気持ちっていうのは、本当はもっと単純で、ありふれて、さり気なく、優しいものなんです。あなたが家族という世界を守りたいと願うように」 遊星が目を閉じて眠りにつくのが、二人の視界の端に映る。ヨハンは息を呑んだ。柄にもなく、奇跡を認めて、指を組む。 「ああ……」 星が綺麗だった。サテライト――衛星の名を冠するこの地区は、シティよりも星が綺麗だ。遊星も、その名前のように煌めく、星のような存在になる。そうしていつか、あの赤色と出会うのだ。 きっとどこの世界でも。 「不動、君ってやつは、まったく本当にすごいやつだな。モーメント・エンジンなんてものを完成させた時点で奇人変人だってことは十分わかっていたが……、いや、そういうふうに言うやつ、俺はそうそういないと思うぞ」 「博士も似たり寄ったりだと思いますけどねぇ。ふふ、でも、ありがたくお言葉頂戴しておきますよ。アンデルセン博士。ほんの戯れですが……良ければ祈りませんか。あの星々に、我々の信じるものを」 「いいぜ。俺が祈ることも、祈る相手も、ま、決まりきってるしな」 そうしてヨハンは胸の前で十の字の印を結んだ。随分と昔に棄ててしまった仕草だが、その様はヨハンの佇まいにぴたりと沿っており美しい。やはり彼の祈りは聖職者の祈りのようだ、と不動は思考する。神父が祈るように、形のない十字架を胸元に掲げて彼は祈っているのだ。 彼の信仰は今なお確かに遊城十代の中に息づいている。 永遠に。 |