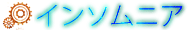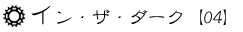それからパパとママは代わる代わる私達に学生時代の話をしてくれた。アカデミア本校の七不思議、怪談話、ライバル達のこと。「井戸の底にさ、カードが棄てられてたんだ。それで化けて出てきたことがあった。当たり前だよなぁ」ママはすごく嬉しそうに昔のことを教えてくれる。「プロ・デュエリストをいっぱい招いて学校中がサバイバルデュエル大会になったこともあったっけ。母さんはちょっと色々あって出られなかったんだけど」。 ママの話には色んな精霊の話が出てきて、中でも儀式に失敗して生贄を求めたサイコ・ショッカーの話なんかは傑作だった。そういえば昔、もう本当に昔だけども……精霊界でサイコ・ショッカーに突然平謝りされたことがあった気がする。きっとあれはそのことをママに言うのが怖いから私のところに来たのだ。 それからジェリー・ビーンズマンの話。パパが昔助けたトムという男の子のフェイバリットだったジェリー・ビーンズマンをめぐるレアカードハンターとの因縁、とかとか。物心ついた時から精霊が見えたパパとママは、私達と変わらず、彼らと共に生きてきた。 ふと、それぞれの肩に乗っているハネクリボーとルビー・カーバンクルが誇らしげにしているのが目に入る。この子たち嬉しいんだわ。こんなに精霊のことを愛しているパパとママの元へ来れたことが、すごく、すごく。 ママがたくさんの思い出を喋り切ったところで、ようやくパパが口を開く。高校三年生の始業式の日。留学生代表VS本校代表の模範デュエルのこと。パパとママはそれですぐに意気投合して、友達になり、一緒に馬鹿やったり、色んなことをやったんだっていう。 「世界も何度か救ったんだ。内緒だよ」 「そのうち何回か、ヨハンはすぐ自己犠牲に走りたがってさあ……俺は本当に嫌だったんだぞ。龍亞と龍可も、最初から自分を犠牲にして他を助けようなんて考えちゃだめだ。自分もまとめて助けられるように考えて、それでもどうしても無理そうだったら、覚悟して、悔いの残らないようにやりなさい。残された方の気持ち、二人はわかるだろう?」 「うん。パパとママは……私達と離ればなれになってたことを、後悔してないのね」 「してないよ。それで二人がこんなにまっすぐ、いい子に育ったんだから。二人は恨んでるかもしれないけど」 「恨んでなんか……ただ、すごく、すごく寂しかったの。羨ましかった。でも今は大丈夫よ。パパとママがどうしてそうしなきゃならなかったのか、私、わかる気がする」 パパとママは《精霊暴走》のあと、私達を置いていなくなった。だけどそれは私達を守るために自らを捧げたからなのだと、私はもう知っている。 それがいいことだとは、お世辞にも言えないと思う。悪い手段だとさえ。そのために、私達の両親は数年間もの間ずっと非人道的な実験の対象にされていたのだとママのデッキの精霊カードエクスクルーダーが教えてくれた時、私も龍亞もすごくショックだった。 こうして今、当たり前の家族として暮らしていられることがとても尊い奇跡なのだと私はそうして痛いほど肌に感じたのだ。 「でももう、二度とやらないでね。今度はもう、私達ちゃんと戦えるわ」 「うーん。親としては、あんまり子供を戦わせたりはしたくないんだけど……一番いいのは、このまま何事もなく毎日が過ぎていくことだ。平和ボケするぐらいがちょうどいいよ」 「それは無理じゃないかなぁ。十代はトラブルメーカーだから」 「でもほら、今は、遊星もいるし。ファイブディーズの皆は今世界中散り散りになってるけど、それって裏を返せば世界中に仲間がいるってことじゃん。すっごく頼もしくない?」 「ああ、そうだな。仲間がいるって、本当に心強いことだよ」 ママが頷いた。パパがアルバムを閉じ、両親に挟まれて座る私達をじっと見る。つられてママも。パパのエメラルドの色をした瞳とママの栗みたいな艶のある焦げ茶色をした瞳が私はずっと好きだった。私達の目はそれを掛け合わせたような黄土色をしている。それが、紛れもなく私達が二人の子供なんだってことを表しているようで、口にしたことはないけれど私はそのことをとても大事にしている。 ――いつか、私と龍亞はパパとママより先に死んでしまうけれど。 「もっと話聞いてたかったけど、なんだかお腹空いてきちゃったし今日はここまでにしましょ。ね、パパ。それにママも。私ね、二人がどうして結婚したのか、今日本当の理由がわかった気がするわ」 「ん? 何だ、言ってごらん」 「『家族』って、とても幸せなことね。私が知る限り、それより尊いものはそうないもの。……きっと、パパとママは家族になるために出逢ったんだわ。そして私と龍亞は、もっと深く結び付いた家族になるためにパパとママの間に生まれてきたの」 私達がパパとママの子供で、家族で、仲間がいて、生きていたということは決してなかったことにはならない。 おはようとおやすみのキスをするみたいに、なんでもないように、私達はずっとずっとヨハン・アンデルセンと遊城十代の子供なんだ。 「そうだね。俺の気持ちも龍可と一緒。……それじゃさ、ご飯作ろうよ。時計よく見たら話に夢中で、お昼ご飯食べ損ねちゃってるじゃん」 「あ、ほんとだ。悪い悪いすっかり忘れちゃったな。夜ご飯にはちょっと早いけどそうするか!」 ママがしんみりした空気を蹴破るように明るい声でそう言った。そのまま鼻歌なんか歌い出して、夕飯のメニューをどうしようかって考え始める。 パパがそれをゆっくり追いかけて、ミートローフがいいだとか、それが無理ならロールキャベツにしようだなんて口を出す。「両方とも時間のかかる料理じゃん」って、龍亞がぼやいた。尤もだ。 私もスリッパを履いて立ち上がり、台所に駆けていく。いつか必ず終わりが訪れるのと同じように、今ある幸福も私にとってはすごく確かで、手が触れることのできる現実だった。 「あぁ」 何か、酷く幸福な夢を見ていた、ように思う。遊城龍可は病院のベッドの上で目を開いた。色の褪せた硝子玉にはもうろくな色が映らない。盲いた黄土色の瞳で、焦点の定まらないまま昔世界だったものをぼんやりと眺め見た。ずっと寝転がっているのは知っている。今視界であるものに映っているのは、だから多分天井なんだろう。 龍可は寝たきりだ。龍亞も。もう起き上がる力がないのだ。随分と年をとり、もうじきに寿命で迎えが来ることを兄妹揃って察知していた。二人はとても長く生きた。幸せだった。死ぬのは、不思議と怖くない。 双子でずっと一緒だった。生まれてから楽しい時も辛い時も一緒にいた。離れなかった。最期も同じ瞬間に迎えるんだって龍亞も龍可も知っている。だから怖くはないんだと思う。他にもっと大きな理由があるように思うけれど……。 怖いのは、やはり、両親を残して先に行くことだ。(ごめんなさい)覚束ない口の代わりに幻影の中のまだ若かった少女が口を開く。(先に死んじゃう親不孝者でごめんなさい。でも私達、幸せだった) 少女の隣に少年が立つ。たくさん無茶をしていた頃の、肉体が頑丈だった龍亞。龍亞は龍可と同じようにまぶたを伏せり、幻の手を幻の手に繋ぎ合わせて佇んでいる。(パパとママの子供に生まれてこれて良かった。愛してる。ずっと) 幻の目を見開くと、若かった頃と同じようにクリアに視界が開けて視覚情報がいちどきに二人の意識に流れ込んでくる。個室の中の二つのベッド。その中に無数のコードやチューブに繋がれた老体が一つずつ横たわっていて、それぞれに十代とヨハンが付き添っていた。自分の意識の中に自分の姿を捉えていることに二人は特に疑問を抱いていない。きっと死に際に幽体離脱でもしているのだ。 十代は床にへたり込み、龍亞の元で泣き崩れていた。大丈夫、怖くないって昔十代は言っていたけれど、やはりその時になると、それがとてつもなく苦しいことで、涙が止められないのだった。 「龍亞……龍可……何か……何か言ってくれよ……」 父親と母親の元に寄って屈み込んでみるが、やはりこの幽霊のような体では彼らの目には映らないらしい。元々父母は幽霊を見ることの出来る体質だったけれども、そういうのとは別で今の二人は特別なのだろうと思われた。 兄妹はお互いに示し合わせて頷く。残された僅かな時間で、両親に触れたいと二人で無言のうちに取り決めた。 「龍亞……龍可……俺の子供達……」 十代が龍亞の手に触れる。ヨハンも龍可の手に。温かかった。父母の体温は、記憶にあるままずっと不変の、太陽みたいな温もりを龍亞と龍可に与えてくれる。 太陽。それで龍可には、「どうして死が怖くないのか」、その本当の理由がわかった。なんて簡単な事だったのだろう。最初からそう決まっていたのだ。 恐れることなど、何も。 「ああ……」 龍可が力の籠もらない指先でそれでも龍亞に触れ、落ち窪んだ瞳をようよう開いて両親に向けた。 そして年老いた娘はその時初めて愛を知った生娘のような表情をして、嗄れた声で絞り出すように、最期の言葉を口にする。 「わたしたち、パパとママに、還っていくんだわ」 ◇◆◇◆◇ 幻をみていた。まだ幼い子供達が大はしゃぎで公園を駆け回っている。二人はシーソーに乗るのが大好きだった。ブランコもだ。よく二人乗りをしたがって、危ないって言って止めてもまるで聞きやしなかった。その度によくわからない屁理屈を自信満々に聞かされたものだ。「ぼくと龍可はだいじょうぶ」、といつも上の兄はそう言った。「ぜったい。ぜったいだよ」。 二人が遊んでいた公園はもう大分昔に取り壊されて、なくなってしまった。トップスのビルのすぐそばにあった自然公園。今十代の目に入るのは錆びついたジャングルジムと、腐って使い物にならないシーソー、それからチェーンごと椅子が撤去されたブランコの残骸、寂れ果てた公園の名残だ。子供達はもうどこにもいなかった。世界中探したって、どれだけ人智を超えた力を使ったってその結果は変わりようがない。 でもそれは、仕方のないことだった。生まれる前からわかっていたことだ。人間として生を受けた子供達に定められていた運命。あらゆるものには寿命があって、それを過ぎると駄目になってしまう。それは肉体面での話であったり、また精神的な内実における話であったりもした。公園が寿命を迎えたように、子供達も寿命を迎えたのだ。 それだけのことだ。 「引きずってる?」 生涯の伴侶に決めた男が立ち尽くすその隣に立って問う。「答えはイエスしかないぜ、十代。何故って俺もだ」そうして男はシニカルに笑った。 「あの子達が最後に遺した言葉が、鼓膜から脳味噌に焼き付いて、こびりつき、消えていかないんだ」 「ああ」 「耳の奥で、今でもまだがんがん言ってる。『わたしたち、パパとママに、還っていくんだわ』って、あの子はそう言ったけど……喪われたものはもう二度とは帰ってこないよ。もう二度と、永遠に、龍亞も龍可も俺に『おかえり』も『ただいま』も言ってはくれないんだ」 「仏教思想だな。輪廻転生。『われわれは野の草となり、地となり、そこから上っていく大気へ、そうして天となった後には再び地へ戻る雨水となり……』」 「そういう難しい話をしたいわけじゃないよ」 「『……永劫を繰り返す』。俺だって別にこれからとうとうと十代にありがたい坊さんの話をしようってことはちっとも考えちゃいないぞ。十代。龍亞と龍可は俺達から生まれた尊い命だ。十代の身体に宿り、十代が腹を痛めて、そうして生まれた。それに絶対に違いはない。そうして死を迎えたあの子達はいずれ大地に溶け、あらゆる恵みとなり、俺達の中に還ってくるんだ。……こういうと、結局論理じみてて、十代はそういうんじゃないってまた言うかもしれないけど。俺はそういうことだと思う。――あの子達は俺達を愛してくれた」 ヨハンの手が十代の身体を抱き留める。十代は涙を隠そうともせずに泣き続けて、嗚咽を漏らす。 壊れた公園。荒れた空。子供達のいない世界。けれどそれでも、ヨハンと十代が今立っている世界は尊いもので、破滅を迎えていいものなんかじゃない。 「ヨハン、俺さ、俺さ……」 「うん」 「ずっとあの子達のことを覚えて生きるよ。決して忘れない。俺が愛した家族のこと、俺が守った家族のこと。そして、家族が愛したこの世界のこと……」 鼻水を啜って自分に言い聞かせるみたいに言う。十代が愛した子供達、その子供達が彼らの仲間と共に命を賭して守ろうとした世界。かつて龍亞も龍可も何度もその身を賭して戦った。遊星や、ジャック、クロウ、アキ、信じるもののために。 彼らだけではない。十代自身も戦ってきた。ヨハンも。戦って守りたかった。武藤遊戯もそうだ。彼と運命の結びつきで出会った名もなきファラオ、二人は、名前を探す傍らで幾度も滅亡の危機に瀕した世界を救ってきた。 「家族だけじゃない。俺の敬愛するたくさんのひとたちがこの世界を愛したから。俺は、ずっとこの世界を守っていくものになりたい」 見渡す限りにスクラップが散乱するくず鉄の海の中で十代は言った。世界は荒廃した。鈍色がパノラマのようにぐるりと広がり、世界を覆い尽くした。けれどそれは終わりではない。荒廃はまだ、滅亡ではない。 「あの人たちが守りたかったものを」 ヨハンと十代は生きていて、動くことが出来るのだ。それはきっと、まだ二人にやるべきことが残されているからなのだろう。 「……ゾーンの話じゃ」 「ああ」 「この世界は途中まで正しい歴史を辿っていたのが何か変な力で分岐しちまったんだって言う。俺達の記憶の中には確かに遊星がいて、遊星はチームの皆と戦って、歴史を変えたはずなんだ。破滅の未来を回避した。なのに、彼らが死んで百年も経たないうちにこの有様。何らかの外的要因が働いてるんじゃないかって、俺は思う」 「ゾーン自身も、積極的にあの頃のネオドミノシティを滅ぼすつもりはないって言ってたしな。少なくとも『この世界のゾーン』は遊星の成し遂げた歴史変革の影響を受けてるんだ。だとしたら、何の影響で歴史は歪められたんだ? イリアステルじゃないのだとしたら?」 「でも俺には、イリアステル以外にそういう干渉を出来る存在が思い当たらないよ。イリアステルが動けるのは、それを極めたゾーンがタイムワープを繰り返せるからだ。だから有り得るとすれば……『イリアステル』しかない。この世界じゃない、もっと別の場所の」 「例えば遊星に戦いを挑んだ?」 「それは違うな。並行世界でのゾーン達は、『正史』で自分達が遊星達に敗れたことを皆知っているはずなんだ。システム的にはそうだって、これもゾーン本人が明言した。だとするのならば」 比較的なだらかなくず鉄の山に腰掛けてゾーンが分けてくれたデバイスを起動する。この中には彼が掻き集めた「この世界最後のデータ群」が残されており、かつては重要保護機密だったもの、誰それの個人情報、名前も顔も知らない誰かの日記、どこかの政党のプロパガンダ……そういったものが脈絡なく見境なく収められている。ある意味で人類最後の叡智の結晶、のようなものだった。 その膨大なデータの中から必要と思われたものを取り出し、ポップアップで大きく表示させる。《機密》という電子印の下に「海馬コーポレーション代表取締役海馬瀬人」の署名があり、これが事業利用に関する事柄ではなく彼個人の興味による調査の結果である旨が記してあった。 内容は《ドーマ帝国とオレイカルコスについて》。太古から「欲望の石」オレイカルコスの力で不老不死となり世界を操っていたアトランティスの古代ドーマ帝国の長ダーツと、それに纏わる自らと武藤遊戯達の戦いのこと、科学の力でその不可思議な現象が解明仕切れなかったことへの不満、そういった長々とした論述の最後に簡潔なまとめが記されている。――「人の願いは、それが純粋であればあるほど、追い詰められた時に絶対的な悪意に変わり得る」。ダーツは哀れな男だった、という一文でその文書は締められていた。 「何者かの純粋な願いがやがて純粋な悪意となり、世界を滅ぼそうとしている……?」 同じく《機密》の電子印の下に「海馬コーポレーション特別技術開発局MIDS局長不動遊星」の署名がある次の書類を取り出す。これは彼が青年時代に経験した「イリアステル」との戦いを留めた私的文書を引用した「イリアステル」の持つ技術を解析・言及したレポートであるらしく、種々の小難しい学術用語が並び十代にはその内容がうまく判読出来そうにはなかった。 しかし興をひくものはある。四体のアンドロイドとその出自についてのレポート内容がそれだ。 同じ人間の幼年期・青年期・老年期を模した三体のアンドロイドで出来上がっている「アポリア」、かつて十代も戦ったことがある歴史改革の前線に出ていた「パラドックス」。そして不動遊星の友となり彼に最後の試練と希望を託したという「アンチノミー」、ネオドミノを滅ぼさんとした彼らイリアステルの盟主「ゾーン」……彼らは皆一律に友たるゾーンの願いで、ゾーンのために動き、ゾーンはそれら全ての動きを把握していた。それはどの世界でもイリアステルが存在する限り根本的には変わらないシステムのはずだ。しかしこの世界のゾーンによると、長らくの間「アンチノミー」の動向が不確かなのだという。 「アンチノミー……『ブルーノ』は、遊星の友達だった。チームファイブディーズの仲間だ。一番、遊星の近くにいたアンドロイド。それは一番強く遊星の影響を受けていたっていうことじゃないか?」 最後の書類を取り出してスクロールする。これには《機密》印はなく、ゾーンの素っ気ない電子署名があるのみだった。内容は「英雄因子」について。「武藤遊戯」「遊城十代」「不動遊星」の三人の名前が並べられ、彼らの歴史的特異性、分岐点との関連性、その影響力如何についてのゾーンの分析と見識が述べられている。 「『英雄因子は、大きく世界を揺るがす根幹となり、歴史を良くも悪くも狂わせる。歴史の伸縮特性を最も色濃く持ち……よって歴史変革を行うにあたって、正史に戻そうとする働きを持つ彼らを出来る限り速やかに無力化しなければならない』。こういうふうに書いてあるけど、実際遊星はうまいこと無力化出来なかった。そのために送り込んだブルーノは、やっぱり、遊星に惹かれてしまって……この世界のゾーンにとってそれは失敗だった。『アンチノミー』は確かに『ブルーノ』に偽装して不動遊星に取り入る目的で送り込まれたんだけど、結果的に『アンチノミー』を『ブルーノ』に狂わせてしまった可能性が否めない、ってこのゾーンは考えてるみたいだな。なあ、ヨハン。俺さ、今すごく怖いことを考えているんだ」 「ああ……奇遇だな十代。俺もだよ」 「俺は、もし俺達の知っているゾーンが言うように誰かが歴史を狂わせようとしているのだとしたら、それは誰かの悪意によるものだと思ってた。現状では世界が終わった方がいい、っていう意思の働きが見られるからな。もしもだ。もしも、それがそういう誰かの悪意に端をなすことじゃなかったとして……誰かの『純粋な願い』に端をなすものだったとしたら……」 デバイスの電源を落とす。ホログラム表示されていた書類が一瞬で掻き消え、視界を占める色は一面の灰色に戻った。十代は震える声で同じ可能性に思い至ったらしい隣のヨハンに振り向き、尋ねる。 「それってすごく、恐ろしいことなんじゃないか?」 ヨハンは何かを考えているように目を細め、無言で頷いた。もしもこの歪な歴史改革の根幹が、ただ不当性を訴えて力技で排除すればいいだけの悪意ではないのだとしたら。 「それでも俺達は行かなくちゃ」 ヨハンがぽつりと漏らした。十代は目をぱちくりさせて彼をまじまじと見る。 「そうだとしても、俺達が信じて守ろうとしたものをこんなふうに歪めようとするのは、間違っているよ。例えそれが純粋な願いに起因しているのだとしても、こうなってしまえば最早それは悪質なエゴと何ら変わらない。十代には、身に覚えすらあるはずだ。覇王十代が何をしようとしたのか」 「……ああ。覚えてるよ。忘れられるもんか」 「『人の願いは、それが純粋であればあるほど、追い詰められた時に絶対的な悪意に変わり得る』。その結果成り変わりつつある滅亡を待つ世界が、誰もの望む未来じゃなかったはずだ。遊戯さんも、遊星も、そんなもののために戦ったわけじゃないって俺は思う。龍亞や龍可も。生きてたら……そう言ったかもしれない。『そんなふうにくよくよしてるの、ママらしくない』とかさ」 「そうだな……」 その言葉に目を瞑ると、背中を押してくれる小さな手を感じた。丁度十三、四の子供の手だ。ヨハンも同じものを感じたらしく、二人して大慌てで振り返った。延々と地平線の果てまでスクラップの海山が続いている。空は鈍い。 『行ってらっしゃいママ。ママは、ヒーローなんだものね』 娘の声がそう言った。 『そうそう。遊星、ずーっとママのこと、そう言ってたよ。『十代さんは、決して諦めず……いつもワクワクしていた』ってさ。俺達も知ってる。ママは、いつも、かっこよかった』 息子の声がそう言った。 『ずっと一緒よ、パパ、ママ』 「龍可」 『俺達、パパとママの中にいつもいるから』 「龍亞」 『愛してる』 腕の中で砂になり溶けていくように儚い声だった。きっと幻聴なのだ。けれどこれほど確かな幻聴なんて他には存在しないと十代とヨハンは確信していた。子供達は生まれた場所へ還っていった。何もない虚空を抱き締める。この身体を巡る血の中に、子供達の残滓があるようなそんな気がする。 「俺も……俺達も、ずっと、愛してる。ありがとう、俺の子供達……行こう、ヨハン。そうだよな。なんでもやってみるまではわかんないし……ぶつかってみるまでは、何を考えたってそれはただの推論だ」 「そうそう。十代は、そのぐらいアバウトで、向こう見ずで、適当なぐらいが丁度いいよ」 「細かいところはヨハンがなんとかしてくれるんだろ?」 「十代が突っ走るからね」 「だから俺は前を向いて走っていけるのさ」 まだ涙に濡れて赤い目じりのままで不器用にウインクをする。 「感謝してる」 それからどちらからともなくキスをした。約束事の確認みたいなものだ。口に出さなくてもそれで全て伝えられる。 そうして二人はゾーンの力を借り、過去へと飛び出していく。望まない形で変えられていく世界の崩壊を止めるために、あの懐かしいネオドミノシティへ。 ゼロ・リバースが失われて、ごくありふれた青年となった「青い英雄」のいる時代へと。 途中うっかり手を離した隙に時空の波にもまれて離れ離れになってしまい、ヨハンは予定した時代に辿り着いたものの十代は座標を誤って遊星の真上に落下してしまうのだが、それはまた、もう少し状況が進んだ先での話だ。 《イン・ザ・ダーク/END.》 《インソムニア・END》 |