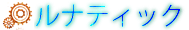「――話は、これで終わりよ」 淡々と話をし続けた龍可は締めの言葉すらも平坦に口にした。それは感情が欠けているというよりも、どうにか、心を殺して平静を保とうとしているようで見ている側の遊星達を不安にさせる。 「パパとママは。世界を愛していたわ。家族のいる世界、仲間達の生きた世界を。弔いと、そして抱擁なの。あの二人が世界を守ろうとするのは……命がとても尊いことを知っているから……」 「……二人は、自分達の最期を覚えているんだな……?」 「ええ」 遊星がおずおずと尋ねる。間髪入れず返された龍可の短い返答に遊星はただ一言「そうか」とだけ言った。遊星にはこの世界で生まれた不動遊星以外の記憶はない。前世なんてものはもってのほか、龍亞や龍可の言うところの、「パラレル・ワールド」の自分の記憶も。 それは遊星ばかりではなくジャックやクロウ、アキにブルーノも同じだ。存在こそ昨日アンデルセン博士が仄めかしてはいたが、殆ど眉唾であったし……現につい昨日まで双子だってパラレル・ワールドの自分が何をどうしていたかなんて露ほども知りはしなかった。 だからきっかけさえあれば、ここにいる誰もがその「記憶」を手に入れる可能性だって決して低い訳じゃないのかもしれない。遊星はそれが怖い。 双子の話に出てきた「自分の知らない不動遊星」が、自分より優れた存在で、その幻影に苦しめられるのだとしたら? そうでなくとも、老衰し息を引き取る自分の姿なんてものを見せられてしまったら…… 「あのね、遊星。私達……『パラレル・ワールドの遊城龍亞と遊城龍可』は、死ぬのが怖くなかったの。私達ちょっと変わってるのかもね。あの時私達は、自分達が生まれた場所へ還っていくのをはっきりと自覚したわ。母親の羊水の中に還元されるみたいに……『世界の真理』を垣間見たみたいに」 「今も? 今も怖くないのか」 「今も。むしろ、私は自ら進んでそれを選ぶわ――正しい歴史を取り戻すためならば」 龍可の黄土色の瞳が、遊星の青色をまっすぐに見つめる。遊城十代が不動遊星にそうするのと同じ強さで、ぴたりと照準を合わせ決して反らすことなどないように。 正しい歴史。急に、さっと青ざめていくようなフレーズだ。ブルーノが怯えているみたいな顔をして龍可を見た。 「じゃあ、龍可は……やっぱりアンデルセン博士みたいに、この世界は正しい歴史じゃないって、そう言うの?」 「うん。今ならはっきりそう言えるし、信じるしかないって、わかる。この世界は、間違ってるわ。このままだとそう遠くない未来にモーメントの逆暴走で本当に破滅してしまう。『あの世界』で不動遊星が最も避けたかった道へと進んでいく破滅のレールの上をただ走ってる。放っておいたら全部だめになっちゃう」 「何か、明確に違うことがあるんだね」 「そう。俺達、調べたんだ。この世界には《ゼロ・リバース》がない」 ブルーノの問いに龍亞が答える。目も、口元も、何もかもどれ一つ笑っていない。 「それってすごくおかしいんだよ」 「――何故だ?」 「そもそもゼロ・リバースって、《イリアステル》が意図的に引き起こしたことなんだ。あれは酷い事故だった……ってこれは受け売りなんだけど……って誰も彼もが言ったけどそれでもゼロ・リバースはイリアステルがよりよい未来、破滅の手っ取り早い回避を願って引き起こしたものだった。いつだったか大人になった遊星が教えてくれた。『シミュレートの結果、擁護するわけではないが正しい未来を導くのに件の《ゼロ・リバース》事件は必要不可欠な要素だった』って。敵のイリアステルのボスだった《ゾーン》は遊星の思考回路をコピーしたアンドロイドだ。遊星がその結論に至ったんなら、ゾーンもそうだったんだと思う。……なのにこの世界には《ゼロ・リバース》がない。影一つでさえ」 難しい言葉を噛みしめるように一つ一つ並べていく。いくつかは遊星にも聞き覚えのある名前だ。《イリアステル》。つい最近龍亞を狙った少年が所属する組織の名前。 「龍亞は、いや、並行世界の俺達は《イリアステル》を知っているんだな。あの赤毛の少年が龍亞に言ったように」 「ん……それはそうなんだけど、なんか、引っかかるんだよなぁ……。あのルチアーノ、俺が知ってるルチアーノとちょっと違った気がする。知っていたのよりももっとずれてる。ヘンなんだ。大体、ルチアーノの奴があんなに俺を殺したがる理由、全然わかんないし……あと、パパとママに執着するのなんかもっと意味わかんない。正しい歴史ではあの二人とイリアステルに接点なんかなかったんだ」 「それも違和感の一つってワケか。しっかし……」 クロウがドライな声で言った。乾いて、どうしたものか考えあぐねている。視線で促されてジャックが咳払いをして、遊星を支えるように手を伸ばした。あまりにも沢山の事柄が氾濫して遊星はもうぼちぼち限界がきてもおかしくないことを二人は察知していた。 「参ったな」 鳥の巣みたいなオレンジの頭をかきむしってクロウが心底どうしたらいいものかわからないという声でぼやく。ほとほと困り果てている。クロウだって遊星やジャック達と今まで様々な事に首を突っ込み、解決していった実績を持っているがそれはもっとスケールの小さな事柄だ。一番大きくて、新興宗教組織の壊滅。世界まるまるをカードに戦うようなことはとても手に負えそうには思えない。 ヨハン・アンデルセンはそれを何度もやってのけたんだと彼等の子供を名乗る二人は言う。遊城十代も。そしてここにはいない不動遊星も。俄には信じ難い。でも双子は嘘を吐く顔をしていない。 「俺達は、一体何を信じりゃいいんだ?」 「自分の守りたいものを信じるしかないって、ずっとママは言ってたよ」 「だから、クロウやジャック、アキさん、それに遊星が私達の話した歴史よりも、今確かにここにある世界を守りたいっていうのなら、それでいいと思うの。誰もそれを諫めないわ。仕方のないことだから」 「……でも、だからこそ俺達はパパとママがそうするように世界を守りたい。もし、それで今ここにいる遊星達を裏切ってしまうのだとしても。ごめん」 先に今謝っとく。龍亞が腰を折った。 「それで今ここにいる全員を殺すことになっても」 「――龍亞!!」 「だってそうなんだ。正しい歴史のためにこの世界を犠牲にするって、そういうこと。……パパとママはこの世界の人間じゃないからわかんないけど、俺達皆、最初からいなかったことになっちゃうんだよ」 はじめから全てゼロになる。時空渡航を繰り返す男のありふれたSF小説の結末の一つのように。男が「完璧に」過去を歪めてしまった場合、男が元々いた世界は、分岐するはずのない可能性としてあらゆる並行線から拒絶されて男の存在自体が消えてしまうのだ。 今あるこの《ゼロ・リバース》のない世界は本来あり得てはならない意図的に逸らされた世界。歪に歪められた分岐してはいけなかった可能性。はじまりの《Z‐ONE》が悉く可能性を潰して回り、正史を導く前ともまた違う。 龍可と龍亞はそれを確信出来る。「遊城十代」が死んでいるこの世界なら。 「死ぬのが怖くない、ってあなたたち言ったわね」 不意にアキがそんなことを聞いた。双子はそこで初めてきょとんとして、顔を見合わせる。アキの表情には他の四人のような戸惑いや、怯え、怒りはない。アキはとても不思議な表情をしていて、まるでそれは「遊城・十代・アンデルセン」が息子と娘を見るようなそんな顔だ。 「……う、うん」 「それは、とても危ない考え方よ。他の四人が今何を考えているのか私は知らないわ。だけどそれとは関係なく、二人とも、ご両親に命は大事にしなさいって教わらなかったの?」 「え?」 「『どちらでも』よ。親は、子供を死なせたくないものだわ。一命を賭して守ろうとすらする。あなたのご両親はきっとそんなふうに命を軽々しく考えて欲しいとは思っていない。それがわからないのなら結局何も成せないのと、違うかしら」 アキの声は厳しい。母親に叱られているような気分になる。龍亞は十代の言葉を思い出して反芻した。『そのうち何回か、ヨハンはすぐ自己犠牲に走りたがってさあ……俺は本当に嫌だったんだぞ。龍亞と龍可も、最初から自分を犠牲にして他を助けようなんて考えちゃだめだ。自分もまとめて助けられるように考えて、それでもどうしても無理そうだったら、覚悟して、悔いの残らないようにやりなさい。残された方の気持ち、二人はわかるだろう?』 「親を大事に思う気持ちはわかるの。私も、お父さんとお母さんはとても大切だから。……だから、龍亞と龍可がそうしたいのなら、やりたいようにやればいいと思う。私もやりたいようにするわ。それで私達の目的が一致ないしは違っても、それはそれで仕方ないのよ。だけどこれだけは覚えておいて。私達は仲間よ。ずっとね」 何をしていたってよ、アキが念を押して二人の手を掴んだ。ささくれ立ったところのない、細くしなやかで、たおやかであり、しかし芯の通った美しい指先。 握力が強いわけではない。しかしとても強い母親の慈愛のような指先だった。 「……アキさん、ママみたい」 「そうね、十代は、アンデルセン博士に対しては割と女性みたいなところがあるから」 「ううん、違うの。お母さんなのね。アキさんはとても優しいお母さんになるわ。……そう。私達、実は知ってるのよ」 世界中に散り散りになったチーム・ファイブディーズの面々がどんな大人になっていったのか。龍可は白衣を翻した女医の姿を知っている。彼女は同じように白衣を着た彼の隣に立ち、そして、 「アキさんは幸福なお母さんだったわ」 彼によく似た子供をその胸に抱いて双子に見せてくれた。十代とヨハンにも。 するとアキは流石にその言葉にびっくりしたようで、照れたようにほんのりと頬を赤らめる。隣に立つ夫が誰なのかに思いを馳せ――或いは察して、しかしそれを口には出さず、「そんなもしものことは知らないわ」と嘯いた。 「どんな結果になってもそれが私の手にするものよ。あなた達の言葉に言い換えればそれが私の世界なのだわ。ねえ、龍亞、龍可。あなた達はちゃんと信じてる?」 「……何を?」 「自分自身をよ」 アキがきっぱりと言った。 「誰より自分を愛してあげなさい。自分を捨て石みたいに扱ったら、私は絶対にそれを許さないから。遊星が仕方ないと言っても、ジャックが諦めろと言っても、クロウがどうしようもないって首を振っても、ブルーノが仕方ないんだって零してもよ。それにね、私は信じてるの。十代とアンデルセン博士はきっと最後には遊星も――世界中の全てを巻き込んで、全部救いにきてしまうのよ」 両腕で双子を包み込んだ。アキの後れ毛が頭に当たって、くすぐったい。 「……ありがとう」 「もう行くの?」 「……うん。パパとママに、まだちゃんと何も伝えられてないから……行かなきゃ。アキ姉ちゃん、それから遊星、ジャック、クロウ、ブルーノも」 「あ……ああ」 「『ちょっと』出かけてくるよ」 「そう、わかったわ」 アキが手を振るとつられたようにブルーノも手を振った。遊星は仁王立ちでそれを見守り、クロウは「仕方のない弟達だな」というふうに双子を見ている。本当のことを言うと、龍亞は十代とヨハンにつくことを決めた時に「裏切り者」と罵られることさえ覚悟していたから(遊星のヨハンの嫌いようは、あれは嘘じゃない。本当の本物だ)それは拍子抜けしてしまいそうなぐらいに、穏やかな光景に見えた。 可能性は一つじゃないということを思う。この世界は確かに、イリアステルによって歪に歪められた世界だけど、もしかしたらひょっとして――全部丸く上手く納めてしまえることだって、あり得ないわけじゃないんじゃないか? 「ねぇ龍可、ブルーノのことさ、ほんとに言わなくてよかったの?」 普通に、和やかに、いつもみたいに見送られてポッポタイムを後にして帰り路を歩きながら龍亞はそれを尋ねた。それは最初に、ポッポタイムに戻る道すがら龍可が言い出したことだ。「ブルーノが本当は《イリアステル》のアンドロイドであるアンチノミーであるはずだ」ということは、この場では彼らに伏せておこうと龍可は提案した。 「確かに、今言ったら皆殊更混乱して、下手したら仲間割れみたいなことになっちゃうかもしれないけど」 「それもあるんだけどね。なんとなく、ブルーノのことってすごくデリケートな問題だと思うの。あれは多分遊星が何とかしないといけないことだわ。私達が軽々しく手を出しちゃいけないんだと思う」 「ふーん? そういうもんなのかなぁ……」 「多分ね」 あまり歯切れのよくない調子で龍可がそんなふうに締めた。 ◇◆◇◆◇ 水底の、気怠く生暖かく、優しい羊水のようなぬかるみを肌に感じて遊城十代は目を覚ました。知らない風景が視界いっぱいに広がっている。アクアリウムのガラス製空中ドームみたいな水の天井の上に、僅かに差す日の光と無数の魚達が泳ぎ回るのが人間を超越した眼球に視認出来た。深海生物達が我が物顔で闊歩している。 「起きたか」 世界中で一番にやさしくて、一番に厳しく、一番頼りになって、一番愛している声が耳に舞い降りてきた。ヨハン・アンデルセン。遊城十代が悪魔の呪いで地に縛り付けた彼の唯一神。 「……起きた」 「気分は? 優れないのなら、無理しないでいい。どうせここは正しい時の流れから外れた場所だから、時間は無限にある」 「いや、大丈夫。ちょっと、あの子の感情と記憶が重たいけど……」 「ああ」 「起きられるよ」 悪魔ユベルの喪われていた能力が全て戻ってきている。精霊能力も再生能力にも問題は見られない。記憶の方も完璧だ。《ルルイエの聖女》のレコードも含めて完全に思い出した。 大丈夫だ。もう一度立ち上がって歩き出せる。 「……もしかして、ユベルの部分を取り戻した時……」 「そ。全部一緒に流れてきた。あの子は自分のことを作り物の、出来損ないの人形だって言ったけど……それは確かに真実なんだけど、ちゃんと悲しむことと喜ぶことを知っていた。誰かを愛することも。女としてヨハンに焦がれ、母親としてルチアーノを愛してた……」 「ルチアーノ?」 「そう。ルチアーノだよ。これはかなり大きな情報アドバンテージだ。ルチアーノがどういうふうに『正史と違う』のか、その仕様調整をしたあの子は知ってた。だから今ならそれが俺にもわかる。――ルチアーノは、ユベルの力を持っている」 のろのろと起き上がり、両手のひらを開いて、海底都市ルルイエを見渡した。オレイカルコスの呪縛を受けた呪われた邪神の眠る都市群。その時空の狂った空間で、実働何千年になるかもわからない時を過ごすことを余儀なくされた機械人形のメモリーが随分と重たい。心のないアンドロイドが本当の意味で人を愛するようになるぐらい、ずっと、彼女はここで誰かを待っていた。 ヨハン・アンデルセンという会ったこともない偶像を? それは確かに真実の一端だ。本物の遊城十代から引き継いだ記憶の中にあるヨハンという男に彼女は神性を見出し崇拝していた。アイドルに憧れる女子中学生みたいに。 だけど彼女はそれ以上に、プラント機能の唯一の成功作であるルチアーノを溺愛し、また、偽りの造物主であるゾーンを恐れていた。 「ゾーンに壊されるぐらいなら、ヨハンに殺されたかったんだ。根底にある考えは自殺志願者と同じだけど……それって恐ろしいことじゃないか? 機械人形が自殺志願するなんて。でも同時にルチアーノを残していくことも気に病んでた。ルチアーノが救われないことを」 「母性愛か」 「そう。俺が龍亞と龍可のことが心配なのと何も変わらない。なあ、ヨハン。俺達はこれから遊星達のいるあの場所に行くだろう?」 「ああ。多少出遅れてしまったが、イリアステルの攻撃も始まっているし、そろそろ軌道修正に本腰入れないとな」 「俺は、その中でイリアステルも救いたい。せめてルチアーノだけでも……ただ壊すのは簡単だ。暴力で平定するのは簡単。だけど、そうじゃいけないんだと思う」 久方ぶりに見た雌雄同体の体。悪魔ユベルの魂と融合し、純粋な人ではなくなってしまった自分をそれでも皆変わりなく受け入れてくれた。ルルイエの聖女にはそれがなかった。ルチアーノにも。聖女はこの地における見せしめのモニュメントだった。 機械人形だから、人じゃないから、構わない。倫理にもとる非道を気が狂うほどの長い間強いられた彼女はどんな気持ちでそれを言ったのだろう。きっと本心だったのだろう。嘘偽りのない。 嘘吐きのプログラムを組み込まれていない機械人形は嘘が吐けない。 「遊星になんて説明しようかなぁ」 「ああ。遊星くん、十代に随分ご執心だったから」 「何だよ、余裕じゃんヨハン」 「ちっともさ。じゃなきゃ十代に酒を盛ったり口実付けて家に連れ込んだりなんかするもんか」 「おまえあれ確信犯だったのか」 「そりゃあね」 実に人間くさくヨハンが首を振った。ルビーがヨハンの肩の上で申し訳無さそうな顔をしている。ハネクリボーが、それに近寄って「似たもの同士だから」と首を振る。 「いつでも君が帰ってこれるようにして、五年間待ってた。気が長いんですねって不動に言われたけど、十代のためなら百年でも二百年でも俺は待ったよ」 「……赤いエプロン、割と、好きだったよ」 「どうも」 照れ隠しをするようにふいと顔を背けてそう言い捨てるとヨハンはとても優しい顔で笑った。 ルルイエの聖女が磔にされていた十字架を最後に仰ぎ見る。あの高い場所に括りつけられ、剥き出しのボディを晒して崇拝されていた少女の幻影がまだ、見える気がした。右も左もわからない生まれたばかりの少女をああして辱めるように安置し、祈る神の出来損ないとして扱う。吐き気がする。それが悲しんでいいことだと教えられなかった彼女は最後まで自分を哀れだとは思わなかった。 或いは、哀れだと、認めたくなかったのかもしれない。 「ゾーンは二人いるよ」 十代は胸に手を当てて絞り出すように言った。 「そして、俺達を送り出した方じゃない――あの子を作り、歴史を歪めようとしているそいつは、狂ってる」 ◇◆◇◆◇ 放心しきったという表情で、何から受け止めていいのか、何から受け入れなければいけないのかわからない、と遊星は首を振った。双子の話に一番戸惑っているのは間違いなく遊星で、逆に一番最初に適応したのはアキだった。 「龍亞と龍可は意味のない嘘を吐くような子じゃないわ。それで大体合点がいくもの。それに遊星、あなたまるで二人に今生の別れを言い渡されたみたいな顔をしているけれど、別にそういうことじゃないでしょう?」 アキは澄まし顔だ。ジャックが息を吐き、クロウも肩を竦める。「意気地なしなのね」アキが横目で言った。「遊星、あなたはそんなに怖いの?」 「……アキが落ち着きすぎているんだ」 「なんとなくこんなふうになるんじゃないかって、十代が来た時からずっとわかってたわ」 遊星の泣き言みたいな声をとりつく島もなく一刀両断する。「みんなもう少し落ち着いた方がいいわよ」腕組みをして、宥めるように言うと紅茶のポットを手に取った。入りっぱなしの冷え切った茶葉を捨てて新しいパッケージを開封する。カモミールとマリーゴールドのブレンド。 「そんな世界の終わりみたいな顔をして」 「……実際、龍亞の説明じゃあよ、そういうことになるんじゃないのか?」 「それは、ちょっと早計に過ぎると私は思ってる」 とぽとぽと規則的な音を立てて五つのマグに注がれていく透き通った液体を朧に見ながら遊星はアキとクロウの遣り取りを聞いていた。透明な黄色の、カモミールブレンドのハーブティー。昔もこの茶を振る舞われたことがある。遊星が十六歳になったばかりの時に父に呼び出されて訪れた海馬コーポレーションの応接室で、確か。 綺麗な女性社員が、「ご子息の口にはちょっと合わないかしら」と困ったような顔をして出してくれたことを覚えている。遊星の父が仕事疲れが出てきた頃に好んで煎れてもらうものなのだとその時彼女は言っていた。口にすると、苦かった。父はそんな遊星を見て静かに手招きをする。「煮詰まってきた時とか、これを飲むとちょっといい感じになるんだ。さあ遊星、こっちへおいで。渡したいものがある」 父に手を引かれるようにして、酷く巨大で、厳重な金庫室の前に連れてこられた。予想だにしなかった光景に驚いて、父に尋ねる。これはなんだ。何故、俺が、こんな場所に。 「さあ、それは私も知らないんだ。言伝なんだよ。遊星が十六になったら、この中にあるものをきみに渡すようにとね」 「一体誰がそんなことを?」 「それなんだけどね……私も、その名を聞いた時は酷く驚いたものだ。何せ理論が通らない。だけど本当だ」 父がパネルに指を滑らせて、長ったらしい暗証番号をすらすらと入力していく。「遊星、指紋認証するから指を出して」そう言われて右手を機械に差し出す。最終アンロックを通達する電子音。重々しい音がして、鉄の扉がギィ……と開いた。 「中に箱があるだろう。取って」 「あ……ああ」 言われるままに伸ばした先の箱は、小さく、頑丈で、とても重かった。奇妙な形をした黄金の箱だ。中央に目玉のシンボルが描かれていて、確かこれはエジプト美術を習った時に目にしたウィジャト眼のシンボルだったはずだ、と思う。あの真贋を司る。 「これは……」 「≪封印の黄金櫃≫、という名らしい。ほら、カードにもあるだろう。あれのモデルの本物だそうだ。詳しいことは一緒に付いてる手紙を見るといいよ。父さんもそれ以上は知らされていない。これは『遊星だけが』手にすることを許され、『必ず遊星が』蓋を開ける日が来るものなのだと」 父に言われて初めて手紙が添えられていたことに気がついた。手にとって開封する。几帳面な、古くさいインクの匂いがする手書きの書面だ。 「『不動遊星へ……』」 ――この手紙を貴様が無事に読めているということは、我が社は変わりなく世界の頂点に君臨しているということだろう。流石は我がKCだ。さて、本題だが、オレは遊戯の代理で貴様にこうして文をしたためてやっている。感謝しろ。別に遊戯に弱みを握られたわけではない。 それは≪黄金の封印櫃≫だ。武藤遊戯の私有品になる。レプリカなどではない紛れのない本物だ。遊戯が死に際の遺言にそれを『絶対に』貴様に遺し、手に渡るようにとオレに懇願して来たのでオレはそのように取り計らってやった。 正直オレとしては、まだ生まれてもいない人間のことを名指しで指定するなど正気の沙汰ではないと思うが……イシズが未来視したのに加えて確かな確証があるなどと抜かすので遊戯の計算では不動遊星とかいう子供が、我が社の関係者としてそのうち生まれることになっているらしい。まあ、知ったことではない。だが、オレとしてもこの封印櫃は遊戯の望む人間以外の手に渡るべきではないと考えこのように厳重な保管方法を取った。盗人に盗まれでもしたらたまったものではないからな。重ねて感謝しろ。 遊戯からの伝言で、最後にもう一つだ。その箱は、『その時が来るまでは開けるな』。これは絶対だ、とあのお人好しが珍しく強く言い切った。逆らわない方が賢明だろうな。尤も、その時が来るまでは開かないだろうとも言っていたが。 その時が、どういった有事なのかはオレにはわからん。聞くな。ただ、『まるで世界が終わってしまいそうな時』だとかそんなよくわからんことを遊戯は言っていた。フン、馬鹿馬鹿しい。我がKCある限り世界など滅びん。終末論崇拝者め。 そういうわけで、貴様は武藤遊戯より封印櫃を託された。その後は好きにしろ。オレはそこまでは任されていない。捨てられるものなら捨てるもいい。煮るなり焼くなりどうとでもするんだな。 海馬瀬人―― 「……海馬……瀬人……? あの、青眼の白龍使いの?」 「そう、軍需産業から手を引いた後の海馬コーポレーションの初代会長の海馬瀬人その人からの直筆だ。その手紙だけで軽く億単位の値段が付くだろうけど……まあ、そんなことはどうでもいいね。手紙に何て書いてあったのか私は知らないけど、封印櫃も、手紙も、大事にしておきなさい。そういうのは得てしていつか必要な時が来るものだ」 「必要な」 「縁の巡り合わせってやつだね。それを海馬会長が遊星に託すのに意味がないとは私は思えない」 父は悪戯っ子のように唇に人差し指を添えてそう言った。まるで運命の話をする魔法使いみたいに。 「……世界の終わり、か」 「なんだ遊星、口を開いたと思えばお前までクロウに同調するのか」 「いや……心当たりと言うべきか、今、必要なものを思い出したんだ。世界が終わってしまいそうな時に、と渡された箱なんだが。ずっと忘れていたんだが、今急にそのことを思い出して……」 「へ? オカルトか何か?」 「わからない。……確か部屋の奥に置いてあったはずだから……取ってくる。アキ、少し時間がかかるかもしれないから俺の分は後にしておいてくれ」 「え、ええ。わかったわ」 言うなり足早に立ち上がって、自室へ駆け込んだ。 手放してはいけないと思って、引っ越した時確かにここに持ってきたはずだ。クローゼットの奥だったろうか。それとも、戸棚の最下層? どこだろう。どこだっただろうか。絶対に汚れないように、壊れないように、傷がつかないように、かなり厳重に保管していた。 心当たりのある場所を片端からひっくり返して、部屋が汚れることさえ気にせずにどかどかと放り投げるように私物の山を漁る。普段の遊星ならとても考えられないが、今は一刻も早くそれを見つけるのが先だと思ったのだ。 やがて綺麗に整理整頓されていたはずの部屋がまるで引っ越し直後のように足の踏み場もない状態になり、ようやくのことでそれは姿を現した。白いプラスチックのケースに南京錠が取り付けられている。鍵がどこにあるのかもう思い出せなかったので万能キーでそれを強引に解錠し、手紙と封印櫃を手に取ると勢いよく部屋を飛び出し、ガレージに戻った。 「遊星?! どうしたの、そんなに慌てて、危ないよ……?!」 ブルーノの制止の声を無視して、中央のテーブルにドンとそれを置く。「何だそれ。なんかエジプト財宝のレプリカ?」クロウが尋ねた。 「っつか……まさか……本物?」 「本物だ。百年前の……≪決闘王≫武藤遊戯の私物で、海馬瀬人を経由して数年前俺が譲り受けた。非常に不思議なことに、添えられていた手紙にはまだ生まれてもいなかった俺の名前が一字一句違わず記されていて……そして、『世界が終わってしまいそうな時に』開けるようにと、そこには書いてあった」 「はあ?」 「だから……その……だな」 これ以上言葉にして説明するのが面倒になって、尻切れの言葉を吐いて封印櫃の蓋に手をかける。実を言うと、十七歳の時に一度堪えきれず開封を試みたことがあったのだ。だがびくともしなかった。確かにその時、終末の兆しなんてものはどこにもなかった。 今は開けられるような気がする。いいや、開けなければいけないのだとさえ。 「おい遊星、まさかお前ここで開ける気か?!」 「ああ」 声を出すのももどかしくて返答は自然と素っ気ないものになった。重たい純金製の蓋が、遊星の手の動きに合わせてずれていく。開いた。やはり今は、『しかるべき時』なのか。 蓋が完全に本体から離れて、中身が姿を現すのにそう時間はかからなかった。中には逆三角の、これもやはり黄金色をした物体が入っている。長いチェーンが繋がっていて、その場の誰もが息を呑んだ。 「こりゃ……とんでもねえもんが出てきたぞ」 「俺の記憶が正しければだが。それは確か……」 「俺もそう思う。遊戯さんが、付けていた……」 手にとって、特に深く考えることなく首にかける。重たく、堅く、冷たい。遊星は、いや、この世界の殆どの人間がその奇妙なアクセサリーの名前を知っている。 ≪千年パズル≫。決闘王武藤遊戯が常に首から提げ、肌身離すことのなかったという、彼のシンボルだ。 「だが……何故こんなものが……ッ?!」 重みを確認してそれを首から外そうと思った時、突如閃光が走り、遊星は反射的に目を瞑った。 眩しさに耐え、恐る恐る目を開く。まだ視界が白んでいて、目が慣れていない。その中に形成されていく一つのシルエットがあって、遊星は言葉を失った。特徴的なシルエットだ。紅葉のような頭に、黒い革のボンテージ・ファッション。だが足がない。透けている。生きた人間では、ない。 では何なのだ。何が、遊星の前に姿を現そうとしているのだ? 『――やあ、遊星。きっとまたキミに会うことが出来ると信じていたぜ』 そうして、振り向いた彼は紫のような、紅のような瞳で遊星を認めるとにこりと笑ってそう言った。 |