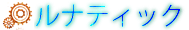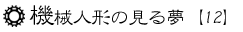『きっとまたきみに会えると信じていたぜ。きみとの再会を心待ちにしていたんだ。あぁ、といっても、オレにとっては再会だがきみからしてみれば初対面か。オレのことは?』 「……知って、ます。《決闘王》武藤遊戯」 『正しくは、それは相棒の名前であってオレを指し示す言葉じゃないんだがな。オレは名なしの幽霊さ。だから相棒の名を借りている。今までも……多分、これからしばらくも。……オレのことをかつて預言者の女はこう呼んだよ。《名もなきファラオ》、と』 名もなきファラオを自称し、武藤遊戯の姿をした幽霊は屈託なく笑った。一体、何がどうなっているのだ? わからない。この幽霊は、何故、パズルの中から。 『簡単なことさ。オレはこの千年パズルの中で眠っていた。パズルの精霊と思ってくれても構わないぜ。殆ど、お伽噺のランプの魔神と変わらないからな。尤も願いを三つ叶えるといったようなことは出来ないが――』 「な、なんですか……」 『きみの手助けなら出来る。いくらでもな、遊星』 遊戯の幽霊が手を差し出す。半透明で、きっと触れたら通り抜けてしまうだろうと傍目からも思われたけれど遊星はそれに手を伸ばした。掴むと、すかすかとやっぱり通り抜けてしまったけれど、それでよかった。 『よろしくな』遊戯が言う。有無を言わせぬ、為政者のような重みのある言葉だ。その場に居合わせた遊星以外の人間は、それに異を唱えることも賛同することも出来ずにただ黙って彼らを見ていなければならなかった。遊戯の、言外のオーラのようなものが彼らをそうさせていた。 『オレが呼び出されたってことは、きっと今にも世界が終わりそうな、そういう危機に直面しているんだろう。そういう決まりだったからな。本当は、オレのことをパズルから呼び出せるのは相棒だけなんだ。千年に一人の魂の巡り合わせだった。だけどそれじゃ、オレは頼まれた役目を果たせない。それで相棒が設けた制約がそれだ。遊星、キミはどのくらい話を聞いている?』 「え、あの、いや……まったく。海馬社長からの手紙で、世界の危機に開く、とはありました、けど。だから俺は……」 『なるほどな……海馬め、相も変わらず説明がヘタクソだ』 「説明」 『ああ。とはいえオレもさして上手いわけじゃない。むしろ、下手な方だ。だがなんとか聞き取って欲しい。それがオレが約束した第一の役割』 遊戯の目つきが険しく、鋭くなる。彼はそうしてすぅと人差し指を出し、遊星を指し示すと厳かに唇を開いた。 『――きみとだ、不動遊星。オレは百年前にパラレル・ワールドからやってきた二十五歳の不動遊星から頼まれた、メッセンジャーとしてきみを待っていた』 ◇◆◇◆◇ 二十五歳の不動遊星が住んでいた世界。英雄が世界を救い続けてきた、理論上「もっとも整合性がとれた、一番に正しい世界」であったはずのその世界は、ある日突然、一切の前触れなく崩壊した。不可抗力の、酷く強大な某かの力によるそれは侵攻だった。 世界は滅亡した。音もなく忍び寄り、子供が蟻を踏み潰すような気軽さで、内緒話をする時にそっと人差し指を唇に添えるように静かに滅んだ。不動遊星が守りたかった世界は、その遊星をこそ嘲笑うかのように、まったく手が届かない未知の場所で終わってしまったのだ。 その後は暗黒だった。救いのない暗闇だ。どれだけ広いのか或いは狭いのかもわからない世界で、不動遊星は独りだった。意識を苛む孤独。しかし気が狂うようなその中にやがて光が差し、男の声で遊星に事実を告げる。 『あなたを起点として歴史の改竄が開始されている。そこを脱してターニング・ポイントへ向かってください。あなたなら出来るはずだ。……時間がないのです。私を信用してくれますか、正史の英雄よ――私はあなたとは別のパラレル・ワールドに存在するZ‐ONE。あなたに焦がれた愚かな科学者の、また別の末路です』 遊星は彼を信用した。信用する他に、道はなかった。 そうして不動遊星は赤き龍の力を借り、必然に導かれてある時空へと流れ着く。それが歴史が歪められたこの世界の童実野町。《ゼロ・リバースのない世界》で、英雄因子の因果に導かれ《武藤遊戯》《名もなきファラオ》《遊城十代》《不動遊星》が一堂に会することとなった《パラドックス》との決戦場だったのだ。 『パラドックスは、歴史を改竄し、オレ達を亡き者にすることを目的として現れたようだった。どうもオレ達が邪魔だったらしい。ヤツは確か、歴史の伸縮特性がどうたらとか言ってたな。よくわからないが、オレ達の存在が歪められた歴史を元通りにしようとする働きに関与しているようだった。――つまり、オレ達が揃っていれば歴史は今からでも元に戻せる可能性があるということだ。歴史の改竄については、流石にもう、知ってるだろ』 「あ……はい。龍亞が……俺達の仲間の、子供が。パラレル・ワールドでの記憶を思い出したって。この世界に《ゼロ・リバース》がないのは、明らかに、不自然だって」 『ほお? その子供、何者だ?』 「……《向こう》では十代さんを親に持っていたって」 『ああ、十代の。あいつも因果の特異点の一人だったな、確かに』 「この世界での十代さんをご存じなんですか」 『オレの弟子だ。知らないはずがないだろう。明るく、いい子だが、影があまりにもなくて、少し不安になるような子でもあった。もう、死んだろうがな。相棒が死に、オレがパズルに引っ込んだ頃には十代も随分年を取って老いてしまっていた』 遊戯が懐かしむように言う。彼の言う「遊城十代」は、つまり、空から落ちてきた記憶喪失の彼ではなく、教科書やデュエルチャンピオン・レコードに載っている方の「遊城十代」なのだろう。遊星が生まれてくるとっくの昔に亡くなっている方の彼だ。遊星の知らないヒーロー使い。 では、遊星があの日抱き止めてチームの皆と暮らしていた彼は一体どこから現れたのだ? 『さて、そのパラドックスは遊星言うところの《イリアステル》の一人だったわけだが、その遊星が知っていた組織とは随分様変わりしてしまっていたようだった。遊星はイリアステルを指して『今は《ヴェルズ》と呼んだ方が正しいかもしれない』と言っていたな。ヴェルズ――オレにはそれが何を示すのかよくわからないが』 「……カードのカテゴリのことではないのか。ここ十年の間に登場したシンクロモンスター達を主軸とするカテゴリだ。決闘王、貴方が知らないのも無理はない」 『ああ、シンクロ、か。オレも遊星がデュエルで見せたものしか知らないな。そうか、それはこの時代でポピュラーになる新しい形式なんだな。では、ヴェルズカテゴリに何か特徴はないか? ええと……』 「ジャック。俺の名はジャック・アトラスだ。ヴェルズだが、この特徴というべきか、テーマは『他カテゴリの侵食』だったはず。代表的なのは……」 「《ヴェルズ・オピオン》、《ヴェルズ・バハムート》、《ヴェルズ・ウロボロス》。そのどれもが《氷結界の三龍》がヴェルズ化した、というバックグラウンドストーリーに基づいていて……まさか……そういうことなのか?」 ジャックの後を継いでモンスターの名前を挙げてから、遊星がはっとしたように呟く。それらに当てはめられる法則性が、奇妙な形で遊戯の説明に合致したのだ。 ――かつて氷結界の一族という禁断の力を求めた呪術一族があり、彼らがその力として得たものの制御出来ずに暴走した、というストーリーを与えられていたのが氷結界の三龍である。それら《ブリューナク》《トリシューラ》《グングニール》は後にヴェルズに取り込まれ、それぞれ《オピオン》《ウロボロス》《バハムート》になったとされている。 それに基づいて考えれば、《イリアステル》が《ヴェルズ》になったというのは、つまり…… 視線で訴えると遊戯が静かに頷いた。 『ああ、きみの考えた通りだろうとオレも思う。パラドックス自身、自らのことを《オピオン》に例えていたからな。何らかの原因があり、彼らは突如歴史を改竄するための行動に出た。その元となった出来事が何なのかはわからないが。奴らを放っておけば、歴史は悉く書き換わり、歪められ、正しかったものは消え失せ最後には全てが滅ぶだろう。きみ達は、ヴェルズの物語の最後を知っているか?』 「ええと……確か、ヴェルズの侵攻により世界が滅亡の危機に瀕したので、天から《セイクリッド》が降臨して全面戦争を行い、最終的に創世神ソフィアの調停により活動を休止した、っていう内容だったと思うわ」 『なるほど。創世神なんて都合のいいものが現れない以上、オレ達でどうにかするしかないというわけか。パラレル・ワールドからの使者であるオレはさしずめセイクリッドに相当する立ち位置、ってことだな。あんまりオレは、正義の味方ってがらでもないんだがな』 遊戯が首を振った。 とんでもない話だ、と遊星は考える。なんて規模の話なのだ。世界をいくつも巻き込んで、時間を数百年も、いやひょっとすると数千年、数億年も股にかけて数え切れない数の人々を……生命を巻き込んで、それを成就しようとする。世界規模のエゴイズム。イリアステルの、いいや、ヴェルズの盟主はそれによって何を得たくて、そんな荒唐無稽なことに手を染めてしまったのだ? そうまでして、それでも手に入らないものとは、何なのだ。 ふと、十代の姿が脳裏を過ぎる。遊城十代。あの強く美しい人。あの人は、ヨハン・アンデルセンを選んだあの人は、不動遊星にとってはそのぐらい遠く手に入らないひとなのだろうというぼんやりした空想。 だけど遊星には、そんなことをしてまで遊城十代が欲しいとは思えない。それはそれで、敗北は敗北で、受け止めねばいけないものだ。 それに十代には憧れているけれども、焦がれているけれども、手に入れて何をするというのだろう。あの人はそういう人ではないのだ。鳥籠に閉じ込めておける金糸雀ではない。あの人は、そんなものは全てぶち壊して、もっと遠くへ行ってしまうだろう。 『きっとね、彼はいずれ遊星の前から姿を消すよ』。父親に言われたあの怜悧な一言がぶり返した。不動遊星はその時、心のどこかで、遊城十代を「諦めて」しまった。 だが、もしも。もしも、ヨハン・アンデルセンを前にしても、遊城十代に否定されても、それを諦めきることが出来なかったのだとしたら。 そしてそこに「運悪く」何かの要因が重なり、実行出来るだけの力が与えられていたら? ジャックが遊星を一瞥して、それから遊戯に向き直った。遊戯がそれに気がついて『何か?』と腕組みをしたまま尋ねる。 『聞きたいことがあるって顔だな』 「……ああ。武藤遊戯。貴方が見た、遊星の扱ったシンクロモンスターとは、一体何だ?」 『……それがどうかしたのか?』 「いや……歴史が変わっている、と貴方は散々繰り返していただろう。それならば、そのモンスター自身も、こちらの世界とあちらの世界では、違うのではないかと。もしそれが必要だったら、どうするんだ」 『さあな。そういうのは、大抵、その時なるようになるものさ』 飄々としてつかみ所のない声で、肩を竦める。事実彼は今までずっと、大抵のことを「必要な時になるようにして」きたのだろう。そういう無意識の自信の裏付けにも思えた。歴史が少し変わっていたところで、やはり武藤遊戯は、《英雄》に他ならないのか。 では遊城十代も? ……不動遊星も? 遊戯が口を開く。 『――それじゃ教えてやるが、オレが覚えている遊星のモンスターは一体だけだ。そいつは一目で『普通じゃない』ってわかるような、とんでもないモンスターだった。味方でなかったら、と今思い出してもそう感じる。名前は《シューティング・クェーサー・ドラゴン》。光属性、ドラゴン族、そしてオレの神のカードすらも超越した十二というレベルを持つ超上級モンスターだ』 そして遊戯は、遊星もジャックもクロウもアキも、ブルーノも知らない、初めて耳にするモンスターの名前をごく当たり前に口にした。 この時代の不動遊星が扱うドラゴン族のシンクロモンスターは、《スターダスト・ドラゴン》ただ一枚きりなのだ。 ◇◆◇◆◇ 海浜公園の高台の広場のところに急いで戻ると、やはり、あの二人はそこにいた。遊城十代とヨハン・アンデルセン。私達の大切な両親、二人揃っていつも世界を守ってきたヒーロー達は、私と龍亞の姿を認めて手を振る。 ママがもう、いつもの、あの全部全部ぶち壊して、強引にでも皆を助けてくれるあの力強い人で、遊星やブルーノ達と一緒に暮らしていた「記憶喪失の遊城十代」ではないのだということを私はその姿で知った。半人半精の特異性ゆえにもたらされる修復能力と、精霊《ユベル》との融合で変化した雌雄同体のシルエットは、シティのカフェで男物の制服を着てウェイターをやっていた頃の彼には見られない、不可思議な姿だった。 だけど私にとっては見慣れた姿だ。向こうの世界の私達は、あの身体をしたママのお腹から生まれてきた。 「子供がこんな時間に出歩くもんじゃないぞ」 シニカルなママの声。「でも、多分、わかってて来てるんだよな」とちょっと諦めたふうな言葉が続く。私達が駆け寄ると、ちゃんと抱き止めてくれる。温かい。ポッポタイムのガレージで三人してひっついて、ブルーノに「熊の親子みたいだね」と言われたのを思い出す。 「私……わたし……パパとママが元気そうで、ちゃんとそこに立ってて、よかったって……。ルチアーノが。二人を、海に沈めて、それがすごく、怖くて……」 「うん」 「またいなくなっちゃうんじゃないかって思った」 「うん」 「もうどこにも行かない?」 「一応そのつもり」 ママが笑ってそう答えると、パパも笑った。龍亞も、半泣きになりながら笑っている。二人はいつだって世界を救ってきたし、いつだって私達のところへ最後は帰ってきてくれたけど、でもやっぱり、怖かったのだ。 ルチアーノのあんな表情を、私達は知らなかった。私の知っているルチアーノも大概すごい顔をしていたけれど、それでも初めて見る、強い憎悪と深い悲しみと、絶望、そして悪意と敵意がそこにはあった。 あの子は、きっと世界が大っ嫌いなのだ。自分ごと壊してしまいたいと思えるぐらいに。 あの子は世界中全てを敵に回して、そうして、何をしたいのだろうか。 ママの手が私の髪を梳く。 「あの子は、本質では……龍亞と龍可と……普通の子供と一緒なんだ。母親に焦がれてる。結局のところ、それだけなのに、でも機械人形だったから。ゾーンに造られたアンドロイドだったから、あんなふうにもがいて苦しそうな顔をするんだ」 「ママは何か知ってるの?」 「俺じゃなくて、あの子の母親がさ。全部知ってたよ。――海底都市に、ゾーンが造った存在しないはずのアンドロイドがもう一体いたんだ。そいつは俺から抜き取ったユベルの力を核にした《遊城十代のコピー》だった。それが、今のルチアーノにとっての母親。だけどそこで《聖女》として趣味悪く祀られていたあの子はヨハンに壊して貰いたがったから」 「ああ。きっと死に物狂いで俺達を襲ってくるぞ。それこそ命を賭して。きっとあの子は今、そのためなら全然壊れたっていいって、そう思っているよ」 パパも龍亞の背中を撫でながらそんなことを言った。私はすぐにその言葉の意味を飲み込めずに、え、どうして、と思考を停止させてしまう。 ママのコピー? アンドロイド? それってどういうこと? また、ママがよくないことに使われていたってこと? ママが。昔みたいに? 私達のパパとママは、半分が人間で半分が精霊。普通の人間よりずっと強いし、ずっと長い時を生きる。ありふれた人間の私達が向こうの世界で寿命を迎えて死んだ時も二人はまだ三十にさしかかるかもっと若いかぐらいの姿で、私達を見送った。そういう普通じゃない人達だから、昔から悪いことに狙われてきた。一度、二人が五年間もの長い間帰ってこなくなったことがある。丁度向こうの世界で、遊星達と出会ったりシグナーとして戦っていた頃のことだ。 二人が帰って来なかったのは、つがいの実験動物として研究所に拘束されていたからだったということを、私達は後になって知った。 それも、私達を守るために、だ。 「……またママが、酷い目に遭ったの?」 龍亞が私の代わりに、口を開いた。私達はいつも一緒。いつも、同じことのために怒ったり、悲しんだりする。 だけどママは首を振った。そんなことないよって、私のおでこにキスをした。 「俺は大丈夫。ずっと遊星達の所にいただろう? 俺自身は、全然どってことないんだ。大丈夫。そんな顔するもんじゃない。……だけどあの子の母親は、本当に酷い目に遭わされていた、と俺ですら思うよ。あの子は自分がどのくらいの長い時間あの呪われた都市で磔にされていたのか、機械として道具として扱われていたのか知らないんだ。自分が不幸だということを自覚出来なかったのが、プログラムされていた唯一の救いだった。なあ龍亞、龍可、二人は龍亞を傷つけて罵ったルチアーノを許せないかもしれない。だけど母さんは、ルチアーノは誰かに愛されてもいいはずだって、そう思う。あの子の本当の母親はもうどこにもいないけれど。……それって、やっぱ、いけないことかな。俺のいつもの悪い癖かなぁ……」 躊躇いがちにそう尋ねる。ママの悪い癖。それは、色んなことを自分の責任だとか、自分がどうにかしなきゃいけないことだって背負い込んでいってしまうことだ。ママは何でもかんでも抱え込みたがるくせに、人間だから、何でもかんでも抱え込んで平気な顔をしていられるわけじゃない。あんまりそれをやりすぎると、だめになってしまうんだって昔パパがそう言っていた。ママは、そうやって自分を殺してしまったことがあるって。 だけどそれがママの美徳でもあることを私達家族は皆知っている。美しく脆い硝子の城。私はママのそういう完全にはなれないところを愛していたし、それはパパも龍亞も一緒だ。 「そうね。ママの悪い癖よ。……だけどいけないことだとは思わないわ。ねえママ、ママは、きっとそのママのコピーのアンドロイドが見たものを、全部、知ってしまったのね」 「ああ」 確認したらやっぱり頷いた。優しいママ。私達の両親は、何度も裏切られてきたこの世界を、だけどやっぱり、愛している。 「ユベルを回収する時にセットで記憶もついてきた。機械人形で、偽物だったけど、子供のルチアーノを心底愛していたし、ヨハンを愛していた。俺みたいに。俺と一緒だった。……なんにも変わらないんだ。母親は、ただ、子供を守りたいだけ。けれどゼンマイ仕掛けのアンドロイドだったから」 ママの手が、震えているのがわかった。 パパが壊したっていうアンドロイドは、本当の意味では死なないで、ママの中で眠っているのだと私にはそう思えた。ルチアーノが欲しいのは私達のママじゃない。だから、彼女を棄てたり殺すことがパパにもママにも出来なかったんだろう。そのためにママは彼女を自分の中に受け入れたんだ。ユベルにそうしてあげたみたいに。 「みんな幸せになりたいだけなのに、どうしてすれ違ってしまうんだろうな」 ママがぽつりと呟いた。私達の誰も、その答えを持ち合わせてはいない。 ふと思い立って見ると、海浜公園のすぐ隣の海の上にもうカモメは飛んでいなかった。街頭があちこちに灯って、シティには珍しく星がぽつぽつと見えている。「二人は、もう帰りなさい」とパパが言った。高台の広間の時計塔を慌てて見ると、九時を過ぎている。 「こんなに遅くなって、親を心配させるのはよくないことだ」 「……やっぱりばらばらに帰らないと駄目?」 「やっぱり、知らない男の家に上がらせるのはちょっとなあ。親は普通、そういうのをよく思わないもんだ。俺と十代が今からポッポタイムに行ったりなんかしたら間違いなく大変なことになるし」 「ああ、遊星今すっごい混乱してるもんなぁ。パパの顔見たら、わけもわからないまま突進してきそう。そうだよ。ママ、遊星のことどうするわけ?」 「どうするって……俺はずっと遊星のことは頼もしい後輩だと思ってるぞ。だからさ、やっぱ遊星にはとりあえずヨハンと和解してもらって……」 「そこからなんだ……」 「……そんで、一緒に戦えたらいいなあとは思うけど。でもどうするかは遊星の決めることだし。もし遊星が俺を止めるって言うのなら、俺は全力でそれを蹴散らしていくよ」 「うん。ママらしいや」 うんうん龍亞が頷く。ママとママの操るヒーロー達は、どんな雑魚相手でも、親しい人相手でも、それが私達相手でもデュエルとなると決して手加減も情け容赦もしない。頼もしいけど苛烈だ。 スターダスト・ドラゴンから先のシンクロ・モンスターを持っていないシグナーではない遊星では、とても本気のママには太刀打ち出来ないだろう。何しろ、シューティング・クェーサー・ドラゴンを持っていた遊星だってママには一度も勝てたことがなかったのだ。 「そういうわけで母さんはしばらく父さんのとこにいるよ。だから二人はちゃんとトップスの家に帰ること。帰る場所があるってのは、本当に素敵なことだ。いいな?」 「うん」 「わかったわ」 「よろしい。またすぐ会えるよ」 「そうね。……ねえ、一つだけ教えて欲しいことがあるんだけどいいかしら」 「……うん? なんだい?」 気になることがあって呼び止めると、パパが振り返る。私は龍亞の手を握っておずおずとそれを尋ねた。聞いてはいけないことかもしれないけれど、ルチアーノのことを知るために、それを知りたかった。 「その人は、最後になんて言ったの?」 するとパパはびっくりしたように目を見開いて、それから目を瞑る。脳裏に、その時の記憶を呼び覚ましているのかもしれない。すごく悲しそうな顔だった。そうして、 「俺が自分のために泣いてくれたから、捨てたもんじゃないって。そう言って笑ったよ」 とても静かな声でそう教えてくれた。 それは明らかな末期の別れの言葉だったけど、まるでおやすみの挨拶のようだと私には思えた。明日、また何でもなかったみたいに、当たり前みたいに、おはようって言うための別れの言葉にとてもよく似ていた。 きっとルチアーノにも、そういうとても卑怯な言葉を嘯いたのだろう。だから余計にルチアーノは、母親が恋しくなって、失った後になってそのことに気がついて、がむしゃらで、必死なのだ。 ママがそういう人だったのと同じように。 私達はきっとその気持ちを知っている。 ◇◆◇◆◇ 《千年リング》というオカルト・アイテムがあって、それはかの名高い七つの《千年アイテム》の一つなのだが、千年パズルと千年リングには他の五つとは違う特徴が共通して一つあった。どの千年アイテムも不可思議な、時として超常的な能力を発揮するものなのだがこれはそれとは少し毛色の違う特徴だ。 千年パズルと千年リングには、太古の人間の人格が宿っている。 古代エジプトから三千年後、その人格は宿主と巡り会い暗躍するようになる。千年パズルの人格「名もなきファラオ」は武藤遊戯と。千年リングの人格「盗賊王バクラ」は漠良了と。千年に一人の器たる人間との邂逅を経て、ファラオの自らの名を求める旅路は終局へ向けて動き出した。 「正史の上では、そういうことになってる。盗賊王バクラの仕掛けた最後のゲームに勝って、名もなきファラオは自分の名前を取り戻した。その後、全ての千年アイテムは彼の墳墓に祀られてこの世界から姿を消した、らしい。これ、海馬社長の私用メモからの引用なんだけど。だけどこの世界ではファラオは名前を取り戻すことが出来なかった。《ゼロ・リバース》が消えたことで歴史全体に歪みが生じた結果彼は成仏することが出来なくなってしまったらしい。そしてそれは運命が繋がっていた盗賊王の方も一緒だった」 相変わらずこぎれいで、でも一人で暮らすには広すぎるヨハンの家で彼からそんな講釈をたれられる。名もなきファラオ、あの圧倒的な威厳を持つ人には十代も一度だけ会ったことがある。パラドックスと正史で対峙した時のことだ。ブラック・マジシャン使いのシルバーを愛する神域のデュエリストは凄まじいまでの強さを誇っていた。 だけど同時にそれが彼の弱さでもあったのだと、彼を見送った武藤遊戯は寂しげな微笑みと共にそう教えてくれた。 ファラオは武藤遊戯を、巡り会ったたった一人を、あまりにも大事に思いすぎていたのだ。 「そういうわけで、こっちの世界では千年アイテムは未だに手の届くところに現存していたそうだ。届くって言っても、大体墓守の一族が守っていて一般人じゃ手を出すことはまず叶わないらしいけどな。で、やっぱりそれには例外があって、その一つが千年パズル。名もなきファラオの魂が宿るそれは、海馬社長を経由してKC本社に保管され、遊戯さんの遺言で遊星君の手に渡った。不動から聞いた話だから、これは間違いない」 「一つってことは、もう一つはあるってことか。ヨハン、どういうことだか、大体読めたぜ……それ、マジか?」 「大真面目さ。これはつい最近、墓守の一族の末裔から預かった本物だよ。どうやって俺達のことを嗅ぎ付けたのかと思ったけどそこは本職だな。あの一族には《千年タウク》使いが代々いて、現在過去未来を見通すんだって」 リビングルームのテーブルの上に重々しい櫃が置かれる。銀色で、大きめの正方形の櫃だ。なるほど龍亞と龍可を帰したのはこのためもあってか、と十代は一人納得した。確かにこれはあまり大勢が見るべきものではないだろう。 櫃に手を掛けてヨハンが悪戯っ子みたいに笑う。デュエル・アカデミア時代によく見たものだ。懐かしい。 「これは漠良了の遺言でマリク・イシュタールを通じ墓守の一族に預けられた鍵と成り得るピースの一対だ。ただし、この櫃を開けるには条件が一つある。それは『千年パズルを納めた黄金の封印櫃の封が解かれていること』。――さて、ここで問題なんだが十代、君はこいつが開くと思うか?」 「わからないよ、そんなこと言われても。ただ……」 「ただ?」 「開いたら、もう後戻りできないんだろうなってことはわかる」 「そっか」 おずおずとそう答えるとヨハンはすごく綺麗な笑顔で頷いて、あっさりと櫃の蓋に手を掛けた。 |